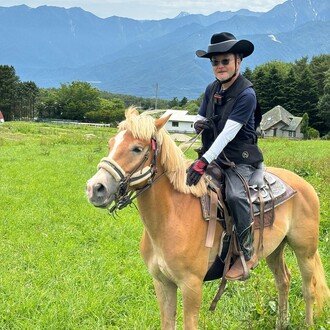流鏑馬神事の事故について考えたこと
先ずは負傷された方々の1日も早いご回復をお祈りいたします。
2024年に発生した流鏑馬神事に関連する2件の事故について解説します。 大村義人
先ずは、2024年の9月16日鎌倉での流鏑馬神事の練習中に起きた事故について。
さらに、2024年10月27日に発生した、宇都宮での流鏑馬神事中の事故について。
鶴岡八幡宮の流鏑馬神事練習中の事故
報道で得たニュースを総合すると
鶴岡八幡宮で開催される予定の流鏑馬神事の前日の練習で落馬事故が発生した
馬が暴れたり転倒した様子はなかった
傷害は頭部と頸部であり(頭部からの出血もあり)意識不明の重体
八幡宮は翌日に催行予定だった神事の中止を決定した
ということでした。
「やっぱり流鏑馬って怖いよね」
「ほら、やっぱり乗馬は事故が心配」
「安全性を重視した対策が必要では?」
という一般のかたからの不安の声が聞こえてきそうなこのニュースを題材に、ひとりの乗馬経験者の視点からこの事故について考えた事をまとめました。
神事としての流鏑馬
先ずは、乗馬競技の流鏑馬(スポーツ流鏑馬)と今回事故があった神事としての流鏑馬の違いについて、私が知る範囲で解説したいと思います。
流鏑馬とは
流鏑馬(やぶさめ)は、日本の伝統的な馬術の一つであり、弓を使って馬上から的を射る弓術でもあります。流鏑馬の技を弓馬術と言う呼び方もあります。
流鏑馬の歴史
流鏑馬の起源は552年、欽明天皇が九州豊前の宇佐で神功皇后と応神天皇を祀り、国に平安を祈願する神事として始まったとされています。日本書紀には、天武天皇が682年に流鏑馬を催し、文武天皇が698年にそれを禁止した記録があります。平安時代には、弓馬礼法が制定され、流鏑馬は神事としても行われました。1063年には源義家による奉納があり、1136年から春日大社で「流鏑馬十騎」が奉納されるようになります。
鎌倉時代には「秀郷流」と呼ばれる技法が普及し、武士や幕府の行事として盛んに行われました。しかし、兵法や武器が進化し、特に室町時代・安土桃山時代には集団戦闘の重要性が高まり、流鏑馬は徐々に廃れていきました。
現在では、流鏑馬は多くの地域で祭りや地域のイベントの一環として継承されています。各地で開催される流鏑馬の競技会では、伝統衣装を身にまとった射手たちが華麗なパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了しています。
神事としての流鏑馬
現在でも流鏑馬は、各地の神社で神事として神様へ奉納されています。
ある調査では、全国で100以上の寺社で流鏑馬が開催されているようですが、今回事故が発生した鶴岡八幡宮は、この中でもとりわけ格式の高い神社のひとつです。
鶴岡八幡宮の流鏑馬神事について
同社の9月14日から16日にわたる例大祭の中で14日の前夜祭にあたる宵宮祭、15日の神幸祭に続いて執り行われる16日の流鏑馬は神事として厳格に執り行われるものになります。
鶴岡八幡宮の神事としての流鏑馬(小笠原流では騎射と総称される流鏑馬・笠懸・犬追物の騎射三つ物のひとつ)では騎射の技術だけでなく、小笠原流の武家の礼法も極めた方が担う格別なものになります。
従って、乗馬が上手いからとか弓が上手いからといって、簡単に参加できる様なものではなく、礼法の心得に加えて訓練と修行の上でに担う特別な役目なのです。
まあ、一言でいえば、武家の作法を極めた騎射のプロ集団が担っているのが小笠原流流鏑馬神事であると言えるでしょう。
鎌倉武士さながらの狩装束に身を包んだ射手が、馬で駆けながら馬場に配された3つの的を射抜く勇壮な神事で、源頼朝公の時代より800年の伝統を受け継いでいます。弓馬術礼法小笠原教場宗家以下一門のご奉仕により勇壮に行われ、鎌倉時代を彷彿させます。
では、このような特別な弓馬術のプロの練習中になぜ事故が起きたのかを推察してみます。
流鏑馬に必要な技術
流鏑馬では、射手が馬に乗り、速いスピードで馬を走らせます。この走り方は「駈歩」または「襲歩」と呼ばれ、最高速度に近い状態です。流鏑馬は弓の命中率を競うだけでなく、同じ命中率同士では速さを争うタイムレースの側面も持っています。
競技のスタイルにはいくつかの種類がありますが、一般的には専用のコースを走り、3か所に設定された的に矢を放ちます。射手は手綱を離し、馬の動きに合わせて体を使い、短時間で連続して弓を引きつつ的を狙わなければなりません。このため、馬術と弓術の両方の高い技術が求められ、バランスと集中力が必要です。
逆に見ると、全速で駆ける馬の上で手放しで操るには、高度な乗馬技術が不可欠です。これは非常に危険を伴う乗馬術といえます。
さらにもう一つの危険な要素は、頭部を保護する装具を付けないことです。通常の馬術競技では、落馬時に備えてヘルメットが義務付けられていますが、流鏑馬では古式の装束を着用するため、頭部を保護するのは帽子だけとされています。
最近の練習中の事故についての記事では、射手がヘルメットを着用していたかどうかの記載はありませんが、頭部からの出血があったとの報告もあるため、ヘルメットは着用されていなかったと推測されます。
本番での神事の際は仕方ないとしても、練習中にヘルメットを使用していれば、重症は避けられたかもしれないと考えました。
宇都宮の二荒山神社の流鏑馬神事での観客を巻き込む事故
「流鏑馬」神事で参加者が落馬 観客含む6人けが 宇都宮
26日午後、宇都宮市中心部にある神社の前の広場で、馬を走らせながら矢を放つ「流鏑馬」の神事が行われていたところ、参加者の1人が馬から落ちて観客が巻き込まれ、幼い子どもを含む6人がけがをしました。
警察によりますと、26日午後4時前、宇都宮市中心部にある二荒山神社の参道の広場で、「流鏑馬」の神事が行われていたところ、参加者の1人が馬から落ち、観客の列に向かって体を投げ出されました。
この事故で、幼い子どもを含む観客5人と参加者のあわせて6人がけがをし、このうち77歳の観客の男性は、右手を骨折した疑いがあるということです。
流鏑馬が行われていた「馬場」と観客の間にはさくが設けられていましたが、馬から落ちた際、さくを乗り越える形で体を投げされたということです。
警察は、参加者がなんらかの理由でバランスを崩し、馬から落ちたとみて、当時の状況を詳しく調べています。
二荒山神社の「流鏑馬」は、毎年10月に行われる恒例の神事で、27日まで2日にわたって行われる予定でしたが、神社は今回の事故を受けて、27日の「流鏑馬」を中止にしました。
こちらは、神事の最中に落馬事故が起こり、幼いお子さんを含む数名が転落した射手によって怪我をされたという事件です。
大変残念ですが、こちらは主催者側の安全管理の問題があったのではないかと思いました。通常、流鏑馬では、ロープや柵で射手と観客を分離していますが、「一応、観客はこの線から中に入らないでください」程度の意味しかありません。
馬が疾走するすぐ脇で観戦するのは、競技の迫力を実感できるのですが、もし射手が観客席側に落馬したり、馬が放馬状態になった場合には、観客の安全は保証されません。
少なくとも、小さなお子さんをそのような席に座らせるのは、安全管理の点からみれば推奨されるべきではなかったと思うのです。
馬術競技・スポーツとしての流鏑馬について
神事としての流鏑馬とは別に、競技として行われる流鏑馬があります。これはスポーツ流鏑馬と呼ばれる馬術競技のひとつです。
馬の上から弓を射る事には変わりがありませんが、誰もが行うスポーツなので、安全性も重視されています。
例えば頭を守る保護帽の着用は必須ですし、普段の練習では、ヘルメットを装着し、安全性と安定性の高いウエスタン鞍が使用されます。
また、正式な試合の際には、装束の下に保護ベストを装着することが推奨されています。

安全性を重視したスポーツ流鏑馬とはいえ、中級・上級の試合では襲歩(全力疾走)に近い速度で走る馬の上で、手綱を離してバランスをとりながら、数秒間隔で騎射を行うのですから並大抵の技術ではありませんね。
スポーツとはいえ、しっかりとした段階的な訓練を重ねて真剣に試合に望む必要がありますね。
あとがき
不幸なことに2024年に「流鏑馬」に関連する事故が続いて発生してしまいました。
乗馬に携る側の者として、この事故が正しく伝わり、乗馬競技の普及や流鏑馬保存に影響が残らないことを祈るばかりです。
この記事が、皆さまのご理解の参考になることを望んでおります。
2002年7月、全国の流鏑馬愛好者が集まって流鏑馬競技連盟が創設され、北海道芽室町で初めての流鏑馬競技会が開催されました。競技としての流鏑馬は、射法や儀式的な部分を重視せず、純粋に的中率が競われます。
普及を第一の目的としているので、馬具や騎手の装束に関しては細かく規定されていません。ただし原則として馬は和種または和種系であることが決められています。
競技規定(流鏑馬競技連盟東北支部 2012年1月7日改正)
【馬】
・和種・和種馬系を基本とするが、馬の大小及び種類は問わない
・各クラブ・各団体が責任を もって選抜した馬を競技馬とする
・個人参加の場合、各主催者団体担当者が判断する。
・首指し良く・足さばき良く・物に動じぬ・物見をせぬ馬が 流鏑馬ホースとして大事である
【馬装】
・和ハミ、和鞍、和鐙とし 三懸を基本とするが最低限三懸を着用
【選手及び選手の服装】
・和装
・保護帽の着用義務
・各クラブ・各団体が責任をもって 選抜した選手を大会に出場させる
・クラブに所属しているが他団体から馬を借りた場合 馬貸主が選手への責任を持つ (クラブが馬の貸し借りに 仲介に入った場合は別である)
・個人参加の場合 各主催者団体担当者が判断する
【走路】
・スタートから的間、ゴールまでの距離は 『スタートから一の的まで約25メール』 『的間約50メートル~60メートル』 『三の的~ゴールまで約25メートル』 とし各会場状況で設定する。
・走路の幅は 約2.5m
・走路から的までの距離は約2m~約5mとし各会場状況で設定する
・的のサイズは45cm~60cm
・走路入口はジョウゴ型、
・埒の高さは約90センチ位が望ましい
【配点・タイム】
・配点、制限タイムも同様各主催者が調整する
(プロ級においては12秒を2012年度は実施し2013年度から正式に制限タイムをルールへ加える予定)
【弓矢】
・弓は和弓とし弓上限10キロ
・矢は90センチ以上の鏑矢とし鏑は直径3センチ以上の角が無く木製とする
(プロ級においては3枚羽の使用を2012年度は実施し2013年度から正式にルールへ加える予定)
15日午前5時55分ごろ、神奈川県鎌倉市雪ノ下の鶴岡八幡宮で「流鏑馬(やぶさめ)神事の練習中に落馬した」と119番通報があった。茨城県守谷市の男性会社員(29)が落馬の際に頭や首を強く打つなどして意識不明の重体。八幡宮は16日の例大祭に予定されていた流鏑馬神事を中止にすると発表した。 県警鎌倉署と八幡宮によると、例大祭で神事を奉納する予定だった弓馬術団体が早朝の境内で練習していたところ、男性が馬から落ちた。馬が暴れたり、転倒したりした様子はなかったという。 15日の神幸祭(しんこうさい)のみこしの渡御でも神職が神馬に騎乗する予定だったというが、急きょ取りやめとなった。流鏑馬神事では3人の射手が技を披露するが、八幡宮は「安全上、同じ事故が起こる可能性は厳に慎まなければいけない」と中止に理解を求めた。 流鏑馬は疾走する馬の上から矢を的に射る儀式。例年多くの観光客が訪れる八幡宮の流鏑馬神事は、鎌倉時代に成立した歴史書「吾妻鏡」に武士たちが源頼朝の前で流鏑馬を披露した記録があり、800年以上の歴史を持つとされる。

いいなと思ったら応援しよう!