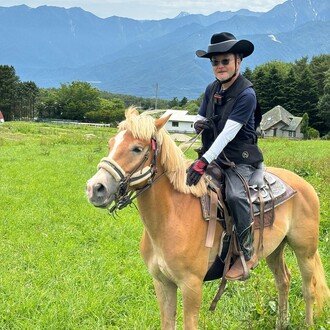《高齢者向け》 マイナ保険証、どうしたら作れるの?

医療関係者であり、高齢者、兼マイナ保険証ユーザーの立場から、マイナ保険証をどうしたら良いのか? お勧めの対処法を考えてみました。
まず、保険証をお持ちでしたら、有効期限を確認してください。
紙(カード)タイプの保険証には必ず有効期限が明記されています。
慌ててマイナカードを作りに役場へ走っていったり、保険情報確認書の発行を請求する必要はありません。対処を考えるのは、現在の健康保険証の期限が切れる前ならゆっくりで大丈夫。
明日からマイナ保険証にしなくちゃいけないということではありません。
こちらも参考にしてください⇩
その上で、保険証の期限が切れたあとにどうしたいのか?決めておきましょう。
決断は2択です。
⬜︎ マイナ保険証を使う
⬜︎ 資格証明書を使う
マイナカードを作りたくない、持ち歩きたくない派の方は、資格証明書が必要になりますので、保険証の発行母体(役所や健保組合)から資格を証明する書類が送付されて来なければ、請求する必要があります。
※健康保険証の発行母体は、12月2日以後、従来のように健康保険証を発行したり送付できなくなります。発行はしてくれませんが、混乱を避けるために代わりに資格証明書を発行してくれる可能性があります。
さて、マイナ保険証を使うぞ、という貴方。
マイナンバーカードをお持ちでしょうか?
お持ちでなければ、まず、マイナカードを入手する必要があります。
これは、自治体が発行していますので、まずは区市町村など自治体の窓口に行って、手続きをしてください。手続きについては、予約が必要な場合がありますので、問い合わせしてください。
なお、スマホだけで簡単に申請ができるというおますさんの記事を見つけたので、リンクしておきます⇩
マイナカードに保険証情報を付与する方法
マイナカードを入手したら、スマホでマイナポータルにアクセスします。
マイナポータルはアプリ版とウェッブ版があります。
アプリ版はこんな感じ⇩

マイナカードを作成した時に決めた、4桁の数字のパスワードと、マイナンバーカードが必要です。
まずは《ログイン》をポチします。
画面の指示に従って、パスワードを入力すると、マイナンバーカードをスマホにかざしてスキャンさせろと要求してきます。

所定の位置にマイナカードを当てるとスキャンが完了して、個人情報に関する領域に入ります。
ここで、健康保険証を登録する作業をします。
登録作業は簡単です。
マイナカードを保険証として利用することに同意するだけです。
登録が完了した後の確認画面はこのようになります。

この画面で、資格情報の確認ができます。
この資格情報は、pdfファイルとしてダウンロードが可能なので、ダウンロードして保管しておくと良いでしょう。
これで、マイナ保険証は完成です!
次回はマイナ保険証の使い方の実際を紹介する予定です。
宜しければこんな記事も書いております。↓

いいなと思ったら応援しよう!