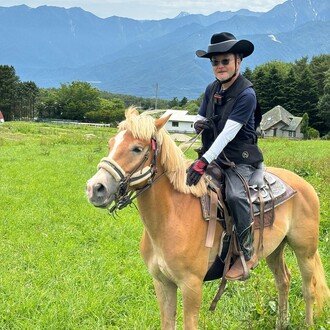乗馬ライダーの忘備録❶手前問題を考える
ヒヒーン❣️
馬に関するエッセイを書いているじーちゃんこと大村義人(ペンネーム )です。
一般の方向けの乗馬ネタの記事を書いておりますが、一般向けと馬ライダー(経験者)向けの記事と一緒に書くと説明がややこしくなるので、この「乗馬ライダーの忘備録」シリーズは乗馬をやっているかた向けとさせていただき、細かい解説は省いております。
説明が下手なので、長文になります。
さて、今回は手前のことを考えてみました。
乗馬における「手前」とは、馬が走る際に、どちらの前脚を先に出すかという動きのことを指すことはご存知の通りです。
特に「駈歩(かけあし)」や「襲歩(しゅうほ)」といった速い歩法で使われます。
馬場などの限られたスペース内で駈歩を出すときには、どこかで曲がるコースを取らないと柵にぶつかりますよね。
(柵を飛び越える選択もある?😅)
この、曲がりながら駈歩を出す時に、いつも課題になるのが手前の問題です。
正直なところ、筆者は外乗ばかりで遊んでいる時には、手前のことなど全然気にしていませんでした 笑。
(外乗での駈歩はほとんど直線のコースで出していましたから、お馬任せでした)
ところが、馬場でのレッスンを受けるようになって初めて、「手前というものがある」という現実に直面しました。
手前というもの自体がわからなかったので、
「手前が違いまーす!」
といわれても。。。
《なんだかわからんけど走ってるからいいんじゃない?》
とか
《そもそも、手前が合ってる状態って?》
と思っていたので、
「手前が違うと、なんか違和感があるでしょ?」
と言われても、よくわからず、実はわかったふりしてました💦
と言うことで、いまさらながら手前の基本をおさらいします
馬は駈歩や襲歩をするときに、右手前と左手前のどちらかの状態で走ります。
それぞれ以下のような違いがあります。
右手前: 馬が右前脚を前に出し、同時に左後脚を踏み出している状態です。右回り
左手前: 馬が左前脚を前に出し、同時に右後脚を踏み出している状態です。左回り
この説明、わかるようでとてもわかりにくいんです。笑
で、
手前の重要性とは?
手前は、馬が円(カーブ)を描いて走るときに重要になります。(逆に言えば、直線を走るときは馬の好み次第)
例えば、右回りに走る際は「右手前」、左回りに走る際は「左手前」が理想的です。これは、正しい手前でないと馬のバランスが崩れやすくなり、怪我や疲労の原因になるためです。
手前の指示
乗馬中に正しい手前を取らせるために、騎手は脚や体重を使って馬に指示を出します。例えば、右手前を取らせたい場合、左脚で強く押し、右脚で軽く支えることで、馬に右手前で走るよう合図を出します。
手前の確認
馬がどちらの手前で走っているかは、馬の前脚や騎手の感覚で確認できます。特に駈歩では、馬の体の動きや前脚の動きで手前を判断することが可能です。
ところで
馬の場合、前脚のことは手ではなく足とか脚と呼びますよね?
前足の状態を示す言葉なら、なぜ「手 前」と呼び「足前」とか「脚前」とか呼ばないのか不思議に思ったことはありませんか?
私、すごく気になってしまったので、調べてみました😅
と言っても、ちょっとなので、チャットGPTで調べてみました。
語源的には、日本語の「手前」は文字通り「手の前」、つまり「自分に近い側」や「内側」を意味します。馬の運動では、乗り手から見て「内側にある前脚(前)」が基準になるため、「手前」という言葉が使われています。
たとえば、馬が左手前で走っている場合、馬の左前脚が進行方向においてリードしている状態です。
ふむふむ
右手前の場合、内側にあたる右足の動きに注目することになります。
ということなんですが、
「日本語トテモムズカシーデス」
わかったようなわからないような☺️
モヤモヤが解消されません。
では英語ではどう表現するのでしょうか?
right lead とか left lead と表現します。
lead と呼ぶので、right lead (右手前)の場合に右足が先に出る的なイメージを持つのは誤解のもとなんです。(筆者も実はそのようなイメージでした 笑)
ちょっとややこしいので、駈歩の際の馬の足の動きを確認しながらイメージを変えましょう。
「リードする側の足は最後に出る」について
左右が混じると混乱するので、
右手前だけで確認しましょう。
先ず、駈歩のスタートは、後脚の蹴り出しから始まりますので、後脚に注目します。
右手前の場合には、左後脚がスタートです
そして、「タッタカ タッタカ」の3拍子ですね
分解すると
左後脚を踏み出す: 左後脚が最初に地面を蹴ります。1拍目 タッタカ
対角線上の右後脚と左前脚が同時に踏み出す: 右後脚と左前脚が同時に地面を蹴ります。2拍目 タッタカ
最後にリードする右前脚が踏み出す: 右前脚が最後に地面を蹴ります。3拍目 タッタカ
これが三拍子のリズムで、「タッタカ、タッタカ」と聞こえるような特徴的な音を生み出します。
イメージできましたでしょうか?
繰り返しになりますが
右手前でリードする脚は右前脚なのですが
最初に出るのが右前脚なのではありません。
最後に出るのが右前脚です。
駈歩の3拍子のリズムの中では、「タッタカ」の「カ」にあたる3拍めのところで右前脚で蹴るのです。
この3拍目で、馬は後脚の推進力の方向(円の接線方向)に対して少し内側(右手前なら右)に踏みこみます。
(馬の身体はカーブの時はカーブに沿った形に曲がっていますので)
こうして右回りの円周上を走れる様に調整している事になります。
もし、右回りの時に左手前になったらどの様になるでしょうか?
進行方向を微調整する脚が左側になってしまうわけですね?
そうなると左足踏む時に内側(右側)寄りに調整しないと右回りができにくくなくなります。
外側の足を内側に踏みこまないと方向が調整できないのですから、左前脚の動きは右脚とクロスするようなイメージです。
(実際にはクロスしていないと思いますが)
人が走る時の動きで考えると実感できるかもしれません。
人が陸上競技場のトラックの曲線区間でこのような走り方をすることをイメージしてみましょう。(陸上競技では、左回りが基本なので、馬が左手前で走るのと同じですね)
走者は、カーブでは遠心力に対応するために、やや左側に身体を傾けて走ると思います。
真っ直ぐ走ると外側のコースに出てしまいますから、進行方向に対してコースを少しずつ左側に修正していきます。
この時、左足(内側の足)が着地するタイミングで調整するパターンと、右足(外側の足)が着地するタイミングで調整するパターンのとどちらが効率よく、しかも減速しないで走れるでしょうか?
たぶん意識していなくても自然に、内側の足で調整しているはずです。
馬が走る時も同じ理屈です。円周の内側の脚の着地場所を進行方向(接線方向)に対して少しだけ内側寄りにずらして踏み込む事でスピードを落とさないで円周上のコースをとることができるのですね。
馬が走る時の動きは、後脚が後輪でエンジンに連結されているのに対して、前脚がハンドルに連結されている前輪のイメージですね。
以上、自分で納得するために考えたリクツですので、間違えているかもしれません。が、推進するときの脚は《後脚+前の外側の脚》で、内側の前脚でコースどり(リード)していると考えれば理解しやすいと思います。
もし、説明が違うよと思われたら、コメントをいただければ幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!