
第8回ケア塾茶山 『星の王子さま』を読む(2018年4月11日)
※使用しているテキストは以下の通り。なお本文中に引用されたテキスト、 イラストも基本的に本書に依る。
アントワーヌ・ド・サン=グジュペリ(稲垣直樹訳)
『星の王子さま』(平凡社ライブラリー、2006年)
※進行役:西川勝(臨床哲学プレイヤー)
※企画:長見有人(ココペリ121代表)
はじめに
西川:
今日で8回目です。40ページからですね。
しかしね、本って頭で読むもんやと思ってたけど、違いますね。体の体調が悪いと、全然入ってこない。歳とったからかもしれませんが、それを最近つくづく感じてます。
昔は本読むときは結構集中して読んでました。一日に三冊四冊って徹夜でね、読んでたことがありました。その時には別段身体が疲れていようと何であろうとお構いなしに頭に入ってきてたっていうか、考え続けられてたんですけどね。
集中力って結局は体力。気力だけじゃないよね。体力。体力っていうのは、健康状態っていうのもあるけど、あとは若さっていうのもある。健康であっても若さはどんどん変わっていくしね。
先月の中頃からずーっと風邪ひいてて体調が悪くって。なかなかこう読んでても、こう目が虚ろに。こう文字をなぞってるだけっていうふうになってしまって。困ったもんです。
ここではいつも声に出して読んでます。あれはやっぱ無理やりにでも身体を参加させるっていう意味があるんかな。やっぱり本を読むときに、その世界をたっぷり味わうためにはやっぱり声に出して読むことが大事かなって気がします。
これまで、ずーっと僕が一人で読んでたんだけど、ちょっとこれからはみんなにも読んでもらおうかな。大谷大学では学生さんに声出して読んでもらってたんです。うん。でも、ちょっとイライラし始めたりして。あまりにも下手くそだったから。あんまり読ますのはやめました。
でも、あれですよ。大谷大学には障害を持ってる学生もいまして。そういう人たちに特別な配慮をしながら授業をしてくださいって言われた、ってこともありました。そういう子が何人かいたんです。
でも、一人の子はうまい。あきれるほど上手に読むんですよ。それからもう一人ね、あれ何やったけな、ちょっとややこしい病名やったんでもう忘れてしまいましたけども、えーと字が読めないんだ。何だったっけ。誰か知りません?
B:ディスレクシア[*1]。
西川:そう、ディスレクシア。有名な俳優さんで誰かいましたよね。
B:『ミッション:インポッシブル2』[*2]に出てたトム・クルーズですかね。
西川:そうそう。トム・クルーズがそうでしたね。ディスレクシアって、「レクシア」っていうのが文字っていう意味でしたよね?
B:読字障害ですよね。ちょっと僕もあんまり詳しく知らないですけど。
[*1] ディスレクシア:dyslexia.語源的には、dys-(困難, 不良)+ ギリシャ語 'lexis'(speech 話すこと),'legein'(to speak 話す)。難読症、失読症。学習障害の一種で、知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書き学習に著しい困難を抱える障害。
[*2] 『ミッション:インポッシブル2』:2000年公開のアメリカのアクション映画。ジョン・ウー監督、トム・クルーズ主演。
西川:
文字を見ても図形のように見えるそうです。だから読んだり書いたりはできないけど、人の話を聞いたりしゃべったりはできる。
哲学科の学生でしたけど。読むことができない人に「朗読せい」って言うのはよくないので、「どうする?」聞いたら、「いや、あの、大丈夫です」とかっていってくれて。覚えてくるんだろうね。
C:え、そらんじるわけですか?
西川:まあ読んでるような、だから勧進帳みたいなものです。
C:すごいな。
西川:
勧進帳みたいなものだけど、声に出して読んでくれるんです。それがものすごく「あ、この子はよう分かってるな」ってわかる。やっぱりある程度は読みで分かるんですよ。「この人よう分かってるな」ってね。うん。
それはだから僕が、人前で読むときも「見透かされるなあ」と思うわけ。下手くそに読んでたら「こいつ分かってないなあ」とばれてしまうわけです。感覚なんですけど。
本を読むっていったときにはどうしても知的な作業って思いがちで、身体というか体のことは二の次になってしまう。でも、実はそんなことはない。深いところで、体で読むっていうのはすごい大事なことだと思います。
サン=テグジュペリ文学の2つの系統
西川:
ちょっと話は変わりますが、『星の王子さま』の著者のサン=テグジュペリっていう人は「行動派の文学」っていうふうに、20世紀の文学史上の中で言われた人です。実際にパイロットですからね。
パイロットも今みたいな時代のパイロットではなくて、飛行機が生まれたばかりで、郵便飛行機で航路を開拓したっていう半ば冒険的な生涯を送っている。それから最後は、戦争中に撃ち落とされて亡くなってるわけですけど。
そういうパイロットとしての経験というものを、こうずっと小説とかエッセイにしてやってきている。なんか他の作品読むでしょ。『城塞』っていうのは僕全部読みきれてないですけど、彼の最初のデビュー作が『南方郵便機』っていうやつです。そのあとは『人間の大地』(『人間の土地』と訳されたり)だとか、『戦う操縦士』[*3]だとか、まあ何冊かもう日本語で翻訳されてるのがあります。それを読むとね、やっぱりものすごく体に効きます。体にこたえてくるっていうか。
高度200メーターぐらいで飛んでいる時から、高度3000メーターとかっていうようなところまで戦闘機なんか使っている時。そうなってくると、ものすごい高いところで、酸素マスクしないと生きていけないんです。サン=テグジュペリも、最後はアメリカ軍の戦闘機に乗ってるから、機内に酸素ボンベもちゃんとつけられてあったし、操縦室の温度なんかも調節してあったんです。
けど、それまでの夜間飛行なんかで、夜にも飛ぶなんていったときのサン=テグジュペリが乗ってた飛行機っていうのは、まったくそんな設備はないんですよ。もうビュービュービュービュー、上に行けば行くほど気温は下がりますからね。
そういう中で、操縦桿が凍りついて動かないだとか。体中も、ものすごい量の服を着てるわけですから、動きが取れないんですよ。動き取れないぐらいの防寒着を着て操縦してるみたいなことがいろいろ書いてある。サン=テグジュペリの文学を読むときには、彼の体験したこと、ほんとに体で体験した事柄っていうのが直に伝わってくるような文章が多いなって思いました。
[*3] 『戦う操縦士』:“Pilote de Guerre” サン=テグジュペリ著、1942年出版(日本語訳:①堀口大學訳、新潮文庫、1956年出版、②『サン=テグジュペリコレクション4 戦う操縦士』、山崎庸一郎訳、みすず書房、2000年出版、など)。
サン=テグジュペリは『星の王子さま』だけが突出して有名なんで、これだけ読むっていうことが、多いでしょう。まあ僕も最初そうでした。でも、やっぱり他の作品なんかを読んでいくといろんな似ているテーマがいっぱい出てくるんです。でもね、『星の王子さま』だけが全然世界が違うんですよ。
山崎庸一郎[*4]っていうサン=テグジュペリの全集をほとんど訳してる仏文学者がいます。彼が、『南方郵便機』っていうサン=テグジュペリのデビュー作とこの『星の王子さま』との関連性、それからまた別の有名な『夜間飛行』と未完の大作『城塞』との関連性の「サン=テグジュペリの文学作品には二つの流れがある」って書いてます。
新潮文庫の堀口大學(まだサン=テグジュペリが生きてた頃にサン=テグジュペリの小説を翻訳した詩人)の解説のあとにあります。僕、結構、堀口大學の詩は好きですね。
それはともかく、山崎庸一郎が書いていたことに「ほお、なるほどなあ」と思ったりしました。
[*4] 山崎庸一郎:やまさき よういちろう。1929-2013、東京生まれ、フランス文学者、学習院大学名誉教授。1990年には『サン=テグジュペリ著作集』(『サン=テグジュペリ・コレクション』)をほぼ全訳、2005年にはこれまでの研究の成果を活かした『ちいさな王子さま(Le Petit Prince)』の新訳を出した。
サン=テグジュペリの小説にはほとんど女性出てこないんです。『南方郵便機』にだけ出てきます。それも、どちらかと言うと『星の王子さま』っぽいんですね。幼い頃に憧れていた女性が金持ちと結婚する。それで退屈な夫婦生活をやってることを知った冒険家のパイロットが彼女を口説きに行く。で、駆け落ちをするわけです。でも、駆け落ちするんだけど、結局その女性とはうまくいかなくなって、別れた彼はまた仕事に戻るっていう。で、仕事に戻って行方不明になっちゃうんです。で、結局、飛行機事故で亡くなるっていうことを暗示させて終わるような小説なんです。
他のサン=テグジュペリの小説はだいたい男ばっかりが出てきて、それも郵便飛行機やったら「郵便飛行機で扱ってる郵便物が操縦士の命よりも大切なんや」みたいな感じです。「何が何でもこの時代の中で夜間飛行を成功させて、世界で一番早い」を証明させたい。
何て言うかな、運搬、流通の機械としての飛行機を確立させようとする、航空業界の人たちの苦闘みたいな。それに命を賭けて次々と命を落としてくパイロットたちの話がほとんどなんですよ。
『戦う操縦士』っていうのもそうなわけで。言ってみたら男臭ーい話ばっかり出てくるんですね。で女性が出てくるのは、まあこの『星の王子さま』と『南方郵便機』だけですね。『星の王子さま』の場合は女性じゃなくて、バラですけど。
だから、稲垣さんも後ろのほうで、『星の王子さま』のいろん複雑な味わいをもう少し見ようと思うと、サン=テグジュペリの他の著作に触れることも必要や、みたいなこと書いていました。確かにそうだとと思います。
まだ、『南方郵便機』と『星の王子さま』の系列と、それから『夜間飛行』だとか『城塞』のような男、男、男のこう全然メルヘンも何もないリアリズムの、構造主義の文学との架け橋はもちろん、何が違うのかっていうことについては、ぼくも考えがついてませんけれども。
『星の王子さま』だけで語っていくと、どうもこうやっぱりあまーい、なんかセンチメンタルな感じに読めるんですけど、そうではない。ものすごく骨太のところがサン=テグジュペリの文学にはある。注意して見ると、『星の王子さま』の中にもそれはやっぱり出てきてるわけです。そんなことを気にしながらこれからを読んでいくと、面白いかなと思ってます。はい。
2つのキーワード
西川:
ということで、読みましょう。40ページからになりますね。最初は僕読みましょうか。
またしてもヒツジのおかげでした。五日目になって、王子さまの日々の暮らしの秘密をぼくがもう一つ知ることができたのは。前置きもなにもなしに、いきなり王子さまはぼくにたずねたのです。じっと口を利かないで長いあいだ考えてきた、その果てに口を開いたようでした。
「ヒツジはね、小さな木を食べるでしょ。だとすると、ヒツジは花だって食べるよね?」
「目の前にあるものはなんだって食べるよ」
「花にトゲがあっても食べるかなあ?」
「ああ、食べる。花にトゲがあったって食べる」
「だとすると、花にトゲがあって、なんの役に立つの?」
ぼくにはよく分かりませんでした。ぼくはそのとき、飛行機のエンジンのきつく締まりすぎたボルトを緩めようと思って、手いっぱいだったのです。ぼくはとても心配になっていました。飛行機の故障が相当ひどいものに思えてきていました。飲み水がどんどんなくなってきて、最悪の事態を覚悟しなければならなくなっていましたから。
「トゲがあって、なんの役に立つの?」
王子さまは一度質問をすると、決して引きさがりませんでした。ボルトがなかなか緩まないので、ぼくはいらいらしていました。ぼくは口から出任せに答えました。
「トゲだって? トゲなんか、なんの役にも立たないよ。花がいじわるだってこと。それだけのことだよ」
「ひどい!」
そう言いながら、しばらく黙りこくったあと、恨みがましい声で王子さまはぼくにこんなふうに言いました。
「君は間違っている。花たちはか弱いんだ。花たちは心が純なんだ。なんとかして安心を手に入れたいんだ。トゲがあったら、自分が怖く見えるだろうって思うんだよ……」
ぼくはなにも答えませんでした。ちょうどそのとき、ぼくはぶつぶつこんな独り言を言っていたのです。
「ボルトのやつ、どうしても緩まないんなら、ハンマーでぶっとばしてやるぞ」王子さまはまたしても、ぼくが考えるじゃまをしました。
「で、君は思うの、花たちが……」
「いやいや、とんでもない! ぼくはなんにも思っちゃいないんだ! ぼくは口から出任せを答えただけなんだ。ぼくはまじめなことで手いっぱいなんだよ」
あっけにとられて、王子さまはぼくを見ました。
「まじめなことだって!」
手にハンマーを握り、指を機械油でべとべとにして、王子さまからすれば醜いこと、この上ない物の上にかがみこむ。そんなぼくが王子さまの目に映っていました。
「君はまるでおとなみたいな口の利き方をする」
そう言われて、ぼくは少し恥ずかしくなりました。そんなぼくに容赦なく、畳みかけるように王子さまは言いました。
「君はなにもかも、ごっちゃにする……。なんでもかんでも、いっしょくたにする!」
王子さまはほんとうにかんかんになって怒っていました。きれいな金髪を風になびかせて、
「赤ら顔の男がいる星を知っている。その赤ら顔は花の匂いをかいだことは一度もないんだ。星を見つめたことも一度もない。人を愛したことも一度もない。明けても暮れてもお金の勘定ばっかりだ。朝から晩まで、君と同じことをのべつ幕なしに言っている。『ぼくはまじめな人間だ! まじめな人間だ!』ってね。そんなことばかり言っているものだから、ふくれあがって自尊心のかたまりになっちゃったんだよ。もうそうなると、人間じゃない。キノコだよ」
「なんだって?」
「キノコだよ」
もう王子さまは怒り心頭に発して、真っ青な顔をしていました。

ヒツジがまずは王子とパイロットとを結びつけたわけです。キーワードになりますね。「ねえ、ヒツジの絵をかいて」と彼らは出会うわけですし、王子の様々な秘密は、そのヒツジにまつわる話題で次々と明らかになってくるわけです。
で、なぜこのヒツジを連れて帰らなきゃいけないのか。バオバブの芽を食べてもらうみたいな話がちらっと前のところでありました。でもそういうただバオバブの小さな芽を食べるだけじゃなくって、花だって食べるっていうことですよね。
こういうヒツジの両義性。必ずしもこうヒツジっていうのは王子にとってただ都合のいいだけのものではないっていう。うん。なのに、そのヒツジを連れて帰りたいって、いったいどういうことなのか。まだ分からないままぼくらは読み続けていってるわけです。
ほんとにまともな、まともなっていうか命の危険がかかっているときに、飛行機を何とか修理して、この危機的な状況から脱出しようとしているパイロットと、そういった生死の問題をまったく超越したような話しかしない王子とは、ディスコミュニケーション起きて当たり前なんです。
この「まじめなこと」っていうのもキーワードの一つになります。普通死にかけてるときに、何とか死なないで危機を脱するというのは「まじめなこと」ですよね。「これどうでもええことや」とは普通思わない。でも、王子さまは「そうじゃない」って言ってるわけです、これ。
ここらへんはもうちょっとしっかり考えないと。『星の王子さま』を子どもたちに安易に読ませていいのかって。この『星の王子さま』の底に流れているものは「命より大事なものがある」っていうそういう考え方ですよ。
「死ぬ」よりも大切なこと
西川:
非常に危険といえば危険なんです。一般常識とは全然違う事柄が、このなんかメルヘンチックな物語の底に流れているということ。だからこれを見過ごしたまんまで、「大切なものは目に見えないんだ」とかっていうような有名なセリフだけが多くの人たちの心をつかんでますけど、これ納得できますか?
サン=テグジュペリはそういう思想の持ち主です。様々な小説の中にも書いてます。特にさっき言った『夜間飛行』だとか『人間の土地』だとか『戦う操縦士』のような男っぽい系列の作品にはいくらでもそういう話が出てきます。
だからサン=テグジュペリの思想がそうだっていうことは分かりますけれども、それを自分がどう引き受けるかです。知識っていうかな、ただ「サン=テグジュペリの『星の王子さま』はこういうあらすじでしょ」「で、こういうことが書いてあるんでしょ」って、「こういうサン=テグジュペリの思想が盛り込まれてますね」なんて評論家的に言うのは、言ってみたら、本についてあれこれ知ってるかもしれない。
でも、その本を自分が読んだっていうことにならないわけです。それに対して自分がどう応答するのかっていうことですよね。分からないなら分からないなりに、分からないまま考え続けるのか。それとも「これは違うんだ、自分の考えとは違うんだ」っていうことで脇によけてしまうのか。
さまざまな方法があると思うんですけど、これが、一番僕にとっては難しいところかな。そりゃかっこいいとは思いますけどね。かっこはいいと思うけれども、自分がそう思えるかって言うと、うーん。もっとあたふたしてるんじゃないかなって思いますよね。
『人間の土地』の中で書かれていますが、サン=テグジュペリ自身もリビア砂漠で不時着して、一緒に乗ってた人と砂漠を三日も四日も歩き回って、遊牧民と出会って助かった。そういう実話があるわけです。
だから彼は実際に砂漠の中で、喉の渇きに苛まれて幻覚を見るぐらい生死の境をさまよい歩いたことあるわけです。他にも墜落事故で頭蓋骨陥没骨折やとかいっぱいやってる。ところが懲りない。この人はそういう男なんですよ。
サン=テグジュペリ自身は懲りない男で、次々と飛び立っていくわけですし、最後の、戦時中に飛び立って行った時も、偵察機だから武器を搭載してないんです。
戦局はだいぶん変わってきて、ナチスはだいぶん連合空軍に押されて戻ってる状況ですけど、丸腰でナチスの空軍たちがいそうなとこに行ってるわけです。もうほとんど死に行ってるようなものです。
それも彼のパイロット経験からすると到底乗りこなせないような高機能の飛行機に乗ってる。しかも、度重なる墜落事故の後遺症で、脱出してパラシュートで逃げるっていうことはほとんど不可能なわけです。アメリカ空軍から、7回の出撃は認められたけど、それ以上はだめだって言われてます。でもそれを無視して飛び続けて、結局最後帰らなかった。
彼が亡くなる前の様々な手紙の中にも自分の死を予感してるようなことはいっぱい書いてあるんですが、でも「死なんていうことは大したことじゃない」って。これ他の小説にもいっぱい出てくるんですよ。
「死の恐怖っていうようなものは事後的に考えることであって、本当にその状況ただ中で生きてる人間にとっては」、ボルトが緩むか緩まないか、その操縦桿が曲がるか曲がらないかっていう、そこに問題は集約されてて、「これで自分の命が終わる」だとかっていう、そんな悠長なことは考えてない。
死の恐怖というのは、死についてベッドの中でうつらうつら考えるみたいな、行動の最中ではないときに作り上げる死に対する人間的な妄想に近いもので、現実の死なんていうのはそういうものじゃない、みたいなことをばんばん書いているわけです。
サン=テグジュペリのそういうところがここの話でも出てる。「まじめなことだって!」「君はまるでおとなみたいな口の利き方をする」って、で「そう言われて、ぼくは少し恥ずかしくなりました」ってあります。
ぼくは少し恥ずかしくなりました。
このことを理解するためには一番最初のゾウを呑み込んだボアの絵を誰にも分かってもらえなかったこのパイロットの幼い時の話、エピソードみたいなのが効いてくるのかもしれません。
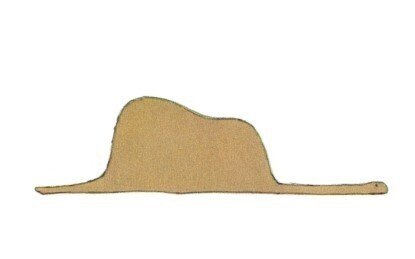
最後に王子が死ぬつもりで別れるって聞いた時のパイロットにも、王子が言う「僕が死んじゃったみたいになるだろうけれども」という現実の死というものと、それから死に対してわれわれが普通持っている恐怖だとか不安だとかっていうものを真っ向から否定する思想が、『星の王子さま』の中にはある。
それについて自分がどう考えるかっていうこと。それも考えるだけじゃあ、どうしようもないんでね。僕は一度も死にかけたことがないんでほんとに分かりませんけど。
席を譲る
西川:
今度のバリアフリー展で、僕は「認知症ケアの先にあること」っていうことで話をすることになっています。ケアにしても看護にしても医療にしても全部そうですけど、生きてる間の話で終わればいいんですけど、死をこう扱わなければとか、うーん、どう言ったらいいんかな。
認知症の人の家族が、20数年だとか、もうほとんど自分の今までの人生を180度変えるようなかたちで在宅介護に取り組んで、一生懸命いろんな様々な苦労をしながら介護をしていくわけです。まあ、認知症そのものは良くなっていくことはもちろんないわけですが、認知症が良くならなくっても認知症と呼ばれているその人と、その介護する家族との関係っていうのは良くなっていきます。
良くなっていくんですが、でもね、やっぱり亡くなるんですよ。この世での別れが必ずやって来ます。でその時に「今までご苦労さまでした」と言われても、これから苦労する必要がなくなってやっと肩の荷が下りたと思っても、解決のつかない虚しさがやっぱり出てくるわけですね。
だから認知症ケアっていうのは、認知症と呼ばれてる人と自分との関係をどうやって修復、折り合いをつけていくかっていうことだけではすまない。その人はやっぱり自分の目の前から消えてしまうわけですよ。いなくなってしまう。で、そのことをどう引き受けれるのか。
人間は自分の死については体験して考えるってことはできませんけれども、自分じゃない他者の死と向き合うことでしか死については学ぶことできないんです。
それが今のところやはりほとんどマイナスの意味しか持っていないっていうのかな。あー、どう言ったらいいのか。「一生懸命したけれども、結局良くもならなかったし、死んでしまいました」っていう人たちが現実に多いわけです。じゃあそれをどう考えていくのかって。
その意味で僕は最近「死ぬ」っていうことについて考えています。普通、死というのは個人の能力の全面的な否定ですよね。もうその人立てない、歩けない、しゃべれない、食べれない。まあ言ってみたら、焼いてしまったらもう目の前にいなくなるっていうことですから。その人の能力ということで言うと、すべてができなくなるっていうか。
だから「人間死ねばゴミになる」みたいな言い方も、ある意味ではできてしまう。でもその人が自身のために何をするか、ではなく考えるとしたら、死ぬ、この世を去るっていうことは何か。そんなことを考えていた時、僕はふっと「席を譲る」っていう言葉を思い浮かべたんです。「この世の席を譲ってくれてるんや」と。この世での席。
「お先に。ごちそうさまでした」みたいな感じで出て行ったとしたら、死というのは、自分にとって何かできるわけじゃないですけど、人に譲るという行為になる。
最後に自分のこの世の席を、のちに続いて来る者たちに譲るんだというふうに考えれば、死というのは最大のやっぱり贈り物として、他者に対しての行為と言うことができるわけです。
その人自身にとってはもうできることはなくなるんですけれども、それも含めてすべてをその次の人に譲るっていうふうに考えると。
で、これね、別に僕がなんか特別に考えたことじゃない。よくよく考えてみたら、われわれは「譲られた」って思いながら、やっぱり生きてきたと思うんですよね。
次、まあ隠居にしてもそうですけど、歳をとれば若い者に席を譲るって、役割を譲っていく、どんどん譲っていくと。人が死ななければ人だらけになって、どんどん限られた世界になっていくし、次の新しいもんが生まれることができなくなってしまう。余地がなくなってくるわけです。
だからそういう意味では、必ず新陳代謝じゃないですけども、次のものが新しく生まれ、生きようと思えば、そりゃ死んで席を譲っていかなきゃいけない。
でも、これが普通にはなかなかできない。なかなか自分のものを人のために譲るっていうのはできない。死がすべての人に等しく与えられてるっていうのはこれはいいことで、いい人でも悪い人でもけちんぼでも気前のいい人でも、とにかく全員。やっぱり結局はこの席を譲るっていうかたちでこの世を去る。
そういう意味で個人個人ができることの能力にはいろんな差があるけれども、この世の席を譲るということではどんな人も同じなんだって、死という一点において。
そんなかたちで死の意味を捉えることはできないかと思っているわけです。そうすると最後の最後に、生きてる間は到底無理だった「譲り渡す」、自分のすべてのものを譲り渡すっていうことが、死ということで初めて可能になると考えることできるわけですよ。
サン=テグジュペリが死というものより、この命が死ぬということより大切なことがあるんだっていうのも恐らく、個人が何かを成し遂げるっていうことだけではやっぱり語り尽くせない、人間の生きる価値っていうのがあるんじゃないか。
さっき言った男っぽいスタイルのところありますよね。命を、自分の命なんか簡単にその会社の使命のために投げ出すみたいなところ。でもそれもどちらかと言うと、やっぱり何か自分ではないものに自分の命を「譲り渡す」っていうこと(捧げるっていう言い方もあるかもしれないですけど)。
それがものすごい問題なんじゃないかなって思います。それを間違えて読むと、サン=テグジュペリの冒険家精神っていうか前人未到のこう新しい夜間飛行を達成したとか、南米への航空路を開拓したとかいう、何か「できた」ってところで評価してしまう。
そうじゃなくて、自分の欲望とか、自分の何か願いとかじゃないもの、そういうものを超えたものに対して自分の命をこう対峙させて生きていく。
死ぬという行為
西川:
そういうことが、恐らく『星の王子さま』では繰り返されている。「一度なじみになったものには責任があるんだ」「だから帰るんだ」っていう。そういうかたちでかなりソフトな感じになってるわけですけど、根っこに流れてるのはたぶんそうなんですよ。
それをみなさまはどう思うかっていうことですけど。僕は少なくとも今、誰かのために死ねるかっていうと、うーん、可愛い子どもたちの顔を思い浮かべても、誰の顔を思い浮かべても、ちょっと死ねない。
その人を助けに行ったら自分が確実に死ぬと分かってる時に、自分が助けに行けるかっていうと、うーん、たぶんできないんじゃないかなって、やっぱり思っちゃうわけです。
でもそんな僕にも必ず死が訪れるわけですよ。生きてる間おくびょうであって、その自分の持ってるものは手放したくないっていうようなけちんぼが、それでも最後の最後にはそうやってこの世の席を誰かに譲って行くっていうかたちでこの世を去っていく。
だから看取りっていうのは「譲ってもらい・もらった」ことを受け取るのが大事なわけです。「安楽な死を迎えてもらおう」と緩和ケアなんかでそういうことをよく言うわけですけども、死にゆく人に何か援助するっていうのは、やっぱり僕ベクトルが間違ってると思う。
生きてる間に、だからあんまり大したことはできないわけですよ。しょせんケアが何だかんだって言ったところで。言ったところでやっぱり自分可愛いんですよ。ついついやっぱりね、「自分たちのケアが良かったから、この人はこんな安らかな顔をして亡くなったんや」とかって、自分の手柄話にすぐ回収しようとしてしまう。
そういうのがまったくなかったら、人間はそういう仕事に耐えられないんですよ。でも、人がこの世を去るっていう時には、そういうものすべて捨てて次のものに譲る。僕たちは、看取りの中で、そういう意味をやっぱり受け取って行く必要があるんじゃないんかなあって思います。
認知症ケアなんていうのは、だいたい自立支援だとか、いったん獲得した能力が低下してきてるのをもういっぺん何とかして元に戻そうだとか、もうなんかわけの分からん話ばっかりやってるんです。
そうではなくって、だからできなくなったかのように見えるがゆえに、今まで「できる、できない」の世界で生きてた人間は決してできないこと、つまり席を譲るっていう。まあ最後はそういうかたちの存在になりうるんじゃないかって思います。でないとあまりにも、人をケアするっていうのの最後が悲しすぎる。
「何とかこの人のために。この人がもっと元気になってくれるように」とか、まあとどのつまりはちょっと「安らかな死に顔でした」みたいなところで満足しなくちゃいけないわけですけど、安らかな死に顔よりもにこにこ笑ってくれるほうが嬉しいに決まってるわけです。何かどっかでごまかさないといけない。
「天国に召されたんだと思います」みたいなかたちで言うよりも、事実、死というかたちでこの世の席を譲ったんだっていうことを、やっぱり考えたいですね。そういう人たちがいなければ、私たちの生はないし、私たちの生もそれにしがみついてたらその後ろから来る人、のちに来る人たちっていうか、の命もないんだと。命というのはそういう連綿とした流れの中での役割でしかないんだっていうことを、もっと考える必要があるんじゃないかと思います。
そういうことが今ほんとうに分かりにくい時代になってるわけです。こないだ家族の会の代表のお母さんが98歳で亡くなったんです。98歳で亡くなられて、17年間お家で介護されてた。葬儀の時にその代表がひと言言ったのは、お母さん小春っていうんですけど、「小春は自分が生まれた家で98年の生涯を終えることができました」って。
すごいと思いません? 98年前からある家なんですよ。ここなんかでも古いですけど、ちょっと田舎の家の歴史のある家だったら、おじいさん、亡くなった人の肖像写真がいっぱいありますよね。肖像写真がなくても位牌があったりだとかってかたちだったり。家っていうのは一人の人生よりも歴史が長いんですよ。そんなところで生きてきた人にとっては、自分より大いなるもの、そういう家で自分は生まれて育って、またその大いなるものに抱かれたままこの世を去るっていうことです。
ところが僕たちはですね、明治以降っていうか個人の自由というか居場所も自由やし、とんとことんとこ居場所変えるわけですよね。この後ろに出てきますけど、「人間て可哀想だねえ」って「根がないからねえ」って「ころころ風に転がっていくよね」みたいな感じですね。
となってくるともう自分だけですよ。自分がすべての基準なわけです。病院のこう壁を見ながら死んだところで、そうじゃなくて自分がやっとの思いで住宅ローン組んで買った家の中で死のうと何であろうと、それは自分の歴史よりももっと短い。そういう箱の中で亡くなっていくわけです。
これで、大いなるものの中に抱かれたって思えるでしょうか。やっぱり思えないですよね。「私が死ぬ」としか思えないですよ。でも、そういう自分が生まれ育ったっていうことも、自分の生まれ育つ前、自分の父母も、その前も、っていう長い歴史なんです。
別にそんな大きなお屋敷でなくてもいいんです。家でなくても、その故郷の景色でもいい。山でも、って山もいきなりなくなったりしますけど。まあ、山や海とかね。そういう人間の一人の人生よりももっと、大いなる自然の環境っていうもの、自分の生まれ故郷としてイメージがあれば、やはり自分を超えたものの中で自分が命を引き受けて、さらに次の誰かに引き継ぎながら生まれ育ち、そしてそこに抱かれて死んでいくって思えるんでしょう。
今、僕たちはそうではなくて、すべてを自分の都合のいいようにやっちゃうわけですよね。住むところも、自分が住みたいところに住むわけです。それで風が入ってこないように、虫が入ってこないようにサッシにする。そんなかたちで自分にとって都合のいい小部屋の中に生きるような生き方をしてるのが、まあ現代社会なわけです。
自分を超えた何かっていうものと向き合う生活をほとんどしてない。昔は、文明とか科学技術がそれほど発達してなかったし、市場化されてなかったから、ある意味自然と向き合いながら生きざるをえなかったわけです。でもそれはある一方では、常に自分の命っていうものを支える大いなるものとの繋がりっていうことが感じられてた時代なのかもしれない。
でも、今も同じように自然はあるんですよ。自然はあるし、僕たちの命っていうのも、出生の時に「西川勝」になって、死亡の時に、この戸籍消えるんですけれど、これは近代法学的なところでの人間のあり方であって、自然界の中での人間のあり方では全然ないわけです。
だから自分というものの存在を、言ってみれば契約的な、近代の法的な制度の中で「誕生から死まで」みたいな、その間の「人格」みたいな、「人格同一性」みたいなことをいろいろ言うわけです。そうじゃない世界観とか死生観ていうようなものをやっぱり考えないと、とどのつまりわれわれはなんか非常に悲しい、悲しい人生の終わり方をしなければいけないんじゃないかと思います。
この本を翻訳した稲垣直樹さんが、清水書院でずいぶん若い頃にサン=テグジュペリに関する解説書を書いています。サン=テグジュペリは1900年生まれですから、19世紀の人なんですよ。20世紀に活躍した人でも19世紀生まれ。まあ言ってみたら、貴族が没落していく時代の最後の貴族なんです。
だから伝統とか習慣だとかっていうものをすごく大事にするんですよね。その伝統、習慣の中の守り神としての女性像っていうのが、サン=テグジュペリの他の小説の中にもいっぱい出てくるんです。まあこのバラに関してはちょっと違うかもしれませんけども。
習慣が大事だっていうような話ありましたね。バオバブのときね。「自分の身支度をするのと同じようにして、星の身支度をせなあかんねん」とか、ああいう話なんかもです。彼は自分のこう願望だとか自分の能力とかで自分の生き方を決めるんじゃなくって、先祖代々っていうか、ずーっとこう受け継がれてきた人の生きるかたちっていうものを大切にすることの意味を書いてます。
普通、われわれは、そんなしがらみから逃れて、自分の個性を自由に発揮させるべきだっていうような教育を受けてるし、そこに価値があると思っているんです。けれど、その最後は個人として死んでしまうということであれば、これね、ものすごいさみしい話なんですよね。さみしい話になってしまう。
『星の王子さま』の中で、生と死についてはあまり理屈っぽく書いてないんですよね。他の小説ではいろいろサン=テグジュペリ言ってますけど、『星の王子さま』の中では、非常に暗示的にしか物語の中では出てきてません。でもやっぱり大きなテーマとしてあると僕は思います。
キノコという悪口?
西川:それとキノコ。「人間じゃない、キノコだよ」って。なんで「キノコや」とか言うと思います?まあここらへんからちょっと、みんなの意見聞いてみよう。なんでキノコやって言うと思います?
D:うーん、なんか、
西川:キノコってフランス語で悪口なんかな?
D:なんかまあ生き物みたいだけど、別に血が流れてるわけでもなくって、みたいな、
西川:「キノコだよ、人間じゃないキノコだよ」。人間じゃないと言えばそれだけでぐさっときますけどね。だけどキノコだって言われたって、なんかドコモのあのキャラクターじゃないけど、キノコが可愛いっていうやつもいますからね。どう思いますか?
C:英訳ではマッシュルーム。
西川:うん。フランス語ではchampignon(シャンピニオン)ですけどね。
C:一緒なんです? おんなじこと?
西川:うん、同じです。
西川:ね、どう思います? これ。なんで「キノコだよ」って。なんでキノコやろね? これ。「人間じゃない玉ねぎだよ、中身がないんだから」とかって言うんだったらわかるけど。
A:頭でっかちってことですかね?マッシュルームの形が。
西川:そうだね。頭でっかちはだめだっていう価値観ですね。「あの人頭いい」っていうのを、「そんなん人間じゃないよ、キノコだよ」って、サン=テグジュペリだったらたぶん言うね。「あの人頭いいなあ」って言ったら、今の世界やったらほめ言葉やけど、「そんなん人間じゃないよ、キノコだよ」ってなってしまうのかもしれない。いかがですか?
A:えー。いやあ、分かんないですね。
西川:
いやいや、別に答えないですからね。でもそこらへんも考えていくと面白い。血も出ないしっていうような部分、なんかかさかさに乾いててね。あと花が咲くわけでもないし。でも食べれるけどなあ。でも美味しそうに見えるやつは食べたら当たったりするしね。まあ頭でっかちっていう感じはほんとに形としてそんな気はしますけどね。僕最初分からなかった。キノコって言われてそんなに傷つくかなあと思ってね。
王子さまにとっての「まじめなこと」
A:
「もう何百万年も前から、花たちはトゲをこしらえているんだ。もう何百万年も前から、ヒツジたちはトゲがあっても花たちを食べているんだ。身を守るのに、なんの役にも立たないトゲを、なんで花たちはそんなに躍起になってこしらえるんだろう。そういうことを知ろうとするのは、まじめじゃないっていうのかい? ヒツジたちと花たちの戦いは大切じゃないのかい? 赤ら顔の太った男の金勘定と比べて、まじめでも、大切でもないっていうのかい? ぼくがこの世でたった一輪の花と知り合いで、その花は、ぼくの星以外ではどこにも生えていない。ある朝、ちょっと魔がさして、小さなヒツジが花をぺろりと食べてしまうことだってある。それがね、大切じゃないっていうのかい?」
王子さまは真っ赤になって怒りました。それから、先をつづけました。
西川:
シープ(sheep)って言ったら単数も複数も一緒ですね。でも、ここでわざわざ稲垣さんは「<ヒツジたち>はトゲがあっても花たちを食べているんだ」とかって、複数にわざわざこう訳してるんですよ。「何百万年も前からヒツジはトゲがあっても花を食べるんだ」って訳したほうが何となくすっと分かるはずなのに、わざわざ「たち」って言ってるんですね。
「小さなヒツジが花をぺろりと食べてしまう」っていうのは、これは実際に王子が連れて帰るヒツジが、王子が大切にした花を食べるっていうことなんです。ここらへんが稲垣さんてすごい人だなと思うんですよ。そういうふうにきちんと複数にするとかしないとかっていうことをものすごく考えているんじゃないかなって。
単純に概念的なことじゃなくって「ヒツジたちと花たち」っていう群れ同士の戦いみたいなもの。単純に「ヒツジは花を食べる」とかじゃない「ヒツジたち」です。わーっと群れでいると、様々なヒツジたちのなかには花を食べないやつもいるかもしれないけど、「ヒツジたち」という群になると、花たちはなんか「食べられる」みたいになる。花たちもこうトゲをこうまとって「食べられたくない」って身を守ろうとする。
だから歴史上どちらかがどちらかを全滅させてるわけじゃないでしょう?何百万年も攻防が繰り返されてるわけですよ。「ヒツジは花を食べる」って言うたら一つの普遍的な真理のようになります。必ずヒツジはバラを食べてしまう、っていうふうにはっきりしてしまうんですけども、「何百万年も前からヒツジたちは花たちを」っていうふうにすると、具体的なヒツジと花とのこうやり取りっていうか攻防みたいなものが目に浮かんでくる。僕はものすごい丁寧な翻訳をしてるなあみたいなことを思います。
「なんで花たちはそんなに躍起になってこしらえるんだろう。そういうことを知ろうとするのは、まじめじゃないっていうのかい?」
でもこれ、要するに答えは分からないわけですよ。トゲはほとんど役には立たない。ヒツジは目の前にあるものだったら何でも食べるわけです。トゲがあったって何があったって。何百万年も前からそんなふうにして、ヒツジたちに襲われたりだとかしてるのに、なんでバラがいまだに躍起になってそんなトゲを作ろうとしてるんやろうってことは分からないわけです。
でも「そのことの理由を知ろうとするのが、まじめなことじゃないっていうのか」って王子は言ってる。考えたところで分からない不条理な出来事なのに。
たとえば、「なんで人は死ななあかんのに生まれてくるんや?」を「そういうもんなんや」で終わらせない。そういう考えても考えても答えの出そうにないようなことです。考えたからといって、今日明日の人生や暮らしに何か大きな変わりがあるわけでもないし、知ったところで相変わらずヒツジたちは花たちを食べようとする。でも「なんでその花たちはそうやってトゲを作ろうとしているんだろう」「それを知りたいっていうことは、まじめな願いだろう」って王子は言ってるんです。
それに引き換え、「このボルトを緩めて機械が直ったら、この水のない砂漠から俺は帰れる」ってこれ、はっきりしてるわけです。そしてパイロットは「だからそのことで僕は手いっぱいなんだ。まじめなことで手いっぱいなんだ」って言ってる。でも王子は「そんなことはまじめじゃない」って言ってるわけです。分かります?
王子は、いわゆる答えが出るものについてあれこれ考えることについてはまじめじゃないって言ってるわけです。それは大人がまじめって言うだけだと。本当に考えなくてはならないのは、ヒツジたちとバラたちとの間の、なんか一見理解し難いようなこの戦いの意味っていうこと。そのことを知ろうとすることのほうがずっとまじめなんだって言ってるわけです。
これも、みなさんどう思います?簡単そうに書いてあるけど、これはそういうふうにまで突き詰めて考えてみると、なかなか「そうやね」とは言いにくいですよ。考えても答えのないようなことを、って、どんなことがあるんでしょうね?
やっぱり僕たちは考えてもしょうがないことはあんまり考えなくなってるのかな?みなさんどうですか?「これを、このことを考えるっていうことが、まじめじゃないっていうのかい?」って言えるような問いを自分が持ってるかどうか。「六十五になったらどうやって暮らしていこかな」みたいな老後の生活設計とか、「いや、これから自分のキャリアパスをどうしようかな」とか。そういうことはだいたいまじめなことやと言われてるわけですよ。
でも王子に言わせたら、「そんなことはまじめなことじゃない」って、「おとなみたいな口の利き方をするね」って言うんですよ。まあ、老後の生活を考えるやとか、自分のこれからのキャリアをどうするかなんてことは、死にかけの砂漠で飛行機のエンジンを直すことよりはずっと卑近なことです。もっと命かかってることを一生懸命やった時に、王子はパイロットに怒るんですよ。
「君はおとなみたいなこと言うね」みたいに。それで、そのヒツジたちと花たちとの戦いについて考えろと「これがまじめじゃないって言うのか」とかって言って怒るんですよ。ねえ、だんだんついていけなくなるでしょ。「なんだ、こいつ?」みたいにね。
でもそう思った時に、はたして自分に、この王子のように「こういうことを知ろうというのは、まじめじゃないとでも言うのかい?」って、こう本気になって怒れるような、自分が知りたいことって何かあるかどうかですよ。「なぜ僕は、なぜ僕は亀じゃなく人間に生まれてきたんだろう」とかね。普通は笑われてしまうわけですけど。
そして「なんでバラはそんな役にも立たないトゲを作るの?」「そんなんいじわるなだけや」って、またパイロットは王子にボロクソに怒られてるわけです。ちょっと理屈になりそうなこと言ったら怒られるわけです。
真剣に命のかかってるエンジン直してるときにも怒られ、それでもういろいろ言うから、もう「それもバラがいじわるやからやろ」って、とりあえず理屈としては分かるじゃないですか。でもそれ言ったらカンカンになってまた怒られるわけですよ。
この王子は、いったいどんなことを考えたい、っていうか知りたいと思ってる人なのか。それを自分に引き写してみるとどうなんでしょうかね。
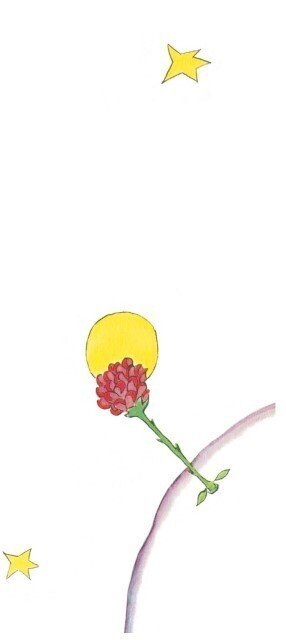
満天の星が光を失ってしまう
A:
「何百万、何千万という数の星に、たった一輪しか咲かない花をだれかが好きだったら、そのだれかが星空を見あげるとき、たったそれだけのことで、幸せだな、って思うんだよ。その子はこんなふうに独り言を言う、『あの満天の星のどこかに、ぼくの花が咲いているんだ……』ってね。けれども、もしヒツジがその花を食べてしまったら、その子は感じるんだよ、まるで満天の星という星が急に光をなくしてしまったみたいにね。そういうことが大切じゃないっていうの?」
もう、それ以上、王子さまはなにも言えませんでした。突然、王子さまは、しくしく泣きだしてしまったのです。夜のとばりがもう降りていました。ぼくは手から道具を放りだしていました。「ハンマーがなんだ、ボルトがなんだ、喉がカラカラに渇いていることがなんだ、死ぬことがなんだ」そんなふうにぼくは思っていました。「ある星、ある惑星、ぼくの星、この地球の上に、慰めてやらなくてはいけない王子さまがいるんだ!」ぼくは王子さまを両腕に抱きかかえました。王子さまの体を揺すりました。王子さまにこんな言葉をかけながら。「だいじょうぶだよ、君の愛する花は、危ない目になんかあいっこないよ……。君のヒツジにはめるように、ぼくが口輪をかいてあげるからね……。君の花を守るように、花の覆いをかいてあげるからね。ぼくは……」ぼくはなんと言ったらよいか、よく分かりませんでした。ぼくは自分がじょうずにものが言えないと思いました。いったいどうしたら王子さまの心に触れ、王子さまの心に寄り添えるか、分かりませんでした……。ほんとうに不思議なものです、涙の王国というものは。
西川:
ここもすごく大切なことがいっぱい書いてあるところです。最後まで今読んでもらった部分は『星の王子さま』の物語に影響してきます。「君のヒツジにはめるように、ぼくが口輪をかいてあげるからね」って言うんですけど、口輪を描いても、口輪をはめる革紐を描くのを忘れたみたいなみたいに。
だから「ヒツジがバラを食べてしまったとしたら」、それから「いや食べなかったとしたら」「満天の星が変わる」みたいな話も最後のほうにも出てきます。
あと「何百万、何千万という数の星に、たった一輪しか咲かない花を」っていうのもですね。これもこの「たった一輪しか咲かない」っていうのが、どう言ったらいいんかな、数えられる一輪っていうかではないんですね。
あとで出てきますけど、五千本ものバラと出会って王子は泣き伏すんですよね。「この世界にたった一本しかないと思ってた花が、ここにはこんなにある」みたいな感じでね、泣いちゃうわけです。
でももう一度「たった一輪しか咲かない花」ってここでは言い換えてるんです。いったんがっくりきたんですよ。この、だからこれは二回目読む人しか分からないんです。「たった一輪しか咲かない花」っていうこの「たった一輪」っていうのを、「この世に一輪しかない」と王子は思い込んでた時期があったわけです。まだ他でバラ見たことがなかったから。
でも地球にやって来てバラ園見て、「えーっ」ってこう「こんなにある」って思って、「僕は宇宙でたった一輪しかないと思ってて、だからって思ってたのに、こんなにたくさんある」って思ってがっくりくるんですよ。
がっくりくるけれども、またここで「たった一輪の花」っていうふうにバラのことを言い直してるんです。だからそれはまた後ほどどういうふうにしてオンリーワンになるのか、そのことの意味ですね。数えられる1から、どう言うたらええんかな、ちょっとうまい言い方見つかりませんけれども、意味が変わってくるっていうことはまあちょっと気をつけといてもらいたいです。
45ページに「そういうことが大切じゃないっていうの?」って書いてあるじゃないですか。「そういうこと」を言い換えるとどうなると思います?
「幸せだな、って思うんだよ」って書いてあるじゃないですか?だから、幸せについてですよね。でもその幸せはいかにももろくて儚くて、っていうことです。でその儚さっていうのは何によるのかっていう。
これ世界まで変わってしまうっていうことですよね。「好きだったら」「満天の星が変わる」。誰かを好きになるっていうこと、それは幸せになることだ。でも、たったそれだけのことで「幸せだな」って思うんですからね。誰かを好きになるっていうことは幸せになることなんですよ。
でも、「もしヒツジがその花を食べてしまったら」。その花がいなくなったとしたら、さっきの言ってる、何遍も言ってる死の問題もそうかもしれませんけど。「好きな人があそこにいるんだ」と、「いるんだ」って思ったらたとえ遠くても幸せだけど、近くにいてても「もういないんだ」と思ったらだめになっちゃうわけですよ。幸せじゃなくなってしまうわけですよ。
だから好きになるだけじゃだめなんです。その好きになった相手がいないとだめ。でも、そんなふうにして幸せっていうのは、相手がいるいないで、儚い、がらっと変わってしまうような、その幸せっていうのは自分の気持ちだけじゃないって言ってるわけです。満天の星の光が変わるって言ってる、この世界が変わるって言ってるんですよ。
自分の心持ちだけが変わるって言ってるんじゃないんですよ。この世の世界から好きだったその人が一人消えてなくなったっていうだけのことじゃないんです。星までが光を失ってしまうっていう。
で、今はこういうふうに捉えがちなんですよ。分かります? 認知症ケア一生懸命やってて、「たとえ認知症になってもいい」「僕の、私の目の前にいる」「一生懸命ケアするっていうこと、大切にするっていうことで、今までとは違う人生が見えてきた」って多くの家族さんが言います。
でも、いなくなったら世界が変わる。ガシャッて変わってしまう。いや、「それでいいのかなあ」「どうなんだろう」っていうことです。
沈黙と涙の王国
西川:
続いて「もう、それ以上、王子さまはなにも言えませんでした」ってなってます。だから、そういう幸せとか愛だとか、幸せと愛の関係、そして愛する者がいるいないで世界が変わってしまうっていうような、愛と世界の移り変わりの不思議みたいなこと、を考えると、その次の言葉、もう出てこないんです。もう泣くしかないっていうことになっちゃうんです。「しくしく泣き出してしまったのです」ってなる。
「もう、それ以上、王子さまはなにも言えませんでした」って、ワーッてもう怒り倒して、文句言い倒したわけでしょ? 言うだけ言ったあとの沈黙に何があるのかっていうことです。言ったことだけに王子の言いたいことがあるわけじゃないんですよ。
あと、黙るっていうこと。「もう何も言えなくなる」っていうかたちで言うことの意味。言葉が生まれる前の沈黙と、言葉を発したあとの沈黙っていうのはやっぱり僕は意味が違うと思うんです。
ここで王子があれだけ真っ青になって、真っ赤になって、パイロットに言い続けたあとの沈黙にはいったい何が意味されているのか?まだここに何にも書いてないんです。だから「ハンマーがなんだ、ボルトがなんだ」って「死ぬことがなんなんだ」っていうふうにパイロットは変わってるんですよ。これ「キノコだ」とかって、わーーと言われたから変わったわけじゃないんですよ。
「夜のとばりがもう降りていました」っていうの、これも上手いですよね、サン=テグジュペリ。夜のとばりが降りてたらもう暗くて修理はできないですよ。だからそもそももう道具放り出すようなことになってるんです。そういう生き死にの話を放り出す。沈黙とともに夜のとばりが降りて、そして涙の王国に連れて行かれるっていうふうになってるわけです。
この涙の王国っていうのは聖書的な意味があるのかな? 涙の谷っていうのはあるよね?
D:うん、そうですね。
西川:
涙の王国っていう言い方は、僕、聖書の中での話はよく分かりません。だから、この涙の王国は、僕いまだによく分かりません。
「ハンマーがなんだ、ボルトがなんだ、喉がカラカラに渇いてることがなんだ」って言ってるのは、全部これパイロットの身の回りのことです。ちっちゃいちっちゃい世界ですよ。ハンマーは自分が持ってたもんです。ボルトも自分がやろうと思ってるボルトですね。喉も自分の体のことです。「死ぬことがなんだ」って、自分の命です。
じゃなくって、そのあとは「ある星、ある惑星、このぼくの星、この地球の上に」って、めちゃくちゃでかい宇宙の話に変わってるんですよ。見てる世界がまったく広がっていくっていうか、全然違ったものに変わるわけですよね。
この変換を起こしたものはいったい何なのか。何がパイロットをこういうふうに、目の前にあるっていうか自分のそういうせまーい世界から、こんな宇宙的なところにまで引き上げたのか、っていうことですよね。
ぼくは自分がじょうずにものが言えないと思いました。いったいどうしたら王子さまの心に触れ、王子さまの心に寄り添えるか、分かりませんでした……。ほんとうに不思議なものです、涙の王国というものは。
必死になればなるほどこうなってしまう。相手の心に寄り添うだとかね、そういうことはケアの場面でもいっぱいつらい話を聞いて、何とか、何とか慰めてあげようっていうか力になってあげようと思っても、相手がもう何も言わずにただ泣いているっていったときには、もうかける言葉もなくしてしまうっていうことなんでしょう。
涙の王国っていうものにみなさんは出会われたことがありますか?僕は結構あるんです。でも結構逃げてしまうな。逃げてしまいますよね。
沈黙をきく
西川:
『南方郵便機』っていう、さっき処女作の話しました。ジャック・ベルニスっていう主人公がいるんですけど、彼は港、港じゃないですけど、飛行機場、飛行機場に女を作るわけですね。もう命がけの仕事ですから、そんなつかの間の愛をやるんです。
当時の郵便飛行は命がけの仕事なわけです。次の飛行機に乗るって言ったら、女たちは止めようとする。それこそ船乗りを止める港の女みたいなもんですけど、泣かれるのは嫌だから、疲れさせるだけ疲れさせといて、夜中の三時ぐらいに涙で濡れた女を放って出て行く。ってな感じのことをサン=テグジュペリがいっぱい書いてました。僕には「こっちのほうがよう分かるけどなあ」と思ったり。こうやって「涙の国というものは不思議ですよね」って言われてもね。
ともあれ、この時、このシーンにパイロットがこれだけ大きく変われる何かが、この王子のあれだけ怒ったあとの沈黙と涙にあったんですよ。説得されてパイロットは変わったわけじゃないんです。だから「ほんとうに不思議なものです、涙の王国というものは」っていう、そう思える人だから変われたんですよ。
「いったい何が言いたいの?」「何が困ってるの?」とか言って、相手からいくら言葉を引き出したところで、やっぱりそばにいる人間ていうのは変われないんですよ。
そうじゃなくって、相手がしゃべるだけしゃべったあと、もうものが言えなくなってしまって、涙の王国の住人になってしまった時に「不思議なものです」ってなる。「自分はじょうずにものが言えない」って思った時に、そのそばにいる者のありようがすさまじく変わるっていう。
普通は、自分のことをちゃんと言えない、ただ泣いてるだけみたいな人に対しては「援助者としてはお手上げや」って「何がしてほしいのか分からんし、ただ泣いてるだけじゃ分からん」みたいなことになっちゃいますけど、そうじゃないんですよ。
そうじゃなくって、大きく変わるときにはその沈黙と涙の王国の住人に対して「ほんとうに不思議なもんだ」っていうことをこう感じられるかどうかだと思うんです。どう思います?
僕はそういうことが書いてあるんやなっていうことは分かりますが、その涙の王国に触れるとどうだろうなあ。まあ、昔、精神科で働いていたとき、エッセイでも書きましたけど、『夜空のラーメン』ってのがありました。
いきなり泣かれて、「わーっ」て「僕生きてていいんですか」とかって言って、ラーメンの汁半分やったやつが泣き出して。もう唖然としてしまった時がありました。
あの時はこんな感じがしましたけど、あれだけ真っ正直に出してくれる人ってそんなに出会えません。ちょっとこちらが慰めめいたことを言うたら、「ありがとうございました」って頭下げる患者さんばっかりですからね。えー、時には「お前らに何が分かる!」ってにらみつけられることもあります。
怒りでぶわーって言われることありますけど、怒りのあとの沈黙まで僕は聞いていなかったのかもしれない。王子が真っ青になって、「このキノコ!」って怒る。そこまで僕が聞けなかったのかもしれません。
「まじめなこと」ってなんでしょうね。「君はなにもかも、ごっちゃにする……。なんでもかんでも、いっしょくたにする」「つまらんことも大切なこともごちゃまぜにしてる」「何が大切なのかをきっちり分けないといけない」。その時の王子が言ったまじめなのこと。
普通、僕たちが暮らしている中で至極大切だと思われてることを大切とは言ってないです。それから、パイロットは王子の言ったことで「変わった」わけではない。言えなくなって、沈黙になって、涙の国の住人になって、その人のそばにいたことで「変わった」んだっていうこと。
この二つが『星の王子さま』を読んでケアを考えるときに、非常に大切なところかなと思います。普通、沈黙と涙だけでかける言葉もないって言うたらディスコミニケーションの最たるもんです。泣いてる人に慰めの言葉ももう見つからなくなってしまってるわけですからね。でも、ここにものすごく大切なことがあるんじゃないかっていう予感が僕はするんです。
今日はこれぐらいで終わろうと思います。みなさんにもいろんなところで考えてもらって、何かあれば話してもらえればと思います。
見送りが暴動になる?
D:うーん。もう死ぬこともどうでもいい、みたいな、くらいの大事なことっていうのがあるんだなあっていう。なんかそうだなあ、愛する、そして失うっていうことがまだちょっとよく分かんないっていうか、その。うーん。
西川:誰かを好きになる、それだけで幸せになれるんだっていうのが分からないっていう?
D:うーん、そうですね。そうなったことないのかもしれないなと思うんですけど。
西川:まあ錯覚かもしれんけどね。
C:正しいとかは置いといてその、大きな、大いなる者に抱かれて亡くなっていくっていうのはまあよく分かるんですけど。まあ実際、今自分がもうそんな歴史のある家に住んでなくって、マンション住まいしてて、そういう人いっぱいいるので、もう既にそういう人にとっての死ってね、大いなる者に抱かれたいなあって思ってても、叶えられないような死でしょ?
西川:家に関して言ったらね。
C:家に関してね。だからその、東北なんか行くと、結構昔の日本の、良き日本というかは残ってますよね。まあ津波でこう破壊された地域はすごく気の毒ですけど、原発はもう一つ悲惨やけどね、飯館村とか…。そういう、とか、あと昔の人だって、由緒正しかったりお金のある人はそうやって大きな屋敷持ってね、代々が連なってたかも分からへんけど、庶民の人たちってそら時代によってはほんとに化野(あだしの)[*5]とか鳥辺野(とりべの)[*6]とかね、京都の葬送地が三つあるでしょ? うーん、北大路千本のあたりとか。
[*5] 化野(あだしの):京都の嵯峨の奥にある小倉山の麓の野。古くは山城国葛野(かどの)郡嵯峨といい、かつては風葬の地、近世は鳥辺山とともに火葬場として知られた。
[*6] 鳥辺野(とりべの):京都市の一地域を指す地域名。平安時代以来の墓所として、北野蓮台野、西の化野とともに京都の三大墓地をなしている。
西川:結局、所払いっていうことが一番の刑罰だからですね。自分たちが生まれ育ったところから追い出されるっていうこと、コミュニティから除外されるっていうこと。だから「家」っていうのは、それがコミュニティであったり、まあ何か別のものがやっぱり必要ですよね。きっとね。顔なじみの人たちに見守られてっていうか、まあ死のその時でなくてもいいんですけれども、どうなんでしょうかね?
C:あの、釜ヶ崎のおじさんらはどうなん…、あのー、無縁…、いっぱい集まってきはるでしょ? 亡くなってからそういう独特な葬送のやり方ってあるのかな?
西川:
見送りの会っていうのがあります。「あっこちゃんの会」のあと、僕といつもよく飲みに行ってたEさんっていう人がいました。生活保護のおっちゃんに酒おごってもらってましたけど。
彼がひと花センターにあんまり来なくなって。「どうしたんかなあ」と思ってたら、酔っ払って街でけんかかなんかして、それで殴られて帰ったみたいな、ちょっと意識がぼーっとしてたみたいな感じで、部屋でタバコ吸って、それでボヤで全身大火傷になって、結局病院で亡くなって。
事件性があるっていうことで、警察にずっと死体置かれてて葬儀も何もできなくて。で、親戚も引き取りに来なくって、40日後に葬儀が行われました。まあ彼自身もそういう見送りの会っていうのをしてましたね。まあ孤立死は仕方がないね、もう。
死ぬ時にそばに人がいないっていうことはありうる。でも葬送の儀もないみたいなのが、釜ヶ崎の場合現実なんですよ。だからそれは自分たちの中で何とかしていこうっていうふうにやってたんやけど、その願いもなかなか叶えられなくって。
実際には法律的に難しいんですよ。要するに親戚でも何でもないのに「遺体よこせ、葬儀するから」言うたって。葬祭権っていうんですか? なんかそういうものを譲り渡すとかそういうことをいろいろ手続きしないと、実際にはやりづらいみたいです。
本当にね、法律でがんじがらめになってるところあるんです。そこからいったん外れたら最後、戻れないんですよ。うん。今の社会というのは甘いもんじゃなくって、毎日毎日ひと花センターでこう仲良く話している人であっても、いったん亡くなったら関係のない人ですから。
どんなにその「誰それさんの遺体に会わせて」って言ったって、「あんた関係ないから」って会わせてもらえない。検死に行って、検死から生活保護だからって、役所の葬祭扶助の葬儀をするところに持っていかれて「葬儀をやった」っていうことになって、無縁仏に納骨されるみたいなことがもうほんとに横行してるわけ。横行っていうか、それが通常の行政の処理の方法なんですよ。
だからそれに対して、見送りの会ってやっているのは、美談のように見えるけど、行政的にはものすごくめちゃくちゃ反抗的なんです。もう暴動とおんなじ。要するに世間のルールを「それおかしいやろ」って言ってるわけで。昔みたいに物投げたりだとかっていうわけじゃないですけど、基本的に社会のいうことを聞いてたら、それこそ人間の情が通らない場面っていうのは山ほどあります。
だから、彼らが今一生懸命求めてるんだと思いますよ。自分が生きてる時に、孤独の中で、少なくとも見送りの会の活動なんかしてる人たちは、その孤独に甘んずるっていう考えはないですよね。もう一度何とかして、ここで出会った縁を大切にしたいと思ってる。
でもそれは行政的になかなか支援が得られなかったりする。ひと花センターもそうですけど、あれは生活保護受給者の社会的つながり事業ですから、これも特区だからできるんですよ。生活保護を受けてるっていうことは、その生活保護ですべてを賄いなさいっていうこと。生活保護を受けてる人にさらなるサービスっていうのはおかしいっていうことになってるんです。分かります?
ひと花センターに行けば、講師がいてなんかするじゃないですか。講師には講師料出てるわけですから、お金かかってるわけ。そんなことを「何で生活保護のやつらにせなあかんねん」って。だから西成でないとできないんですよ。どこでもやったらいいと思うんですけど、できないのは、生活保護だと「個人に生活保護をしたらもうそれで終わり。あと一切だめ。儲けたらその生活保護費から引く」っていう。
厳然たる個人単位なんですよ。生活保護を受けることによって社会的に孤立してしまうっていうのは、よく考えたら変な話なんですけどね。変な話なんだけど、基本のベースがお金として行政から支給されたら、「もう人とは付き合うなよ」っていうことになっちゃうんですよ。
だから本当はほんとに理不尽な話です。ヒツジと花との戦いみたいなもんで。「世の中こうなってるんや」って言ったって、世の中っていうのが、政権が変わったら、もうころころころころ変わるわけですから。
僕たちが常識で言ってる「世間は」って言うときの世間っていうのは、ほんとにある時期ある政権のある政策でしかないわけで。まあ、よく分かりませんけど、はい。
C:ありがとうございます。
西川:
今、ひと花センターの予算は三分の一になりました。予算三分の一。もうたぶん人件費も払えない。今、四人でやってるんですけど1,500万しかないですよ、最初7,000万やったのが。給与払えないですよね。
そういうかたちでどんどんどんどん…。「しっかりやってくれ」って言うんですよ。「やってくれ」って言うけど金は出さないから、やめろっていうことです。
そんな感じで役人は金勘定で話するわけです。生活保護っていうものの法的な根拠とかっていうところだけ、非常にまじめな顔してしゃべるわけです。でもあの、そういうことがほんとに大切なのかっていうと、それこそ「お前ら人間じゃない、キノコだ」みたいな話になってしまうわけですけど。
C:理由、なんか後付けみたいですね。
西川:涙の王国に近づいたことのないようなやつばっかりが作ってるんでね。はい。どうでしょうか? 何でもいいですよ。
なぜ「その子」なのか
F:
えっと、シナリオの書く、去年勉強をちょっとしてきて、んで、何か一本書かなあかんかったんですけども。だいぶ以前に子ども電話相談室って、なんか春休みとかあるんですね。
で、ラジオでたまたま車乗ってる時に聞いたんですけども、その時におばあちゃんから電話かかってきて、孫と一緒に暮らしてると。お父さんもお母さんも事情があっていなくって、で小学生の孫なんだけど、ほんとにいい子なんですよ。もう、困らせない。でも自分ちょっと病気にならはって、おばあちゃんが。で、もうほんとにいい子だから逆に心配で、この先どうしたらいいか?みたいなことの電話相談をされてた。それをたまたま聞いたんです。
でこの、ちょっとそのシナリオ書く時に、その子のことはもう何年も前なんやけどずーっと心の奥にあって、その子の…、それをまあ、素材って言ったらまあ失礼なんですけども、書きたいなあと思って。まあまだ書けてないんですけども。
その時に「そんな子はまあやっぱ基本世の中いっぱい、そういう境遇の子はいる」と、まあ一緒に勉強してた人たち言ってて。ああそうだなあ、とは思ってたんですけども、やっぱ最終的に私の結論は、そのラジオで聞いたその子のことをやっぱり書こうっていう。
まあたまたま出会った、けど私にとっては気になって、まあそういう意味では馴染みになって、馴染みになったかけがえのない一人だなって思って。この先書けるかどうか分かんないんですけど。
その子のためにじゃないんですけども、その子のこと書きたいっていうほうが…、方向にやっとこう結論が。その一般的なそういう子のことじゃなくって、っていうのを。でそれがちょっと、こう『星の王子さま』読んでて、それとちょっと私の中で重なった部分がすごいあって、そういうことを思い出しました。はい。
西川:
はい。ここでも「前置きも何もなしに、突然彼は聞きました」「じっと考えてたその果てのように」って言ってるじゃないですか。だから簡単にぽんと言葉が出てきたように書いてるけど、実はその前に沈黙があるって書いてあるわけです。
前置きもなにもなしに、いきなり王子さまはぼくにたずねたのです。じっと口を利かないで長いあいだ考えてきた、その果てに口を開いたようでした。
だから、Ⅶ章がはじまる前にも、じっと長い間、口を開かずに考えてる。たぶんそのいい子っていうのはそうなんですよ。「なんでー? なんでお母ちゃんがいないの?」とか、そのこう、怒りの手前の沈黙っていうか。
でもさっきも言いましたけど、言葉の前の沈黙とそれから言葉のあとの沈黙っていうのは、やっぱり意味が違うって思います。僕たちはついついコミュニケーションって言うと、言葉の意味の交換で、「相手の言ったこと」を考えてしまうんです。
僕なんかもそう悪い癖があって、相手の言ったことを揚げ足取りばっかりして。そうすると必ず相手との関係悪くなります。必ず悪くなる。でも、大切なことっていうのはたぶんその、ある言葉を自分が触れたときに、その前にある沈黙、そしてそのあとに訪れた沈黙を、どれだけ自分が深く広く感じとることができるのかっていうことかもしれない。
僕なんかもうしゃべりですから、話す前の沈黙も短いし、話したあとの沈黙も短いので、あかんなあと思います。でも、そういうの大事だと思います。ほんとはシナリオでもそうですね。言葉と言葉の間ってすごい大切かなと思います。
「このキノコ!」「黙れ、粘菌!」
A:今日初めて参加させていただきまして。よろしくお願いします。子どもの頃にあの、読んだはずなんですけど、ちょっとこの、えっと平凡社のほうが見つけられなくて、今日来るまでにはちょっと読んでこなかったんですけども、今日のところを読んで、ですよね?
西川:いや別に、何でもいいですよ。
A:はい、あのー、そうですね、あの、これだけこの主人公の人が変わったのは、何でなんやろな? って、なんか普通に読んでたらたぶん普通に、なんか通り過ぎてしまいそうだなと今思いました。
西川:しつこいんですよ、ここの読書会。しつこいんですね。なかなか進まない。効率は悪いけれど、ゆっくり歩かないと見えない景色もありますんで、みたいな感じでやってます。
A:表面的に取ったら、こう生きるためのことよりもなんか大事な、生きることには何の役にも立たないけど、人間にはなんか大事なものがあるっていうようなことのようにも思えますけど、なんかそんな単純なことじゃないのかなあとか。
西川:
僕は『星の王子さま』だけじゃなくて、ここから自分に問われたこととして、もう本から離れていいと思ってるんです。「じゃあ僕にとってまじめなことって何かな?」とか「自分が涙の王国と出会ったことあるかな?」とか「誰かの沈黙のそんなに深く心動かされたことがあるかな?」、「自分の世界を忘れて、そんなもっと違うところで、この星、この地球の上に僕の目の前にって、みたいなこと考えたことあるかな?」みたいなね。
ただあらすじを知るんじゃなくて、自分にこう引き写してみて、大切な本になるのかならないのか。僕は『星の王子さま』ってそういう意味で、どっちか言うたらものすごく「痛い」本ですよ。
バラのとこなんか読んだら、痛い話ばっかりやしね。だから「痛いけれども考えたほうがいいよね」って思える本なのかどうなのか。結構大事なところをそれぞれが見つけていったらいいかなと思います。
G:沈黙の話があったんですけど。ハンマーの…、真っ暗で修理ができないからってその、うーん、私にとってはハンマーでボルトが緩まなくて、喉がカラカラに渇いている状況で、こんな気分にはとてもなれへんなと。なんか逆にすごいこう、王子さまに近寄るよりはなんか離れていくような、自分の状況からすると、そっちから移れへんやろなと思って。
西川:いや僕もそうですよ、もちろん。
G:ちょっと、だから理解しがたいな、みたいな。
西川:
だからここらへんが、こう物語としたら突拍子もないように思うでしょ?他のサン=テグジュペリの様々なやつを読むと、「やっぱサン=テグジュペリってこんなやつなんやー」みたいな「えげつないやつやなー」みたいなところがあるんですよ。
彼の人生を知るっていうことが、彼の生き方みたいなものを知ることが、この『星の王子さま』をある程度、リアルなものにするところはあると思います。これ僕が書いたって誰も感動しないと思います。
やっぱり背景がちゃんとあるんです。会ったことはないですけど、読んでみた限りではやっぱり強い印象を与える人だったみたいです。
長見:キノコ、あの、キノコってところがちょっと面白いなあと思ったね。
西川:ココペリでこれから流行る?。「このキノコ!」とか言って。
長見:キノコに失礼な気も。ココペリ、キノコ好きの人結構いるよ。
西川:いるなあ。
長見:だからHさんとか気悪くするんじゃないかと思ってね。
西川:「黙れ、粘菌!」とか言ってね。
長見:これ他のとこでも出てくるんですかね、キノコ?
西川:キノコは出てこないね。
長見:出てこない、これだけ? うーん、なんかかわいそうやな。
一同:(笑)
西川:実際に星めぐりの時に「キノコ」って言って文句言うかな?言ってないんじゃないかな?あー、銀行員には直接は言ってませんね。
I:僕もここはすごく印象深いところなんですけどね、この「君はまるで大人みたいな口の利き方をする」っていうのは。僕が大学院行く時になんかこう「研究をもうちょっと続けたい」って言ったら、「もう生活ができないから」って理由で先生が止めるんですね。うん。僕としてはそんな理由で止めてほしくなかったですよね。大学で研究をしてる研究者の人として、そこはね。
西川:そうだよね。
I:「そんなことはどうでもいいからやれ」ってとか、あるいは「もうちょっと、研究者としてこう劣ってるから仕方がない。やめろ」とかそういうようなね、僕の研究内容を見て批判してとかでね、して止めてほしかったですよね。止めるにしたってね。なんかこうそんなね、「生計を立てることを優先しろ」みたいなことを、研究者の人に言ってほしくなかった。みたいなことで結構絶望を感じた覚えがありまして。もうそうなってくると、もうその人に対して、その人ともう付き合っても無駄だなと思ってしまうっていうところがあったので。
西川:「キノコだ!」って言って逃げる。
一同:(笑)
I:そう言いたくなることって結構多いですね。
西川:これから覚えとくとよいかもしれない。そう言うやつと出会ったら「キノコだ!」って言って相手にしない。
一同:(笑)
I:相手にすごくこう感情移入してしまうんですけど。でもその一方で、パイロットも「この子にはなんか喉が渇いて死にそうとかそんなことが分からないんだなあ」みたいなセリフもあったと思いますけど、確かに王子さま、なんかこういうことを言うわりには、命がけで苦しんでるみたいな感じもしないですよね、なんか。死とかそういうものの恐怖とかから超越してて。
西川:いや、最後はやっぱり怖がりますよ、最後にね。最後のところね。
I:
ちょっと怖がってるけど、なんかこう超自然的なところもあるので、なんか星から星へ移動したりとか、お腹を空かそうとしてないのかとかよく分からないところがあるし。
そのうえでなんか、でも「水は飲みたい」とか、欲求になんか支配されてる存在でもあるようにも思えるんで、そこらへんがよく分からない。完全に感情移入できないってところがありますね。
涙のちから
J:私はなんか、涙がやっぱり不思議なものだなって。
西川:そうですね。
J:私も一ヶ月前に大学卒業して、卒業の日に卒業パーティーがあったりとかして、大学時代すっごい嫌いだった先生がいて。でもその日、その先生が一番激しく泣いてました。でなんか、ちょっとすごい心に響いてて、嫌いになれないなって思うようになりました。もしその先生がそのときまだ笑顔だったら、たぶん私何とも思わないかもしれないですけど、でもなんかそういう、人それぞれだと思いますけど、私はやっぱりあの、笑うよりなんか泣くってことの力がすごいって思います。
西川:
ねー、涙ってなんであんなに…。なんででしょうね?眼球結膜の保護のために泣くわけちゃうからなあ。他人の分泌物の中で平気で手に触れれるのは涙だけとか言いますね。いくら好きな人でも鼻水とかね、よだれとかね、その他諸々にはさわれないけど、涙なら拭ってあげるみたいなことありますね。
だから涙が持ってるこう人間的な意味をいろいろ考えるともっと面白いかもしれない。でもこれ生理なんでしょうかね?教えられて泣くわけでもないよね。やっぱり文化なのかな?どうなんだろう?泣かない文化ってあるのかな?泣く文化っていうのはよく聞くけどね。
まあ「武士の子は泣くな」とか「男は一生に三度しか泣いたらあかん」とか、日本のね、昔のまあ侍の子はね、一生に三回しか人前で涙を見せるなっていうのはよく言われたっていうんですけど。
どう思います?涙って。ボロボロ、ポロポロって涙出るっていうのは後天的に身につけるものですか、学習するものだろうか。
その嫌いだった先生が「悪かった。俺あんなこと、あのときごめんなさい」って言ったわけじゃないよね?ただ泣いてる。そしたら「あ、嫌いやったけど、いや、嫌いじゃないかもね」みたいな。こういうこと、ほんまに不思議ですね。でも「うそ涙」っていうのもあるからなあ。
K:えっとなんか、王子さまとパイロットの考え方は結構ずれていますよね。なんか、最近はえーと、エンパシー[*7]っていうことにすごく興味があって。まあ人間と人間、人間と動物とか植物…、いろんな形式がありますけど、交流するときはいつも自分の立場で自分の意見を言い張って、で相手の言葉は全然聞かなくて。なんかエンパシーがある人は結構少ないです。
[*7] エンパシー:empathy、感情移入。人の気持ちを思いやること。シンパシー(sympathy)は他人と感情を共有することをいい、エンパシーは、他人と自分を同一視することなく、他人の心情をくむことをさす。
西川:エンパシー?シンパシー?
K:シンパシーは同情。エンパシーはなんか他人の痛みが感じれることで。
J:共感?
K:うん、そう、共感することはとても珍しいです。最近友だちと、心理的な障害のある友だちと交流するときは、相手の話をちゃんと聞いて、どんなことを聞いて、とか話して。で、うん、何でこんなにつらくなってるのかっていうことを聞いたり。
西川:そうですね。ただ何て言うかな、「私、悲しいのよ」って、「そう、悲しいのね」っていうかたちで言葉で聞く。カウンセリングなんかでよくやりますけど、あの同じように繰り返すっていう。これね「悲しいのよ」って言ってる中身が全然違うかもしれないでしょう?
K:そうです。
西川:でも、その泣いてる人を見て自分もこう、こう瞼が熱くなってくるっていうのはある。これね、同じ涙が流れてくんねん、なんか不思議に。
K:え、そうなんですか。
西川:だから身体的な共鳴は、やっぱり言葉を理解してそれをこう送り返すっていうのよりも、もっと根が深いようなところがあるじゃないかな?
K:たとえば、うーん、「君の悲しみが分かりますけど、でもこれは人生ですから頑張って」。
西川:それは共感とは言わないね。だからそういう意味で「涙の王国」というのはそういう言葉的なところでの理解をこう遮断するっていうかね、そういうこともあるかもしれないですけどね。
K:うーん、このチャプターで、恐らく王子さまの心が、パイロットの不安も理解できなかったって感じが。
西川:ある意味冷たい男だねえ。一生懸命機械直してんのに。
K:冷たいです。うん。キノコもかわいそう。
一同:(笑)
西川:はい、そうですね。別にこれを聖典にする必要はないんでね。違うというところは違うでいいと思います。
L:
キノコのところ。私は、何だろう、何だか、そう言われてほんとに傷つくような言葉なのか、とかそういうことがちょっと分かなかったです。「キノコだよ」っていうとこを読むと、何だかむしろちょっとユーモアを感じて。
前にこう、「そうなると象の上に象を積み上げなければいけなくなるなあ」って言ってたこう王子さまの発言を思い出して、なんかそれとおんなじような、ちょっとユーモアみたいなのを私は感じました。
でもどんな、どういう思いで王子さまが、うーん。ものすごく批判して言ってはいるとは思うんですけども、作者の意図としてそれだけなのかどうかは、ちょっと分からないなあ。
西川:まあね、ツッコミみたいな。
<
「『ぼくはまじめな人間だ! まじめな人間だ!』ってね。そんなことばっかり言っているものだから、ふくれあがって自尊心のかたまりになっちゃったんだよ。もうそうなると、人間じゃない。キノコだよ」
>
なんかこう大阪人のノリですね。どちらかと言うとこの悪口の言い方は。
M:えーと、何て言うか、どっちも、何…、結構難しいな。僕は王子さまもパイロットもどっちもよく分かんないなあ、と感じました。
西川:
はい、それでいいんですよ。そんな簡単に分からないです、この本は。だいたい簡単に分かると思われてるけどそうじゃないよね、っていうことを確かめてるのがこの読書会で、分かるようになるために読んでんじゃないですよ。分かってたと思うのが「実は違うよね」っていうそこらへんがありますよね。
ケアを考えるっていうこともそうですね。「ケアっていうのは困ってる人のためになんかしてあげることでしょ」って、簡単に分かってることを、ちょっと、「そうじゃないんじゃないの?」って、いうのが大切なところかなと思います。はい。
N:僕はやっぱ「涙の王国」が、突然やなというか。「王がいるんだ」と思ったし、さっきおっしゃったように、その、どっか聖書とか引用元があるのかもしれないですけど、なんかね。
西川:「涙の王国」、英語ではどう訳してましたっけ? フランス語見ても分からないからな。
C:涙の、ただ国、国です。
西川:「涙の王国」ていう言い方すると、要するに涙が王様ですね。そういうふうに理解したらいいなじゃないかな。「涙の王国の王様はくしゃみです」っていうことはないもんね。
一同:(笑)
西川:だから涙が一番力を持っているそういう場所って理解するのがいいんじゃないですかね。
N:星じゃないんだなと思って。
西川:え?
N:星でもないんだなと思って。このあと星がいっぱい出てくるので、なんか「涙の星」とかだったらまあ、そういう世界観なんだと思うんですけど。まあ王が出てきたりすることもあるんですけど。涙の王国っていうのがすごい、また違う世界観というか。うーん、なんか、ちょっと。
西川:ここ僕も気になって丸はくるくるくるくる付けてますね。「涙の王国」て書いて矢印書いて、結局何も書いてない。
N:(笑)
西川:
「分からない」っていうことなんでしょうね。僕も一番最初かどうかはわからないけど、ずいぶん昔には「死ぬことがなんだ」っていうところにピューッて書いてあって、「やけになっているのか?それとも強い反省なのか?」とかって書いてますね。
やっぱり今の読み方とは全然違いますね。最初の頃は「あれ、なんやこれ、パイロットがやけになってるわ」ぐらいにしか読んでない。だから読み方どんどんどんどん変わっていく。それがいいことか悪いことか知りませんけど、僕にとってはそういうふうにして自分が変われる、幾度も変われるような本が素晴らしい本だと思ってます。
一度読んだらそれで分かったような気になって、何度読んでも新しいものが付け加わらない本っていうのは「もう捨ててもええかな」みたいな感じですね。読むたんびにやっぱ違うものが見えてくるっていうのは、そういう意味ではいいね。
はい。じゃあちょうど20時25分になりましたので、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。
(第8回終了)
