
【線たちの12月】見えるもの、見えないもの、聞こえるもの、聞こえないもの
ほんとじゃん?
ほんとに見えたら
――――浅倉 透※シャニマスの『線たちの12月』の感想になり、同シナリオのネタバレを含みます。また以下のコミュ等についても、軽く触れています。
・アンティーカコミュ『見て見ぬふりをなさって』
・恋鐘 LP
・咲耶 GRAD、LP
・【当日じゃない日】白瀬 咲耶
・【紺碧のボーダーライン】白瀬 咲耶
・【賑やか四畳半】三峰 結華
・冬優子 WING
・【ダウト】樋口 円香
・ジブリ『魔女の宅急便』(ニシンのパイ)
また引用する画像は、下記ゲーム内画像・©になります。
・ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)」
・©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
初見の印象は、線は人と人の間を結ぶもの、円は人と人を含むものであり、私たちはペンを持つのは、自然とそれを求めてしまうから、という風に感じた。

『線たちの12月』は多くの線たち――人と人の間にあるもの――を描くことにより、多様な、人と人の間で起こりうること、起こっていることに言及した作品だと思う。そこには透ちゃんの言う「ほんとじゃん?ほんとに見えたら」が幾重にも発生しており、人と人の間に線を引くことの難しさが垣間見れる。そして、最後は「祈る」しかないという実際的な落としどころが示唆される。『線たちの12月』の感想を一言で言うと「人間関係って難しい」。
物語の主要な対比としては「ルカと灯織」と「おばばと透」がある。おばばは透自身のことは見ておらず、透の上に孫を見ていた。同様にルカは灯織自身を見ておらず、美琴を重ねて見ていた。また上記とは別に、人と線を結ぶことが苦手な小糸を中心とした話がなされる。まとまりのないオムニバス的な感想になるが、まずルカから見ていこう。
ルカと世界

彼女はそれとなくいつも「うるさい」と言う。とても感受性の強い子で、下記の発言がその感性の一例を示している。

注意してほしいのは、サイネージそのものとしてはただ点滅しているだけということだ。「プレゼントを買え」とサイネージ自体は言わない。ルカの、この発言の裏にある感覚は「派手な色で人目を引いて購買を促進しようとする売り手の意図」をルカが連想した結果、サイネージの元に意志のようなものを感じとる感性による。ただし、サイネージを設置した人がどう思っていたかは実際のところはわからない。ただの派手好きだったかもしれないし、実際にルカの連想通り販売促進目的だったかもしれない。客観的には本来決定不可能なことだ。しかしながら「プレゼントを買え」と言っているようにルカは(主観的に)感じる。つまり、これはルカの心の投影でしかない。
昔の恋人との品を残しておくか処分するかという論争がある。ルカがどちら派かはわからないが、少なくとも残しておいた場合、ルカは「うるさくて」やってけないだろう。そのような品は過去の出来事を想起させ、またその反射として現在の”失われた”状態をも強く連想させるから。ルカは「モノはただのモノ」と割り切ることができるようには見えない。モノに付属する意志のようなもの、記憶の残滓のようなものを、否応なしに感じてしまう。その感覚を彼女は聴覚的に例えて「うるさい」と形容しているのだろう。
ルカの、この汎神論的/アニミズム的感性は――誰もが多少は持っているものだが――霧子に匹敵するほどに強いものに思える。しかし、霧子の見えている世界は霧子に優しく語りかけてくるのに対し、ルカの見えている世界はルカに対してとても強迫的で迫害的だ。『神様は死んだ、って』という彼女の楽曲は、ルカの見えている世界――ルカの心を投影した世界――を端的に表している。
なぜルカは神様に言及するのか。ルカは何事にも意思のようなものを強く感じる感性を持っている。派手なサイネージが「プレゼントを買え」という意思の元にあるかに感じられたのと同じように、”私のこの見捨てられた状態自体”が何らかの意志の元でもたらされたように感じることができる。もし、そのような状況をデザインした者がいるとすれば――できるとするならば――それはきっと神様のような位置の存在だろう。しかし、ルカには神様が今このときを、なぜこのようにデザインしたのか、その意図が読み取れない。この”読み取れない”は神様は黙ったまま――つまり、死んでいるみたいだ――という風に捉えられる。
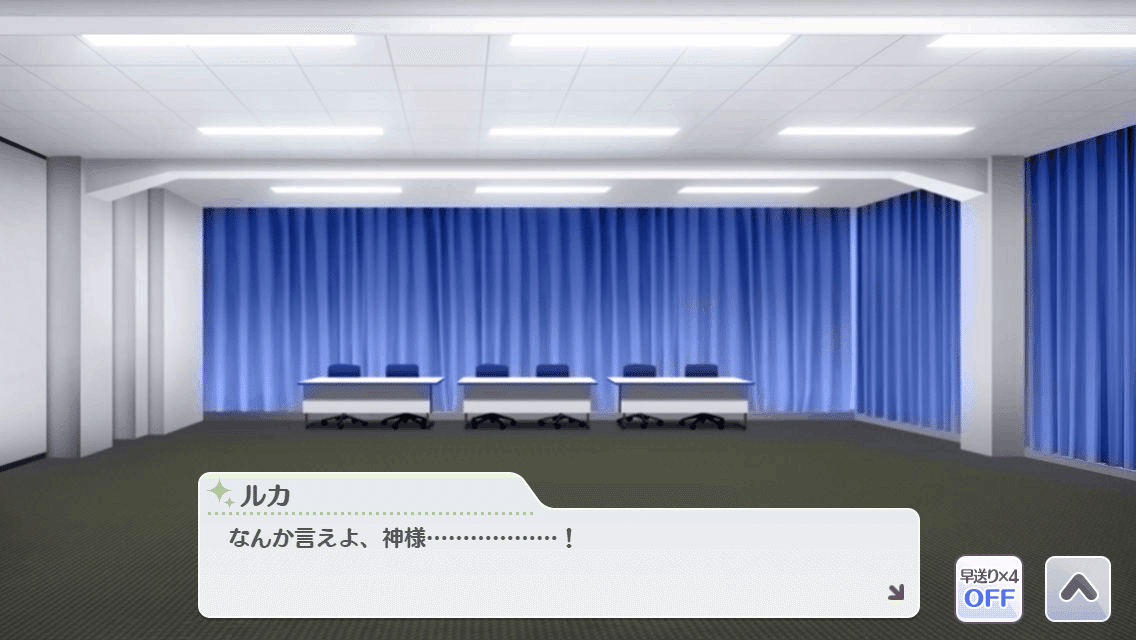
強迫的で迫害的な世界が見えているルカに対して、つい世界はそんなんじゃないよと声をかけたくなる。SNSのリプは――ナルシシズムの強さが鼻にはつくが――「火の用心」の掛け声のように、人によっては嫌がる(ルカには迫害的に見える可能性がある)かもしれないが、「こうした声がある場所がいつか安心できる場所になるかもしれない」という「祈り」なのだろう。

ナルシシズムの強さが目立つが……

『線たちの12月』はルカが雪に美琴との過去の出来事を投影することから始まる。そして、”失われている今”さえも思い浮かばせる雪は、ルカに「ゴミ」と形容される。
ルカと灯織、ルカとP
物語はルカと灯織の関係性の構築から始まっていく。灯織は、指導者の指定によって、あるスタジオにて冬季集中レッスンを行うことになる。そのスタジオはルカの事務所がオーナーをしているスタジオであった。そこでは練習生が廊下で練習しているのが当たり前の雰囲気があり、空気に当てられた灯織も空き時間に廊下で練習を行うようになる。その傍で、練習生たちに対してはとても穏やかに接するルカが見られる。

灯織の事情を知らないルカには、灯織は同じ事務所の練習生の一人に見え、またコンビニで灯織がレジの順番を抜かされるという出来事を介して、ルカは自分自身と灯織を「正直者」という言葉で線を結んでいることが垣間見れる。また後に「クソ真面目に基礎をしてきた雰囲気がウチの練習生らしい」と述べており、彼女が相手に身内感を感じる経路の1つはきっと「正直者」「真面目」と言ったニュアンスで自身と同一視できる存在なのだろうなと推測できる。

しかし、灯織に関しては、身内感以上に、ルカは灯織の真面目さに対し、美琴を重ねたことが演出で直接的に示される。ルカは灯織の上に美琴を見る。


ルカがコンタクトレンズを外しているという描写は、283プロの風野灯織だと容姿から判別できなかったというだけではなく、メタファー的に、ルカは灯織自身のことを直接見ておらず、その上に重ねた美琴を見ているという心的な様相も示唆しているように思える。ルンルン気分で灯織とのレッスンに挑もうとしているルカは――向かう最中の雪への描写からしても――きっと美琴とのレッスンに挑むような心地なのだろう。また283プロのPと邂逅後に、灯織に対面しての一言が「283プロだったのかよ」「風野灯織だったのかよ」ではなく、「そんなツラだったのかよ」なのが、それまで灯織自身を見てなかったことを強調しているように感じられる。
そして、灯織とルカの間に――しかも灯織に取って代わるような形で――ルカにとって迫害者である283プロ(のP)が現れる。ルカはPに対して罵声を浴びせる。この罵声の内容は、第三者(読者)から見て、Pが心にも思っていないことだということは分かる。Pはここでは「派手なサイネージ」と同じだ。ルカにはP自身は見えず、Pが迫害者に見えている。

ルカは美琴や天井努(283プロ=私を迫害しあざ笑うもの)をそれぞれ灯織やPに重ねている。ルカは灯織の生真面目さ以外の部分も含めた灯織自身やP自身を見ることはなく、新たな線を引くことはできなかった。もし仮に灯織とルカが幼馴染だったとしたら、ルカは灯織に283プロは辞めろと迫るかもしれないが、灯織との個人的な繋がりは切ることまでは至らなかったのではないかと私は思う。
この出来事の後に、灯織は自分から名乗るべきだったと思い悩むが、第三者視点から言って、どちらにせよ厳しかったじゃないだろうか。まだ灯織から打ち明けた方が線が残る可能性はあっただろうが、283プロは今のルカにとってはほぼタブーだから。灯織はルカとの関係を大切に思っているし、ふくろうのタオルのように灯織はルカ自身を見ていたように思う。だが、相手側の事情で線が届かないことは起こりうる。私たちにできるのは線が結べますようにと願いながら、線を引こうとすることまで、ということなのだろう。
灯織(美琴)がいるべき場所にP(283プロ)が現れ、灯織(美琴)はいない。演出の意図はわかるが、シャニマス君結構エグイぞ。
咲耶とおばば
おばばの話の前に、咲耶さんの思い悩みを見ていこう。咲耶さんは図書館であるクリスマスカードを見つける。そして、そのクリスマスカードをどうすべきか思い悩む。図書館のカウンターに渡して済ますことはせず、一方で、家の所在の確認まで行くが、おばばに渡そうとはしない。そして「クリスマスまでに、何かわかるといいな」と言って立ち去る。一見すると中途半端な行動に見えるが、そこにはクリスマスカードを届けたい気持ちもあるけど、届けるべきでないかもしれない、という咲耶さんの葛藤が見える。
個人的な見立てだが、咲耶さんはきっと、もしおばばが喜んでくれるならば是非届けたいとは思うけど、逆に悲しい思いをさせてしまうかもしれないという懸念を払拭できない状態なのではないだろうか。例えば、おばばは現在はもう過去の悲しい出来事を乗り越えて生きているのかもしれない。そこに悲しい出来事を思い出させるようなものを届けてしまったら?
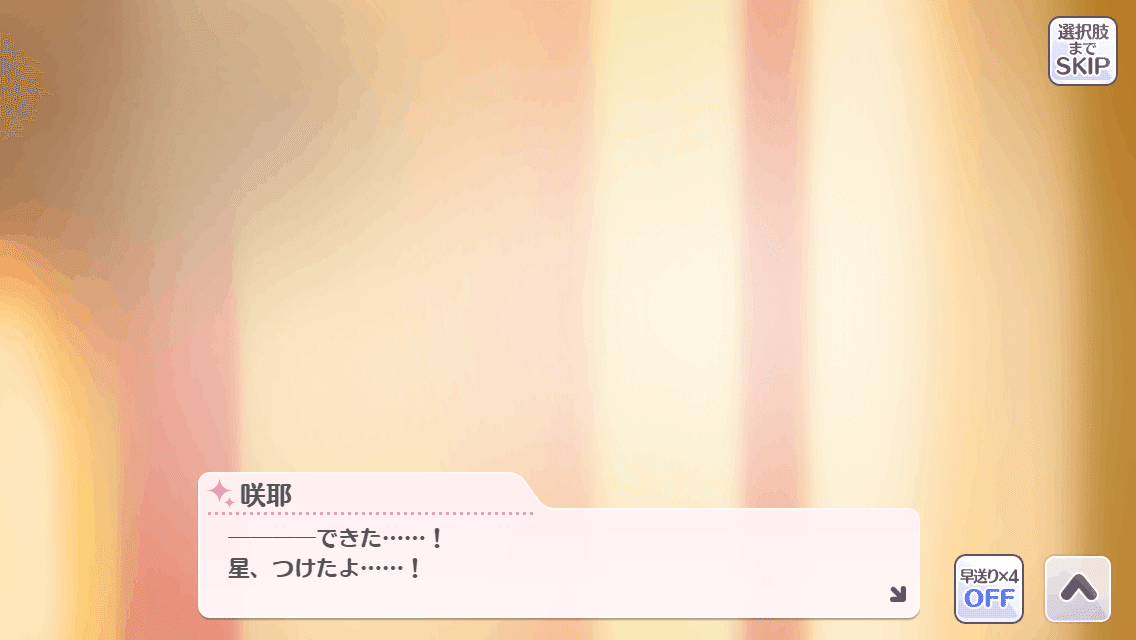
『【当日じゃない日】白瀬 咲耶』で語られた場面だろう
『線たちの12月』では咲耶さんの過去のクリスマスらしき回想のカットインが入るが、詳細に語られることはない。実は個別のコミュ(『【当日じゃない日】白瀬 咲耶』)にて、この場面はモノローグ的に語られている。クリスマス当日じゃない日に父親とツリーの用意をする。本人は父親と一緒に楽しめることが嬉しく、クリスマスは大好きと述べる。しかし、コミュの終わり方のそことない歯切れの悪さや「今でも、この時期は特に誰もが、より幸せであってほしい――」というどこか誇張的な表現、また他のコミュで咲耶さんが父親を慮り、寂しいという気持ちを言えなかったという内心も加味すると、楽しかったことは嘘じゃないけど、そのときが楽しかったからこそ、思い出す際に、そのとき以外のときの寂しかった思いも襲ってきたんじゃないかなと思う。ちょうどルカが雪に嫌な思いをさせられたように。「より幸せであってほしい」という妙な表現が出てくるのはそのあたりの機微に見える。


だから、このカットインの意味するところは、クリスマスカードというものが咲耶さんにこの寂しい思いも思い起こさせた、ということではないだろうか。そして、咲耶さんは思ったんじゃないだろうか。同様におばばに負の感情を思い起こさせない保証はどこにあるのだろうか、と。咲耶さんにはおばばは見えず、下手にカードを渡すことはできない。
このような逡巡はアンティーカらしくて、『見て見ぬふりをなさって』で主題になっていたのを思い出す。相手の事情を知らず、一方的に助けたいから助けに動くのは、結局自分のエゴでしかないのではないかと、心に留めながら行動する。咲耶さんはきっとSNSでのリプはしないだろう。

おばばと透
火の用心の巡回にて、一同はおばばと邂逅する。町内会の人曰く、以前は孫と暮らしていたが、既に孫は亡くなっており、おばばは一人暮らしをしているという。クリスマスカードはその亡くなられたお孫さんからだったのだろう、と一同は目を合わせる。おばばは寒い冬の中、庭に佇む――それはどこか『アイムベリーベリーソーリー』の寡婦を連想させる。咲耶さんは胸を押さえて、クリスマスカードのことを口に出さないよう堪える。しかし、おばばは唐突に透に「おかえり」と声をかける。その台詞からおばばが透の上に孫を投影したことが伺える。透はその投影を否定することなく受け入れ、クリスマスカードの言葉――幸せでいてね――を伝えて、おばばと別れる。
別れた後、咲耶が真っ先に透に尋ねる。それは咲耶にとって壁だったものを超えたからだろう。透は答える。おばばが――孫を投影をしたということは――望んでいたということだし(「そうして欲しいのかな」)、それに答えただけだと。咲耶さんが受けて補足する。良い結果になると何か根拠があっることはなく、おばばがそれを望んでいたようだし、もうそこから先は、幸福感を感じるか寂寥感を感じるかは本人次第であり、良い結果(幸せ)になりますようにと願うしかない、「祈る」しかない。実際におばばがどのように感じたのか。それは決して描写されることはなく場面は終わる。「幸せでいてね」という言葉は孫の言葉であると同時に、透の言葉でもある。

このおばばと透のやり取りがどこか衝撃的なのは、透が投影を否定せずに、孫になりきったという点にある。それはある意味、透が自分で自分を殺す行為だから。おばばから透自身が見られることがないということを透自身が肯定した(この強さは特に智代子先輩が持つ類の強さに見える)。おばばには透ちゃんは見えてないし、透ちゃんも自身を見せる気もないけど、そこには「相手にとって幸せでありますように」という、見えない「思い」はある。もちろん心に押しとどめた咲耶さんの中にも。
Pと声優さん
おばばと透(と孫)の関係の構造。実はアイマスPには馴染み深いなと思った。それはアイマスのライブと同じ構図だから。Pは声優さんの上にアイドルを見ている。このライブは声優さん自身が主目的ではない。声優さんはある意味で自らを殺していると言える。
私が初めてアイマスのライブの存在を知ったとき、残酷だけど先進的だなと感じたのを覚えている。残酷なのは上の通り、主として声優さん自身は見られていないということ。先進的だと思ったのは、アーティストという存在自体が内在的にその構造は持っており――ライブを見に来る人はアーティスト個人に会いに来る、というよりそのアーティスト性を見に来るだろう――それを最初から分離させている、という点にだった。声優さんの仕事内容自体、この乖離を最初から孕んだ職業ではあるものの、ライブでこの大人数の前であからさまに見せつけられるということは――職業倫理から彼女らは表には出さないだろうが――人によっては葛藤を強く抱え込むのではないだろうかと思う。
この構造を否定するならば、アイマスという名目ではなく、声優さんたちのライブとして開催すべきであり、アイマスのライブという時点でこの構造は不可避だ。アイマスのライブは声優さんの「思い」「祈り」の元で成り立っているというのが分かる。構造を否定するのではなく、「思い」「祈り」を感謝して受け取るべきなのだろう。(そしてできればなんらかの形でお返しできれば……)
ニシンのパイ
『線たちの12月』にはない、少し逸脱した内容になってしまうが、もし仮にそのような「思い」を受け取る場合、そして、それがお門違いだった場合に私たちはどう対応すべきなのだろうか。思い出すのは、ジブリの『魔女の宅急便』の「ニシンのパイ」の下りだ。
場面を端的に述べると、おばあさんが孫のために「ニシンのパイ」を作り、キキが嵐の中届けるが、孫は「あたしこのパイ嫌いなのよね」と言いながら受け取り、ドアの向こうに消えていく。よくあることではあるもの、嫌いな人はとても嫌いな場面である。
この場面、孫は「ニシンのパイ」というモノは受け取っても「思い」は受け取らなかった場面になる。もちろんおばあさんのチョイスミスが前提にあるものの、必死に配達したキキの「思い」も踏みにじられた場面だ。『魔女の宅急便』ではこの”踏みにじられうる”という出来事を契機にして、キキが大人になっていく話になる。透ちゃんや咲耶さんはキキの立ち位置に近い。実際に相手が幸せになるかどうかは分からない。
仮に私がこの場面で孫だった場合、どう対応すべきだっただろうか。パイが嫌いなのはしょうがない。でも、パイは嫌いでも「思い」には報いるべきなんじゃないだろうか。受け取るのはモノや音だけではなく、「思い」であるということ。ニシンのパイは笑顔で受け取ろう、と誰かが言っていたのはそういうことだろう。
またここで嫌な顔をしてしまった場合、今後、相手が次の善意の行為をなすときの障壁となってしまう。ちょうど咲耶さんが躊躇したように。話が少し飛んでしまうが、この障壁ができてしまうと乗り越えるのは大変なことで、大抵の人は”仕事”という言葉で乗り越えていく――この場合乗り越えるというより無視するような感覚に近い気がする――が、そんな中でも恋鐘のLPは”アイドル”という言葉でこの類の障壁を超える話だったのが印象に残っていてる。

小糸とP
『線たちの12月』の話に戻ろう。まず小糸とPの関係の話を。小糸だけの話というよりノクチルというユニット全体にまつわる話でもある。
Pは小糸に対して、火の用心のボランティアへの参加を任意で促す。あくまで断っても良いという体である。Pの立ち位置的にも妥当な態度だろう。しかし、小糸は少し目を逸らしつつ、条件付きで許諾する。後に透ちゃんに「やだーて言う?」と指摘されるように、小糸にとってはとても苦手で、嫌な選択だったことがはっきりと分かる。
実はこのPと小糸のやり取りには、ポストモダンの寛容な父性の問題が孕んでいる。下記のシジェクの説明が端的でわかりやすい。
見かけ上の寛容さに隠された権力について語るジジェクの動画に字幕をつけました pic.twitter.com/Jha1LkCmTf
— ジョージ (@jo2geor2) December 23, 2022
つまり、小糸ちゃんには選択の余地はないように聞こえてしまっているということ。実質強制と感じてしまう。それは、拳銃を突きつけられながらどっちを選んでもいいよと言われているようなもので、形式的な自由はあれど、実質的な自由はない。
後に咲耶さんを介して、Pの意図は、人と人の関係の中にあるぬくもりを小糸にも体験してほしかったんじゃないかと示唆されるが、小糸ちゃんにそのような意図が(この時点で)伝わることはない。またPも人となりからして、断られたらちゃんと引き下がっただろうが、この誘いが強制的に聞こえがちになることを見えていないように見える。
任意のようでいて強制的に課されること。円香の言う”仕事”である。


任意の確認段階でも、水着モデルのオファーを”やらせたい”のですよね、と円香は受け取る。
ノクチルの構造を見るとき、各人のこの”仕事”に対する態度が1つの切口になる。小糸ちゃんは(円香から見て)”仕事”をさせられているという自覚がない子であるが、『線たちの12月』では、その小糸ちゃん自身が今回のボランティアを”仕事”とこぼしたのがとても印象的だった。本当に小糸ちゃんにとって苦手で、嫌で、断りたかったことだったのだろう。どれくらい嫌だったかというと、道中の諸々のことがあれど、初日に学校を出るのが遅くて遅刻する程度に彼女を後ろに引っ張っていたことが伺える。


凛世と小糸
小糸は凛世とボランティア活動のバディを組むことになる。凛世が活動日誌の下書きをして小糸に見せるのだが、小糸は一言OKを出して早々に立ち去ってしまう。凛世は、小糸のその姿に何か怒っているのではないか、そして思いつくとすれば、勝手に日誌(の下書き)を書いたことではないかと逡巡する。
読者視点から見ると、小糸ちゃんはどう立ち回ればいいのかが良くわからず、フリーズに近い状態になっているだけ――小糸ちゃんにとって<他者>は私を圧倒してくる存在だから――だと分かるのだけど、凛世から見ると、放クラのメンバーや友達とは違い、小糸は自己開示を極力さけて、あたかも関係性を作るのを拒絶しているかのように見えてしまっている。
小糸ちゃんの知らないこと。それは私たちは意図しないメッセージを不意に送ってしまうということ。例えば、ただ机に突っ伏している――寝不足なだけかもしれない――姿や、ただ突っ立っている姿だけでも、関係性を紡ぐ気はないというメッセージを、実際にそういう意図はなくても否応なしに届けてしまう。そう相手に見えてしまうということ。
凛世の知らないこと。凛世の悩みに対して、咲耶さんも透ちゃんも直接的には回答をしない。小糸ちゃんはこういうのが苦手だから、と一言あれば凛世の悩みは解消されたかもしれない。ただこの物語では一歩踏み込んで、透ちゃんは「そうじゃん? そう見えたら」「だからないんじゃん。見えるとこ」と言う。透ちゃんの行間の空いた言葉に含まれる内容は、私たちはお互いに結局見えているものでしか判断できない、だから見せないといけない、ということじゃないだろうか。凛世には小糸が避けているかのような姿しか見えないが、一方で小糸側から見ると、小糸には凛世がどうしたいのかが見えない状態でもあるということ。透ちゃんは小糸は飴が好きとだけ伝えて場を離れる。

作中、凛世は今までどちらかというと相手側から歩み寄りをしてくれることが多かったことが仄めかされる。今回の小糸ちゃんとのつながりは、凛世にとっても新たな一歩で、凛世から歩み寄りを見せる話でもあるのだろう。飴を送る――灯織からルカのタオルへの言及も同じ――という行為はモノを贈るだけでなく、付属する言外のメッセージも送っている。それは必ずしも思った通りに届くとは限らないけど、思った通りに届くことを願って贈られる。それを見て、小糸も返せるようになる。そうやって線ができていく。
『線たちの12月』は凛世と小糸という率直な二人なので、お互いに微笑み合って物語が終わりを迎える。線を結ぶためにはまず見せないといけないよねということが示唆される。
火の用心
「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ
人と人の間にあるあたたかさを、もし火に例えるならば、火の用心とは、かつてのあたたかさを求めて、新たな火をつけれなかったこと、線を引きなかったことを指すのではないだろうか。ルカやおばばは、かつてのあたたかさを求めて、灯織や透と線を引くことはできなかった。それは、かつての火が新たな線を燃やしてしまったとも言えるかもしれない。
蛇足的だが、ルカやおばばの投影(線の引き方)は「転移」と呼ばれるものだろう。この言葉は専門的な分野でもかなり曖昧に使われているが、この言葉の創始者であるフロイトの定義が比較的近い。一つの似ているところ(唯一対象)をもって、相手を別の相手に重ねている。相手自身を見ていない。
見せるものは
作中の言及はここまでで、まず見せることが第一歩目だけど、実際にはもうちょい難しい話になっていく。”相手に見せる”という行為は複雑な様相を孕んでいるから。「どう見せるか。どこまで見せるか。何を見せないか。相手はどう見たがっているのか。それにどこまで応えるのか。」という問題。
例えば、結華はアンティーカのメンバーを初めて家に呼ぶ際に何は見せて大丈夫かと準備したり、冬優子は<他者>に求められる姿と素の自分との差異に強く引っかかっていることが示される。


またルカのSNSも象徴的で、ファンの彼女らはナルシシズムに満ちていて、きっと今のルカを手放せない(ナルシシズムの悪い側面が出ている)。もしルカが変わって行くことがあれば、その際に1つの障害になるのは避けられないだろう。この類の壁は元モデルの咲耶さんのGRADやLPで焦点が当てられていて、咲耶さんが背負う咎という形になっている。”見せる・見られる”という行為から個別の問題が発展していくことが見える。

ゴミ
最後に。「道具を道具たらしめるものは何か」と同じように、「ゴミをゴミたらしめるものは何か」。
物語の終わりに、キービジュアルとアイドルたちの多少騒がしい声をバックに、ルカの独白がなされる。灯織には寂しい気持ちを満たす暖かい声と捉えられるが、ルカにとっては雪を介して聞こえてくるそれは「うるさい」騒音以外の何ものでもないだろう。

雪は雪で、ゴミではない。声は声で、騒音ではない。線は線で、羽ではない。円は円で、果実ではない。文字さえも究極的にはただの染みでしかない。(これらは、シニフィアンのシニフィアン性と呼ばれる)
夜空には星はあっても、星座そのものはない。星の並びの上に、私たちの心を介して、星座が見えてくる。雪についても、雪をゴミのようだと捉えることもできるし、美しいものとも捉えることができる。
小糸ちゃん含むノクチルの仕事の見え方(星座)が変わりますように。ルカの世界の見え方(星座)が変わりますように。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

