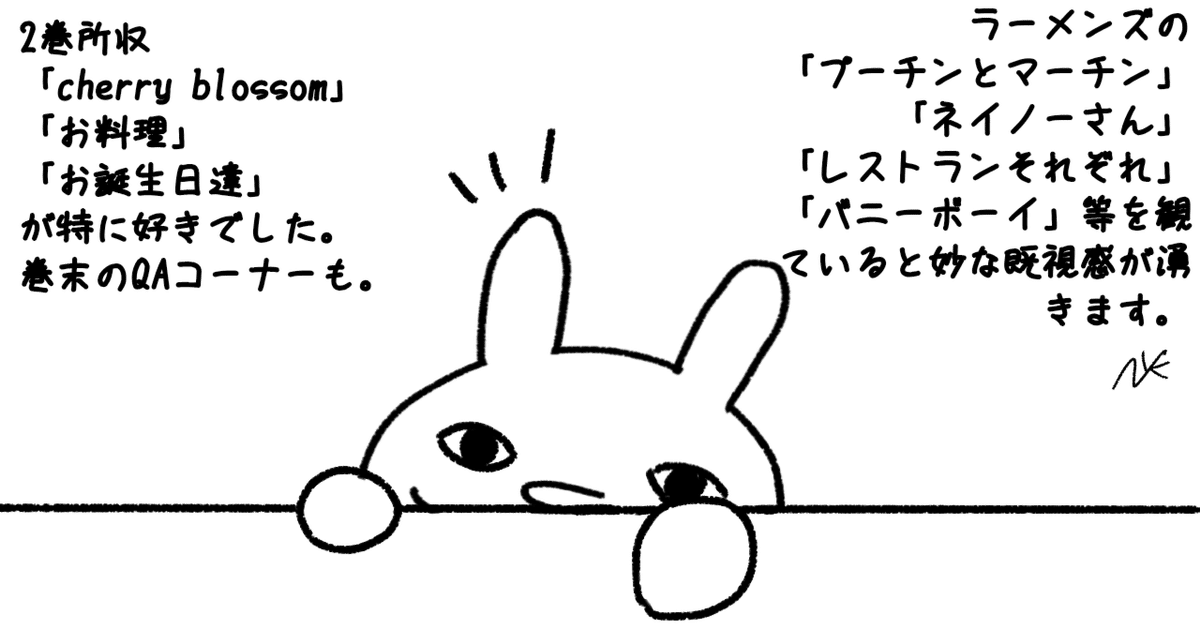
「あ、『鼻兎』の人だ」から始まる幾度かの出会いについて。
はじめに。幼い自分を何度もシュールな世界に引きずり込んで笑わせ、驚かせてくれた”鼻兎”に御礼申し上げたい。生き方を見つめ直すような出会いって今までたくさんあったし、これからもきっとたくさんあるんだろうけど、とある入り口のいちばん近くで貴方と出会えたことがすごく幸運だったとこの頃思います。
教室で話題について行けないのは漫画やゲームがうちにないからだ。3DSもマリオカートもなめこ栽培キットもポケモンも知らない。テレビを勝手に見ることも許されなかった。真夜中や夜明け前にこっそり起きて深夜アニメを音量3で見たこともあるし、生まれて初めて自分のお小遣いで本屋に行き、家族に内緒で漫画やCDを買ったこともある。そのたびに必要のない罪悪感を覚えたものだ。
買い与えられた本も譲り受けた本もとうの昔に読み終えた。近所の図書館もそれほど好みと合わない。合わないなりに無理矢理面白い本を探したし、自分でキャラクターを考えて小説を書いたことだってある。だいぶご都合主義の物語、その書きかけが積み上がっていったが、完成させるにはあまりにも知識が足りなかったし、センスの器は空っぽだった。今思えば明らかにインプット不足だ。田舎町で世の中とのアクセスも悪い。欲しいものがない街と流行について行かない家。その中でずっと空腹のような気持ちを抱えていた。
そんな家で唯一治外法権になっていたのが祖父母の部屋である。そこでは夕方六時半になるまでテレビを見てよかったし、知らない小説や雑誌がいっぱいあって、リビングとはすこし違う匂いがした。ので、あの頃の夕方のEテレに関してはちょっと詳しい。でも六時半って天才てれびくんとかビットワールドがいちばん面白くなるタイミングなんだよな。あの引き裂かれるようなつらさ。昨日のことのように思い出せる。
ここまでが小学生当時の私の自己紹介である。本題はここから入る。
いつものように許可をもらってテレビを見ていたとき、ふと祖母の本棚にあった続き物の本二冊が気にかかった。

『Hana-Usagi』
以下、ローマ字だか英語だかフランス語だか、とにかく私の知らない不思議な単語の羅列(今翻訳をかけてみたが上から3行目以降は仏語らしい。訳すなら「この漫画は劇作家が描きました。」「変な兎と周りのやつらの物語」ってとこだろうか)。
黄緑色の帯が一冊目、水色の帯はおそらく二冊目。紐しおりがついていておしゃれなデザインだけど、ぱっと見た感じ、この厚み、小説ではなさそう。あと「ハナウサギ」って響きがかわいい。帯の後ろからぴこんと飛び出ている耳もかわいい。面白そう。
興味本位でぺらっとめくってみた。あっ、漫画だ。この家ではレアなタイプの書籍だ。
どんなものかなとさらに頁を繰った瞬間、両目の幅がかなり広く、笑ってんだか無表情だか曖昧の、鼻の長さが結構ある変な兎と目が合った。
…………
「かわいくねえ~……」
ごめんなさい鼻兎。本当にごめんなさい。でも当時小学生の自分は率直にそう思ったんです。どういうキャラデザだよ。ハナってそっちのハナだったか。
気を取り直して読んでみる。変な鼻の兎を取り巻く物語。約3頁で一話の漫画。大体オチがシュール。「面白いのか、これ」と疑いながらも頁をめくる手は止まらずどんどん読み進めていく。たまに立ち止まって読み直す。なんか変だなと思ったら、途中から台詞が打ち込んだ文字から手書きのそれに変わっていた。独特のくるんとした字体が世界観をやわらかくしている。どちらかといえば悪筆なのでこういう筆跡の人が羨ましい。
展開が時々ぶっ飛んでいる。くすっとしつつも、「そんなのありかよ」と毎回新鮮に驚かされる。読んでいて正直ぴんと来ないネタもあるにはあったが、何か面白いことを言っているのだろう、と想像はついた。そういう意味では大人向けの漫画だったのだろうか。でもむしろ知らない語彙が出てくるときの方が楽しい。背伸びして大人の世界を覗いているような気分になるから。幼い私のボキャブラリに「替え玉」「キャンセル待ち」「日東駒専」といった単語たちが追加された。覚えたところで意味は知らなかったし使い道はなかったが、今でもそれらの言葉は何となく面白い響きをもって脳内に刷り込まれている。
誰かの気を引こうと見栄を張る鼻兎。面白いものを見せようとするも反応されず落ち込む鼻兎。桜に攫われる鼻兎。自分だけ炬燵に入れない鼻兎。エスプレッソで眠れない鼻兎。考え込みすぎて寝付けない鼻兎。『鼻兎』の世界観を好きになるのに時間はかからなかった。面白いはずなのにどこか漂う寂しさや虚しさに、子供ながらぞわりとさせられた。
読むのに夢中になった私はついに、勝手にリビングに持ち出して親やきょうだいに紹介することにした。おばあちゃん、勝手に持ち出してごめんなさい。ただ、その時祖母が教えてくれた話によればこの二冊、元々祖母が買ったのではなく、10年近く前、祖母が入院していた時に叔母(=祖母の娘)に貰ったのだそうだ。ベッドの上での時間をやり過ごすのに『鼻兎』。なるほど、退屈しないかもしれない。
当時の自分は好きな書籍を他人に勧めるときは、一番笑った部分をいちいち声に出して耳元で読み上げるというやかましい方法をとっていた。もっとも『鼻兎』は、読み心地がすごく良かった。声に出して読みたい台詞がたくさんあった。「ダンス」なんて、七五調でリズムが良くて、今でも何も見ないで全部の台詞を諳んじることができる。さぞ迷惑だったろうが、幸いにして妹や母は食いついた。妹と二人で、最初のストーリーから全部声に出して朗読し、オチで「ふへへへ」と変な声で笑った。笑い続けていたけど、「お誕生日をください2」では、思わず胸がつきんとなって喋れなくなってしまった。自分の誕生日や生まれたところを何も知らない鼻兎が、ある人に自分の誕生日をもらう祝福の話。そう、展開が時々ぶっ飛んでいるのだ。笑いを期待していると突然、切なくて温かい話が来る。そういうバランスでこの世界観は成り立っている。
誕生日を好きな人が描いたのかな、と子供心にぼんやり思った。祝ったり祝われたりするのが好きなのかな。あるいは。誕生日という口実があれば大事な人にたくさん「おめでとう」と言える人、とか。
表紙に戻ってみる。上に書かれた言語の羅列は相変わらず謎のまま、代わりに下半分をすっぽり覆う帯に自然と目がいく。
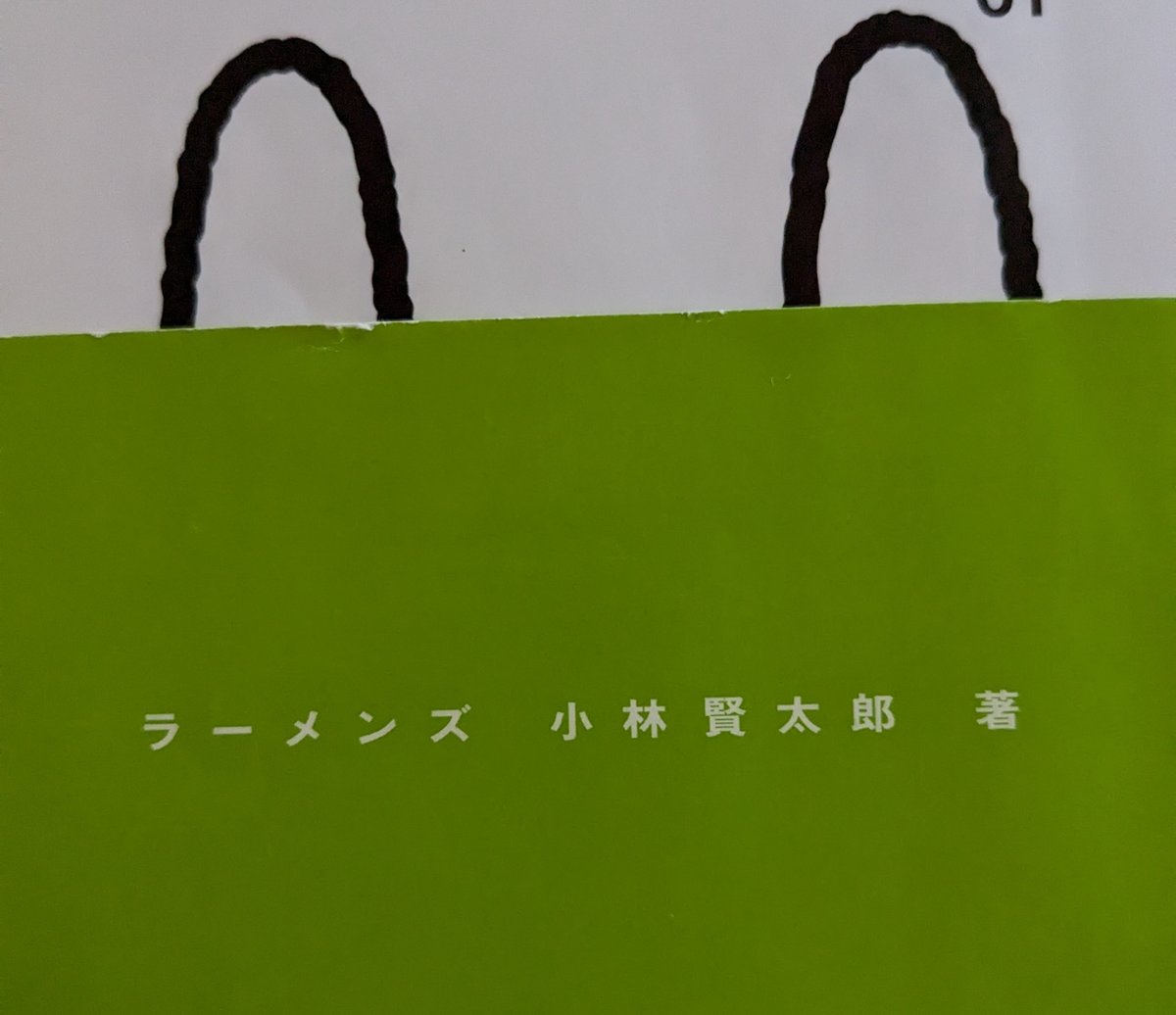
「 ラ ー メ ン ズ 小 林 賢 太 郎 著 」
私のボキャブラリに新たな言葉が追加された瞬間である。
追加された、というだけでラーメンズが何の人かは知らないし、小林賢太郎が何者かもわからない。姿かたちも定義もさっぱりのその固有名詞を、私はとりあえず「『鼻兎』の人」として覚えておくことにした。覚えるだけで詳しく調べようという興味は湧かなかった。多分、テレビでも聞いたことないし。そもそもテレビ勝手に見ちゃダメだし。
その後幾度も、その名前に遭遇するとは思ってもいなかった。
そこから間もなくして中学生になった。その頃いちばん影響を受けた小説家は西尾維新だったと思う。ドラマにもなった『掟上今日子』シリーズから入り、『物語』シリーズ、『戯言』シリーズ、『伝説』シリーズ、『りぽぐら!』、『少女不十分』エトセトラエトセトラ。12歳から15歳の頃の思い出はこれらの小説抜きには語れない。
当時の私は独特のスピード感ある文体に一気に引き込まれた。技巧を凝らした言葉遊びや韻の踏み方がことごとくかっこいい。何ページかに一回は真似してみたいキメ台詞や名言が登場する。飛び込んでくる文字情報が頭の中でリズムを生み、脳内で弾ける感覚。その心地よさに中毒になった。小学生の時から書いていた創作にもかなり影響した。
自分には合わない、そう思い込んでいた図書館には西尾作品が沢山置いてあった。昼休みも休日も図書館に籠もるようになり、そこにない本は外部から取り寄せてまで目を通した。
そんなある日、いつものように西尾維新の著作を探していた時、そこに思いがけない名前を見つけた。
「あ、『鼻兎』の人だ」

そうだよな? ここに書かれている「小林賢太郎」って『鼻兎』の作者の、あの人だよな?
思わぬところで好きな作品と好きな作品の生みの親同士のコラボを知ってしまった。わくわくしながら読んでみた。彼に関しては本当に『鼻兎』の事しか分からないので、ちょっとでも言及してくれたらいいな、という期待を込めて。というかこの布陣に入ってる「『鼻兎』の人」、何の人なんだよ。「ラーメンズ」っていうぐらいだからお笑い芸人みたいな人なのかなと思ったらどうもそれだけじゃなさそうだ。「パフォーミングアーティスト」って書いてあるし。何の人なんだ。
当時は意外なコラボだな、と思ったが今思えば、「そりゃそうだわな」という感じである。ワードセンスに関して言えば通ずる気がするもん。日本語の可能性を追求するところとか、言葉で遊ぶことに本気で向き合うところとか。
ここからしばらく、三~四年ほど『鼻兎』から離れる時期が来る。
強いて言えば一度部活の先輩に『鼻兎』を勧める機会があり、その時に初めて全四巻の作品だと知ったことか。あと一応グッズも探せばあるらしい。そうか、だいぶ昔の漫画だもんな。さすがに完結しているよな。ちなみに中学生になった妹は、英会話の授業で「好きな動物やキャラクターの一日を想像し、一枚の紙に英語でポスター風に書く」といった課題に対し「鼻兎の一日」と題した力作を提出していた。面白かった。許可をとっていないのでここには載せられないが文章も絵柄も本家に忠実で、非常にクオリティの高い作品であった。
が、正直それぐらいだ。とにかく毎日が目まぐるしく忙しく、自分のことで心身ともに必死だった。世間も世間で大パニックだった。勝手にテレビを見ても怒られなくなったし、二度ほど口喧嘩じみた話し合いをした末スマホも買ってもらったが、知らなくてもいい情報ばかり入ってくる。ちなみに小学生の時から続けていた創作のシリーズは、話の方向がおかしくなったので一旦書くのをやめることにした。
段々と「好きな漫画は?」と聞かれた時『鼻兎』を挙げることもなくなった。心の中に留め置かれていたはずのその存在を、口に出さなくなった。
「『鼻兎』の人」の名前にも遭遇しなかった。いや、時系列的には何度かテレビやラジオ、ニュースでその名前を聞いているが、そしてまるっきり思い出せない訳でもないが、キャパが飽和状態だった当時の自分は「ふうん。深追いするの面倒だな」とブラウザバックした(正直に言えばその時読んでいた関連記事内でのライターの言い分がどうも気に食わなかった、というのもまあ、ある。そうやって自衛したことが正しかったのかは今もわからない)。
なりたい姿が確かにあったのに何も行動できなくて、毎日のようにストレスは溜まった。人生初の暗黒期到来。そういう時期だったもんで、何かを思う余裕もないまま時間はどんどん流れて行った。
その後の私はほとんど逃げのような進路を選んだ。けれど、ようやく何かを思う余裕ができた。だけどその「余裕」も瞬く間に別の何かで埋め合わされていった。
それでも何度か、YouTubeのサジェストに「ラーメンズ」とか「NAMIKIBASHI」とかの名を冠した動画が流れてくるのだ。ニコニコ動画でパロディが多数あるのもその頃知った。
「あ、『鼻兎』の人だ」
https://youtu.be/k0cwNRrIv4k?si=oraGVZMq-wYa35dB
記憶が正しければいちばん初めに見たのは『箸』だったかな。サジェストされるままに再生ボタンを押す。特に何かを期待していたわけではないけど、普通に面白い。このシュールな感じは、この人の持ち味なのか。
そういえば。ラーメンズってこんな活動していたのか。いや、それより前にラーメンズは、小林賢太郎と片桐仁は、こういう風貌の人たちなのか、そんな初歩的なところをようやく認識した。そういえば高校時代好きだったアーティストのMVにも出ていたような。こっちのひとは椎名林檎の『茎(STEM)』にいたような。こっちのひとはMr.Childrenの『エソラ』にいたような。なんだかそれ以外にも、もしかしたらいろんなところで見ていたような。点と点が線でつながるような感覚、とまではいかなくとも、つなぐべき点が霞の向こうにあることを知ったような感覚だった。
偶然出会ったNAMIKIBASHIの動画で不覚にも笑わされてからだいぶ年月が流れた頃。
Twitter(現X)でおすすめ欄をぼうっと眺めていると、それは急に流れてきた。
「あ、『鼻兎』の人だ」
というより『鼻兎』そのものだった。
今の絵柄のそいつを見るのは初めてのことだった。
— ハナウサカイグリ (@kkw_event) March 30, 2023
当時の自分のツイートを見るに、どうやら見つけたのはこの漫画が投稿された日だと思われる。
ふっと口元がほころんで、そうして無性に懐かしくなった。
鼻兎、お前まだいたのか。アカウントがあるのか。今を生きていたのか。LINEスタンプにもなったのか。というかカタカナ書きなんだ。「ハナウサギ」になったんだ。記憶よりもかなりカワイイ気がするし、表情も豊かになっている。登場人物もなんか違う。
違和感はすぐに懐かしさと安堵に変わった。表情があまり変わらないところが可愛いのだと思っていたけど、そんなことなかった。そうか、こいつはそんな顔で笑うんだな。はっきりとわかりやすく喜怒哀楽を表に出せるようになったんだな(なお、この件に関しては「鼻兎は何考えてるのかわからない顔なのがいいんじゃないのか」というテーマで妹と議論になりました。結論は秒で出た。「どっちも可愛いから良し」)。昔お世話になった記憶がありありとよみがえった。もう会うことはないと思っていたのに、物語が更新されている。この世界のどこかで同じ時間を生きている、そんな感慨がじんわりと体内を温める。
嬉しくて前の作品も一気に遡ってみた。表情が豊かなハナウサギだが、構ってもらいたくて気を引こうとするところや静かな押しの強さは健在だった。そして変わらず面白かった。読んでいて以前のような寂しい気分にはならないな、と思った。違和感はすぐにハナウサギが寂しがっていなくてよかった、という安堵に変わった。
「あ、『鼻兎』の人だ」
小林賢太郎演劇作品『うるう』をYouTubeに公開しました。
— スタジオコンテナ (@kkw_official) February 20, 2024
収益は、日本赤十字社を通じ、令和6年能登半島地震の被災地に寄付いたします。https://t.co/mztsEnu9jx pic.twitter.com/maFKI8eXAM
昨年2月、『うるう』がYouTubeで期間限定で公開された。その旨を告知する投稿がタイムラインに流れてきた。
あらすじを見て、直感的に面白そうだなと思った。
ただ、自分にこれを見る集中力があるだろうか。「よし、見よう」と思い立ち、再生ボタンを押すモチベーションがあるだろうか。最近色んな界隈に首つっこんでいるけど、演劇作品を見るマインドができているだろうか。今までほとんど素通りしていたけど、ちゃんと小林賢太郎の作品に向き合ってみるのって面白いだろうか。
でも、「『鼻兎』の人」だし。
間違いなく自分に刺さるものはあるんじゃないか。そこは信じていいんじゃないか。
思い立ったうちに観ないと、そう思って公開された次の日の夜、きちんと時間を作って再生ボタンを押した。
自分の中で色々と期待値を上げまくっていた気がする。それが杞憂だと気づいたのは本編開始から五分ほど経った頃だった。ものすごく楽しかった。黙ってとりあえず最後まで見ればいいのに、主人公ヨイチが回想で同級生にからかわれている場面で一旦止めて妹に連絡した。
「これ面白いわ」
「途中に出てくるパペットの顔が完全にヤツだった🐰」
「ギャグのテンポがめっちゃ鼻兎」
これに対して妹からの返信は
「小林賢太郎ってはなうさぎの人やんな」
それだけだった。多分これは見るつもりないな、と思った。そういうものである。次に会う時にDVDを携えて真横で鑑賞会でも開いてやろうか。
結論、『うるう』はものすごく面白かった。いっぱい笑って時々泣けた。観てよかった、と心の底から思った。
「小林賢太郎を知ったの「鼻兎」なんだけど、シュールでカオスな鼻兎が時々見せる、駆け寄って抱きしめたくなるような孤独感が好きだったなー、そしてギャグシーンにいつも元気貰ってたなー、と思い出した」、見終えた直後、Twitterでそんなことを呟いた。
めぐりめぐって、ようやくラーメンズのコントを見始めたのは、『うるう』の配信期間が終わった後である。ちなみに初めて見たコントは「count」だった。「1.5人」に、なぜか爆笑してしまった。そこから縦横無尽に、公演の順序も考えず五月雨式に見て行った。そんなふうにしてあの日ボキャブラリに加わった「ラーメンズ 小林賢太郎」の「ラーメンズ」の部分を答え合わせしていった。
「あー、やっぱり『鼻兎』の人だなぁ」
リズム感のある台詞の連続。ありそうでどこにも存在しない曲を歌ったり踊ったりする二人。主語のない会話を「〇〇って何?」と聞き返すギャグ。たまに出てくる見栄っ張り。無茶苦茶な答えのクイズ。ツッコミ不在のまま半ば強引に進行するストーリー。あとやっぱり誕生日ネタ多いな(「縄跳び部」、「斜めの日」、「バースデー」、「後藤を待ちながら」)。好きなのかな。
みんな『鼻兎』で見覚えがあった。既視感だらけだった。けどやっぱり『鼻兎』とは違う新鮮さと鋭利さがあった。舞台ならではの臨場感もあった。
笑いに対して入念に技巧を凝らした脚本。シンプルを美しいと思わせてくれる演出。笑わせてきながらも、ほろ苦く残る別れの気配と恐怖の余韻。日常の中にそうそういない強烈なキャラクター。そこに命を宿す強烈な演者二人。
誰も見たことのない風景を思い描き続ける男と、見えていなかったはずのそれを可視化し自在に体現する男の、奇跡にも近い化学反応。
数週間後ようやくYouTubeに上がっているすべてのコントを見終えた私は、ひとりの部屋で声を上げて笑いながら、彼らと同じ時代に生まれたことに甚く感謝し、せめてあと10年早く生まれたかったなぁとちょっぴり後悔することになる。
で。見終えた後の私の暮らしはがらりと色彩を変え、休日になるたびに関連書籍や公演のDVDを集めるようになり、2024年の秋には縁あってコント公演『並行食堂』を観に行ったりもしたのだが、それはまた別のお話。
結局「『鼻兎』の人」が何者なのか未だぴんと来ていない。だって『鼻兎』以外にも色々作ってるんだもん。あと肩書きが「ラーメンズ」だけじゃないし。というか肩書きのつけようがないことばかりなさってらっしゃるし。ゆえに、一周回って今も小林賢太郎という存在は私の中で「『鼻兎』の人」のイメージのままである。「『鼻兎』の人」がまた何か作ってるな、きっと面白いんだろうな、という感じ。ただ、最近はそこに一種のリスペクトも加わった。「推し」とはちょっと違う感覚かもしれない。ラベルの貼りようがわからない、むしろ貼るのがもったいないと感じるような、明快にして漠然とした「好きだな」という感情。
昔の自分に言えることは「覚悟しとけよ」ということだろうか。お前が読んでいるそれは沼の入り口で人生の分岐点で、価値観の礎になるからな。

人の心は、そのときに求めていることを受け取るんだと思います。感動を求めている人は、感動を。学びを求めている人は、学びを。救いを求めている人は、救いを。
だから表現者は、やりたい表現に没頭していればいいんです。受け取り方は、受け取ってくれる人の心が決めることです。
『表現を仕事にするということ』。
ラーメンズに「ハマった」と自覚した後、速攻で書店で入手しその日のうちに一気読みしたが、この一節がすとんと気持ちよく腑に落ちた。ああそうか。そうだな。今までハマってきた作品って、小説でも映画でも音楽でも、どれだけふざけていても作り手は至って誠実で熱くて、全力な人が多かった。真面目に真剣に、楽しいことを突き詰めていける人の創るものだからこんなに好きでい続けられたのかな。それが変な鼻の変なウサギだったとしても。でもあの日『鼻兎』を読んでいた私は、枯渇していたセンスみたいなものをたしかに掴んでいた気がするのだ。田舎の街で、話題について行けない自分でも、ハナウサギという面白いやつに出会えたからいいか、と前向きになれたのだ。
そして「『鼻兎』の人」というここ数年(正確には九年)の偏った認識も、ある意味では幸運だったのかもしれない。あんな面白い世界を描ける人だと知っていたからこそ、今になって興味を持つことができた。後々出会った作品たちも「『鼻兎』の人」以外の先入観や事前知識がなかった分、純粋に楽しむことができた。
オチがつかない文章になってきたのでこの辺で。季節みたいに、人生にも周期ってあるもんですね、と近頃ハナウサギを見ていると思います。再会、ともいうのかな。いやちょっと違う。会うたびに知らなかったことが増えていく。幾度かの「懐かしいな」をしながら、「初めまして」が多すぎてワクワクさせられっぱなしだ。
顔を上げる。雑然とした机の上、放り出された手帳には来月観に行く舞台の予定が書き込まれていて、壁に掛けられたコルクボードにはチケットがピンで留めてある。楽しみだな、とまだ観てもいないのに笑みがこぼれている。
さいごに。幼い自分を何度もシュールな世界に引きずり込んで笑わせ、驚かせてくれた小林賢太郎さんにこそっとここで感謝を述べておく。『鼻兎』を、変だけどめちゃくちゃかわいいやつをこの世に連れて来てくれてありがとうございます。貴方というひとを知ったきっかけが『鼻兎』で本当に良かった。
執筆BGM。
『鼻兎』から離れていた時期に聴いていた曲からふたつ。「眠り」がテーマの楽曲ってなぜか時々、鼻兎が眠れなくなる話(2巻所収の「寝る」とか)を思い出すんですよね。眠れない夜に寂しがってないといいけどな。
