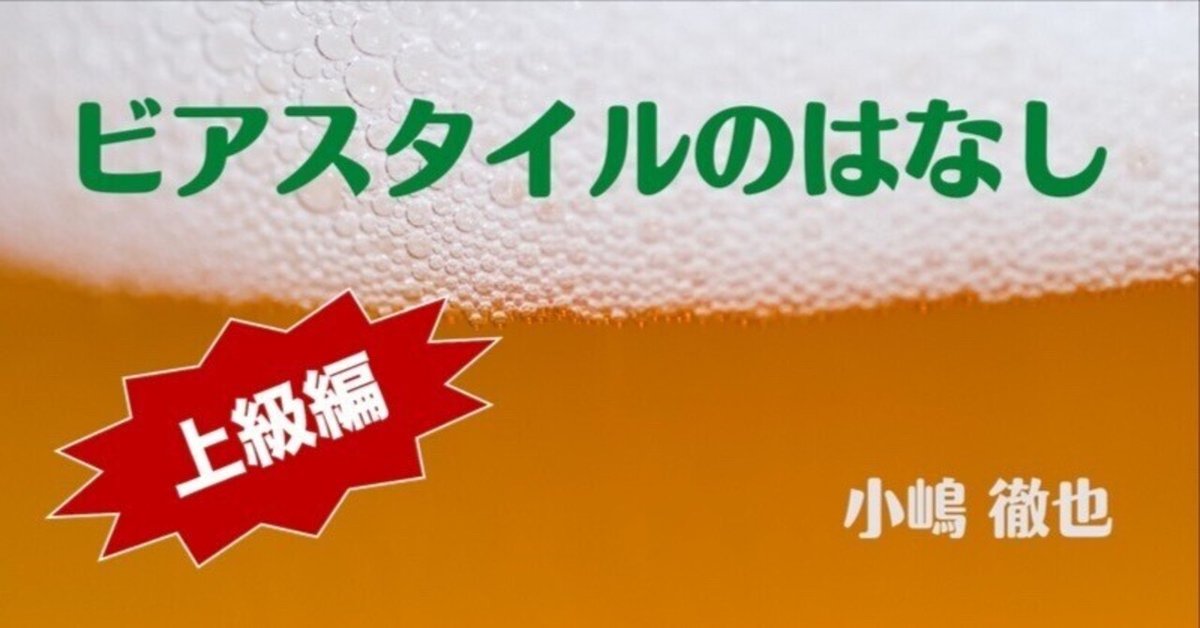
3. 柚子ビール
柚子ビールは2020年に日本で定義された新しいビアスタイルである。柚子を使用したビールはそれまでにも数多く作られていたが、以前は「2. フルーツビール」にカテゴライズされていた。そのため、スタイルガイドラインの記述もフルーツビールと共通する部分が多いが、柚子ならではの特徴も少なくない。
まずは、柚子ビールというスタイルが誕生した経緯から話を始め、その後、スタイルガイドラインの内容を吟味していこう。
スタイル誕生の背景
先に述べた通り、柚子ビールは日本地ビール協会が発行しているビアスタイルガイドラインの2020年版で定義された新しいビアスタイルである。米国を含め、日本以外のガイドラインにはまだ掲載されておらず、日本発のビアスタイルとして世界に発信を始めた、いわば出来たてほやほやのビアスタイルと言えるだろう。
これまでのビアスタイルガイドラインに収録されてきた日本由来のビアスタイルとしては他にも以下のようなものがある。
酒イーストビール
節税型発泡酒
その他のビール風味アルコール飲料
このうち、酒イーストビールは海外でも多くの商用サンプルがあり、米国 Brewers Association(BA)のガイドラインでも古くから Japanese Sake-Yeast Beer として定義されている。節税型発泡酒とその他のビール風味アルコール飲料(いわゆる第3のビール)は日本のガイドラインだけに見られる独自のビアスタイルである。
一方、日本を含むアジア地域では、フルーツなどの副原料を用いたビールのバリエーションが非常に豊かで、この地域の特徴を活かしたビアスタイルを世界に向かって発信していこうという動きが2010年代の後半から見られるようになった。この中で白羽の矢が立ったのが柚子を使ったビールである。
特に2018年のInternational Beer Cup(IBC)では、フルーツビールのボトル・缶部門の金賞と銅賞が共に韓国の Whasoo Brewery、The Tableが醸造した柚子を用いたビールで、ケグ部門でも金賞は日本の常陸野ネストビールが醸造した柚子ラガーであった。
BAのウェブサイトには、新しいビアスタイルの定義について以下のような記述がある。
The Brewers Association’s beer style guidelines reflect, as much as possible, historical significance, authenticity, or a high profile in the current commercial beer market. Often, the historical significance is not clear, or a new beer type in a current market may represent only a passing fad and is quickly forgotten. For these reasons, the addition of a style or the modification of an existing one is not undertaken lightly and is the product of research, consultation, and consideration of market actualities, and may take place over several years.
要するに、新しいビアスタイルを定義する際には、歴史的な重要性や現在のマーケットにおいて商用のサンプルがどの程度流通しているか、一時的なブームで終わるリスクが少ないか、などを慎重に検討した上で時間をかけて議論すべき、ということである。
以上のことに基づいて議論を進めた結果、柚子を使ったビールは審査会での実績もさることながら、日本だけではなく韓国や台湾などでも数多く作られていることから、2020年版のガイドラインからアジア地域を代表するビアスタイル、日本発の新しいビアスタイルとして柚子ビールというカテゴリーが誕生したわけである。
なお、2022年のガイドラインからは、同様に日本発のビアスタイルとして緑茶などお茶を使ったビアスタイルも新たに定義されている。これについてはまた先の回で扱うことにしよう。
では、以降では実際のガイドラインの記述について吟味を進めていくことにする。
外観
まず、前回のフルーツビールと今回の柚子ビールの外観について共通する部分を整理しておこう。
色合いは、ベースにしたスタイルに基づいて、ペールから非常にダークな色の範囲(SRMは5〜50)
外観はクリアでも濁っていても許される
逆に相違点は、フルーツビールの記述にあった「使用したフルーツの色を反映している場合が多い」という文が柚子ビールの記述には見られないことくらいである。実際、柚子のどの部分を使用するかにもよるが、柚子による色は黄色系の色に限られるとすれば、ほぼベースのビアスタイルの色が反映される場合が多いと考えられる。ちなみに、色度数の部分には柚子ビールの場合にも「または使用したフルーツの色」という注釈がついている。ひょっとするとこの部分は不要であるかもしれないが、例えばベースのビールがジャーマンピルスナーなど、ピルスナー麦芽だけを用いた淡い色のビールである場合には柚子果汁などを用いることでさらにSRM値が低下する可能性も考えられる。そういう意味では、この注釈を残しておくことにも一定の意味はあるかもしれない。
アロマとフレーバー
柚子ビールについては、柚子の果実としての特徴に基づき、次のような記述がなされている。
柚子は日本の特産品で、強い香りと酸味を特徴とし、皮がでこぼこしている柑橘系フルーツである。柚子ビールは、柚子を丸ごと、果汁、シロップ、粉末、あるいは表皮を糖化時、煮沸時、一次発酵時または二次発酵時に使用することにより、ほかのキャラクターと調和したフルーティーまたはスパイシーなキャラクター(強弱を問わない)を備えている。
フルーツビールとの相違点をあえて太字で記載したが、柚子の使い方として果実を丸ごと使う場合、シロップや粉末を使う場合、さらには果皮を使う場合について言及している。これらは実際の商用サンプルで見られた例を考慮に入れた記述だろう。さらには柚子、特に果皮から感じられるスパイシーなキャラクターが付与されるという点も、フルーツビールでは見られなかった表現であり、柚子ビールに独特な特徴であると言える。
アロマやフレーバーに関するその他の部分は、フルーツビールと同様である。具体的には以下のように記されている。
柚子のアロマ、フレーバーは強弱を問わず、ホップアロマに負けない程度にはっきりしている
ホップのアロマ・フレーバーは感じられないレベルかミディアム・ロー以下
ホップの苦味は非常にローからミディアムで他とバランスがとれている
モルトのアロマ・フレーバーも感じられないレベルからミディアム・ロー
したがって、基本的な考え方は一般のフルーツビールの場合と違わない。柚子ならではの特徴が追加されているだけ、と考えればよい。
他のスタイルとの差別化
使用する酵母はベースのビアスタイルに基づいてラガー酵母でもエール酵母でもいい、というのはフルーツビールと同様であるが、フルーツビールとは大きく違うのが、他のスタイルとの区別についてである。
小麦を使用した柚子ビールまたはベルジャン酵母で発酵させた柚子ビールも、このビアスタイルに該当する。また、柚子にハチミツを加えたビールも、柚子ビールに該当する。
フルーツビールの場合は、小麦を使用した場合は「4. フルーツ・ウィートビール」に分類、ベルジャン酵母で発酵させた場合も、「5. ベルジャンスタイル・フルーツビール」や「29. ブレットビール」などに分類というルールがあったが、柚子に関しては柚子ビールのスタイルを優先すべき、ということである。柚子と蜂蜜は相性がいいため、両者を用いたビールも見かけることもあるが、蜂蜜を使った場合であっても、「15. ハニービール」ではなく、この柚子ビールのスタイルを優先せよということである。
一方、常に柚子ビールを優先すべし、というわけではなく、例外がある。例えば、柚子と唐辛子を同時に使用した場合である。柚子七味、なんてものがあるので、これを用いたビールも実際に商用サンプルが存在する。前回のフルーツビールの回でも述べたが、実は唐辛子を使用した場合は、量の多少に関わらず、例外なく「11. チリビール」に分類すべし、という記述がある。以下にチリビールのスタイルの記述を引用する。
チリペッパー(トウガラシ)を含んだビールはすべてチリビールに該当する。
したがって、いくら柚子を使用していたとしても七味唐辛子が使用された時点で、そのビールは「11. チリビール」に分類されるべきなのである。実際、今年行なわれたInternational Beer Cup(IBC)2024においても、チリビールのケグ部門で、長野県の麗人酒造が醸造した「ゆず七味唐辛子ビール」が銅賞を受賞している。ちなみに同社は、「七味唐辛子ビール」でも金賞を受賞している。これらは日本の食文化をうまく反映したサンプルであると言えるかもしれない。いずれにせよ、本当はフルーツビールと同様に唐辛子を使用した場合についても言及しておくのが親切なのかもしれない。
その他の特徴やパラメータ・注意点など
ボディはベースにしたビアスタイルによって異なる、という点はフルーツビールの記述と全く同じである。さらには初期比重、最終比重、アルコール度数、ビタネス・ユニットなどのパラメータもフルーツビールの場合とまったく同一である。
フルーツなどの副原料を用いたスタイルの場合は審査会に出品する際に付加的な情報を明記しなければいけないという注意点があることは前回も述べた。これについても多くの部分がフルーツビールと共通している。具体的な共通部分は以下の通りである。
ベースにしたビアスタイル名を明記
柚子を使用したタイミング(糖化時、煮沸時、一次発酵時、二次発酵時あるいはそれ以外)
ベースのスタイルが既存のビアスタイルのどれにも合致しない場合は「既存のスタイル外」と書いても構わない
フルーツビールと柚子ビールの記述における相違点は2点あり、一つは使用した柚子の形状として、果実を丸ごと使うのか、果汁、シロップ、粉末あるいは表皮などどの部分を使うのか明記することという点である。フルーツビールの場合は単に使用したフルーツの種類だけしか求められていなかった。二つめは、フルーツビールの場合にも記載されていた「そのほか特別な原料を使用していればその名前と使用法を明記すること」である。柚子ビールの場合は、この「特別な原料」の例として「ハチミツや小麦など」というのが明示されている。これは、上で述べた通り、柚子とハチミツを同時に使用するサンプルが日本や韓国などに多く見られること、加えて、小麦を用いた場合もフルーツ・ウィートビールではなく、このスタイルを優先して考えるというルールに則った記述である。
日本地ビール協会が主催するIBCなどの審査会では、柚子ビールの出品数は比較的多く、今年のIBC2024においては、ジャーマンスタイル・ピルスナーと並び全体の13番目に出品数の多いスタイルであった。日本だけではなく韓国など海外の醸造所が金賞を受賞する例も見られる。アジアを代表するビアスタイルとして、いずれBAなど海外のガイドラインにも含まれる日が訪れるだろうか?
おくゆかしく宣伝を…
さて,このようなビアスタイルについて楽しくざっくりと知りたいという方には、拙訳の『コンプリート・ビア・コース:真のビア・ギークになるための12講』(楽工社)がオススメ。米国のジャーナリスト、ジョシュア・M・バーンステインの手による『The Complete Beer Course』の日本語版だ。80を超えるビアスタイルについてその歴史や特徴が多彩な図版とともに紹介されている他、ちょっとマニアックなトリビアも散りばめられている。300ページを超える大著ながら、オールカラーで読みやすく、ビール片手にゆっくりとページをめくるのは素晴らしい体験となることだろう。1回か2回飲みに行くくらいのコストで一生モノの知識が手に入ること間違いなしだ。

また、ビールのテイスティング法やビアスタイルについてしっかりと学んでみたいという方には、私も講師を務める日本地ビール協会の「ビアテイスター®セミナー」をお薦めしたい。たった1日の講習でビールの専門家としての基礎を学ぶことができ、最後に行なわれる認定試験に合格すれば晴れて「ビアテイスター®」の称号も手に入る。ぜひ挑戦してみてほしい。東京や横浜の会場ならば、私が講師を担当する回に当たるかもしれない。すでに資格をお持ちの皆さんは、ぜひ周りの方に薦めていただきたい。会場で会いましょう。

