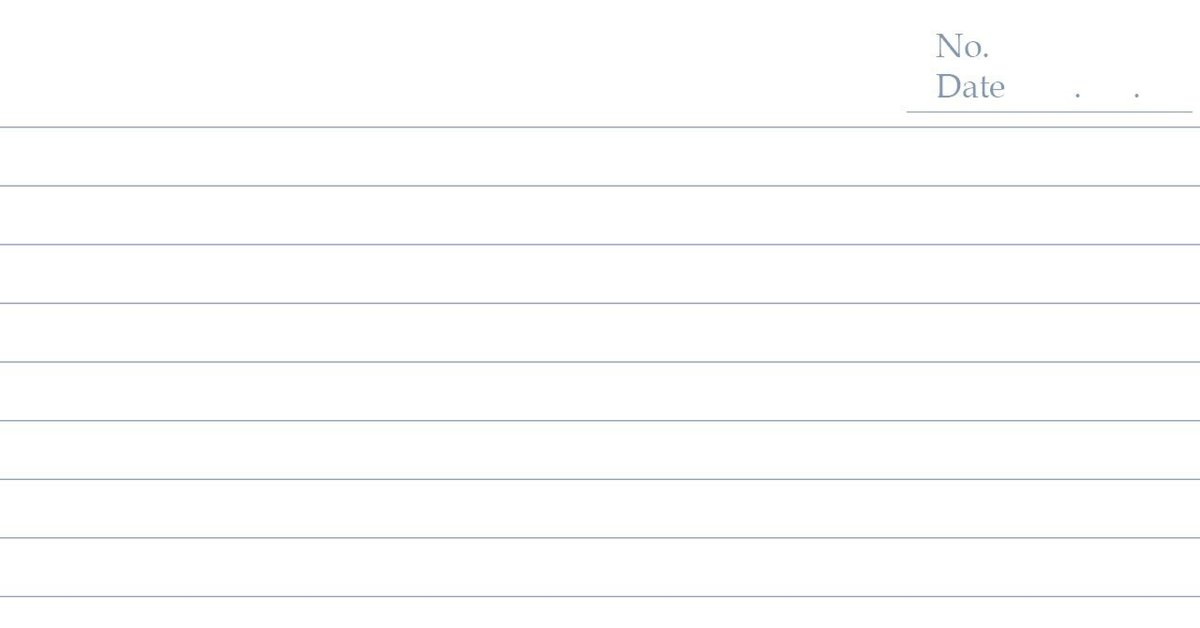
【読書記録】英米の怪異・幽霊譚本
『ゴーストリィ・フォークロア』南條 竹則 著
副題「17世紀~20世紀初頭の英国怪異譚」。
パール系用紙に飾り曲線の箔押し追加なカバーや、黒紙にメタルインク刷のトビラ、本文も黒でなく紫系の色インク刷と、装丁がまずお洒落というか独自路線。
そして本文も、著者の自称が「吾輩」だし、「蟷螂」「到底」「髑髏」のように難読語(読み方の難しい熟語やその漢字本来の読みどおり読まない語。ふりがなは付いてるけど)があったり、語尾が「かしらん?」「~ぢゃ」だったりと、「…これは何十年前の本の再刊なのか?」と思ってしまった(実際は2020年1月初版発行)。
ただ、本編本文にも「『源氏物語』は現代口語に訳すことはなくて、読みやすい近世文語に訳すのも一つの手」といった話が出てくるのだけれど(古典を疑古調文体で訳すのは、欧米でもよくあることだという)、この本の内容もだいぶ前の怪異話だし、本文の筆致が古風で丁度よいのかも。。
なるほど完全に現代口語にされてしまうと、やんごとなき姫君が御簾の向こうで歌を詠むにも雰囲気が出ない…(しみじみ)
日本になくイギリスにあるのがバラッドの伝統。
バラッドは元々詠み人知らずの口承文芸で、内容は様々だが物語の性格が強く、超自然を歌ったお化け物が重要な一分野をなすという。
日本でもお化けの口承文芸は数多いが、韻文なら「歌われて」「歌に乗って」語られるが、散文だから「語る」ものだそうで、それは自分自身も実感としてあり……日本の場合、民話もだが子守歌や遊び歌も、あまり韻を踏んでいない気がするのですよね。欧米の詩はもう「踏んで踏んで更に踏む」と踏むことが使命つか生きがいみたいに見えるくらいだのに(言い過ぎ)。
中世盛んだったバラッドも、近世以降は消滅。しかしトマス・パーシーなどの文人たちによって収集と記録が進められたので、今日でも多くの古謡を読むことが出来るのだという。
また、19世紀初め(いわゆる「ロマン派」の時代)には名だたる詩人たちが民謡の形式に則って書いた詩を発表し、古謡とは中身が違えど形式だけは似ている「文芸バラッド」というジャンルも成立。
洋の東西を問わず、芸術家は過去に学んでいる(悪く言えば過去の型を借りて自作を生み出すネタにしてる)んだなあと思ったり。
それこそいろんな話が載っていて、そこには欧米らしい思想と文化があり、逆に世界規模で見られる話の類型が存在していたり(異類婚姻譚、継子いじめ、なんかはよく見る)。
日本ではあまり知られていない英国の詩人や文学者が何人も紹介されていたり。
イギリスと一口に言ってしまうけれども、イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランドからなる連合王国であり、各国間には過去から現在に至るまでの歴史と感情との軌跡というか軋轢的なものが残されていると再認識したり。。
中でも自分的に印象に残ったのが、
芥川龍之介版『杜子春』が、『唐宋伝奇集』中の『玄怪録』の杜子春話と比べるとだいぶ違う点。
芥川がこれと違うものを原典として書いた可能性は無論あり、そちらの原典には沿っていたのかもしれない。しかしながら、『玄怪録』と比べると、芥川版『杜子春』はだいぶん日本風かつ子供向けに改変されている、ということになる…のだそうで。
主人公が仙人になりたくて無言の行に入るが、自身の親が獄卒に責めを受ける姿を見て、遂に言葉を発してしまう・・・というのが芥川版。
『玄怪録』では、主人公は自身も斬り殺され、地獄に行って責め苦にあった後、女性として生まれ変わる。文人と結婚し子供をもうけるが、そこでも無言を貫いたため、夫は「お前、俺を馬鹿にしてるのだろう」と激怒、子供の両足を掴み、頭を石に叩きつける。子供の頭が砕け、血が飛び散ったとき、女に転生した主人公は「ああ!」と呻いてしまう。
*
芥川の杜子春は子が親を思う気持ちから声を出したが、こちらはその逆で、子への愛情故に無言の行をしくじるのである。しかも、それが父親の愛情ではなく、母親がお腹を痛めて生んだ我が子に寄せる強い感情であり、その心を知らしめるために杜子春を女に生まれ変わらせる、という手の込んだ趣向になっている。
(引用)
*
「なんか騙されてたかもな感…これがホントなら、ちゃんと説明せえよ芥川先生よぉ」という感じだった(正直な感想)。
原典として使ったものがあって、あちこち変えたというのならば。誤解のないように、いっそ名前ごと変えてほしい(切実な気持ち)
ちなみに、なぜ杜子春の話になったかといえば、アイルランド版杜子春とでも呼べそうな話(芥川版でなく『玄怪録』版のように、不老不死を目指し無言の行をする女が我が子の死を見て声を上げる…という)が存在していた、というところからでした。。
「ファム・ファタル」という語は日本では「宿命の女」と訳されるが、原語の意味は「命取りな女」に近く、男をトロかす佳い女だがトロかすだけでなく滅ぼさないと気が済まない。
*
女郎蜘蛛だ。雌蟷螂だ。おとこごろしだ。
(引用)
*
は、かなり生々しい。
日本では猫はよく化けるが、犬は桃太郎でもいうように味方の立ち位置で、こちらを脅かす、いわば敵側の妖怪として出てくるのをあまり目にしない。しかしブリテン島では恐ろしい猟犬が幾つも出てくるといい、「黒い犬」が代表格で、コナン・ドイルの『バスカヴィル家の犬』もこうした下地に基づいているという。
これは、日本ならば殿様の狩りといえば鷹狩りで、お鷹組が偉そうにしていた訳だが、英国では猟犬を使って狐や鹿を追う狩であり、「dog」でなく「hound」、つまり「猟犬」の語が、犬あるいはそれ以外の何物かの妖怪に使われる(ことが多いらしい…本文を読むに。ただし代表格の「黒い犬」は「ブラック・ドッグ」と対応している)。追われる狐や鹿にとって猟犬は「地獄の鬼」で、狩を楽しみ狐や鹿を追い殺す人間の側が、殺される側になりかわる想像力を働かせたことが、猟犬妖怪が生まれた理由ではないか、と。
それにしても末章『老水夫行』(前述「文芸バラッド」の代表作、「The Rime of the Ancient Mariner」の邦訳タイトルが、章タイトルになっている)にもあったけど、英国文学者だから英国の文学だけに精通してればいいという話でもないんだよなと再認識。それは他地域の文学、さらには文学に留まらず歴史その他の学問にも言えることで。
この「行」は中国の韻文の一ジャンルであり、英語「rime(「ナーサリー・ライム」のライムrhyme=韻、韻文とほぼ同義の語と扱っている辞書も)」の訳語として古人が当てたものという。つまり、この詩を翻訳した人物は、英国文学・英語・英国文化のみならず、中国文学に関する知識もあったということで。文字通りの「老いた水夫が行く」と読んではいけなかったのだ。
特定分野のプロフェッショナルを養成するのはいい、でもその分野「だけ」の「プロ」というのはどうなのかなと……本業以外でも才能をみせる天才が世の中には幾らでも居るし、逆に言えば、何かに特別秀でた人は他にも「玄人はだし」くらいの趣味がある、ということじゃないかと。そんな風に思う次第です。。
掲載順に書いたら、なんかまとまりが無くなってしまったけど……そんなところです。。
ともあれ、東洋人の無いものねだり的に欧州の民話に妖精や聖騎士みたいな美麗イメージとかばかり抱いてると、「人間、恐怖を感じる根っこには世界共通の領域がある」というか、実際そうでもない話もあったりするし、心臓に毛を生やさねばと思えますよね(爆)
『ゴーストランド 幽霊のいるアメリカ史』
コリン・ディッキー著、照井 ひろ美 訳
アメリカ合衆国は、国家としての歴史は世界規模でみれば浅いのかもしれないが、入植、原住民との闘争、独立、奴隷制度と南北戦争、銃と犯罪、自殺や事件事故、のように遺恨を残し死んだ者達が幽霊となってこの世に留まる要素を十二分に備えており。
しかし巻頭の「これは、幽霊に関する主張の真偽について語る本ではない。」という著者の言葉。更に、訳者の「各地に伝わる幽霊の物語を人々がどのように扱い、どうやって向き合ってきたかが生き生きと語られています。」との評からも分かるように、これはオカルトではなく民俗学だとしても直球ストライクとはちょっと違くて、もしかしたら社会学的なところにも入ってる本なのかもと思ったり(※個人の見解です。ちなみに図書分類の番号としては380:民俗学でしたが)。もちろん世界的に言える傾向も中にはあるんだろうけども、他地域・他国とは異なる事情が幽霊話にも反映されている部分も確かにある、そんな印象を持ちました。
中でも、
*
そしてここに、幽霊の仕組みの中心的なパラドックスがある。生者を幽霊に変えるのはその人を空っぽにすること、きわめて重要ななにかを奪うことだ。だが、死者を幽霊として生かし続けるのは、その人を思い出と歴史で満たすこと、そうしなければ失われてしまうものを生かし続けておくことなのだ。
(引用)
*
は示唆的に感じます。
幽霊話の出現と定着は、偶然と生ける人間の、ときに迂闊な思い込み、という事例も。
シカゴ・グレイスランドの墓地では、アイネズ・クラークという少女の泣き声が聞こえるかもしれない、という。
雷に打たれて亡くなった幼女の墓には幼い少女の石像が立ち、彼女はまだ雷を怖がっていて、雷雨の間は像が消えてなくなる、と人々は言い張る。
しかし、調べてみるとこの少女の死因はジフテリアで、彼女の母親は再婚でクラーク姓となったばかりのときに娘を亡くし、後には前の結婚で子供がいたことを否定。埋葬記録に名前の誤記載があったり、像が作られたのもアイネズの為ではなく販促サンプルだったとかで、大方の意見は一致するという。
*
つまり、子供の身元にまつわる些細な混乱と、石像の目的の説明がすぐに見つからなかったことが原因で伝説が生まれ、話題になったというわけで、たしかに記録の管理がずさんなところには幽霊がいつもやって来る。
(引用)
*
実際問題、幽霊の噂が独り歩きしてるというか、詳しく調べてみると「出る」人物は死んだ場所も理由も違っていたりするケースがそれなりに存在するみたいな感じで。なんか噂話って無責任だなと思ったり・・・。
補足としては、アメリカでもまた葬送様式が変遷中らしく(日本で土葬が火葬に取って代わられ絶滅寸前であるように、アメリカでも庭園墓地での贅沢で豪華な葬儀を行う時代は終わりに近づいているのかもしれない、と)。教会墓地→庭園墓地→・・・。墓地を訪ねる人が減れば、墓地は放置され、幽霊も増えるのではないか、とのこと。
幽霊話を観光・ビジネスに利用する地域や組織もある。
ある種の無生物は、ある種の行動の痕跡を記録する用意ができていて、それをあとで再生する、とするストーン・テープ理論とも呼ばれる考え方があるという。
この理論に沿えば、橋で起きた事件そして被害者の悲鳴を橋の石材が記憶していて、再生するのだと。それが、その場所での犠牲者=地縛霊の説明ともなるらしい。これは日本でも時折見聞きする、災害や事故、自殺の現場で犠牲者が命を絶ったときの出来事が繰り返し再生されているような状態を生者が目撃する話に通じる。
そして、幽霊の大部分は「生きている人によって作り出されたイメージにすぎない」という考え方も出てくる。
この、ストーン・テープ理論と生者による心霊的プロジェクター役割論とにより、私には「幽霊の出方とは、さながら生者の力量次第」みたいにも感じられた。
正直、幽霊が出る場所というのは、邸・病院・通り、など、ある意味人間が行きそうなところほぼどこでもという印象もあるが、「幽霊屋敷」というとその土地のことをよく知らない金持ちが引越してきた贅沢で広大な邸であり、家族が呪われたがごとく次々死んでいく、的なイメージが強い気は私もしている。なので、やって来た金持ちは地元の人々とくに貧しい層の反感を買うというのも、複数の話から見える。反感というのも「あんたらのせいで、この町・村全体のイメージが悪化した」だったり。。
地元の幽霊、超常的な不動産問題、もてる者ともたざる者の対立の超自然的な展開。そんなものに悩まされている町は、注意深くみればアメリカのどの州にでもある、と著者は言っているようで、「不動産をめぐる争いほど幽霊をもたらすものはない」とも記す。これにも納得する。
今現在、SNSでは登録者・利用者が亡くなったことを知らないサービス提供元が、死後もそのアイコンをあちこちで表示させる、あるいは第三者が死者の写真と知ってか知らずか、ありし日の写真を無断借用し広告や出会い系的なのに利用してしまうこともあるそうで、それもある意味「ネットが生み出す幽霊」と言えるのかもしれず。
未来が分かるのなら解約してから旅立つのだろうけど、そんなの分からない人が大多数ですからね…今後もそういう事例はなくならないのだろうと。
著者による一文、
*
幽霊話は、私たちが過去とどう向き合うか、または向き合わないかの話だ――どのように情報を処理して、過去を物語り、その歴史の中に生じた空白をどう理解するかということになる。
(引用)
*
のように、言ってしまえば幽霊話は生者が未解決事項を説明するための一方便、であるのかもしれません。
ただ、一方で著者は「たとえきっぱり追い払うことができたとしても、我々には幽霊が必要なのだ。」とも述べる。幽霊は重要であり、我々は真実を知りすぎたくないと思っている、と。
そうなると、元から答えなどない問いなのかもしれません。
ところで、アメリカの有名な怪談といって私が思い出すのは、暗殺されたリンカーン大統領がホワイトハウスで目撃されたとか、フォックス姉妹の霊交信、セーラムの魔女裁判、あたりですが。
過去に読んだとある本に「アメリカで降霊会に集まったのは所謂暇な主婦たちが多く、そういえば今時のスピリチュアルにハマるのも、こういう層な気がする」的なことが書いてあって、全力で肯定もせんけど全面否定も出来んなぁ、と思ったものです(爆)。霊界との交信は、家父長制が強い当時の世の中にあって立場が弱かった婦女子の生きがいというか晴れ舞台、あるいは「はけ口」であったのかもしれない、という考え方には相応に納得がいきます。
現代日本でも、近代科学文明の進化・浸透により闇が減って駆逐されていくはずだった妖怪が滅びていないのは、都市部もまた妖怪出現に必要な要素を備え、妖怪という存在を通し何かを表現したいと思う人間――若い女性や子供が多い――が存在し、迷信と否定されても生み出され続けるからだ、といったことを小松和彦氏が書いていたし(『怪異の民俗学②妖怪』小松 和彦 責任編集)…それと重複する部分もあるのかな、と。
それにしても、フォックス姉が「最初に家で聞こえた『叩く音』は、でっち上げだった」と公の場で告白するも心霊主義者たちに非難されて撤回せざるを得なくなったって話……
よく、「お化け屋敷が開業すると、やがて本物が集まって来る」といいます。最初は自作自演だったのかもしれないけれども、いつからか「本物」が関わるようになっていた…という可能性もあった、かもしれません。
コナン・ドイルも巻き込まれた妖精写真の真贋をめぐるコティングリー妖精事件でも、当事者の少女たちが老婆になってから「あれは自分たちでやったこと」と古典的ともいえるトリックを明かしたわけですが、「でも、ただ1枚だけ、私たちがやったものではない写真があるのです」、つまり「大半が捏造なのは認めるけど、本物が存在するのだ」と主張したことが付記されてたりしますから(この妖精事件に関してはネット上にも記事があるので、詳細や典拠はそちらを参照されたし)。。
セーラムの魔女裁判では逮捕・処刑された人物の財産は没収されて特定の人物が潤った事実が存在し、この事件に関しては諸説あれど「仕組まれた陰謀説」も真実味を帯びているとしか。
欧州の魔女狩りもそういう部分があったのだろうけど、世間的に人付き合いが悪いとか、健康面に不安があったりとか、あとは人が羨む財産的なの持ってたとか…そういう「厄介者」「恵まれた者」に矛先が向けられたというのはあるんじゃないかなと思わざるを得ない。
そんなこんなを考え合わせ、強いて何かまとめるとするなら、「死者よりむしろ生きている人間のほうが怖いんじゃないか」になってしまう(地)。
でも実際そうなのかもですね。。
