
この社会を生き抜く子どもを育てるためのヒントは「小学校受験」にあり
慶應幼稚舎、慶應横浜、早稲田に140名合格!(※2024年度合格者) 最難関小学校受験に強い幼児教室として、多くの親たちに支持されているスイング幼児教室が教えるおうち教育のメソッドが一冊にまとめられた、『スイング幼児教室が教える 冒険力の育て方』。本書の「はじめに」を公開します。
小学校受験には、子育ての重要なヒントがある
小学校受験を取り巻く状況は、この10年間で大きく変化しました。特に小学校受験に興味関心を示す親たちが確実に増えてきました。
「私立小学校ではどんな教育を行っているのですか」「小学校受験ではどんな試験を実施するのですか」「受験をするためにはどんな準備が必要ですか」、そんな質問を受けることが増えています。今や小学校受験は子どもを持つ親たちにとって、関心の高いトピックのひとつになったと言えるでしょう。
背景にあるのは、社会に対する意識の変化です。パンデミックや自然災害、世界情勢の急激な変化などの乱世を経験した私たちは、先の見通しが立たない未来を生き抜くためには、これまでのやり方では通用しないと感じるようになりました。そして子どもを持つ多くの親たちが、単に学力を高めるだけの教育では十分ではないと気づき始めています。
これからの社会を生き抜くことができる子どもに育てるためにはどんな教育が必要でしょうか。そのヒントとなるのが小学校受験です。この本を、小学校受験をしない方でも、子育ての参考にしていただき、親子の学びに取り入れてほしいと思います。

これからの子育てで問われるのは未来への可能性
小学校受験では、学力のみで合否を決める学校はほとんどありません。入学試験で取り入れている学校も多い「行動観察」の試験では、グループでの共同作業を通して他者との関わり方を多面的に評価します。単にリーダーシップを取ればいいということではなく、グループの中で自分の役割を見つけ、適切な発言や行動を取れるかどうか、目的達成への意欲、判断力などを採点します。
多くの私立小学校は、これからの社会を自分の力で周囲の人と協力しながら生きていくことができる人材を育てたいという考え方を持っています。入学を希望する子どもたちには、勉強ができるだけという、詰め込み式の準備で得られるような紋切り型の能力ではなく、他者を尊重できることや自分のことは自分でできる生活力、自らの想いを言語や形にして伝える表現力など、人間としての総合的な力が求められています。
これらは、子どもたちの未来に必ず役に立つ能力です。そして、小学校受験に向けた学びは、単に合格を勝ち取るためだけではなく、子どもたちの未来を豊かにする取り組みのひとつであること。そのことを今の時代の親たちは感じ取っていると思います。
小学校受験の評価方法は、企業の就職試験とよく似ています。就職試験で受験者に問われるのは、知識や常識だけではありません。面接ではこれまでどのような活動や経験をしてきたかを問い、グループワークやディスカッションなどを通じてコミュニケーション能力を多面的に評価します。企業が人材に求めているのは、状況の変化に対応しながら成果を上げることや、周囲の人と協力しながら仕事を進められることなど、学力だけでは測ることができない人間力としてのポテンシャルの高さです。
小学校受験と就職試験という「入口」「出口」は多面的評価、その間にある中学受験、高校受験、大学受験は学力中心の評価となり、試験方法が大きく異なってきます。まさに、小学校受験の学びは、社会で活躍できる力の基礎・基本であり、子どものポテンシャルを高めるものでもあるのです。
今、子どもたちに必要なのは冒険力
これからの未来へと踏み出していく子どもたちに必要なのは、【成功するかどうかわからなくても、まずはやってみようと行動し挑戦する力】だと考えています。それが冒険力です。
冒険力は、今大人たちに必要と言われているレジリエンス(困難にあってもしなやかに回復する力)と言いかえることもできます。
冒険力を身につけておけば、困難にぶち当たっても前向きな気持ちを失わず、知らない道でもワクワクしながら進んでいけます。どんなときも勇気を持って、一歩を踏み出すことができるのです。冒険力は子どもたちの未来を支える力になります。そして大人になってからますます必要となる力です。
冒険力は、本人に意欲があれば中学生や高校生になってからでも身につけることはできます。しかしながら、親が子どもを導きながら一緒に学ぶことができるのは、幼稚園、保育園の年少から小学校低学年くらいまで。この時期なら、生活の中で親子で楽しみながら学びを深めることが可能です。
今から始めれば、生きていく上での基礎・基本となる学びを、子育てという大切な時期に身につけさせることができます。幼児期からの学びはかわいそうなことではありません。むしろ幼児期だからこそ、親子で楽しみながら、家庭生活の中で取り組むことができます。そこで得た力は、これからの人生の大きな武器になるはずです。
「子ども」というフィルターを排除し、ひとりの人間として向き合う
私たち「スイング幼児教室」は、幼児であってもひとりの人間としての個性を認め、学力に限らず幼児期に必要なあらゆる力を高い水準で身につけることを目標としています。
小学校受験を通して子どもたちの多面的な能力を育むためのメソッドを研究してきました。幼児教室を創立し、短期間で合格実績を大きく伸ばすことができたのは、私たちの学びのメソッドが、これからの時代のニーズにマッチしたこと。そして家庭の教育ニーズや私立小学校の学びの変化にスピード感を持って対応してきたからだと考えています。
小学校受験は情報の非対称性が大きい世界です。小学校側の意図しない誤情報が、入学を希望する親の間に蔓延することもあります。しかし私たちは、家庭と小学校をつなぐ教室として適切な情報を提供することを心がけてきました。誤った情報や噂話などのノイズを排除し、やるべきこととやらなくていいことを区別し、必要ではないことは「必要ではない」とオープンに伝えています。やっておいた方が無難だろう、という曖昧な考え方や先生たちの属人的な判断はしないで、必要なことに集中して取り組むことが、子どもへの不必要な負荷を減らし、結果につながる一番の近道だと考えています。こうした姿勢も、親たちのニーズに合っていたのではないでしょうか。
そして私たちは、子どもたちのことを子ども扱いしないようにしています。ひとりの人間として、子どもたちに向き合っていきます。子どもも大人と同様に、それぞれ個性を持ったひとりの人間です。子どもだからこうすればよろこぶだろう、子どもだからこんなことはできるはずがない、子どもだから仕方がない、という偏った子どもフィルターでの考え方はしないようにしています。
小学校受験に取り組むことは、合格という目標へのアプローチとして有効なだけではなく、これからの人生にも必ず役に立つものだと実感しています。だからこそ、家庭での取り組みを通じて親子が絆を深めることもできるのです。そうした親子の様子を、私たちはずっと見てきました。
学びの始まりは、親子の関係づくりから
この本では、私たちがこれまで培ってきた冒険力を育むメソッドを公開します。幼稚園、保育園の年少から年中、年長、さらに小学校低学年の子どもに取り組んでほしいメソッドです。どれも家庭でできるものですから、ぜひ実践して冒険力を育んでいきましょう。
子どもが学びの実践をするにあたっては、親のサポートが必要です。親の振る舞いや声のかけ方は子どもの気持ちや行動に大きく影響します。それが学びの成果につながりますから、親が果たす役割はとても大きいのです。
そこでまず親が子どもと向き合うときの心構えから確認します。
Part1でチェックシートを用意していますので、自分自身がどのような親のタイプなのかを確認しましょう。自分自身や考え方の癖を知った上で、子どもを幸せに導く思考を身につけていただきたいと思います。
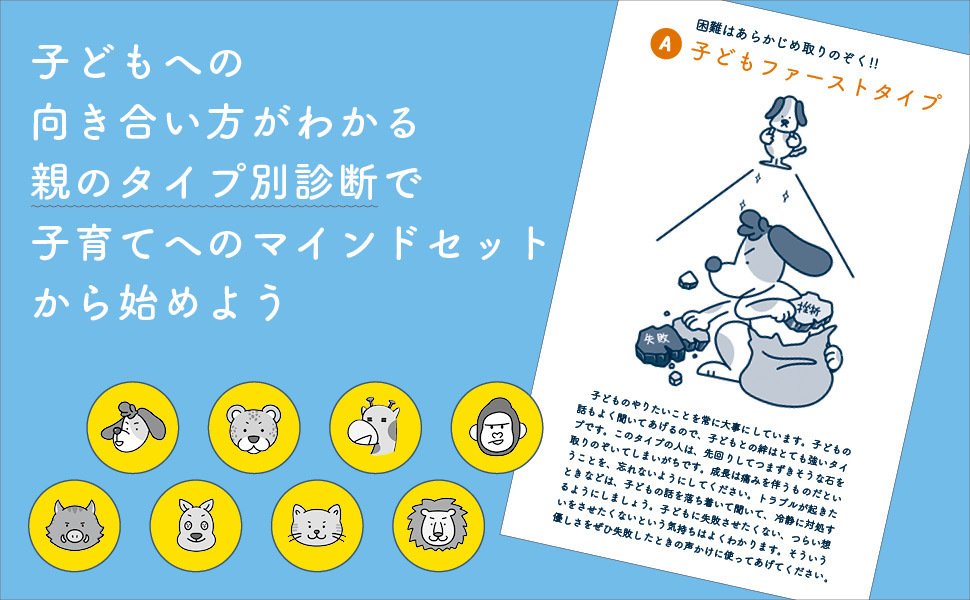
子どもと一緒に冒険力マップをつくろう
Part2では、子どもの現在地と目指すべき方向を明らかにして冒険力マップをつくりましょう。ここではスイング幼児教室で使っている願書作成シートをもとに質問を用意しました。その上で子どもの現在地を把握して戦略を練ります。これが冒険力マップです。
まず明らかにしたいのは、子どもの得意なこと、苦手なこと。今、何ができて何ができないのか。現在地がわかってこそ、成長や課題に気づくことができます。その上で「どんな大人になってほしいのか」というゴールを設定します。目指したい場所は、成長に伴って変わっていくものですが、学びを実践するにあたりマップを作成することで今やるべきことが明確になります。
Part3では、私たちが培ってきた学びのメソッドを公開します。子どもがゴールにたどりつくために必要な学びを「くらし力」「コミュニケーション力」「ちしき力」「からだ力」に分けて、「年少まで」「年中年長」「小学校低学年」という3つの年代ごとに課題をピックアップします。どれも家庭で取り組めることです。
年代ごとの区切りはあくまで目安や目標にすぎません。たとえば、「うちの子は年長なのに、年少の課題ができていない」と気にしないようにしてください。子どもによって、苦手なこと、得意なことは違いますし、成長のスピードもさまざまです。できなかったことを、できるようにするために、親子で一歩ずつ取り組んでいくこと、そのプロセスを大切にしましょう。
ここでは課題ごとに、過去に私立小学校で出題された入試問題も掲載します。小学校受験を検討している方はもちろん、興味や関心のある方もぜひ参考にしてください。
さらにそれぞれのパートでは、親が陥りやすい傾向に沿って、子どもの学びに楽しい気持ちで寄り添えるようアドバイスをします。親は子どもの学びのよき伴走者であることを、常に覚えておくようにしましょう。

親子で冒険を始めよう
子どもたちがまだ見ぬ未来に踏み出すこと、それはまさに冒険の始まりです。期待や不安を抱えながらも、自分で道を拓く勇気を持たなければ前には進めません。
「できないことをできるようにする」という目標に向かって、親子で一緒に取り組むことは、それぞれの人生の中でなかなか経験できないことであり、あとで振り返ったときにもとても幸せな時間だったと思うでしょう。
この本を参考に、貴重な親子時間を増やしてください。
私たちと一緒に冒険を始めましょう。

