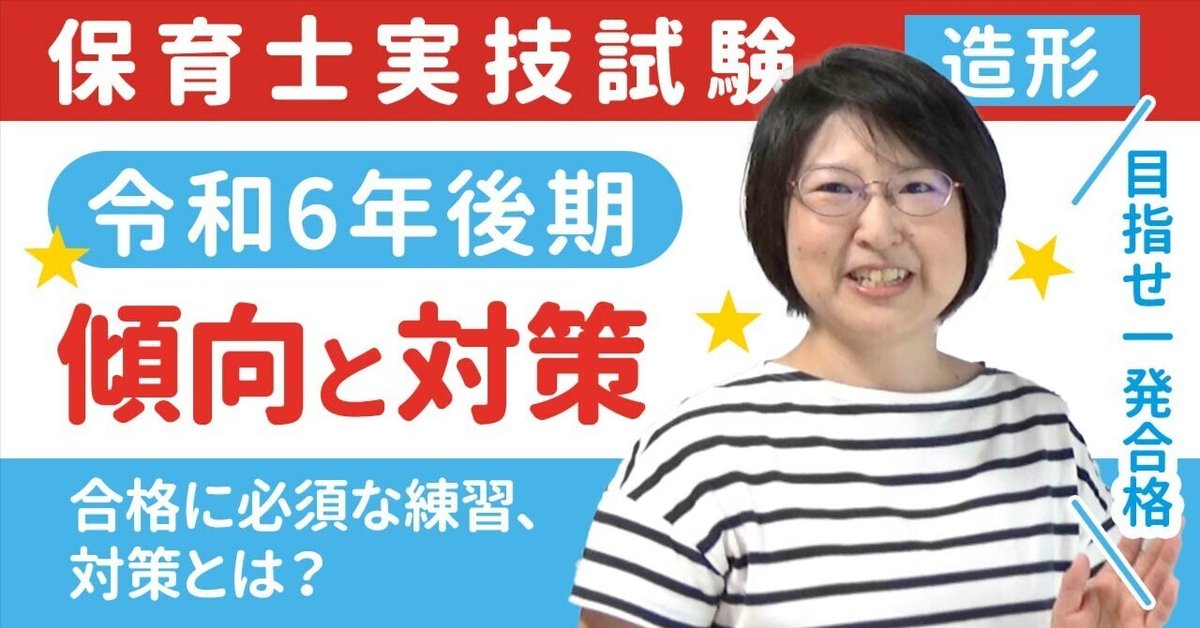
【保育士実技試験】令和6年後期【2024年】造形試験の傾向と対策 めざせ一発合格!合格に必要な対策と練習とは?!
こんにちはしろうずです。
筆記試験終了の皆さん、お疲れ様でした。
この記事では以前の試験傾向を踏まえつつ、令和6年後期の試験の予想とそれに向けての対策について説明していきます。
本記事はプロモーションを含みます。
*Amazonのアソシエイトとして、白水弘美(工房しろうず)は適格販売により収入を得ています。
Youtubeでの解説はこちらから
直近の試験の傾向
前回、令和6年の前期の造形試験はこんな問題が出題されました。
問題
【事例】を読み、次の3つの条件をすべて満たして、
解答用紙の枠内にその情景を描きなさい。
【事例】
E保育所の3歳児クラスの保育室には、子どもたちが自由に遊ぶことができる空き箱や使い終わった素材を集めて入れたカゴが置いてあります。子どもたちはそれらの空き箱等を使って遊んでいます。保育士は、その様子を子どもたちのそばで見守っています。
<条件>
1.【事例】に書かれている保育の様子がわかるように描くこと。
2. 子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと。
3.枠内全体を色鉛筆で着彩すること。
ざっくり構造を言いますと、軽く前置きがあり、その下に事例という形で、保育の状況が書いてあり、試験で満たすべき条件が3つ書いてあります。
そして、条件1で、事例通りに描くように指示する、という形です。事例と条件が一致するように指定がされています。
条件2では描く人間の設定と人数、条件3では色鉛筆での着彩の指定がなされていますね。
この事例の内容次第で試験傾向が大きく変わるというのがここ数年見られる傾向です。(*もっと以前は、事例そのものは変わらないのですが、条件で「〜して遊んでいる様子をかく」という大まかな指定でした。その場合は、条件さえ踏まえていれば、事例通りでなくても良いと解釈できます。)
●事例について(=条件1)
事例の内容については、前回の令和6年前期の造形試験では、遊びの内容がやや抽象的な指定で受験生が想像力を働かせる必要がありました。
【事例】
E保育所の3歳児クラスの保育室には、子どもたちが自由に遊ぶことができる空き箱や使い終わった素材を集めて入れたカゴが置いてあります。子どもたちはそれらの空き箱等を使って遊んでいます。保育士は、その様子を子どもたちのそばで見守っています。
具体的には指定の物品である空き箱や使い終わった素材を使いつつ、「子どもたちはそれらの空き箱等を使って遊んでいます」と述べられていますから、具体的な遊びをそれぞれの受験生が自分で考え、それを絵に起こす必要があった、ということです。
保育士の現場経験がない人はもしかすると、想像するのが難しいと感じた人もいたかもしれません。
その1年前の試験、令和5年前期の試験では指定がギチギチでした。
【事例】
S保育所の4歳児クラスの子どもたちは、雨の日の園庭で傘をさしたり、長靴やレインウェアを身に付けたりして遊んでいます。保育士は、水たまりで遊ぶ子どもや、空き容器に雨水を溜めたり、雨音を聴いたりする子どもをそばで見守りながら遊びに加わっています。
傘・長靴・レインウェアといった物品の指定に、子ども全員の遊び方の具体的な指定。これはこれで難しいですね。指定された遊び方を即座にイメージし、そのポーズを描けるだけの技術が必要です。この問題の時は保育の現場にふさわしい遊びを考える必要はなかったですが、どのようなポーズをとっていれば指定された遊びに見えるかを考えなくてはならなかったために、受験生にとってはかなり難しく感じた方が多かったように思います。思いついていても描けない、という点、指定をすべてこなさなければならないというプレッシャーがあったようです。
(*私は保育の現場が思いつかないことが多いので、その点が楽だと思いましたが、受験生はそうではなかったようです)
令和5年の後期からは少し自由度があがりました。
【事例】
N保育所の2歳児クラスの子どもたちが、保育室の床の上に広げられた模造紙に、クレヨンで自由に線を描いたり色を塗ったりしています。保育士は、そばで子どもたちのつぶやきを聴きながら見守っています。
情景の指定はありつつも、子どもの遊び方の指定は2種類で、自由に線を描いたり色を塗ったり、と比較的受験生が描きやすい指定だったように思います。強いて言うと、床の上の模造紙に対してクレヨン遊びをしているため、しゃがんでいるか、床に寝転がっているかを描かなければならない点が、そのポーズが描けない人には難しかったかもしれません。
つまり令和5年後期と令和6年前期の2回続けて自由度が比較的ある試験傾向が続いていると解釈できます。この試験傾向は引き継がれるのではないかなと私は予想しています。
あまり令和5年前期のように、細かな指定はないと信じたいですね。
●テーマ(お題)について
テーマについては毎回異なったテーマが選ばれています。
季節性のあるテーマについては後期は秋から3月上旬くらいまでの行事や遊びが選ばれると考えています。
季節性がないテーマについては、何が選ばれてもおかしくないですが、どの保育の現場でもよく行われている遊び、テーマが選択されると思います。
ご年配の方には聞いたことがないようなカタカナの遊びも指定されることがあります。
フィンガーペイントの回ではわからなかったと言う方もいらっしゃいました。ただ、英単語がわかりやすいため、なんとなく想像がついたと思います。
たとえカタカナの遊びが出題されて、聞いたことがなかったとしても、前後の文章から、なんとなく情景がわかるな、という感じの問題にはしてくれると思いますよ。造形試験で受験生に問われているのは、筆記試験の知識ではないからです。その点はそこまで心配しなくても良いです。
対策について
では、どんな対策をしていったらいいでしょうか?ここからは具体的な対策と練習内容を考えていきます。
1)保育の現場のイメージを高める
まず、ある程度、保育の現場のイメージを高めておきましょう。
まず保育園の行事、先ほども言いましたが今回は後期試験ですので、秋から冬、3月くらいにかけての行事を押さえておきましょう。後期試験において、春夏のテーマはこれまで出題されたことはありません。
保育園、年間行事、など、インターネットで検索をかけると、だいたいの行事がわかると思います。イメージができないものだけ、調べるといいでしょう。
また行事以外の平常時についても、保育園でどんな遊びをしているのか、現場の写真でイメージを高めておきましょう。これもやはりインターネットで調べることができます。便利な世の中ですね。積極的にインターネットを使っていきましょう。
なお、調べるの、もう面倒くさい!と言う方は最後に述べるテキスト、「予想問題イラスト集」のご購入もご検討ください。お題集(例題集)という形でリストを作っています。
また保育実習理論で学んだ、絵の具を用いた技法も一通り復習しておきましょう。
色鉛筆で表現しづらそうなものは出ないと思いますがスタンピング、デカルコマニー、コラージュなどは表現しやすく、一度はやった経験がある人も多いと思います。シャボン液に絵の具を混ぜて遊ぶという手法もあります。これも出題される可能性は十分にあります。
何を意味するのか、ここでは説明しませんが一通り復習はしておいてください。大体こんなところだったかと…。詳しくは、みなさまお手持ちの筆記試験用のテキストでご確認ください!
・フロッタージュ
・デカルコマニー
・バブルアート(シャボン遊び)
・バチック
・コラージュ
・フィンガーペインティング
・スタンピング
・スパッタリング
・たらし絵
・スクラッチ
・マーブリング
2)確実に書けるポーズを作っておこう
正面と横向きの立っている人物と座っている人物は、最低でも描けるようになっておかないと相当に苦戦が予想されます。
また歩いている、走っている、物を投げる、など基本的な動きについても、「運動会」などと指定された場合に必要になってきますのでマスターする必要があります。投げるは割と使う気がしますね…。
壊滅的に絵が描けないと言う方は、とにかく基本的なポーズのみで良いので、まずはそれを繰り返し練習してマスターしておいてください。いろんなポーズが描けるようになるのはそのあとで良いです。
また、初心者の方は、まずは基本的な形から綺麗に描く練習をするといいケースが多いです。絵が苦手という方は、ここでつまづいているケースが多いです。
直線やまる、四角とか、こういった形を綺麗に描けないと、これは合否に関わるということを覚えておいてください。繰り返し形を綺麗に描く練習をしましょう。
*壊滅的に絵が描けない方は、造形ドリルが私のおすすめ商品です。ぜひご検討ください。
3)何をして遊んでいるかがきちんとわかるように描く練習をする
合否にかかわる重要なところです。何をしているのかがわからないと条件が満たせません。
パッと見て、あ、ほにゃららをしているんだなとわかってもらえる絵を描く必要があるのです。
例えばですが、令和6年前期でいくと、空き箱や使い終わった素材を使って、遊んでいる様子を描く必要がありました。
この指定を満たすためには、まず箱やその素材などが、パッと見てわかるように描く必要があります。
また、その箱や素材をどのように使っているのか、具体的な情景をイメージできなくてはいけません。箱や素材ををただ持っているだけでは、条件を満たすためには十分ではありません。例えば、箱を積み木のように積み重ねている/腕に通したり頭にかぶったりしている、というような具体的情景をイメージする必要があります。

いつも描き慣れたポーズをベースに使って、どう描いたら、採点する人に伝わるかをよく考えて、その上で物と体の位置を考えて描きましょう。
例えば、箱を積み木のように積み重ねている様子を描くには、まず箱が子どもの手前に複数個積み重なっている様子を描く必要がありそうです。また、積み重ねて遊んでいるのですから、子どもはその一番上の箱を置こうとしているところ、または置いた状態のいずれかを描くと伝わりやすいでしょう。
…ということは、手は箱を持っていて、視線は箱に向いている/あるいは積み重なった箱の前に立って、保育士に視線を合わせて伝えている、などの様子をかけなくてはいけない、ということになります。

このように、しっかり具体的に遊んでいる様子を設定してあげる必要があります。難しく描きましたが、パッと見て、何をして遊んでいるか第三者にわかること、これが大事ということです。合格するためには、そのための練習が必要になります。
なお、視線を合わせるのは初心者でもできる方が多いですので、そこまで難しいことではありません。あまり心配しないでも大丈夫ですよ。
(*注 予想問題イラスト集にて「問題文から具体的イメージを描き起こす」という章で説明しています。
テキスト販売のお知らせ
全部で四冊販売しております。そのうち、人体を描く練習ができるテキストは三冊です。
壊滅的に描けない人は、「造形ドリル」からスタートしてみてください。ドリル形式で繰り返し練習でマスターできます。また構図の作り方も掲載。苦手分野ごとに繰り返し練習することで上達が期待できます。不合格の方を添削指導する中で生まれたテキスト。きちんとこれで皆さん上達されています。絵に苦手意識のある方に特におすすめです。
見ながら描けるけれど、初心者です、と言う方は、「顔と人体の描き方のキホン」をお勧めします。基本的な図形が描ける方なら誰でも、正面と横向きの人体が描けるようになる、というコンセプトです。
見ながらなら描けて、ある程度人体を描くのは大丈夫と言う方は、バリエーションを増やすために「ポーズ集」がいいと思います。基本のポーズに加えて、斜め向きの人物の参考ポーズを複数書いてあります。さらに上を目指したい方はこちらがお勧めです。保育に使える小物集も付録としておつけしてあります。
最後の一冊、予想問題イラスト集についてですが、実際の試験と同様のイラストが見たい、と言う方向けです。
19センチ四方、色鉛筆での実寸作品を見たいと言う方は、予想問題イラスト集をご購入ください。予想問題20問とその色鉛筆による解答例、ほかに類題や別構図などもあり、イラストが多くて助かったというお声を多数いただいております。
また巻末に、イラストはありませんが、簡易なお題集(=テーマ・例題集)も載せています。保育の現場の経験のない方も、さまざまな保育の現場で使われる遊びをイメージできるようにしています。ぜひご検討ください。
なお、テキストの詳細と活用方法についてはこちらの記事に詳しく述べています。ご購入前に一読くださると幸いです。
実技試験本番まで頑張っていきましょう!最後までお読みくださりありがとうございました。
