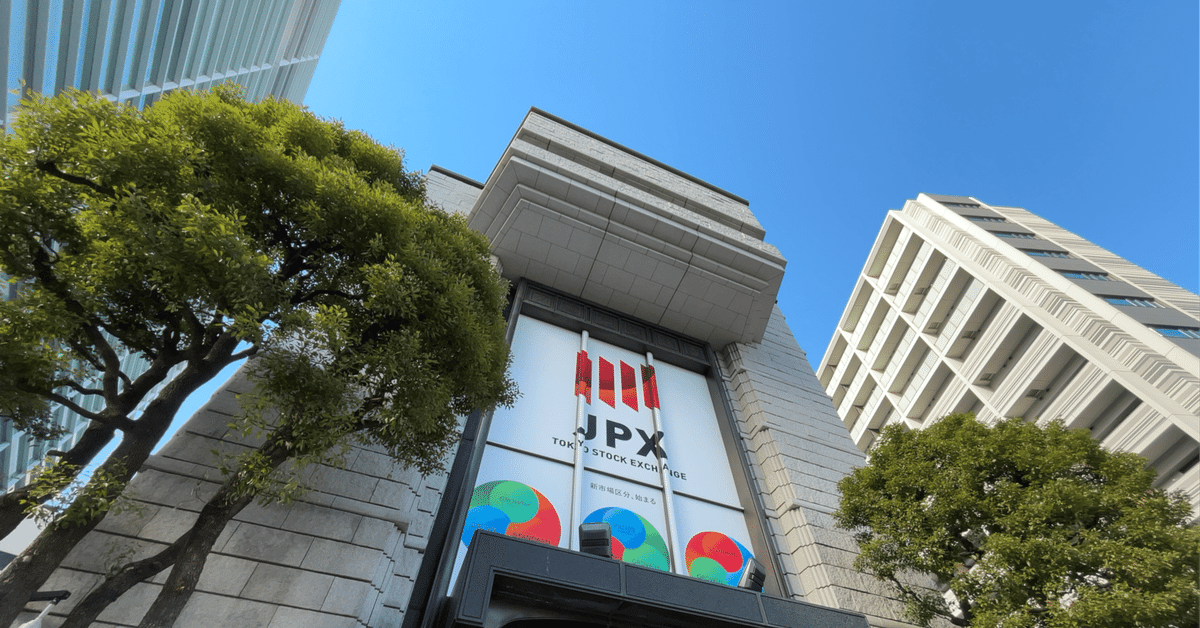
長期保有銘柄選びにPERもPBRもROEも不要?
銘柄選定における主要3指数はPER、PBR、ROE。皆さんご存知でしょう。
あくまで私の意見ですが、長期投資をする場合必ずしもこれらは必要ないと考えています。
「んなわけねぇだろ!お前はアホか?」
と鋭いツッコミを入れたくなると思いますが、お付き合いください。
指標へのダメ出し
まずはこれらの指標のダメなところを説明します。
PER:株価収益率
株価を一株あたり当期純利益で割ることで算出されます。
問題は、この指標の算出に「株価」を使っていることです。株価は年間を通して動きます。実にダイナミックに。
いつの時点の株価を使うかで結果が変わります。そして短期的に株価を動かすのは需給です。
銘柄の財務状況を探る指標としては、私は信用していないです。
PBR:株価純資産倍率
株価を一株あたり純資産で割ることで算出されます。
PERと同じく指標を算出するのに株価を使うのがあまり信用していないポイントです。
PBRが1を割り込んでいる銘柄は株価が過小評価されているので「買い」だと言われることが多いです。
例えば株価が100円で、1株あたり純資産が200円の会社の株式を1株買ったらどうでしょうか?
買い値の後ろに潜在的にその倍の価値が控えているように見えるわけです。
さて私がPBRを使わない理由は2つあります。PERと同じく株価いかんによって結果が変わることが一つ。もう一つはセクターによってPBRが1を割るのが当然の場合があるからです。
詳しくは書きませんが、例えば銀行業はその性質上、PBRが低く出ます。
ROE:自己資本利益率
ROEは当期純利益を純資産で割ることで算出します。
実は私も参考として使うことがあります。(不要と主張しているのに)
この指標に関しては株価が介在しないためPERやPBRと比べるとまだマシというのが私の考えです。
しかしこの指標にも難点はあります。使う数字に純利益が含まれているからです。
純利益は販売促進費から税金までありとあらゆる要素を考慮した上での最終利益です。これを使うことは一見合理的に見えます。
しかし、裏を返せばその企業の本業で稼いだお金でないものを混ぜ込むことができるということです。
鉱業で有名なとある会社は本業では稼いでおらず、国外の某カンガルーの国にある炭鉱会社からの配当金が主たる収入源だったりします。
いわばゾンビみたいな企業ですね。そういう会社でもROEの数字としては悪くなかったりするものです。
何を見てる?①ー営業キャッシュフローマージンー
営業キャッシュフローマージンです。
「そんな指標聞いたことねえぞ!」という方はぜひお付き合いください。
営業キャッシュフローマージンとは
まず営業キャッシュフローとは、一言で説明するならば、本業で立てた売り上げのうち最終的に会社の手元に残った現金です。
営業キャッシュフローを売上高で割った数字のパーセンテージのことを営業キャッシュフローマージンと呼びます。
売上高のどれくらいの割合を現金収入に結び付けられているかを把握することができる指標です。
私はこの営業キャッシュフローマージンの過去10年間の数字を弾き出して安定した数字かどうかを確認しています。
手計算の労を惜しむべきではない
営業キャッシュフローマージンはしばしば自分で手計算する必要があります。でも元になる数字は決算情報や四季報を見れば得られるものになります。
自分のお金を使って買い、長期間にわたって運用するのであれば、最初は慎重に、きちんと調べてから買うべきだと思いませんか?
営業キャッシュフローマージンの適正値
私の投資している米国株では15%から35%程度が適正と言われます。日本株で15%を超える銘柄は少ないのではないかと思われます。
何を見てる②EPS:一株あたり純利益
先ほど純利益にダメ出しをしましたが、それが含まれるEPSは確認しています。
EPSを見る理由
ごくごく簡単に数字を入手できるからです。
また株式に関連する指標でありながら株価と直接は連動しないので、客観性が担保されていると考えています。
EPSに関しては過去10年分を確認して、継続的に伸ばすことができているかを確認しています。
まとめ
かぶもなかが銘柄選定するときに見ている指標は
営業キャッシュフローマージン
EPS(1株あたり純利益)
上記の過去10年分
です。とにかくあなた自身のお金です。運用は慎重に、自己責任です。
