
しらももは花も果実も反り返る 芥川龍之介の俳句をどう読むか⑰

白桃や莟うるめる枝の反り
この句には
白桃は沾(ウル)み緋桃は煙りけり
と主題が転じたものがある。ところでこの句の季節はいつか。それすら曖昧な人が多いようだ。季節が解らないということは殆どその句を読んでいないことになる。
うる・む [2] 【潤む】 (動マ五[四])
(1)うるおいを帯びる。ぬれる。「目が―・む」
(2)輪郭などがぼやける。「明かりが―・んで見える」
(3)涙声になる。「―・む声を震はして/色懺悔(紅葉)」
(4)強く打ったりつねられたりして青あざになる。「疵ガ―・ム/ヘボン」[和名抄]
(5)果実が熟して,色が変わる。[日葡]
辞書を引き、引き比べ、辞書を疑おう。
うる・む【潤む】 〔自五〕
①(打たれ、またはつねられて)皮膚が青黒くなる。為忠百首「形見にと―・むばかりもつみしかな」
②色や形があざやかでなくなる。
③しめりけを帯びる。「目が―・む」 ④涙声になる。
うる・む【潤む】 [動マ五(四)]
(1)湿りけを帯びる。また、水分を帯びて、くもったようになる。物の輪郭がぼやける。「霧に―・む町の灯」
(2)目に涙がにじむ。「目が―・む」
(3)涙で声がはっきりしなくなる。涙声になる。「声が―・む」
(4)打たれたりつねられたりして、皮膚が青黒くなる。「傷ガ―・ム」〈和英語林集成〉
(5)色つやが薄れる。鮮やかでなくなる。「灰捨てて白梅―・む垣根かな/凡兆」〈猿蓑〉
うる・む【潤む】 (動五)
(1)うるおいを帯びる。「目が―・む」
(2)輪郭などがぼやける。「明かりが―・んでいる」
(3)泣き声になる。「声が―・む」
うる・む【潤む】
〔自マ五(四)〕
1 打たれたり、つねられたりした跡が、青黒く色づく。あざになる。また、寒さで皮膚が紫色になる。*塵袋‐六「さむくてはだへのうるめるなり」
2 果実が熟して、緑色から赤色に変わる(日葡辞書)。
3 色つやが薄れる。あざやかでなくなる。*俳・猿蓑‐四「灰捨(すて)て白梅うるむ垣ねかな」
4 水分を含んでしめりけを帯びる。
しめりけを帯びて曇る。霧やもやなどでかすむ。「小雨に潤む街灯」目やそのまわりが涙でぬれる。転じて、涙がにじむ。*浮・好色万金丹‐三「目もとに泪(なみだ)一雫(ひとしづく)うるめば」泣いて声がはっきりしなくなる。泣き声になる。*人情・春色恵の花‐二「こゑうるみてなみだぐむ」
うる・む【潤む】
《自動詞五段活用》活用表
水分をふくむ。しめりけをおびる。しめりけをおびたようにみえる。用例(滝井孝作)
〔目が〕涙でぬれる。用例(野上弥生子)
〔もや・きり・きり雨などのために〕かすんでみえる。ぼやけてみえる。用例(石原慎太郎)「霧雨に潤む灯」
〔声・音などが、いまにも泣き出しそうに〕ふるえてさえなくなる。用例(山本有三)《文語形》《四段活用》
うる・む【潤む】
〘自五〙
❶ 湿りけを帯びて物の輪郭がぼやけて見える。かすんで見える。
「街の灯が夜霧に━」
「山並みが霞かすみに━」
❷ 涙がにじんで、目がぬれたようになる。
「目が━・んで視界がぼやける」
「心なしか目が━・んでいるようだった」
❸ 涙で声がはっきりしなくなる。涙声になる。
「声が━・んで、今にも泣き出しそうだ」
関連語
大分類‖水に関わる行為‖みずにかかわるこうい
中分類‖濡れる‖ぬれる
うるむ【潤む】
(自五)
水けを帯びて、曇ったようになる。
「目が―〔=涙がにじむ〕/声が―〔=涙声になる〕/星が―〔=ぼんやりかすんで見える〕」
[名]潤み
[他動]潤ませる(下一)
「目を―」
白桃や莟うるめる枝の反り・芥川龍之介
— 俳句新派 (@shonan2591) October 26, 2018
この白桃は花である
白桃や人と人間は違う
白桃を星野高士は桃の実だとしているが
句からは、花とも解釈でき、意味が違ってくる。
「人と人間」の解釈は説明なしでは意図は不可解。
(シャガール擬製の鶏と桃太郎桃(天津桃)の挿絵はスルーする) pic.twitter.com/WVpV5L9iRe
※ 星野高士さんは高浜虚子のひ孫。
莟は「つぼみ」「はなしべ」なので花が咲きかけと思いきや、枝が反り、「うるめる」なので果実が熟して,色が変わるという意味に解釈できる。

蛇笏も花のつぼみの色の変化と見ている。しかし色の変化では枝は反らない。この非合理性を正当化するために室生犀星は「枝のなり」と姿に変えてしまう。
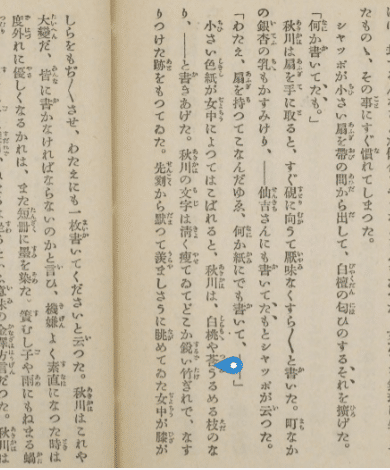
そう、枝の反りで花のつぼみでは大袈裟なのだ。果実の熟したのを室生犀星は自身のなかで合理化してしまった。それだけ「反り」は引っかかる言葉なのであろう。
私はこう考える。
莟と書いた芥川は枝を反らせることで花か実かと惑わせる意図はなかろう。
座敷には妻の古雛を飾りぬ。書斎には唯高麗の壺に手づから剪りきりたるひと枝をさしつつ。
白桃や莟うるめる枝の反り
白桃の花が咲くのは春、実るのは夏である。白桃は七月ごろから出荷される。この句にこうして「古雛」「剪りきりたるひと枝」と添えられていることから、莟は花の莟であり、果実ではないことが解る。しかし莟は果実のように膨らみ、枝はことさら自慢でもするかのように反らせていたのであろう。
この枝の反りという誇張法がこの句の味わいなのではないか。いや、これは活花の「反り」だ。

こうなるともう何なのか解らない。
室生犀星はいい加減にした方がいい。

白桃は「しらもも」と訓じよう。
【余談】
白桃や日永うして西王母 子規
1899年(明治32年)、磐梨郡物理村(現・岡山市東区瀬戸町)の大久保重五郎は、上海桃の実から「白水桃(白桃)」を発見した。大久保は、1901年(明治34年)に新品種「白桃」を生み出した。白桃は強い甘みとねっとりした食感を持ち、最高の水蜜桃として栽培が広まった。白桃の発見以来、新品種の開発が続き、1932年には西岡仲一によって清水白桃が開発された。この清水白桃は高級白桃の代名詞として知られる
この子規の白桃の句が明治三十二年の作だとすると、どうにも辻褄が合わない。
時空が歪んでいる。
ついでに言えば、芥川が見たのが白桃の花の莟であったかどうかも甚だ怪しい。
どうも白桃の莟はピンク色で、言われなければ白桃とは解らない。
BOTCHAN de Natsume Soseki en la Editorial Impedimenta#NatsumeSoseki | #EditorialImpedimenta | #LibreriaNadasdy | #Literatura | #Libros | #LibroNuevo | #VentaDeLibros | #LibrosCDMX | #LibrosMexico | #Botchan | #LiteraturaJaponesa | #Novela | #Japon pic.twitter.com/Tgo3veRoCb
— Alberto Nadásdy (@alberto_nadasdy) October 21, 2023
坊ちゃんは五分刈り。
