
【タイ・facebook運用】40,000フォロワー獲得までにやったこと
今回の記事はタイでのfacebookの運用などについて細かく記載していきます。今後タイローカル向けにfacebookページなどを展開のご予定の方はぜひ参考にしてみてください。
タイでfacebookページ運用を始めた理由
当時、タイでオウンドメディアを運営しており、順調にSEOが伸びてきたタイミングで、自分の中で「タイのSEOマーケティグ」について理解できてきた一方、「SEOだけでは物足りない」「やはり一流のタイメディアはfacebookページも力を入れている」ということで、facebookページも研究し始めました。
タイではfacebookページを運用していない企業の方が珍しく、一応自分もfacebookページは開設していたものの、全く数字が伸びていない状態でした。
またタイでのfacebookのポテンシャルは大きく、刺さるコンテンツならそこまでフォロワーが多くなくても「シェア数」が30-50、多い時では100を超えてきます。それにつれてリーチ数も増えてきますので、多くの方にコンテンツを届ける上でfacebook運用は欠かせません。
ただfacebookを運用するといっても、コンテンツの作り方が一般的なウェブサイトのコンテンツと違うため、最初は数字を伸ばすのに苦労しました。
一方で、あらゆるトピックを配信したり、様々な方法を試していくうちに、徐々に傾向が掴めてきました。
そこからfacebookフォロワーが300~400だったのに対して、6ヶ月ほどで5000フォロワーにまで拡大。これでもフォロワーは少ない方ですが、エンゲージメント(どれだけ投稿に対してアクションがあったか)では、フォロワーが倍多い競合ページを超えるようになりました。
正直、フォローワーなどは広告をかければ獲得できます。しかし、よく見かけるfacebookページのフォロワー数は数万、数十万といるのに、いいねやシェアが全くついていないページもよくあります。
本当に有益なコンテンツを配信していたら、エンゲージメントが高いはず。なので、facebookに置ける重要なKPIをフォロワーではなく、エンゲージメントに置いて進めていきました。
タイの方に「普段、どんなビジネス向けのメディアを読んでいるの?」とヒアリングをし、どのメディアが成功しているのかを観察し始めました。
タイにはたくさんのクリエイティブなメディアがありますが、タイでよく読まれているビジネス向けのメディアをいくつか紹介します。
【あわせて読みたい】
タイで人気のビジネスメディアのfacebookページ紹介
Brand Inside

Brand Insideはビジネス全般のニュースなどを取り扱っていて、タイの多くのビジネスマンがフォローしています。
実際に、僕と一緒に働くタイ人のスタッフや知り合いのタイ人経営者の方もこちらのページをフォローしていたので、ベンチマークする上では良い対象になるのではないかと思います。

The standard

こちらもビジネスマン向けを対象としていますが、メディアだけでなく、オンラインでビジネス界のインフルエンサーの方と対談したり、動画コンテンツや、インフォグラフィックのコンテンツにもフォーカスしています。
このThe Standardはfacebookページを運営する際に結構参考にしました。

a day
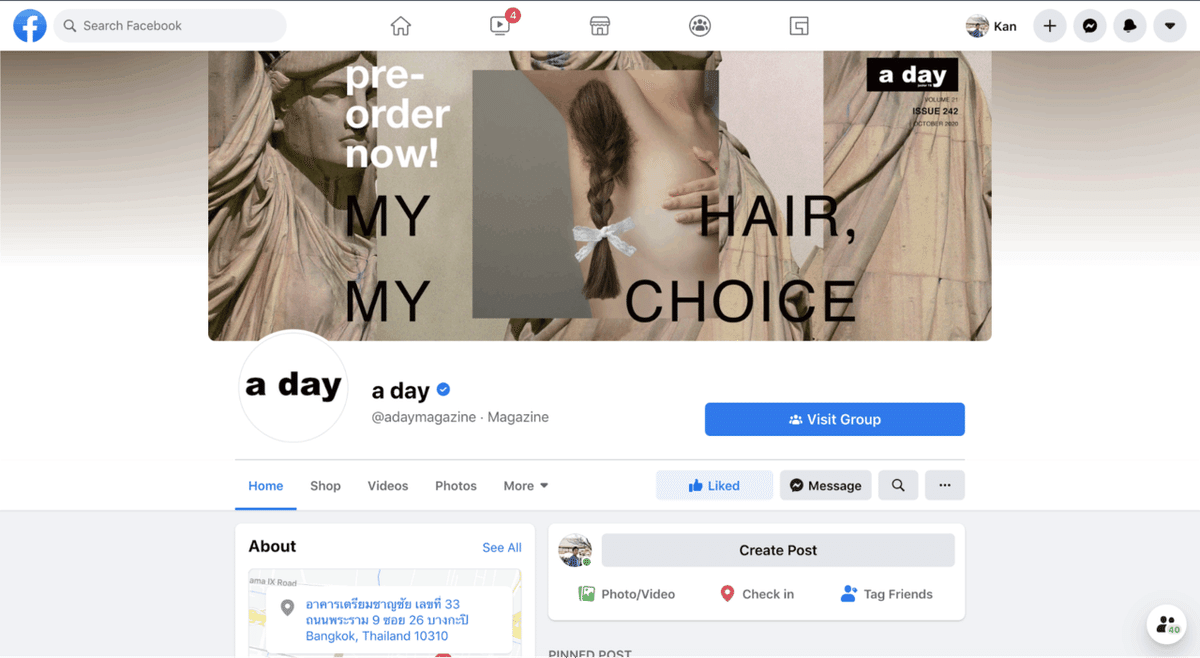
a dayはガチガチのビジネスマガジンというよりも、あらゆる社会現象をクリエティブに伝えるメディア、といった印象があります。
なので、クリエイティブなどをとっても他のメディアよりも違った雰囲気があり、インタビューコンテンツのサムネイルを作成したりする際に参考にしました。

タイのfacebookは「ビジュアル」が重要である。
多くのfacebookページを見ていると、やはり見た目を重視したクリエティブが多いことがわかってきます。
「一目でどんなコンテンツなのかがわかるか」「ついスクロールを止めたくなるキャッチーな見出しを使っているか。」に意識を尖らせて、コンテンツを作っていく必要がありました。
一方、タイ人ユーザーの傾向として、良いコンテンツに対してはいいね、シェア、コメントを積極的にする傾向にあり、コンテンツがうまくオーディエンスに刺さると、瞬く間にシェアされ、多くの方にリーチできます。
しかし、全てのコンテンツが刺さるという訳ではないので、他のメディアも注意深く研究し、また投稿のコメント欄の内容も翻訳してまで読むくらいに細かくチェックしていく必要があります。
それを習慣化していると、徐々にタイの方が何を面白いと感じて読んでいるのか、シェアしているのかが徐々に見えてきます。
タイのfacebook運用でやってはいけないこと
タイでのfacebook運用でやってはいけないことについても紹介します。
日系企業だけではなく、海外の企業でもよく見られるのが、一つのfaceboookアカウントに、タイ語、日本語、英語など複数の言語が混ぜた状態で運用してしまうことです。
運用する側としては、一つのアカウントで世界中の顧客にリーチできると考えがちですが、言語をバラバラに運用していると、誰に向けて発信しているのかが定まらず、フォロワーがつきにくい傾向があります。
私もfacebook運用をする際にいろんなアカウントを研究しましたが、複数の言語で運用しているアカウントで大きく伸びているところはありません。
また、「グローバルな会社という見せ方をしたい」といった運用側の理由で英語だけの発信するやり方もタイでは適しているとは言えません。
タイ人の母国語はタイ語なので、タイ人に向けて発信する場合はタイ語で運用しましょう。
タイのfacebookページ運用で重視するべきこと
これまで他のメディアを研究することが大事といってきましたが、とはいってもfacebookページ立ち上げた時には、どのコンテンツが刺さるかわかりません。そのため、
-google analyticsを分析して、メディア内でよく見られているコンテンツを投稿してみる。
-そのあとにインフォグラフィックなどにチャレンジして、どのグラフィックが成功するかについても分析し、テンプレート化する。
などの対策も取っていました。それ以外の詳細な部分にも気を配ることで立派なfacebookへと成長します。
「フォントまでこだわってる?」神は細部に宿る
facebookのコンテンツに限らず、タイで作るサイトやランディングページはフォントにまでこだわっています。
タイ語もフォントが変われば、見た目も大きく変わってきます。タイで立ち上げ当初、「メディアが全然美しくない」と言われました。
メディアが美しくないと言われたのは初めてですが、「どのポイントが美しくないのか」と聞くと、「グラフィックもそうだけど、フォントが、、、」という返答があってからは、他のタイのサービスサイトやコンテンツの見出しなどで使っているフォントを注意深く見るようになりました。
よく見ると、「確かに違うし、このフォント、すごくクリエティブでいい...」と、タイのデザインの常識が見えるようになってきました。そこからフォントをダウンロードして、クリエイティブを作成する際には、フォントなども注意するようになりました。

ちなみにタイの見出しなどでよく使われている、おすすめフォントは以下です。
-kanit
https://fonts.google.com/specimen/Kanit?query=kanit
-Mitr
https://fonts.google.com/specimen/Mitr?query=mitr
facebook上で重要視した指標
facebookで重要視した指標は、先ほども書きましたが第一にエンゲージメント、次にリーチです。
facebook上にはあらゆる指標がありますが、よりシンプルな指標をおいたほうが良いと思ったので、まずはどのようにしてエンゲージメントをあげるか、リーチを伸ばすかについて考えました。
エンゲージメントとは、いいねやシェア、写真・リンクをクリックするなどがあります。ファンに毎回アクションを取ってもらえれば、facebookのアルゴリズム上、そのページがユーザーのフィードに優先的に表示されるようになります。
またそれだけではなく、どれだけ長い時間そのポストを読んでもらえるか、つまり「ユーザーにとって関心が高いコンテンツか」も重視します。
そのためただグラフィックを作成するだけでなく、投稿内のテキストの内容などにも神経を尖らせます。
気づけば一定のページがいつも表示されることはあると思いますが、facebookは各ユーザーの嗜好にあわせて、最適な情報を表示するようにしています。
そのため、多くのユーザーにいつも我々のページを表示させるためには、まずエンゲージメントを高めていかなければいけませんでした。
そのため、投稿してはその翌朝にエンゲージメント数を確認し、低い要因や高い要因をなるべく言語化して、細かい分析を積み重ねて行きました。
同じタイプの投稿やグラフィックの種類によっても、内容が変われば大きくリーチやエンゲージメントが変わってきます。
分析する中で見えてきた特徴としては、
-課題解決型の情報よりも、今話題の情報、テクノロジーに関するのエンゲージメントが高い
→タイの方によると、最先端の話などが好きらしい..
-アルバムスタイル(画像が3~4枚が掲載されているコンテンツ)はエンゲージメントを高めやすい。
→タイでは視覚的な情報によって判断されることが多い印象。なのでタイの他の広告の訴求もグラフィックを多量に用いたものが多いし、またCMなどで演技される俳優さんもオーバーリアクションの方が多い,,,。じっくり読んでわかるよりも、パッとみてすぐにわかるかが重要ではないかと..
-すぐに明日使えるtipsまでに落とし込めているか。
→複雑な概念やトピックをそのままシェアするよりも、上記のようにインフォグラフィックなどを用いて視覚的に伝えていく方が効果的です。
タイのfacebookページ運用は「レッドオーシャン」
タイで一番使われているソーシャルメディアがfacebookと言えども、タイでのfacebook運用は簡単ではありません。
他にもたくさんのクリエティブなメディアやフォロワーからのエンゲージメントが高いメディアが乱立しているためです。またfacebook上でオーディエンスの目にとめてもらうには2-3秒以内で、どれだけ魅力的なコンテンツやトピックを提供し、また、どれだけわかりやすく伝えるかが大事です。
そのため、タイのコンテンツチームには常に以下の内容を口すっぱく伝えています。
読者は基本的に「読まない」「信じない」「動かない」
読者は基本的に読まないです。これはタイに限らず、全世界のオーディエンスにあてはまると思います。
よっぽどブランド力の高いメディアでない限り、読まないオーディエンスに対して、どのように訴求するかが重要になります。
また、メディアについて信じてもらうためには権威性が重要になります。自分たちが発信するだけでなく、各専門分野の外部パートナーを見つけて、コンテンツを発信してもらうなどもしていくべきでしょう。
読者は基本的に動かないので、「URLを貼っておけばこのページにいって読んでくれるだろう」という甘い考えは捨てましょう。
例えば「facebookからこのページに移動してもらう」など顧客にアクションを起こしてほしい場合は、それなりのメリットを訴求するべきです。
そのページに行くことで何が得られるのか。どんなメリットがあるのか。あなたの業務にどんな良い影響があるのかについても深く考え、記述していきましょう。
「自分視点」「無目的」「自分が好きだから」は避ける
常に大量の情報に晒されている顧客の目に、どうやって自分たちのコンテンツを見てもらうかについては、まずはコンテンツ作成する際の心構えが重要になります。
例えば
「このコンテンツ、なんで作ったの?」
「誰の、どんな課題を解決するの?」
「どういう情報を提供すれば、その課題は解決できるの?」
と一つ一つ明確にします。
まず「なんで作ったのか」について「自分が作りたいから」という返答がよくタイスタッフからきますが、「じゃあ、このコンテンツでどういう課題を解決したいか?」と聞くと、そこで一旦回答がとまります。
「多分こういう課題があって、こういう情報を提供すれば...etc」とまた答えをくれるので、その返答に応じて「じゃあ、この冒頭部分の訴求ポイントがそのターゲットに対して弱くないか」といった話をします。
そういう議論を繰り返しながら、一つ一つ小さいなポイントを見直すと、新人メンバーでもその日投稿した「エンゲージメント数が昨日の2倍」といったこともざらにあります。
要は、顧客の目線に立って考えているか、顧客のマインドを明確にイメージしようとしているか、facebookをスクロールしている姿、その時にいる場所、その人がスマホを見ながら取っている別の行動についても、しっかり考えてコンテンツ作っているか?と常にいっています。多分、彼らにとってストレスかもしれませんが、それくらいしないと、顧客は読んでくれません。
facebookが伸びればLINE登録者数も伸びる。
一度、ブランドのエンゲージメントを高めると、そこからチャンネル開設をした際にも、ユーザーが登録やフォローをしてくれやすくなります。例えば、facebookである程度エンゲージメントが獲得できるようになると、次にLINE for businessを展開した際にも、誘導しやすくなります。
例えば毎日facebookでコンテンツを投稿している場合、コンテンツの末尾に必ずLINE for business を登録するURLなどを貼っておくとそこからユーザー登録を増やすことができます。
毎日facebookのポストにLINE登録の導線を貼るということを徹底した結果、LINEアカウントの登録数は開始6ヶ月で900を超え、そこまでプッシュしていないにも関わらず、順調に伸びています。
これは今まで有益なコンテンツを提供し続け、オーディエンスとの信頼を構築していたという部分もあります。
またLINEユーザーの特徴として、メールマガジンよりも圧倒的に開封率やクリック率が高い傾向にあります。
人事を対象としたメールマガジンもタイで配信したことがありますし、インドネシア拠点のメルマガも数字を見たりはしていますが、開封率が10%~20%に対してLINEの開封率は50%以上、またメールマガジン内のURLなどのクリック率が3~5%に対して、LINEは10%以上を超えてきます。
メールマガジンに比べてそこまで大量の情報を送れないといった点もありますが、一度信頼を得たユーザーのエンゲージメントのあらゆる局面で効果を発揮します。
ローカルから信頼を得られるようなコンテンツ配信を。
信頼を得る上での指標にフォロワー数ではなく、エンゲージメントに置いた点は今ではよかったと思います。
おかげで、多くの人事からfacebookページ向けに質問が寄せられ、また人事系のサービスを展開している企業からはサービスのPRや取材してほしいとの依頼も入ってくるようになりました。
タイで徐々にHR系のメディアとして存在感を強め始め、HR系のプラットフォームを目指しつつある中で、これらの姿に近づけているのも、これまで書いてきた細かい部分の見直しや、ユーザーを第一に考えたコンテンツ作りが一番大きいかと思います。
国が違ってもコンテンツマーケティングの本質は同じである。
これまで読んできた方は「それって日本のマーケティングでも言えることでしょう」と思われたかもしれませんが、実はその通りで、国が変われど現地のビジネスパーソンも困っていることがあります。
その困りごとに対して、どのように解決策を提供するかを考えるだけです。
非常にシンプルですね。現地の方にヒアリングしたり、数字を見ながら事実だけを見つめることが海外では重要になります。
なぜなら「タイ人は文字を読まない」などといったこともよく日本人からよく聞くため、それが事実かどうかはやってみないとわかりません。
周りの声は一意見として参考にしながらも、マーケットに深く入り込んで、じっくりと現地の顧客と向き合っていく必要があります。
そのため、これから海外で何か始められる際は、文化や商習慣の違いなどを複雑に考えず、「彼らは何に付いて困ってるのか」をシンプルに突き詰めていくべきでしょう。
多くの方が日本から海外に挑戦し、日本のプレゼンスが高まっていくことを祈って、このnoteを書き終えたいとおもいます。
タイの事業に関する30分無料相談受付中
タイの事業でご相談がある場合はお気軽にご連絡ください。オンライン面談で30分ほど質問にお答えします。
タイのカルチャーについて
タイの商習慣について
タイ現地のマーケティングについて
など
私の経験からお話できることもありますが、業界業種によっては専門外のこともあります。その場合は周りのタイ人経営者や日本人経営者、その分野の専門家を紹介することも可能です。
以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
https://corestory.co.jp/contact
