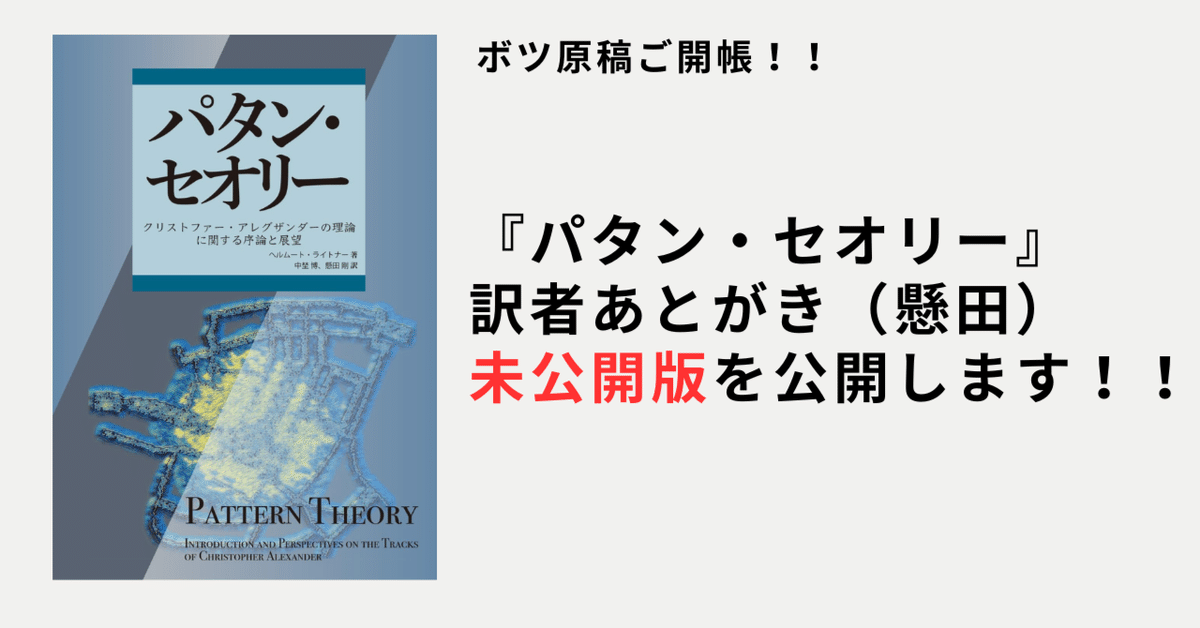
『パタン・セオリー』訳者あとがきの未公開版を公開します
なぜボツ原稿を公開するのか?
以降に本記事で述べるのは、『パタン・セオリー』の訳者あとがきを最初に書いた版です。
実際に書籍に掲載されているものは、本記事とは別バージョンになります。(『パタン・セオリー』に掲載しているのとほぼ同じ版を、Web版はiki-ikiにて公開しています。)
最初に書いた版は、長すぎるため一旦削除してリライトした経緯があるのですが、私のパタン・ランゲージ、パタン・セオリーを取り巻く問題意識を書いたため、せっかくなのでそちらも公開したいと考えました。
パタンセオリー翻訳の動機の裏側
もともと『パタン・セオリー』の翻訳企画の前には、『The Nature of Order』のVol.2(NOO2巻)の翻訳出版を実現したいという企画がありました。出版社からの翻訳出版が絶望的な状態なので、なんとかしてクラウドファンディングで資金を募り、自分で出版社を立ち上げるなどしても翻訳したい、という内容でした。しかし、いきなり大著であるNOO2巻に取り組むには一歩が大きすぎる、という判断で、もっと薄く翻訳しやすい『Pattern Theory』を先に翻訳しよう、という話に切り替えました。
結果的には、『パタン・セオリー』を翻訳出版できたことは、非常に良い体験となりました。クラウドファンディングによる応援を受け、出版社を介さずに自分たちで翻訳権の購入契約・翻訳・出版・販売プロセスを一通り体験することができたからです。この200ページ弱の薄い翻訳書ですが、この裏にはそこに至る想いやドラマが含まれています。
また、パタン・ランゲージに対しての想いは、アレグザンダーの直弟子である中埜博さんは当然として、2000年からパタン・ランゲージに目覚めた私自身も、それなりの想いがありました。その一端を「訳者あとがき(懸田)」に書いてボツにしたものをベースにリライトしました。よかったらお読みください。
訳者あとがき(懸田) 2024/07/18版
本書『パタン・セオリー』の原著である『Pattern Theory』をAmazon.co.jpで見つけたのは、コロナ禍に入った直後の2020年6月のことでした。すぐに著者にLinkedIn経由でメッセージを送ったのがもう4年も前になります。本書がクリストファー・アレグザンダー氏の『パタン・ランゲージ』を始めとする彼の建築を超えたシステム理論を、コンパクトにまとめていた点に非常に驚いたのを思い出します。
私は、1999年にソフトウェア技術者として本書にも紹介されている「デザインパターン」に出会い、アレグザンダーの『パタン・ランゲージ』にはじめて触れました。その後、オブジェクト指向開発、アジャイルソフトウェア開発の実践、ウィキシステムの利用を通じてパタン・セオリーに触れていきました。また2007年よりパーマカルチャーを学び実践するうえで、パタン・セオリーとパーマカルチャーの共通性にも気づき両者を結びつけようともしました。このあたりの経緯は原著者ライトナー氏とほとんど同じであり、運命を感じています。
ソフトウェア開発の文脈では、パタン・ランゲージというツールは、変化が激しい新しい技術分野であるソフトウェア開発の現場で見つかった様々な知見を、形式化して共有していくという目的に非常にマッチしました。1994年には「Pattern Languages of Programs」(PLoP)と銘打ったカンファレンスがアメリカで開催され、ソフトウェア開発に携わる人々が、現場の知見をパタンという形でまとめ、持ち寄り、相互交流しながら質を高めていくというコミュニティがスタートしたのです。日本国内でも1999年にJPLoPというパタンコミュニティが立ち上がりました。ソフトウェア開発という分野で働く私にとって、パタンとは「知見をまとめ共有する方法」であり、パタンを使うことは「先人の知恵が凝縮された言葉」を扱うということでした。私自身、実際の開発でデザインパターンや、JPLoPで公開されたパタンを現場で使って助けてもらい、その効果を実感していました。
一方で、パタンには問題点もあることに気づき始めました。それは「とりあえずデザインパターンを使う」「デザインパターンをたくさん使えばいい設計」という風潮が生まれていたことでした。現場の要求や問題とは関係なくとりあえずパタンを使うとどうなるか。注意しなければ、最初から複雑で必要とされていない機能まで考慮した設計になってしまいます。またその設計の元となるパタンの設計意図・扱う文脈を、パタンの利用者が理解せずに使うことで、「何のために」という設計意図が見えず後からメンテナンスが困難な設計になり得ます。つまり「パタンとは、利用者が問題に直面してから扱わないと、その意図も状況への必要性もなく適応しない」ということです。
もう一つ気になる点は、アレグザンダーがパタン・ランゲージを定式化することで実現したかった「生命の質(名付け得ぬ質)」についてです。彼は、専門家が握りしめていたデザイン行為を、受益者である利用者に向けて解放し、利用者が己の要求に対するデザインを可能にして、専門家がデザイン行為を支援することを通じて、生命の質を生み出そうとしました。しかしソフトウェア開発の現場での現実は、パタン・ランゲージを作って使うのは専門家ばかりで、利用者(当事者)のエンパワーメントはごっそりと抜けていると感じていました。(元々のソフトウェア開発へのパタン・ランゲージへの応用は、利用者が自らデザインするためのパタンの考案からはじまった。参考→https://kdmsnr.com/translations/using-pattern-languages-for-oop/)
「専門家が、専門家のために作り、専門家が使う」パタンでは、本来アレグザンダーが求めていたものからズレていることに気づいたのです。専門家として自分たちの知見をまとめ共有することの価値はよくわかります。しかし、それではアレグザンダーが本来実現したかった「生命の質」の生成には到達しないのではないか、と。(このあたりの経緯は以下に詳しく書いてあります)
この二つの問題をまとめると、ソフトウェア開発におけるパタンムーブメントは「パタン・ランゲージを作る」ことばかりに着目していて「パタン・ランゲージの使い方」という観点・理解がごっそりと抜け落ちていると感じていたのです。これらの問題は、ソフトウェア開発の文脈で言えば、アジャイル開発のプロセス、顧客や利用者を巻き込むチームによってある程度対応はできていましたが、十分ではないと感じていました。なにより「生命の質」と「ビジネス的な成功」は等価なのか?という根源的な疑問もありました。
2009年から共訳者の中埜博さんに出会いパタン・ランゲージやネイチャーオブオーダーを学ぶ機会を頂いて、上記の問題が自分の中で一層クリアになり、更にはどうすればいいのかも見えてきました。前者については「構造保存変容」という「生命展開(Unfolding)プロセス(センタリングともいいます)」、後者については、利用者主体で行う、心から願うビジョンをランゲージとして作成するプロセスと、実現プロセスの専門家の支援という役割の変化でした。しかし、残念ながらこの部分を詳細に記述したNOO2巻以降や『The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle Between Two World-Systems』は日本では翻訳されていません。特に『The Battle』については、日本がその舞台であるのにもかかわらず、日本人が日本語で読むことができないのです。(なんと記事公開時点で『The Battle〜』はAmazon.co.jpから入手できなくなっていました!!)
ライトナー氏がまえがきで「日本とパタン・セオリーは深いつながりがある」と書いてくれましたが、たとえ起源はそうであっても、実際の認知・理解度ではNOOやBattleが英語圏で出版された2003〜2013年からおよそ10〜20年遅れているといっても過言ではありません。しかし2020年に『Pattern Theory』を見つけて、当時私が感じた問題とそれについての解決策がアレグザンダーの言葉とともに記されていました。英語圏に比べて20年遅れているかもしれませんが、追いつくための一歩が本書で踏み出せるのではないかという期待を持っています。
一方この20年の間に、1990年代からソフトウェア開発の文脈で行われていたように、様々な分野においての経験や暗黙的な知恵をパタンにまとめる活動(パタンコミュニティ)が継続され広がってきました。この点は先輩たちのJPLoPの活動を引き継いでパタンコミュニティの活動を続けていた早稲田大学の鷲崎先生、そしてソフトウェア開発以外の分野のパタン・ランゲージの普及を先導してきた慶応大学の井庭先生らの力による所が非常に大きいです。2010年から、日本を中心にアジアで開催されているAsianPLoPというカンファレンスがほぼ毎年実施されており、そこで少なくとも毎年パタン・ランゲージに関して集うコミュニティの機会が作られています。お二人とも2000年代からパタン・コミュニティで一緒に活動してきた仲間であり、その献身的な姿勢には本当に頭が下がります。そのような活動の延長として本書があります。
本書は建築の分野から生まれたパタン・セオリーを、様々な分野へと応用・展開させていくことを意図しています。比較的薄くて手に取りやすく、概要を掴みやすくなっているため、原著者の狙い通り、様々な分野の方々に広く知ってもらい、興味を持ってもらうには最適だと思います。結果的に本書が大著の『ネイチャー・オブ・オーダー』よりも先に読まれることが、広く世界観を知ってもらう上で重要なのかもしれません。
そして、本書が提示する「生命(いのち)の質」という、一見スピリチュアル的なことばにも注目して頂きたいと思います。「生命の質」を感じるとは、自分の「生命との共鳴」を感じる、ということです。本書に何度も出てくる「全体性」とは、デザイン対象が、それを含む更に大きな全体と不可分であるというだけでなく、「あなた自身が全体でもあり、デザイン対象と不可分であり、より大きな全体の一部である」という意味も含まれています。つまり、対象の「生命を感じる」とは、あなたの「生命を感じる」ことであり、対象はあなた自身でもあるのです。結論を言えば「自分の生命を感じることができなければ、対象の生命を感じることもできない」のです。
この点については、個人的には「個人の全体性の探求」が結果的には最短ではないかという仮説を立てています。本書とは離れますが、由佐さんの『ザ・メンタルモデル』に代表される内的世界の自己分離の統合への道のりは、アレグザンダーの言う「全体性」にまっすぐに通じていると直観しています。
つまり、自我(生存本能)の痛みの回避行動に無意識に駆動されている現実を自覚して、自己(=いのち・源・ソース)の意識からの行動を選択できるようになることは、「共鳴を感じる」ことに繋がるということです。
このあたりは本書から外れるので詳しくは述べませんが、私たちは、自分の感じた恐れ・不安・怒りのような不快感情は「あってはならない」と無自覚に切り捨てたり、「感じたこと」を「気のせい」や「考えてみたらおかしい」などとなかったことにしています。「心や身体で感じよう」とするよりも「頭で考えよう」とすることに慣れすぎているのです。この状態では「共鳴」を感じることは難しいでしょう。
アレグザンダーの語る「感じたこと」を物差しにするということは、「自分の感じたことを信頼する」ということです。論理的に考え判断することも依然として重要ですが、アレグザンダーはこれに加えて「自分の感じたものを信頼して使え」と提案しているのです。
これは普段から慣れていなければ、とても恐ろしくてできないかもしれません。感情・感覚を使うということは、自分の感じたものをありのまま受容して信頼する「自己信頼」が必要です。怖くても飛び込んでみる「勇気」が必要です。私たちは、どこまでいってもデザイン対象と不可分であり、常に本質的な課題は「自分の内側にある」のです。
アレグザンダーの実現したかった世界は、すべてが生命に溢れる世界です。彼は人、生物、人工物、そして地球全体が、生命の輝きを放つ世界を実現するための探求に人生を捧げ、2022年に光の世界に戻りました。後を継ぐ私たちが、少しでも世界や自分自身が「いのちの輝き」を放ち、次の世代に繋いでいくための礎とならなければいけません。その一歩に少しでも本書が貢献できれば、これほど嬉しいことはありません。
翻訳についての一切の責任は訳者の2人にあります。本書はKindle Digital Publishing(KDP)プラットフォームを通じて出版しますので、皆さんからのフィードバックを受けて、一般の出版社経由ではできない頻繁な更新も可能です。是非とも気になる点がありましたら、ご指摘いただければと思います。
最後に、本書は多くの人々の支えによって実現されました。通常行われる出版社を通じた翻訳書でなく、翻訳権の購入やその契約、翻訳およびそのレビュープロセス、編集作業、そしてそれらの資金を募るためのクラウドファンディングを含めた、本書の出版に関するすべての活動を仲間とともに行ってきました。翻訳エージェント経由でなく直接翻訳権交渉という一風変わった形にもかかわらず、日本における出版を快諾して頂いた原著者のライトナーさん、私家版翻訳プロジェクトに尽力してくれた蜂須賀さん、共に翻訳出版プロジェクトを立ち上げた師匠でもあり共訳者でもある中埜さん、プロジェクトのプロデューサーとして八面六臂の活躍をしてくれた高柳さん、クラウドファンディング以降に一緒に行動してくれた川西さん、倉林さん、笹さん、花井さん、短期間にも関わらず多くの的確なレビューをして頂いた浅野さん、羽生田さん、編集作業を「権利を購入して」行ってくれた野口さん、そして人生初のクラウドファンディングを通じて本書を応援・支援して頂いた多くの方々、そして最後に、書籍に関わると途端に生活が乱れる私を、温かく見守り応援してくれた、妻の恵子、息子の覚志、大輝、その他応援してくれたすべての人に感謝を込めて。
2024年7月18日、本格的に夏を感じた愛媛県松山市にて 懸田 剛
いいなと思ったら応援しよう!

