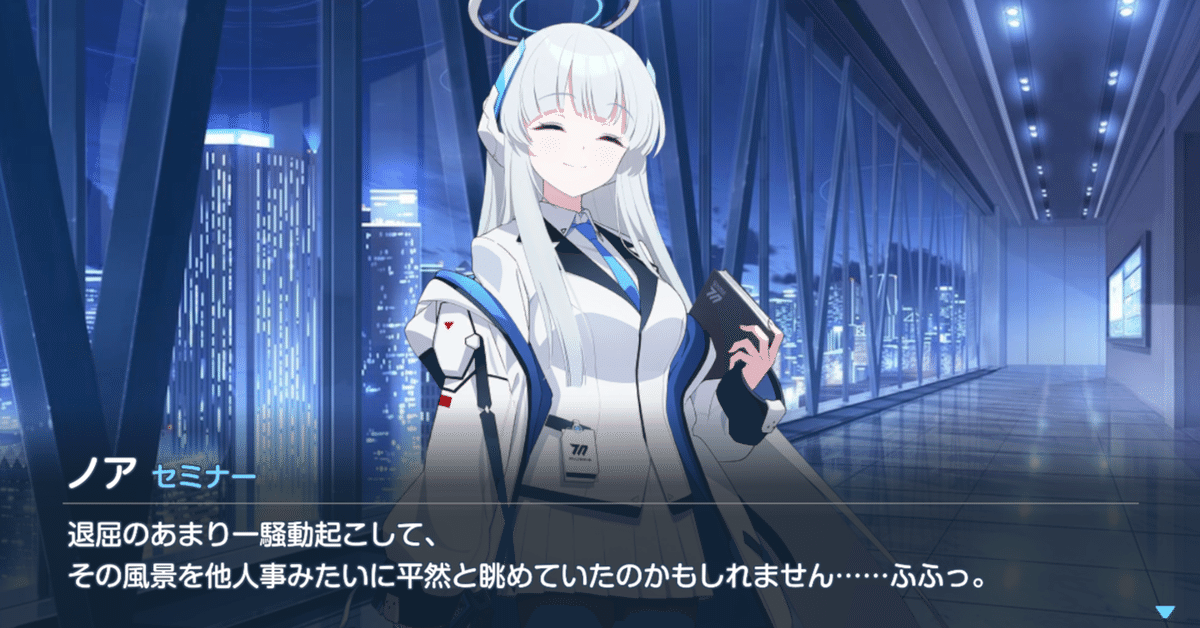
『生塩ノア』試論―詩人とエクリチュール―
※(9/21)改題と、全体的に文章をわかりやすく編集しました。内容は極力変えないように努めましたが…。
1.はじめに
ブルーアーカイブのノアのキャラエピソード及びメモリアルロビーがかなり面白いのでしっかり読んでみるという試みです。哲学的な領域からゆるめにアプローチしながら私見を交えていく……という感じの内容になっています。
ゲーム内のキャラストーリーを読んでいないと当然ですが理解できないような書き方をしているので注意。
2.エクリチュールとパロール
さて、私たちが普段相互コミュニケーションに用いる言葉は、エクリチュール(書かれたもの)とパロール(音声言語)とに二分することができる。これは書き言葉と話し言葉と言い換えて差支えない。あるいはエクリチュールを「書記」と訳すこともできると思う。
この二つの伝達手段はかなり古くから対立した二項であると見做されており、どっちの方が根源的かとか優越するか、みたいな議論が交わされ続けていたのが近代西欧哲学のワンシーン……なのだが、なぜそういったことを説明するかと言えば、ノアが書記官であり、また詩人でもある書き手であるからだ。しかもそれを前面的に押し出しているキャラクターだといえる。


記録というのはエクリチュールの本領。
ミレニアムサイエンススクールの生徒会【セミナー】の書記官として彼女は、日常的に起こっているあらゆることを観察し、記録するということが習慣として身についている(しかも秒単位で)。書記であることこそがそのまま彼女のパーソナリティになっている。
そもそもエクリチュールとは「時間を隔てて、その内容を伝達する」ということに存在意義がある。より短く言うと、<記録>的な言葉こそがエクリチュールなのだ。エクリチュールは書かれた文字であるから、時代を越えて残り続ける。

対してパロール(音声言語)にはそれができない。むしろそうであるからエクリチュールが生まれたという因果で説明される。ABと声に出して言葉を発音するとき、Bを発音する時にAの音はもう消えている……というように、音声というものには記録性がない。そのため、時間の経過に耐える道具として書き言葉が生まれた。
また、二者の対比は、エクリチュールは空間、パロールは時間の軸でしばしば表現される。書き言葉は紙の上の空間に広がり物理的に残り続ける、対して話し言葉は音の連続による時間の軸に広がるためである。
言い換えるとエクリチュールは永遠であり、パロールはその反対――瞬間とか刹那とかであるといえる。日本には「無常」という言葉があるので、響きとしてはそれが適切なような気がする。
もっと言うと、エクリチュールは客観、パロールは主観という項で二者は対立する。パロールが個人による話し言葉である以上は、たとえ同じことを言う場合でもその人独自の話し方や調子が伴うので、音声を書き起こした文章よりも直の音声の方がよりその人の主観が混じる。エクリチュールでは同じ内容を伝達するには同じ文字を書くだけで済むため、そこに個人的な差異がない。その内容を客体化する。こうした特性は電話とメールの違いを例に挙げると理解しやすいかもしれない。
これらを合わせて、
エクリチュール=永遠、客観なるもの
パロール=刹那的、主観なるもの
であるということを、まず言っておく必要がある。
とにかくここでは、それぞれがこういった特性をもつ以上は、例えば同じ内容を言葉で伝えようとする場合でも、それを話すのと書くのとでは異なった意味が付随して来る、ということをいったん覚えておいていただきたい。
3.言葉の恣意性―言葉にするのはこわい
閑話休題。先ほどの内容を踏まえてノアがエクリチュールをその身で体現するキャラクターであるということを再考すると、ノアについて、あるいはエクリチュールについてが相互に理解しやすのではないかと思う。
ノアのアイデンティティは書記、書記行為こそエクリチュールらしいエクリチュールである……つまり彼女の専売特許が、エクリチュールを扱う行為である。そういうことを言いたかったための前置き説明だった。
そしてもう一つ分かることとして彼女は、事実以外のことを記述していない。
先ほどエクリチュールを「永遠」「客観」と置き換えたことを思い出してほしい。 エクリチュール・パロールを<永遠ー客観><無常ー主観>の軸で考える時、人間存在はそもそも後者、パロール的である――ように見える。このことを突き詰めていくとじつは悪循環なのですが、とりあえずこう結論づけることはできる、と思う。
つまり、本来主観的かつ無常な存在が人間である。しかしだからこそ、エクリチュールという永遠の客体を用いてその逆で在ろうとする――そう、理性によって。こういう見方はどうだろうか。
人間が生み出した書記行為というのは、大げさにいえばこのような人間存在の根源に逆行する性質であるように思う。そういう意味では、人間の理性によって生み出されたエクリチュールこそもっとも人間的、という人もいるかもしれない。まあこんなことは枝葉末節。

しかし、エクリチュールが客観的な言語とはいえ、そこには必ずしも書き手の意図や責任が付き纏ってしまう。これが先ほど述べた問題で、それは、書かれた「それ」は記録性、大げさにいえば<永遠>性を帯びる。ということに関わってくる。
例えばエクリチュールによる物語文学以前の口承伝承(パロール)による物語は、ある意味ではそれを避けてきた。それはなぜか。それが「文字」という歴然たる証拠を残さない刹那の物語であるためだ。パロールがエクリチュールに対し刹那的な言語であることは説明した通り。
パロールはいわば、オフレコの言語だ。その<刹那>性のためにそうした特性をもっている。ここまで書くと、察しの良い方なら本記事で言いたいことが見えてきたのでないだろうか。
逆に例えば、仮名で書かれたエクリチュールである日本の古典物語文学の多くは、作者から登場人物に対する敬語表現にとても敏感だったりもする。それは、その作品が「書かれた」物語である以上は、必ず貴族社会の中のどこかに身を置く実在の作者が存在したためとも言われる。エクリチュールは残されるから、それを自分のものとして誰かに読まれるということ意識せざるを得ない。
書くという行為は永遠だから、そこにはもういないはずの書き手の所在を読者に指し示しつづける。だから、たとえば近代の文学論において、書かれていることの意味を作者に還元しようとする行為を批判したテクスト論は有名だ。書かれた文章は作家の手を離れるから、書き手の意図や意志とは関係なく、自律的なテクスト(織物)として読まれるべき、というもの。このテクスト論は、テクストひいてはそれを構成する言葉の持つ、作者に縛られない無際限の力をとらえるとともに、逆説的に言語表現における作家と読者のコミュニケーションの限界を示したものでもある。
前述のテクスト論はロラン・バルトだが、同時に仏哲学者デリダも、「誤配」という言葉を用いて似たことを主張している。
(ノアはボードレール愛読者の仏文少女なので、こういったポストモダン思想的なテーマが掲げられているのだと思う)
それは、作家が本当に伝えたかったことは本当の意味のままで伝わらないという読者とのコミュニケーションの深い断絶だ。書かれたものは、読者によって分解・再構築されるから、作家が書こうと思った真実と読者が読み取ったものは同じものたりえない。作家でなくても、誰の名前にもこれは置き換えることはできると思う。これは、ある意味では人間の言葉による対話行為全般に拡張していうことができるからだ。
たとえそこに書かれている内容を理解することに成功したとて(本当に?)、そして、それが一本の筋が通った理論として成立した読みでも、果たして書き手の気持ちや意図したものと一致するとはいえない。
そのため、「本当のこと」というのは自分の外側へ出て行った瞬間に、好き勝手に読まれてしまうという性質を帯びる。つまり、誰のものでもなく、同時に誰のものでもあるというテクストになってしまう。
要は程度の問題なのだ。この記事も生塩ノアというキャラクターをテクストとして好き勝手に解読しているのだから。こういうやり方は先ほどのロラン・バルトの著作から発展した批評の方法論である作品論というものに近しい読解の仕方で、これは近代文学や批評理論に触れたことのある方には危機馴染みがあると思う。
繰り返しだが、パロールよりエクリチュールであるこその深い問題がある。書かれたものは残り続け、毎秒ごとにその文脈は微細に変化しつづける。例えば終戦前に書かれた小説を読む時に、我々の世代では必然的に戦後というコードからしかそれを読むことしかできない。文字が長い時間を残り続けると、こうして新しい読み方が生まれ続けるのだ。そのうえ、読者の誤解を解くには作者とテクストの距離があまりに遠く離れてしまっていて手のつけようがない。書かれたテクストというのは逃れようもなくそうした問題にさらされ続ける。

そしてさらに深く突き詰めると、言葉にして表現し、それを読み解くという行為は「本当のこと」を言葉に翻訳してしまうことでもある。言葉にした瞬間に、「本当のこと」は言葉に閉じ込められるといっていい。誰かが自分の気持ちを語る時、それが言葉になったその瞬間に恣意性をもってしまう。
わたしたちが何かを言う時、まず形のない言いたいことがあって、それを形ある言葉にコンバートするプロセスがある。何かを聴き入れる時も、最も自分に適した言葉にコンバートする。その過程の中で本質の劣化は逃れ得ない。書かれる以前の原型の観念と書かれた言葉は、じつは違う形をしている。つまり、言葉というのは一種の記号であり、物事の本質じたいはその彼岸にあるといえるのだ。
ノアというキャラクターの核はここにあると思う。言葉を扱う詩人であるから、言語の恣意性、そしてそれによる影響の恐ろしさを知っているからこそ、あえて語らない――「本当のこと」を書き記さない。
書記行為を遂行するとき、努めて事実だけを客観的に記録する――それは裏返って、主観的な真実の一切を記録しない、という手法である。
ここで説明したのは、エクリチュールは時間を隔てて残るけれど、だからこそ書かれた瞬間から一つのテクストになってしまうという問題があるということ。そして、それを読む人や、あるいは時間の経過によって、あらゆる文脈で読まれてしまうことを避けられないということである。
むろん、これをどう読むかも読者のみなさんに任されている。
個人的な如何なる意図も含まない事実の記録は、ディスコミュニケーションを生みにくい。残り続ける言葉であるから、誤解を生み続けて一人歩きしてしまうのが言葉であるから、それを知っているノアは超客観的記録という手法を取るのだろうと思う。言葉に誠実であるから、コミュニケーションの断絶を知っているからこそ客観に徹しているのではないだろうか。
しかし一方で、彼女には記録以外にも書くものがある。
それが詩である。彼女にとっての「詩」は「記録」に対しての逆の位相に置かれるものであるといえる。
それはつまり、客観であるところのエクリチュールに対して、極めて主観的なエクリチュールとして、位置づけることができるということ。
無常の存在である人間の存在の根源を貫く何かを、あえて言葉という記録に残すことで永遠にしようとする。圧倒的主観である自らの感覚を、書記行為によって客体化する。そういう構図が仕組まれているという見方が出来ると思う。
また、本来言葉にすることができない「本当のこと」=本質的な事柄を、しかし言葉を以て言葉に直そうとしている――そういう試みなのではないか――言葉にできないものを、あえて言葉にして打ち出そうとしている行為が彼女にとっての詩作に位置づけられるのではないか、という説をここに打ち立てようと思う。
4.ボードレール「異邦人」について
このために長い前置きが必要だった。
ここではメモリアルロビーを扱うつもりである。他のシナリオを個別に見ても発見があるはずだが、ここでは割愛する。

雨の日に出会った先生とノア。先生が曇ったガラスの内側に落書きをしていると、ノアもそれに応じて何かを書き出して――というシーン。
さてこのメモリアルロビーを読み解く鍵は二つ、ボードレール「異邦人」及びその周辺・前述のエクリチュール・パロールの特性である。何も真に受ける必要はないのだが、一つの切り口としてそうも読める……というものとして捉えてほしい。
ノアが先生に倣いガラスに書いているのは、ボードレールの「異邦人」という詩。ヒントは、ノアのモモトークのコメントが「キヴォトスの憂鬱」(詩集『巴里の憂鬱』の引用。『異邦人』はそのうちの一つ目の詩)であることが挙げられるか。実装前のPVに登場していた段階では詩集『悪の華』を手にしていたとも聞いた。
とりあえず、以下「異邦人」を全文引いてみることにする。
――お前は誰が一番好きか? 云ってみ給え、謎なる男よ、お前の父か、お前の母か、妹か、弟か?
――私には父も母も妹も弟もいない。
――友人たちか?
――今君の口にしたその言葉は、私には今日の日まで意味の解らない代ものだよ。
――お前の祖国か?
――どういう経度の下にそれが位置しているかさえ、私は知っていない。
――美人か?
――そいつが不死の女神なら、歓んで愛しもしようか。
――金か?
――私はそれが大嫌い、諸君が神さまを嫌うようにさ。
――えへっ! じゃ、お前は何が好きなんだ、唐変木の異人さん?
――私は雲が好きなんだ、……あそこを、……ああして飛んでいく雲、……あの素敵滅法界な雲が好きなんだよ!
ノアが引用しているのは「お前は誰が一番好きか? 云ってみ給え、謎なる男よ」なる冒頭部分。で、この部分だけが引用されているせいでツイッターでこれが一人歩きして、「卑しい」みたいな変な捉え方をされているように見受けられた。
もちろんこの「卑しい」というのはオタク的なタームで、文字通りの意味ではないのだが……と、こうしてみると言葉の読まれ方のこわさというものの一端が分かるだろう。でも、私が正当派の読みとも限らないから、ある意味公平に、正誤や良し悪しを問うことは面倒である。
しかし、少なくとも元のボードレールはもちろん、ハーレム系ラノベ的文脈でいう「どっちが好きなの?」みたいな話ではないわけである。
新潮文庫の背表紙にはこう書かれている。
父母兄弟よりも、祖国よりも、お金よりも、雲を愛すると宣言して、詩人の立場を鮮明に打ち出した『異人さん』
こうも説明されてしまうと素人の私にはもはや言えることがないのだが、だいたいこの通りに理解してよいのではないかと思う。私なりに考えるボードレールの方への解釈で重要な点は、詩の中で、質問者でなく答えている方の人間――異邦人がボードレール本人であるということかな。
そして、これはノアの引用においても同じことだ。つまり、ノアをボードレールに置き換える。ノアが詩を書く人であるからだ。
異邦人というのはもちろん比喩的な意味であり、巴里=キヴォトスという街の都市空間において、その中に溶け込まないのが詩人――それが自分だという告白、というように読んだが、いかがだろう。孤独の告白ないしは決意といえる。
つまり、ノア=キヴォトスにおける異邦人。(結論1)
雲のほかに誰も何も愛さない、という言葉は、ボードレール同様にノア自身に還元される。だから「キヴォトスの憂鬱」である。
しかしノアが「異邦人」であるのはいい。が、しかし、残された疑問が浮かんでくる。なぜなら、ノアがガラスに書いたのは問いかけであるから――つまり、先生こそがそれに答えるべき「異邦人」であるべきなのだ。そうなってくると、先生が唯一キヴォトスの外側から来た人間――そう、原義の異邦人であるということが思い出される。
そして先生はキヴォトス唯一の「大人」であり、メインストーリーにおいて連邦生徒会長から託された――と、まあ、説明しなくてもご理解いただけると信じたいが、ともかく、キヴォトスという都市を一つの空間として見る時に、先生という人間自体が極めて異質な存在であるということは作品全体を通底して語られている。先生もキヴォトスにおける異邦人なのだ。(結論2)
そうなってくると、ノアは先生に対しての問いかけとして、「お前は誰が一番好きか?」=「お前も、誰も好きなんかではないんだろう?」=「先生も、私の同類としての孤独を抱えているんだろう?」と言っている、ということになってくる。孤独というのはボードレール風に言うと「憂鬱《スプリーン》」「倦怠《アンニュイ》」ということになるのかな。
ノアが巴里=キヴォトスにおける異邦人であるということと、先生がその同類であるということがここに描かれている。そして、それは答えを必要とする言葉ではないけれど、ノアはそのことを先生に問うている。
ノアも先生も、ともに異邦人である(結論3)というのが私のこの場面における解釈だが、どうだろうか。
そういう前提で、特に注目したいのはメモロビ後の以下の台詞で、これは二回目の引用になるが……。

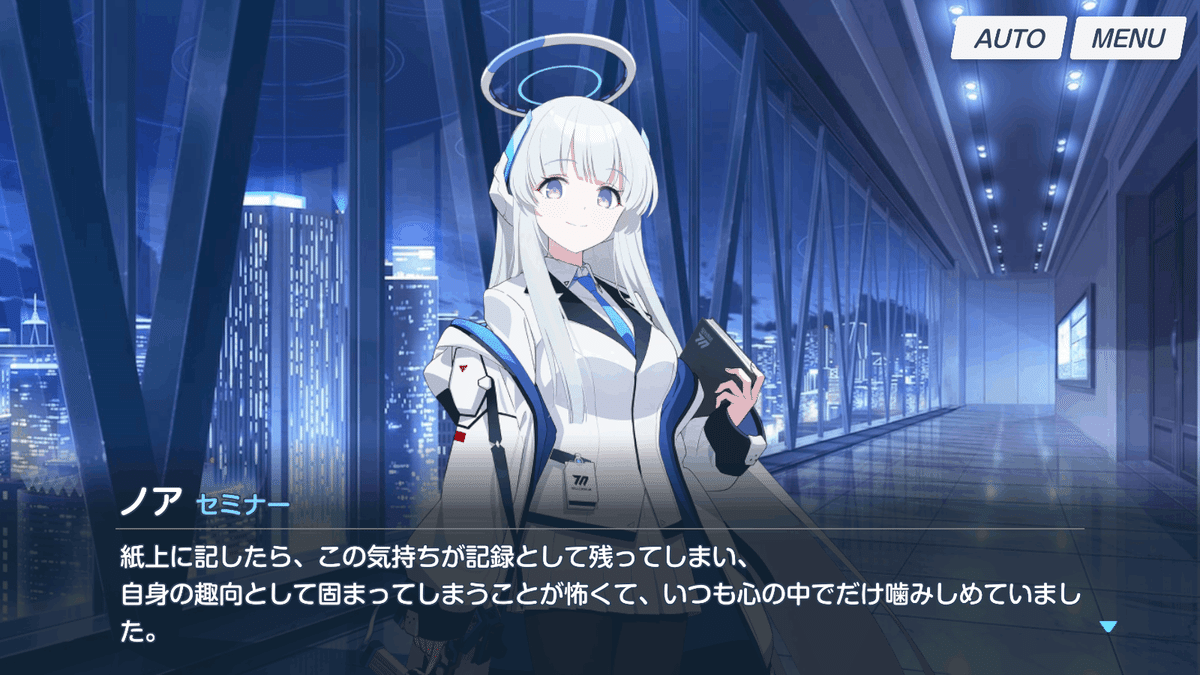
「異邦人」であることが「自身の趣向として固まってしまう」ということはつまり、自分の性質が<詩人>であるとともにそれが<孤独>な性質であるということを自ら決定づけてしまうことを意味する。言葉にする、特に「書く」ということの意義は先ほど解説した通りだが、ノアが言う通り、エクリチュールになった瞬間にそれは永遠に「固まってしまう」のだ。だから恐ろしいのも当然のことだ。
ならば、ノアがなぜ「異邦人」の一節をついに書くことができたのか。その理由を明らかにするということがこの記事で書きたかったことである。それは最初から本論でしつこく述べて来た、エクリチュールとパロールの問題に帰着していく。
5.ガラスのページに書かれた詩はエクリチュールなのか?



「刹那の記録」というレトリック――これら二つは相反する概念である。つまりエクリチュールとパロールの表象でもある。ガラスの曇りにに書かれた文字というのは、記録という性質を持ちながら乾いてしまえば記録されることはないという刹那性、刹那と言いながら少しの間だけ残ってしまう記録性を同時に内包している。
さて、ガラスに書かれた文字をエクリチュールと呼ぶことができるだろうか。
答えはむろん、「そうであり、そうでない」ということになる。メモリアルロビーで起こっているこのガラス上の書記行為は、前述の通り確かに認めることができる文字であるからエクリチュールではあるのだが、雨が止めばいずれ消えてしまうということから<記録>という軸においてそぐわず、しかし一瞬の間、ノアと先生だけの前に確かに現前する言葉であるから、パロール的でもない。エクリチュールとパロール……こうした諸概念の対立は、このガラスのページの上では解体されている。
つまり、どちらかでなくてはいけないという二元論を解体し、新たなかたちを再構築するという、ジャック・デリダのいうところの脱構築がここに起こっているのだ。ここに生まれているのはエクリチュールでもパロールでもない新たなコミュニケーションの形式であるといえるだろう。
ガラスに書かれた文字はいかなる客観的事実でもないノアと先生の心。その新しいことばは記録性から恣意性から逃れ、子供のように思ったことをさらけ出しても何のそしりを受けることもないのだ。ノアが胸に抱えていた「本当のこと」、つまり、「異邦人」の感覚……それを書き出しても、憚られる必要はない。それがエクリチュールによって客体化され、永遠のものになってしまうということも起こり得ないからだ。しかも、二人ともが「異邦人」だから、孤独でもない。
先生がノアにもたらしたのはこういったことではなかったか。
そこには救いがある。テクストに縛られ、がんじがらめになった人に、いかなる文脈からも独立したノートを与え、心ゆくままに「本当のこと」を語り明かすことのできる時間をもたらした……やさしい赦しが、ここに与えられているのではないだろうか。


6.おわりに
なんだかとても遠回りをした気がするし、わざわざ言われるでもないことを大げさに言ってしまった感がある。ともあれ、僕はノアのことがすごく好きだし、彼女の話がしたかった。
詩は、「何ひとつ書く事はない」という一文で書き始めることができる。何かの記事で谷川俊太郎がそう言っていたのを読んだ。
「何ひとつ書く事はない」と、それでもそう書いている。書く事はないと言い放つことで語っているという逆説が、本当らしいと思う。何ごとも直接に語ることはできない。だから、いかに語らないか、語らないでその周辺を埋めていくことで型抜きのようにそれをえぐりだす……そういう作業が、言葉による創作なのではないか、と思わなくない。言葉は万能ではないから、沈黙を空白を以て語る。詩人は言葉のむなしさをしっているからこそ詩人たりえるというのが、この頃考えるところ。
何ひとつ書く事はない
私の肉体は陽にさらされている
私の妻は美しい
私の子供たちは健康だ
本当の事を云おうか
詩人のふりはしてるが
私は詩人ではない
私は造られそしてここに放置されている
岩の間にほら太陽があんなに落ちて
海はかえって昏い
この白昼の静寂のほかに
君に告げたい事はない
たとえ君がその国で血を流していようと
ああこの不変の眩しさ!
だが、金狼《ジャッカル》にもあれ、豹にもあれ、牝狼にもあれ、
猿にも、蠍にも、禿鷹にも、蛇にもあれ、
われらの悪徳をとりあつめた穢らわしい動物園の、
啼き、吼え、唸り、這いまわる怪物どものさなかに、
さらに醜く、さらに邪な、さらに不浄な者が一匹いる!
大仰な身振りもせず大きな声も立てないが、
進んで地球を廃墟にしてしまうことも、
ひとあくびにこの世を呑みこむことも、やりかねない。
これこそ〈倦怠《アンニュイ》〉だ!――目には心ならずも涙、
水煙管くゆらせながら、断頭台の夢を見る。
きみは知っている、読者よ、この繊細《デリケート》な怪物を、
――偽善の読者よ、――私の同類、――私の兄弟よ!
