
あらためてシャッターの「幕速」というものについて考えてみた
※この記事は有料に設定していますが、本文はすべて無料でお読みいただけます。
フィルム時代はシャッターの幕速なんてろくに気にしたこともなかったし、デジタルになってからもおおむねスルーですごしてきた。
が、電子シャッターしかないシグマfpを使うようになって、幕速の速い遅いという問題にいやおうなく直面することになって、それで少し記事にまとめてみようと思いはじめた。
最初は電子シャッターの幕速を調べる方法だけと思っていたのが、あれもこれもと書いているうちにだいぶ長くなってしまった。
正直なところ、知らなくたってどうということもないことではあるのだけれど、知っておいて損はしないはずだし、もしかしたらいつかどこかで役に立つかもしれない。
と思い込むことにしておく。ので、お暇な方はどうぞお付き合いくださいまし。
お代は見てのお帰り方式だ。気に入っていただけたら購入なりサポートなりをいただけると励みになりますんでよろしくお願いしたい。
幕速の前に「幕」ってなんなの?
レンズ交換式デジタルカメラで主流となっているフォーカルプレーンシャッターは、2枚の幕を使って露光時間(撮像センサーに光が当たる時間=シャッタースピード)を調整する仕組みになっている。
この2枚の幕のうち、先に走る幕=露光をはじめる幕を「先幕」と言い、後には知る幕=露光を終了する幕を「後幕」と言う。英語だとそれぞれ「1st curtain」「2nd curtain」となる。
カメラ関連の用語で「電子先幕シャッター」とか「後幕シンクロ」というのを目にしたことがあるかもしれない。その「幕」がこれだ。
最近のカメラでは金属やカーボン製の薄い羽根を複数枚組み合わせたタイプが一般的だが、部品として見る場合は「シャッター羽根」と言う一方、機能として考える場合は「シャッター幕」と言う。
ちょっとややこしいかもしれない。
幕速とは走行開始から終了までの所要時間を言う
で、「幕速」と言うからにはこのシャッターの幕のスピードのことかと思うと、実はそうではない。
どういう理由なのかはわからないが、なぜか幕速は時間ではかることになっている。
「○○mm/秒」みたいに「距離÷時間」のかたちではなくて、「××msec(ミリ秒)」のかたち、つまり時間の長さであらわすのが業界の作法である。
この場合、対象となるのは、先幕なり後幕なりが画面の端からスタートして反対側の端に到達するまでの時間を指す。
まあ、シャッタースピードにしたって「スピード」と言いつつ実態は「時間」だったりするので、あまり細かく考えないことにしといたほうが肩が凝らなくていいと思う。
現行のレンズ交換式カメラのほとんどは縦走りのフォーカルプレーンシャッターを使っている。縦というのは画面の短辺のことで、35mm判フルサイズの場合はおよそ24mm。
なので、幕速は先幕か後幕が24mmの距離を走り切るのに必要な時間であわらすことになる。
厳密に言えば「××msec/24mm」と書くのが「速度」をあらわす場合には正しいことになるだろう。
ただし、35mm判フルサイズよりも画面の小さなAPS-Cサイズやマイクロフォーサーズでは短辺の長さが短くなる。そのため、幕速の数字が同じであれば、より長い距離を走るもののほうが幕のスピードは速いことになる。
シャッターの方式による幕速の違いを知っておこう
手もとにあるデータの中からフィルム一眼レフの幕速をいくつか拾ってみる。
キヤノンEOS-1N 2.7msec
ニコンFM2N 3.3msec
キヤノンEOS Kiss 6.3msec
いずれも縦走りのフォーカルプレーンシャッターなので、走行距離は24mmだ。
実は幕速の情報は公式にはあまり出ていない。まるっと非公開にしているメーカーもあるし、機種によって聞くと教えてもらえるケースもある。
が、いずれにしても、スペック表に幕速の数字が載っているのは見た記憶がない。
なので、今のカメラがどの程度なのかははっきりとはわからないが、だいたいのはそんなに変わっていないと思う。もしかしたら、ソニーのα1あたりはもう少し速くなっているかもしれないが。
そのへんはさておき、メカシャッターの幕速は速いもので2.7msec。遅いものは6.3msecぐらい。と、アバウトに考えておけばいいだろう。
電子先幕シャッターも、後幕は物理的な幕を使うので、幕速としてはメカシャッターと同じだ。
残る電子シャッターはというと、これがぐっと遅い。
こちらも公式の数字は出ていなくて、ネット上で探すと個人あるいは団体がはかった非公式の数字が見つかったりする。
が、その数字がメカシャッターのと比べるとあからさまに遅いのだ。
どれぐらいかと言うと、メカシャッターの10倍とか20倍とかがざらだったりする。
たとえば、ワタシが愛用しているSIGMA fpなんかだとJPEGや12ビットRAWのときで25msecぐらい。14ビットRAWのときだとその倍の50msecぐらいになるのである。
遅いよね?
そう。電子シャッターの幕速は、ごく一部のものすげーヤツを別にすれば、めちゃんこ遅いのだ。
蛍光灯を使って電子シャッターの幕速を調べる方法
インバーター式でない普通の(と言うか、昔ながらの)蛍光灯を使うと、だいたいのカメラは電子シャッターの幕速を調べることができる。
方法はすこぶる簡単で、まずシャッタースピードを1/1000秒ぐらいにして蛍光灯で照明された壁を撮る。シャッタースピード以外は適当でかまわない。

すると、こんなふうな縞々な壁が写るはずだ。
で、画像上の縞々のパターンを数える。
この明暗の縞々パターンの数に「10」または「8.33」を掛ける。
それで出てきた数字がお使いのカメラの電子シャッターの幕速だ。
掛ける数字が「10」なのか「8.33」なのかは、お住まいの地域の電源周波数による。
50Hzの地域の方は「10」を、60Hzの地域の方は「8.33」を掛ける。
さっきの画像はSIGMA fpで撮ったもので、縞々パターンは5つ分ぐらい。ワタシが住んでいるのは50Hzの地域なので、
「5×10=50」
となる。つまり、幕速は50msecとなる。
EOS-1Nの18.5倍、EOS Kissの7.5倍遅い。そういう数字なのだ。
ちなみにこれは14ビットRAWのときの数字で、12ビットRAWやJPEGのときは25msecぐらいに速くなる。
機種ごとの電子シャッターの幕速
ワタシ個人も電子シャッターの幕速のデータはほとんど持っていなくて、手もとにあるのをいくつか載せておく。
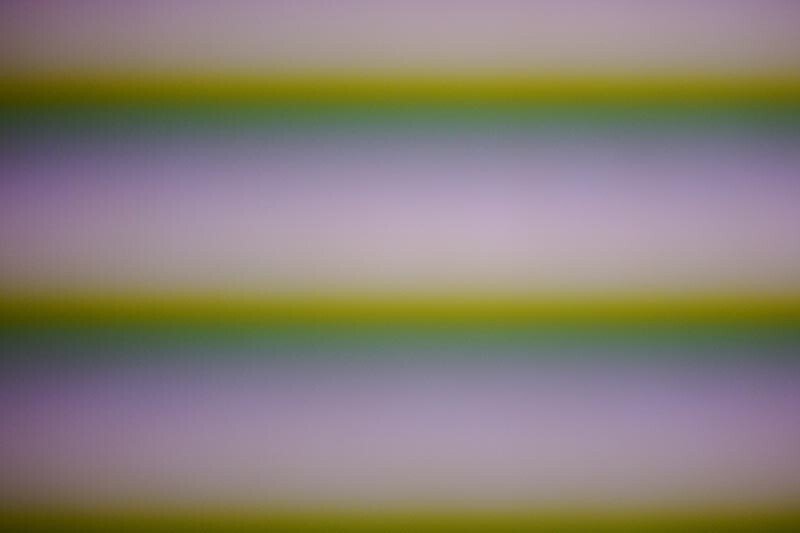
シグマfp(12ビットRAW) 2.5パターン 25msec

シグマfp(14ビットRAW) 5パターン 50msec

シグマfp L(12ビットRAW) 5.3パターン 53msec

シグマfp L(14ビットRAW) 9.7パターン 97msec

ソニーα7R III(1枚撮り・14ビットRAW) 7パターン 70msec

ソニーα7R III(連写・12ビットRAW) 3.5パターン 35msec

キヤノンEOS 90D(14ビットRAW) 4.7パターン 47msec

ソニーα6300(サイレント撮影・12ビットRAW) 4.7パターン 47msec
とまあ、こんな感じで上にあげたメカシャッターに比べると圧倒的に遅いのがわかる。
それから、画素数が多い機種ほど遅くなる傾向があるのと、同じ機種でも12ビットRAWやJPEGのみより14ビットRAWのほうが2倍ぐらいに遅くなる。
また、この縞々のパターンはシャッタースピードを遅くしていくと目立たなくなる。
シャッタースピードが「1/電源周波数」秒のとき、それからその1段上と1段下のシャッタースピードのときは、縞々は薄くなってほとんど気にならなくなる。
なので、50Hzの地域であれば1/100秒か1/50秒、1/25秒で撮れば問題なく普通に写せる。
ついでに書くと、ソニーのα1やα9シリーズのような積層型撮像センサーを搭載した機種は、電子シャッターとしては驚くほどに幕速が速い。ネットで見た情報ではα1は4msec程度、α9は6.7msec程度であるらしい。
これぐらいのレベルになると専門的な知識と機材を用意しないといけなくなるので、ワタシ的にはお手上げになる。
幕速が遅いと動く被写体が歪んで写る
ところで、幕速が遅いとどういう問題が起きるのだろうか。
というのを考えてみたい。
たとえば、幕速が50msecのカメラの場合、画面の短辺の端から端まで、つまり画面の上から下まで(または下から上まで)走り切るのに50msecかかる。
50msecとは1,000分の50秒、つまり0.05秒。まあ、短いと言えば短い時間だが、1秒の20分の1=1/20秒と書くと、そこそこ遅い感じがしてくる。
ここでは画面の上から下に向かって幕が走ることにする。なので、横位置で人物を取ると頭から順に写っていって足が最後になる。
イメージとしてはこんな感じ。
なお、テキストの表示幅が36字以上でないとまともに見えないので、そこはうまいことやってください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□
□□■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
これの上から順に1行ずつ読み取っていくようなかっこうだ。
このときに右側の人物だけが画面の右から左に移動しているとする。頭のてっぺんが写りはじめてから足先が写り終えるまでに左に9マス移動するとする。
そうすると、頭が写りはじめてから足先が写るまでのあいだに人物が移動するわけだから、胴体は頭よりも左に、腰はさらに左、足はもっと左に写ることになる。
ので、こうなる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□
□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□
□□■■■■■■■■■■■□□□□□□□■■■■■■■■■■■□□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
斜めに写っちゃうんである。
こういうことが起きる。
動く被写体が斜めに歪んで写ることから、「動体歪み」と言う。
左側の人物は移動していないので、頭の真下に足先が写る。まっすぐで歪みがない。
動くものだけが歪む。だから「動体歪み」なわけだ。
そして、この動体歪みは被写体の移動するスピードが速いほど、それから幕速が遅いほど強くなる。
人物の移動スピードが同じであれば、幕速を3倍速くすると右側の人物の移動距離は1/3に減る。ので、動体歪みも3マス分になる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□
□□■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
だいぶまっすぐな写り方になる。
9倍速ければひとマス移動するかどうかのうちに写り終えてしまうのだから動体歪みはちょっぴり、もしくはほぼゼロ。無視できるレベルになる。
というのがあるので、幕速は速いほどいい。そういうわけだ。
動かない被写体だって歪むことがある
ややこしいのは、シャッタースピードの速い遅いと動体歪みの度合いが無関係なこと。
ひとつひとつの画素に光が当たる時間はシャッタースピードだけで決まる。それに対して、画像全体の撮りはじめから撮り終わりまでの時間は幕速とシャッタースピードを足したものになる。
なので、ある程度シャッタースピードが速い条件では、手持ち撮影時のカメラの揺れがブレではなく、揺れと言うか歪みとしてあらわれる。
たとえば、露光中にカメラが左右に揺れるとどうなるか?
というのを考えてみる。
カメラが左右に揺れることで撮像センサーに映る映像も左右に揺れることになる。その揺れる像を上から順に1行ずつ読み取っていくわけだ。
すると、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□
□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□
□■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□□□
□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□□
□□■■□■■■■■□■■□□□□□□□□□□■■□■■■■■□■■□□
□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□□
□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□
□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□
□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□
□□□□□□■■□■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
こんなふうに写る。
ぐにゃぐにゃだ。
なので、「コンニャク現象」などとも呼ばれる。
あるいは「ローリング歪み」とか「ローリングシャッター歪み」と言う。
ローリングシャッターと言うのは上から順(または下から順)に読み取っていく方式の電子シャッターのことで、順番なので当然いちばん上といちばん下とで時間差が生じる。この時間差が「幕速」である。
一方、全部まとめて同時に読み取りができる撮像センサーもあって、こちらはグローバルシャッターと呼ぶ。
グローバルシャッターだと上の端も下の端もまったく同時に写せるので幕速はゼロmsec。必然的に動体歪み、ローリングシャッター歪みは発生しない。
このグローバルシャッターを持つ撮像センサーはすでに実用化されているのだが(そもそもCCD撮像センサーはグローバルシャッターだったりするのだ)、今の時点では一眼レフにもミラーレスカメラにも使われていない。
メカシャッターの幕速のストロボ同調速が目安
電子シャッターの幕速は簡単な方法で調べられるが、メカシャッターのはどうだろうか。
これもはかる方法はあるが、手軽にというわけにはいかない。が、スペックデータからおおざっぱに範囲を絞り込むことはできる。
スペック表のシャッターの欄の「フラッシュ同調速度」とか「Xシンクロ」とか書かれているシャッタースピードがある。
この同調速度はストロボを発光させるタイミングが確保できるいちばん速いシャッタースピードで、これより高速になると先幕が走り終える前に後幕が走りはじめるので、ストロボを発光させても画面全体に光が当たらなくなる。
ややこしい話ははしょるが、幕速が速いほど同調速度が高くなる、という関係がある。つまり、同調速度が高い=幕速が速いということだ。
同調速度の前後のシャッタースピードを表にして以下にあげておく。
1/2段系列の数字と1/3段系列の数字が混ざっているのでちょっと不自然に感じるかもしれない。

ちなみに、シャッタースピードは「2のx乗」で計算するので正規の数字はけっこう中途半端になるのを、わかりやすく丸めて表記することになっている。
1/250秒と称しているのは、実際には1/256秒なわけだ。で、右側のが分数表記のを小数点表記になおしたものとなる。
で、同調速度が1/250秒のカメラの場合、幕速は3.91msecより速くなくてはならない。
そうでないと、先幕が走り終えて、ストロボに光っていいよって信号が流れて、実際にストロボが光って、それから後幕が走りはじめる、という流れが成立しなくなる。
なおかつ、1/250秒のうえの1/320秒よりは遅い。なので、幕速は3.91msecから3.10msecのあいだ。ということになる。
ただし、ストロボの発光のタイミングが多少ズレても問題が起きないように時間的余裕を少し持たせてある。そのため、実際の幕速は3.10msecよりもやや速い可能性はある。そのへんはお含みおきいただきたい。
最初のほうに書いたフィルム一眼レフの数字から考えると、ニコンFM2Nの3.3msecは1/250秒(3.91msec)より速くて1/320秒(3.10msec)より遅い。ので、同調速度は1/250秒。
キヤノンEOS-1Nの2.7msecはうまくタイミングを調整できさえすれば1/320秒にはできたかもしれないが、メカ(シャッター)と電子(ストロボ)の連携は単純ではないので余裕を見込んで1/250秒に抑えてあるのかもしれない。
そういうややこしいのを抜きにしてざっとで考えると、同調速度が1/160秒なら幕速は6.20msecから5.52msecのあいだ、1/180秒なら5.52msecから4.92msecのあいだ、というぐらいに思っておけばそう遠くないはずだ。
まとめ
さて、冒頭にも書いたように、幕速について知ったところでたいしたお得はないと思うが、カメラという機械がどういうふうに動くのかに興味のある方には楽しんでもらえたのではないかと思っている。
せっかくなので、動体歪み、ローリングシャッター歪みによって、写りがどういうふうに変わるのかがわかる作例画像をいくつか載せておく。
シグマfpとソニーα7R IIIの電子シャッターでの動体歪みの比較、同じ2機種で電子シャッターとメカシャッターの比較、それからシグマfp Lで静止被写体を撮ったときの被写体の変形がわかる比較だ。
予想どおりの写りでしかないが、記事をご購入いただいた方にだけごらんいただけるようにしておく。
毎度毎度で恐縮だが、ライターとしての活動へのご理解とご支援をいただけるとうれしく思う。
ここから先は
¥ 100
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
