
「高齢者虐待を一緒に解決しよう!実践的な取り組み方法とは?」
概要
この記事は、約8年間、地域包括支援センターで高齢者虐待対応を行ってきた社会福祉士である私が、介護事業所として行わなければならない法定研修の一環で居宅介護支援事業所にて実施した「高齢者虐待研修」についてまとめたものです。
様々な高齢者虐待防止研修の資料と比べ、
・事例をもとに説明し、聞いている職員がイメージしやすいようにしている
・制度のみをつらつら話すのではなく、高齢者虐待対応の実際について明らかにしている
・本人、養護者支援において必要な「ケアマネジャー」と「行政・地域包括支援センター」のよりよい連携について明らかにしている
ということを売りにして構成しました。
高齢者虐待対応に不安を抱えているケアマネジャーの方、行政や地域包括支援センターとどのように連携を図っていくべきか悩んでいる居宅介護支援事業所の管理者の方、地域包括支援センターへの入職を考えているけど自分に虐待対応が出来るのかと不安を感じている方、などにオススメの記事となっております。
はじめに
こんにちは。衣笠翔太@ソーシャルワーカーと申します。
私は独立型社会福祉士として、現在活動しています。
独立型社会福祉士として名乗るからには、どこかに所属しながら給与をもらう形を早くに脱し、自身で事業を起こし、収入を発生させる。そこを目指していかなければなりません。
これまで雇用された会社員としての働き方しか経験したことのない私には、自分で売り上げを作っていくということがまだまだ困難な状況ではありますが、「まずは少額でもいいから自分のアウトプットをもとに売り上げをつくってみよう」と考え、自分の経験で価値提供できそうな高齢者虐待対応に関する話をケアマネジャー向けの研修としてまとめ、有料noteで売ることにしました。
しかし、高齢者虐待対応研修に関する記事は他にも多数ある。
ただ解説しているだけでは、他と比べて差別化できない。
そこで、他と差別化するためにも、自身の経歴やこれまでの体験をなるべく明らかにしていくことにしました。
そのため、この高齢者虐待対応研修を一読いただけたら
高齢者虐待対応において大切なこと・行政や地域包括支援センターと連携しながらどのように支援すればいいのか
を知っていただけるかと思います。
①高齢者虐待防止法とは?

高齢者虐待防止法の大きな目的としては4つ。
・高齢者虐待の防止(予防、啓発)
・高齢者虐待防止等に関する国等の責務を明確化
1.関係省庁、その他関係機関、民間団体との連携強化を行うこと。
2.専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等を講ずるように努めること。
3.高齢者虐待に係る通報義務について必要な広報啓発活動をすること。
を明記している。
・虐待を受けた高齢者の保護
高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援する。
・養護者への支援
高齢者本人とともに養護者を支援することが大切。
虐待の解消と高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けて、養護者への支援を適切に行うことが必要。
この研修では主に「虐待を受けた高齢者の保護」「養護者への支援」に重点を置いて解説する。

まず高齢者虐待には2種類あり、
①養護者による虐待
②要介護施設従事者等による虐待
がある。
①養護者による虐待
養護者とは、高齢者の身辺の世話や金銭の管理等を行っている高齢者の家族、親族等。同居しているかどうかは問わない。
②養介護従事者等による虐待
直接介護に携わる職員、経営者、管理者からの虐待。
今回の研修では、①養護者による虐待について触れる。
②どのような行為が虐待にあたるか
高齢者虐待の類型について振り返る。
実際に私が高齢者虐待対応を行った事例をもとにお話する。

〇「夫のために・・」度を超えたリハビリ【身体的虐待】
脳梗塞で半身麻痺があるAさん。
妻は少しでも元気になってほしいとの想いから、介護保険サービスでのリハビリ以外にも、自費サービスによるリハビリを導入するが、Aさんは過剰なリハビリに疲労感が強く、「もうしんどい。こんなに運動できない。」と話す。それに対し、妻は「そんなこと言ってたら、良くならない!」とAさんに強く当たり、リハビリを強要する。
養護者である妻の「Aさんに元気になってほしい」との想いについては理解できるが、脳梗塞発症から1年以上経過し、状態が固定化していたAさんにとってはかなり過酷なものであった。
妻の想いに理解を示しながらも、どのようにAさんの想いや身体状況を理解してもらうか。
ケアマネジャー、介護事業所だけでなく医療関係者にも協力を仰ぎ、Aさんの想いの言語化や、Aさんの身体状況を医療的な視点から妻へ伝えてもらうなど様々な機関と連携しながら、Aさんと養護者である妻への支援を検討した事例であった。

〇見て見ぬふりも、ネグレクト【ネグレクト】
Bさんは、娘、孫(男性、20歳前後)との3人暮らし。
ケアマネジャーより、「食事が十分に提供されていない様子」と相談あり。
訪問すると、Bさんの枕元には、コンビニのおにぎりが一つ。
話を聴くと、それが1日分の食事とのこと。
娘とは全く連絡が取れず、自宅訪問時にも会えない。
たまたま自宅にいた孫とは接触を取ることは出来たが、孫自身はBさんへ提供されている食事の状況の理解はあったが、何ら手立ては行っていないと話される。
孫に悪気はなく、どのように対応したらいいのかわからない。どこに相談したらいいのかがわからなかったのではと話を聴いて感じた。
ただし、状況が理解できているのに傍観していただけとなり、虐待認定に係る事実となる。
地域の総合相談窓口である地域包括支援センターがまだまだ周知されていないこと。知っていたとしても、”相談する”という行動を起こすハードルの高さが高くあるということを感じた事例であった。

認認介護の末に【心理的虐待】
Cさんは夫と2人暮らし。
Cさんは認知症を発症。夫は介護者となる。
献身的にCさんの介護を夫は行っていたが、夫自身も認知症と診断される。
夫の認知症進行とともに、Cさんへの威圧的な態度や暴力もみられるようになる。
夫の認知症進行に伴い、これまで出来ていた家事やCさんの介護に支障が出てきていたため、Cさんの介護サービスの増加や、夫の介護保険申請を勧めていたが、なかなか受け入れてくれない。
夫は、Cさんの介護による負担とともに、自身の認知症の発症・進行していく状況をなかなか受け入れられなかったのではないかと感じる。
その後は、日々変わっていく状況に対し、夫とともに「どうしていきたいか」と話し合い、方向性を決めていく中で、徐々に自身で介護申請やサービスの利用を選択していかれた。
時間は要するケースであったが、本人支援とともに養護者支援の必要性や大切さを印象づけられたケースであった。
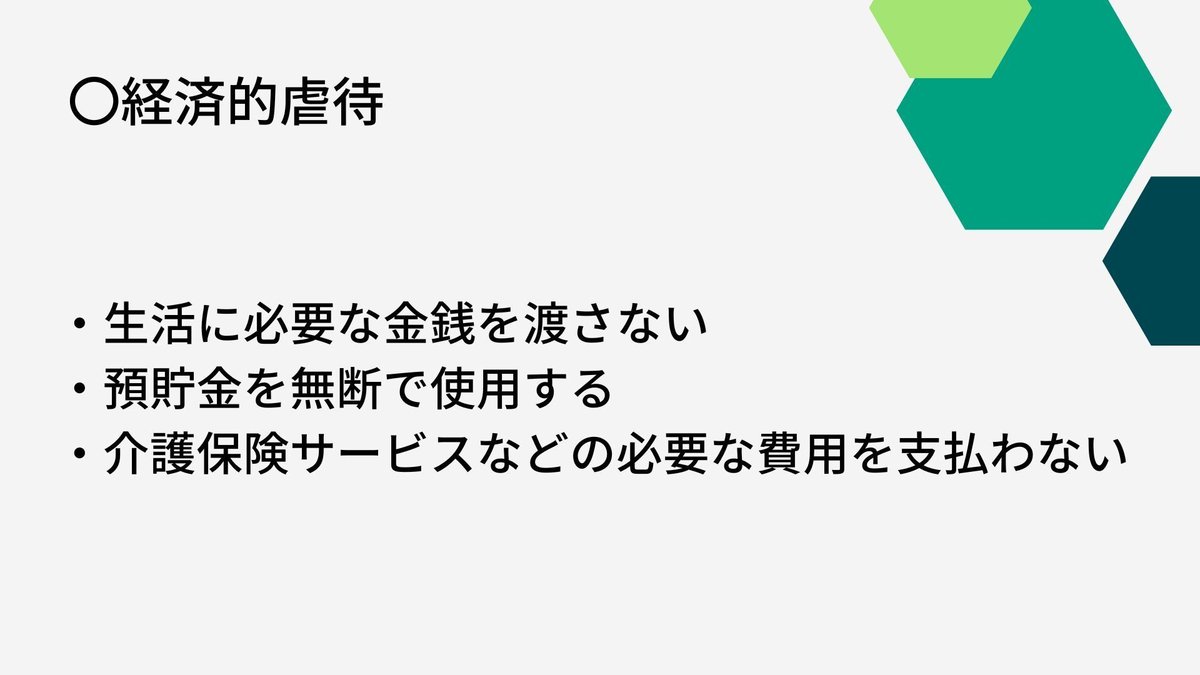
一緒に住んでいたらお財布は一緒??【経済的虐待】
Dさんと息子の2人暮らし。
Dさんはデイサービスを利用しているが、利用料金を滞納していること。
理由としては、息子が抱えている借金返済に本人の年金が利用されていることが原因と判明する。
虐待状態を解消するために、息子の債務整理がキーとなっていたが、なかなか応じてくれず、「自身で仕事を目いっぱいして返していく」と頑なに話される息子が印象的であった。
息子自身も持病を抱えていたため、余計に無理できないのではないかと心配していたので、尚更であったが、結局弁護士への相談には至らなかった。
息子の「相談した方がいいのはわかってる。けど、それは出来ないんです」と話されたその言葉の意味が掴めなかったことが心残りであった。
③高齢者虐待かもしれないと思ったときは

「高齢者を受けたと思われる高齢者を発見した人は市町村(地域包括支援センター)に速やかに通報する義務がある」
虐待があったと断定されてから相談するのではなく、思われる事象が発生した段階で、速やかに相談することが求められている。
「高齢者本人や養護者に虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利侵害が確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する」
虐待している、されているといった自覚は問わず、客観的に確認できる場合は虐待疑いと考えて、対応を検討する必要がある。
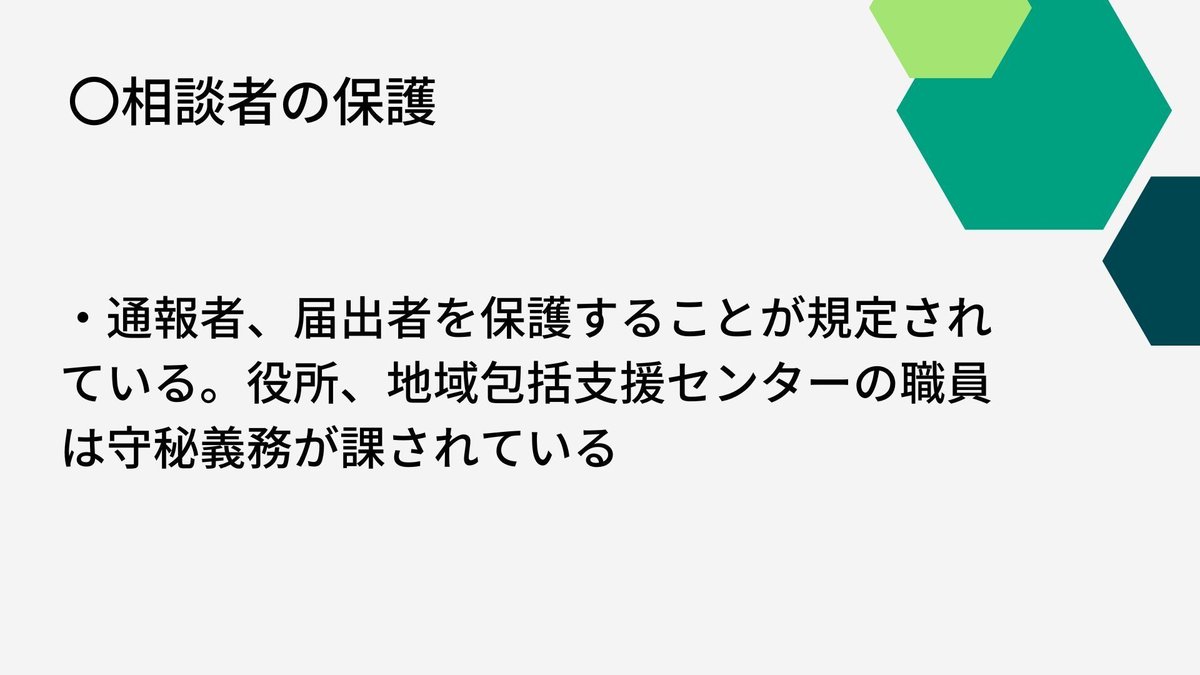
通報・届出を行うことで、高齢者本人や家族などと関係性が悪化してしまうのではないかと懸念し、通報・届出をためらってしまうことがあると聞くが、役所や地域包括支援センター職員には守秘義務が課せられており、相談者の保護を図るように言われている。
関係性を壊したくないという気持ちもわからなくないが、
「権利侵害が起こっている状況を放置しておくこと」と「本人や家族とよい関係をキープしていくこと」どちらが大切かを考えてみるべき。
④高齢者虐待対応の大きな流れ
〇初動期

目視や写真、記録、聞き取りなどから速やかに事実確認を行い、高齢者の生命や身体の安全確保など緊急性があるかの判断を行う。

事実確認から得た情報をもとに、「虐待の有無」「緊急性の有無」を判断。
高齢者の生命に関わるような事態がみられる場合は、入院・措置入所などを行い、本人の生命や身体の保護を優先し、本人と養護者を離す場合もある。
〇対応期


「虐待の解消」と「安心して生活できる環境整備」を目指し、計画を立案し、実行する。
そこで大切になってくるのが、「養護者支援」である。
在宅で養護者による虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉えてしまいがちであるが、介護疲れや養護者自身が何らかの支援(経済的な問題、養護者自身に障がい・疾病があるなど)を必要としている場合も少なくない。

また、虐待の背景として
・他の家族等との関係性
・経済状況
・医療的課題
・近隣との関係
など様々な問題が虐待の背景にあることを理解しておく必要がある。
高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の状況からその家庭が抱えている問題を理解し、高齢者や養護者・家族に対する支援を行うことが必要となってくる。
そうなってきた際に、ケアマネジャー・介護事業所・行政・地域包括支援センターだけでは対応できない課題も表出してくる。
その際は、関係機関や他の専門職と連携し、チーム対応を行っていく必要がある。
〇終結期

立案した支援計画の実施→評価→再度計画立案・実施を行っていく中で、「虐待状態の解消」「安心して生活できる環境整備」が確認できたところで、虐待対応は終結し、通常のケアマネジメントへ移行していく(行政や地域包括支援センターの介入は終了)。
⑤もし自分が担当するケースで虐待を疑うようなことがあったら

実際、自分が担当するケースで「もしかして・・・」といったことがあると、相談することをためらうことがあるかもしれない。
しかし、冷静に何を優先すべきかを考える必要がある。
現状が続くことで本人の権利が何らか侵害されている(可能性がある)のであれば、行政や地域包括支援センターへの通報・相談が必要。
虐待対応をこれまでしてきた経験から言うと、虐待ケースの大半がケアマネジメントだけで課題解決していくことが難しいと感じている。
そのため、早期に相談し、様々な人を巻き込んで対応を検討していくことが必要と考える。

行政・地域包括支援センターへ通報・相談するにあたって、まずは事業所内で相談してほしい。
それは担当ケアマネジャーだけでこのケースを抱えるのではなく、組織として対応を検討してほしいということ。そして、一人のケアマネジャーのみに負担が集中しないよう支え合えるシステムを作っておく必要があることからである。
⑥最後に
以上、私の経験から高齢者虐待対応の重要性についてお伝えしました。ケアマネジャーや地域包括支援センターの連携が不可欠であること、早期の相談が重要であることをご理解いただけたでしょうか。高齢者の権利擁護には私たち一人ひとりの積極的な関与が求められます。ぜひ、他の記事やnoteの更新もチェックして、高齢者虐待対応に関心を持ち続けてください。あなたの一歩が社会の良い変化に繋がります。
いいなと思ったら応援しよう!

