
岬鷺宮先生『あした、裸足でこい。』読書感想文

──『予測』は、この世で一番面白いゲームだ。俺は飽きずにそれを繰り返してきた。──
その一文に私は、はっとさせられました。
これは『あした、裸足でこい。』の主人公、坂本巡の言葉です。
物語の序盤で坂本巡はこれまで自分の行ってきた数々の『予測』を思い起こします。
明日から本気を出して勉強をすれば、試験で悪い点を取ることを回避できるのでは。
もっと周囲に溶け込む努力をすれば、今からでも友達ができる可能性があるのでは。
次の休み時間に、あの人に声をかけることができたなら、復縁できるかもしれない。
しかし幾多の『予測』は行動を伴うことがなく、結局それらはただの『妄想』として霧散していくのでした。
そんな妄想と共にあった三年間の高校生活ともお別れである卒業式のあと、坂本巡は、かつて交際していたこともあったのに今は世界的なアーティストとして成功しているため疎遠になっていた少女、二斗千華が遺書を残して失踪したことを知ります。
茫然とする坂本巡は導かれるように思い出の部室に足を運び、そこで奇妙な体験をします。
気づけば目の前に、桜と少女。
初対面のように少女は名乗ります。「わたし、二斗千華っていいます」
そこで坂本巡は自分が高校一年生の春に戻ってきたことを理解します。
ずいぶん都合のいい話だな、と思いました。
ここから坂本巡は過去の経験と反省をもとに、二斗千華を失わないよう、学校生活を更新していくのは目に見えています。
娯楽作品なのでそうあるべきなのはわかります。
とはいえ、どこか冷めた目で物語を追っていると、ほどなく私は己の浅はかさを痛感しました。
人生における選択とは、失敗と成功の二択ではありません。
左に向かって歩いた結果がよくなかったからといって、右に向かって走れば上手くいくかといえば、そうではないでしょう。
そこにあるのは正解ではなく、別の課題です。
やり直しの世界で坂本巡の前には次々と未曾有の問題が降りかかります。
せっかく与えられたチャンスなのに、またくじけそうになる。
それでも立ち上がることができたのは、予測を妄想で終わらせない信念が今の自分にはあるから。
この本を読んでいるとき、不思議な気持ちが胸にあふれてきました。
今、私は中学一年生です。
もしかして私はもう一度、中学一年生をやり直しているのかもしれない。
そんなことを思うようになりました。
私も坂本巡のように毎日『予測』をしています。そしてそれを行動に移せずにいます。
私にとっても『予測』は都合のいい妄想でしかないのです。
今のままだと私は中学三年生になって卒業式のあとで、こんなことを考えているかもしれません
何もない三年間だったな。もし、もう一度やり直せたら──。
こんな話を聞いたことはありませんか?
あなたはきっと十年前、五年前、いや一年前でいいから人生をやり直したいと思っているでしょう。
たった今、戻ってきたんですよ。その未来から。
この物語が素敵なのは、よりよい明日のために予測を実行するべし、という結論だけを採用していないところです。
あとがきで作者の岬鷺宮先生は、こんなことをいってくれています。
油断と惰性に任せた日々も、それはそれで美しいと。
全てを肯定してくれる。だけど、きみのやりたいことはもうわかっているんだろう? と物語でそっと気づかせてくれる。
岬鷺宮先生は非凡な作家だと思います。
これからの人生できっと私は何度も迷うでしょう。逃げるでしょう。立ち止まるでしょう。間違うでしょう。
だけど再び歩き出せるでしょう。
この一冊が、私の道標になってくれるから。
品川区にある中学校に通っている一年生の女子、逢赤依流の提出したこの感想文はその年の全国中学生読書感想文コンテストにおいて見事、最優秀賞を受賞して、大きな話題を呼んだ。
ちなみにこの感想文には学校の教師やコンテストの審査員たちの知らない秘密が一つある。
感想文を書いた時点で依流は『あした、裸足でこい。』を全く読んでいなかったのである。
一ページも、一行も、一文字も読んでいなければ、あらすじも知らない、表紙すら見ていない。
タイトルだけで、いつも靴下をはいて土俵に上がろうとする相撲部員とそれを叱る教師のコメディー作品だと想像していた。
依流は持ち前の才能でネット上にアップされた『あした、裸足でこい。』のAmazonレビュー、ファンの感想、掲示板で交わされた考察を抽出して、一本の感想文としてまとめ、それが高く評価されたのだ。
大人たちには絶対わからないとたかをくくっていたのに、この秘密を最もバレてはいけない相手にバレてしまっていた。
殺し屋である。
体育館で校長先生から表彰され、鼻歌まじりで教室に帰ろうとしていたところ、素早く首根っこをつかまれ体育館の裏に連行される。
壁にたたきつけられ、尻もちをつく。立ち上がることも許されず眉間に銃口を押しつけられた。
依流が見上げた先には『殺し屋 女 金髪』で検索したら出てきそうなスリムで冷酷なオーラをまとった20代前半とおぼしき女性。
「お前、あの感想文、読まずに書いただろ?」
体温をまるで感じない声色で殺し屋は依流を尋問する。
害虫駆除業者の全員が害虫を憎むあまりその職業を選択したかどうかはわからない。
しかしこの殺し屋は人間が嫌いという理由で殺し屋を営んでいた。
だから、殺しに躊躇はない。
だが、この殺し屋は本を愛していた。
誰かの感想を読むのも好きだった。
同時に憎んでいるものもあった。
学生がなんらかのコンテストに応募した読書感想文である。
本人の意思の見えない、その本が好きで書いたと思えない、親や教師からの指図を感じる紛い物。
あるいは、明らかに作品を読まずに誰かの感想をコピー&ペーストしてきたような模造品。
どちらも机の奥で干からびてカビのはえた食パンのように目もあてられない悲劇である。
そういうことをするガキはいないほうがいい。
いつもの殺し屋なら、さっさと引き金を引いているところだが、今回に限り、解決しておきたい疑問があった。
「一つ答えろ。お前のあの感想文、わざと不完全にしただろう? どうしてだ?」
「…………」
殺し屋の言葉に依流は一瞬驚いた表情を見せたが、問いには答えなかった。
「所々文章のつながりが妙だし、オチの大どんでん返しにふれてないのも不自然だ。コンテストで点を取りたいならもっとちゃんとできたはずだ。だけどお前はそれをしなかった。つまりあの感想文には大人たちに評価される以外に何か別の目的があった。それはなんだ?」
「…………」
「……わかった。死ね」
「待ってください!」
およそ五〇メートル先から少女の叫び。
殺し屋と依流は同時にそちらに振り向く。
「……枝鈴ちゃん」と依流は声をもらす。
小野道枝鈴は一目散に駆け寄り、依流と殺し屋の間に割って入る。
「何してるんですか! 依流ちゃんから離れてください!」
枝鈴は殺し屋に抗議する。
依流と枝鈴はクラスメイトだ。
「お前には関係ない」
「関係なくないです」
依流と枝鈴は幼馴染でもある。
「こいつは物語と、それを愛する者を汚した。万死に値する。だが残念なことに人は万回も死ねない。だからせめて私が一回殺す」
「それを愛する者?」
「岬鷺宮の『あした、裸足でこい。』の感想文だ。あれはこいつが書いたものじゃない。こいつは他人の感想を盗んで不当な利益を得た。作品の作者だけじゃない。感想文の作者のためにもこいつを殺す」
「だったら猶更やめてください! 私は怒ってませんから」
「……お前があの感想文の作者なのか?」
「そうです」
「だったら話は早い。お前が殺れ」
殺し屋は拳銃のグリップを枝鈴に握らせようとする。
「やりません!」
「なぜだ? 腹が立たないのか?」
「もう一度いいますけど、怒ってないです。でも知りたいです」枝鈴は依流と目を合わせる。「どうして、こんなことしたの?」
「……だって枝鈴ちゃん、夏休みの宿題で、読書感想文、提出しなかったから……あのときのこと、まだ引きずってるんでしょ?」
殺し屋は訊ねる。「あのとき、とは?」
虫歯でも疼いたみたいに言い淀んだ枝鈴だったが、覚悟をきめて、ささやくように語りはじめる。
「私、岬鷺宮先生の大ファンなんです。それで小学生のとき『三角の距離は限りないゼロ』の感想文を一生懸命書いたら、クラスのみんなに真面目だってからかわれたり、親に書いてもらったんだろうって疑われたりして……」
声はそこでとまった。
殺し屋は知っている。
圧倒的な読書量と作品への愛情と熱意をもって執筆されたため、その年齢に似つかわしくない感想を書き上げてしまう子供がいることを。
「だから枝鈴ちゃんは感想文、書かなくなった。でも枝鈴ちゃんが岬鷺宮の感想を書かないなんてありえないから、絶対どこかで書いてるってわかるから、だからネットで探したの」
依流は持ち前の才能でネット上にアップされた『あした、裸足でこい。』のAmazonレビュー、ファンの感想、掲示板で交わされた考察の中から枝鈴が書いたであろうと思われる文面だけを抽出して、一本の感想文としてまとめ上げた。
「不思議だったんだけど、どうして依流ちゃんは私が書いた文章がわかったの?」
「そ、それは……」依流は頬を赤らめてうつむく。「わ、わたしは枝鈴ちゃんの感想文のファンだから……」
好きな作家の文体なら、わかるのだ。
「依流ちゃん……」
「ねえ、枝鈴ちゃん! 枝鈴ちゃんが感想文を書かなくなってから私たち、ちょっと距離ができちゃったけど、また小学生のときみたいに好きな本のお話とか一緒にしようよ。もっと仲良くしようよ、二斗千華と五十嵐萌寧みたいに!」
「……う、うん。私もずっとそうしたいと思ってた……あれ? 依流ちゃん、それって『あした、裸足でこい。』のエピソードだよね? どうして知ってるの? 読んでないはずなのに」
「あんなすごい感想文読んだら、読まずにはいられないでしょ」
感想文を組み立てた時点では未読だったものの、そのあとすぐ依流は『あした、裸足でこい。』を読み耽ていた。
「そうだったんだ……そういえば依流ちゃん、ネットにアップした私の文章を全部くっつけなかったのはなんで? 見つけられなかったとか?」
「全部見つけたよ。だけど一番好きな部分は私だけのものにしたかったの。それに完璧な状態じゃなくても枝鈴ちゃんの感想文は日本一だってみんなに認められたでしょ。だからもう怖がらないで、これからもどんどん感想文を書いて読ませてよ。だけど本当は誰かのためじゃなくて、私だけに読ませてほしいな……なんて」
「依流ちゃん……」
「枝鈴ちゃん……」
見つめあう中学一年生、女子、二人。
「──う」
暗殺でもされかけてるみたいに、殺し屋は心臓あたりを強く掴む。
「どうしました?」と訊ねる枝鈴。
「……いや、急にドストライクな百合がはじまったせいで動悸がしただけだから心配ない……よし、おちついた。さあ、キスとかしていいぞ」
「するわけないでしょ」依流は殺し屋のように冷たくはなつ。
よいものを見させてもらった。
まだ今日のノルマが残ってるので、ちょっとこれから、こんなやついないほうが世のためだってクズを何人か殺してくる。
そういい残して、殺し屋は去っていった。
殺し屋にとっての殺しとは、駅前でティッシュを配ってる人のティッシュみたいなものなのだろうかと依流と枝鈴は疑問を持ったけれど、追及はしないことにした。
帰り道。
「だけど、本当にびっくりしたよ」身振り手振りで依流は伝える。「あんな気になるところで終わるとは思わなかった」
『あした、裸足でこい。』第一巻の感想である。
「次はもっとすごいよ」とっくに読了済みの枝鈴は、どこか得意気だ。
「じゃあこれから枝鈴ちゃんの家にいって、つづき読ませてよ」
「もちろん」
依流と枝鈴は手をつないだ。
依流は左手、枝鈴は右手。指と指を自然に絡めて。
嬉しくなって、枝鈴は口を開く。
「二巻もすごいところからはじまるんだよ。二斗のモノローグがね──」
その刹那、枝鈴の首筋に冷たい感触があてられた。
見ると、細長い刃。
それは、日本刀だった。
「……お前いま、ネタバレしただろ?」
『殺し屋 女子高生 日本刀』で検索したら表示されそうな少女が、絶対零度の殺意をあらわにして現れた。
こちらの女子高生、見た目にたがわぬ殺し屋である。
この殺し屋も物語を愛していた。
ゆえに、ネタバレする者は無条件で排除することを信条にしていた。
依流と枝鈴。
放課後はまだおわらない。
おまけ








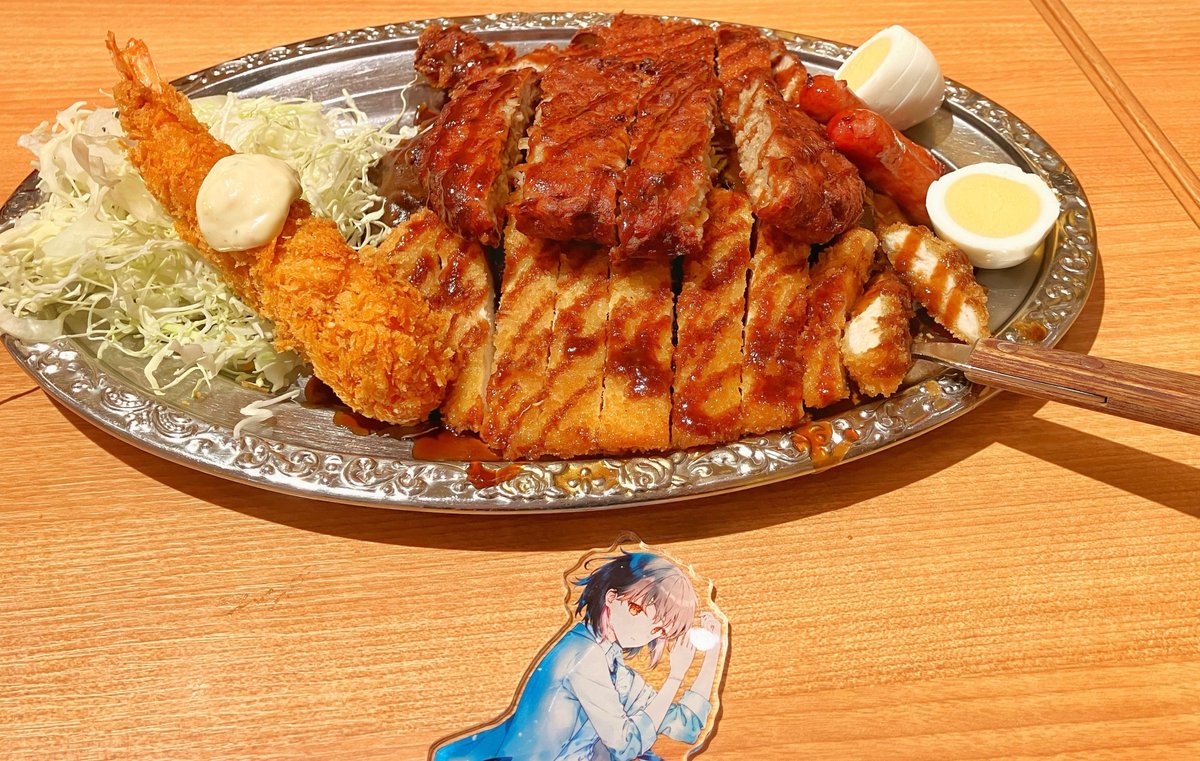
主人公がいっぱい『予測』するお話
