
有象利路先生『組織の宿敵と結婚したらめちゃ甘い』読書感想文
「うまい棒にいつも敗北してるんだ」
付き合いはじめてそろそろ一年になる先輩が神妙な面持ちで、ずっと隠してきたけど大事な話があると耳元でささやいてきたので、いったい何を言ってくるのか身構えると、そんなことを白状してきた。
嬉しいニュースでも悪い報せでもなく、どうでもいい自白だった。
十七年生きてきて、うまい棒に負けた人を見たのは、はじめてだ。
ちなみに、うまい棒に勝った人にも会ったことはない。
そもそも勝敗条件が不明だ。
言いたいことを言ってすっきりしたのか、先輩は懺悔を終えた罪人みたいに晴れた表情でいつも食べているお菓子の袋を開けて、中身を口に放り込んでいる。
「聞くのもバカバカしいんですけど、なんですか、その、うまい棒に負けてるって」
「お菓子を取り扱ってる店舗にいけば、ほぼ確実に、うまい棒はおいてあるだろ?」
「そうですね」
「ほしくなるだろ?」
「時と場合によりますね」
「私はいつもほしくなるんだ」
「じゃあ、買えばいいじゃないですか」
「なぜかいつも違うのを買ってしまうんだ」
「というか先輩、いつも同じの買ってますよね」
子供のラクガキみたいなイラストのついた、子供がふざけてつけたような名前のお菓子を先輩は毎日欠かさず食べている。
商品名とパッケージはアレだけど、その味は唯一無二でばつぐんにおいしいのがくやしい。さらにそのお菓子には一つの謎がある。
「先輩がいつも食べてるそれ、どこで買ってるんです?」
うまい棒と違い、どの店にも並んでいないのだ。スーパーでも駄菓子屋でも見たことがない。
「ひみつ」
「いじわるしないでくださいよ」
「いじわるじゃないよ。きみと一緒に食べるのが好きなんだ」
そういうと先輩は一粒を私の口に入れてきた。
やはり、おいしい。
そしてやはり、私はこの人が好きだ。
小学三年生のとき、深夜にたまたまテレビでやっていた少女歌劇レヴュースタァライトというアニメにハマった。
そこに登場する天堂真矢というキャラに一目ぼれをして、どういうわけか当時の私は、自分はきっと高校生になれば天堂真矢のような女性とお付き合いするのだろうと確信していた。
中高一貫の女子校を選んだ理由の一つはそこにある。
別に男の子が嫌いというのではなくて、女の子が好きなのだ。
とはいえアニメと現実は違うし、人生は妄想通りにいかない。
実際付き合うことになった先輩は天堂真矢と見た目も性格も違う。
外観は神楽ひかりっぽいし、性格は先輩でしかない。
「おや?」と先輩は首をかしげる。「腕のそこ、どうしたんだい?」
先輩の視線の先は私の右手首に向けられていた。
そこを見て、私も、おや? っとなる。
おそらく油性ペンのものと思われる塗料が少しついていた。
まあ、家で洗えばいいかと思っていると、おもむろに先輩は私の腕に顔を近づけて、口を開いて舌を出し、該当の箇所を拭うように舐めた。
「ちょっと先輩、きたないですよ!」
舐められたことが不快なのではなく、先輩の口がよごれることを心配しているのだ。
「そうだね。人のよごれを舐めるなんて、そもそも気持ち悪くて出来るわけない。でもそれをしたいと思えるのは……愛があるからだよ」
なんだか唐突に芝居がかった口調と態度になる。
こういうときの先輩は、あれだ。
「それも有象利路ですか?」
「組織の宿敵と結婚したらめちゃ甘いの288ページからの引用だよ。少しアレンジしてるけどね」
早速、元ネタを教えてくれた。きっと言いたくて言いたくてうずうずしていたのだろう。
「有象ごっこがやりたくて、私の手を舐めたんですか?」
「それもあるけど、舐めたかったのも事実だね。一石二鳥だよ」
「だからって急に舐めないでくださいよ。ここ学校ですよ?」
「別にいいじゃないか、はじめてのときだって放課後の教室で──ぐむ」
袋ごとお菓子を先輩の口に押し込む。
「最低。もう知りません」
私は肩を怒らせながら下駄箱に向かう。
先輩はお菓子をたいらげてから、私を追いかけてくる。
「というわけで、今日こそうまい棒に勝とうと思う」
というわけで、学校の近所の駄菓子屋の前にいる。
「がんばってください。応援してます」
私は心の底からどうでもいいという仕草で見送った。
店に入って一分もしないうちに、先輩は手ぶらで戻ってきた。
まさか、もう負けてしまったとでもいうのだろうか、うまい棒に。
「お金、かして」
空っぽの手のひらを差し出してきた。
「いやですよ。それに先輩、お金持ちじゃないですか」
「現金しかダメっぽいんだよ。私、現金持ち歩かない主義だし」
嫌味の一つや二つや三つくらい言ってやろうと思ったものの、それも面倒なので、財布の中から百円玉を取り出して先輩の手のひらに乗せる。
子供におこづかいをあげる親の気分だ。
「えー」なぜか不服な表情の先輩。「千円かしてよ」
「なんでですか。うまい棒って一本十五円くらいですよね?」
「他にもいろいろ買いたいものを見つけたんだ」
「……今回だけですよ?」
渋々、お札を渡す。
「サンキュ」
海面にひょっこり顔を出した魚をついばむ野鳥のような動きで先輩は私のお金を奪うと、スキップしながら店内へ消えた。
数分後、とぼとぼと店から出てきた先輩の手には、巨大な麩菓子、アニメキャラのお面、他にも『なつかしいお菓子』でググったら出てきそうな品々が確認できるけれど、肝心のうまい棒が見当たらない。
「ごめん、負けた。次は勝つからもう千円かして?」
パチンコで惨敗したクズみたいなこと言いだしましたよ、この人は。
「いやです。ダメです。かしません」
「そんなこと言わないでよ。ここであきらめたら、もう死ぬまでうまい棒に勝てない気がするんだ」
「じゃあ先輩のお葬式には棺桶いっぱいのうまい棒を詰めてあげますよ」
「有象利路作品もお願ね」
「はいはい」
私は先輩に背を向けて、距離を取る。
「あれ? もしかして機嫌悪かったりする?」
ほんのちょっとだけ慌てた様子で、先輩は私に近づく。
「別に、どこも悪くないですよ」
「ほんとに?」
先輩は私を背中から抱きしめてくる。
「いま、そういうのやめてください」
「ほら、やっぱり機嫌悪いじゃん」
「……」
私は沈黙で壁を作る。
「そこにちょっといい喫茶店あるでしょ、パフェでも食べる? ごちそうするよ?」
「……」
わざとらしく長い間を作ったあとで、私はうなずく。
ときどき私はどうしようもない。
先輩を試すようなまねをして、甘やかしてほしくなる。
これが原因でいつか愛想をつかされるのでは危惧したこともあったけど、今はもう、そういう心配はしていない。
私の浅はかな策略など先輩はとっくにお見通しで、先輩自身も後輩とのたわむれを楽しんでいる気がするからだ。
そんなことより、このパフェはおいしい。
明るく気品ある店内で、シャンデリアの妖精みたいなフルーツパフェをほおばって、私は幸せだった。
パフェはフランス語のパルフェが語源とされていて、そのパルフェは英語でパーフェクトと同意であり、つまりパフェはパーフェクトな食べものなのだ。異論はない。パーフェクトだ。
「おいしい?」先輩は訊いてくる。
「はい、おいしいです」生クリームのたっぷりついたフルーツをぱくり。
「幸せ?」
「はい、とっても幸せです」このプリンの部分も絶品。
「そのパフェ、5980円だって。なんのためらいもなく一番高いの注文してくれてありがとう」
「どういたしまして。6000円でもおかしくないくらい、おいしいですよ」
「それはよかった。20円もお得だ」
「先輩」
「うん?」
「あーん」
食べやすいサイズにカットされたメロンをスプーンにのせて、先輩の口のそばまで運ぶ。
先輩はきょろきょろ辺りを確認して、ペロっとカメレオンみたいにそれを口にしまいこむ。
二人きりのときは王様みたいに振る舞うくせに、まわりに誰かいるときの先輩はなんだかかわいくなる。
「ところで、今度の日曜日に神社いこうよ」
「神社ですか? 急にどうして?」
「決まってるだろ? 神様に新年のご挨拶だよ」
「今度の日曜ですよね? 新年どころかクリスマス前ですよ?」
「クリスマスケーキを一番おいしく食べられるのはいつだと思う?」
「え? それは、クリスマスイブ、とか?」
「正解はクリスマスの一週間前だよ」
そのタイミングで食べるのはもはやクリスマスケーキではなくて、普通のケーキなのでは? と問う私に対して、先輩はこう答えた。
クリスマスのケーキは主力商品だ。だから量産して作り置きされてる。
生の洋菓子は完成した瞬間から鮮度は失われていく。
つまりクリスマスやイブに買うケーキはお店に並んだばかりのものでも、すでにある程度、味が落ちた状態なのだそうだ。
これは量販店に限らず、良心的な専門店であっても、いつもより桁違いの数を作るため、出来栄えに多少の当たりはずれが生じているという。
専門店でクリスマスの一週間前に購入するケーキ。
それが先輩のたどり着いた最適解。
職人さんの心にまだ余裕があるのと同時にそろそろ本番に向けてスイッチも入っているので、それはそれは見事なものが仕上がるという。
先輩の主張に一定の説得力はあるものの、クリスマス当日の夕方に、半額シールの貼られたケーキを買って帰って、翌日、ちょっとしなびれたそれを食べるのがたまらなく好きな私は少し居心地がわるい。
「神様へのお願いも同じとは思わないかい?」
「えっと、つまり、年明けと同時に、どばっとみんなから願いを聞かされても対応が雑になりがちだから、誰もいないときにいけば、願いを叶えてもらいやすくなると?」
「正解。よくわかってるじゃないか」
「願いとケーキは違いますよね?」
「同じだよ。みんな、それが大好きじゃないか」
「ただの言葉遊びじゃないですか」
「それにこの説は実証済みなんでね」
「?」
引っかかる言い方だったけど、先輩とお出かけは単純に嬉しいので、私はその日を楽しみにした。
当日。
品川から山手線に乗って、秋葉原でおりる。
「これから行く場所って、神田明神ですよね。私、はじめてですよ」
「実は私もなんだ。今回の祈願にはもってこいの場所だと思ってね」
「どんなことをお願いするんです?」
「有象利路先生のさらなる飛躍だよ」
やっぱり。
とうか、先輩の願いなど他にないのだろう。
「これを言うのは、きみにもはじめてだけど──」
目的地への道中、先輩は語りはじめる。
先輩が中学一年生のころ、近所の本屋さんにて。
スタッフおすすめコーナーの棚で『ぼくたちの青春は覇権を取れない。 -昇陽高校アニメーション研究部・活動録-』という一冊があった。
先輩はその本に惹かれた。
厳密にはパッケージに描かれている女の子のふとももに。
買って帰って読んでみて、ベッドの上でひっくり返った。
これまで読んだことのない物語で、しかもとびっきり面白い。
当然その存在を信じて疑わなかった続編は、どれだけ検索しても出てきてくれない。
どうやらぼくたちの青春は派遣を取れない。にはつづきがないと知って、自律神経が乱れ、めまいを覚えた。
ただ幸運だったのは、作者の有象利路の作風は先輩と相性がよく、先輩は作品と同時に作者のファンになったこと。
不運だったのは、有象利路の才能は世間的にまだ広まっていないようで、刊行のペースが不定期ということ。
これはよくない。もっと世界に有象利路を知らしめなければ。
これは大きな損失だ。
どうすればいい?
SNSでバズるとか?
そんなものは一過性であり、頼りない。
そもそも人の力には限界がある。
ではどうする?
神様の力でもかりる?
いい考えだ。
──というわけで、今回のこれを思いついたのだそうだ。
「先輩」話を聞き終えて、私は、ゆっくりと伝える。「その話、もう二十回は聞かされてます」
気づけば、目的地は目の前に。






しっかりお願いを済ませて、秋葉原に戻ると、やたら目立つ看板と遭遇。







とりあえずこれを飲んでおけばラーメンのカロリーはチャラになるのではと近くのコンビニで買ったホット緑茶を飲んでいると、先輩はスマホとにらめっこを開始する。
「どうかしました?」
「有象作品にもコラボの話とかこないのかなと思ってね。新作のイラストなんか汎用性高そうだろ?」

慣れた手つきでスマホを操作して、先輩は架空のコラボイラストを作成していく。いくつか御覧いただこう。



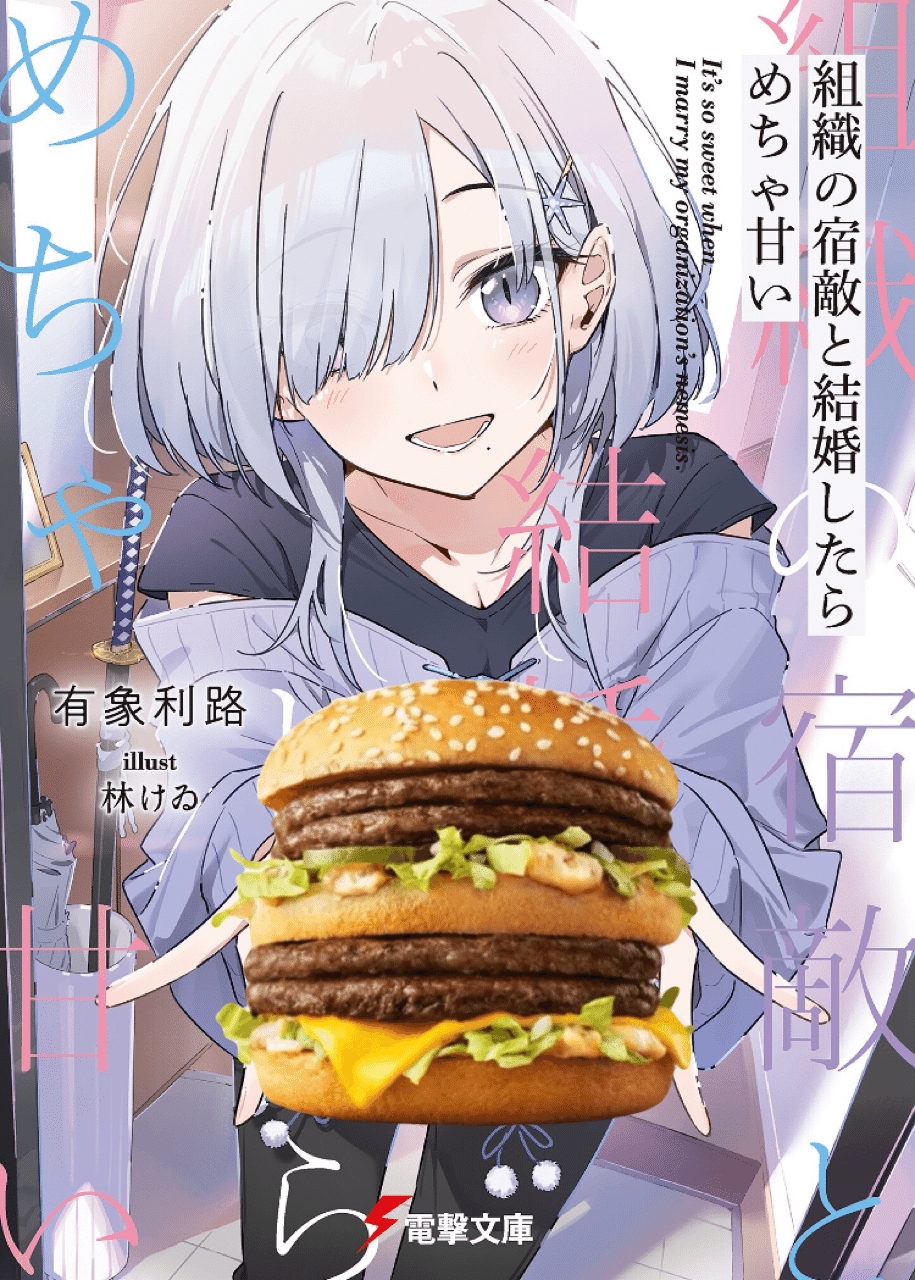











個人的な感想だと、オリジン弁当の完成度が高いと思う。
実際にありそうだ。

「そういえば先輩」
「うん?」
「今回のこの早めの参拝には効果が実証済みだみたいなこと言ってたじゃないですか」
「うん? ああ、そうだね」
「本当なんですか?」
「本当だよ」
「どんなお願いが叶ったんですか?」
「きみだよ」
「え?」
「私は生まれつき他人に興味が持てなくてね。どこかこわれてるじゃないかって思うこともあったけど、それで困ったこともないから気にしなかった。でももしこんな私にも素敵な人みたいな存在がいるとしたらぜひとも出会わせてほしいってお願いしたんだ。そしたら次の日、学校できみをみつけた。ベンチに座って。有象利路の本を読んでるきみを」
誰か教えてほしい。
きっとあなたは知ってるはずなんだ。
漫画、小説、アニメ、ゲーム、なんでもいい。
少なくとも私は知らない。
これより素敵な恋の告白を。
先輩も教えてはくれないだろう。
だってもう、先輩はいないから。
恋人を亡くしましたといえば、たいていの人は哀れみを向けてくれる。
しかし、その死因が隕石の衝突だと知ると、なんとも曖昧な顔をする。
先輩は例の一般家庭に隕石衝突事故の、たった一人の犠牲者となった。
不謹慎は承知でいうけど、なんとも先輩らしい奇抜な最期だといえる。
──あらゆる道具には役目というものがある。その役目を果たすまで生き続け、そして果たせば死ぬ。駄目になったからじゃない。それにとっての何かを終えたから死を選んだだけ。そこに、人間の介在する余地なんてない──
有象利路の『組織の宿敵と結婚したらめちゃ甘い』からの引用だ。
この一節が目に入ったとき、なんだか鋭く刺さって、思わずそのページをスマホで撮影した。
先輩も、そういうことなんだろうか?
私との何かを終えたから、ここからいなくなってしまったのだろうか?
わからない。
大切な人を失った悲しみが大きすぎて、悲しみごと失ってしまった。
泣きすぎて、泣き方も忘れてしまった。
先輩がいなくなって16日と2時間39分7秒経過したけど、私の時間は動いてはくれない。
先輩は私との出会いを神様からの贈りもののようにいってくれた。
先輩は知らないだろう。
それは私も同じなのだ。
私も誰かに関心を持つことができないでいた。
でもそんなある日、本屋さんで生まれてはじめて他人に目を奪われた。
その人が買った本を自分も買って、それを読んでいたらまたあの人に会えるんじゃないかと期待した。
翌日、あなたは私の前にあらわれてくれた。
一人でいると倒れそうになる。
だから適当にコンビニに入る。
ただ茫然と商品をながめている。
「……会いたい」
つぶやいた次の瞬間、信じられないものが目に飛び込んできた。
子供のラクガキみたいなイラストのついた、子供がふざけてつけたような名前のお菓子。
先輩が毎日食べていた、どうしても見つけることができなかったもの。
一瞬固まって、それから小さく吹き出した。
笑ったのは実に16日と2時間48分8秒ぶりだ。
「こんなところにいたのか」
お菓子を手に取る。
──きみと一緒に食べるのが好きなんだ──
先輩からそう言われた気がした。
もちろん、私の妄想にすぎない。
だけど。
とりあえず今日のところはお菓子を食べながら有象利路を読むとしよう。

本作ですがおかげ様で紙・電子ともに初動も好調で、非常に反響も大きく、また有象先生自身もこのように仰っておりましたので続きを書いていただくことにいたしました……!
— 電撃文庫 (@bunko_dengeki) December 14, 2023
ということで、読者の皆様がお待ちしておりますので原稿よろしくお願いします!(➡ @toshmichi_uzo) https://t.co/L8JtT6T4Cn pic.twitter.com/4eV2vuFLAk
おまけ

こちらは2023年の12月中旬に撮影したものです。
同じ場所で2024年の年明けに撮影したのがこちら。

みなさまの願いが全て叶いますように。
