
日本アルプスの旅【中編】
10月末の日本アルプス旅の続き
前編(初日〜3日目)は↓です。
4日目
岐阜駅周りのアーケード街を散歩。
地元の高校生たちの通学路になっていた。上から彫刻達が見守ってる。

所々レッドカーペットが敷いてあるようになっているのが、この通りに似つかわしくなくて面白かった。

少しだけ移動して、みんなの森ぎふメディアコスモスへ。

伊東豊雄建築。
みんなの森 ぎふメディアコスモスは、「知の拠点」の役割を担う市立中央図書館、「絆の拠点」となる市民活動交流センター、多文化交流プラザ及び「文化の拠点」となる展示ギャラリー等からなる複合文化施設です。
市立中央図書館として岐阜市役所の隣に建てられていて、図書館のほかに、ビジターセンターやスターバックスも併設されている。
開館時間前に着いてしまったけど、学生はもちろん社会人ぽい人たちも開館前から並んでいた。
ファサードは山々の稜線を思わせる波波の形状になっているらしく、周囲を囲んでいる山々とシルエットが同じで、街の中での異質感は全然なかった。

館内も波波の格子屋根に大規模な照明・シェードが吊り下がっていて、その中に読書スペースや休憩スペースなどが空間づくられている。
シェードの部分以外は天窓や天井照明はなく、明暗がきれいに分かれていて、陰影の綺麗な空間だった。



車で少し北上し、郡上八幡へ。
大学生のころに自転車で岐阜を回ったことがあって、そのときには夜通し踊り明かす「郡上踊り」にも参加したけれど、明るい時間の町は見れなかったのでもう一度行けてよかった。


郡上八幡は長良川の川沿いにある町で、古い家並みや商家が並んでいる静かな町。
町のあちこちで水が流れていて、川の水も透明度が高く、まさに水の都という感じだった(この日は豪雨だったので、水まみれの一日だった)。

敷き詰められた玉石と脇を流れる水路がある散策路


こういう場所のパフェが一番おいしい
南下して美濃方面へ。




根道神社の隣にあり、モネの睡蓮のよう
美濃の町に到着。

岐阜県の中心部に位置し、美濃和紙の産地として有名である。「うだつのあがる町並み」として知られる市街地は1999年5月13日に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された歴史的風致の街である。


「君の名は」に出てきた駅ってこんなんじゃなかったっけ
電車の乗り降りする人がぽつぽつとしかいない
町の各所で美濃和紙で作った明かりアート展の作品を展示していて、町に街灯がほとんどないことも相まって幻想的な町並みだった。
作品自体は、地元の美術学生や子供が作ったものらしい。


この日は水曜日だったのだけど、美濃の町で飲食店がほぼ営業していなかったので、市街地まで車で6~7km走ってスシローで食べた。
たまにはこういう日があってもいい。久々に回転寿司食べたけど美味しかった。庶民舌なので。

この日泊まったゲストハウス、1人1部屋あったけど壁が天井から50㎝くらい空いてて、音が筒抜けだった。
深夜にその隙間から誰かに覗かれてる、みたいなホラー展開ありそうな部屋。
5日目
ゲストハウスから徒歩圏内にある喫茶店でモーニング。
雨は無事あがって、綺麗な鱗雲が。

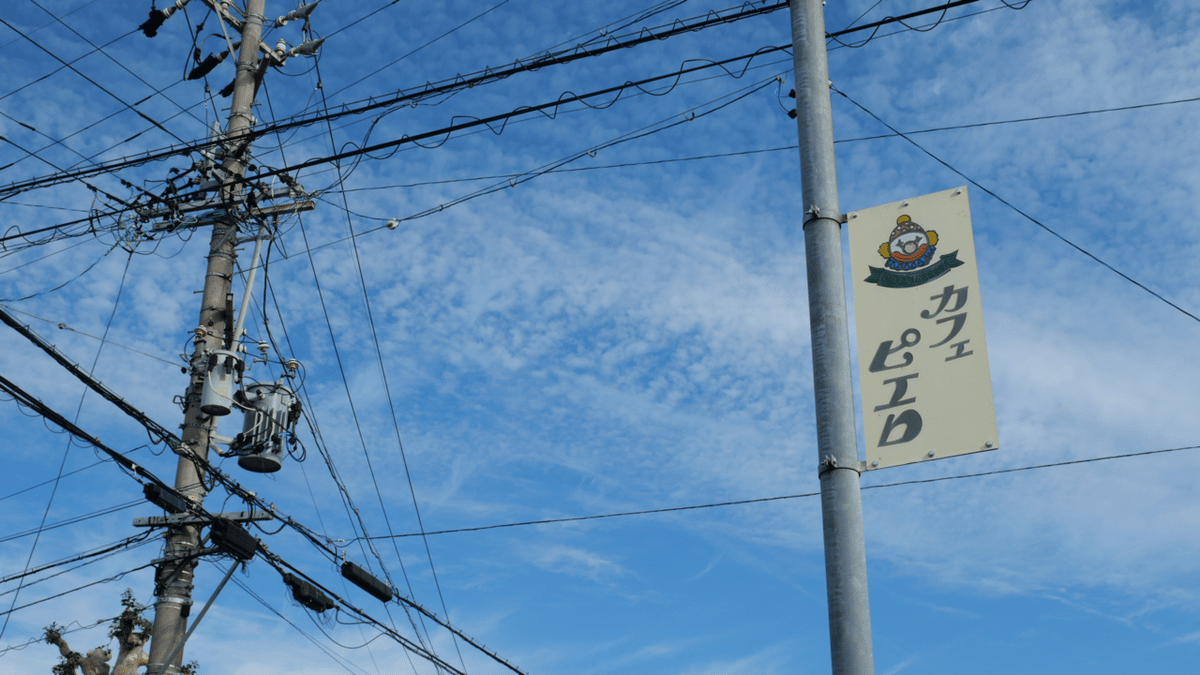
ゴミ袋に傘がさしてあるかわいい光景。

「松久永助紙店」で美濃和紙を撚って作った糸を買った、何に使うかわからんけど、綺麗な草木染だったので。


岐阜北部の飛騨高山方面へ。
HIDAの高山ショールームがあり、クラフトマーケットやカフェが併設されている。



空間は隈研吾で、インテリアはHIDAの家具

高山駅に到着。

高山にある遊朴館 HIDA GALLERYへ。

2024年10月19日にオープンした、HIDAが運営するギャラリー。
企画展として『山の向こうに呼び合うものは 松本の木工と飛騨の杉展』(10月19日(土)〜11月17日(日))を開催します。信州松本の4名の作家の「人と作品」を紹介するとともに、期間中はトークセッションや実演、ワークショップを行うほか、併設のショップでは日本の優れた木工技術を支える高品質な木工具や、暮らしを彩るクラフト雑貨を販売します。紅葉が美しい秋の高山で森の恵みと手仕事がつくり出す豊かな世界をお楽しみください。
遊朴館は旅程に入れてなく、HIDAショールームで教えてもらった。オープンから間もない施設で、最初の企画展として4名の作家の木工具・クラフト雑貨を展示。
HIDAの営業・デザイン担当の方が展示内容を紹介してくれたが、元々コクヨで働いていたらしい。
木工家具に魅入られて高山に移住し働いてるということだった。思わぬところで同じ業界の方に遭遇。



木べらを探していたら大久保公太郎という方のものを紹介してくれた。
桜と栗の木の2種類があり、木が同じでも木目の表情や木の色合いが全然違って、10分くらい選んで無事購入。
日下部民芸館へ。

重要文化財日下部家住宅は、昭和41年より日下部民藝館として建物の公開と日下部家所蔵の文物を展示、また建物を活かした多様な文化事業を行っています。柳宗悦が提唱した「民藝運動」の思想に共感した初代館長、日下部禮一の思いを受け継いで、日本人の自然への共鳴する心、各地の風土から生まれる人々の生活の美を見いだした「民藝」が示すものの見方、考え方、共に生き、自由である暮らしの規範を日々の活動を通して具現化することを目指しています。
この期間、落合陽一「どちらにしようかな、ヌルの神様の言うとおり:円環・曼荼羅・三巴」開催中。



夕食は、飛騨牛のすき焼きと地酒3種の飲み比べセット


店の建屋自体が、蔵を改装して作ったそう。
隣に座っていた外国人観光客も同じものを頼んでいて、食べ方を聞かれた。やっぱり生卵に抵抗ありそう。
前編と後編で終えるつもりだったけれど、思いのほか長くなったので残り2日分はまた後編で書きます(たぶん)
