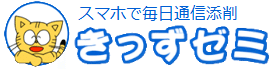松山奇談 八百八狸Ⅲ
第 三 席
さて、その子は犬の乳で育ったというので、伏太郎と名付けられましたが、中々どうして、この伏太郎の力は尋常ではなく、どんな夜中でも足音で直ぐに目を覚ましまして、暗闇の中でもはっきり物が見えるという、誠に不思議な人間なのでございます。
伏太郎が十二才の時に父親が大病に罹り、夜も寝ずに看病をしていて、
「父さん、僕はね。人から『母さんがいない』と、言われますが、母さんはどうされたの」
と、聞きますと、
「お前の母さんは、お前が生れて三日目に死んでしまった。それでお前が飲む乳がなくて困っていると、家で飼っていた野白という犬が乳を飲ませてくれて育ったのがお前だ。それで不思議なことに夜中でも目が見えるようになったんだ。その野白という犬が死んだ時に夢見に立って、『お前の陰身に添って守護するから』といい、また、お前が危うい時には、『ざんがい身の性来を知るからは心に心心して見よ』と言えば、お前に害を及ぼそうとする魔物の正体がお前には分るから、と言っていたのでこの事は忘れるな。それと、この飛騨の高山の御城下に進藤玄一郎という剣術の先生がいるので、そこに行って修業し、後藤の家名を立てくれ」
と遺言して、右源太は死にました。すると、近辺の者が家に来て、残こっていた物を処分をしてしまいました。
残された伏太郎は、家や僅かの家財を売り払って、病気中の借財を返すと、心細くも御城下に行き、進藤玄一郎の道場を訪ね、
「私は高山の片田舎から参りました伏太郎と申す者で御座います。どうか御当家で御膳焚きにでも御使い下さい。御給金は頂きませんので、恐れ入りますがその代わりに、先生に剣術を教えて頂きとう存じます。如何で御座いましょうか」
取次の門弟がこれを先生に伝えると、
「妙な奴が来たな。兎も角、通して見ろ」
と、言われたので奥に連れて行きますと、
(人品も賤しくなさそうだ)
と、思った先生は、
「お前は幾つだ」
と、尋ねると、
「はい、十二才で御座います」
「力は有るか」
「それ程でも御座いませんが、二十貫(七十五㎏)目位な物であればさほど重いとも思いません」
「十二才で二十貫目の物が重くないとは大力ではないか。両親はいないのか」
「二人共亡くなって、御座いません」
「不憫なことだ。飯は焚かんでいいから、当家に居ろ」
と、許しました。
(どこかに見どころがある)
と、見た進藤先生は伏太郎を家に置いて諸用をさせました。すると、これがまたよく働きます。その内に間ができると道場にも入れ、門弟達と剣の稽古をさせてみると、これも結構出来ます。
十二才から稽古を始めて次第に上達し、十六才になると兄弟子も叶わなくなってきまして、これを見た進藤先生も感心して、直接稽古つけてくれるようになり、伏太郎は懸命に励んでいました。

然るに伏太郎が十八才の時、この道場の玄関に一人の修業者が現われ、
「お頼み申します」
と、見れば年の頃は二十七八の偉丈夫、
「手前は江戸表に住居致している、一刀流剣道指南の眞田藤馬と申します。剣道修業の為に諸国を歩きし者ですが、御当所において先生の御雷名をお聞き致し、是非とも先生に御手合せを願いたく推参致しました。御取次を願いたい」
取次が早速に奥に通し、先生との面会を済すと、まずは弟子達が立合い、伏太郎も出ましたが悉く負けてしまいます。最後には先生が立合いますと相打ちでございました。
先生は感心して、
「失礼ながら貴殿はよい腕をお持ちだ、手前は最早四十八才に成るが、これまで貴殿のような御方に出会った事がない。御用がないのなら、少しの間でも、当道場に足を御止めなられては如何で御座るか」
「有難う存じます。幸い手前もこの辺の地理を踏みたく存じまするゆえ、御厄介に成ります」
といって、滞在する事になりました。
誠に進藤先生はよくもてなし、門弟達も『眞田さん』『眞田さん』と大層扱いが良い。これも腕前が勝れていたからでございましょう。
すると、当家の娘であるお雪さんという十九になる別嬪が、眞田藤馬に心を寄せるようになり、これを知った伏太郎は、嫉妬じゃないが癪に障ります。
(いまいましい奴だ。しかし、腕が立つのでまともには叶わねえ。あの眞田藤馬という奴をギャフンといわせる工夫はないものだろうか…。よしそうだ、ここは一番驚かしてやれ)
と、伏太郎が機会を伺っていると、先生が出張稽古に出る事を知りました。先生はこれに出ると三日位は帰りません。
(この時ぞ)
と、思った伏太郎は、
「もし眞田さん」
「これは後藤殿、何か」
「貴方様は諸国を御修行なされたとのことですが、『神面鳥羽玉敵かくれ』という事を御存知であろうか」
「何で御座る」
「『何で御座る』と、申すのであれば御承知ないとみえまする。この『神面鳥羽玉敵かくれ』と申すのは、夜分に敵に斬り付けられても、暗闇だからといって戦えないようでは、修業した甲斐がありません。ですから、どんな暗い所でも戦える技で御座います」
「尤もの事、よい心掛けで御座る。貴公はその技を使えるので御座ろうか」
「使える様心掛けております」
「これは珍しい。暗闇での試合は経験が無いので」
「暗闇だからといって戦えないようでは、剣術も役に立ちません。それは座頭が芝居を見るようなもので、隣りに聞く訳にはいきませんので、普段から慣らしておくのが肝心かと存知ます」
「成程御尤も、然らば今晩、私と立合って頂けますかな」
「分り申した」

その晩道場において互いに道着を付け、
「伏太郎殿、準備が出来ました」
「よろしゅう御座いますか。燈火を消しますよ」
といい、プット燈火を吹き消すと、急に真っ暗になり戸惑っていた眞田に、伏太郎は、
「御免」
と、打ち込んだ。
「参った」
伏太郎は間を置かず、
「御小手」
「参った…。あいや暫く、暫く御控えを、誠に恐れ入り申す」
「どう致しまして、只今燈火を付け申す」
といって、燈火を点じると、藤馬は、
「貴殿の御腕前、実に驚き入った。斯くまでの御修行は嘸かし御骨折りの事と御察し申しまする」
といって、眞田藤馬は閉口しました。
翌日帰宅した先生に、眞田が、
「先生、実に恐れ入って御座います」
「何が恐れ入りましたかな」
「左様で、先日先生が手前と御手合せ下されました際、相打ちで御座いましたが、あれは先生が手加減下されたという事を、昨晩初めて知りました。実に以って、恐れ入って御座います」
「はあ、先刻から貴殿は恐れ入ったと言われるが何に恐れ入りなされたかな」
「去れば昨夜、道場に於いて伏太郎殿と立合を致したところ、拙者は三本とも伏太郎殿に打たれました。これは『神面鳥羽玉敵隠れ』とか申しまする技だそうですが、伏太郎殿でさえあの通り、況や先生に於いては、と驚き入って御座います」
「はあ、左様か」
と言ったものの、先生はそんな事は夢にも知らない。知らない、というも悔しいので、知っているふりをして曖昧に答えました。
それで伏太郎を呼び寄せ、
「その方は『神面鳥羽玉敵隠れ』というのを知っているそうだが、左様か」
「御意で御座います。暗闇の中で敵と立合う事を『神面鳥羽玉敵隠れ』と心得ています」
「然らば、今宵道場にて立合たいと思うが、相手をしてくれるか」
「お稽古をして上げましょう」
「何」
「いえ、こっちの事で御座います」
その晩道場において、伏太郎が、
「先生、御道着を御付け下さい。御仕度が出来次第、燈火を消します」
というと、先生は面は勿論小手も指し、すっかり仕度を済ますと、竹刀を取り、
「さぁ、よろしい」
「では、燈火を消します」
といって、プッと燈火を消しますと、道場は真っ暗になり、先生は、
(これは暗い)
と、思いましたが、伏太郎は見えるので先生の隙を狙って、
「御面」
といって飛び込み、ビシッと打ち込みました。
流石の先生も見事に一本面を取られ、
「参った」
といいましたが、すぐさま、
「御胴」
「参った」
「御小手」
「参った」
と、伏太郎がのべつ構わずに無暗に打ち込んでくるので先生は堪らず、
「伏太郎待て待て、最前から『参った』と申しておろう。まずは燈火を点けろ」
「畏まりました」
といって、伏太郎が燈火を点けてみると、先生が屈み込んで唸っています。
「さあ、道着をお取り下さい」
「どうも不思議な奴だな。兎に角、座敷に来い」
といって、燈火を消して自分の座敷に行きますと、
「伏太郎、煙草入れを忘れてきた」
「取って参りましょう」
「燈火がなければ分るまい」
「いえ、燈火には及びません」
と、いって出ていくと、暫くして煙草入れを持って帰って来て、
「へい、ここに置きます」
「何処にあった」
「刀掛けの傍にありました」
「うん、貴様は夜中でも物が見えるのだな」
「へい、燈火がなくてもよく見えます」
というのを聞き、先生は、
(はて、稀有な奴だぞ、六年間誰一人として尋ねて来る者もなく、寒中でも寒いといった事はない。何時でも直ぐに起きるし、力はあり気転は利く。これは化物か。まさか化物じゃあるまいが、何にしろ奇味の悪い奴だ)
と思って、伏太郎に、
「ここに二十五金ある。これを持って修業に出ろ」
と言いました。
伏太郎は大いに悦び、先生に別れを告げて高山の城下を出発しました。

伏太郎が十八才の秋の事、加賀の金沢の御城下に差し掛かり、本陣伝右衛門の出店で湊屋六兵衛という旅籠屋において、酒肴を誂て貰っていると、家中が恐ろしく騒々しくしていた。
伏太郎が、
「これ女中、家内が大層騒がしいが何かあったのか」
と聞くと、女中が、
「はい、御本家の大御新造様が御立退きで御座います」
「何だと」
「御本家の大御新造様が御立退きで御座います」
「御立退き、何処へ立退く」
「何処へという事でも御座いませんが、御本家の御新造様が狐に取り付かれまして、貴方、余程の古狐と見え、三年の間全治しなかったので御座います。ところが、今度いよいよ立退くというのですが、『油揚を一万枚に赤飯を十石出せ』というのだそうで、私共はその品を誂えて、御本家へ運んでいるので御座います。それで騒がしく致しているので御座います」
「はぁ、左様か…。一寸亭主を呼んでくれんか」
と言われたので、女中が主人の六兵衛に伝えますと、
「忙しい中だ。何とでも言って置けば良かったのだ。だが、仕方がない。会ってみるか」
といって、座敷にいき、
「えー、六兵衛で御座いますが、何ぞ御用でも御座りましょうか」
「いや六兵衛、他でもない。本家の御新造が狐に取り付かれたと聞いたが」
「はい、左様で御座います。本家の伝右衛門の内儀が三年前から狐に取り付かれまして、種々な事を試したのですが、誠にしぶとく、立退きませんでした。ところがいよいよ立退くと言い出して、『その代わり赤飯と油揚げをくれろ』と言いますので、誂えて、出来上がったものを、順次本家へ持ち運んでいるところで御座いまして、故に、自然と騒がしく致しているので御座います」
「そうか、そこで主人相談だが、俺は諸国を修業中に不思議な秘術を会得して、これ迄に数人に試みてきたが随分効果があったと自負している。こういう狐付きなどには打って付だと思うがどうだろう。俺が伝右衛門の処へ行って、秘術を以って狐を落して遣ろうと思うのだが」
「そういう事であれば、伝右衛門始め家内の者も嘸かし悦ぶ事で御座いましょう。甚だ御言葉に甘えるようですが、御足労をお願い致します」
「よろしい。では、直ぐに行こう」
と、伏太郎は案内として六兵衛を同道させ、本陣の伝右衛門方へ行きました。
早速、主人の伝右衛門始め親類一同に委細を話し、その上で伝右衛門のお内儀が伏せっているところへ行ってみますと、狐の注文により楠の中には山盛りの赤飯が、また、板の上にはこれも山盛りの油揚が乗っていて湯気を立てています。伝右衛門の内儀は妊婦のように布団に寄り掛り、目をきょろきょろさせています。
伏太郎は人を遠ざけ、次の間で様子を窺がい、四ッ(九時)頃にその病人の処へそっと行くと、ピタット肩を押えて、
「ざんがいの身の性来を知らなければ心に心心して見よ」
と唱え、プーと息を吹っ掛けました。
すると、その病人が三百年も経つかと思うばかりの一匹の雌狐に変わると同時に、裏の窓から数匹の子狐が飛び込んで来て、
「御婆さん御馳走様、有難う御座います」

と礼をいいながら、赤飯だの油揚を無暗矢鱈に掴んで喰っています。
成程、これならば十石の赤飯や一万枚の油揚もなくなるはずでございます。
伏太郎は、
「己、妖怪め」
とその雌狐を押えて、キラリ一刀を抜き放ち、胸元をブスリと突き刺しました。
狐は、
「キャッ」
と、一声。
(何事か)
と、駆つけた伝右衛門始め親類一同は、これを見て、
「お侍様、貴方は私の家内を殺しまいたな」
「いや、これは其元のお内儀でない。一匹の古狐だ。仮に其元のお内儀の姿をしておったのだ。今に正体が分かるので、驚くな」
と、制しその儘にして置くと、成程夜明け方になると一匹の狐になりました。
直ちに伝右衛門からこの事を御上に届出しますと、御検視が下りることになりました。
この老狐は、金沢の城下の外れにある金沢山に住むおぶんきつねで、それが伝右衛門の奥さんを喰い殺し、その体を借りていたのでございます。
古狐を切り捨てた腕を御役人方が称美し、これを御上に報告した事で、召し抱えが許されたのですが、伏太郎はこれを辞退しまして、少々の手当を受取って、ここを立去りましてございます。
その後、廻り廻って伊豫の松山に辿り着きまして、奥平久兵衛の推薦で隠岐守に奉公することとなった件は、前席にて述べたところでございます。
桃李申し上げます。金沢を出立しましてより、伏太郎は後藤小源太と改名致しました。よって以後、小源太と呼びますので、御承知おき願います。