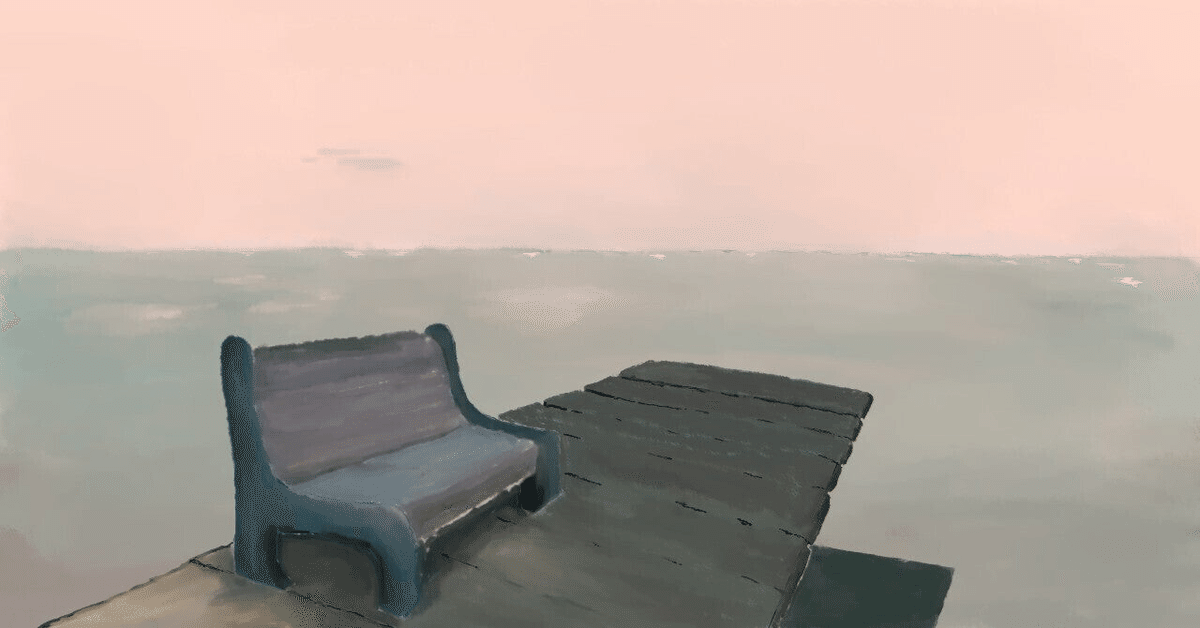
辺りを見渡す雪蛍 1
灰色に濁った曇天の空を、いまさら感傷的な面持ちで見上げるほど、僕は人間臭くはない。視界の端には忌々しき木造校舎、昨日積もった雪だろうか ──いや、昨日は久しくみた晴天であり、用務員の天狗爺がわざわざグラウンドに出て、日々の雪かきから賜る霜焼けた両手を、太陽に見せびらかせていたのだった……。
とにかく、いつ頃降り出し、またいつ頃降り止んだかさえ分からぬ平らな雪の塊が、軋んだ木造校舎の屋根、そのなだらかな曲線にべたりと張り付いているようで、僕が真正面からジッと睨まないからか、それら冬の塊は視界から消えようとしなかった。逃げようとしなかった。
「あんた、そりゃあ昨日はええ天気やったよ」
用務室の窓を開けて、天狗爺が僕に言った。曇天に対する皮肉とも思えた。彼はさらに身を乗り出そうと左手に力を入れたものの、鈍い音が我々の隙間を通り抜けるのみで、以降なにをしても頑固な窓は頑なに動こうとしない。
彼は窓枠を強く叩いた。屋根よりわずかな雪が落ちて、僕の肩に当たった。そして弾けた。
「あぁ、こういうのを〈頑な〉というんじゃ」
天狗爺は笑った。こちらもつられて笑った。
肩の雪を払った瞬間、その頑なな窓は大きな音を立て崩れ落ちてしまった。あまりの不快音に、僕はその場で立ち竦むしかない。
──あまり頑固ではいかん。
彼は、その霜焼けた手を握り、いま床に着地しようとする自らの血液を、落下の様を、茫然とした表情で眺めていた。まるで意図せず手を上げてしまった父親のような、哀れな顔で。
「親はなぁ……。そう、子供は強いもんやと思い込んどる。でも、忘れとった。ガラスと同じで弱いんじゃ、脆いんじゃ」
ゆっくりと箒でガラス片を集める彼、そんな哀愁に気を取られて、ふたたび雪が降り出したことに、僕はしばらく気がつかなかった。
陽が落ちた頃、降雪はさらに勢いを増して、ガラスと同様に弱くて脆い、年季の入った校舎に襲いかかっていた。教室に残っていた数少ない生徒はそれを意に介さず、ただ暇潰しのための会話を続けていた。
過疎化の進行が思いやられる田舎街、数十人しかいない中等部生徒のうち、部活に精を出す者はその六割程度だった。他の三割は夕方には閉まってしまう喫茶店の常連客── 皆、制服のポケットに煙草を忍ばせているような連中で、終業のチャイムが鳴る頃、彼らも喫茶店のドアベルを鳴らしているに違いない。
残る一割、それが僕も含まれる居残り組などと呼ばれた生徒である。両親が山裾の街まで働きに出ており、帰宅を知らせる連絡が教員室の古い電話機に届かない限り、教室に身を囚われ続けている生徒とも言える。夕刻、遠くの方で小さな電話音を認めた後、宿直の先生が教室のドアを静かに開ける。それまで笑いながら喋っていた生徒は、皆ぴたりと口を閉じる。
葛西、帰る準備をしなさい……。
「また明日なぁ!」と手を振る友人、羨望の眼差しを向ける我々。まだ平和な光景である。
稀に、気遣いを勘違いした先生が、なにやら紙束を持って教室に入ってくる。浮き足立つ皆を前に、嬉しそうな表情を浮かべこう告げる。
── さぁ、小テストで評価点を稼ごうや。
地獄絵図とはこのような光景なのだろう。
しかしながら、彼らは一人一人確実に、着実に帰路についてゆく。僕は、静寂の教室にいて窓ガラスに反射するボヤけた自らを司会とし、孤独なるトークショーを想う。そして気付く。
「もう一人の僕も、恐らく話下手なのだろう」
