
『カレンダーストーリーズ』ウラ3月 「彼岸問答」 【掌編小説】作:小泉清美
むせ返るような若葉の香に、時折混じるきな臭さは、まるで頚木のようだ。
徐々に強さを増すそれは、この身から歩む気力を奪うようで、私はついに立ち止まった。
強く閉ざした双眸の力を緩めると、眼前の暗闇はまぶたの向こうより差す春の陽に一掃される。
まぶたの中の白き世界にしばらく佇んだあと、私は意を決し、そろりと目を開いた。
すると再び、私の視界は黒で埋まる。
我が前に広がるのは、うららかな春の景色に見合わぬ地獄絵図。
焼け焦げた木の柱が幾重にも折り重なり、それらの中に、同じく灰と化した巻物や布きれが覗いている。
これは、山寺の残骸だ。
天保十四年、水戸藩よって行われた廃仏毀釈により、多くの寺が廃された。
ここも類に漏れることなく、私が荒行に出ている間に、水戸の息のかかった者共に火を放たれたようだ。
私の名は春光。この寺に住んでいた坊主だ。
歳は二十と七。
私は残骸の中に足を踏み入れると、そのまま仏像が安置されていたあたりにまで歩を進め、一心不乱にその場を手で掻いた。すると程なく黒光りした仏像の左手(ゆんで)が姿を現したので、私は素早くそれを布きれで包み、懐へと収めた。
急いでこの場から立ち去らねば。誰かに見られでもしたら厄介だ。
懐中の仏への懺悔もそこそこに、私は急いで踵を返すと、一目散に藪の中へ駆け込んだ。
焼失した山寺から里へ下り、さらに一里ほど東へ進んだところにある沢のほとりに、竹馬の友・東町錦風(ひがしまちきんぷう)の住まいはある。
立て付けの悪い引き戸を開けると、今度は膠(にかわ)の独特な匂いが鼻についた。
錦風は、最近ようやく名が知れるようになってきたばかりの、駆け出しの町絵師だ。
絵師とはいえ、錦風の生い立ちは決して恵まれたものではない。
行商をしていた父御(ててご)を早くに亡くした錦風と兄弟たちを、母御は命を削って養った。
朝早くから身を粉にして働き、時には私娼(無許可の売春婦)として男の袖を引いた。
そんな境遇から、錦風一家は里の住人たちに蔑まれ、錦風の額には石つぶてによる痣が絶えなかったのを、私は覚えている。
その有様を哀れに思った我が師・慶安和尚は、山寺に幸薄い幼子たちを招きいれ、私たち小坊主ともに、字や和算を教えた。
これが私と錦風の、竹馬の友たる所以である。
錦風の住まいは、板張りの粗末なぼろ屋であり、屋根に空いた穴から差す春の木漏れ日が、幾つもの筆が転がる文机に、白いまだら模様を浮かび上がらせていた。
どうやら住まいの主は留守らしい。
私は、ぼろ箪笥から自分の袈裟を引っ張り出し肩にかけると、やおら裏の沢へ向かった。
そして、懐に忍ばせていた仏像の左手を水につけすすを洗い落とすと、それを木の根元へと立てかけ、手を合わせる。
袈裟には袖を通さず、肩にかけたままで。
これは決して伊達を気取っているのではなく、人の気配を感じたらすぐに坊主のいでたちを解くための用意に過ぎない。
荒行が百日。帰った日に起きた放火から六十余日。
すっかり伸びた髪が黒い袈裟と共に、暖かな風に揺れる。
袈裟をだらしなく引っ掛けたざんばら髪の私の姿を、天の御仏は如何に思うのか。
我今見聞し、受持することを得たり
願わくば、如来の第一義を解せん――
経(きょう)は読む者の五感を研ぎ澄まし、その心から恐れを退散させる。
その証拠に、私はいつの間にか背後に忍び寄った人の気配に動じることなく、その者が発するかすかな音と香から、人物の姿と様子を、細部に至るまで脳裏に再現してみせた。
「わらび・・・か。」
私の問いかけに、背後の人物は返事の代わりとして、抱えていた匂い立つわらびの束を、我が目の前に差し出した。
「今日の夕餉(ゆうげ)だ。少し待てよ、今これを茹でてしまうから。しかし、人を誘っておいて先に始めているとは、何ともせっかちな坊主じゃないか。」
「今のは読経の前の開経偈 (かいきょうげ)だよ。お帰り錦風。わらびとは良い供物だなぁ。お前の母御もさぞ喜ぶだろう」
「夕餉、だといっただろうに。」
錦風はゆっくりとした動作でわらびの束をざるに空けると、それを沢で洗い始める。
「早くしろよ。今日は春の彼岸の入りだ。先祖たちもお前の母御も、早う家に帰りたいと、あの世の門で待っておるぞ」
「母御母御というな。腹が立つ。」
錦風は苛立たしげに眉間にしわを寄せながらも、わらびを鍋へと移し土間へ運ぶ。
「その仏像のかけらからするに、位牌はひとつも見つからなかったようだな。まあいい。ああ、俺は鍋を見ているから、もう始めてくれてもいいぞ。簡単な経を手短に読んでくれ。」
「わらびを煮るまで待つよ。罰当たりめ。」
「俺は忙しいんだ。このあと絵の仕事もある。明るいうちに色を決めておきたい。」
そんなやり取りを交わしながら、錦風は鍋を火にくべる。そして文机に置いてあった描きかけの錦絵を手にし、さらに暗澹たる表情を浮かべた。
ここ数日、錦風は一貫してあんな様子だ。絵を描きかけては消し、まるめ、その度に深いため息をつく。
私には親友としての立場上、その理由にだいたいの予測はついていたのだが、放っておくのも忍びなく、そのこころをこの場で問うことにした。
「錦風。よもやお前、師匠に癪に障る提言でもされたのか?」
錦風は、私の言葉が終わる前に手にしていた紙をまるめ、恨みのこもった言葉を吐き捨てた。
「ああ、されたとも。あの爺め、俺の絵に向かって、春画あがりの絵描きは線に勢いが足らなくてかなわぬ、などとほざきやがった。ふざけやがって!」
やはり・・・。
私はやるせなさに口をへの字に曲げると、静かな水面に視線を落とした。
錦風は、幸薄かった己の境遇を怨んでいる。そして何より、母御の所業を怨んでいる。
そもそも、錦風の絵が評判になったきっかけは、岡場所(小規模の売春宿)で客相手に売った春画だった。
庶民には高尚な山水画よりも、低俗な春画が好まれるもの。
春画が売れ出し、小銭が溜まった錦風が、蕎麦を食いに行こうと誘ってくれたことがあったが、その時私は確かに聞いた。酒をあおり、気を良くした錦風が、こう呟いたのを。
「俺が春画を描いたのは他でもねえ。お袋に対する仕返しなのさ」
生きる糧を得るためとはいえ、身を売った母親を、錦風は許せなかった。
そして、その許せない“色の世界”を描くことにより実力をつけ、飯を食らう己が許せなかったのだ。
春画は人づてに売れに売れ、その評判を聞いた絵師・歌川国芳に実力を認められた錦風が、その門下となったのが天保十四年。
折りしも世は、老中・水戸忠邦による天保の改革の最中にあり、質素倹約・風紀粛清の号令の元、浮世絵や役者絵などがご法度になるという、絵師にとっては受難の時代である。
師の歌川邦芳は、幕府の理不尽な弾圧に反旗を翻し、浮世絵の中に精一杯の皮肉を込め世に出した。
そんな人物の門下となれば、危険なことは確かであったが、それでも私は錦風が体制批判の熱に踊らされ、人生に影を落とした母御への恨みを忘れてくれたらよいのに、などと考えていたのだが・・・。
師と作風について論駁を繰り返す度、錦風の胸は母御への恨みを蘇らせ、増幅させた。
この男は母御への偏った執着から、長きに渡りずっと地獄の中にいる。
結局のところ、有能な師匠も、公平に子供たちを愛した慶安和尚も、彼岸に帰る先祖の霊も・・・。そして、親友の私でさえも、錦風を奈落から救うことができないのだ。
錦風を救えるのは、ただ一人。御仏をおいて他にいないに違いない。
そう思って私は錦風に、母御の彼岸供養を切り出した。
始めは嫌がっていた錦風だったが、再三の懇願の末、ようやく首を縦に振ったのが数日前。
春の日に、坊主の説教を聞きながら人並みに供養の儀式を経れば、この男の心境に、少しばかりの良き変化がもたらされるのではないだろうか?
私自身をいえば、100日の荒行を終え、寺を始めすべての財を失った今なら、御仏の霊感をこの身に受けることが出来るやもしれぬという、不思議な自信に溢れていた。
ああ、こんな考えは手前勝手な驕りだ。仏門に帰依する者が魔によって見せられる、はかない幻想にすぎない。これをわが師・慶安和尚が知ったら、何とされるだろう。
春の陽が、私の黒き袈裟を暖める。
その心地よさに、私はついうつらうつらしながらも、彼岸に戻るだろう慶安和尚の顔を思い浮かべていた。
幼少時、和尚の前に座して聞いた、説教の数々が頭をよぎる。
そういえば和尚は、錦風をこんな風にいっていたな・・・。
『春光や、聞いておくれ。私はあの生意気な絵描きに、御仏を感じずにはおれんのだよ・・・。』
ぼんやりとした意識の中で、和尚の懐かしい顔がほころぶ。糸のように細い眼は常に弧を描き、子供たちが悪さをしても決して怒りはしなかった、温厚な和尚。
和尚の微笑みにつられ、朦朧とした私の口が、自然と言葉をつむぎ出す。
「そういえばなぁ、錦風。和尚が生前こんなことをいっていたよ。お前の中に御仏を感じる、と。」
「なんだ、唐突に。」
火にかけた鍋を気にしつつも、私の後ろであぐらをかいていた錦風が、怪訝そうな声をあげる。
「つまりなぁ。」
私は相変わらずぼんやりとしながらも、自らが発した言葉の整合性を求め、蓄積された修行の記憶から、適当な答えを探した。
「こういうことよ。何か一芸に通じるということは、尊い価値があるものさ。それが絵の道であれ、仏の道であれな。 」
「やめろやめろ。坊主の説教など聞きたくない。」
錦風は、まるで解せぬという風に頭を掻きむしったが、しばらくの沈黙ののち、そういえば、と口を開いた。
「一芸に秀でることが解脱への道へ通ずるとは、今まで考えたことがなかったが・・・。お前なら知っているだろう、芭蕉の神号の話を。」
「バショウ?・・・ああ、歌詠みの松尾芭蕉か。ええと、あれはいつの話だったか・・・。」
唐突に出た芭蕉の名に少々困惑しながらも、私の意識は未だ和尚の幻覚と共にあった。言葉の続かぬ友の代わりに、錦風が続ける。
「俺が弟子入りしたのと同じ年だから、天保十四年だ。俳人の田川鳳朗とかいう者が、京の二条家に誓願した末に、花下大神という神号を下賜されたらしい。死んでから百五十年後に、ただの歌詠みが神になったわけだ。」
「人が神にねぇ・・・。まあそれも、水戸の神仏分離を盛り立てるための茶番なのだろうけれど。」
私はかろうじて、錦風の言葉に相槌をうちながらも、意識は一層和尚の幻想へ傾倒していった。何故ならば目の前の和尚は、先ほどからその口を動かし、私に何かを語りかけているように見えたからだ。私は必死にその唇を読もうと試みるが、とんと理解できない。ただひとつ分かるのは、和尚が私の名を呼び、それに続けて何かを訴えているようだ。
・・・春光、・・・○○○・・・。
・・・春光、・・・○○○・・・・。
この時私は、錦風の声の様子が徐々に変わってゆくのに気付きはしなかった。和尚の言葉に気を取られる私に、錦風がゆっくりと問いかける。
「なあ、春光。人は死んでから天国か地獄へ行き、そしていつかは生まれ変わる。輪廻転生というやつだな。苦しい人生をようやく終えたかと思えば、またおぎゃあとこの世に生まれ、何度も何度も腹をすかせたり戦をしたりせにゃあならん。これこそが、まさに地獄と思わないか?」
「ああ、そうだなぁ。」
「人は常に人であり、死してもなお人であり続ける。・・・ならば芭蕉のごとく、人が神になったのならば、どうなる?」
「そうさなぁ・・・。」
「・・・・・・」
問答の最中にも、和尚は絶えず口を動かし続ける。
・・・春光、○○○と。
必死に訴えかける和尚の様子が、どこか滑稽なように思えて、私は笑い出しそうになるのを堪えながら、首を傾けた。そして錦風への返答は、一貫して記憶から言葉を適当に見繕うと、ほとんど無意識のうちに声に出していた。
「神になったのであれば、輪廻の輪から外れるのではないか?二度とこの世に生まれ出ることもなければ、地獄を味わうこともない・・・。」
・・・春光、○○○・・・。
・・・春光、○○○・・・。
私の何気ない返答に、錦風が身を乗り出す。
「芭蕉を神としたのは、誰だ?」
「誓願した先が二条家ならば・・・、朝廷・・・だろう?」
「ほう・・・。ならば朝廷には、神と同等の力がある、という理屈が立つな。・・・・・・神を殺せば、地獄どころか、三界(仏教でいう欲界・色界・無色界の三つの総称)ごときれいに消え失せるかもしれん・・・ 。」
「うん・・・。そうかもしれんな。」
和尚の声が、大きさを増す。
春光、○○○。
春光、○○○!
座していた錦風の気配が、ふわりと立ち上がる。
そして、足を引きずるようにして歩く足音が、ざりりざりりと私に近づき、錦風はこれまで聞いたことのないような低い声で、最後の質問を問いかけた。
「朝廷に相対する敵とは?」
「会津に桑名。庄内、長岡・・・・・・。」
春光、もう言ってはならぬ!!
意識の中で大きく見開かれた和尚の眼に、私は恐怖を覚えながら現実へと引き戻された。
同時に、すっかり変わってしまった錦風の様子にようやく気付き、冷たい汗が背筋を伝う。
竹馬の友は私のすぐ隣に立ち、面を伏せたまま微動だにしない。
「・・・・・・。」
緊張感を帯びた静寂が、私と錦風を包み込んだ。
しかし、その静寂の中にぐつぐつと煮える鍋の音が混ざり込むと、錦風は思い出したかのように土間へ向かって歩き出した。
歩きながら錦風は、小さいながらもしっかりとした口調で言葉を紡いだ。
「さあ、わらびが煮えた。待たせて済まなかったな。彼岸の回向を始めよう。ああ、良い彼岸だ。お陰で新たな仕事も決まったよ。」
「新たな・・・仕事?」
嫌な予感が念頭をよぎり、私は声を震わせる。
「ああ。師匠の家には脱藩浪士が多く入り浸っていてね。そいつらがよく、幕府が募集している京の警備の志願のために必用だからと、書簡や手形の写しを求めて俺を頼ってくるんだ。そういったものを偽造するには、春画上がりの繊細な筆先が必要なんだろうな。」
「偽造?錦風、まさかお前・・・」
「素晴らしいじゃないか。俺が手がけたものが兵を生み、時代を動かしてゆくのだと思えば。頃合を見て、俺も京へ向かおう。この手で朝廷に挑み、神を下し、三界共々奈落へ葬ってやる。その時こそ終わるんだ。戦にまみれた人の世が。そして、筆を折りたくとも折れぬ、俺の地獄が。」
友の言葉に、私は愕然とした。
・・・取り返しのつかないことを口にしてしまった・・・。御仏の慈悲により、この男を救おうとしていた結果が、まさかこんな様相を呈するとは・・。
私の胃の府に、吐き気を伴う強い怒りが、ふつふつとこみ上げる。
この怒りとは無論、驕り高ぶっていた己に対しての怒りだ。
錦風の中は、確かに世の中と母御への怨みという魔が住んでいた。しかし私の中にも、いつの間にか驕りを餌とする魔が住み着いていたのだ。己の未熟さが故の驕りが、錦風の魔に油を注いでしまった・・・。
「最悪の彼岸だ。」
不思議なことに、強い怒りは後悔の涙を生じさせることはなく、時が経つにつれ私の心は、虚無感で満たされていった。
私は再び、意識の中に和尚の像を作り出し、それに向けて気のない懺悔をする。
慶安和尚。仏道をゆくことに、私はもう疲れました・・・。
私は読経を途中で中断すると、ようやく竹馬の友の顔をまじまじと見つめ、疲れた笑みを浮かべた。
「なあお前、どうせなら、わらび飯にしないか」
唐突な私の物言いに、口を半開きにする錦風。
「仏に供えるのか?」
「いいや、夕餉さ」
堕ちた絵師と、堕ちた坊主。
二人の屈託のない笑い声が、弥生の空に響き渡る。
その様子を、木の根元に置き忘れられた仏像の焦げた左手が、静かに見守っていた。
弘化三年、弥生の彼岸の話である。
ウラ3月「彼岸問答」作:小泉清美
cover design・仲井希代子(ケシュ ハモニウム × ケシュ#203)
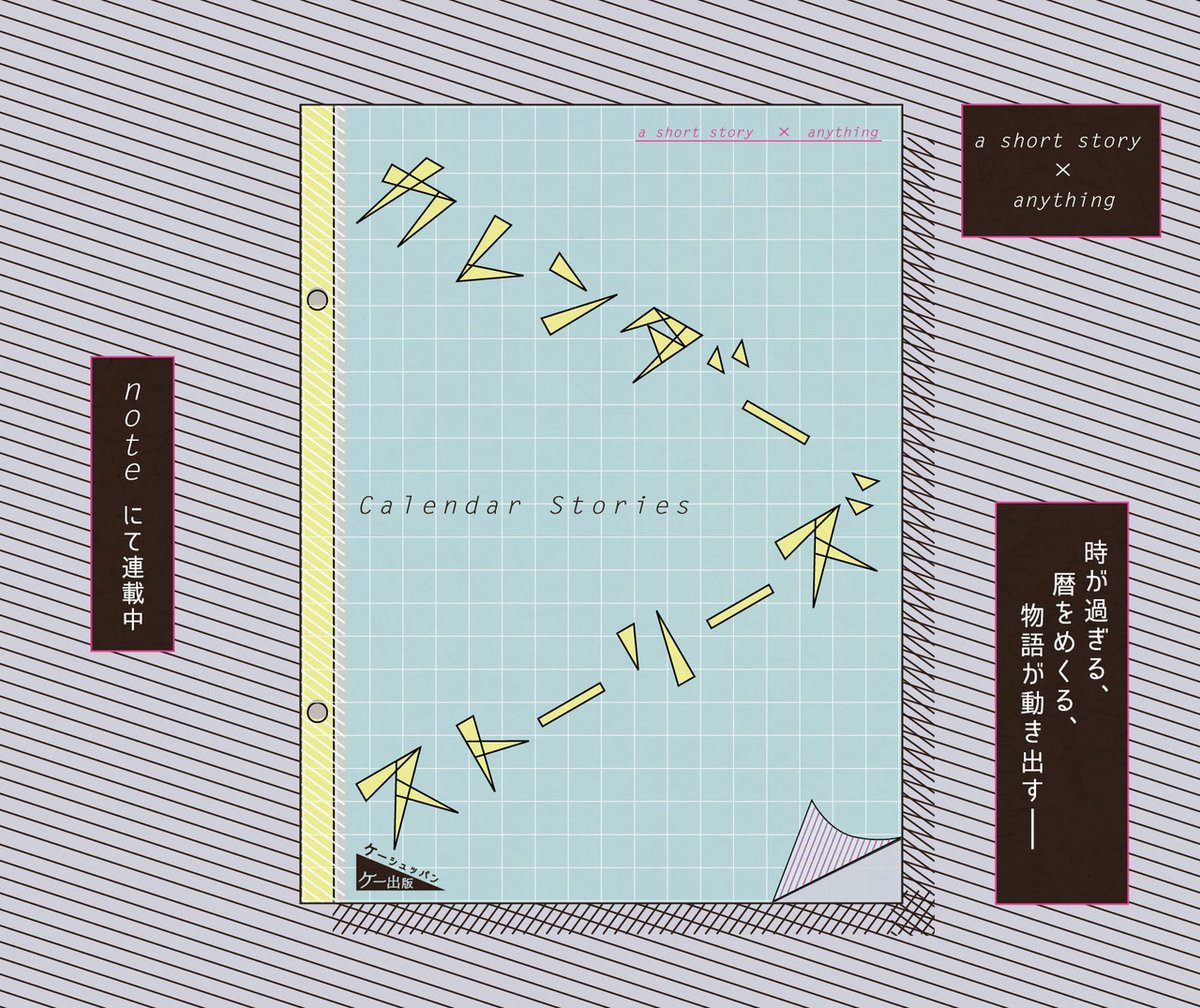
*『カレンダーストーリーズ』とは…"丘本さちを"と"毎月のゲスト"が文章やイラスト、音楽などで月々のストーリーを綴っていく連載企画です。第一月曜日は「オモテ○月」として丘本の短編小説が、第三月曜日は「ウラ○月」としてゲストの物語が更新されます。
※2016年 10月の更新をもって『カレンダーストーリーズ』の連載は終了しました。お読みいただいた皆様ありがとうございました。
3月のゲスト:小泉 清美(こいずみ きよみ)
1981年生まれ。静岡県富士市在住。
2004年、第3回スクウェア・エニックスマンガ大賞少年マンガ部門において、遥緒ジョウのPNで佳作&審査員特別賞受賞。高校卒業後、地元のフリーペーパー誌での4コマ・コラムの連載を経て、現在は日本初のクリケット漫画・バガヴァット・クリース制作中(英語版1巻好評発売中)。
●ケシュ ハモニウム(問い合わせ)
Web → http://www.kesyu.com
Facebook → https://www.facebook.com/kesyuhamo
Twitter → https://twitter.com/KesyuHamonium
