
構造計画研究所・石塚広一氏インタビュー(後編) 『構造計画研究所におけるデジタル技術の活用』~工学的アプローチの実践~
【はじめに】
前回に引き続き、株式会社構造計画研究所 石塚広一氏のインタビュー記事をお届けします。今回も、構造設計でのデジタル活用事例や、異業種とのコラボレーションについて幅広くお伺いしています。
■プロフィール
石塚 広一
株式会社構造計画研究所 構造設計2部 部長
大学時代に川口衞氏、佐々木睦朗氏に師事し、構造設計を学ぶ。大学院修了後、株式会社構造計画研究所入社。入社後は一貫して構造設計に従事。主に免震・制振の特殊な建築物を数多く担当。大規模再開発プロジェクトや、ファサードデザインと構造設計を組み合わせた商業施設の新築設計、CLTハイブリッド構造を用いた木造構造設計、プロポーザルへの参加、実験コンサルティングなど様々なプロジェクトに参画。部門長としてイノベーションの創出と新たな挑戦を誘発するための風土づくりにも尽力。
大江 太人
Fortec Architect株式会社代表
東京大学工学部建築学科において建築家・隈研吾氏に師事した後、株式会社竹中工務店、株式会社プランテック総合計画事務所(設計事務所)・プランテックファシリティーズ(施工会社)取締役、株式会社プランテックアソシエイツ取締役副社長を経て、Fortec Architect株式会社を創業。ハーバードビジネススクールMBA修了。一級建築士。
【画像解析や3Dデータを活用し、業務を効率化】
岡本:前回は、構造設計におけるBIM活用を中心にお話を伺いましたが、他にはどんなデジタル技術を取り入れているのでしょうか?
石塚:構造実験などのコンサルティングを行うときには、DIC(デジタル画像相関法)も活用しています。DICは、画像の変化を解析し、材料のひずみを可視化する手法です。以前は、ひずみ量を知りたい材料に、ひずみゲージというテープのようなセンサーを接着し、その伸び縮みを計測して力と変形の関係を計測するアナログな手法を採っていました。
DICは、試験体の表面にスプレーした模様の変化をカメラで認識しながら画像を解析し、カラーコンター図(3次元解析結果の可視化手法)に表示していく手法です。材料に力が加わった時の変化や、ひび割れの入り方などについて、スプレーのまだら模様の変化で確認できます。こうしたシミュレーションはコンピュータ上でも可能ですが、リアルな実験結果と照らし合わせることで、シミュレーションの整合性が分かり、試験回数も減らせます。この技術は、メーカーの工法開発、金物開発などに役立てられています。

材料の強度を測る引張試験にデジタル画像相関法(DIC)を活用。材料が破断に至るまでの変形やひずみを可視化することができる。
岡本:既存の建築物の改修工事の場合はどんなデジタル技術を活用されていますか?
石塚:当社では、耐震診断や改修工事も多く手がけています。100年以上前に建てられた大学の食堂や、1960年代・1970年代に建てられた県庁・図書館など、建築年数が長く、重要な施設の耐震改修も多いですね。
免震改修工事では、建物自体をジャッキアップし、地震の揺れを緩和する積層ゴムを柱の下に設置します。まずは、現地調査の後、既存の図書を確認し、情報を取得するのですが、古い建築物の場合、躯体や荷重の確認のために再度現地に向かうと、既存図書と全く違う状況になっていることがよくあります。補強材の設置によって配管等の設備に干渉するかどうか、施工が可能かどうかも確認しなければなりません。現地に何度も足を運ぶことが、業務の煩雑化につながっていました。
そこで当社では、現地調査業務の効率化のため、3Dスキャンデータの活用を一部物件で活用しています。使用しているのは、当社が提携しているドイツ・NavVis社の製品です。この移動式計測デバイスには、4台のカメラと、点群データを取得する2台のLiDARが搭載されています。このデバイスを装着して現場を歩いていくだけで点群データとパノラマ画像を取得し、さらにはふたつを組み合わせて3Dビューワーで表示します。点群データから寸法や面積の推定も可能ですし、3Dデータ内に設備機器の詳細や更新時期など、情報タグを埋め込むこともできます。3Dビューワーは、ストリートビューのように閲覧できるので、まるでその場にいるかのように現況を把握できます。精度±8mmとかなり高精度なので、改修工事に非常に役立つツールとなっています。

NavVis社は、現場の3Dデータを高速で取得する移動式計測デバイスと、そのデータを可視化する3Dビューワーを開発。構造計画研究所では、NavVis社の製品を実際の現場で活用しながら、導入コンサルティングも手がけている。
石塚:現地に制震ブレース等の耐震補強部材を設置した場合のモデリングも、現況ベースで確認できます。設備機器が多くある複雑な現場でも分かりやすく可視化できるので、関係者全員の合意形成にも役立ちます。

補強後も含めた可視化環境をNavVis内に構築することで、建築物の所有者や関係者との合意形成に役立てている。
大江:私も耐震改修工事のプロジェクト・マネジメントを複数件手がけていますが、古い建物の改修工事は非常に手間がかかりますよね。問題がある箇所は隠蔽されていることが多く、仕上げを剥がしてびっくりするような状況に出会うことがあります。築100年以上の本来は価値がある建造物でも、改修工事の大変さゆえに、建物を壊すしかないケースはよくあります。
本来はアメリカやヨーロッパのように、建物がストックされていくのが理想ですが、比較的木造建築が多く、地震も多い日本の場合、スクラップ&ビルドの流れが生まれたのも当然かもしれません。今後こうした技術でリノベーションがしやすくなり、資産価値の継続にもつながっていくことを期待します。
【技術者と世間の間にある情報のギャップを埋めたい】
岡本:その他にもデジタル技術を活用している事例はありますか?
石塚:そうですね。構造設計者のコミュニケーション向上にもデジタルを活用しています。私は入社1年目から、技術者と世間との認識のギャップに課題を感じていました。例えば、耐震・制震・免震の違いについて、技術者と一般の方々の理解には大きな差があります。
耐震構造は、地震の大きな力が外部から加わった際に、柱や梁を壊して力を吸収し、建物全体が潰れないようにする設計です。地震の時にどこから壊すか、どう壊れたら安全かを考えているのが、耐震構造なのです。

石塚:2016年4月に発生した熊本地震の調査に参加した時には、建物の柱にクラックが入ったり、壊れてしまった建物を多く目にしました。ある体育館は、天井が落下し、間仕切りが倒壊して復旧が難しい状況でした。しかし、この体育館の柱と梁は無損傷のため、建築基準法での耐震性は確保されたことになるのです。この状況を見たら、建物所有者や居住者は「耐震構造だから」と安心することはできません。一方で、同じ熊本地震で被災した免震構造のホテルは、積層ゴムがエネルギーを吸収し、無傷で通常営業を行っていました。

耐震構造の施設が建物の骨格は維持されているものの、天井や間仕切りなどが破損しているのに対して、免震構造のビルでは天井、間仕切りなどの構造物も含めた躯体全体はほぼ被害を免れていた。
石塚:私は、構造設計者として長年免震構造の設計に携わってきたので、免震構造を採用するメリットをよく知っています。この事実を多くの人に伝えるためには、一般の方々にも理解してもらえるように言語化・可視化することが必要です。そこで、当社ではデジタルツールを活用したいくつかの取り組みをスタートしています。
まず一つ目が、地震防災ソリューションを提供している白山工業株式会社の製品であるコンパクトな自走式の地震動再現装置「地震ザブトン」に乗り、VRゴーグルをつけて、耐震と免震の揺れの違いを体験できるシステムを作りました。揺れや物の落ち方、音などをリアルに体験することで、免震構造のメリットを知ってもらうことを目的にしています。

石塚:もう一つは、株式会社ブリヂストンとの共同実験です。被験者にウェアラブルセンサーを付け、心拍や脈を計測しながら、耐震構造と免震構造の揺れをそれぞれ体験してもらい、交感神経と副交感神経の働きを検証しました。結果的に、耐震構造に比べて、免震構造の方がストレスを感じにくいと数値的に示すことができました。今後この結果は、病院関係者が参加する医療関連学会にて発表予定です。トルコでは、病院はすべて免震構造で建設すると国が定めていますし、中国でも一定規模以上の病院は免震構造となっています。私は日本もそうなるべきだと考えており、今後も啓蒙活動を続けていく予定です。

地震の体験は、身体的外傷を免れても、PTSD等の精神的疾患、心不全・脳卒中等の発生確率を高める可能性がある。建物の免震化は、地震の揺れによるストレス回避の適切な手段だと数値化して証明した。
岡本:BIMと同様に、技術者と施主・一般顧客との間にある情報格差が大きいのですね。
石塚:その通りです。免震構造はコストが高くなると思われがちですが、ライフサイクルコストを意識している施主や、BCPに投資したい施主にはメリットがあります。企業の総務部門や維持管理部門に、建築に精通したアドバイザーがサポートに入るだけでも、設計の効率化、コスト、安全性が大きく変わると思います。
大江:建築は専門的な部分が多いので、建てるプロセスだけでなくその後の修繕のプロセスもどうしてもブラックボックスになりやすい業界です。技術的な部分は建築基準法に守られていますが、今後はコスト管理や維持管理といったビジネスに関わる部分にも専門家が入るべきだと思います。一般の方にも分かりやすく嚙み砕いて話ができる人才の必要性は高まっていますね。
【デジタルを積極的に活用し、エンジニアリング側からのアプローチも推進】
岡本:異業種とのコラボレーション事例について、他にも事例があれば教えてください。
石塚:当社では毎年、「KKE Vision」というプライベートイベントを開催しています。2022年6月のテーマは、「領域を超える」だったのですが、実際に今、自治体や異業種とのコラボレーションに積極的に取り組んでいます。

石塚:当社には、防災支援、情報通信、電波伝搬など、幅広いシミュレーションに対応できるチームがあります。建築分野で培ってきた実績を都市スケールでも活用できるように、今後はさまざまなプロジェクトの企画段階から入り、付加価値のある提案をしていきたいと考えています。
例えば、自然災害のシミュレーションでは、洪水や津波の動き、避難時の人流を可視化し、津波避難タワーの建設候補地の検討など、自治体の防災計画に役立てていただいています。

津波避難シミュレーション
石塚:その他にも、高層ホテルの屋上にあるプールのスロッシング解析や、さまざまな環境下での電波伝播解析、植物の育成シミュレーション等にも当社の技術を活用しています。シミュレーションできる事案はどんどん増えていますが、最も重要なのは課題設計です。何を目的としたシミュレーションかを把握し、活用できる技術をピックアップして、全体をコーディネートしていける人才は今後一層求められていくと思います。
構造設計技術者は、自分の技術領域を深める傾向が強いので、異業種とのコラボレーションを進めていく人が少ないです。意匠や計画側の方々はすでにデジタル技術を積極的に導入していますが、今後は我々のようなエンジニアリング側からのアプローチも進めていくべきだと考えています。デジタルを活用しながら領域を越境し、社会に価値のある取り組みができる人才も育てていきたいです。
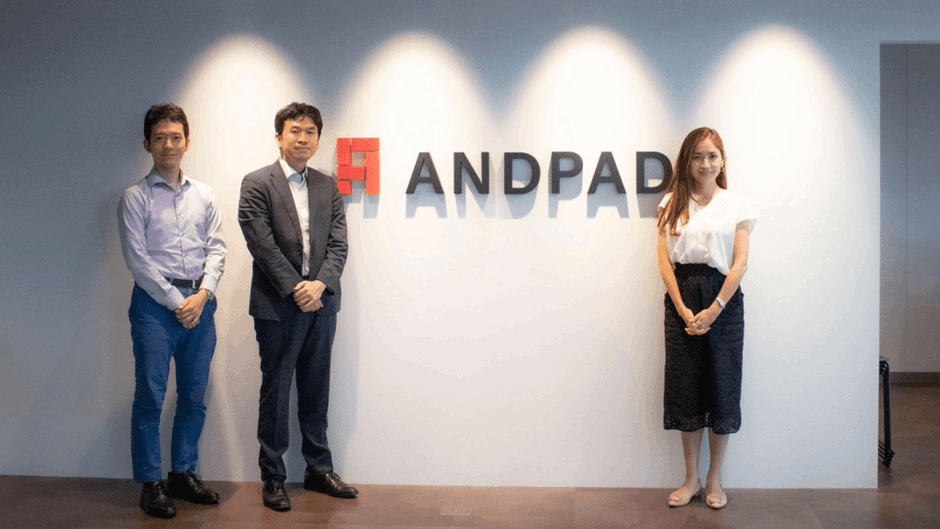
【おわりに】
後編では、株式会社構造計画研究所におけるBIM以外のデジタル技術の活用と、異業種とのさまざまなコラボレーション事例を中心にお話を伺いました。
BIM以外にも、これだけ多くのデジタル技術を活用して、実業務に役立てているのは率直に驚きました。また、設計事務所でありながら、数多くの異業種企業と積極的にコラボレーションしていく姿勢は、同社ならではの特徴だと強く感じました。
今後もさまざまデジタル技術を活用して、設計・建築のアップデートを牽引していただきたいと思います。
本研究所では、今後も建設DXに関わる様々なテーマを取り上げてご紹介しますので、引き続きよろしくお願いいたします!
