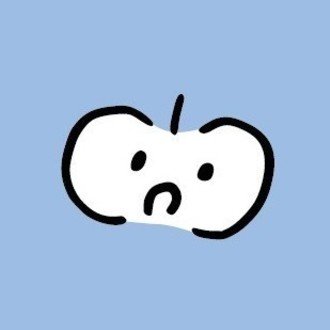エビデンスで社会をよくする:DSTサミット開催!
2023年7月31日に開催された「DST summit vol.1 エビデンスで社会をよくする」というイベントにお邪魔しました!
データの力で社会問題の解決に取り組んでいく「Data for Social Transformation(DST)」の主催イベントということで、今回は2022年度にスタートした研究の紹介と、2023年度から新たに始まる研究プロジェクトの発表が行われました。また、河野太郎デジタル大臣をはじめとする産学官のリーダーたちによる座談会「エビデンスが導く日本の未来」も行われました。

このnoteでは、DST summit vol.1 の開催当日の模様と、その関連情報をご紹介していきたいと思います!
■ 職場のエビデンスを作れ!
DSTは、錚々たる企業と研究者がタッグを組んで、データの力で社会問題の解決に取り組んでいくことを目的として、2022年に設立された団体です。
第1弾の研究テーマは 労働 で、主に職場での働き方や、生活との両立を支えるためのエビデンスをつくっていくための、以下の3つの研究プロジェクトが進められています。
当日は、各プロジェクトの紹介が、The Breakthrough Company GO代表・三浦崇宏氏の司会のもとで進められました。
小島武仁 先生(東京大学)たちが進める「新入社員配属の常識を変える! 希望をかなえ、生産性を高めるマッチング理論」
山口慎太郎 先生(東京大学)たちが進めているのは「『男性育休』で企業はどう変わるのか? 男性育休推進実証実験」
山本則子 先生(東京大学)たちが進めているのは、「介護離職者 10 万人をゼロに 介護離職防止プロジェクト」

■ 新入社員配属にマッチング理論を:小島武仁先生
まず最初に、複数の企業の新入社員配属に「マッチング理論」を導入し、その効果を測定することでマッチング理論の一般的な有効性に関するエビデンスの構築を目指すプロジェクトが小島先生によって紹介されました。
マッチング理論の導入によって、以下の効果が期待されています。複数の企業に導入し、データを蓄積して分析することで、確かなエビデンスとして実証しようという試みです。
新入社員の希望が配属に反映されることによる業務理解・キャリア形成に対する意識の向上
配属の決定プロセスの透明性が向上されることによる納得感の向上
配属の適材適所が実現することによる組織へのエンゲージメントの向上・離職率の削減
配属決定に必要な人事部門の工数削減
なお、この理論的な背景と導入事例の詳細は、『経済セミナー』2023年4・5月号の特集「経済学でビジネスを動かせ!」に収録された、小田原悠朗「企業の人事にマッチング理論を実装する——東京大学マーケットデザインセンターの実践」で紹介されています。こちらもあわせて、ぜひご覧ください!(現在は、特集のみをバインドして550円(税込)で提供している経済セミナーe-bookでも発売中です)
■ 父親の育休は企業にとってコストか投資か?:山口慎太郎先生
山口先生からは、男性育休の取得率向上を目指した実証実験に関する取り組みが説明されました。
日本の育休制度は、実はOECDによっても世界で最も手厚い制度として評価されています。それなのに、男性の育休取得率は国際的にみても極めて低いのが実情です。
そこで、複数の企業で育休取得の当事者と管理職に対して、男性育休取得の意義を説明する研修を実施し、取得促進効果を測定するための介入実験を行うプロジェクトが計画されています。
このプロジェクトを通じて、「制度自体は世界一なのになぜ日本では男性の育休取得が進まないのか?」「男性育休は、企業や職場にとってコストなのか、それともメリットはあるのか?」といった疑問への答えをみつけたい、との抱負も語られました。
特に短期的には職場にとってコストに感じられがちな育休取得ですが、実は長期的には企業・職場にとってもさまざまなメリットがあるかもしれません。個々人の生産性の向上や、男性育休を整備することで優秀な人材が集まる、といった可能性もあります。
しかしこれらはあくまでも、想像や個人の感想の域を得ません。なぜなら、世界的に見てもまだこうした問いに関するエビデンスが十分ではないためです。
近年のジェンダーギャップや少子化、家族政策に関する研究をサーベイした、Cortés and Pan (2022,JEL) やDoepke et al. (2023, Handbook of The Economics of The Family)でも男性の育児休業取得に関する議論が取り上げられていますが、まだまだ研究成果の蓄積が十分ではなく、研究途上という印象です。日本で、いくつもの企業で実施される介入実験を通じて確かなエビデンスが蓄積されていくことが大いに期待できるプロジェクトです。
なお、山口先生は著書『子育て支援の経済学』でも育休政策やジェンダー平等の意義を始め、保育・育児支援政策に関するエビデンスを凝縮して解説しています。こちらもあわせて、ぜひご覧ください!
■ 介護離職を防ぐために:山本則子先生
山本先生たちが取り組まれているプロジェクトでは、介護離職防止に関するエビデンスの蓄積を目指しています。もし、働いている人が介護を担わなければならなくなった場合に、どんな問題が発生するのでしょうか。
介護の役割を担うことで、離職をはじめ、仕事に大きな影響を及ぼすことがすでに知られています。また、日本では介護休業の制度は整いつつあるものの、その制度を利用する人がまだまだ少ないと言います。理由は、支援が少ないこと、カミングアウトが困難であること、両立可能な仕事分担がなされないことなどが指摘されいるそうです。一方で、介護保険サービス等のサービスを利用することで、介護と仕事の両立が可能であるとの指摘もなされています。
このプロジェクトでは、介護離職による経済損失が莫大なものになる可能性を指摘し、どうすれば介護と仕事を両立しやすい職場風土を作ることができるかを検証するために、複数の企業で実証実験を行っています。
具体的には、E-learningやワークショップを通じた介護への理解を醸成する介入プログラムを実施することで、心理的安全性の高い介護にやさしい職場風土をどうすれば醸成できるかを実証することで、エビデンスを蓄積していこうという試みです。日本では、今後高齢化の進行に伴い、介護が多くの人々にとってより身近な問題となっていきます。誰でも介護を担う可能性のある中で、仕事や生活と両立できるような社会を実現するための知見を蓄積していくこのプロジェクトは非常に重要です。
■ 2023年度スタートの研究プロジェクト
続いて、慶應義塾大学教授でDSTの共同代表理事である宮田裕章先生から、新たに2023年度からスタートする、以下の2つのプロジェクトについて発表があり、それぞれの研究計画が紹介されました。

「社会実装に向けた『効果の低い医療(low value care)』のリスト作成とその医療費に与える影響」
「食事体験の多面性が健康的な食事選択とウェルビーイングに与える影響:日本文化に根ざした新たなエビデ ンスの創出」
1つ目は、特に効果が低いというエビデンスのある医療行為(low value care)をリストアップしていこうという試みで、東京大学の宮脇敦士先生が概要をプレゼンテーションされました。
2つ目は、健康に良い食の実証ということで、実際の食事だけでなく、どう食べるか?(食事体験) 何を食べるか(食事選択)とウェルビーイングの関連をふまえたエビデンスを蓄積していこうというプロジェクトで、慶應義塾大学の野村周平先生が概要を紹介されました。
■ エビデンスが導く日本の未来~産官学のリーダーが語る
基調セッション「エビデンスが導く日本の未来〜産官学のリーダーが語る」では、
河野太郎・デジタル大臣
新浪剛史・経済同友会代表幹事、サントリーホールディングス株式会社代表取締役
津川友介・カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授
髙島 宗一郎・福岡市長
山田メユミ・株式会社アイスタイル取締役[モデレーター]
が登壇されました。

津川友介准教授(左下)、新浪剛史代表取締役(右下)
マイナンバーが普及した先に何が待っているか? という問いに対して、まずはデータを収集することの重要性が強調され、そのデータを有効に活用して、医療・介護を持続可能でより効果的なものとすべく、さまざまな議論が活発に展開されました。そして、DSTという民間団体の立場から、政策の現場でもデータやエビデンスの重要性を浸透させ、政策を改善しながら実施していくべく決意が語られました。
■ おわりに
以上、DST summit vol.1 の参加レポートをお送りしました。経セミにもと登場頂いている小島先生、山口先生の研究プロジェクトをはじめ、多くの興味深いデータを活用した研究が実施され、日本でエビデンスが積み上げられていくきっかけになりそうな予感がする動きだと感じます。今後も、DSTで行われるさまざまな研究プロジェクトをウォッチしていきたいと思います!
なお、ミクスOnline様の記事では「エビデンスが導く日本の未来像~産官学のリーダーが語る」の模様の方を中心に、当日の様子がまとめられています。
DSTのウェブサイトでも当日の様子がたくさんの写真とともに紹介されています。
最後に、『経済セミナー』最新号、およびバックナンバーの情報は、以下のサイトからご覧いただけます。こちらもよろしくお願いします!
いいなと思ったら応援しよう!