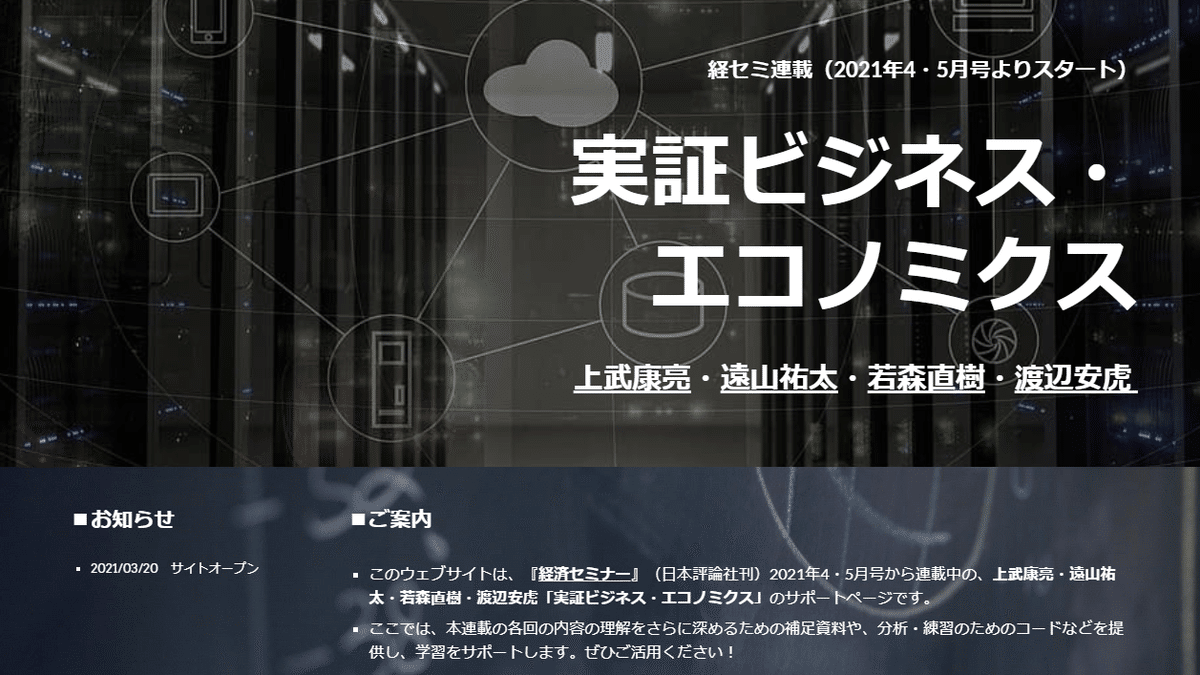「実証ビジネス・エコノミクス」に込めた想い(経セミ連載第1回より)
このnoteでは、『経済セミナー』2021年4・5月号からスタートの連載:
上武康亮・遠山祐太・若森直樹・渡辺安虎
「実証ビジネス・エコノミクス」
の第1回の内容(前半部分)を公開します!
第1回では、さんざん「役に立たない!」と言われてきた経済学、特にミクロ経済学が、データ分析と融合して役立つ強力な武器に変貌していること、実際に多くの現場で使われ始めていることを紹介しつつ、その具体的な道具立てとはどんなものか、何が・どのようにビジネスや政策の現場で使えるのかなどといった内容について、著者4名が熱い想いとともに語ります。それでは早速、ご覧下さい!


1 実証ビジネス・エコノミクス?
1.1 ビジネスと実証ミクロ経済学の出会い
「経済学は抽象的で役に立たない」。その代表格のようにいわれてきたのが、ミクロ経済学だろう。役に立つかどうかとその学問の重要性にはまったく関係はないだろうが、一般には役に立たないと思われてきたこととは裏腹に、ミクロ経済学者はミクロ経済学が役に立つ道具だと信じてきた。では、ミクロ経済学は役に立つのか役に立たないのか。当のミクロ経済学では、ミクロ経済学の有用性はどのように示すことができるだろうか。
ミクロ経済学的な考え方に基づけば、「役に立つのであれば実際にその道具は選ばれ、役に立たないのであれば選ばれない」といえるだろう。では実際に、ミクロ経済学はどこで使われているだろうか。
2000年代くらいまでは、「ビジネスに役に立つ経済学」といえばマクロ経済学とファイナンスの独壇場だった。民間企業で働く経済学博士号保有者の大半は証券会社やヘッジファンドに所属する人々で、その主な業務はマクロ経済モデルを用いた景気予測や、資産価格モデルを用いた金融商品の価格付けだった。そこでは、ミクロ経済学はまったく選ばれていなかった。
この状況が劇的に変化したのが、2010年代の10年であった。わずか10年の間に実証分析を得意とする多くのミクロ経済学者がIT企業、いわゆる「テック企業」で活躍するようになった。2010年代は、まさに「テック企業がミクロ経済学を発見した10年」であった。表1は、Athey and Luca (2019) に基づく2020年時点での経済学者チームを持つ企業のリストだ。上武(2020)によれば、Amazon.comではこの表をまとめた時点ですでに200人を超す経済学者が働いており、UberやNetflix等でも数十人規模の経済学者チームが存在しているという。これらの企業のうち、2010年時点で経済学者を雇用していたのはGoogleとeBayだけだったように記憶している。また、このリストからわかるように、米国の企業だけではなく、Alibaba(阿里巴巴集団)やライドシェアのDidi(滴滴出行)といった中国のテック企業も、経済学者チームを近年抱えるようになっている。これらのシーンで活用される経済学は、近年大きく発展してきた実証ミクロ経済学と呼ばれるアプローチである。

では、これらの経済学者が実際に使っている道具立てとはどんなものなのだろうか。この連載ではこの実証ミクロ経済学、特にわれわれが「実証ビジネス・エコノミクス」と呼ぶ道具立てについて説明していくことを主な目的とする。
1.2 ビジネスを対象とする実証分析
この連載は実証ビジネス・エコノミクスという、経済学に詳しい人には(そして経済学に詳しくない人にも)不思議なタイトルになっている。経済学に詳しい人の中にはビジネス・エコノミクスなどという分野はないという人もいるだろう。ここでは、ビジネスの意思決定に関するミクロ経済学、特に産業組織論と呼ばれる消費者・企業行動を分析する道具立ての中でも、データを用いて実証的に分析を行うものを総称して実証ビジネス・エコノミクスと呼んでいる。経済学にあまりなじみのないビジネスデータを分析するデータサイエンティストの方々や他分野の学生・研究者の方々にも興味を持ってもらえればと思い、筆者4人でこのように呼ぶこととした。なお、この連載では経営戦略やマーケティングのトピックを中心に扱うが、人事や組織の分野でも経済学による分析が盛んに行われている(注1)。
実際の中身は実証産業組織論という分野で開発されてきた道具立てだ。実証分析の対象をビジネスに置き、そのための道具を開発してきた「産業組織論」(Industrial Organization、通称IO。時に産業経済学、Industrial Economicsと呼ばれることもある)の中でも、データを用いて実証的に分析するのが実証産業組織論(以後、「実証IO」と呼ぶ)だ。
実証IOが開発してきたビジネスを分析するための道具は、実際にビジネスで利用される実証分析の道具でもある。IOは企業の行動を分析し、産業について考察し、競争政策や規制が企業や消費者にどのように影響するかを研究する分野だ。IOでは価格付け(差別化された財の価格付け、価格カルテル、抱き合わせ販売、サブスクリプションや後述するダイナミック・プライシングなど、さまざまなトピックがある)、参入・退出、生産性、投資、研究開発(R&D)、合併・買収といった企業行動のさまざまな側面が分析されてきた。近年では、理論研究からの知見を実際の産業・ビジネスに応用する形での実証分析が非常に盛んになりつつある (注2)。
IOの実証分析においては、いわゆる構造推定アプローチと呼ばれる方法が中心的な方法だ。この連載に登場する道具立ても、すべてこの構造推定アプローチに基づく。実際、Amazon.comに現在在籍する4人のチーフエコノミストのうちの3人(Patrick Bajari, Igal Hendel, Phillip Leslie)は構造推定アプローチを専門とするIOの研究者だ。では、この構造推定アプローチとはどのようなアプローチなのか。
構造推定アプローチの「構造」とは、ミクロ経済学モデルの「構造」を意味している。そして構造推定アプローチとは、実際の状況に応じて消費者や企業行動のミクロ経済学モデル(たとえば、「企業の新規市場への参入に関するゲーム理論モデル」)を書き、そのモデルそのものを推定するアプローチだ。構造推定アプローチでは、そのモデルに関わるすべてのアウトカム(結果)変数を利用してミクロ経済学モデルのパラメター(たとえば、効用関数や生産関数のパラメター)を推定し、この推定されたモデルを利用してビジネス戦略や政府の政策などが変更された場合に消費者や企業がどのように反応するかを考える反実仮想シミュレーションを行う。一方、これと対比されるのが誘導型アプローチと呼ばれるもので、この場合はモデルから誘導されるある変数YとXの関係について、YをXに回帰するなどして仮説検定するアプローチだ。
当然ながら、これだけの説明ではそのイメージがまったく沸かないだろうが、具体的なモデルとその推定については次回以降の連載で異なるタイプのモデルを用いて説明していくこととする。
2 この連載が目指すもの
筆者4人がこの連載を始めようと思った最大の理由は、研究にもビジネスにも、そして政策(特に競争政策)にも有用な実証IOの道具立てについて、具体的な応用例とともに学べるようなものを、より多くの方々に届けたいと考えたからだ。これまで、実際にモデルを推定するための具体的な手続きをわかりやすく説明している教科書はほとんど見られなかった。これは、実証IOの道具を学ぶには大学院の授業で論文を読みながらコードを書いて身に付けていくというのが標準的なトレーニング方法だったからだ。
この連載では、各トピックで用いられる標準的なモデルを、実際にコードを書いて推定することを想定しながら解説することで、大学院の授業で標準的なトレーニングを受けなくても独学で構造推定の手法を学ぶことができるような環境を提供する。それにより、経済学、実証IOの道具をビジネスや政策の現場で利用してもらいたいと、筆者らは考えている (この連載のサポートサイト[こちら]では、各回で用いる分析コードやデータ、補足説明などの資料を提供していく予定である)。
また、「経済学以外のバックグラウンドでデータ分析をしている方々に経済学的な構造推定のアプローチを具体的に伝えたい」というのも、筆者4人の思うところだ。ランダム化比較試験(A/Bテスト)やマッチング法などの計量経済学において発展してきた、いわゆる因果推論手法は、今ではビジネスデータ分析において幅広く活用されている(注4) 。その手法は背後にある変数間の関係(構造)については深く入らず、「ある施策XがあるアウトカムYに与えた影響」を極力シンプルな形で切り出す手法といえよう。しかしながら、因果推論的アプローチは「構造」まで深く踏み込まないがゆえに、企業-消費者や企業間の戦略的相互依存関係や、動学的関係を扱うことが非常に難しいという側面を持つ。当然ながらこれらの戦略的・動学的要素は実際のビジネスの現場における意思決定において非常に重要となるものであろう。
一方で、構造推定アプローチにおいては、データの背後にある消費者・企業の意思決定に踏み込んだうえでデータ分析を行う。その結果、データからより深い情報(たとえば消費者の潜在的な選好)を得ると同時に、「まだ実行されていない施策XがアウトカムYに与える影響」を評価するための反実仮想シミュレーションを行うことができる。ビジネス・政策課題を分析するうえで、因果推論手法を補完する非常に強力なツールと言えよう。この連載を通じて、「ミクロ経済学」と「データ分析」を融合した、「構造推定の力」を感じ取ってもらいたい。
3 構成の紹介
実証IOでは主に1990年代から2010年代にかけて、さまざまなビジネスシーンに対応するモデルとその推定手法が開発されてきた。この連載では、その中でも汎用性が高く、比較的すぐにビジネスで活用できると思われる4つの手法について、その応用例を紹介しながら詳しく見ていくことにする。4つの手法とは、「(差別化された財の)需要推定」「静学ゲームの推定」「経済主体単体での時間を通じた意思決定モデル(single agent dynamic model)の推定」、そして「動学ゲームの推定」だ(注5)。これにあわせて、この連載も大きく4つのパートで構成する予定である。各パートでは、まず分析手法の基礎を提供したうえで、実際にどのような問題解決に活用できるかを、応用事例を通じて解説する。ここではその導入として、それぞれの手法について、どのような場面で用いられるかをイメージしやすくするため、少しだけ紹介しよう。
企業が直面する課題の中でおそらく最も重要な問いは、ある財やサービスに「どのような価格を設定すればよいか」ということであろう。たとえば、もしあなたが新しい商品を開発し、それを売り出そうとする際に、どのような価格を設定するだろうか。おそらく、まずは類似の商品がないか、あるならどのような企業がそれを販売しているかを調べ、ライバル商品の価格を参考にしつつ、どの程度の価格を設定したらどの程度販売できるかを予想し、利潤を最大化するような価格を選ぶのではないだろうか。このときに一番重要な部分は「どの程度の価格を設定したら、どの程度販売できるか」であり、これはまさに経済学でいうところの需要関数である。つまり、企業にとって最も重要な課題である利潤を最大化するような価格を選ぶためには、需要関数を推定する必要がある。そのため、第1パートではまず、「(差別化された財の)需要推定」について取り上げる。
さて、需要関数は、誰のどのような行動から導出されるものだろうか。それは、消費者の購買行動である。たとえば、あなたが牛乳を買おうとスーパーマーケットに行った際に、ある食品メーカーのブランド牛乳Aが210円、スーパーのプライベートブランド牛乳Bが140円で販売されていたとしよう。あなたなら、どちらを購入するだろうか。安さに魅力を感じて牛乳Bを選ぶだろうか、それとも、価格はあまり気にせず牛乳Aを選ぶだろうか。もし牛乳Bが160円になったらどうだろうか。
このように、需要関数の背後には消費者1人ひとりの選択があり、そのような消費者の効用最大化問題に立ち戻り需要関数を推定するのが、構造推定のアプローチ方法である。
このようにして得られた需要関数には、企業の価格戦略やマーケティングの観点からの用途もあるが、日本の公正取引委員会を含む各国の競争当局が合併の影響をシミュレーションし審査する際にも用いられることがある(注6)。たとえば、互いに似たような自動車を製造・販売している巨大な自動車メーカーAとBが合併しようとした場合、競争当局は認めるべきだろうか。このような状況では、合併後にどのような価格が実現するかを考える必要がある。定性的には、今まではライバル企業が安くしてくる可能性を考慮して低い価格を設定せざるをえなかったかもしれないが、合併後にはライバルが(少なくとも1社は)減るため、今までよりも高い価格になると予想される。しかし、推定された需要関数を用いれば、新たな均衡を反実仮想シミュレーションで求めることができ、定量的な評価も可能になる。そして、もし合併後の企業の市場支配力があまりに高くなりすぎる(消費者余剰が毀損される)ようであれば、当局はそのような合併を認めないだろう。
続く第2パートでは、価格設定と並んで企業が直面する大きな課題の1つである、「ある市場、もしくは、ある分野に参入するか否か」という意思決定の問題を考える。たとえば、航空会社が新たな路線を就航させるか否か、スーパーマーケットが新しい土地に開店するか否か(開店するのであればどこに開店するのか)、病院が新たな高額医療機器(たとえばPETやMRIなど)を導入して画像診断分野のサービスに参入するかなどが、ここで考える企業の意思決定問題である。このような参入の意思決定を考えるうえで難しいのは、参入を考えている市場の特性(人口の規模や成長率など)だけでなく、ライバル企業との戦略的相互依存関係も同時に考慮しなければならない点である。たとえば、新たな路線での就航を検討する際には、他社が現在その路線に就航しているか(または同じタイミングで就航させる可能性があるか)などにも依存しているし、ある地域にコンビニエンス・ストアが出店するか否かは、おそらく他のチェーンが何店舗すでに開設しているかに依存するだろう。第2パートでは、こうしたゲーム理論的状況にある企業の行動から、企業の参入に関わる費用・便益を推定する方法を解説する。
さて第2パートまでは、消費者も企業も、将来のことを考慮せず、現在の効用や利益を最大化するような意思決定をしていると考えていた。一方、第3パート、第4パートでは、現在だけではなく、将来に何が起きるかも考慮したうえで意思決定をする消費者や企業について考える。経済学では、そのような問題を動学的意思決定問題という。
動学的意思決定と書くと非現実的なことのように聞こえるかもしれないが、われわれ消費者は日常的に、将来のことを考慮して動学的な意思決定をしている。たとえば、次の旅行のために航空券を購入するとしよう。航空券の価格は、企業が需要量等の状況にあわせて動学的に価格を設定するダイナミック・プライシングにより日々変動し、通常出発日の直前に高くなっていく。あなたは、いつ航空券を購入するだろうか。なるべく安い価格で買いたいと考えるのが当然ながら、今日の時点で明日の価格は正確にはわからないので、自分の予想する明日の価格と現在の価格を比べ、底値がついたと予想したタイミングで購入するだろう。ただし、もし今日買わないと、同じ座席は明日には他の客にとられて買えなくなってしまうかもしれない。このようなとき、消費者は将来を考えながら購入の意思決定をしている。
また、企業も同様に将来を考慮して意思決定をしている。たとえば、あなたがハンバーガーチェーンのマネージャーで、新たな出店計画を練っているとしよう。当然、需要の多そうな地域に出店したいと考えるだろうが、もしかしたらライバル企業も同様に考えており、結果として近接地域に出店してしまい、競争が激化してしまうかもしれない。また、同地域にはすでに自社が出店しており、同じ地域にさらに出店すると同チェーン内でカニバリゼーション(共食い)をしてしまうかもしれない。このような問題を考える際には、現在の出店の意思決定が将来の意思決定に与える影響を考慮しなければならない。
上記の例のように、消費者も企業も将来を見越して行動している状況において、最適なダイナミック・プライシングはどのようなものか(1つ目の例)、またはライバル企業が将来の出店計画を発表し、コミットしてきた場合にどのように戦略を立てればよいか(2つ目の例)などを考えるのが第3パート、第4パートの目的である。第3パートでは、1つ目の例のように他の消費者や企業の影響を無視できるような、一人の意思決定者の問題を考え、第4パートでは、2つ目の例のように、企業間の明示的な戦略的相互依存関係がある状況について考えていく。
これらの例は、反実仮想的な戦略や政策の効果を検証するという意味で、第1パート、第2パートで扱ってきた問題と本質的に同じであるが、違うのは消費者や企業の行動を表す構造モデルにおいて、明示的に将来の影響を組み込む必要があるという点である。そのようなときに役立つのが動的計画法と呼ばれる方法である。消費者や企業の動学的意思決定問題を、動的計画法を用いてモデルに落とし込むことにより、データから構造パラメターを推定することができる。動的計画法の基礎は、第3パートで詳しく解説する予定である。ここまで来ると、もう実証IOのフロンティアである。その先は、最新の論文を自力で読み進め、実際のケースに適用することが可能になるであろう。
4 準備運動:離散選択モデルの基礎
これまでに紹介してきたように、この連載では消費者・企業がさまざまな場面で直面する意思決定問題の実証分析を取り上げて行く。その中でしばしば用いられるのが、離散選択モデルと呼ばれるフレームワークである。離散選択モデルは消費者・企業の意思決定分析に限らず、応用範囲が非常に広いフレームワークである。
本節では次回以降の連載への準備運動として、離散選択モデルの基礎について解説する。次回以降では、今回導入した離散選択モデルがさまざまな形で拡張される。そこでの分析事例を通じて、ビジネス課題の分析にどのようにして用いられるかを実感できるだろう。
離散選択問題とは、……
……[続く:以降は本編をご覧ください]……
注1) 企業内組織・人事における実証分析に関しては大湾(2017)を、理論分析については伊藤・小林・宮原(2019)を参照されたい。
注2) この連載では、必要に応じて産業組織論の理論を紹介する。参考になる学部レベルの産業組織理論の教科書としては花薗(2018)や小田切(2019)、大学院レベルとしてはTirole(1988)が挙げられる。
注3) この連載のサポートサイト(こちら)では、各回で用いる分析コードやデータ、補足説明などの資料を提供していく予定である。
注4) 因果推論アプローチの入門として伊藤(2017)、またビジネスへの応用を取り上げている文献としてタディ(2020)や安井(2020)が挙げられる。
注5) この連載ではカバーできない主要な手法には、生産関数の推定とオークションの推定がある。生産関数の推定についてはAckerberg et al. (2007) の2節や中村(2014)を、オークションの推定についてはPaarch and Hong (2006) やAthey and Haile (2007) などを参照していただきたい。
注6) ただし、実際の政策現場では時間的な制約から、もっと簡便な手法が用いられることも多い。
■サポートサイトも充実!!
以上、本連載のねらいや著者たちの想いをお伝えする第1回の前半部分をご覧いただききました。このあとは、準備運動として、消費者が携帯電話端末を選ぶシーンを題材に離散選択モデルの基礎の基礎を解説しています。次回以降解説される実際の分析手法の土台となる重要なパートになりますので、ぜひ本編をご覧いただければと思います。
さて、本連載では解説とともに、以下の【本連載サポートサイト】にて、実際に用いられた分析プログラムを提供し、読者の皆さまも実際に分析を体験しながら学べる環境を整備したいと考えています。使用ソフトは、Rを予定しています(追って、JuliaやMatlab等で補完することも検討中です)。
https://sites.google.com/view/keisemi-ebiz/
以上、『経済セミナー』2021年4・5月号からスタートの連載、上武康亮・遠山祐太・若森直樹・渡辺安虎「実証ビジネス・エコノミクス」のご案内とともに、第1回の内容を少しだけお届けしました。
今号の特集は、「経済学でデータを活かす」というタイトルで、渡辺安虎先生が取締役を務める東京大学エコノミックコンサルティングのチーフエコノミスト、宮川大介先生も登場しています。本連載とあわせて、ぜひご覧ください!!


いいなと思ったら応援しよう!