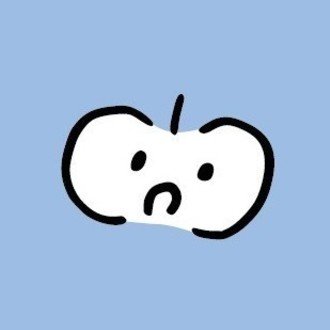アジア経済研究所 夏期公開講座 潜入レポート!
2023年8月7日に開催された、ジェトロ・アジア経済研究所・夏期公開講座「次世代の実証開発経済学」に参加してきました!
■アジア経済研究所 夏期公開講座とは?
ジェトロ・アジア経済研究所は、地域・政治・経済などに関する注目度の高いテーマを取り上げた公開講座を毎年行っています。
所属研究員や大学研究者などの講師陣が、直々にわかりやすく解説をしてくれるのが大きな特徴です。
この記事を書いているSは、「開発経済学、アジア経済に関心があり、卒業論文のテーマにしたい」と考えている学生はぜひ行くべし!という感想を持ちました。
大規模な講演会形式ではなく、少人数のワークショップのような形で行われていますので、講師との距離が近い!
講座を聴講して自分の関心のあるテーマについて全体像をつかんだのち、講師の先生方に質問したりテーマについて相談したりすることも比較的可能なのではないでしょうか。
■書籍:『次世代の実証経済学』
今回お邪魔した講座は、弊社から7月に刊行した書籍『次世代の実証経済学』の内容に基づいています。
本書について簡単にご紹介します。
本書を一言で表すとしたら、「第一線で活躍する実証経済学者から次世代へ向けた壮大な手紙」です。
「理論」と「実証」という経済学研究における2本の柱のうち、実証の存在感が大きくなってきたのは比較的最近のことです。
特に2010年代以降から現在にかけては、RCTや自然実験を用いて因果関係の検証を行う論文が開発・労働分野を中心に増えてきています(後述の大塚先生のご報告でも言及されていました)。
こうした傾向は近年のノーベル経済学賞の動向を見るとお分かりいただけると思います。
2019年はRCTを用いた開発分野での研究功績、2021年は自然実験など因果推論の手法を用いた労働分野での研究功績に対して賞が贈られています[注1]。
一方で、実証分析に関する手法の進化や実証論文の急激な増加がもたらしたものは、メリットばかりではありません。
では、どのような課題があるのでしょうか?
本書では、日本の実証経済学をリードする研究者たちが各分野(開発、労働、貿易、行動、経済史、マクロ)における実証研究の手法や現状、課題を概観し、今後の実証研究はどうあるべきかについて議論をしています。
議論の中身が気になる方は本書をお手に取ってみてください↓
■公開講座の様子
今回の公開講座では、以下の3名の先生方がご登壇されました。
澤田康幸先生(東京大学大学院経済学研究科教授)
高野久紀先生(京都大学大学院経済学研究科准教授)
大塚啓二郎先生(ジェトロ・アジア経済研究所新領域研究センター 上席主任調査研究員、神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授)
■実証経済学における「世代交代」:澤田康幸先生

まず最初に、『次世代の実証経済学』の第1章の内容をもとに澤田康幸先生に発表いただきました!
澤田先生には、各「世代」における実証方法の変遷やそれに伴う問題を整理し、新しい世代における実証研究の展望を解説していただきました。
本書全体を貫く大切な論点です。
これまでの古典的な計量経済学を用いる「第一世代」には因果推論上の課題が、RCTを取り入れた「第二世代」には研究の再現性や実践上の課題がそれぞれあり、「第三世代」は産官学民の連携強化などさまざまな主体を巻き込んで建設的な実証を積み重ねていく必要性を強調しておられました。
より詳しい内容は本書第1章をご参照ください!
■実証開発経済学の手法の進化と今後の課題を整理!:高野久紀先生

続いて、高野先生には実証(開発)経済学の手法面での発展や研究の潮流についてより具体的に解説をしていただきました。
RCT革命前夜から革命後現在に至るまでの実証研究手法の変遷、構造推定アプローチの概要、研究関心・問いの変化、データ利用における革命など、重要なトピックが盛りだくさんでした。
ボリュームのある内容でしたが、大変コンパクトにまとめられていました!
詳細が気になる方は本書第5章へ!
■実証経済学の未来は?:大塚啓二郎先生

最後に、第3章と終章の内容について大塚先生にご報告いただきました。
RCTや自然実験を用いた近年の実証経済学の動向、実態認識(≒ドメイン知識)や多様な連携の重要性など、本書の核ともいえる重要な視点と今後の実証研究の展望について丁寧に解説していただきました。
主要ジャーナルにおけるRCT・自然実験の論文数の変化等のデータもお示しいただき、信頼性革命の前後で実証経済学がいかに変容したかがよく分かる内容でした。
大塚先生は実証における「実態認識」の重要性を長きにわたって主張してこられたわけですから、説得力が違います。机の上でデータばかり見ていた大学院生の頃の自分に聞かせたい内容でした。
※個人的には、最近のジャーナルの査読は減点主義的で、面白いが粗い論文が少なくなったというお話が面白かったです。
詳細は本書第3章・終章をチェック!
■おわりに
編集作業を通じて『次世代の実証経済学』を最初から最後まで読んでいましたが、先生方からのご説明を聞くことによって新たに学ぶことがありました。
今回ご登壇いただいた先生方、ジェトロ・アジア経済研究所の皆様には心より感謝申し上げます。
■関連記事・書籍
『次世代の実証経済学』はこちら↓
本書の企画の元となった記事は『経済セミナー』2022年8・9月号にあります↓
大塚啓二郎特命教授「瑞宝重光章」受章記念シンポジウム
私の目指す開発経済学
……大塚啓二郎・橋野知子・園部哲史・黒崎卓・澤田康幸
※注1:2019年はアビジット・バナジー、エスター・デュフロ、マイケル・クレマーの3氏、2021年はデービッド・カード、ヨシュア・アングリスト、グイド・インベンスの3氏がノーベル経済学賞(スウェーデン国立銀行賞)を受賞。
いいなと思ったら応援しよう!