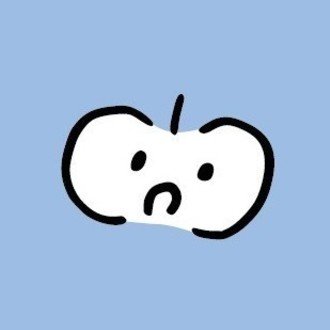齊藤誠「『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』を読む」
この note では、2025年1月発売:
佐々木周作・大竹文雄・齋藤智也
『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』
の書評を公開しています!
評者は、名古屋大学の 齊藤誠 先生です。
『行動経済学で「未知のワクチン」に
向き合う』を読む
齊藤 誠
Saito Makoto
名古屋大学大学院経済学研究科教授
1992年、マサチューセッツ工科大学経済学部博士課程修了(Ph.D.)。住友信託銀行調査部、ブリティッシュコロンビア大学経済学部助教授、京都大学経済学部助教授、大阪大学大学院経済学研究科助教授、一橋大学大学院経済学研究科教授などを経て、2019年より現職。
日経・経済図書文化賞(2001年)、日本経済学会・石川賞(2007年)、毎日新聞社エコノミスト賞(2008年)、全国銀行学術研究振興財団賞(2010年)、石橋湛山賞(2012年)、紫綬褒章(2014年春)。近著に、『財政規律とマクロ経済――規律の棚上げと遵守の対立をこえて』(名古屋大学出版会、2023年)がある。
工夫された章立て
本書は、新型コロナウィルスに関する政策研究に実際に従事した研究者の貴重な証言である。本書の大きな特徴であるが、著者たちが取り組んだ行動経済学に基づく政策研究を詳しく紹介するとともに、読者がより客観的なコンテキストに彼らの政策研究を置くことができるように章立てが工夫されている。
本書の章立てでは、政策研究のリーダーであった佐々木が第1章から第9章の主要章を執筆している。第1部から第3部には、新型コロナ対策分科会の委員であった大竹が執筆した「大竹文雄の目」というセクションが設けられている。また、第2部から第4部の「当時を振り返る」というセクションと第10章では、佐々木と大竹に感染症の専門家である齋藤が加わった鼎談が収められている。
佐々木の主要章、大竹の回顧、齋藤の加わった鼎談という3種類の章立てが、彼らが取り組んできた政策研究を多角的に評価する視点を読者に提供している。
政策ニーズに応えてきた行動経済学的研究
彼らの政策研究は、ナッジと呼ばれる行動経済学のコンセプトを用いながら政策ニーズに首尾よく応えてきた。ここでいうナッジについて、佐々木の説明を引いてみよう。
人々の心理的・行動経済学的特性をふまえて、またはそれを活用して、強制することなく、高額の金銭的インセンティブを用いることもなく、自分自身や社会にとって最適な選択を人々が自発的に実行できるように促すためのメッセージやデザイン・仕組み・制度(87頁)
政府がファイザー社などとワクチン供給に合意すると(2020年7月)、ワクチンが実用化する前から接種意向に関する研究に着手した。彼らは、まず、人々の接種意向がかなり高いことを示した(第2章)。
また、人々の自律性を妨げることなく接種意向を高めるためにさまざまなナッジ・メッセージを提案してきた(第3章)。そこでは、社会比較メッセージ、利得フレームの社会的影響メッセージ、損失フレームの社会的影響メッセージという3つのナッジ・メッセージが検討されている(88頁)。
21年2月から医療従事者に、次に4月から高齢者にワクチン接種が開始されると、政府は、5月に「1日100万回接種」を目標とした。彼らは、政府目標に先行して接種意向が実際の接種につなげるためのナッジに関するフィールド実験に挑戦した(第5章)。
政府が6月に65歳未満の二回接種が10~11月に完了するまでには、ブースター接種にナッジが必要かどうかを検討していた(第7章)。
9月になると、政府は「ワクチンを2回打った人について、まさに将来の絵姿がどうなるかというところを早くお示しいただきたい」と分科会に諮問した(137頁)。第2部の「大竹文雄の目」によると、大竹たちは、行動経済学というよりも、経済学的な根拠から、ワクチン・検査パッケージ(接種や陰性の証明書)を条件として行動制限を緩和することを提案した。
自らの成功を相対化する著者たちの姿勢
こうして内容を紹介すると、本書は、行動経済学に基づいた政策研究の成功例を著した書籍と受け取られるであろう。本書はまさにそうした性格の書籍なのである。しかし、本書のすばらしさは、成功事例の紹介にとどまることなく、著者たちが自らの政策研究を相対化する視点を提供しているところである。
大竹は、分科会で主張がことごとく対立した押谷仁委員の意見を詳しく紹介している。齋藤は、感染症の専門家として新型コロナワクチンをめぐる状況を率直に語っている。佐々木も、経済学研究者としての戸惑いを随所で記している。
おそらく、新型コロナワクチンをめぐる政策議論を難しくした背景として、当該ワクチンは、発症予防や重症化予防の効果があるものの、感染予防効果が期待できないことが当初から認識されていたからであろう。先に引いたナッジの定義にそっていうと、「自分自身や社会にとって最適な選択」が大変に見えづらい状況に、私たちの社会は直面した。
大竹が詳しく引いているが、押谷は分科会で「これまで人類の歴史の中で十分な感染阻止効果を持つ呼吸器ウィルスに対するワクチンができたことがないという事実がある」と発言している(42頁)。押谷のこうした認識に基づけば、ワクチンを新型コロナ感染対策の主軸に置くことができない。事実、押谷は、クラスター対策(積極的疫学調査)を感染症対策の中核として展開してきた。
佐々木は、研究の当初、開発過程のワクチンに感染予防効果がないことに戸惑ったようである。彼が困惑したのは、ワクチン接種に関する経済学的研究のほとんどは、感染予防効果を備えているワクチンが感染リスクを低減することが前提とされていたからである。しかし、佐々木は、すぐに重症化予防効果を中心にワクチン接種を考えるようになった。
大竹も、当初から、ワクチンの感染予防効果の欠如を正確に認識していた。しかし、押谷とはまったく反対に、重症化予防効果があるのであれば、重症化リスクの高い高齢者に優先して接種する感染症対策を展開していけばよいと考えた。
大竹は、接種過程でアルファ株には感染予防効果もあることが確認されると、青壮年へのワクチン接種や、彼・彼女らの接種を促すワクチン・検査パッケージを提言した。一方、デルタ株やオミクロン株に感染予防効果がないことが判明すると、大竹は再び高齢者接種に絞ることを奨める。
しかし、佐々木や大竹がワクチン接種を主軸に感染症対策を考えることができたのも、政府がファイザー社などとワクチン供給を合意し、国民への接種を推進していく政治決定をしたからである。そうした決定の下でワクチン確保やワクチン接種に対する多額の予算が確保され、被害者の救済措置が講じられた。
クラスター対策とナッジの補完の可能性
佐々木や大竹は、ワクチン接種の政治決定を前提に行動経済学研究者として最善を尽くし、押谷は、感染症研究者としてその前提そのものに異議申し立てを行ったといえないか。逆にいうと、佐々木や大竹が感染症研究者でなかったからこそ、そうした前提に柔軟に立つことができたのかもしれない。
感染症研究者である齋藤は、「世界中でワクチン接種が始まったとして、どこかで重大な有害事象が報告されて接種が止まること」を深く懸念していた(132頁)。そうした事態になれば、「政府は国民を人体実験に使おうとした」と厳しく批判されかねない。
また、齋藤は、「日本はかなり感染を抑えることに成功していたこともあって、感染の影響やワクチンの効果がよくわからないという状況だった」と述べている(299頁)。海外の研究者たちは、日本の感染事情を配慮しながらワクチンの効果に関して慎重な書きぶりをしていた佐々木たちの論文を不思議に思った(297~8頁)。
確かに、日本でも重症患者や死者が町にあふれかえっていれば、人々は、ワクチンの効果を信じ、ワクチン接種を必死で望んだであろう。多くの日本人が接種するかどうかを迷い、ナッジが有効である余地があったのも、感染抑制に成功していたからこそと考えることもできる。押谷たちが推進したクラスター対策は間違いなく感染抑制に貢献してきた。
こうして見てくると、押谷たちのクラスター対策と佐々木たちのナッジ・スキームは、補完していた可能性もある。本書が魅力的なのは、ワクチン接種をめぐって異なる分野の研究者たちが、自分たちの領分で必死に戦ってきたことを記録しているからである。
(『経済セミナー』2025年6・7月号掲載予定の同名記事を先行公開)
書籍情報のご紹介
『行動経済学で「未知のワクチン」に向き合う』の詳細は以下のサイトをご覧ください:
同書の「プロローグ」と「あとがき」は、以下の経セミ note にて公開中です:
主な目次
プロローグ(佐々木周作)
第1部 「未知のワクチン」にどう向き合うか?
第1章 「未知のワクチン」に向き合うための基本道具
[大竹文雄の目] ワクチン導入をめぐる政策議論
第2部 「未知のワクチン」の接種開始前夜
第2章 「接種を受けるつもり」を測定する意義〜たかが意向、されど意向〜
第3章 自律性を阻害せずに接種意向を高めるナッジ・メッセージの探究
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] エビデンスのつくり方と使われ方
[大竹文雄の目] 接種勧奨と出口戦略をめぐる政策議論
第3部 「未知のワクチン」の接種はじまる
第4章 接種意向は水物か?〜実際の行動とのギャップ〜
第5章 ナッジは実際の行動も促すのか?〜フィールド実験による挑戦〜
第6章 ワクチン接種の意外な効果
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] パンデミック下の研究開発と社会実装
[大竹文雄の目] ワクチン効果の変化と行動制限の必要性をめぐる政策議論
第4部 ワクチン普及後の世界〜「未知」から「既知」へ〜
第7章 ブースター接種にナッジは必要か?
第8章 ワクチン接種者と非接種者の分断と共生
[佐々木・大竹・齋藤の「当時を振り返る」] ナッジの意味とは
第5部 ネクスト・パンデミックのために「行動経済学+感染症学」ができること
第9章 将来のパンデミックに向けた10の政策研究アジェンダ
第10章 政策研究アジェンダの「実現可能性」を議論する
あとがき(大竹文雄、齋藤智也)
いいなと思ったら応援しよう!