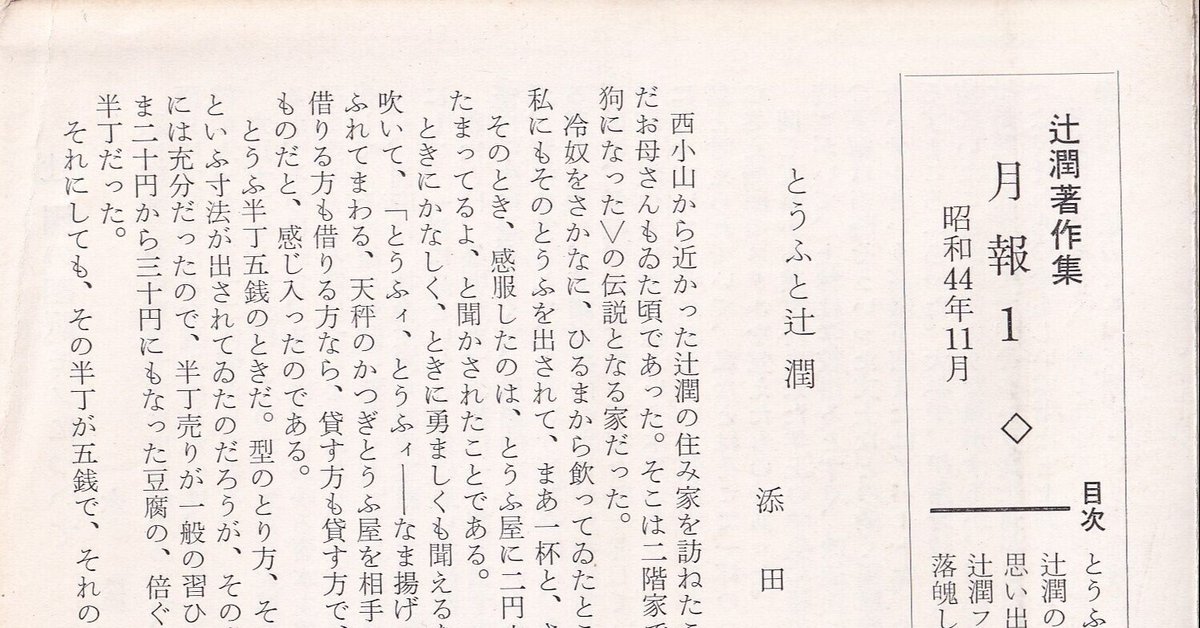
辻潤著作集月報1
親記事>『辻潤著作集』月報の入力作業と覚え書き
――――――――――――――――――――――――――――――――――
辻潤著作集 月報1
昭和44年11月
オリオン出版社
東京都中央区銀座8丁目19番地3号・和泉ビル
とうふと辻潤
添田知道
西小山から近かった辻潤の住み家を訪ねたことがあった。まだお母さんもゐた頃であった。そこは二階家で、あとで、<天狗になった>の伝説となる家だった。
冷奴をさかなに、ひるまから飲ってゐたところだったので、私にもそのとうふを出されて、まあ一杯と、さされた。
そのとき、感服したのは、とうふ屋に二円六十五銭、払ひがたまってるよ、と聞かされたことである。
ときにかなしく、ときに勇ましくも聞えるあの三角ラッパを吹いて、「とうふィ、とうふィ――なま揚げェがんもどき」とふれてまわる、天秤のかつぎとうふ屋を相手の話なのである。借りる方も借りる方なら、貸す方も貸す方で、ともに天晴れなものだと、感じ入ったのである。
とうふ半丁五銭のときだ。型のとり方、その切り方で、一丁といふ寸法が出されてゐたのだろうが、その半分で、一人の用には充分だったので、半丁売りが一般の習ひになってゐた。いま二十円から三十円にもなった豆腐の、倍ぐらいもあるのが、半丁だった。
それにしても、その半丁が五銭で、それの二円六十銭といふと、五十三個のとうふをタダで食べてゐたわけだ。(あとで払ったかどうかを知らないので)とうふは安くて、うまくて、栄養価もあった。<庶民>といはれるともがらは、みな豆腐を愛したが、辻は江戸っ子の流れを濃くひいてゐたのだから、よけいとうふは好きだったろう。
帰るときに、いっしょに出てきた。歩いてゐると、伊庭孝のところへ寄ってみようと言ひ出した。ちょうど私の道順だった。
伊庭孝の玄関は鍵がかかってゐて、訪っても返事がなかった。石段を下りようとすると、辻が枝折戸をあけて、台所ロヘ行き、戸に手をかけると、するするとあいた。そこから入って行った辻が、今度はその中側から、顔を出し、手招きをした。
「居るよ、ゐるよ。居たよ、ゐたよ。麻雀してる。おいでよ、おいでよ」
私も伊庭を知らないわけではなかったにしろ、台所からあがる気にはなれなかった。
「玄関から入れない家へはあがらないよ」と石段を下りた。だからそのあとの座敷の模様は知らない。
この手は私の家でもよくくらったものだったが、それはそれとして、あのとうふ好きの辻潤が、今日現在の、アメリカ大豆の、箸にもかからぬふにゃふにや豆腐を、食はされないですんだのは、まだしもの、せめてもの、幸せであったのかもしれないなどと思ったりもする。なさけない日々である。(作家)
辻潤の翻訳モノについて
末松定
私は昭和三年に東京大学を出たのであるが、私などが少し真面目に文学書などを読み出しだのは、それより七年前、高等学校に入った大正十二年頃からである。
大正十二年といえば、その夏、東京の大震災のあった年であるが、その後から、日本は、いわゆる資本主義社会の矛盾の様子を至るところ露呈するようになり、社会主義運動なども活発化して、その波の雑誌「種蒔く人」などの発刊も見るに至った。
が、当時は、社会主義も無政主義心共産主義もいっしょくたにして、一様に赤といわれ、赤は悪い奴に決っていた。
私などは、昼頃起きて学校に一丁顔を出す程度の、単なる怠惰な学生に過ぎなくて、思想的にどうということはなかったが、青年の常として、こういう反社会的の、良風美俗に反抗する底の人物に、英雄崇拝的のあこがれを感じたものであった。当時は、学校附近の本郷の下宿を転々としていたわけであるが肴町の坂の上に南天堂という本屋があって、その二階が喫茶店になっていて、そこがそういう無政府主義者やテロリストの巣窟と考えられていて、私などはそこで一杯のコーヒーをすするのさえ無限のスリルを覚えたものであった。
同じ五高から英文科に来た年上の学生に徳広巌城(今の上林暁)がいて、上林は学校出るとすぐ、改造社に入ったが、上林の下宿は当時そういった文士などの多く部屋借りしていた南富士ホテルという高級下宿またはアパートを、つい鼻の下に見降ろすところにあった。大杉栄、伊藤野枝なども、たしかこの下宿にいたことがあるような気がするが、確かではない。上林も改造社に入り立てで、そういう文士連がまだ珍らしかった時代でよくそれらの珍らしい噂話などを聞かされたものであった。
それから間もなく、神近市子が、大杉の咽喉(のど)を、大森の宿で、短刀でもって刺すという、当時としては驚天動地の件事が起きた。私などもやはり、日木人の判官ビイキで、この時は英雄大杉よりも、フラレ男の辻潤の方に万腔の同情をそそいだものであった。
というのは、私はそれ以前から辻潤の文章、それも本人の書いた「ですべら」などというのは勿論であるが、それ以上にその翻訳。スチルネルの「唯一者とその所有」、ジョージ・ムアの「一青年の告白」、ド・ケンシーの「阿片溺愛者の告白」、ロンブロオの「天才論」、特にこの四冊はことの外愛読していてそののちの自分の人生論的にも、生活的にも可なり強い影響を興えているのではないかと思えるほどであったのでそのショックはかなり大きかった。
そういそ意味では、中でもスチルネルの本が一番強い効果があったようで、自分の青年時代を取り扱った「二十才の日記」という日記体の小説のなかにも、辻潤訳のスチルネルのこの本を読んで感激するところを、約一頁近くにわたって縷々として記述しているほどである。(作家・北九州大学教授)
思い出話
山本正一
第一話、ある日(夕方)マコト君が彼のパパからの使として一ひらの紙ぎれを持参し、私にすぐ来てくれるようにとのこと、はて何事であろう、とにかく同君に従い洗足の家、即ち天狗になった家の二階へ案内された。階下には品のいいお婆さんと、キヨさんが子供と寝ていたように思う。
彼、辻さんは寝そべつて煙草をふかしていたが、私の顔を見上げると起き上りながら至極まじめに「君達の月下氷人をつとめてあげるよ」そんな意味のことをいわれたのにはいささか面喰らった。君達というのは私と丁女、即ち今は私の女房のことなのである。
さて、私がどんな返事をしたかはきれいに忘れてしまったが当時私達の間柄を知る筈もない辻さんが、なぜ急にあんなことをいい出したのかというギモンは未だに解けずにいる。またあの時二階の壁にかかっていた半折の軸、(文句は忘れたが辻さん自筆の)まっ赤に額取りされた軸の印象が妙に脳裡にこびりついて離れない。
第二話 昭和八年の正月(八月に慈雲堂病院に入院している)即ち辻さんが四十九歳の正月は、当時私がいた芝白金の家(第一話のマコト君が来た家)で迎えた筈である。というのはその時一杯気嫌で書いてくれた半折「もろもろの垢をおとせるおさな児の四十九歳ということ勿れ」という狂歌と、居合わせた義弟の敏郎のために「新しき年の初の十四男かな」という狂句が手元に残っているからである。
狂句といえば、義弟一彦が高田の馬場で古本屋をはじめたとき、一六堂という屋号をつけてくれ、半紙に「一六と張ってみたれど空手なり」と書いたのが煤けたままに残っている。
第三話 「癩人の独語」出版記念会が新宿の白十字楼上で催された時のこと、会もすでに終りに近づいた頃、辻さんが席を起って階下におりで行ったようであったが、まもなく数人の浮浪者風の若者を連れて席に戻り、残りの飲物や食物をふるまう異様な光景が出現した。思うにこれらの人達は会費が払へなくて、住来で今日の祝賀会に参加した人達なのであった。
第四話 右と回じ会での席上、私の隣に座った老年の婦人が話に立った萩原朔太郎を指してあの人はどんな人かと聞くから詩人ですよと答えたら、萩原氏に向って詩吟を希望した。どうやらこのご婦人は詩吟をやる人に間違えたらしい。辻さんの交友の広さが偲ばれるのである。
第五話 目黒駅近くの屋台で辻さん私と友人三人で泡盛を呑んで、さてこれから品川へ行こうということになった、女郎屋である。三人の持金集めて五円、これでは駄目だと思ったが辻さんはもう円タクを呼び止めていた。辻さんは私達を待たしておいて、片っ端から交渉して歩いたが素気なく断られた。何もいひ出さないうちに、手まねで敬遠する楼もあった。辻さんの異様な風体におそれをなしたのである。慚くのことで五円足らずで三人上楼することが出来たが、ムロン割部屋である。あの夜一番元気のあったのは辻さんであったが、辻さんの長いアゴヒゲが相方の顔に垂れ下るのをムズがるアバズレ声が忘れられない。
第六話 辻さんの訪問がはげしくなるにつれ、私の母は不快の情を顔にするようになってきた。ことに戦争になってからはノミやシラミの類の始末に困った。しかし、それ以上にいけなかったことは、ある晩のこと蚊帳の中の母を襲ってさんざ困らせてからである。別の日丁女も組伏せられ悲鳴をあげたことがあり、乳房に何ヶ所かの歯の跡が残っていた。かような行為が少量の酒でも突発するようになったのは、明らかに精神の異常を示したものと思はざるを得ない。(寮管理人)
辻潤ファン
高木護
昭和七年のこと、パリから松尾邦之助氏は、「セルパン」の九月号(第十九号)に「少数者辻潤」なる一文を寄稿して、そのなかで、「辻潤は″日本の宝だ”といっておられる。何で、辻潤が日本の宝であるかということは、わたしがここで書くまでにないことだろう。その一文には、日本のジャーナリズムよ辻潤をもっと大事にしてほしい――という松尾氏の切なる願いがこめられている。
わたしが辻潤のなまえを耳にしたのは、ずっとおそく、昭和十七年のことだった。賻多の丸善書店の小僧だったわたしは、仲よしの売場の娘さんから、「これ、うちの母さんの愛読書なの」と、『絶望の書』を見せられた。「こりゃ、何かいた」というわたしえの、娘さんの説明は、「うちの母さん、辻潤ファンよ」というだけだった。わたしがファンという言葉を耳にしたのも、そのときがはじめてだったような気がする。ファンという言葉が、何だか、秘密めいてひびいてきた。
『絶望の書』のなかで、わたしは(わかりもしないのに!)「こんとら・ちくとら」に、とりわけ心酔した。”飯が食えねえ、仕事がねえ、てんでらでんのでツかいカカア持ちやでんでらでんか” ”なんたら長い五月雨、爺さん欠伸にカビ生えか…………” ”全たいおいらのような阿呆や、低脳はどう始末してくれるんだい″といったくだりなどは、おもしろくておもしろくて………
その頃、出入りしては、なにくれと面倒を見てもらっていた古本屋の南陽堂主人は、辻潤の著書を一揃いそろえていたが、わたしをつかまえては、アナやダダやニヒルの講釈をよくしてくれた。そして、もっとも人間らしゅう生きるには、アナだけじゃいかん、ダダだけじゃいかん、ニヒルだけじゃいかん、この三つの精神ば、チャンポンにせんといかんばい――とも南陽堂はいった。わたしは、こら、えらいことたいと思った。南陽堂は、またたとえば、書物展望社といった本屋や、そこから出版した書物のなまえを、やたらに教え込んでくれた。ついでにとはいわなかったが、酒まで教え込んでくれた。
指おれば、わたしが十五歳のときだった。(詩人)
落魄してから
戸田達雄
私は辻さんの晩年を知っているばかりで、円本の印税が入ったので令息まこと君を伴ってパリヘ行ったころなどは残念ながら知らない。関東大震災より前だったと思うが、浅草雷門にあったカフェ・アメリカで、ご機嫌な様子を、連れて行ってくれた先輩に「あれが辻潤だよ」と教えられたことがあったばかりだ。その後、東中野駅前のある店に、辻さんと、小島きよ(夕マニュウキヨ)女史、故矢橋丈吉君と四人で入ったことがある。辻さんはエビスビールが好きで、それを注文し、女給さんが四人のコップに一本のビールを注ぎきよ女史の分が半分ぐらいしがないことになり、女史が女給さんをひどく怒ってどなりつけたのに当惑したことがあった。知り合ったといえば洗足住まいのころだが、まこと君はもうオリオン社に入社していた。″天狗″になったころだ。
親しいつきあいは、申しては失礼ながら、落魄の色の濃くなった。戦前、戦中のことでよく木挽町五丁目のオリオン社の四階の私の部屋にも登ってきた。
「昼飯を食わせろ」というので「只という法はありませんよ。尺八を一曲聞かせて…」というと、いつも腰に差していた飴色の尺八で、トロイメライやユーモレスクといった、私にもわかる曲を、それは上手に吹いたものだった。
戦争が激しくなり、われわれも敗色みたいなものを感じはじめたころ、中西悟堂さんに会ったら「昨日おもしろい人がきた。それは辻潤で、ちょうどふかし藷をたべていたので奨めて一緒にたべた」と話された。翌日か、矢橋君にその話を伝えたところ私の話し方が悪かったのか、矢橋君がいきなり怒り出して「悟堂かどんなに偉いのか、おもしろい人とは何だ」いうので私は困ってしまった。(日本理科美術会員)
編集室だより
◇本書の校訂は、辻潤の作風をこわさぬよう出来るだけ原本に忠実に編集した。
◇二巻<癡人の独語>解説・村松正俊―は、一月中旬刊行予定。
編集委員
松尾邦之助
村松正俊
添田知道
安藤更生
辻まこと
片柳忠男
菅野青顔
高木護
――――――――――――――――――――――――――――――――――
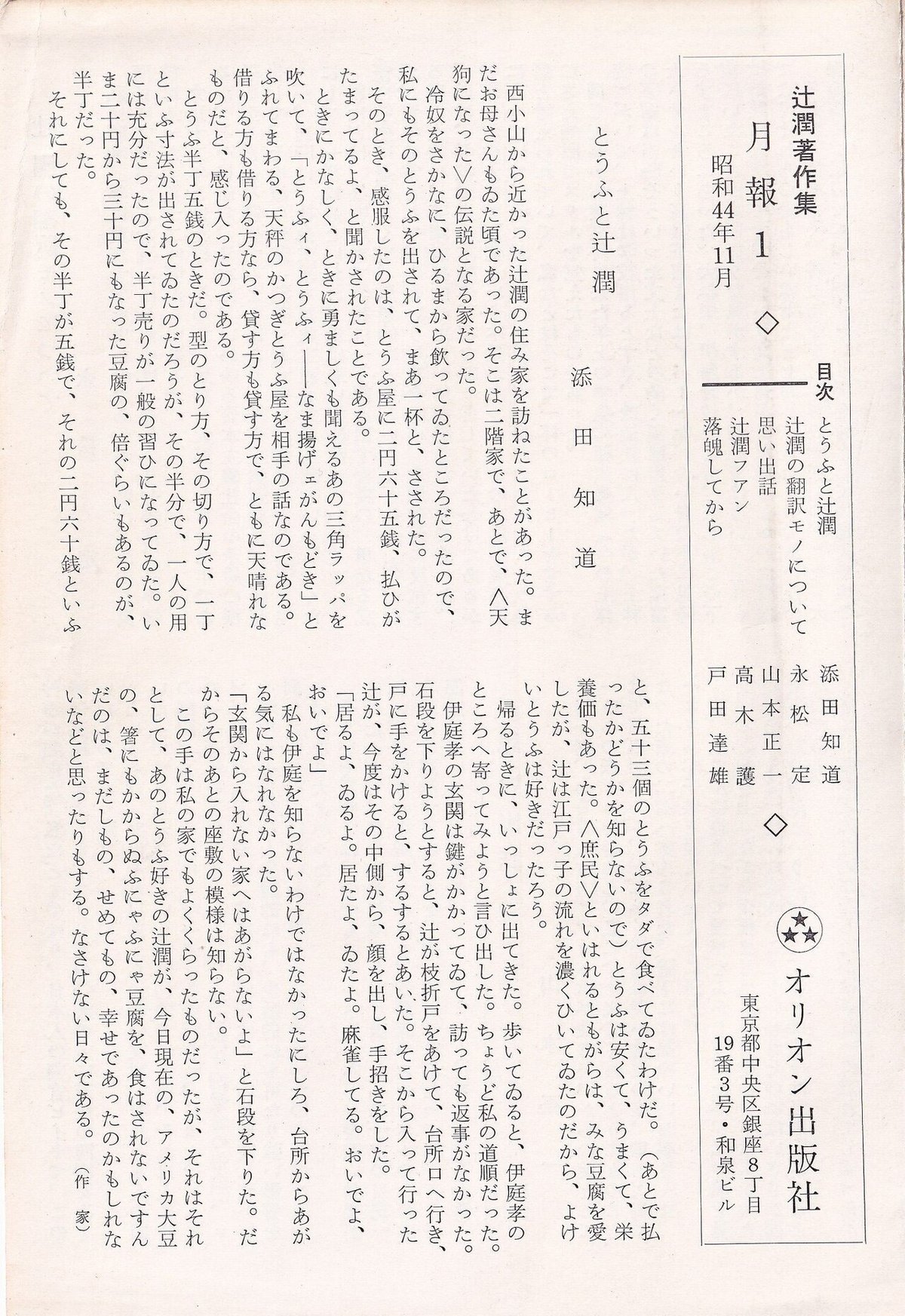


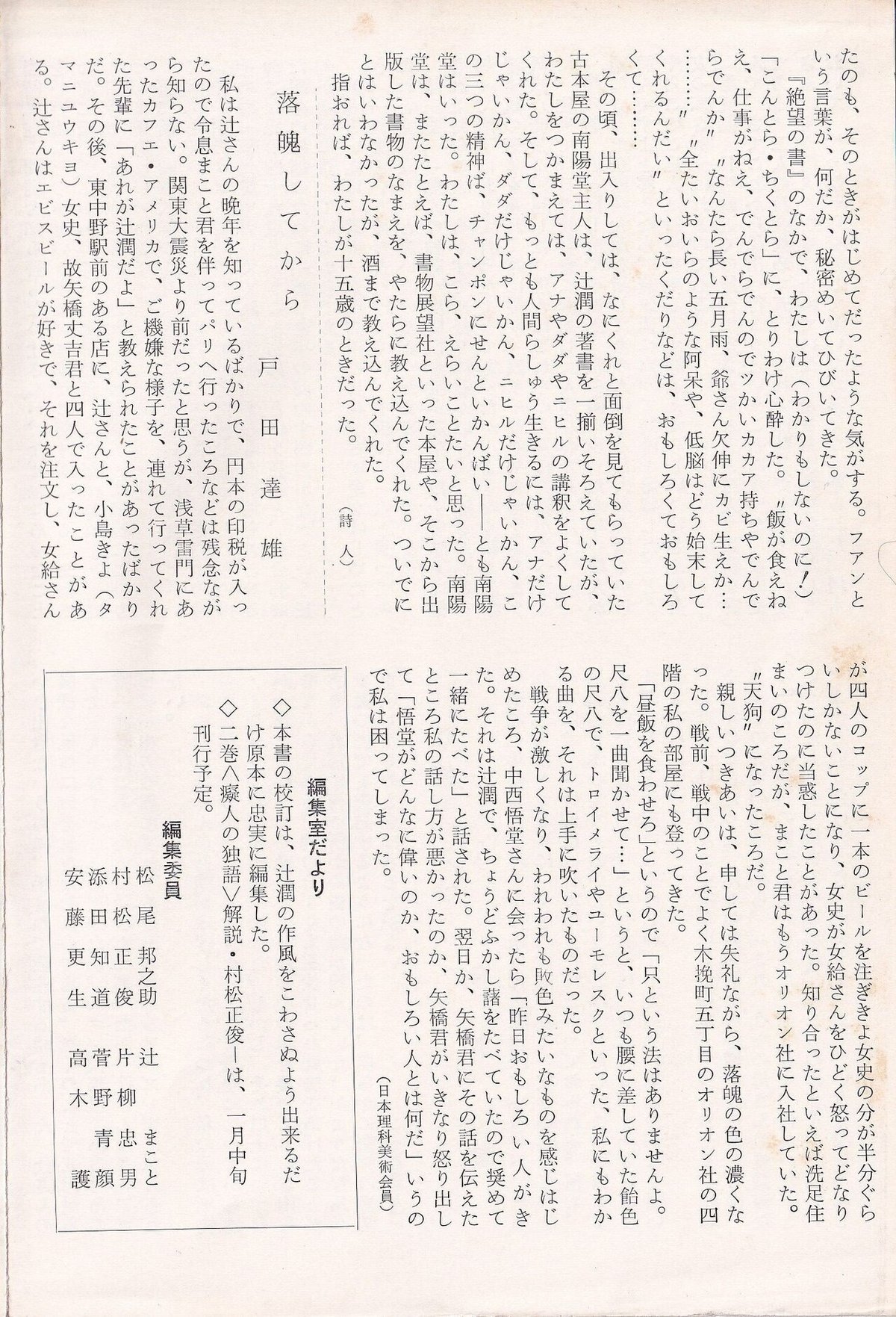
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
