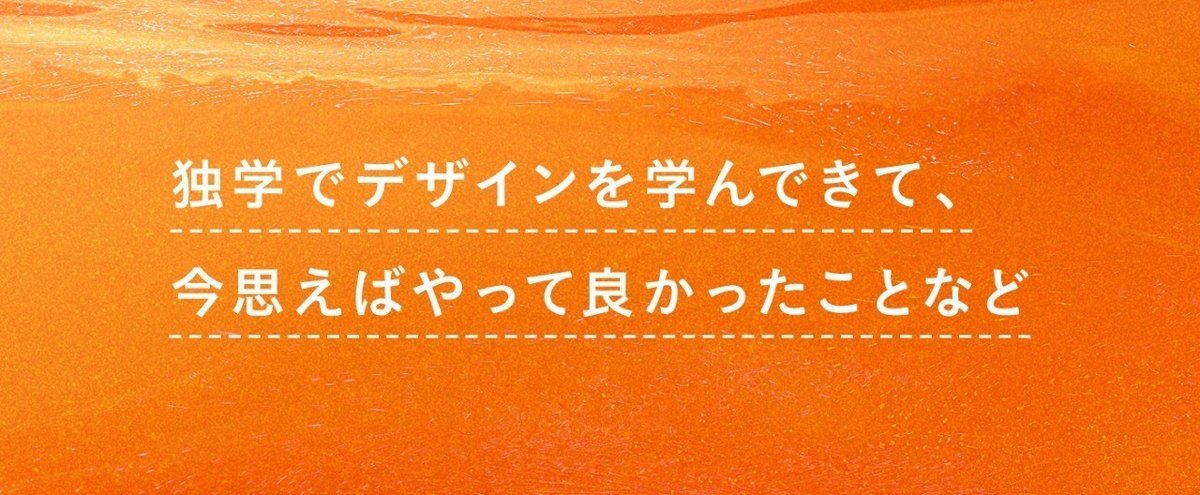
独学でデザインを学んできて、今思えばやって良かったことなど
脇道にそれつつも、10年以上デザインの勉強を独学してきて、役に立ったことをまとめてみる。
自分に足りないスキルを効率よく補う
まずは、がむしゃらにやらずに優先順位をつけていく。
デザインの上手さを分解すると、
・知識量(デザインルールや文法を知っているか)
・ソフトの慣れ(手際よくPhotoshopとかを使えるか)
・引き出しの豊富さ
・ヒアリングやプレゼンテーションなどのコミュニケーション力
・目的理解力や、デザインの言語化などの思考力
などなどがあいまって、総合点で評価されていく。
ここでのポイントは、短期間でモノになることから練習すること。
例えば、Photoshopに慣れることは毎日いじっていたら、半年とかで自在に使えるようになっていく。逆に思考力は一生かかって磨いていくものに思える。
整理すると、
半年コース → 知識とソフトへの慣れ
数年コース → 引き出しを増やしつつ、ヒアリングやプレゼンを磨く
一生コース → 思考力を鍛える
となる。
もちろん、練習しないと伸びないので数年かかるスキルを放置していて良いわけではないが、早く一人前になれることは、さっさとモノにしてしまったほうがフットワークは軽くなり、ボトルネックが減っていく。
知識は名著数冊を精読する
今、旬の知識と普遍的な知識がある。
普遍的な知識は、版を重ねた名著として残っているので読み込んでみる。
おすすめは、『ノンデザイナーズ・デザインブック』『なるほどデザイン』
など、Amazonのカテゴリー1位になるようなもの。
独学でやっていると、誤解をして覚えてしまうこともあるが、やるだけやったあとのほうが、後々だれかに弟子入りしても精度の高い赤字がもらえる。
ソフトは毎日さわって慣れていく
インターンの人を見ているとよくあるのが、ソフトの使い方に慣れていないとそちらに意識を持ってかれてしまい、他の知識があっても発揮せずに疲れてしまう現象。肩がきゅーっとなっている。
ソフトに慣れるポイント
・よく使う機能だけ覚えれば良いので、無理に練習しないで普通にたくさん使っていく
「1週間で覚える」的な教本だと使わない機能にも時間を使うので、参考にするなら逆引き系の本でとにかく触っていく
・普段使わない動作に慣れる
「正確に配置する」「べジュ曲線を書く」など普段のパソコン操作では求められない動作は体力的にも消耗するので、肉体労働だと思って慣れていく。
・疲れる動作はなるべく自動化する
グリッドを揃えたりは、ある程度ソフトがサポートしてくれる。こういった地味に精神削るアクションはなるべく自動化して大量を温存できるようにする。
・脳内Photoshopが出来たら、慣れた証
脳内でPhotoshopなりの画面がイメージできて、空で操作できたら慣れた証
引き出すを増やす
ウェブサイトのボタンひとつ、雑誌の見出しひとつ見ても沢山のパターンがある。ひとつひとつは何処かでみたことがあるパーツでも、その組み合わせ・アレンジの積み重ねで、オリジナリティが出てくる。
引き出しを増やすコツ
・生活してて接するもの全部がヒントになる
ウェブサイトや雑誌はもちろん、街なかの広告、コンビニの商品などを観察して、このあしらいはなんの意味があるのだろう?と考察してみる。特に有名雑誌や大手メーカーのお菓子やジュースのパッケージで無駄な装飾はまずないので観察対象におすすめ。
・目立たないものほど、優れたデザインである
見逃してしまうような意匠ほど、裏で良い仕事をしてると思って探してみる
どうしてもキャリアと比例するヒアリングとプレゼン力
課題(悩み)をデザインで解決するのがデザイナーなので、相手の課題・悩みをまず教えてもらうことから仕事が始まる。
ところが「なにを言うかではなく、誰が言うか」は本当で、ある程度のキャリアがないと甘く見られてしまい、ちゃんと開示してもらえなかったりする。
年齢と実績が解決していくことだけど、意図的に練習として取り入れていたのは、クラウドソーシングでの非対面の提案だ。
非対面なので、年齢や性別は開示せずに(ほぼ)純粋にこちらの提案で判断される。また、まともな案件には数十の提案が集まるので、初回で刺さらないと返信ももらえない。募集文の少ない情報から「相手の課題を想像し」「でも、決めつけず」「端的に具体的な解決案」を提示する。
お金を稼ぐ手段としては効率が悪かったが、提案の練習としてはとても良かった。
頑張って仕事して、大人にならないと思考力は身につかない
クライアントのことを理解できていないと、良い提案は出来ないのは当たり前だけど、そのために必要な思考力や経験は沢山勉強しないと身につかない。ところが思考力は、見た目のデザインほど可視化されないので、自己評価では結構あるように勘違いして、知った顔で提案をしてしまう。
フリーランス、学生のうちから思考力を鍛えるコツは、経営者、ビジネスオーナーに提案させてもらうこと。
制作仕事として考えると、広告代理店経由などの仕事がやりやすいが、ビジネスでの思考力を鍛えるには、濾過されていないダイレクトな判断が効く。
デザイナーの価値観とは異なるルールでジャッジされるが、その違いが思考の差、浅さにあたる。そのとき、イケイケでも売上が出ていなそうなスタートアップより、小売や飲食店など売上が回っている業態がオススメ。
滅茶苦茶を言われてるうちに、
目的理解力 → なんのためにデザインをするのか
デザインの言語化 → 自分のデザインがどう役に立つのか
が身についていく(気がする)
この原稿を書きながら、昔のメールを読み返すと思慮の浅いことをメールしていたなと反省と、よく相手してもらえたなと感謝すること然り。
がむしゃらにやって、しばらくしたらやらないことを決める
今思えばをメモにしたのが前述までの内容だが、実際はその時々に良かれと思って、やってきた感じだ。上に書いたことは、やって損がないと言えることなので、やるだけやったら次は技術変化や自分のキャリアを見て、なにをしないか決めることが大事なんだろう。僕は「技術が進化しても普遍的に求められるデザインの原則」は重視している。
(今も、トコトン文字組みをしたことがなかったので、改めて学び直している。AdobeのAIが進化したら文字組みが不要になる気もするが、最後は人のゆらぎみたいなものが求められるほうに賭けている)
