
Antilatencyを使ってみる。
こんにちは。
モーショントラッキングシステムAntilatencyを触ってみたのでその所感をまとめます。
Antilatency (https://antilatency.com/)
モーショントラッキングシステムです。
マーカー付きのマットを敷いて、それぞれとAltと呼ばれるトラッカーとの位置関係から、3次元位置を割り出す方式です。トラッカーはPCに取り付ける受信機と無線で通信します。
複数セットをつなげることにより、無限大にトラッキングエリアを広げることのできる点が強みのようです。
セットアップ
こちらの説明ページに手順は書いてあります。
大きくは、
1. マットの設置
2. ソフトウェアのセットアップ
3. デバイスのファームウェアアップデート
4. SDKのダウンロード
になります。
始めに、マットの敷き方から書いてありますが、自分ははじめに以下のことを知らなかったので途中であれれとなってしまいました。(もう少し先にちゃんと調べればよかった。)
・各モジュールの名前
・各モジュールの役割
似た名前のものが多くてどれがどれなのかとはじめは混乱しました。
各モジュールの説明
1. Alt Tracker
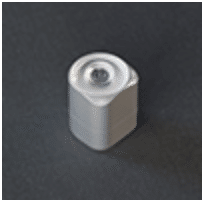
一番重要なトラッカーです。マットのマそれぞれのマーカーとの距離を図るために使用します。
これ単体では無線の通信はしません。一番高価なモジュールです。
2. Wired USB Socket

トラッカーをPCにUSBで取り付けられるようにするモジュールです。有線でつなぐことで、トラッカーの位置を取得できます。
3. HMD Radio Socket

Wired USB Socketに無線通信機能がついたものです。
これを主にPC側の受信機として使用します。
実際これがあればWired USB Socket要らないのではないかと思います。
4. Tag

無線通信時に、トラッキングしたいものに取り付けます。これにAlt Trackerを取り付ける形になります。なので実際のトラッカーはこの大きさになるようです。USB-c接続部分がついており、充電に使用するようです。
5. Bracer

ハンドトラッキング時などに使用しやすいタイプの無線タグです。
Tagと違ってUSB-C接続部分がありません。
6. 名称不明(USB-a モジュール)

Bracerを充電する時に使うモジュールのようです。これだけ何故かUSB-Aです。どうもTagの充電には使えないようでした。何故なのか。
7. Pico G2 Socket
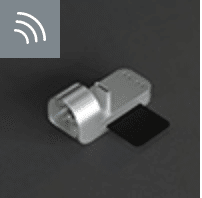
HMDのPico G2をと連携使用する時に使用する無線タグ。
先に挙げたこちらの説明ページに手順は書いてありますので手順の詳しい説明は割愛します。
1. マットの設置
マットは設置するとこんな感じです。


2セット時は以下のようになります。単純に隣合わせに敷く訳ではないので注意してください。


2. ソフトウェアのセットアップ
AntilatencyServiceというソフトウェアをインストールします。
これをつかって、マットの設置の方式、VRヘッドセットの取り付け位置、タグのカスタムネームを決められます。
これだけでキャリブレーションはほとんど必要になりません。
3. デバイスのファームウェアアップデート
AntilatencyServiceをつかいますが、初回は必要ありませんでした。
Alt Trackerのアップデートにはシリアル固有のアップデータが必要なため、事前に開発チームにメールをする必要があるようです。
4. SDKのダウンロード
SDKと合わせてUnitySample、Unreal Sample, Native Sampleがダウンロードされます。
UnitySampleを実行してみる。
Alt Sampleを実行してみました。単体のカメラトラッキングです。
軽いのでその分激しく動くことができますが、かなり激しく動いても、結構追従してきました。
マット外であっても4mほどなら途切れることなく追従しました。
しばらく使用していても位置ズレはありませんでした。
6年ほど前に某企業の見学で、現実空間のカメラのトラッキングスタジオをみましたが、その環境が簡単につくれてしまうことに技術の進歩を露骨に実感しました。
2年ほど前の学生時にも作品のシステムの一部にカメラトラッキングを取り入れたことがあるのですが、その時はVIVEのモーションコントローラーを使っていました。それに比べると、キャリブレーションの速度、センサーのサイズ、重量など圧倒的に使いやすくなっています。
自身の作品のアップデートにも使いたいなと思うところです。
今回は以上になります。
