
「ハッタツソン 体験ワークショップ」に参加してきた!
会社の有志グループの情報共有の場でふと目に留まった「ハッタツソン」というリアル開催のワークショップイベント。
「発達障害を持たれる方との対話を通じて、これまでの働き方の仕組みや環境に埋め込まれた「常識」考え直し、新たな”働く環境・仕組み”を考えてみませんか?」とのフレーズに魅かれ参加してきました!このnoteでは本ワークショップでの学びを備忘録的に整理して記載します!
0.そもそも「ハッタツソン」とは?
ホームページからの参照となりますが、一言で紹介すると以下とのこと!
「目に見えづらい課題」について発達障害のある方とそうでない方がチームを組み、誰もが過ごしやすい社会を実現するサービスや仕組みを考え/作る 3日間のアイデア共創プログラム
もう少し補足説明をすると「インクルーシブデザイン」という考え方を土台としている取り組みとのことでした。
~インクルーシブデザインとは? ( ..)φ_~
高齢者や障害のある方など、様々な違いのある人の視点を企画作りに活かすイギリス発祥のデザイン思考。普段排除されがちな人の視点をサービス・製品開発・仕組みづくりに取り入れる手法🔧である。
(参考:一般社団法人インクルーシブデザイン協会 (inclusive-design.jp))
今回の「ハッタツソン 体験ワークショップ」は、上述のアイデア共創プログラムやインクルーシブデザインに関するエッセンスを抽出する形で構成された2時間構成のワークショップとなっていました。

1.「ハッタツソン 体験ワークショップ」の概要
今回参加したワークショップは大きく以下の内容で構成されていました。
ちなみに、ワークショップ自体の主なアウトプットは以下の様な感じです!
👇
「”みんなが理想の働き方ができる”ための3要素を選び、”その環境に新たに出会った人”のストーリーを起承転結で思い描く」
「ハッタツソン 体験ワークショップ」の全体構成 ※各グループ3~4名
ーーーーーー
[1] アイスブレイク:あるあるカード(シート状)を用いた自己紹介 ※後述
[2] ワーク①:自分の職場での困りごとを振り返り、シェアする
[3] ワーク②:自分にとって理想の働き方を満たす要素を考え、シェアする
[4] ワーク④:”みんなが理想の働き方ができる”ための3要素を選ぶ
[5] ワーク⑤:上記の3要素を満たす実際の働き方・環境を想像する
[6] ワーク⑥:”その環境に新たに出会った人”のストーリーを起承転結で紹介
ーーーーーー
ワークショップの具体的な流れは上記の通りですが、更に簡単に整理すると
「まず個人ベースでテーマに沿った振り返りを行い」
「メンバー間でシェアしながら対話を行い」
「まとめながら、気付きを得ていく/整理していく」
という形式で、とても分かりやすくてシンプルな構成でした。(筆者主観)。
実際に体験してみて、非常に魅力的なワークショップであることを感じたのですが、魅力的なワークショップとしての形を支えている要素として、冒頭のアイスブレイクで登場した "あるあるカード (シート状)" の存在と、各グループに "実際に発達障害をお持ちの方が同席" して下さっていたことが大きい様に感じましたので、以下にて特出しで書き残します!

〇あるあるカード(シート状)について
シンプルに説明すると、あるあるカード(シート状)は
"弱み"として分類されそうな特性が全12個記載されているシート
になっていました。(主観に基づく説明です)

~あるあるカード(シート状)について もう少し詳しく ( ..)φ_~
ハッタツソン2020 Online (2020/12/5〜7 開催)にて最優秀賞・オーディエンス賞を受賞した「凸凹”あるこう”カードゲーム」の中の「あるあるカード」の部分をシート化したもの。
「凸凹”あるこう”カードゲーム」は上記ハッタツソンに参加された "ノノトミー"というチームが「社会の側が発達障害の特性を理解していないのではないか?」という疑問に向き合う中で誕生したカードゲーム。
➡紹介記事:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000069706.html
➡ピッチ動画:https://www.youtube.com/watch?v=V4RKGLPPKXg
アイスブレイクでは、簡単な自己紹介と共に「あるあるカード中の内容から、自分の"あるある"を紹介する」というステップがあったのですが、お互い初対面の方に自分の弱み(と思われがちな特性)をシェアすることによって、短時間のアイスブレイクながら メインのワークに向けて "お互いが内に持つ考えを発話するための準備” の様なものが出来た様に感じます。
~雑感メモ ( ..)φ_~
自分の弱み(と思われがちな特性)って、少なくとも自分は日頃積極的には話さないのですが "あるあるカード" のアシストにより、話慣れないながらも他の方に伝えることができました。
(ちなみに紹介したのは「忘れっぽい」と「あいまいが苦手」です)
各参加者が自分のあるあるを紹介する度に、そこには付箋(名前)を貼っていったのですが、自己紹介が終わった時点では以下の様になりました。
もともとがシート状であるため、参加者それぞれが明らかに "異なるあるある(特性/弱み)" を持っている ことが明確に俯瞰できる状態となっており、「ひとり一人の特性って本当に違うんだな」ということを自分は体感できました。このアイスブレイクだけでとても興味深かったです。

~雑感メモ ( ..)φ_~
職場などでも、このあるあるカード(シート状)を用いて、お互いに自己紹介し合ってみたいと思いました。30分程度やってみるだけでも、お互いに多くの「えっ、そうだったんだ!」が得られそうな気がします。
〇発達障害について<LDとASDとADHD>
本ワークショップでは、各グループに1名ほど 発達障害を持たれる方が参加してくださっていました。(自分たちのグループは途中バトンタッチがあり、2名の方と関わらせて頂くことが出来ました)
自分達がご一緒させて頂いたのは、1人はLD(学習障害)をお持ちの方、もう1人はASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動性障害)を併発で持たれている方でした (言われるまで全く気付きませんでした)。
その方々にお話を伺う中で印象的だったことをそれぞれ紹介します。
~印象的だったエピソード①:LD(学習障害)をお持ちの方 ( ..)φ_~
"手書きが苦手であるため、日頃 文章を作成する時にはスマホやPCを活用する" との話でした。スマホやPCを活用すれば不便はないとのことで、そのワークショップの場でも終始スマホにメモを取られていました。
その様な話を聞きながら、スマホを持っていない時 (例えば、小学生や中学生だった頃など) はとても大変だったのではないかと想像しながら、自分がイメージする "必要十分な環境" が揺さぶられるのを感じました。
~印象的だったエピソード②:ASDとADHDを持たれている方 ( ..)φ_~
"急に予定が空くと混乱してしまう" とのことで、例えば「14:00からAをやらなきゃ」と認識している状況の中で、別の方が(気を利かせたつもりで)「Aやっておいたよ」という状況が突然生じると「Aという予定がなくなった」ということに混乱し、受け入れるのに非常に時間がかかるというもの。
自分自身、仕事などで良かれと思って先回りフォロー(事後連絡は添えながら)をすることもあるのですが、”人によってはそれは混乱を生じるかもしれない” という視点を得ることが出来たのは非常に貴重でした。

2.参加したグループでのアウトプット
以下では、僕らのグループが約2時間のワークショップを通じてアウトプ ットした以下の2点を参考紹介します!
① "みんなが理想の働き方ができる" ための3要素
② "その3要素を満たす環境に新たに出会った人"のストーリー
① "みんなが理想の働き方ができる" ための3要素
僕らのグループが導いた3要素は以下でした。
[1] それぞれが <自分の当たり前> を疑える環境がある
[2] ひとり一人が <自分の好き> を自然に出せる
[3] 仕事の <ゴールに向かうルート> を自由に選べる
[1] それぞれが <自分の当たり前> を疑える環境がある
"みんなが理想"を目指す中においては、その場にいるひとり一人が「自分の当たり前に縛られない状態 / 自分の思う当たり前から解放されている状態」となっていることが望ましいと考える中で、まずこの要素が挙がりました。
その"環境"を作り出すのは、そこに置かれている「モノ」かもしれないし、すでにそこにいる「人」かもしれないし、その場での「コミュニケーション」かもしれません、、、「どういうものがその"環境"を生み出すのか?」 まではワークショップ時点で明確に分からないまでも、"それぞれが <自分の当たり前> を疑える環境がある" ということは1つ大切ではないかと考えました。

("自分にとっての当たり前”って、1人で内省してもなかなか気付けないですよね~。何かしら外的な揺さぶりがやっぱり必要な様に感じます💡)
[2] ひとり一人が <自分の好き> を自然に出せる
アイスブレイク時に "あるあるカード(シート状)" でのやりとりを通じ、グループメンバーの特性が多様であることを改めて感じつつ、
「ひとり一人が自分の言葉で発言できると良いよね」
「それぞれがオリジナリティを発揮しながら仕事ができると良いよね」
という会話が弾む中で、「"ひとり一人が <自分の好き> を自然に出せる" という状態であることが良いよね」という言葉に集約されていきました。
それぞれが自然に出していった<自分の好き>に基づいて仕事を行うことができれば、ひとり一人がオリジナリティをより一層発揮しながら、より良い形で働き・アウトプットを出せるのではないか?と考えました。
~雑感メモ ( ..)φ_~
個人的にはここでの "自然に出せる" という言葉が大切ではないか感じています。最近では 1on1 などのキーワードと共に「会話によってより良い関係性を築く」という視点が強くなっていますが、必ずしも会話が "自然に出せる" を生み出すとは限らない様に思います。その点を加味しながら "自然に出せる" の姿を目指して試行錯誤出来ると良いだろうなと思います。

[3] 仕事の <ゴールに向かうルート> を自由に選べる
実際に仕事を進める上においても、
「お互いに気持ちの良いペース/テンポで進められると良いよね」
「それぞれの自主性に基づいた動きが取れると良いよね」
と会話が進む中で、逆説的に「それぞれが<自分の好き>に基づいて仕事が出来ていたとしても、仕事の進め方における制約が多ければ、それって "理想の働き方" ではないよね」という話が挙がりました。
ここでの "仕事の進め方における制約" は、働く時間や環境に始まり、仕事の進め方に関するペース配分、リスク管理の仕方なども含むイメージです。
その様な話の中で、「それって仕事の <ゴールに向かうルート> を自由に選べるということかも」という会話になり、この要素を考えました。
~雑感メモ ( ..)φ_~
この要素が挙がるまでのサイドトークとして「<ゴールに向かうルート>を自由に選べるようにするためには、ゴール(目標)が明確に設定・共有されていないといけないよね~」という話も挙がり、個人的には「 確かに!Σ( ̄□ ̄ )!!」と少しハッとしたされられた部分がありました。
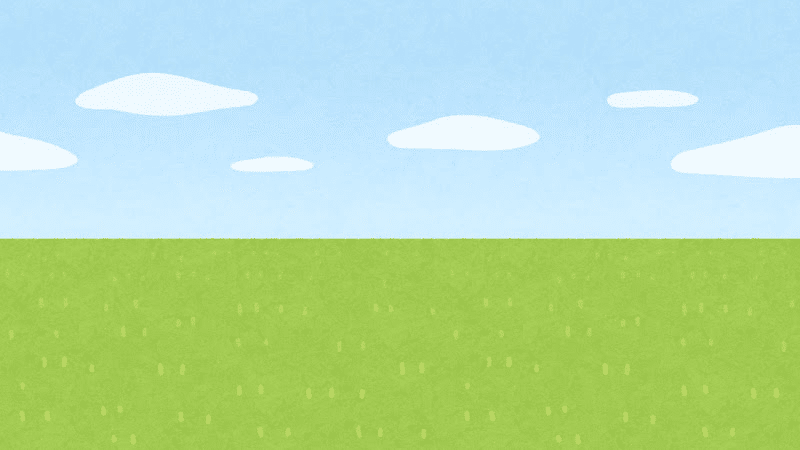
② "その3要素を満たす環境に新たに出会った人"のストーリー
上述の3要素を満たす環境が【仮】にあったとして、その環境に新たに出会った人が どのように感じるのか? を起承転結でストーリーにしました。
"みんなが理想の働き方ができる" ための3要素
[1] それぞれが <自分の当たり前> を疑える環境がある
[2] ひとり一人が <自分の好き> を自然に出せる
[3] 仕事の <ゴールに向かうルート> を自由に選べる
ーーー
◆起 (話の前提や背景を説明する部分)◆
”その環境”での行われる多様な働き方・交えられる多様な考え方に触れる中で、これまで自分が持っていた "当たり前" とのギャップを感じて驚く。
ーーー
◇承 (話に動きが生じる部分)◇
日々"その環境"で働く中で、自分が感じたギャップの正体を探ることになる。その中で、自分自身の "当たり前" と向き合っていく。
ーーー
◆転 (話の本題となる部分)◆
自分自身と向き合う中で、ふと "これまで目を向けていなかった自分" に気付いたり、見つけたり。"自分の好き" に対して理解・認識を深めていく。
ーーー
◇結 (話の結末となる部分)◇
理解・認識を深めた "自分の好き" を "その環境" で発信していく。そして、自分自身をより一層活かした仕事や進め方を出来る様になっていく。

上記で紹介した3要素を満たす環境というものが「具体的にどういう環境であるのか?」については、短いワークの時間のみでは深め切れてませんが、
自分自身としては、このワークショップで具体的イメージを導出することが大切なのではなく、それぞれ異なる特性を持つグループメンバーが共感・納得しながら抽出していった3要素を踏まえながら「その3要素を満たす環境にするためにはどうすれば良いのか?」を【自らの問い】として日々向き合っていくことが大切なのだろうと、このnoteを書きながら改めて思う次第です。
3.ワークショップに参加してみて
ここまでのnoteで、"個々のワークで印象的だったこと・感じたこと" はだいぶ書き連ねてきましたが、ここでは「ワークショップ全体を通して印象的だったこと」を1つ挙げて、まとめとしたいと思います。
(だいぶ長文だったかと思いますが、ここまで読んでくださっている方には感謝しかありません♪ ありがとうございます!。゚(´□`゚)゚。)
〇"ひとり一人の特性(弱み)"から理想の働き方を考える魅力
ここで自分が書きたいことは正直タイトルの通りです!
これまで職場などでも「どういう働き方が良いのか?」を考える機会ありましたが、何気なく会話を始めてしまうと、それぞれが「今の職場での働き方」を振り返る中で、頭に思い浮かんだことを発話する形となり、
気が付けばに "会議の進め方" や "資料作成" や "他部門との連携" などについて「いかにすれば効率良く進められるか?」の様な話 (それはそれで大切だけど、どことなく近視眼的な話) に推移してしまう様にも感じていました。

一方で今回のワークショップでは、"あるあるカード(シート状)" を用いて、
・それぞれが自分の特性(弱みの様なもの)を認識する
ということがメインのワーク前に出来たことで、
・自分の特性に紐づく職場での困りごとを紹介し合う
様な流れが生まれた様に思います。
その人の特性に紐づく形で紹介される職場でのお困りごとは、自然と (語り手にとって) 自分事に溢れた話となり、聞き手側もより自然と前のめりになる様に感じました。
その自分事に溢れたお困りごとを土台として行う会話 の中においては、「いかにすれば効率良く進められるか?」の様な "どことなく近視眼的な議論" は挙がる余地もなく、より本質的な部分に近づいていけるような会話 に出来る様に今回の体験を通じて思いました。(とても貴重な気付きでした!)
~雑感メモ ( ..)φ_~
(前半でも少し触れましたが) お互いに自分の特性(弱み)を紹介し合っていることで、それ以降の会話は "お互いが内に持つ考えを発話する" 心理的ハードルが下がり、より会話内容の厚みも増す様に感じました。
会話相手の方と "心理的安全性のある関係" を築くにあたっては、「自分の特性(弱み)」を受け入れて貰うことがまず1つ大切なのかもしれませんね。
4.最後に
2時間ほどのワークショップでしたが、多くの気付きや学びが得られたとても貴重な機会でした。
内容をアップデートしながら、今後も定期開催されるそうなので、気になった方はこちら👇のホームページを時々覗いてみると良いかもしれません♪
本ワークショップの参加者の方は "多様性や働き方、共創" 等について日々真剣に思考と実践を重ねられている素敵な方ばかりでした。ワーク終了後の他参加者の方とアフタートークも魅力の一つかもしれません ^^

