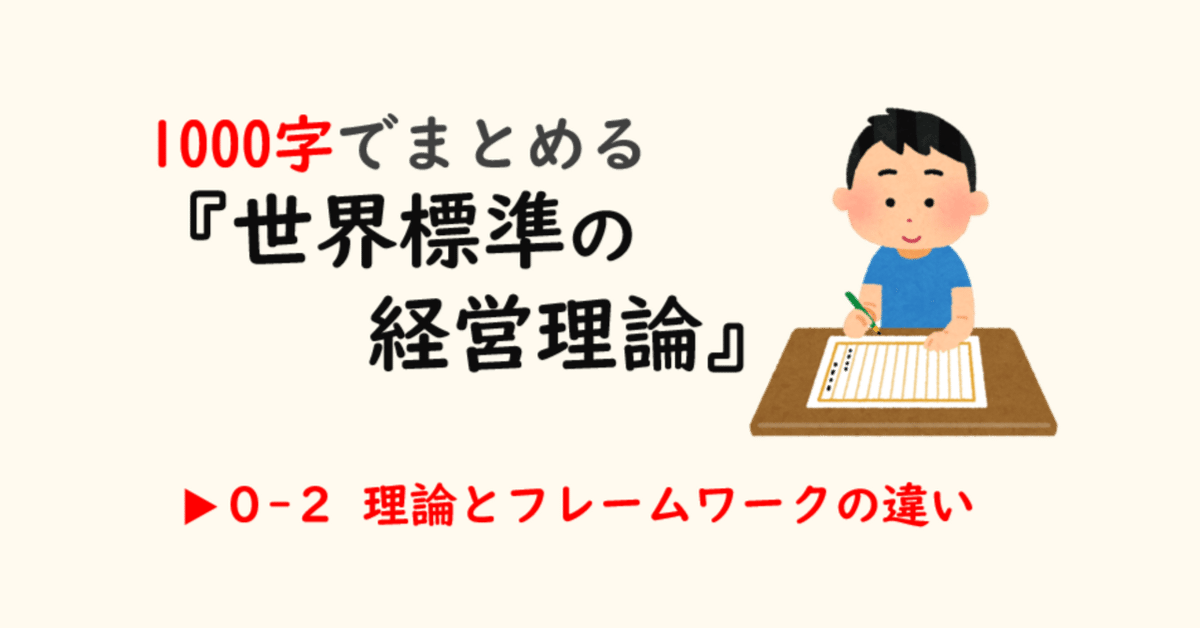
1000字でまとめる『世界標準の経営理論』~ 0-2 理論とフレームワークの違い (序章②) ~
2019年12月に早稲田大学の入山教授が出版した『世界標準の経営理論』。出版早々に購入するも、面白そうな章だけつまみ食いした以降は、3年ほど本棚の肥やしとなっていた。しかし、2022年10月にマネジメントへの一歩へを踏み出す中で【経営】への関心が再び高まり、この機会に丁寧に読み直すことにした。
本noteは自身の咀嚼を主な目的として、各章の概要を各noteで "1000字程度" で整理すると共に、読む中で感じたことを記録する備忘録である。なお、今の自分にとって目に留まった章から順番に触れていく。
(導入説明 300字、各章概要 1000字、振り返り 500~1000字 構成である📣)
1.本文概要:理論とフレームワークの違い
✄『世界標準の経営理論』該当ページ:P17~P26 ✄
ーーー
理論の目的は「経営・ビジネスのhow、when、whyに応えること」である。特に重要なのはwhyであり、経営学、心理学、社会学のいずれかの人間・組織の思考・行動の根本原理から、「なぜそうなるのか」を説明することが理論の目的である。
その上で「何が理論か?」については未だに学者間で論争中であるが、一方で「何が理論ではないか?」については、コンセンサス(合意)が取れている。『理論ではないもの』は、以下の5つの特徴を有する。
■理論ではないもの:5つの特徴
特徴① 参考文献や引用の羅列は、理論ではない。
特徴② データを記述しただけでは、理論ではない。
特徴③ 概念の説明は、理論ではない。
特徴④ 図表は、理論ではない
特徴⑤ 命題や仮説だけでは、理論ではない。
命題が普遍的に多く企業・個人に当てはまるかを、統計分析などで検証したのみでは理論ではない。「なぜそういえるのか?(why)」まで説明されなければ、完成した理論ではない。
ーーー
経営学の知見は、実際のビジネスパーソンに2つのルートから貢献しうる。
■第1ルート:フレームワーク化
理論そのものは抽象的で、実務で使いやすいとは限らない。だから実践のために "理論を使いやすいフレームワーク" に落とし込む。その代表例がポーターの『競争の戦略』で紹介される「ファイブ・フォース」などである。
「SWOT」や「BCGマトリックス」はコンサルタント等が、その実務経験を通じて生んだものであり、経営理論とは関連のないフレームワークである。
■第2ルート:思考の軸とする
「ファイブフォース」の様に綺麗にフレームワークに落とし込まれる例は極めて少ない。そのため、「経営理論」の内「標準」と言えるものについて、基本原理から丁寧に分かりやすく紹介することにより、思考の軸とする。
特に欧米の経営学界では基本的に「学術論文」を書かないと出世できないので、実務家のために理論をフレームワーク化する様な「実務論文」を書くインセンティブが乏しい。
ーーー
2.本章に対する振り返り
本書中で示された "理論ではないものの5つの特徴" を踏まえることにより、他関連書籍の記載内容の位置づけを見分ける1つの判断軸を得られたことが今の自分にとっては有意義である様に感じる章であった。自身は「マネジメント」の文脈で学びを深めているところであるが、油断すると数多の書籍に埋もれがちである。その状況に対する牽制になりそうである。
ーーー
また、フレームワークを活用するにあたっては、「そのフレームワークはどの様な背景から提唱されたものであるのか? (その裏に理論はあるのか? 知見を分かりやすい形にしたものなのか?) 」を理解する必要性についても改めて感じる次第であった。目に見える分かりやすいフレームワークのみに触れて、分かったつもりにならない様にすることが大切かもしれない。
ーーー
その上で、多くの経営理論がフレームワークになっていないとのことを踏まえると、経営理論に触れた上でのアウトプットの1つの形として『自分オリジナルのフレームワークに落とし込む』ということを行う視点を持っても良いのかもしれない。それにより、各理論をより咀嚼しながら、自分自身の思考の軸をより安定的に広がりがあるものに出来る様に考える。
【参考資料】
ここまでお読み頂きましてありがとうございました!💐
この記事は「自分のための学び」を公開している形ですが、一読頂いた方にとって、何かお役に立つ部分があったなら甚幸です!
「知恵はかい出さんとあかん、井戸から水を汲み上げる様に」を大事にしながら、日々のマネジメントに対する振り返りをツイートしています👇
