時枝誠記と現象学 9
第2章 詞辞論
第8節 「文の概念について」
1937年と時枝誠記
「時枝誠記伝」(1)には、言語過程説の理論を構築し、「文の概念について」などを執筆していた1937年当時の時枝について、次のような記述があります。
このように、学問上は花々しい活躍が続いていたけれども、生活面・精神面では、いろいろ苦々しい、心を悩ます出来事が続出していたようである。このことは、「朝鮮の思ひ出(一)(二)」にも記してないが、断片的に後で直接先生から伺った内容を振り返ってみると相当深刻なものであったようである。その苦しみを、論文を書くことにより、剣道の稽古に打込むことにより、学生を自宅に招いて酒宴を開くことなどによって乗り越えようとされていたのである。また、昭和六年に起こった満州事変、一二年の日支事変も先生にとっては憂鬱なことであったらしく、これらの戦争の余波としての或事件が、先生をして、朝鮮を去り、大学教授も辞めようとまで決心させる事態を生むことになるのである。
私たちはともすると忘れがちですが、1937年当時、時枝は現在のソウルにあった京城帝国大学の教授でした。時枝誠記が当時、朝鮮という「辺境」において、いろいろな重圧のもと、いろいろな苦悩とともに学究生活を送り、論文を書いていたことがうかがわれます。「或事件」を含め、当時時枝が抱えていた「心を悩ます出来事」については、また別の機会に触れることができればと考えています。
言語本質観と「形態部」の認識方法
時枝誠記は1937年5月3日に「語の形式的接続と意味的接続」を脱稿したのち、1937年6月1日に「言語過程に於ける美的形式について」(『文学』、1937年11月および1938年1月)を脱稿し、続けて1937年9月21日に「文の概念について(上)(下)」(『国語と国文学』1937年11月および12月)を脱稿します。詞辞論と深く関係してくるところから、ここではまず、後者のほうをとりあげることにします。「文の概念について」という論文において時枝はまず、一般的に文論の前提となっている、意味と音声との結合したものが言語であるという「言語二面観」の考えかた自体に疑義を呈し、そうした「言語二面観」の立場から展開される語や文やその形態に関する学問的体系は、それ自体がそもそも正しいものかどうか怪しいものであると問題提起します。そこで時枝は、もう一度原点に立ち返って、われわれに与えられているのは、具体的な音声や文字の連続それのみである、という立場から始めるべきではないか、と語り、このような学的状況下において、いかにして語や文やその形態を認識するべきなのか、と問いを立てます。
時枝の言語本質観は、「言語は、これを概観するならば、分裂綜合によつて展開する思想の流れを、これに対応する音声或は文字を媒材として、これを分節的に線条的に外部に表現する処の心的過程の一形式である」(「文の概念について(上)」)というものです。時枝はこのような言語本質観の立場から、文法研究の対象となる形態部の認識方法について、次のように述べます。
言語が我々の対象として経験される手懸りは、可聴的な音声或は可視的な文字以外の何ものでもない。文法研究の対象となる形態部なるものが、音声及び文字によつて表現される場合に於いても、先づ最初に形態部に基準を求めると云ふことは不可能なことであつて、形態部の認識は、勢ひ形態ならざる他のものに拠るより他はないのである。たつ(龍)、たつ(立)の二語に於いて、後者の「つ」が形態部であると云ふことは、この語の音声・文字の形式の上からは、直に観取することは出来ないことである。且つ又言語はその表現に於いて、音声・文字の不断の連続であるが故に、これら形式のみの上から、語を区割し、切り取り、単位を決定することは不可能なことである。かくの如く、言語の連続の分析を可能ならしめるものは、音声文字の如き言語の形式的部分でもなく、又形態部でもない。それならば、何が音の連鎖中に語を切取り、形態部を認識せしめるかと云ふならば、それは言語によつて表現せられる思想内容即ち意味に他ならない。詳に云ふならば、思想の起伏、脈絡即ち一般に意味の分節と意味の連関関係とがそれである。これを試に図に表すならば、

の如き関係になるであらう。嘗て私は、小林(英夫)氏に、解釈と文法の問題に関連して、次の様なことを語つたことがある。形態部が文の解釈を可能にするのでなく、先づ文の解釈が予め明らかになつて、然る後に形態部が明らかになるのではないか。形態部が如何にして認識されるかが、先づ問題ではなかろうかと。
このような時枝の問いかけに対し、小林英夫はそれは「哲学の問題」だと返答しますが、時枝はいやちがう、「音声・文字を通して意味が先づ把握される」ことが先であると主張します。時枝のこうした内容の優位性を主張する叙述は、そもそも「音韻」というものも、表現主体の「主体的な音声意識」においてのみ識別可能であるとする『原論』での叙述(2)や、「観察的立場は、常に主体的立場を前提とすることによつてのみ可能とされる」という時枝の立場論(3)を彷彿とさせるものがあります。
ともあれ時枝はこのように、文法研究の対象となる形態部の認識においては、まず最初に文の解釈、すなわち「意味の分節と意味連関の把握」、いいかえれば「語と語との連関関係の把握」が重要であり、そこから形態部の認識を始めるべきであると主張します。そして、そのような立場から語や文の内在的な研究を行ない法則を見出そうとしたもの、いいかえれば「かかる心的過程の或る連鎖をとつて、そこに意味に従つて分節された個々の過程即ち一語と一語との相関関係の間に横たわる法則的なものを見出そうとした」のが論文「語の形式的接続と意味的接続」であったと述べます。
すでに第七節で紹介したように、時枝は「語の形式的接続と意味的接続」において、自らの言語本質観の立場から日本語の文を意味的に分析しており、そこでは、「観念語(辞)」による「添加関係」が意味的なかたまりとしての「連結的構造」を形成し、「概念語(詞)」による「統合関係」が語や句を入子型にまとめる「包合的構造(入子型構造)」を形成していると主張して、この二つの構造が絡み合い重層化を成しているところに日本語の文の意味的な面での法則性を見出そうとしていました。
過去の文論の検討
次に時枝は、過去の「文」についての学説について、ひとつひとつ簡単に考察を加えていきます。
まず最初に、言語学者シャルル・バイイの文論、すなわち「文とは判断の伝達であ」り、それは「題(thēme)」と「説(propos)」というニ項から成るという、論理的観点からつくられた文論をとりあげます。これは、いいかえれば文とは「主語」「述語」から成るという、日本語の現実にはあまりそぐわない文論です。こうした文論について時枝は、たとえば「come!」のような一語文の表現を「I commended you to come」と置き換えて文と認めるという、窮屈な説明にならざるをえなくなり、次第に説得力を失っていったと述べます。
次に時枝は、ヘンリー・スウィートの次のような言葉を引用します。
A sentence is a word or group of words capable of expressing a complete thought or meaning.
この「文とは思想の完全なる或は完結せる表現である」(「文の概念について」)という説も、日本においては、「完結と完全といふ二の概念が混同されたが為」(同上)に、「完結(complete)」の概念が実は文の条件として重要なものであるかもしれないのに、無意味なものとして葬り去られてしまったと時枝は説明します。
山田孝雄の文論・陳述論
次に時枝は、山田孝雄の有名な統覚作用論を含む文論について言及します。山田孝雄の統覚作用論、文論は次のようなものでした。
……一の語又は語の数多の集合体が、文とするを得る所以のものはその内面に存する思想の力たるなり。惟ふに思想とは人の意識の活動にして種々の観念が、ある一点に於いて関係を有し、その点に於いて結合せられたるものならざるべからず。而してこの統一点は唯一なるべし。意識の主点は一なればなり。この故に一の思想には必ず一の統合作用存すべきなり。今これを名づけて統覚作用といふ。この統覚作用これ実に思想の生命なり。この統覚作用によりて統合せられたる思想の言語といふ形にあらはされたるもの即ち文なりとす。この故に一の語にせよ、数多の語よりなるにせよ、ある統覚作用によりて統合せられたる思想の発表なる場合には文と認むべきものとす。
統覚作用とは、意識の統合作用を汎くさせるものなれば、説明、想像、疑問、命令、禁制、欲求、感動等一切の思想を網羅するものなり。
このように、山田はこれまでの論理的観点からの文論とは異なり、文の背後に表現主体の思想を想定し、そしてその思想が統合作用(あるいは統覚作用)によって統合され、まとまり、それが実際に表現されたものが文であると言います。この考えかたからすると、それまで文と認められなかった感動や希望をあらわすいわゆる体言止めの文、すなわち「喚体の句」も文と認められることになり、時枝はその点を評価します。
また、山田の文論で特徴的なのは、思想の段階で「主位の観念」と「賓位の観念」とを統合する作用、いいかえれば思想の内容を統合する作用のことを文法学上「陳述作用」と呼び、欧米の言語でいうならば「繫辞」がこれに該当するものとし、かつ日本語においてそれは述格に存すると規定したことです(なお、「主位の観念」と「賓位の観念」とが存在する一般的な文のことを山田は「述体の句」とよびます)。
抑も陳述をなすといふことは之を思想の方面よりいへば主位の観念と賓位の観念との二者の関係を明かにすることにして、その主賓の二者が合一すべき関係にあるか、合一すべからぬ関係にあるかを決定する思想の作用を以て内面の要素として、そを言語の上に発表したるに外ならず。

命題の形をとれる句は二元性を有するものにして理性的の発表形式にして、主格と賓格との相対立するありて、述格がこれを統一する性質のものにして、その意識の統一点は述格に寓せられてあるものなり。
時枝は山田がその文論において、思想を統合する作用を陳述作用と呼び、これがあることを文の条件とし、しかもそれが「主位の観念」とも「賓位の観念」とも別のものとして規定して、両者を統一する作用としていることについて、賛意を表しています(4)。けれども、山田が陳述作用が述格すなわち用言に存するとしたことには疑問を呈します。
元来用言は属性概念を有するものであるが、氏が述格と云ふ時、かかる属性概念即ち賓位の概念と陳述作用との結合したものと考へられたのであるが、かく考へることは正しいことであらうか。この二者は氏の図解にも明示されて居る様に合一せられたものではなくして、本来別個のものである。
「氏の図解」というのは、上に示した「主位」「賓位」「繫辞」であらわした図解をさしています。たしかに、「月明らかなり」や「花紅なり」、あるいは「山は雪か」「外は雨らしい」などにおいては、この図解のように、「主位」や「賓位」とは別にこれらのあとに「繫辞」(この場合は「なり」「か」「らしい」)が連結されているので、この「繫辞」が「陳述作用」を表現していると言うことは可能です。ところが山田は、「外は寒い」「風がそよぐ」などの例においては、「寒い」「そよぐ」など用言が属性概念とともに「陳述作用」(判断概念)をも表現していると述べているのであり、それは例の図解にそぐわないことになります。時枝はこうした矛盾を指摘して、
…用言を用ゐて賓位概念を表す場合には、たまたま陳述が言語的に表現されなかつたのであつて、用言に陳述の能力が寓せられて居ると見るのは、却つて氏の陳述の根本観念に矛盾する様に考へられるのである。
と述べます。このように、時枝はこの論文ですでに用言に関係する陳述という問題構成において、「用言に陳述の能力が寓せられて居る」という表現を否定するようになっており、あとでまた具体的に触れますが、用言においては陳述(判断)を「言語形式零の形に於いて累加する」(「文の概念について(下)」)という表現を用いるようになっています。前節で三浦つとむの言葉を引用して指摘したように、日本語は膠着語であり、属性の表現と判断の表現とを別々に表現する構造になっているので、用言と陳述という問題構成においては、この時枝の考えかた(零記号を含む)、すなわち用言と陳述とを分けて考える方が日本語の現実に合致しているといえるでしょう。
時枝はこのように山田の文論における陳述作用論を基本的には支持しつつも、用言と陳述との関係についての山田の考えかたには異義を唱えます。そして次に、山田の「喚体の句」(感動や希望をあらわしたりする、いわゆる体言止めに代表される文)をとりあげます。山田孝雄は「喚体の句」と陳述との関係については、次のように述べていました。
次にその主格述格の差別の立てられぬものは直感的の発表形式にして一元性のものにして、呼格の語を中心とするものにして、その意識の統一点はその呼格に寓せられてあるものにしてその形式は対象を喚(よ)びかくるさまなるによりてこれを喚体の句と名づく。
ここにいう「呼格」とは、「…文中にありて他の語と何等の形式的関係なしに立てるもの」(5)のことをさし、その名前の由来は「その対象又は対者を呼びかけて指定する」(6)からというものであり、ほとんどの場合、いわゆる名詞がこれに該当します。また、「その意識の統一点」とは、「統覚作用」のことをさしています。つまり上の引用文で山田は、おおざっぱにいうと、「体言止め」の文に代表される「喚体の句」においては、「統覚作用」は「呼格」にあると述べていることになります。ただ、厳密に、どこに統覚作用が働いているというような、具体的な記述はありません。
これに対して時枝は次のように述べます。
述体の句に於ける統覚作用即ち陳述が、主位賓位の概念の外にあつてこれを統合することによつて文を認めようとする立場を固執するならば、喚体の句に於いて、これを統合する統覚作用の言語的表現は、例へば、
妙なる笛の音よ
に於いては、助詞「よ」になければならない筈である。呼格の語は、単に感情的統合作用の対象若しくは内容素材であるに過ぎないのである。山田氏が喚体の句の本質をここに求めず、却つてその素材の構造に求めたと云ふことは(「日本文法学概論」945頁)、氏の文に対する根本概念を放棄したものと云はなければならない。
山田孝雄は、「喚体の句」においては、「連体格ーーー中心骨子たる体言」という構成をもって「感動」をあらわしているとしました(7) が、時枝はこのことを手厳しく批判しています。たしかに、時枝理論によれば「助詞」「助動詞」「零記号の陳述」が「感動」をあらわしているといえますが、山田の「喚体」論においては、「述体」論における「陳述」に相当する構文機能の提示がありません(8)。この点においては、時枝の指摘は的を射ているといえるでしょう。
時枝誠記の文論①――思想の表現と意識内容・意識作用
時枝誠記が音声と意味の結合したものが言語であるという「言語二面観」に疑問をもっており、自らは、思想の流れなど過程的構造をその背後にもつところの心的過程の一形式を言語として規定していたことはすでに見てきたところですが、時枝は文の本質を語るにあたって、まず言語の背後に存在する「思想」「意識内容」「意識作用」といったことを問題にします。
…我々が若し意識に映ずる種々なる表象或は概念を文字或は音声に表現して、山、川、月、花、行く、見る、走る等と云つた場合、それは意識の内容を表出したのであつて、これを思想の表現とは云ひ得ないであらう。それは思想内容の表現であつて、未だ自我の活動を意味する思想そのものの表現ではない。(中略)「山」「行く」と云ふ言語自体は、概念作用を表現して居るのではなくして、概念作用によつて素材化され、内容化されたものを表現して居るのである。従つてこれを思想の表現とはいふことが出来ない。若し、「山だ」「川だ」と云つた場合、そこに始めて、概念作用とその内容である概念とが表現されたので、これを思想の表現と云ふことが出来る。ここに思想と云ふ語が曖昧であるならば、意識と呼んでもよい。表象や概念は意識内容であつても、意識作用自体ではない。語は一般に概念作用を経過する表現であるが故に、それは意識内容として客観化され、対象化された思想の一面的表現であると云ふことが出来る。以下私は思想と云ふ語を、意識内容と意識作用との融合した意識状態を指すことにするであらう。右述べた「山」「行く」の如き表象或は概念のみの言語表現は、思想の一面的表現であつて、実は極めて抽象的にのみ考へ得られる事実であり、或は時として脳神経の病的状態に於いてのみ現れる現象であつて、現実的な我々の思想は、常に、意識に現れる内容的な表象或は概念と同時に、それらに対する判断、感情、意志、立場の如き自我の活動を伴ふものであつて、両者合体して始めて思想表現となるのである。
こうして、時枝は、文を語るにあたって、まず言語の背後に、自我の主体的な活動を想定し、意識内容と意識作用との結合したものとしての「思想」を想定します。そして「思想」の表現されたものが言語であり、文であるということになります。「言語」の学問的分析に際して自然科学的言語観を批判して人間の「表現行為」の側面を重視した(9)時枝は、「文」の学問的規定に際しても「表現行為」の過程を重要視していたといえるでしょう。ここで時枝が述べていることを理解している人は意外と少ないものと思われます。私たちは、よく辞書に記載されている「山」「行く」「楽しい」など見出しの記号を「言語」とか「言葉」と言いますが、時枝の言語本質観によると、それらは厳密にいうとその背後に上記のような人間の意識における理知的な営みが存在しないので、「言語」「言葉」ではないということになります。猫がパソコンのキーボードを叩いて表示された記号は、それがどんなに理解可能な文章だったとしても、「言語」ではないことになります。表象や概念など対象的なものと人間の判断、感情、意志など自我の活動とが合一してはじめて現実的に言語が形成されるというわけです。
時枝誠記の文論②――概念語(詞)と観念語(辞)の結合
時枝は文成立の第一条件として、次のように述べます。
文が思想の表現であり、思想は上に述べた如く客観界と自我との結合した体験にあるとするならば、文は即ち概念語(詞)と観念語(辞)との結合に於いて表現されると云ひ得るであらう。自我の活動の表現形式零なる場合を除いて、
花・か 花・よ 花・なり 花・だ 花・らしい
の如きは皆文と考へられるのである。
次に、国語に於ける用言は、その辞書的語彙としては属性概念を表すのであるが、具体的思想の表現に於いては、或る事物に就いての判断を、言語形式零の形に於いて累加する。例へば
暖い 咲く
と云つた場合、「暖い」と判断し、「咲く」と陳述する自我の活動は、言語形式には現れて来ない。併しかかる自我の活動が累加されて居ると見る限り、これも思想の表現であつて、文と考へなければならない。前例の図式に倣へば、

この累加的表現も、若し判断が単純な肯定より否定、想像、疑問等に移るならば、前例の如く線条的表現となるのである。

右の如く用言が文と認められるのは、これらの語が、「風が暖い」「花が咲く」といふ様に、論理的形式に置き換へられるが故ではなく、右の図に示した如く、主客の合一した思想の表現と認められるからである。
第6節で見てきたように、時枝は話者の心理や主体的なもののみを表現する語(=辞)と、それ以外の主に対象世界や属性などを表現する語(=詞)とに二大別しましたが、これらの合一を文成立の第一条件とします。これによって、論理的形式以外のものも文とすることができるだけでなく、いわゆる「喚体の句」や一語文における陳述のありかたも、零記号の陳述や助詞および助動詞によるものとして合理的に説明できることになります(10)。ここでも、用言における陳述作用の説明に際し、「併有」という表現が使われておらず、用言に「自我の活動が累加されて居る」と述べられています。用言における属性表現と判断表現の「併有」説は、早くもこの段階(1937年9月21日時点)で否定されてしまっていると見てよさそうです。
また、時枝は、思想の表現はそもそも統一の意識なしには成立しえないものであるとして、思想表現の統一は観念語(辞)の「総括機能」によるものであると規定します。
総括機能は、観念語の持つ特有の機能であつて、その点助詞助動詞は全く共通して居る。用言に累加される陳述作用が、機能的に見て助詞助動詞と同様であることは既に述べたが、而もこの三者助詞助動詞陳述作用は、それによつて総括される語及び語群の直下に接続し、整然たる一体系を形造るのである。国語に於ける文の統一の意識より見ても、重要なのは、主語述語ではなく、観念語及び陳述作用であつて、これらを除いては、文の成立しないことが明らかになつたと思ふ。助詞助動詞陳述作用等を、総括機能として見る時、陳述作用が単に用言にのみ寓せられてると云ふ見解の誤であることは明らかにされるであらう。
文の統一という観点において、主語述語より辞すなわち主体的表現が重要であるというのは、私もそのとおりだと思いますが、けれども文末の辞の表現がそれまでの表現全体を総括しているとする考えかたは、仁田義雄氏をはじめとして批判する人も多く(11)、三浦つとむも指摘しているように、そういった考えかたはある種のフェティシズムととらえられてしまいかねず(12)、私自身は、文における主体的表現の重要性を指摘する程度でよいのではないかと思います。それよりも、私には、文の理解としての観点から、むしろ時枝の創始になる「入子型構造形式」の有用性を強調するほうがはるかに有意義であるように思われます。なぜなら、時枝の「入子型構造形式」は、文の解析において重要である、詞辞の融合したひとかたまり、あるいは複数のかたまりである「連結的構造」の可視化や、三浦つとむのいう多重世界(13)を可視化するものとして、きわめて有効なものだと思われるからです。
時枝誠記の文論③――表現の完結
時枝は文成立の二つ目の条件として、「表現の完結」ということを取り上げます。
……更に一の重要な条件は、思想の表現が完結されて居ると云ふ意識である。文は詞と辞の結合にありとしたが、次の如き例に於いては、
花・は 雨降る・べく 美しけれ・ども
「花」「雨降る」「美しけれ」は、夫々詞或は詞の群であり、「は」「べく」「ども」は夫々辞であつて、詞辞二者の結合から成立して居るのであるが、我々はこれを文とは考へない。何となれば、右の如き結合に於いては、思想が完結されず、下に何等か続くべき勢を示して居るからである。即ち「は」「べく」「ども」は未完結な辞だからである。かく考へて来るならば、文の認識に於いて他の重要な条件は、詞に辞が結合することであると同時に、その辞は完結する処の辞でなければならないと云ふことである。
近年の文法書では、句点から句点までのひと続きの文字の連なりを「文」とするなど極端な形式主義的な規定が見受けられます(14)が、時枝の完結ということは、その前に思想の表現と詞辞の合一という内容的な規定が存在している点で異なっているとともに、完結を明示する辞の表現形式すなわち多くの場合辞の「終止形」を伴うものであるとしているところが異なります。
また、時枝は文の完結ということに絡めて、次のような興味深い発言をしています。
……語形変化によつて語の接続を形造る国語に於いては、文の完結が、話者の志向作用の表現と同様に、語の形式の上に明示されて居ると云ふことは、接続によつて語形式を変化させることのない印欧語と比較して、国語の特質を物語る一点であると思ふ。若し国語に於いて、断続の関係を明示する語形式の発達がなかつたならば、国語は恐らく断続を表すべき他の形態上の変化例へば音の抑揚の如きものを発達させたであらう。
時枝は例として、「おい娘、兵士が一人来たらう」という文を挙げ、このまま「らう」を推量の表現と同時に疑問の表現としても使う場合は、「尻上がりの抑揚」を累加させる必要があるが、問いかけの終助詞「か」連結させて「来たらうか」とすれば、通常の平坦な抑揚で完結させることができると述べています。ここから推測されることは、日本語においては、断続の関係を明示する語形式の発達によって、さらにいえば多種多様な助詞助動詞の発達によって、言語としての主体的表現の多種多様な発達へとつながると同時に、その反面ジェスチャーや抑揚など非言語表現としての主体的表現の発達がその他の形態の言語に比べて抑制されたのではないか、ということです。逆にいえば、日本語の表現力を豊かにしようとするならば、助詞助動詞など主体的表現の表現力を重点的に磨けばよいのではないかということになります。このへんはまた別の機会に論じてみたい、興味深い論点だと思います。
現象学の影響について
さきほど、文末の辞がそれまでの表現内容を総括するという時枝独自の「総括作用」論について少し触れましたが、時枝独自のこの「総括作用」論あるいは「総括機能」論の背景にあるかもしれないであろう山内得立(やまうちとくりゅう)による現象学の記述を次に挙げておこうと思います。
……ノエマの種々なる変様を存在様相(Seinsmodalitȁt)といふならばノエシスの様々なる様態を、之に対して信念様相(Glaubensmodalitȁt)と名づけ得るであらう。信念(Doxa)といふ語の下にフッセールはノエマの存在様式に相対するもの、即ち一方に於てこの存在とは異りながら、同時に之を存在的として把捉する(fűr seiend-halten)ところのものを理解する。信念的性質はそれ故に意識が或物について措定的に働く(setzende, thetische)ところに、換言すればこの或物に存在といふ賓辞を付加し、それを存在として把捉するところにあらはれるのである。表象も客観化作用として常に何等かの客観に関係するであらうが、併し表象作用が単に或ものを指示するだけであるならば、そこには信念的性質があらはれない。表象には単に表象的なるものと、措定的なるものとが区別せられねばならぬ。前者はただ或客体に関係するのみであつて、それについては如何なる存在の措定をも試みないのであるが、後者に於てはそれに加へて何等かの措定的作用が行はれ、対象を単に対象としてではなく、存在するか又は存在しないものとして決定しようとする。(中略)そこでは志向作用は単に一肢的でなくして多肢的(mehrstrahlig)であり、少くとも肯定及び否定の二肢的関係に於て立つであらう。さうして精神作用が多肢的措定作用として表はれるといふのは即ち判断作用として働くことに外ならない。表象と判断とは心的作用としても全く別種の領域に属し、さうしてそれらの互に異るのはこの意味の信念的要素(doxische Element)の有無によつて定まるのである。表象は単に名義的(nominale)な志向作用であるが、判断は実義的なる措定作用である。前者に於て取扱はるゝものは単なる名にすぎないが、後者に於ては存在についての何等かの措定的言表が問題となる。
「表象作用」のように単にあるものを指示するだけでなく、判断の種々相を措定する作用である「措定作用」、何らかの「信念的性質」を有するところの「措定作用」について語られていますが、時枝の言語過程説においては、この「措定作用」的なものとして「総括作用」が語られていたのかもしれません(まだ確信をもって言うことはできませんが)。
また、「表象と判断とは心的作用としても全く別種の領域に属し…」の部分などは、時枝が「文の解釈上より見た助詞助動詞」にて新しい語の二大別の理論である新しい詞辞論を発表するに際し、その理論的根拠のひとつともなりえた可能性があると思います。
さらにもう少し、時枝の「総括作用」論、「総括機能」論に関係している可能性のある山内得立の記述を紹介しておこうと思います。
……此等のノエシスは時にはたゞ一つの作用として働くと共に又多くの結合的作用としても働く。意識と意識とは互に結合するのみならず、また正に一つの意識にまで結合するであらう。我々はこれ等の意識を単に一肢的なる(monothetische)作用から区別して多肢的(polithetische)又は綜合的(synthetische)なる作用と名づける。ノエマに多くの対象を土台とした高次の対象が考へらるゝやうに、ノエシスにも多くの作用から成立つた多肢的なる措定作用が考へ得られる。
表象はたゞ一肢的なる措定作用であるが、判断は本来的に多肢的なる肯定又は否定作用の孰れかである。判断の綜合的性質は例へば次の如く考へることによつて明かにせらるゝであらう。親が子を愛すといふとき親と子との二つの対象が先づ表象せられねばならぬことはいふまでもないが、判断に於てはたゞ此等の表象が次々に措定せらるゝといふだけではない。人はそこに表象の単なる継次的意識をのみでなく、一つの判断を――表象を結合する意識の統一を有たねばならぬ。この統一の故にこそ判断は綜合的であり得るからである。判断作用を行ふといふことは此の総合的意識に於て或ものに対して措定的に関係し、これについて何事かを言ひ表はすことに外ならない。高次の対象が多くの対象を土台としながらそれ自らは一つの対象であると同じやうに、綜合的措定作用も多くのノエシスの綜合でありながらそれ自らは一つの作用であらねばならぬ。
併し我々の茲にそして最後に注意すべきことは綜合作用といふ意味についてゞある。(中略)一方に与へられたる内容が、他方に之を綜合する形式があつて、何故にこの両者が結合して客観的知識を構成するかを問ふことはカントの仕事であつた。カントの綜合性は単に二つ以上の意識が結合して高次的なる意識を構成することのみでなく、それが如何にして知識的なる一般妥当性を得能ふかといふ点にあつた。カントでは判断が綜合的であるといふのは概念の分析によつてゞはなく、何等かの意味に於て経験に関係することによつてゞある。さうして知識はそれ故に拡張せらるるのであるが、しかしながら経験は判断に与ふるに一般妥当性を以てはしない。与へられたる内容は雑多であつて統一性を有つてはゐない。雑多の統一が知識成立の条件であり、与へられたる雑多に統一を与へるものが先験的なる形式であるとするならば、カントにとつても意識の統一は認識成立の最後の根拠をなすと云はねばならぬであらう。現象学にとつても判断的措定作用は一々の表象作用の上に立つて居り、一々の表象的ノエシスは、それに対応する表象的ノエマを措定するが、判断はこれ等多くの表象的措定作用を綜合することによつてのみ可能である。併しながら現象学に於てはこの綜合作用が如何なる仕方に於て表象作用の土台の上に立つてゐるかを、綜合せられたる作用と綜合せらるべき作用とが本質的に如何なる関係を有つてゐるかを研究するのみであつて、この綜合作用が論理的に如何にして可能であるかを論じようとはしない。綜合作用は表象作用を土台とするが、それがそれとして存在する点から見れば全く別種の作用であるといはれねばならない。我々はたゞこの二つの措定作用の、夫々に於て存在するところの様式と此等作用間の本質的なる関係とを研究し得れば足るのであつて、カント哲学に於てのやうに先験的形式が如何にしてこの綜合を可能にするかは、そこに問はるべき問題ではないのである。
時枝は「文の形式的接続と意味的接続」において、文の内容を総括するところの辞(観念語)による「総括機能」論を展開していましたが、「総括機能」論を展開するうえで、ここで山内得立が述べている、ひとつひとつの「表象的措定作用」を綜合するところの綜合的な措定作用である「綜合作用」という概念から、なにがしかのヒントを得ていた可能性はあると思います。ちなみに、こうした山内現象学が現在の現象学研究においてどのように位置づけられているのか、私はまったく把握していません。ただ、時枝誠記が1930年代の後半に言語過程説の理論を構築する際、特に「陳述作用」論や「総括機能」論を展開するにあたり、当時の山内得立の「現象学叙説」のこういった記述内容に少なからぬ影響を受けた面があるのではないか、とは考えています。
また、時枝の「文の概念について(下)」には、
……かゝる表現(「蛙飛び込む水の音」――引用者)が更に分析されるならば、
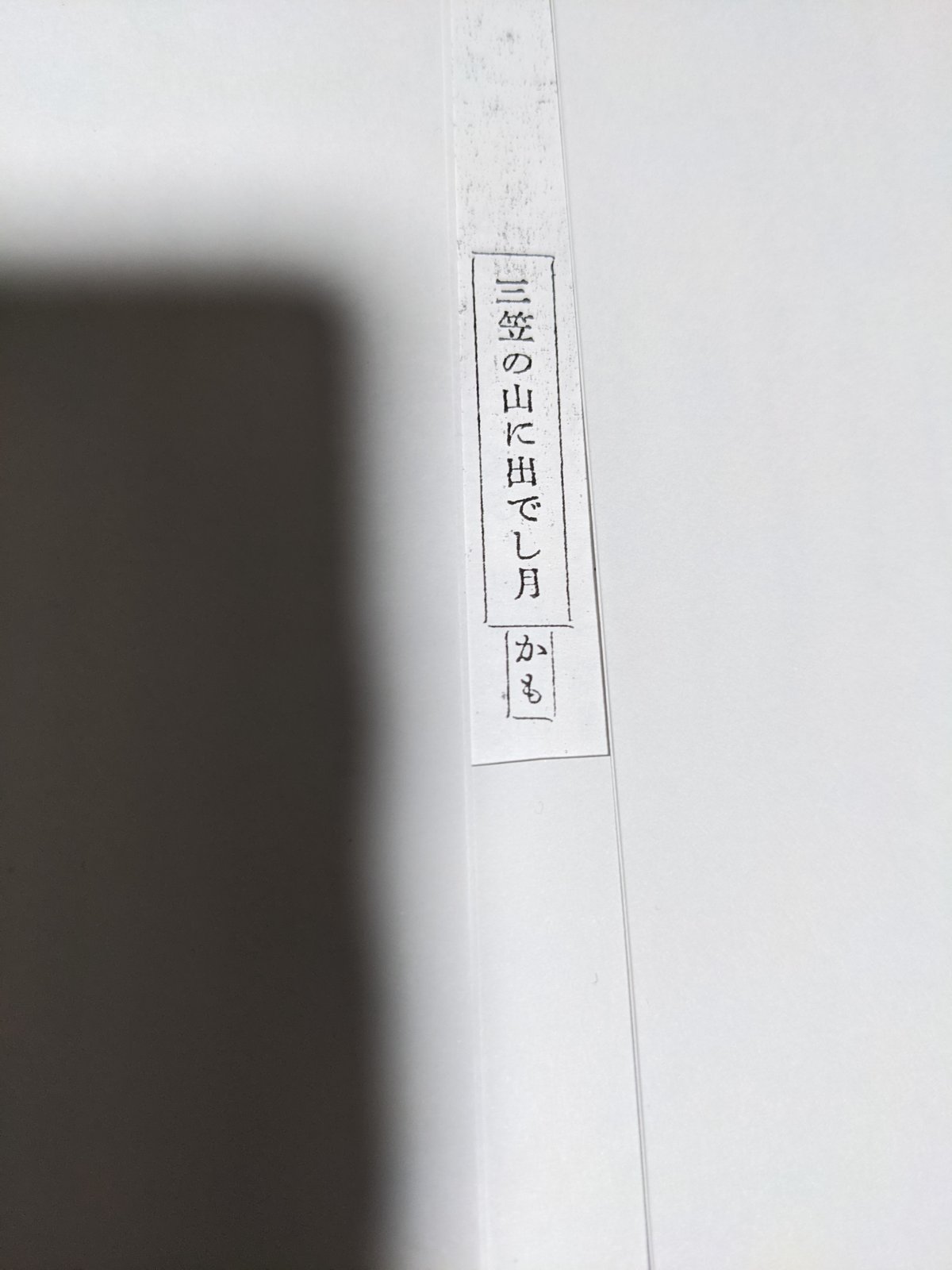
となり、思想の内容と同時に、志向的感情がこれに添加し、線条的に表現せられる。
という部分がありますが、この「志向的感情」の部分は、『原論』へ転載されるにあたり「主体的感情」と書き改められています(15)。総じて時枝は、『原論』をまとめる1940年から1941年にかけての段階においては、現象学的痕跡をなるべく消すように努力していたフシがあります(もっとも、時枝は後年、現象学からの影響について公言するようになっていたため、一時的なものと思われますが)。こうした、1930年代後半の論文と『原論』におけるそれらの内容的な異同の問題については、また別の場所で取り上げて考察してみようと思います。
(2023/3/13 脱稿)
(続く)
~~~
[注]
(1)鈴木一彦「時枝誠記伝」(明治書院企画編集部編『日本語学者列伝』【明治書院、1997年】所収)。
(2)時枝誠記『国語学原論』25~33頁。文庫版『原論(上)』42~50頁。
(3)時枝誠記『国語学原論』29頁。文庫版『原論(上)』45頁。
(4)山田孝雄の「句」論の内容は実質的に文論とみて差し支えないものと思われます。石神照雄「文研究の論理」(石神『日本語文法 体系と方法』【ひつじ書房、1997年】所収)参照。
(5)山田孝雄『日本文法論』【宝文館、1908年】806頁。
(6)同上。
(7)山田孝雄『日本文法学概論』【宝文館、1936年】945頁。
(8)石神照雄氏は、「文に於ける呼格と述格」(『信州大学人文科学論集 33』【コミュニケーション学科編、1999年3月】)において、山田孝雄の「喚体の句」論において「陳述」に該当する構文機能の提示がないことについて、次のように述べています。
……述体に関する山田文法の論理展開では、統覚作用の構文形式への転写に於ける根拠として、用言に「陳述」の概念が用意されていた。しかしながら、呼格に立つ体言には、同様の論理展開を可能にするものとして、何か「X」なる概念が設定されているということはない。(中略)山田文法が呼格について説くところは、述格を説くことと同値的な論理の展開とはなっていない。
そして、石神氏は、「喚体」の場合の統覚作用「X」は、山田自身としては、「感動」として現れていると見做していたのではないかと問題提起しています。
……極論すれば、喚体では述体のような判断の構造的な姿を言語形式として見出せないことから、喚体の判断について独自の論理を抽出できず、単に感動といったものを以て統覚作用と見なしたのではないかと考えられる。
(中略)
統覚作用は、述体と喚体とでその指すところの内実が異なる水準であることを了解する必要があろう。山田文法は、感動に包まれた観念の表示として、体言が「呼格」としてあるということを結果として宣言しているに過ぎない。
(9)時枝誠記『言語本質論』【岩波書店、1973年】304~308頁。
(10) ただし、時枝は『日本文法 口語篇』【岩波書店、1950年。183頁】では助詞に陳述機能を認めなくなっています。文庫版(『日本文法 口語篇・文語篇』【講談社学術文庫、2020年】)223頁参照。
(11)仁田義雄(にったよしお)「時枝文法における文認定」【大阪外国語大学学報、1978年3月】。
(12)三浦つとむ『言語過程説の展開』【勁草書房、1983年】475頁。
(13)三浦つとむ『日本語の文法』【勁草書房、1975年】266~274頁。
(14)田近洵一『くわしい国文法 中学1~3年』【文英堂、1993年】11~12頁。
(15)『原論』349頁。文庫版『原論(下)』49頁。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
