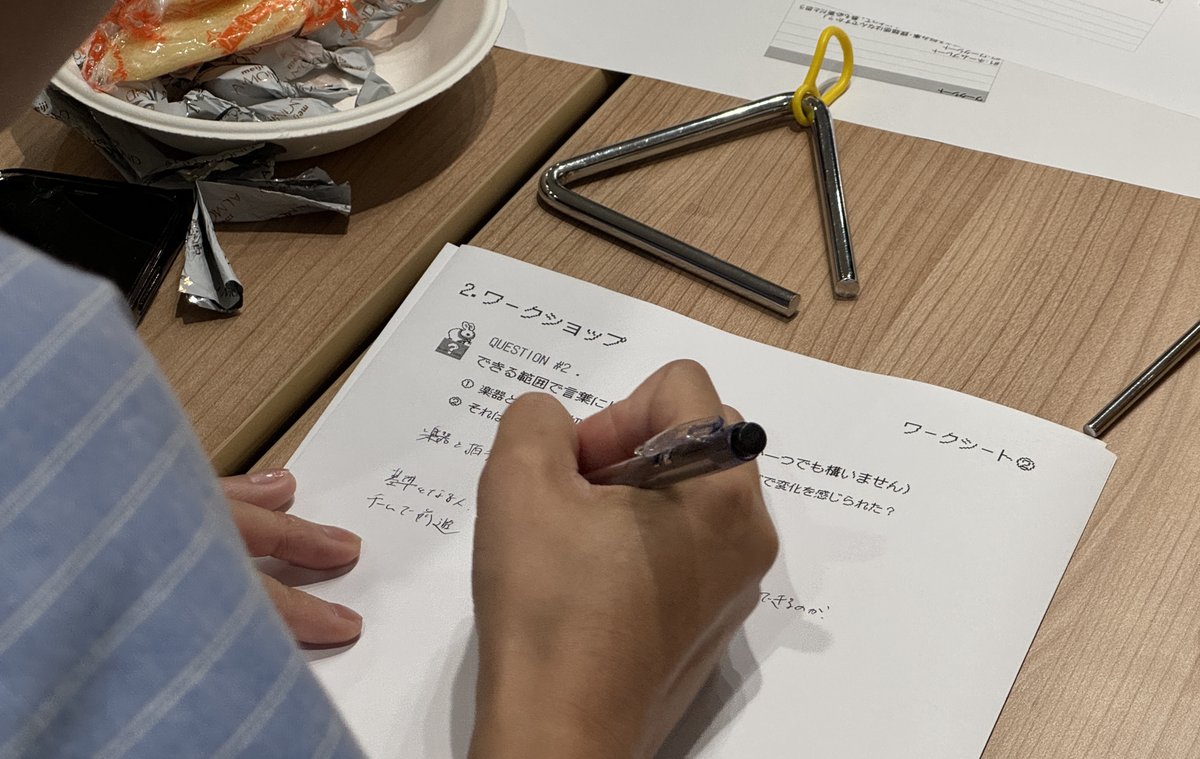「チームワークの秘訣を短時間で体感しよう!」ワークショップイベントレポート
こんにちは、株式会社ハーベストライズ、サービスデザインクエスト代表の川崎です。
本記事はサビクエが5年ぶりにリリースした新作ワークショップ「チームワークの秘訣を短時間で体験しよう!リズムセッションで学ぶチームづくりの要点」について、2回のワークショップ開催を経ての振り返りレポートとなります。
*サービスデザインクエスト(以降 サビクエと記載)は「デザインのナレッジを、あらゆる職種の実務に織り込む」をテーマにした活動です。
*サビクエの活動詳細については、Connpassのコミュニティページ、過去のイベントレポート、株式会社ハーベストライズのコミュニティ紹介ページをご参照ください。
2回のワークショップ開催を経て
約5年ぶりにリリースしたワークショッププログラムは「チーム」に焦点を当てた内容となっています。

リリース後は8月に自主開催したワークショップイベント、12月のSpectrum Tokyo Festival 2024 にて、2回ワークショップを実施しました。
イベントにてご参加いただきました皆様、テストプレイに協力してくださった方々、本当にありがとうございました。
これまでと同様に、当日の様子とご参加いただいた方々の反応をもとに、振り返りと次につながる学びをまとめたいと思います。

アンケート結果
まずはアンケート結果のご報告です。
スコア
8月 サビクエ開催時
楽しめたか?(7段階評価):6.3
難易度(7段階評価:数字か高いほど難しいと感じる ):3.6
期待との合致度(7段階評価):5.4
次回も参加したいか(7段階評価):5.9
12月 Spectrum Tokyo Fest 開催時
楽しめたか?(7段階評価):6.5
難易度(7段階評価:数字か高いほど難しいと感じる ):3.2
期待との合致度(7段階評価):5.7
次回も参加したいか(7段階評価):6.0
誤差の範囲とも言える数字ですが、テーブルレイアウトやスライドの構成など、小さな小さなチューンアップを繰り返したことにより微改善につながったのではないかと解釈しています。
いただいたコメント
アンケートでは本当にたくさんのコメントをいただきました。
以下、コメントの中で印象的だったものを引用掲載しています
本ワークショップはチームワークの要点を言葉で議論し尽くすのではなく、リズムセッションによる体感を得ることでインプットを加速させる事を軸に展開しています。
コメントから「リズムセッションをメタファーにした事のねらい」が成立したことを確認できました。
フィジカルを扱うワークショップで、シンプルに楽しめました!
身体を動かして体感できるのがよかったです
各自の現場での経験レベルに合わせて気づきが変わるようなカリキュラムだった
期待以上でした! この体験は職場に持ち帰るにはどうしたらいいか考えさせられました。
どなたでも参加しやすい、そしてアクティビティにもすぐに入り込めて自分の抱えている課題に投影しやすい構造でとても適切でした
一方で一層悩みや課題感が深くなってしまったというコメントも・・・
実務への取り入れ方が知りたいなと思います。理想はわかったものの、なかなか実務に落とし込むのが難しいと思ってます。
周りを俯瞰して見るという人が組織にいない場合、誰に何を言っても相手にされないのがもどかしいんだと、今日のWSを通して受けて自分のモヤモヤが言語化できてしまいました…。
役割ごとに異なる意見が聞けてとても参考になった。 モヤモヤポイントは出たもののそれを消化する時間がないのが少し残念だった。
振り返り
楽しめた・学びにつながったというポジティブな声と、その結果「より課題感が深くなってしまった」「現実にどう持ち替えれば良いのか悩んでしまう」という葛藤の声が両存するアンケート回答となりました。拝見し、それだけ「チーム」に対して日頃から真摯に向き合っている方々に来ていただいたことを深く感じています。
単一のワークショップ一回で解決できることではありませんが、「意識の持ち方として印象に残り続ける」・「実務への応用が効く」内容を目指すにあたり、みなさんからいただいた回答は貴重なデータとして活用させていただきます。
ご参加とご回答のほど、ありがとうございました。
振り返りから得た学び
作り手として、2回の開催を経て得た学習は以下となります。
チームワークのベースを理解した先で、各参加者が実務に落とすときの方法へ意識が向く一方、ワークショップの時間内では「具体的な踏み出し方」までクリアにならないためモヤモヤが残る
参加者の立場(ジュニア・シニア・マネージャなどのレイヤー)によって、できるアプローチとできないアプローチがある
ジュニア層においては、現場でコントロールできる事が限られており、アクションの選択肢を少ないと感じる
ジュニア層においてはキャリアの悩みに直結しやすく理想とのギャップを実感することでよりフラストレーションや混乱を強く感じさせてしまう恐れがある
ジュニア層に限らず、実行するにあたって「たった一人でどう立ち向かっていったら良いのか」という悩みを抱えてしまう
上記について、本ワークショップとセットでケアできるような内容をコンテンツ化し別途発信することで不要なストレスを感じずに済む可能性がある
学びから描く次のトライ
さらに細かい改良点が見つかり、アップデートする
参加者が社内へ持ち帰りやすいよう、動画でワークショップができるようにするなどオンラインツールを活用したワークショップに昇華する
関連コンテンツとして「本ワークショップのケア」「チームワークを高める」につながる弊社のナレッジを配信をする
リリース時はXアカウント、またはアンケートにて「関連情報・お知らせを受け取る」と回答いただいた方へメールにて発信して参ります。
また、今回のワークショップでモヤモヤが膨らんでしまった!という場合、noteコメントやXにて率直にお声をお聞かせください。
Xアカウント
筆者:https://x.com/kawasagi9
サービスデザインクエスト公式:https://x.com/SD_Quest
ワークショップの設計意図
以降はワークショッププログラムの概要や作り手目線での設計意図などを記載しています。
(アンケートにて、ワークショップデザインの観点でも興味があるとのコメントをいただいたたため)
興味があれば続けてお読みください。

ワークショップの概要
本ワークショップは「チームワークを体感する」ことで参加前と比べて「チームワークに対する解像度を高める」ことを目的としています。
なぜチームワークに注目したか?
優秀な人材が1人、2人いたところで、個人単位で動くだけでは解決に至れないような、難易度の高いプロジェクトが増えた
所属する組織の全体を捉え、「全体の動き」が向上するようなアクションを取れる人材の必要性が高まっている
「チームワーク」や「チームビルディング」について、意識することが是とされる流れの中、一体何をすれば良いのか?ということは明確になっていない
ワークショッププログラム開発の大要求
チームワークに対する課題感というのは、組織の傾向やどの立場から見るかによって見え方がまちまちです。
故に、メンバーそれぞれの経験やレベルに応じて解くための大きな「共通項」と「現状に応じ模索するための意識づけ」が必要となります。
そのため、本ワークショップの開発にあたっては以下を満たすことを最重要視しています。
一つの解決策を提示するのではなく、複雑な問題を切り分け、そのチームの役割に沿って事業や開発を推進するために『どのような組織でも共通項となるチームワークの前提を示す』こと
ワンショット(よりシンプルに短時間)で体感を得られること
プログラムの流れとハイライト

大要求を踏まえた上で、本プログラムはざっくり次のような流れで進んでいきます。
1:イントロ
チームワーク・チームビルディングの解説や言葉の目線合わせ
2:ワークショップ
「リズムセッション」をメタファーにチームワークを高める工程を段階的に体感
3: 解説と深堀り
「リズムセッション」の過程で得た気づきを深堀
各テーブルで上がった言葉を共有
4:振り返り
実務に適用できる学びを抽出
ワークショップのチューンアップ要綱
ワークショップの目的と狙う効果、大要求に基づき、アンケート回答から以下の観点で学習を取り出しチューンアップ箇所を見繕っています。
課題感がより明確になったか
実務への適用や取り組み方のヒントを得られたか
リズムセッションのメタファーがあることにより理解が捗ったか
リズムセッションにスムーズに取り組めたか(学びに対する集中を阻害しなかったか)
上記を起点に今後も「デザインの考え方」を使って「チームワーク」について幅広く実務に活かせる内容を試行錯誤して作り上げて参ります。
付録
ワークショップ資料
本ワークショップで使用した資料の一部を公開いたします。
ワークショップの設計上、リズムワークに関するスライドの公開は今後参加される方の学習効果を下げる要因となるため割愛・マスキングさせていただいております。
(アンケートにて「関連情報・お知らせを受け取る」と回答いただいた方へは別途全編資料を配布いたします)
チームワークに着目した経緯
動画でも話していますので、興味がありましたらご視聴ください。
ワークショップ風景