
100_編集者としての覚悟と、僕の本づくりについて
覚悟というのは、本来、人に発表する必要がないのはよくわかっているのですが、僕の覚悟は普通とは少し違って、人に話すと嬉しくなるタイプのヤツのようです。もし、あなたに読んでもらえたら、僕の力になります。本当に、ありがとうございます。
転職をしました。
正確に言うと、ビジネス書・人文書・実用書などをつくる書籍編集者の職はそのまま変えずに、2社目に移りました。
今このフレッシュな気持ちが残っている間に、どうしても「編集者」という仕事への気持ちをまとめておきたかったので、この連休のタイミングで一気に書ききりました。
これから先、大変な想いをしたり、大きな失敗をしたり、
人生の岐路に立ったりするようなことがあるかもしれない。
そんなときに、
あのときはこう本気で考えていたんだな
今、あの頃の気持ちを、忘れてしまっていないか
そう気づくための、セーブポイントを一つ作っておきたい。
これが、この文章が生まれた理由です。
(僕はどうやら、こういうことを真面目に考えるタイプの編集者のようです)
基本的に、自分のためのものです。
アタマの中にあることを、一つ残らず書き留めておきます。
だから大きいことを言います。怖いけど言っています。
どうか、そういう記事だと思って読み進めてあげてください。
16,270文字です。(どどん)
※2023/6/15時点
目次です。記事がボリューミーなので、目次の使い方も載せておきます。
■通読する場合
途中に、【いま全体の●%】というガイドを出しているので、ペースメーカーとしてご使用ください。
■部分読みする場合
目次に載っている小見出しに付けている★の数で、内容を分類しています。クリックして、お好きなところから読んでください。
・書籍の編集者になるまで:「★」から
・編集者として読者に届けたいこと:「★★」から
・↑を実現するための、編集者としてのスタンス:「★★★」から
・編集者としての「覚悟」について:「★★★★」から
★「編集者になるためにWEB記事100個書いてやる」。動機は忘れても、毎日1記事を書いていた頃の気持ちは今も覚えている
僕が編集者になってから、まもなく2年が経とうとしています。
(とはいっても、うち1年9ヶ月は編集と営業の兼務だったので、純粋な編集のキャリアが積めていたわけではないのですが)
損保会社での3年間があるので、社会人としては6年目に差し掛かったところです。怖いくらい早いなと思います。
まずはこのアカウントについて。
そもそもこの「ひつじ」のアカウントは、いわゆるTJC(トラディショナル、ジャパニーズ、カンパニー)の大手損害保険会社に勤めていた24歳のお盆休みに、
どうにか人生を変えてやろう。
と思い立ってつくったものです。(↓記念すべき1記事目がこちら)
この時点では、特に編集者になろうとかは考えていませんでした。
本の編集者になることを直感したのは、
その3ヶ月後、会社からの帰り道を歩いている途中のことです。
(この詳細は今回の記事の主題から外れるので、割愛します)
そしてその後このアカウントは、
編集者になるために、まずはWEB記事を100本書く
チャレンジの舞台に進化しました。
(↓その記念すべきキックオフ記事がこちら)
結果として、このトライアルは投稿数80記事くらいで終わってしまいました。目標未達です。
でも僕は、この取組を結果的Good Jobとして整理しています。
それは、この目標を達成するより遥かに大事な
「編集者になる」
を達成できたから。
24歳の4月には損害保険を売っていたのに、いま27歳の4月には本づくりを始めて2年が経とうとしている。
たった3年の間に起きた出来事だとは、時々思えなかったりします。
「運と縁が来たら、いつでもつかめる」。意識していたわけではなかったけれど、それくらいにはジタバタしていた
大手金融から、出版業界に入る。
新卒以外の就活ルートで、未経験から本の編集者になる。
到底無理だろうという壁でした。
詳細は省略しますが、それでも、僕は今、編集者になっています。
もちろん、僕が編集者になれた理由は、僕がすごいからではありません。
でも、「単に運がよかっただけだ」と思っているかというと、実はそれも少し違います。
運と縁と、それを掴むための決死のストラグル。
そして、「すべてがムダかもしれない」「そんなこと意味がない」という自分の心の声と戦えるほどの、狂気に近い確信と、執着。
これが、僕がやりたい仕事にたどりついた理由だと思っています。
※運と縁に恵まれるための苦闘を表すnote記事は、今もこのアカウントに静かに残っています。(note記事タイトル冒頭の001〜081まで)
ネットの世界は、一見、いつでもアクセスできるようで、明確な優先順位付けがある世界。あのnote記事たちがまた日の目を浴びることは、おそらくないでしょう。でも僕にとっては、不格好な一つひとつのnoteが、静かに隠れて光る宝物なのです。
=====ここまでで10%=====
「だから、僕は本を信じている」そう言える理由はあまりにシンプルなので、少し丁寧に説明することにしている
僕が編集者になりたいと思ったのは、
本によって、人生が変わったからです。
僕は、本を通じて、
これから先40年続くと予想していた一本道の人生から抜け出し、自分で道を作っていく選択ができた
のです。
三兄弟の長男として生まれ、中学・高校・大学受験をコンプリートしてくぐり抜け、大学卒業後には、「一流企業だね」と人から評価される大手金融に入る。
いわゆる「恵まれた境遇をフルに使って、置きに行く人生」。
こんなリスクマネジメント人生を25年続けてきた人間を動かしたのが、本だったのです。
※コラム※
……毎回思うのですが、「人生が変わる」って言葉、どうしてもうまく伝わらない感じがします。大きいことを言っているはずなのに、何も心に残らないフレーズ。その理由はいくつかあると思いますが、
仮説1:伝え手の多くが人生が変わっているのに対し、読み手・聞き手の多くが、「人生が変わったことがない」ため
仮説2:別に人生が変わらないのに、そう豪語しているものが多いため、「人生が変わる」という言葉自体の価値が下がっているから
パッと思いつくのはこの2つかなと思います。
話がそれましたが、僕が言いたいのは、
「人生が変わった」という言葉に疑問を感じてはいるものの、
「本で人生が変わった」ことが紛れもない事実だと受け止めているということです。
★★「自分の人生になかったはずのトビラ」は、ひとりでは開けられなかった
僕が本を信じるようになったきっかけは、『メモの魔力』。
恥ずかしいくらいど真ん中の、いわゆるビジネス書ですね。
この話は、僕が23歳の頃、損保に勤めていた頃に遡ります。
当時、つらい仕事に耐え続けていた僕は、
とんでもない量の悩みを抱えていました。
仕事がつまらない。
お客さんのためにも、取引先のためにも、社会のためにもならないような、
「三方悪し・無意義」としか思えない仕事に取り組む日々。
だからやる気も出ないし、当然、人から評価もされない。
時折もらえる「ありがとう」の言葉を素直に受け取れないことが続き、気持ちが滅入っていました。
しかも、それなのにお金がもらえる。
生真面目すぎるかもしれませんが、当時、僕は「このお金はもらっていいお金なのだろうか」と相当ジレンマに感じていました。
まわりの友人は楽しそうにしています。
たまに同窓会に顔を出すと、高校、大学の同級生は、みんな生き生きとして見えました。
もう、なんのために働いているのか、
考えても考えてもわからなくなっていたのです。
今考えてみると、完全にアタマが閉じている状態。
こういうときには、人のアドバイスも、相談も、効果をなしません。
マンガを読んで感動しても、小説を読んで泣いても、現実は何も変わりませんでした。
2次元世界は3次元世界を知覚できないと言います。
当時の僕は、ちょうどこれと同じ状態でした。
知覚できないものは、存在しないのと何ら変わらないのです。
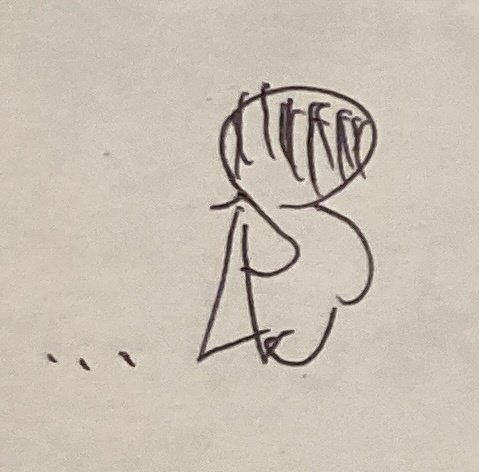
(伝わっていればいいな、と思います)
「遠くで聞こえた雷鳴が、稲妻になって僕を貫通した」身体性を伴う読書体験にハマったのは、間違いなくあの時からだろう
そんなある日、実家でテレビを見ていると、
『世界一受けたい授業』が流れました。
普段から見ているわけではないので、たまたまです。
そこで『メモの魔力』が特集されていました。
番組を見て「なるほどなー」っと思いました。
このとき僕のアタマに、ゴロゴロと音がしていたような記憶があります。
今思うと、無意識に変化の兆しを感じていたのかもしれません。
でも、そうした「無意識の期待」が、まさか本当に僕を生まれ変わらせるとは、少しも気づいていませんでした。
数日後、僕はその本を手に取り、ボーッとページをめくり始めました。
それから30分後、
僕の全身に走ったのは、稲妻でした。
脳が目覚め、身体の力がどこからか湧いて出てきて、
僕の底から新芽が萌え出てきたような気がしたのです。
絵で伝えます。
このときの僕は、こんな感じでした。
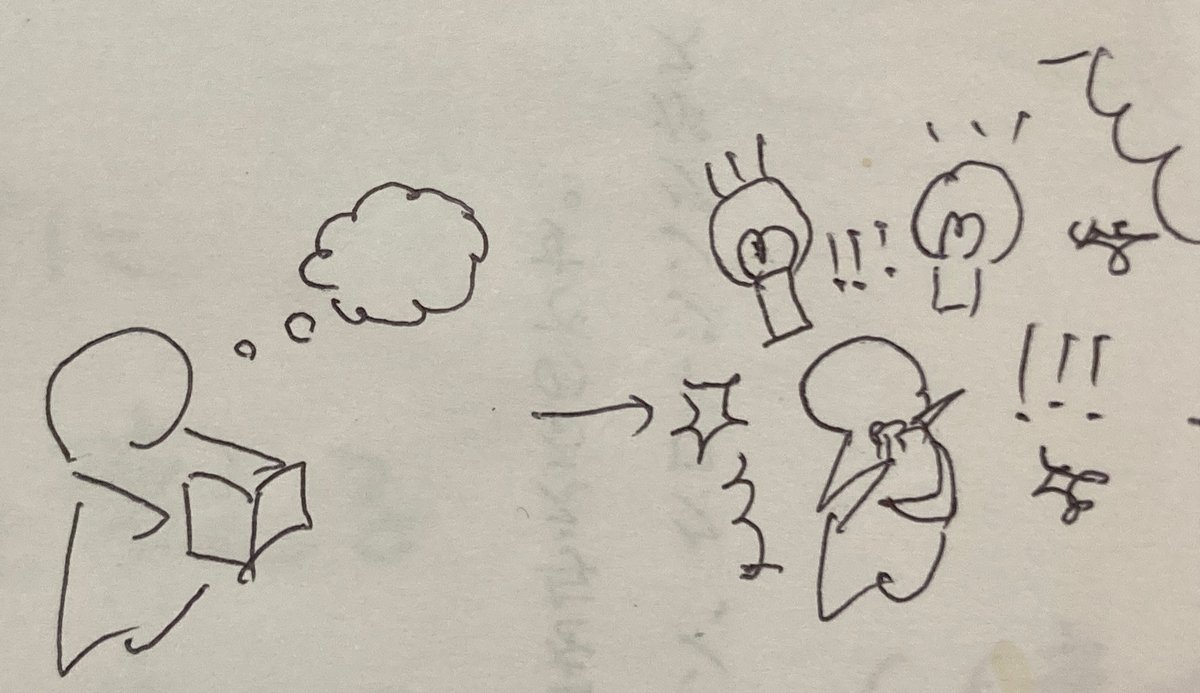
(伝わっていればいいな、と思います)
僕はこの本をすぐに読み終えました。
そして信じられない速さで家を出て、スーパーでA4ノートと4色ボールペンを買っていました。
ちなみに、『メモの魔力』が僕に教えてくれたのは、
ざっくり言うと、こんなことです。
頭の中で考えた内容は、そのままだと忘れていく。
すべて書き出せば形として残るので、行動の蓄積に変わるし、堂々巡りもしづらくなる。
書くことを通じて、自分の考えの過不足を客観視できる。これにより考えの精度が高まる。
さらに、内容を抽象化して転用すれば、思考を人生の全てに転用できる。
どうでしょう。「いいこと書いてあるな」と思いますか?
もしかすると、「これが何?」と思う人はたくさんいるのかもしれませんね。
でも僕は、頭を殴られたような衝撃を受けたのです。
本が僕のアタマを殴ってくれたのは、「強い衝撃があれば開花するくらいまで、経験値が十分貯まっていたから」だったのかもしれない
それまでの僕は、悩みを溜め込み、ぐるぐる考え続け、
テレビを見て、ベッドに寝そべりながら、
いつもいつも嫌な仕事・職場のことばかりを考えてしまっていました。
朝も嫌で起きられません。人に評価されるのも怖い。
そんな繊細で、弱い自分が本当に嫌いでした。
そんなとき、本が僕を殴ったのです。
「僕が毎日思い悩んでしまっているのは、悪いことじゃない」
悩んでいることは、悪いことじゃない。
書き出しさえすれば、それはむしろ超長所になる。
この本は、僕にそういう「気づき」をくれました。
そこから、いつもどおりに繊細に思いを巡らせながら、
僕はとにかくメモを取りました。
考えを深め、分析する。
自分の悩みを詳しく、深く、人に説明できるくらいまで、極めました。
そして、このとき僕は気づきます。
人の目を気にしてばかり生きてきた僕は、
自分の経験したことについて、何がすごいのか多角的に分析すること
人のすごいところを、すごいと見抜く目
それを、たくさんの人に伝えたいと思う気持ちの強さ
わかりやすく、たのしく、伝えようと工夫する努力
無意識のうちに、これらに膨大な時間をかけてきていたのです。
「この本に書かれているのは、僕のことだ」
僕と本が、完璧にシンクロした瞬間でした。
そこから僕は、本屋さんで本を買い、読み、
人の話を聞き、そして毎日のようにノートを書きました。

【知の爆発】→【身体が勝手に行動し始める=メモ】→【自己肯定感爆上がり】
(これはわりと、伝わりはするんじゃないかとは思います)
きっと、本は、
「変わる用意ができている人」
の人生を変えてくれるものなのでしょう。
「編集者になりたい」
思い返せば、そんな直感が訪れてくれたのは、ここから9ヶ月も先のことでした。
僕は、『メモの魔力』で人生が変わったのです。
=====ここまでで35%=====
「知」の力を使わないのは自由だが、この力は本物だ
前置きが随分と長くなりましたが、
僕は、この経験から確信していることがあります。
それは、
「ノウハウ(=何かの、上手いやりかた)はバカにできない」
ということ。
世の中には、
ノウハウってなんだか薄っぺらい、付け焼き刃的
ビジネス書は意識が高そうで、なんだか敬遠しちゃう
そもそも、楽しく生きていればいいだけだし、別に興味がない
そんな声がたくさんあると思います。
でも、ロクに学びもしないのにノウハウをバカにしている人がもしいたとしたら、僕はその人のことを、申し訳ないですが「2次元で止まっている状態ですね」と表現してしまいます。
先人が10年かけて見出した「何かの、上手いやりかた」を、2時間で知れるのです。
これは「知」です。
ただ知るだけでいいのに、知ろうとしないんだから、普通にもったいないです。
「知」を使わないのは個人の勝手ですし、のんびり人生ならば好きにすればいいと思います。
世の中のエンタメに触れていれば、たとえ悩みを抱えていたって、最高の気晴らしができるでしょう(僕もエンタメは大好きです)。
でも、これだけは聞いてください。
本当に伝えたいので、【中央揃え】でお送りします。
自分には才能がない。
すごい人に、自分は一生なれない。
どんなに頑張ってもうまくいかない。
もし、そう悩んでいるとしても、絶対大丈夫です。
何かがうまくいっていなかったとしても、
それはあなたが悪いのではありません。
あなたはただ単に、知らないだけ。
上手いやり方を知りさえすれば、いいのです。
知れば、自分の動きが変わります。
動きが変われば、あなたの本当の凄さが世に少しずつにじみ出ます。
そして、周りが変わり、運と縁が向こうから会いに来ます。
何かを「知る」というのは、それほどのことだと、僕は信じています。
僕は、これまでの「ビジネス書」「人文書」「実用書」が届く範囲の、もう一歩奥にいる人に届く本をつくる
僕が目指している本づくりの話をします。
一番の基本スタンスは、
「もっと知られてほしいことを、もっと知ってもらいたい」。
これが、僕が目指している本づくりの大前提です。
そして僕は、本の力を信じています。
それは、僕自身が助けられたから。
確信なんて、これくらいの根拠で持っていいと思っています。
僕を変えてくれたのは、結果として、本でした。
WEB記事、動画、映画、雑誌ではなかったのです。
でも世の中には、こういう本に出会っている人は、
まだなかなかいないと思います。
僕は、誰に向けて本をつくるわけではありませんが、そういう本をつくっていくことだけは、はっきりと決めています。
だからたとえば、僕は単なる「ビジネス書」はつくらないつもりです。
僕のつくる本の用途は、ビジネスに限らないからです。
実際問題、目の前のビジネスがつまらなくてつまらなくて仕方のない人に、ビジネス本が届く確率は低いでしょう。
「もっとよいビジネスをしよう!」と説かれたところで、ビジネス自体をやりたくないんですから。
事実、僕に「ビジネス書」が届いたのは、書店の「ビジネス書」の棚を通じてではなく、TVが僕のプライベートの時間に食い込んできたからです。
ビジネスとプライベートの境界が融け合う現代では、もっと、奥まで踏み込める力が必要になってくると考えています。
(ビジネス書の代表的なジャンル「自己啓発」も同じです。これも「自己を啓発したい!」という人には届くと思いますが、「僕・私なんてもうだめだ……」と下を向いている人には見えづらいんじゃないかと思います)
僕は、
本の効果範囲の、その先の人にこそ、ノウハウ・知識を届けたい。
これは、僕がこれからつくるすべての本に通ずる哲学です。
既存のジャンルには収まりきらない本をつくったとき、
世界には、きっと何人もの「新しい僕」が生まれるはずです。
世に出るはずのなかった才能に「知」を届け、世に意義のある変化をもたらす。
それが僕のつくる本です。
(たぶん蛇足なのですが、色んな読み手の人がいると思うので念のために補足しておくと、
僕がつくる本がこれからビジネス書の棚に置かれることは当然あると思っています。
転職についての本とか、自己分析系の本とか、目の前のビジネスがつまらなくても手に取るジャンルの本も当然あります。
これはそういった事務的な話ではなく、もっと観念的な、マインドセットの話だと捉えてもらえればと思います)
=====ここまでで50%=====
★★★つくる本のコンセプトが、編集者としての存在意義を確かにする
ここまでは目的。ここからは手段の話です。
僕は本を通じて、ここまで述べてきたようなことを実現します。
そのために必要なのが、僕のつくる本のコンセプト。
コンセプトのない本は、自己満足に陥るのが目に見えているので、
未来の読者と関係づけるコンセプトを、今、定めておきます。
(これがなかなか見出せなかったので、記事の更新が遅れました)
1:僕が本に取り組む理由
本=「具現化したポータブルなコンセプト」である
「そもそもなぜ僕が【本】に取り組むのか」から始めます。
僕は、本は【コンセプトを具現化するのに適した、最高の媒体】だと考えています。
コンセプト=「全体を貫く新しい観点」
具現化=「実際となって現れること」
本はメディアの一つです。つまり、何かのコンテンツ(=中身)を載せて、人に届ける方法の一つということです。
本は特に、ある程度重みのあるコンテンツでその力を発揮します。
そして、重いコンテンツの代表例が【コンセプト】です。
コンセプト=【全体を貫く新しい観点】。明らかに重たそうですね。
生半可な気持ちでは受け止め切れない感じがします。
情報量も必要そうですし、運ぶのにも、受け取るのにも、手間と時間がかかりそうです。
WEB記事、雑誌、新聞、TVニュースとかだと、これは運びきれないでしょう。ビジネスモデル的に速さと数を求められるメディアでは、【コンセプト】の伝送は荷が重いのです。
その点、本は200〜300ページかけて、何か1つのテーマに沿った【全体を貫く新しい観点】を伝えることができます。
WEB記事や雑誌、新聞が自転車やタクシーだとしたら、本はいわば2トントラック。誰かの人生を変えてしまう【コンセプト】を搭載できる、重厚な乗り物なのです。
そして、本は【ポータブル】性を持ちます。
ポータブル=「持ち運びのできるさま」
まず、本は小型かつ軽量です。人の手によってどこにでも持ち運ぶことができます。
たとえば、セミナーや授業といった比較的重厚な内容を伝えられるメディアは、【コンセプト】の荷重に耐えることはできますが、肝心のメディアの運搬ができません。話ができる講師が移動して、開催場所を確保しないといけないので、身軽さに欠けるのです。連続授業などなら、なおさらですね。
さらに、口コミによって広がりやすい適正サイズのユニットでもあります。
友人と話しているときに、WEB記事1つ、動画1つ、TV番組1回だけを人にオススメすることはあまりないのではないでしょうか。
「神回」とかは例外ですが、普通は【媒体名】や【YouTuberの名前】、【番組名】を伝えると思います。別にそれが悪いと言いたいわけではなく、これは、単にそれぞれの耐荷重が異なるということを表しているにすぎません。
単発でのパワーは小さいけれど、連続して見ることで価値が蓄積されていく。こうしたメディアでは、そうやって【コンセプト】が徐々に伝達されていくわけです。
この点でいくと、本は、小型かつ軽量なのに、積載荷重が異様に大きい。文字とイラストだけのシンプルな伝え方で、とんでもない情報量を載せることができるのが、本の特徴です。
伝え方をシンプルに抑えることで【コンセプト】自体を軽量化する。そして手元に届いたところで、読み手の想像力を借りて一気に膨らます。そういうメディアです。読み手に一定の読解能力を求めはしますが、その分、たくさんの荷物を運ぶことができます。
さらに、日本には、本をつくれば日本中のリアル書店やネット書店にわずか数日でリーチできる流通網があります。冷静に考えると、すごいですよね。
端的に言ってしまえば、本は、超コスパのいい乗り物なのです。
僕は編集者として、誰かの人生を変えるためのものを作りたい。
だからこそ僕は、今あるメディアの中で、本を選びました。
本は、僕が本当に伝えたいことを伝えられる、当世随一のメディアなのです。
※重厚なコンテンツを運べるその他のメディア
【マンガ】巻数が多くなるので耐荷重の高いメディアではないが、熱伝導率が異様に高いので、重厚なコンテンツを運ぶことができる。本との親和性も高いが、エンタメのほうがニーズが強い。
【映画】約2時間かけて重厚なコンテンツを届けられるうえに熱伝導率も高いが、ハード(鑑賞環境の良し悪し)に品質が左右されやすい。また、関係者が多いため自分の意見が反映しづらい。
2:僕がつくる本
まず結論。
僕は、
次元を飛び超える「知の爆発的興奮」を、読者の内に噴出させる本
をつくります。
ここから、それぞれの解説です。
まずは、僕の考える「本」像。
そしてその後、コンセプトを「/」で3段階に分けて、解説します。
次元を飛び超える/「知の爆発的興奮」を、/読者の内に噴出させる本
①次元を飛び超える
僕たちが住んでいるのは、少なくとも3次元以上の世界です。
「時間」を軸とした4次元に住んでいるという説もありますね。
でも、僕たちは5次元、6次元はもちろん、それ以上の次元がどのような世界かを知覚することは絶対にできません。
本当は僕たちが気づかないだけで、7次元とか、8次元とかもあるのかもしれません。ですが、知ることはできないのです。
これは、次元の知覚に関する、ある特性が関連しています。
それは、一方通行。
ある次元にいる人は、それより大きい次元のことを知覚できないのです。

※以下は掲載義務がある文言。(NerdBoy1392 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5514315による)
少し、詳しく説明しておきます。
たとえば、3次元は2次元を知覚できます。
※【立体】の世界でも→【面】を知覚できる。
これは、「奥行き」の変数zが増えても、それまでのxとyを引き続き知覚できるためです。
同じように、2次元は1次元を知覚できます。
※【面】の世界でも→【線】を知覚できる。
これも先ほどと同じく「高さ」変数yがあったとしても、それまでのxは引き続き見えるためです。
でも、逆は知覚できません。
たとえば、【線】の世界にいる人は、【面】を理解できません。
「高さ」という概念がないからです。
同じように【面】の世界にいる人は、【立体】を認識できません。
「奥行き」という、考え方そのものが存在しないからです。
↓
これと同じように、【立体】の世界にいる我々は、それより先の次元を知覚できないのです。
本づくりの話に戻ります。
僕のつくる本は、
現次元の世界から新しい次元の世界へ飛び立つための、「新しい変数」の役割を果たします。
どういうことか。
たとえば、それまでx+yでしか説明できなかった事象に、新しく変数zを追加するとどうなるでしょうか。
ぐちゃぐちゃとしてまとまっていなかった、つながりが見出だせなかったx+y状態に、僕の本「新しい変数z」が登場します。
すると、それまで説明できなかったすべての事象が、新しい変数「z」を通じて、明快につながるようになるのです。

After:変数zを追加した三次元で見ると、実はシンプルな赤色の直線だったと気づける
この「新しい変数」は、外から与えられるものではありません。
もともと自分(=読者)の中に存在していたにも関わらず、
知覚ができていなかった「変数」、要は「埋もれていた変数」です。
もともとそこにあったのに、次元の制約で、見えていなかった。
なんとなくモヤモヤしていた。
そういう、隠れたドライバーです。
この変数zを見出した読者は、どんどん変わっていきます。
正確には、その人自体は何も変わっていないのですが、
「新しい変数」=「気づき」を得たことにより、その後の「行動」が変わっていくのです。
新しい変数zを見出したことで、zなしで考えていた頃のことが、あまりに陳腐に思える。
それまでの日常も、その本を読んで変数zを手に入れた前後で、
見え方が全く変わってしまう。
読後、読者のスタンダートなものの見方として、完全にインストールされている。
このような、2次元空間を3次元に、3次元・4次元空間を5次元以上へ連れ出すような本。
読者が【次元を飛び超える】過程を通じて、
【もともと確実にあるのに知覚できなかった変数】の存在に気づける効果を持つ本。
これが、僕がつくる「次元を飛び超える」本です。

「やっぱそうだよなあ」「まあ、よくまとまってるなあ」「退屈しのぎにはなったな」ではダメなのです。
この次元を飛び超えるためのヒントを持っているのが、著者さんです。
著者の方々は、一般人よりも次元の高い世界に住んでいます。
(もちろん比喩です)
それは、生まれ持った才能、独自の経験、社会的立場や成功体験など、さまざまな形で表出しています。
それを、編集者としての僕が見つけ、現世の人々にわかるように伝えるのです。
高次元の世界のものの見え方を、読者の世界とつなぐこと。
これが編集者である僕の役割です。
(「次元を自在に動く」活動になるので、微分積分の考え方が絡んでくるかもしれないですね……)
ちなみに、読み手の想定感想は、こんな感じです。
「そうそう、そうなの! わたしがなんとなく思っていたことなの!」
(↑理解のための新しい変数をインストールできた状態)
②知の爆発的興奮
次元を飛び超えるほどの知です。当然、超すごいはずです。
ただ、僕は次元を飛び超えた経験がないので、生まれたのがこの2です。
(「①次元を飛び超える」で理論的には十分まとまっているのですが、身体感覚ベースで感知できない凄さに不安を覚えました)
まず、僕の本を読むと、読者はこうなります。

説明が難しいので事象を羅列していく形で、実像に迫っていきます。
まず、感想が「ふーん」「へぇ!」では終わりません。
そんなレベルではないのです。一瞬声も出なくなってしまうような、思考の停止と溢出をともなう感動体験です。
そして、本能的に身体が動き出します。
これは、興奮があふれるあまり、つい他の人に話したり、何かに書き留めたりしてしまうということです。
最後に、アタマの中で音がします。
ガラガラ、ドカーン、ビリビリ、パーン。
現実で超時空移動をしているんですから、それくらい当然ですね。
自分の中の何かが壊れる音がするんです。
僕はこれを、知の(知による)「爆発的興奮」と定義しました。
だから、いっとき売れて、すぐに忘れられる、いわゆる「瞬間最大風速の強い本」や、時流が過ぎれば忘れ去られる本、読んだらすぐに捨てられてしまうような本は作りません。
読者の想定感想としては、
「こんな本、初めて! もう、とにかくすごいの!」
(↑抑えきれない興奮で、言語化がうまくいかない状態)
「ほんとに、いいからとりあえず読んでほしい!」
(↑説明ができないが、確かに良かったので、オススメしてしまう)
とかですかね。
(ちなみに感想のセリフは、かなり俗な言い回しをイメージしています。この記事の文体から少しはみ出るのですが、実際の会話は、これくらいのトーンだと思います)
③読者の内に噴出させる
これは、先ほどの「②知の爆発的興奮」が、外からではなく、内的源泉から生まれることを示すための要素です。
僕のつくる本は、外側から圧倒的な知識という名の暴力で殴ったりしません。無責任な言説を、誰彼構わず押し付けたりもしません。
僕の携わる本は、そうではなく、
読者の内に眠っている力を沸騰させる作用を持ちます。
イソップ寓話の『北風と太陽』の最も有名なシーンをイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。
北風が太陽に力比べを挑み、太陽はOKする。
北風と太陽の前に一人の旅人が通りかかる。旅人の服を脱がせたら勝ち、という勝負になった。
北風は、どんどん強い風を当てるが旅人は服を脱ごうとしない。
次に太陽が旅人に日光を注ぐ。旅人は体が温かくなり、上着を脱いで薄着になった。さらにあまりの暑さに途中の池で服を全部脱ぎ、水浴びをする。
力比べは太陽が勝った。
(てにをはを少しいじりました)
https://arasuji-m.com/kitakazetotaiyo/
北風は外から強制的に旅人のコートを脱がそうとしましたが、
太陽は旅人の「コートを脱ぎたい」という気持ちを強める手をとりました。つまり太陽は、もともとそこにある気持ちに、アクセスしたのです。
僕のつくる本も、これと同じです。
読み手の中に潜む感情にアクセスして、「②知の爆発的興奮」を、マグマのように噴出させるのです。
読者の想定感想としては
「もっと前から、この本に出会っていたら……」
(↑感情が読者に内在していた時間を匂わせるもの)
「私のために書かれた本だと思った」
(↑読者の内にダイレクトにアクセスしていることを感じているもの)
です。
特に大事なのは、
とにもかくにも、読者ファーストで本を作るということ。
人間の根源は大きく変わらないでしょうから、
自然と、ロングセラーを目指せるタイプの書籍が増えていくでしょう。
そのためにやれることは、全部やります。
基本動作として徹底します。
ここだけは、絶対にブレません。
※ちなみに、エクスキューズとして。
「アタマを殴られたような衝撃」は、結局、衝動が内から湧いているのでOKです。あと、「飛び超える」は本来「飛び越える」=「越」が正しい用語ですが、意味を込めているのであえて「超」で統一しています。
気にかかった人はとても読みが深いのではないかと思います。レトリックに感度(ただし、狂気に近い)があるので、編集者に向いているのではないかと思います。
=====ここまでで80%=====
★★★★「編集者として恵まれている」と瞬時に感じているのは、「恵まれていないのが何か」をたくさん知っているから
最後になります。
僕は、これまで一度も職場環境に恵まれたことがないと思いこんでいました。
思い込みのあまり、そういう記事を書いちゃったくらいです。
(「あ、こいつ、環境に文句を言って人のせいにするタイプか」と思った人は、時間のあるときにリンク先の記事も読んでほしいです。読むとわかるのですが、僕は過去の環境に悪口を言ってはいませんし、環境のせいですべてが上手くいかないなんてことはまったく思っていません。)
この記事を自信を持って出せたのは、今回の転社先が「恵まれた環境だ」とわかったからです。
社会人を始めて5年目。とうとう、自分が心から納得できる仕事を、スタートできる素地を得ることができました。
不思議なもので、中途半端に良い・悪い環境にいると「環境のせいにしたくない」思考が働くのですが、今回みたいに極端に良い環境に出会うと、そういう思考プロセスを省くことができるのです。
(きっと、極端に悪い環境というのも即分かるのでしょう。どちらかにキャラ立ちしているほうが、玉虫色よりも判断はしやすいです)
ただ、それを差し置いても、良い環境を瞬時に見抜けるのは、僕が「同世代の中では「恵まれていない環境とは何か」を数多く知っているほうである」というのが、関係しています。
=====ここまでで85%=====
「つらかった全てが今のための下積み」というよりも、「下積み全てがチャンスを引き寄せる」のほうが感覚としては近い
僕は本当に、仕事のできない社員でした。
新卒のときは、よく取引先との約束を破りました。
それは、社内の仕事や上司を優先するため。でも、結局取引先をないがしろにしているので、上司には怒られました。
仕事をよく遅らせました。それは、僕が残業すると、僕の上司がその上司に怒られるからです。
ミスを隠しました。
それは、自分が怒られると思ったから。結果、時間が経ってから上司に伝わって、倍以上で怒られました。当たり前ですね。
会社で生き抜くために必要な、最低限の社会人のマナーすら知らなかったし、それを理解できた後でも、怖くて臆してしまい、身動きがとれなくなっていた記憶があります。
何をどう優先すればよかったのか。今なら少なからずわかるのですが、でも、当時は本当に、これで精一杯だったのです。
お酒もあまり飲めませんでした。それでも付き合いで、週4は酒席に顔を出しました。「飲めば強くなるぞ」「やるじゃないか」そう言われて、キャパシティを越えて飲んで、終電を乗り過ごしたことは20回くらいあったのではないかと思います。タクシーに使うお金がバカバカしくて、5000円をケチって3時間歩いて帰っていました。
朝が起きられませんでした。スーツを着て8時10分に出社すると、他の先輩方はみんな揃っています。起きられない自分はなんて根性がないんだろう。なんてだめなんだろう。そう思うと、夜寝るのが怖くなっていきました。
しかもそれらを耐え忍んで、我慢しても、その先にやりたいことがなかったのです。でも、それで仕事をすぐにやめるほど、思い切った決断ができる人間でもありませんでした。
かと言えば、生意気にも「会社組織は、あれもこれも、変えたほうがいいことばかりだ」と感じていました。要らない報告。無駄な手作業。管理の管理の管理。かと思うととんでもない抜け穴……。
毎度、「もっとこうしたい!」「直したい!」と感じていました。
いちいち考えずに、ルールを守るかどうかに集中するほうが、よっぽど幸せだろうと何度も思いました。(事実、そういう人のほうが、しっかりと仕事と幸せを両立していました)
長々と書きました。すみません。
でも長く書いたのは、これが僕の、5年間の下積みだからです。
こんなふうに、僕は、たくさん揉まれて、失敗をして、無様な姿をさらして、それでもいろんな人に支えてもらって、今、なんとかこのスタート地点に立っています。
今は会わなくなってしまったけれど、何度でもお礼を伝えたい先輩がたくさんいます。信頼できる人間としての基本動作を僕に教えてくれたのは、紛れもなくその人たちです。
友達じゃないから、理由なく会うことはもうないかもしれません。でも、一緒に過ごしたその時間が今の僕を作ってくれています。
その当時は「これは下積みだ」なんて思っていませんでした。(そんな打算的に考える余裕はなかったのです)
でも、今になるとわかります。
必死に、本当に必死にやってきたことは、その知識がそれ以降も使えるかどうかとは一切関係なく、僕をつくっているのです。
そのときに感じたこと、考えたことが、僕の未来を、よりよい方向に導いてくれています。
僕はこんな過去を乗り越えて、いま、本の編集者になりました。
とうとう、力を発揮する番が来たのだと、気づき始めています。
環境に恵まれたラッキーボーイには、やることをちゃんとやる「使命」がある。
もちろん、これまでの職場でも、普通に超よかった下積みがいっぱいあります。(先人たちの指南、社会人としての基本動作、数字管理、企画出しの仕組みづくり、人とやりとりするときの作法、意見の伝え方、飲み会の幹事、仕事全体の考え方、想像力の重要さ、社会勉強などなど……)
それでも1ヶ月過ごしてみてわかったのは、少なくとも今の転社先での、悩みは、これまでと大きく質が変わりそうだということです。
社会人6年目に差し掛かって、パワーも強くなった僕が、最高の環境に来ました。
あれをやればもっといいのに。
これをやればもっといいのに。
これまで組織に対して感じてきた不満は、今も現在進行形で、自律した誰かが自動的に解決してくれています。(ありがとうございます)
純粋に編集者としてのアウトプットが出せる環境で、いい本を生み出すことを、僕は今求められている。
そして、僕はそれにどうしても応えたい、応えなければならないと感じている。
最高のマッチングが、今ここに生まれています。
そりゃ、ここで本気をぶつけるしかないです。
力を出せなかったとか言い訳きかないくらいの、マジの勝負どころです。
【おわりに】:「知」の乗り物としての本を編集する。常にその先を見据えていよう
「知」の力を信じている僕は、本の力を信じています。だからこそ、編集者という仕事を選びました。
僕は、「良いものがあったら、それをとにかく人に伝えたくてたまらない」という行動原則のもとで動いています。
僕が人生を賭して編集者として働いていることが、誰かの役に立つ。
この状態を、ずっと続けていきたいのです。
そして、そう強く思うと同時に、僕は、自分が自分らしくあれる一番の方法が、編集者であることだというメンタリティでも本をつくっています。
(つまり、僕が編集者であるのは、自分のためという側面も正直あるということです。素直ですね)
僕が編集者でありつづけるためにも、僕は、世に良い本を生み出す編集者である必要があるのです。頑張らないといけません。よし。
ただ、未来はわかりません。
もしかすると20年経ったころには、本ではない別のメディア・方法に移る可能性もあるのかもしれないな、とは考えています。
それに、僕自身のキャリアを考えたときに、「日本の出版業界にどれだけステイするのか」は、目を背けてはいけないことの一つです。大好きな仕事だからこそ、明るくない面を忘れてはいけない。
一つの本が、日本人全員に届きうる。それほどの力を持っているけれど、業界内の人口は多くない。
それに、「日本は衰退している!」と最前線で感じ続けているのがメディア業界です。僕のような「知」を推し進める人間が、自分の人生に何の対策を打たないなんて、本当にそれでいいのか、なんてことも気になっています。
だからこそ、業界外や海外などでの挑戦、語学の勉強、移住計画など、そういったことへの視野を欠かさないようにしておこうと思っています。
ただそれらについては、いったんアタマの隅に置いてちょくちょく眺めることにしています。
大事なのは、今日僕は、一回ここで腹をくくるということ。
自分が天職だと思える仕事「書籍の編集者」を見つけた。
そして、実際になれた。
3社目で、やっと最高のスタートに立った。
今、まずはこの道を必死で前に進むことが、最適解だと僕は信じています。
最後にまとめです。
僕は、
次元を飛び越える「知の爆発的興奮」を、読者の内に噴出させる本
をつくります。
これが、僕の編集者としての大きな夢であり、矜持であり、20代最後の覚悟です。
本当に全部書き出せたので、
またいつでもここに戻って来れそうです。
ここまで読んでくれた方が、もし僕以外にいたとしたら、本当にありがとうございます。
せっかくのご縁なので、ぜひ、一緒に本をつくりませんか?
最後の最後に、本記事の署名として「ステージの進展・成長とともにマイナーチェンジしているこのアカウントの名前」を3つ並べて終わります。
過去の自分たちと、今の自分が一緒に書いた「共著」。
なんだかオシャレで、心拍数が上がりますね。
では、今日もいい本をつくっていきましょう。
編集者ひつじ 2023.5.9
新米編集者ひつじ 2021.7.1
夢みるこひつじ 2020.8.7
付録:参考書籍など
本書の執筆において、特に参考にした書籍・マンガ・映画などはこちら。
