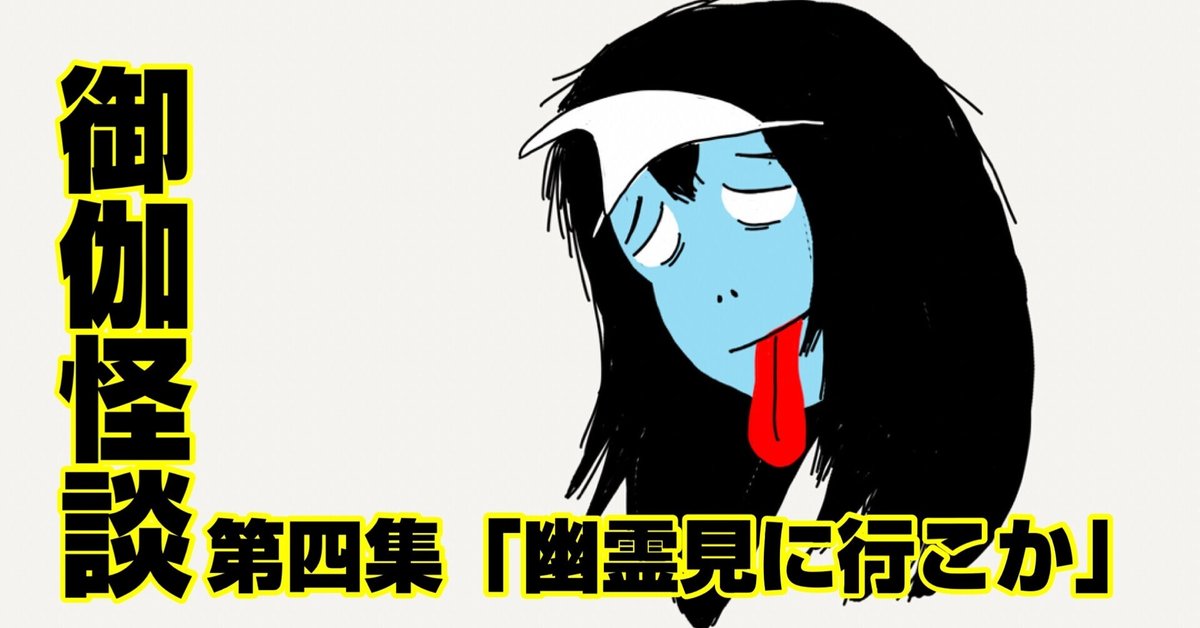
御伽怪談第四集・第四話「イトの逆恨み」
一
延宝年間(1674)のことであった。播磨の国・佐用村に、イトと言う独り身の年増の悪女が住んでいた。家は貧しく、朝夕の飯炊きの煙も立ちかねる暮らしであった。イトは身を寄せる知り合いもなく、侘しい日々を送っていた。
村人を見ては、
「アホンダラめ。今に見とれ……」
と、悪態をつきながらも、
——いつか飢えたとしても、食事をくれるヤツすらおらん。
と、心の内で思い悩む日々であった。
頃は収穫の季節。あちこちで稲刈りが行われ稲穂を干していた。赤蜻蛉が群れ飛ぶ秋の田園はのどかであった。
ふと、イトは、干してある稲穂を見て思った。
——あぁ、あっこから米を盗めたら……あしたっから、食い物の心配、せんでもえぇのに……。
その夜は新月が近く暗かった。闇に乗じて、思い切って少しの米を盗んでみた。
イトは、幼い頃から悪女であった。息をするように嘘を言い、他人を騙す人生であっても、盗みばかりは初めての経験であった。
稲穂に手を伸ばすと胸が高鳴った。最初は少しだけだが、思い切って盗んでみた。
次の日、何となく様子を見ると、誰も騒ぐことはなかった。
——もっとやったかて、大丈夫やし。
やがて、盗んでは様子を伺い、誰も騒がないのを見る度に、
——気付かないのかしらん。それとも無視しくさっておるんやろぅか?
次第に盗みは激しくなって行った。村では米の盗難が続いた。しかし、イトの仕業と気付かない村人たちは、わずかな米のこともあり、
——貧しい者の盗みだから……。
と同情して、誰ひとりとして訴え出る者もなかった。
やがて、イトの米盗みが村中に知れわたった。人々は寄り合って相談し、組頭へ盗みの次第を申し出たのである。
組頭は、ただちにイトを呼び寄せ、
「今より、米盗みを止めるなら、これまでのことは許そう。さもなくば、同じ村の者として、出る所へ出て訴え申す」
と伝えたが、イトは、叫ぶのみであった。
「米なんぞ、盗んでおらんわ。誰がするか、ドアホ」
多くの村人が盗みを目撃していた。組頭としての体面もあった。仕方なくイトを折檻することとなった。数人の男たちにイトを抑えさせ、割れた竹の束で折檻するが、イトは、なお、気分を害して口汚く組頭を罵った。
「何の覚えもないことに難癖つけおって、この土地から追い出すつもりなんやろ。この上は是非もない。陰口をたたく者の家々をまわり、火をつけて、恨みを晴らしてくれるわい」
逆ギレして男たちを振り払い帰ってしまった。組頭は唖然として村の人々にそのことを伝えた。
「虚言にしろ、火をつけるなどと言えば聞き捨てには出来ぬ」
やがて村人とも話し合い、とうとう、ご公儀へ訴え出ることとなった。イトは、その日の内に逮捕され、投獄され、お奉行が判決を言い渡した。
「このような心得の悪い者は、たとえ追放したとしても、どこかで罪を繰り返すであろう」
とのことで、イトはそのまま死罪に決まり、時を移さずして、辰巳谷と言う所で打ち首と決まった。
ニ
イトは土壇場に連れて行かれ、覚悟も出来ないまま叫び続けていた。
「畜生、痛いやないか」
やがて、いよいよ覚悟でもしたものか、泣き出してグシャグシャな顔になりながら、声にならない叫びをあげていた。結局、何を言っているのかは分からなかった。だが、恨んでいることだけは確かだった。
後ろ手に両手を縛られ土壇場に座らされたイトは、横に立った首切り役人の気配を感じた。刃に清めの水がかけられ、流れてゆく。目隠しされて何も見えなかった。首筋にピタリと切っ先が触った時、全身の血の気が引くのを感じ、腰が抜けた。
——これで終わるんか?
そう思うと何も考えられなくなった。人生は儚いものである。頭の中が真っ白になって、そのままゴクリと生唾を飲んだ。その瞬間、首に痛みが走った。痛いと言うより熱かった。頭に重さを感じ、前に倒れる感じがした。倒れたものではなかった。首が落ちたのである。
首筋の熱さの中で、イトの心にひとつの言葉が浮かんだ。
——寂しい。
突然、目の前が明るくなった。目の中に、様々な光景が浮かんできた。
——これは走馬灯?
思い出が流れた。自分の首が胴から離れ地面に落ちるまでのわずかな時間、すべての思い出が頭の中を駆け巡った。イトの目が最後に見たのは、血を噴きながら離れてゆく胴体だった。そしてガクンと落ちきるのを感じた時、何も分からなくなった。
打ち首となったイトの死体は穢れのひとつとして扱われ、とうとう無縁仏となってしまった。生きている時から他人とは無縁な女。地域とも関わりはなく、誰もイトのことを理解しようとする者はなかった。それがである。死んで花実が咲くものか……などとの言葉に似合わず、やがて多くの人々に知られることだろう。まるで死んだからこそ花でも咲いたかのようにである。イトが化けて出るのだ。しかし、これは幽霊とは呼べない。〈幽霊〉とは亡霊の中でも美しい女性の呼び名である。だからイトの場合を〈死霊〉と呼ぶ。死霊は恨みを持って死んだ者の心が残って化けて出たものだ。死霊に出会った者は高熱にうなされると言う。
ふと、気がつくと、イトは持ってゆき場のない孤独に体が震えていた。自分の名前以外、何も思い出せなかった。虚な目で景色を眺めていた。気分は良かった。
——怪我をしていた筈。
と何か思い出して手足を見ると、何だか透けていた。イトは首を傾げたが、すぐにそんなことは忘れた。
「寂しい」
と声が出たが、口は動いていなかった。どこから声が漏れるものか、考えていることが声になっているように感じ、不思議であった。イトのまわりには人魂が飛んでいた。そのことは気にならなかった。寂しいこと以外、何も考えられなくなっていたのである。
脳を失った霊体は何も考えることは出来ない。死ぬ間際の感情が永遠に続くだけだ。永遠と言っても、せいぜい百年くらいで消え去ることが多いが、本人は永遠無限のように毎日を繰り返してゆくだけだ。これが誰か特定の人物に対して強い恨みの念を持って死んだなら、もう少し長く存在していられることだろう。だが、単に寂しいと言う感情のみでは、その終わりは知れている。死んだ者にもいつか終わりは来る。それまで昨日のことを忘れ続け、同じことを繰り返す毎日だった。
三
退屈で苦痛に満ちた日々であった。長い時間を死霊として過ごした後、ようやく次の段階に進むことが出来る。死霊とはそう言う霊的なシステムの中にいて、消え去る日まで、生きる人から息を吸い、その存在を長らえるものであるのだ。
イトは人の姿を探し求めた。誰でも良いから人に会いたくなった。心の中の寂しさを埋めるものが欲しかっただけなのかも知れない。
そんなある日、歩いている見知らぬ男を見つけた。男の名前は知らなかった。顔も見たことはない。だが、そんなことに興味はなかった。誰でも良かったのである。
イトの毎日は夜ばかりであった。昼間を見たことはない。明かりと言えば、まわりを漂う人魂のほのかな青白い光だけだ。だが、暗闇でもハッキリと見えていて、困ることはなかった。なぜ見えるのかについて考えることはなかった。見えるものは見えるのだから受け入れるしかなく、考えるだけ無意味であった。
男はイトに気がつくと驚いたように大きく目を開いた。そして、突然、震え出し、そのまま悲鳴をあげて逃げて行った。
イトは男を追った。寂しさを何とかしたい一心で必死に追いかけた。しかし、ある所まで追いかけると、体が重く動かなくなった。
死霊には居場所と言うものがある。単純な寂しさのみで死霊となったイトは、その居場所から出られないのだ。ふと気がつくと、イトは最初に気づいた場所に戻っていた。どうやって戻ったのかは分からなかった。居場所を超え、体が重くなるのを感じた後で、元いた所にいることを知っただけだ。そんなことが何回かあった。
やがて、処刑された近くの辰巳谷のあたりに、
——イトの死霊が出る。
との噂が流れた。ハッキリと見た者はなかった。だが、噂を聞いた人々は怖気付き、日が暮れてからは誰ひとり歩く者もいなくなった。イトはいよいよ孤独になった。通る人もない場所に、ただひとり佇んで嘆いていた。
それから暫く経ってのことである。鍛冶屋の平左衛門と言う怖れ知らずの男がいた。やつはがっしりとした大柄な体に、鍛冶屋らしい日焼けだか、鍛冶屋焼けだか分からない感じの男であった。
所用があって平福村へ行っての帰り道。すでに夜更けになる頃合であった。元々、大胆な性格だったこともあり、怖ろしいとも思わずに噂の村をトボトボと歩いていた。
ふと、平左衛門は噂を思い出し、鼻で笑った。
——いもせんもんを怖れるなど愚かな。
噂に踊らされている村人を、少し馬鹿にもしていた。死霊など信じていなかったし、見えもしないものがいるなどとは思いもしなかった。
——いるなら見てみたいのぉ。
そう思うと大声で笑った。夜空に声がこだまして、清々しい気分になった。秋の虫たちが黙ると霧のような小雨が降ってきた。
——世間では、確か二十五の朝飯前まで見んかったら、もう、一生、霊を見ることはないと言うやんか。果たして本当やろうか? それについては分からなんなぁ。
平左衛門はへへへと気楽に笑いながら、そんなことを考えていた。
頃は、折しもイトが死罪になった頃と同じ季節。にわかにそぼ降る雨の下、かすかな朧の月影に、平左衛門が辰巳谷の入り口へ差しかかろうとした時、ふと、何気なく道の下の谷川あたりに、白い着物を着た女の姿をうっすらと見た。ハッキリとは見えなかった。
四
だが、屈んで手を洗う姿を不審に思い、
——こんな夜更に女のいる筈もない。
と、頭を振ったが、
——まさか、噂のイトの……。
との想いが頭をよぎり、目を伏せて、足早に行き過ぎようとした。
その刹那、
「のう、悲しや、待ち給え」
と、耳元で、ささやくような声がした。
平左衛門は身の毛がよだち、手足が震え出した。
「のう……」
また声がした。平左衛門は背筋がゾッとして、思わず声を上げた。気がつくと無我夢中で走り出していた。足元も見えない夜の道を走るなど、考えられないほど危険なことだ。だが、そんなことは気にもしていられない。とにかく逃げることだけで頭が精一杯なのだから。
時々、背中に不気味な視線を感じた。その度に背筋がゾッとした。息も荒くなり、手足は絡まった。
——死にとぅない。
その言葉だけが頭の中をよぎった。死霊から逃げる者ほど必死なものはない。意味も分からず、相手の確認もせぬまま、ただひたすら逃げるのである。恐怖だけが心を支配して、目標も目的もなく、足の向くまま逃げて行く。怪我は気にならなかった。と言うより気付きもしなかった。痛みは気持ちに余裕がある時に感じるものだ。必死過ぎる時には、人は何も感じなくなるのである。
やがて平左衛門は、ようやく大願寺村の友人宅へたどり着き、そのまま気を失ってしまった。
友人の太兵は驚いて、
「もうし、もうし」
と呼びかけたが何の反応もなかった。
平左衛門の体は汗まみれで冷え切っていた。硬直して冷たくなった手足は、まるで死人のようだった。ただ荒く息をしているところが死人とは違っていた。
太兵は暫く色々と介抱した。家の者を使い医者を呼んだり気付け薬を求めたりもした。
すると、その甲斐あってか、ようやく正気を取り戻した。
太兵は、
「平左衛門、いかがいたした?」
と尋ねたが、何を聞いても声が震えハッキリとは聞こえなかった。ようやく聞き取れた言葉は、イトが出たと言うものだけだった。
平左衛門は気を取り直して、体調も回復したように見えた。だから翌朝には駕籠を呼び家に送り帰したが、その日から重い熱病にかかってしまった。そして何日か高熱にうなされて、
「イトが……」
と、うわごとを呟きながら、ついに帰らぬ人となった。平左衛門は死ぬ間際、一度意識を取り戻して死霊に出会ったことを家族に物語った。その子孫は今にあって、時々その話を聞き、趣きを書き伝えるものである。
死後の人がなる霊体は、亡魂、亡霊、死霊、怨霊、御霊と位が上がってゆく。
亡魂の別名は〈人魂〉である。
幽霊と言う呼び名は〈亡霊・死霊・怨霊〉の総称で若い女性を意味する呼び名である。
御霊の別名は〈祟り神〉だ。
この物語の中のイトは死霊に属する。生きている者に出会っただけで、その者を高熱などの病にする。しかし死なせてしまうのは、不可抗力のようなものである。もしイトが怨霊の位を獲得していれば、ある程度、自由に生きている人を死なせることが可能だが……。『西播怪談実記』より。〈了〉
* * *
