
アメリカのデジタルノマド事情が示すこれからの働き方:今日のアウトテイク#282(2024-08-26)
<アウトテイク>
・SNSに投稿するのではなく、これを自分SNSとした投稿
・記事として仕上げる前の思索の断片、または下書き
・一部、筆が乗ってきて文字数多いのもあり〼
・たまに過去に書いたネタを展開する場合も
・コワーキング関連のネタが多め
・要するに「伊藤の現在地点」
・いずれKindle本にまとめる予定
#今日のBGM
#今日のコトバ
"歴史の呪いのひとつは、私たちがどんなに望んでも、過去に戻って災難に至る道を変えることができないということだ。
過去には恐ろしい必然性がある。
しかし、未来を変えるのに遅すぎるということはない。"
(ヘザー・コックス・リチャードソン)
#「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」受講者募集開始
9月より、「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」を開講します。
この講座は、14年前のぼくのように、自分たちにコワーキングが必要と考える人たち、そして、コワーキングを利用するコワーカーのカツドウを支援したいと考える人たちを対象にした講座です。
自分たちのローカルコワーキングの開設・運営をお考えの方は、ぜひ、上記のサイトをチェックください。
#アメリカのデジタルノマド事情が示すこれからの働き方
パンデミック以降、世界中でデジタルノマドが増殖している中、アメリカのデジタルノマドが労働人口の11%、1,810万人になった。
Digital nomads move from niche to normal with 18.1M workers
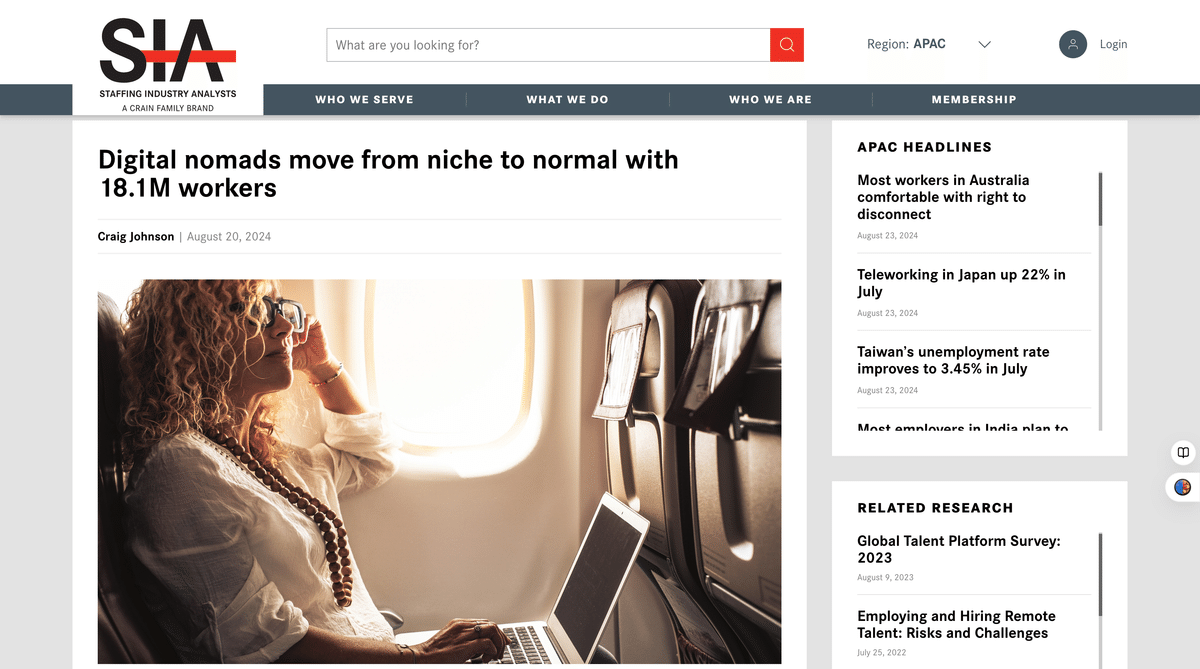
MBO Partnersが8月20日に発表したレポートによると、2023年と比較して今年4.7%増加し、2019年以降147%増加している。あ、アメリカの話ですよ。
こうなると、一時の(コロナ禍の反動的な)トレンドではなく、ごく普通にワークスタイルの一つになったことは間違いない。つまり、企業もリモートワークありきで考えなければならないモードにもうすでに入ってる、ということだ。
興味深い数字がいくつかあるので、共有しておく。
デジタルノマドの数が増加する一方で、独立したワーカーの割合が増加し、従来の仕事を持つ割合は減少している。
今年、デジタルノマドの44%が独立したワーカーで、56%が従来の雇用型のワーカーだった。2023年は38%が独立ワーカーで、62%が雇用型だった。
このあとに「この減少の背景には、「RTO(オフィスへもどれ)」ポリシーがあるようだ」とあるが、「RTO」への反動だとしたら、「RTO」がまるで用を成していないということになる。まあ、そうでしょうね。
しかし、従来の仕事を持つデジタル・ノマド全員が雇用主に自分の状況を報告しているわけではない。
MBO Partnersの調査によると、雇用型の仕事をしているデジタルノマドの14%が、雇用主は自分がデジタルノマドであることを知らないと答えている。
さらに22%は、会社にデジタルノマド・ポリシーがないが、上司から許可を得ていると答えている。
笑ってしまいますね。「雇用主が社員がデジタルノマドであることを知らない」のが14%もいる。一方、まだ社内にそのルールはないが上司が認めているケースが22%。
そういえば、3年前の話だが、日本でも会社に内緒でワーケーションしている「隠れワーケーター」が44.9%も存在したというリポートもあった。
ここが今後増えていって不文律的に、既成事実として受け入れられていくのか、それとも白旗を上げてさっさとリモートワークを公認するか。いずれにしろ、居場所と時間を自由に選んで働くというカタチがデフォルトになるのは明白だ。
そうすると、必然的にコワーキングスペースの必要性が高まる。世界中でコワーキングが増えている理由はそこにある。
以下、ざっと転記しておく。
世代
デジタルノマドの過半数、64%はZ世代またはミレニアル世代である。X世代はわずか25%で、ベビーブーマーは11%でしかない。 デジタルノマドの年齢の中央値は37歳で、56%が既婚かパートナーと同居している。性別
男性はデジタルノマドの55%を占め、女性は40%、そして1% がノンバイナリー。人種別
デジタルノマドの人種構成は、白人67%、黒人21%、ヒスパニック系11%、アジア系6%、その他1%(回答者はこの質問に対して複数の回答をすることができる)。仕事への満足度
デジタルノマドは仕事への満足度が高く、79%が「非常に満足している」と回答。これは全労働者の64%と比べても高い。収入
デジタルノマドの17%は世帯収入が年間25,000ドル以下と回答しているが、46%は75,000ドル以上と回答している。MBO Partnersは、デジタルノマドの64%がフルタイム労働者、36%がパートタイム労働者であると指摘している。高賃金国を含む高コスト地域のデジタルノマドは、収入を伸ばすために比較的生活費の安い地域を旅行することが知られている。課題
デジタルノマドにとっての最大の課題は、27%が経済的ストレスを挙げ、26%が家族や友人と離れること、24%が身の安全、23%が時差による仕事の困難さ、そして21%が旅行による燃え尽き症候群である。米国では
デジタルノマドの40%が、来年は米国でより多くの時間を過ごす予定だと回答している。職業
デジタルノマドの主な職業は、ITが19%、クリエイティブサービスが14%、教育・トレーニングが9%、営業・マーケティング・PRが9%、財務・会計が8%、コンサルティング・コーチング・リサーチが7%となっている。
人種別というのはアメリカのデジタルノマドの、それなので、念の為。
注目は、デジタルノマドは仕事への満足度が高く、79%が「非常に満足している」と回答、というところ。
これだけの人がリモートワーク、あるいはデジタルノマドを選択しているおかげで満足度の高い仕事ができている、という事実は無視できないし、今後ますます増えると思う。
一方、そうは言っても、課題がないわけではない。「家族や友人と離れること」を挙げる人は結構多い。突然、ホームシックにかかって帰国するという人もいる。まあ、そりゃそうですよね。人間なんだから、誰かとつながりを感じられる環境にいないとおかしくなるのは想像がつく。「旅行による燃え尽き症候群」も同じ理由じゃないかしらね。
それと、収入がいくらであろうが、デジタルノマドが比較的生活費の安い地域を旅行するのは理屈が通っている。物価の高い土地にしがみついて、たくさん稼いでもたくさん出ていく生活を続けていれば、なんのために働いているのか判らなくなる。
そのバランスの取れるところを選んで「移働」する、その選択肢を持つということが自由を意味する。古めかしい企業のルールで奴隷のようにがんじがらめにする時代はもう終わりにしよう。
なお、こっちは2022年時点での世界のデジタルノマド事情を書いてる。よかったら併せてご参考に。
ということで、今日はこのへんで。
(カバー画像:Kevin Charit)
ここから先は
最後までお読みいただき有難うございます! この記事がお役に立ちましたらウレシイです。 いただいたサポートは今後の活動に活用させていただきます。
