
小説『エミリーキャット』第38章・ニューヨークの憂鬱
『……』
窓枠に両腕を突いて凭(もた)れかかり、まるで光の吹き溜まりのような遠い街を、黙って見つめていたエミリーは窓外から視線をすべらせ、
彩の眼をじっと見据えた。
『ダルトン?それ、誰のこと?』
『…ビリー・C・ダルトンって画家、エミリー、知らない?
私、ダルトンの絵を観たことがあるの…ロイとそっくりの猫が描かれていて…それに…』
『それに?』
『……それに…その猫と一緒に描かれていた少女が…』
彩はうつ向いて夜風に揺らぐ漆黒の森の繁みが波濤のように続くのを、上から眺めていたが、思い切ってエミリーを見つめ返すと、こう言った。
『エミリーに似てる気がして…』
『…そう…』とエミリーは窓に背を向け、窓枠に凭れながら『でも私はダルトンって姓ではないわ、
これは本当よ』
『……じゃあ…エミリーはなんという姓なの?』
『さっきも言ったわよね、
彩を何年間も蚊帳の外に置かれたような不安で心細い思いにはさせたくないって、だけど私にもすぐに全てをまだ語りたくない様々な事情があるの、だからお願いよ彩、
今、少し、
もう少し、私を信じて待って欲しいの、』
『……エミリー、エミリーは本当にエミリーなの?』
『どういうこと?』
『本当はガートルードって云うんじゃないの?』
『ガートルード…古風な名前ね…
でも彩、私は最初からエミリーと名乗っているけどその通りエミリーよ、エミリー以外の何者でもないわ、
ガートルード・ダルトンじゃないことは確かね、
彩が私を信じてくれるかどうかだと思うけど…』

『……』
『安心して彩、私はエミリーよ、
初めて逢った時から今もずっとエミリー、だって生まれた時からそうなんですもの、
ガートルードなんて人は知らないわ』
『…ああ、エミリー!』
彩はエミリーに抱きついた。
『私、不安で…とても不安で…
エミリーのお父様が画家だって聴いたから混乱してしまって…
なんだか急に怖くなってしまったの、でもエミリーがエミリーなら、もういいの、
ガートルード・ダルトンじゃないのならそれでいいの、』
エミリーに固く抱きすくめられ、
その胸で彩は子供のように泣きじゃくった。
『いずれは姓も何もかも少しずつ彩にはいろいろと話す積もりよ、
だからお願い、彩、
私にもう少し時間をちょうだい、
そんなには待たせないわ、
長い年月、ただひたすらに待たされる苦しさを私はよく知っているもの…。
大切な彩を不安という檻の中にあまりにも長く閉じ込めたりしたくないと思っているわ、
だってそんなことをされたら…
…人は徐々に希望が見えなくなって…
やがて絶望して壊れてしまう…』

『…エミリーお願い、アメリカの話をして、』
彩は話頭を転じて、なんとか無理矢理泣き止もうと努めて言った。
エミリーはそんな彩の黒絹のようにつややかでなめらかな髪に包まれた頭を撫でながら、
その小さな頭に姉のように静かな、労(いたわ)りを籠めた口づけをすると囁くようにこう言った。
『そうね、解った…。
それだって私が自分のことを少しずつ、彩に紐解いてゆくことに繋がるんですものね』
エミリーは鎧戸を閉め、窓を閉めて鍵をかけた。
エアーコンディショナーでもついているのかと思うほど、屋根裏部屋の中の空気はつい今しがたまで窓を開け放っていたというのにふんわり、まろやかで暖かくて心地好い。
ふたりがエミリーのベッドに並んで横たわると猫達がその周りに次々と飛び乗ってきた。
猫達はふたりの顔の傍や、枕上(まくらがみ)、エミリーや彩の腕や肩、足元にまで寄り添うように群れ集った。
猫達が自分達もまるでエミリーの話を聴きたがっているかのような様子で親しげに寄り添ってくるのが、彩にはまるで大勢の家族に取り囲まれているかのような、
ぼんやりとした、と同時に心地好い温もりとなって彼女の中にいまだ、くすぶる不安感の強い縛(いまし)めを優しく緩めてくれるような気がした。
それと同時に彩はこんなにも沢山の猫達とベッドに横たわることは初めてで、その温もりや天鵞絨(ビロード)の様な、なめらかさやふわふわした羽毛のような感触にぴったりと取り囲まれて、妙にわくわくもした。

ふと気がつくとあの甘えん坊のクリスはバターカップと共に大型犬用のドーム型のベッドの中にすっぽりと潜り込み、バターカップに顔や眼の周りをペロペロと舐められながら、うっとりとしている姿が目に入った。
『あら?クリスは来てくれないのね、私、もちろんロイの大ファンだし、猫だけど彼のことリスペクトしているわ…
でもクリスはなんというのか…
私の御贔屓筋なのよね』
と彩が淋しげに言うとエミリーは笑って、
『それはクリスだって解ってくれていると思うわ、だからクリスも彩が御贔屓筋な筈よ、
でも彼はバターカップと一緒にいるのが大、大、大好きなの、
ベッドで猫まみれになるより、
バターカップの犬用ベッドできっちきちになって一緒に眠るほうが嬉しいみたい、よく庭の芝生の上でも、ふたりでまるで仔犬同士みたいにじゃれあって転げ回って遊んでいたりするのよ、ショーンやスイートピーもよく一緒になって仲良くみんなでゴロゴロ…』
エミリーが嬉しそうに顔を輝かせて言うのを見て、彩も嬉しくなり思わず声が弾んだ。
そしてその思わず弾む自分の声に、彩は自分がどんなにエミリーのことが好きなのかを改めて痛感する思いがした。
『素敵な光景でしょうね、
目に浮かぶようだわ
猫と犬が種を越えて仲良くしてるなんて、それを見てる人間まで幸せな気持ちになるわね』

『可愛らしいのよ、とってもね、
…それにそんな彼らを見てると昔の自分を時々思い出してしまうわ、
もちろん私は人間だからクリス達のように無垢では無かったけれど…
それでも子供の頃、芝生の上を転げ回ってあんな風に遊んだ頃が、私にもあったんだなって…
ふっと思い出してしまうの…』
『それはアメリカで?』
『ええ…ニューヨークのバッテリー・パークで…。
日本ではセントラル・パークはとても有名なのに、何故かバッテリー・パークはそれに比べると知名度が低い感じね、でもバッテリー・パークはとても綺麗だし風情もあって…
オーシャンサイドの森がある素敵なところよ、
森の中を走り回る大きな灰色の栗鼠を見ながら、よくその森の中の芝生の上を転げ回って…
わざと努めて子供らしく振る舞っていたのをよく覚えているわ』
『子供らしく?』
『ええ、父を心配させたくなかったの、普通の子供のようにどうやったら見えるんだろうって子供の頃、
頭を痛めて悩んでいたわ、
他の同世代の子供達のやることや言動や反応のしかたとか観察して、
それを真似たりしていたの、
それでもどうしてもそうなれなくて…
それがとても辛かった…』
『何故そんな…』
『母は私のことで酷く悩んでいたわ、だからいつも私に向かっての口癖が…
''お前の脳ミソは腐っている"
"白痴"
"低能児"
''お前なんか生まれてこなけりゃ、よかったのに!"
そして……
‘’こんな子供なら欲しくなかった!
もっと普通のちゃんとした子供と返品交換してもらいたいくらいよ!''

……私は日常的にそんな言葉を浴びせられながら育ったわ…
まるで食事を食べるように私はそんな母の言動を食べて飲んで吸収して育ったの、だって私には他に…どうにも出来なかったもの…
逃げ出すことすら叶わなかった…
それでもやっぱり母は私を愛してくれていたはずだと思うわ…
それを感じていたもの、
でもそれと同じくらい、私のことが母は…厭で厭でたまらなかったんだとも思う…』

『…そんな……酷いわ!
だってその頃まだエミリーは小さな子供だったんでしょう?
大人にだってとても口汚ない罵倒なのに我が子にそんな言葉を吐くだなんて』
『我が子だからだったのかもしれない、私を見ていてイライラしてばかりだったもの、
不器用で…。
本当に何をやらせてもとんでもなく不器用で…。
何一つ人並みに出来やしない、
数字の暗証番号を覚えて左右にダイヤルを振るように回して開けるポストなんて絶対開けることが出来なかったし、忘れ物も多くて学校で提出しないといけないようなものをみんなは提出しているのに、私だけ何故だかいつも抜け落ちたように忘れてしまうの、教師はみんなに言っていることでも、私に個人的には言っていないからと思ってしまったから…
みんなが当たり前のように感じたり察したり、理解して難無く出来ることが私には難しいことがとても多くて…
そういった理解や、その先の言動に繋がる回路がもしかしたら私は他の人と違うのかもしれない、
母が『欠陥商品』『不良品』とよく私を呼んでいたけど…的を得ていると思う部分は確かにあるわ…
とても悲しいことではあるけれど
みんなには必ず当たり前のように稼働し続けるピストンが私の場合
生まれつき動かないのかもしれないし、可笑しな喩えだけど針の無い時計のようなものなのかも…
使い物にならないし、奇妙だし、
見ていて不愉快だし人の迷惑にすらなってしまう、

大人になった今でさえ似たようなシチュエーションでは時々混乱して解らなくなるの、
そんな時、目の前が真っ暗になって言葉を失って何も言えなくなってしまったり不安のあまり吐き気がしてきたり、激しい耳鳴りや頭が粉々になってしまうんではないかと思うほどの頭痛、
不安と恐怖でギリギリ締め上げられてその苦痛で失神してしまうこともある…。
九々も出来ない、四捨五入も解らない、落ち着きが無くて授業中じっとしていることが出来なかったからクラスではいつも問題児だったし、
アルファベットを書けば鏡に映したような逆さまになるし自転車も乗れない、
いまだにリボンや靴紐も結べやしない、23時が何時なのかも解らない、
予想外のことや想定してなかったことがふいに起きたり、
その急な変更を説明不足のまま無理強いされるとどうにも収まらないパニックの嵐が起きてしまう、
不安感で押し潰されそうで全身痛みではち切れそうになるの、
死んでしまうのではないかって、
その癖、こんなに恐ろしい思いを、いつもいつもするくらいなら…
もう死んだほうがマシだと思うほど…
こんな気持ち誰にも解らないわ、
だからよく思うの、
母の言う通り確かに私の脳ミソは腐っているのかもしれない』
『そんなこと…いいえ!
そんなことないわ、なんて酷い…
なんて…!
だってエミリーはとても聡明で…』
と言ったところで彩はあのエミリーの日記帳の何故か徹頭徹尾、反転してしまっていたアルファベットのひきつれたような英文の文字の羅列を思い出し、言葉を詰まらせた。
喘ぐように彼女は言葉の継ぎ穂を探し出すと言った。
『だってエミリー、ピアノは上手でしょう!?』
『でも音符が読めないのよ、』
『じゃどうやって弾くの?』
『全部ヒアリング、
耳で聴いて覚えるの、
だって音符なんて何故あんな呪文のようなものがみんなにはちゃんと読めるのか不思議でしょうがなかったわ、

楽譜を見ながら鍵盤を叩くだなんて…みんな器用なのね、
まるでサーカスの綱渡りを見ているみたい、
…楽譜を見ながら演奏するだなんて、同時進行ってなんだかとても華があって美しいわ、バランスがいい、均衡がとれてるってどうしてあんなに優美に映るのかしら…
自転車に乗って風を切って走ってゆく人やレジに立つ人達がみんな輝かしく見えて…まるでみんな並んで一斉に咲き揃った花壇の花のようで…
…私には…
…ただただ…羨ましかった…

せめて音符を理解したかったけど…楽譜を見ながら、同時に鍵盤の上で指を動かすなんて私にはとても無理…。
どっちかしか出来ないわ、
だいたい音符が読めないんじゃ、
はなからもう"アウト!"って言われているようなものでしょう?』
エミリーがその悲しげな瞳に長い睫毛を臥せて、深い羞恥を滲ませた孤独の奥で消えて無くなりたいと感じていることが彩には色濃く伝わってきて彩はエミリーを思わず雨に濡れた小さな少女を保護したような気持ちになって抱き寄せた。
エミリーは彩の抱擁にほんの少しの間、身を任せていたが固い笑みを浮かべて身を起こすと再び話し始めた。
『母は私のせいで父を失うんじゃないかと気が気じゃなかったんだと今にしたら思うの、
私は父の本当の子供じゃないしお世辞にも優秀とはいえない子供のせいでせっかくの私生児の父親になってくれた奇特で心優しい旦那様を失うことになったらどうしようってきっと心細くて…次の子供を早く欲しがっていたもの、
次の子供はきっともっと正常なちゃんとした子供に決まってるって、''お前みたいな白痴はちゃんとした子供が生まれたらどこかへ養女にやってお払い箱にしてやるから"っていわれ続けて…
子供心にそれが来るのが恐ろしくて恐ろしくてたまらなかったの、
でもだからといって父にそれを言うことも出来なくて…

よく子供部屋のクローゼットに縫いぐるみや人形と一緒にとじ込もって泣いていたわ…
その頃から今もクローゼットに閉じこもる癖が治らなくて…』
エミリーは自嘲するようにわざと渇いた苦しげな笑いを漏らすと冗談めかすようにこう言った。
『本当は母からじゃなくクローゼットの中で自然と生まれたんじゃないかって子供の時よく思っていたの、でもそれを冗談みたいに笑いながら言ったら、本気で母から張り倒されて唇と口の中とをなん針も縫うほど切ったことがあったわ…』

エミリーは目尻に不思議な微笑みを浮かべて愉しげに憂鬱げにそのどちらをも含んだような笑いかたをすると『母は私を殴るのにその時は偶々、私が気に食わないことを言ってくれたという理由があってよかったんだと思うわ、理由も無くただ殴る蹴るの時だって少しも珍しくは無かったもの、殴る為の理由があれば母にはむしろ都合がよかったのよ、''殴りやすかった"はずだもの』『……』
彩は言葉を失っている自分にもどかしさを感じながらもただエミリーを抱き締めて情けなく泣くしかない自分に無力感を感じていた。
『でも父はそんな母の杞憂とは反対に私を愛してくれていたと思うわ、でももっと…私を庇って欲しかった…助けて欲しかったし守って欲しかったの…』
そう言いながらもエミリーは不思議なほどニタニタと嗤っている。
『…お父様はエミリーが虐待されているって知っていたの?』
彩は心弱りの中で抱き寄せた恋人の髪を撫でながら、我ながら無力と感じるやや涙にくぐもったように掠れた声で尋ねた。
『…知らないはずがないと思うわ、どんなに怪我していてもそれを隠したって歩き方がおかしいとか家族だもの、気がつくはずよ、
ピアノが弾けなくなった時も理由は指を骨折したからだけど…
父は何故骨折したのか聴いてもくれなかった、ピアノレッスンのスクールからエレメンタリースクールへ通報があったらしくて当時の家に警官とスクールカウンセラーが来たこともあったのよ、
最初は警官だけだったけど必要だと思ったんでしょうね、翌朝カウンセラーが来て…
でも私はその女性に転んで突き指をしただけだと言い張ったのを昨日のことのようによく覚えているわ、
手のひらに汗をかいていたことも…言い繕うことに息切れを感じながらも必死だった…
だってママを守りたかったから…。
背後で母の忍び泣く声が聴こえていた…みんなだって本当は解っていたんだと思うわ…
でも私はなんとか母を庇いたくて…どうしてあの時、あんなに母を守れるのは私しかいないと思っていたのか、そう強く思い込んでいたのか…解らない…
でも今もひとつだけ解るのは…
愛されたかったの、ただ母から愛されたかった…
可愛がられたかった、抱き締めて欲しかったの、今こうして彩から抱いてもらっているように』

『…エミリー…』
彩は悲しみの国の囚われ人となったようにエミリーを強く抱き締めた。
そして触れると骨格はくっきりと服の上からでも解るのに、肉付きの薄い愛しい背中を優しく撫でた。
『大好きよ、エミリー愛しているわ大切なエミリー、大丈夫よ貴女は賢くて美しい…お母さんが間違っているわ、
…ああ、それにしても、なんて辛かったのかしら…
これから一緒にふたりでエミリーの癒えていない傷をひとつずつ治してゆきましょうね、
時間はかかってもゆっくりとふたりでならきっと大丈夫よ』
エミリーの背中や髪を撫でながら彩は出し抜けにあることに気がついた。
それはエミリーの海より深い悲しみの息も出来ない禍々しいまでの闇の深さとその濃度だった。

エミリーは奇妙な笑みを浮かべたり、自嘲するような笑い声を痙攣のように幽かに立てたまま、声を殺して泣いていたのだ。
エミリーはきっと幼い時からこうやって普通に泣くことが赦されなかったのかもしれない、そのせいでこんな奇妙な癖がついたのかもしれないと彩は思弁した。
泣いているところを人から見られても咄嗟には解らぬよう涙も悲しみも究極なまでに隠忍し、隠し通さなくてはならなかったのかもしれない。
普通に泣くことが赦されなかった少女時代とは一体どんなものなのだろう…彩はその苦しい鋳型に無理矢理嵌め込まれて育ったエミリーの苦しみは今も尚、続いているのだと思い知った。
彩はそのような不自然な人の泣きかたを見たのは初めてのことで、エミリーへの愛情と同時に一抹の狼狽が震える波紋のように生まれるのを感じた。
それは鎮かな池の中へ誰かが投石した後のように、彩の胸の内にみるみる大きく拡がっていった。
その狭間に揺れ動く自分を感じて彩はそんな自分を叱りつけたくなり、彼女は自分で自分が情けなくなった。
すると急に時を刻むような規則正しい音声がどこからか鳴り出して彩はハッとした。
彩はまるでその意味不明な音からエミリーを守ろうとでもするかのようにしっかりと両手で抱き寄せたまま、音の鳴る方角を振り返った。
窓から離れた壁際に濃い飴色のアップライト・ピアノがあり、ピアノの上でメトロノームが黄金(きん)いろの針を左右に揺らしながら、広い室内に虚ろな音を響かせていた。
針の先には何故だか恐らく硝子玉であろう、碧い眼球が突き立ててあり、その眼球が左右に揺れながら彩を凝視し、時には長い睫毛を有した青褪めた瞼を閉じてウィンクしてみせたりもした。
その音は徐々に室(へや)中に幾重にもなって響き渡り、まるで室中に無数のメトロノームが鳴っているかのように彩には思えた。
その音に彩はあのコーヒーカップの中で渦を巻き、その回転で彩の意識を吸い寄せ、支配するかのようだったあの様を思い出した。

ミルクの脂肪の重さは、一旦珈琲の底地に沈んだのち浮かび上がり、
じわじわザワザワとまるで音を立てるように不器量で煮崩れたように形の悪い小花を咲かせたり、蕩(とろ)けたような水玉を無数に生み出したあの珈琲カップのほんの数秒の間、見せる小さな万華鏡の世界。
その世界を彩は思い出してエミリーを抱き締めたまま眩暈を感じて気が遠くなっていった。
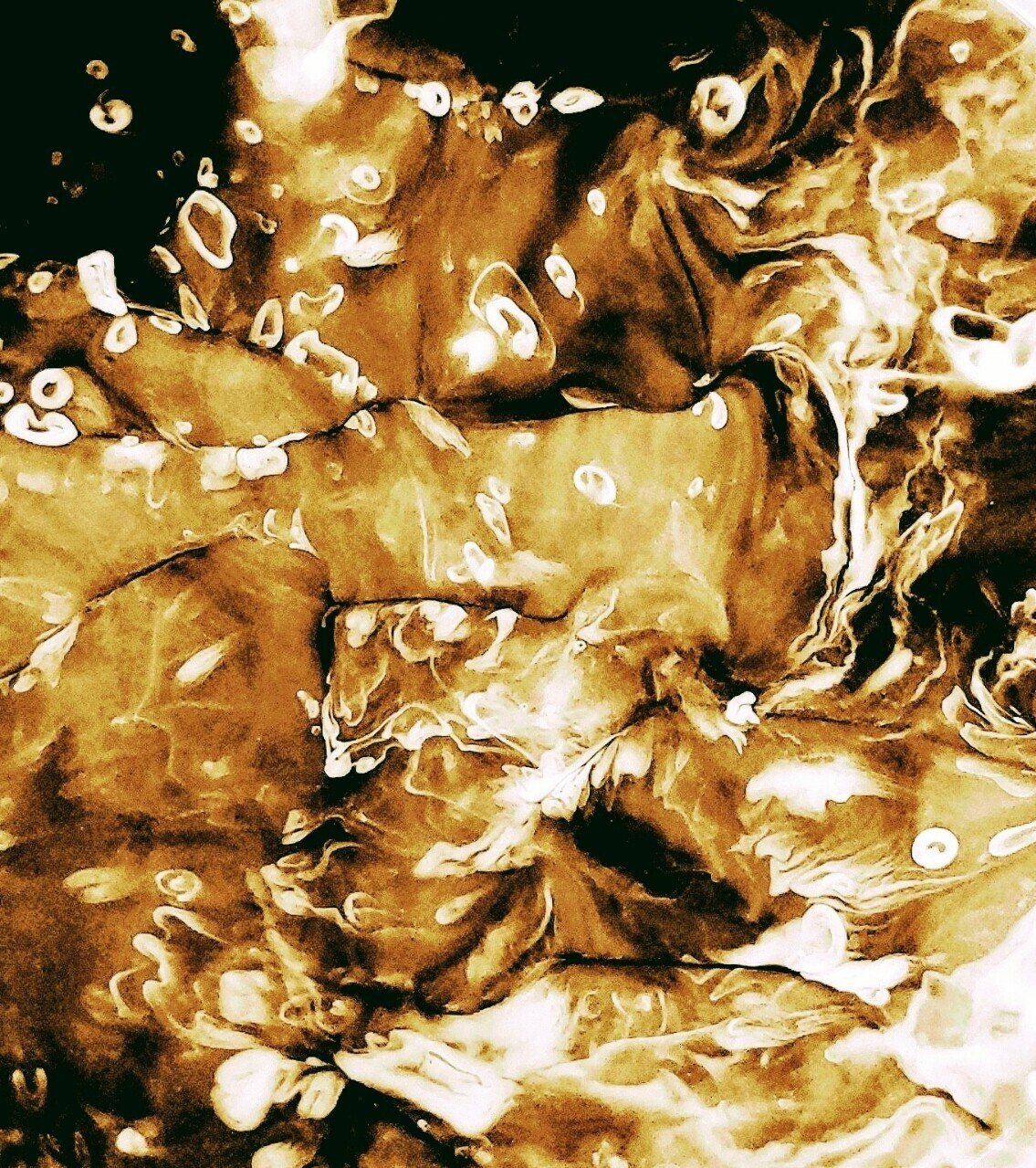
気がつくと彩はベッドに横たわっていた。
毛布を掛けられ、猫達に取り囲まれていた彩は、薄荷水(はっかすい)のようなうんと淡いシースルー・ブルー、
トパーズのような明快なブルー、
翡翠のようなグリーンやアップル・グリーン、
シャンパンゴールドにスモークゴールド、
キャンディのようなダークオレンジといった様々な色の猫達の沢山の瞳に見守られて目が覚めた。
ロイが無遠慮なまでに彩をつらつらと眺めている仏頂面は『お前、なにやってるんだよ?
寝ても覚めても寝てばっかいるヤツだな』とでも言ってそうな顔で、彩はばつの悪い思いでベッドの上で身を起こした。
三毛猫のロージィが優しく彩の顔に頬擦りをしてきて彩は安堵と共に見たのは、
ベッドの隅に腰かけたままのエミリーの淋しげな後ろ姿だった。
『エミリー…?ごめんなさいね、
私ったらいつの間にか、またうっかり眠っていたみたい』
『いいのよ、少し疲れていたようだからほんのり眠ってもらったの、
短時間ではあるけど、深く眠れて、きっと頭がスッキリしたはずよ』
『本当は泣いてる姿を私に見られたくなかったからなんでしょう?』
と言いかかって彩はその言葉を無理矢理、飲み込んだ。
彩はエミリーの深過ぎる悲しみに天を仰ぎたくなるような思いに耐え、ただ無力感に苛まれつつ、そっとエミリーの傍へとベッドの上を四つん這いになって膝寄(いざ)り寄った。
そしてエミリーの隣に座ると、エミリーの手に自分の手のひらを重ね、その肩に頭をもたせ掛けた。
すると耐えかねた涙が彩の右目から左目へと伝い落ち、更にエミリーの肩を微かに濡らした。
『…ねえ彩、父は何故、アメリカへ行ったのだとと思う?』
『さぁ…何故かしら…』
急に取り成すように朗らかな口調となって、話題を転じようと苦闘するエミリーの笑顔に彩はかえって胸が傷んだ。
『父は歳の離れた兄が居たのだけど…。
お兄さんはアメリカに移り住んでて…
家具や衣類やアクセサリーや…
いずれもアンティークの輸入で成功していたの、そこへまるで父は転がり込むように大好きだった印度の旅先からやってきたの、
最初は居候だったんだけどそのうちお兄さんが見つけてくれたアパートメントに住むようになって…。
父は若い頃、印度だけでなくポーランド、ベルリン、ウィーン、ヴェネツィア、香港、マカオ、チベット、それ以外にもありとあらゆる国を放浪していて…イギリスの実家がとても裕福な領地主の家柄だったからよかったようなものの…
最初の頃は本当にまるで聖書に出てくる放蕩息子さながらの若者だったみたい』

『そうなんだ…
でも素敵ね、世界中あちこち周りながら旅だなんて羨ましいわ…
きっと日に焼けた背の高い、ハンサムな英国青年だったんでしょうね』
『背は高いけど…私と同じで青っちろい人だったわ、
だって日に焼けるとピンクのガーベラみたいな肌色になっちゃって、
とてもみっともないのよ、
ガーベラがピンクでも可愛いだけよね?でも人間がそこまでピンクいろになったら本当に気持ち悪いのよ、
だから男性だけどいつも日焼け止めは必需品だったみたい』
エミリーが心から愉しそうに笑ったのを見て彩はそれにつられて思わず心から笑うことが出来た。
『父は最初、アメリカに憧れを持って行ったようだわ、
封建的でともすれば窮屈な節もあるイギリスに比べたら、アメリカは途轍もなく自由の国に思えたんでしょうね、
まだ若かった父はアメリカに夢を馳せたんだと思うわ、バッテリー・パークの中に在る大きな美しい、とてもロマンチックな石造りの橋や、
欄干に太ってまるまるとした海猫やカモメ達が軒並み集う、海沿いからの眺めは遠くに小さく自由の女神が見えて…
路面の凍結を防ぐ為に煙りながら立ちのぼる、冬のニューヨークの地下からの温かいスチームの柱や、街角のホットドッグ売りや新聞スタンド、その中に立つ仏頂面のルーマニア系の老人や、光の洪水の摩天楼、日本のSONYや当時、欧米で人気だったというミドリ・リカーの宣伝、
ラジオ・シティで公演されてるミュージカルの宣伝の絵、今のようなCGで作られたものではなくあれは職人さんの手による立派な絵画だったって、父はよく言っていたわ、

光輝く華美なネオンだけが主張する今の街ではなくて、
当時のニューヨークは今よりずっと街も汚くて治安が悪かったにも関わらず、父にとっては多分その時以上に蠱惑的で生命感に満ちた時は、
もうニューヨークには二度と帰ってはこないんじゃないか
って思えるほどだったみたいね、
だから父からすれば絵心をくすぐらせる場所がニューヨークには沢山あったの、

でも…幼い私の記憶が色濃く始まっている頃には既に父はもう、ニューヨークに失望して落胆していたの、
アメリカではいくら個展をお兄さんの財力や仕事のコネクションを使って繰り返しても、成功の芽は一向に出なかったばかりでなく小さな新聞の論評でさえ『美しいスーツと蝶ネクタイを纏った行儀のよい非常にエレガントな小品…なんの為にニューヨークに彼は来たのだろう?
その意味は全くそのエレガンスの中には見当たらない』といったものでしかなかったらしくて…
でもそれは比較的まだマシな論評のほうだったようで、父が新聞や雑誌を丸めてゴミ箱に投げ捨てたり黙って引き裂いていたのも…
よく覚えているわ、
父とバッテリーパークの傍の海沿いを夕暮れ、手をつないで歩きながら…その時の父の瞳をよく覚えているの…
淋しそうなブルーの瞳の先に、遠く海の上に霞む自由の女神を私は恨めしく思って眺めたのを覚えているの、あの勇ましげで綺麗なひとが、優しい私の父の胸を傷ませているんだって幼い私にだって解ったもの…』


それに父はアメリカが思ったようにはイギリス人の自分を受け入れてはくれないことに腹を立ててもいたの、面と向かって怒ったりはしないけどアメリカ人から見たら誇り高い父は決してアメリカのスタイルや色に微塵も染まらなくて…
小生意気なロンドンボーイに見えたのかもしれないわね、日本人ならアメリカンを愚直なほどストレートに尊敬して、素直に食文化にせよ、なんにせよコピーするけれど、そしてそうすることを楽しめるし、抵抗も持たないけど、父は『アメリカ人を奴隷のように真似たとしてもコピーなんて脆弱なだけだ、僕はどこにいても僕なんだから隷属はしないぞ』っていつも言っていたわ、
でも父の周りのアメリカン達は、
お坊っちゃま育ちの英国青年の父をよくからかったようね、
気取ったキュウリのサンドイッチなんか食べてないでハンバーガーを食えよ、とか本気で忠告されたこともあったらしくて…。
珈琲を飲まないってのもアメリカでは変だし、よくあれで頭がスッキリするな、とか…増してやコーラやルートビア―なんか絶対に飲まない、
それに父は…これは私もだけど、
ミルクティーしか頑なに飲まなくて…アメリカ流のレモンティーには一瞥もくれないかったわ、
その癖、日常的には茶葉からではなくティーバッグでお手軽にお茶を淹れたりするところもアメリカ人から見たら、"そんなんで威張るな!''って突っつき回してやりたくなったんでしょうね、
それでもやっぱりスーツ姿は水際立って素敵だったし気障に見えない程度のさりげないお洒落がイギリス人は上手よ、
靴にもこだわれば、老人でもないのに純銀や象牙の彫り込み細工のライオンや豹の顔がついたグリップの、美しいステッキを必需品というよりは美意識で持ち歩いたりする。
コートや手袋にもこだわる、

アメリカンから見たらイギリスでそうしてることには抵抗無くても、
アメリカでもそんなライフスタイルを貫き通すイギリス人は頑固な貴族のフリをしたスノッブな若年寄りのように感じるのかも…。
ただ気障なだけなら腹立たしいだけで済むのに、ちゃんと板についてて優美だから余計にムッとなる、』
エミリーは楽しげに笑った。

『その癖、俳優並みの完璧な歯並びを誇るアメリカンと違ってイギリス人やヨーロピアンは八重歯のような極端な乱杭歯でさえなければ歯の矯正にはやや無頓着、って自分達の進んだ面と比較して何かにつけてあら探しをしたくなるような対象だったのかもしれないわ、本音をいうと妬みもあったんじゃないかしら…
イギリスの誇りやそれに付随する歴史や…その歴史を彩る分化的香りなんかはアメリカには無いとは言わないまでも薄いわ、
世界一の国と思ってやまないお国柄のアメリカにしてみれば、イギリスだのフランスだのは"郷に入っては郷に従え''が全然通用しなくて、
プライドを持った偉いけどなんだか腹立たしい大先輩のように感じられるのかもしれないわ』
『お父様もニューヨークでは、
やっぱりそんな風にイギリス紳士って感じで貫いていらっしゃったのかしら』
『父はそこまでじゃなかったようなんだけど、でもやっぱりニューヨークに居て疎外感というか、
余所者(よそもの)感覚を味わうことが多かったみたいなの、一番は夢や野望を持ってやって来たニューヨークで自分の作品をコテンパンにのされたことが原因だったとは思うけど…
些細なことでは紅茶のことや、
あとは食事も合わなかったようね…
それにアメリカの女性は快活で魅力的だが品が無い、ってしきりに言っていたわ、だからモデルにしたくないんだって、』
『なるほどね…
なんとなく…行ったこと無いのに解る気がする』
『食べ物にも品が無いって怒っていた時があったわ、
ホットドッグはまだそう怒りを感じなかった父だけどある夜、父と母と私とで決して高級とはいえない、
ごく庶民的な…でもとてもリラックス出来て感じのいいレストランに入ったの、
そしたら私達が注文したハンバーガーがこれはハンバーガーじゃないんじゃないかって思うほどの馬鹿デカさだったの、
よく覚えているんだけどまだ幼かった私は興奮して思わずこう言ってしまったの
''素敵だわ!だってこれから私達はモンスターを食べるのよ!"』
『可愛いエミリー、
傍に居たらきっと抱きしめたくなるほど可愛らしい女の子だったんだと思うわ』

『そう思うのは優しい彩だからよ、母からは怒られるし父も眉をひそめていたけれど…
でもさすがにその時は私よりも目の前に鎮座する巨大ハンバーガーを、一体どうすればワニでも鮫でもチンパンジーでもなく人間らしく食べられるだろうか?って苦慮を巡らせるほうがふたり共、勝(まさ)っていたと思うわ、
何しろひとつひとつのパーツがボリューミイ、それが重なってるんだから途轍もなく嵩高いときてる、
私達は最初、周りの様子を見ながら、見よう見まねでなんとか噛(かじ)りついて食べようとしたんだけど、顎が小さな母が本気で、これじゃ食べる前に私の顎の蝶番(ちょうつがい)が壊れてしまうわ、
なんて言い出すしそのうち苦闘してる私達を見かねて、父がとても大きな声でこう言ったの、
‘’美世子、エミリー
もうやめなさい!そんな大きな口を開けてこんな巨大隕石にかじりつくなんて、はしたないことをレディはしてはいけないっ!‘’って…』
彩がシーツの上で笑い転げるとエミリーは共に笑いながらも不思議なまでに真面目な瞳でこう言った。
『レストランの店員を呼んで父はこうも言ったわ、
もしナイフとフォークがこの店にあれば持って来て欲しいってね、
ねっ?物凄く嫌味でしょう?
まるでニューヨーカー相手に原始人呼ばわりだと思わない?』
そう言いながらもエミリーはとても愉しそうだった。
恐らく辛かったエミリーの幼少時代に僅かに残された明るく楽しい記憶がニューヨークにはあったのかもしれない、と彩は思ってまるで自分のことのように嬉しくなって眼の裏が思わず熱くなるのを感じた。
『ナイフとフォークを使って倒れそうなほど高くて分厚い巨大ハンバーガーを敢えてケーキみたいに横倒しにして器用に切り分けて食べる私達家族を、店員も周りのニューヨークの人達も本当に芯からびっくりしたような顔をして見ていたわ、
みんなからジロジロ見られてとても恥ずかしかったと母が後から言っていたけど私は凄く愉しかった、
父のそういったところが好きだったしね、
黒人の店員さんで優しくてキュートなおじいさんが言った言葉が可笑し過ぎて今も忘れられないわ、
私達がハンバーガーを不思議なくらいお皿の上で滅茶苦茶にせずに、
小さく切ってまるでそういった料理のように口に運ぶのを見てこう言ったの、
"私は長いことアメリカ人をやっているが、いくら大きいからといってハンバーガーをナイフとフォークを使って食べる人達なんて生まれて初めて見たよ''って』
エミリーと彩は顔を見合わせてベッドの上で転げ回って大笑いをした。
彩は自分がまるでニューヨークに居たかのような不思議な高揚感に胸踊らせてエミリーに問うた。
『お父様はニューヨークで働いていたの?』
『ええ、普段はホテルマンとして、当時はペンタ・ホテルと呼ばれていたとても古いホテルで働いていたんですって、
徒歩でメイシーズへも行けて…
メイシーズからはティファニーへもそんなに遠くはなかった記憶があるって父は言っていたわ、
つまり観光客相手には立地的にとてもよいホテルだったと思うの、
裏手にはエンパイアステートビルもあって、とっても綺麗でゴージャスなホテルとはいえなかったけれど、何故ならあまりにも造りが昔のままで、
それが風情に繋がってはいても、
レストルームにはバスも無くて、
ポツンと天井に取り外せないシャワーだけだったり、
エアーコンディショナーもまだ無くて冬なんかはスチームの旧式な暖房だけ、つまりラグジュアリーなお泊まり感を得たい、特に日本人の観光客には不向きなホテルだったかも…。
伝統的ではあっても貴重品を預けるセーフティボックスも数がとても少なくて、伝統的なホテルだから自分達のホテルを昔から愛してくれている馴染み客を大切にはしてもより大勢のお客を呼びたい、増やしたいってタイプの商業的なホテルではなかったのかもしれないわね、
でも父はそんなペンタ・ホテルをとても気に入っていたわ、
どこか古びたヨーロッパの田舎に一軒だけ建つ外国人に媚びない大ホテルのようだって…
私はその喩えにはあまり賛成は出来ないけれどそう思いたかった父の気持ちはなんだか解るような気がするわ…父はそれだけ自由の国と呼ばれる国に居てどうしようもなく不自由で孤独だったのだと思う…

でもペンタ・ホテルの食堂は綺麗だしホテルで働く人達は移民やニューヨークの下町の人柄が善い人が多いって父としては珍しく誉めていたけれど…
自分としてはデパートに勤めたかったようなの、
メイシーズやブルーミングデールのような…
でもイギリス訛りが相応しくないって面接で断られたとか…
父は最初憧れていたリベラルな筈のニューヨークからダメ出しばかり喰らうような気がしていたんだと思うわ…
段々、ニューヨークを嫌うようになっていった…』
『お母様とはニューヨークでご結婚されたの?』
『父はニューヨークである程度、
名前を馳せていたイギリス出身の画家に師事していたけれど…その画家に師事することも父の兄が取り計らってくれたお陰だったの、
その割にはいつまでたってもニューヨークで個展を開くことが出来なくて…やっと開いても滅茶苦茶に云われる、苛立ちと焦燥感に身を焦がしていた父に父の兄のアンブローズが、カリフォルニアのサンディエゴにあるショッピングモールでの個展を、なんとか仕事の伝手で御膳立てしてもらって…
ニューヨークの住所はそのままに、暫くの間、ニューヨークからサンディエゴのバンク・オブ・アメリカに兄のアンブローズから当座の軍資金を振り込んでもらって
サンディエゴへと父は時差を越えてデルタ・エアラインで飛んでいったわ、
そして念願の個展を開いたホルトン・プラザというショッピングモールで夜よりも黒い瞳を持つ可憐で美しい、どこか悲しげな日本の少女と出逢った…。
少なくとも…父は母のことをそう言っていたわ』
『エミリーのお母様ね?』
『ええ…のちに父にとってのミューズ、
ビューティフル・ワールドの礎ともなる、女性…
当時の母はまだ18歳…。
アメリカの18歳なんてもう大人で、イギリスでも似たようなものらしいけど日本人の母は怯えてて…
打ちひしがれたように見えたって…だから手を差し伸べて、保護が必要な少女にしか見えなかったって…
実際、母は本当に独りでとても弱り切っていたの…
そしてそんな母を父は救ったのよ、それと同時に母は…
父の運命を狂わせた人だったと私は思うわ…
そんな積もりは無かったとしても…でも父の運命を一番狂わせてしまったのは…多分この私だったと思う…』
そう断言したエミリーの横顔が悲しみの奥に険しささえ漂わせているのを見て、彩の胸の内にふとあの夢の国の扉の陰から少女の声が言い放った言葉が重なった。

『彩、エミリーは恐ろしい罪を犯して、それを隠している、
この森の中にね…
だから彼女はこの森を立ち去れない、
……永遠に。』


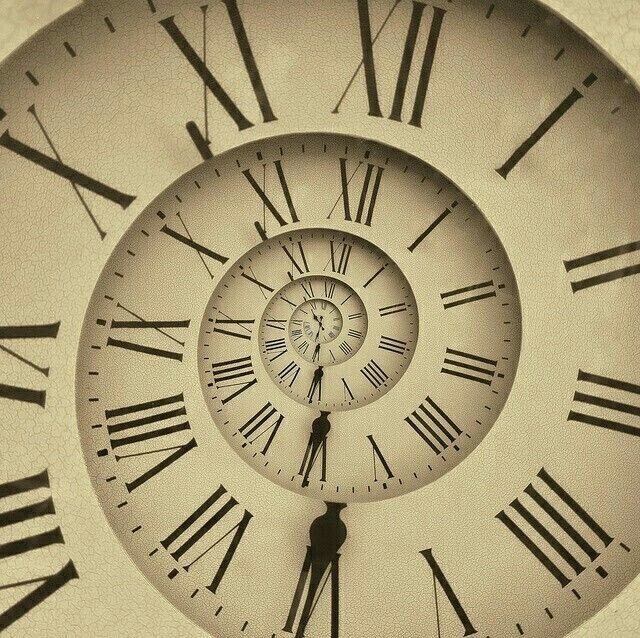
(To be continued…)
