
小説『エミリーキャット』第56章・the gift
エミリーはベビーシッターと共に買い物がてらバッテリーパークへ散歩に出掛けていたのだが、
シッターの車で郊外の自宅へ帰ると、そこで思いもかけないものが彼女を待っていた。
それはエミリーがずっと欲しがっていた『猫』だった。
猫はアデルが生まれた一年前から雇われた24歳のベビーシッターのエイプリルと共にエミリーが散歩から帰宅し、玄関でコートを脱がせてもらっているその時に家の中から現れた。
猫はまるで昔からその家にずっと棲んでいたかのような物怖じしない態度で猫の癖に足音をタタタと立てながら廊下を渡り、エミリーの前へと駆け出してきた。
その態度はまるで『よう、お帰り、お嬢ちゃん』とでも言ってそうに見えた。
エミリーは一目でその大きな仔猫が大好きになり、まだ六歳でありながら彼女は仔猫のことを『きっと彼は私の人生で最も仲のよいパートナーでかけがえのない家族となってくれるに違いないわ!』と思った。
猫は推定、生後三、四ヶ月くらいと云われて連れて帰ったと父親は言ったものの、それよりずっと大きく見えた。
シェルターの女性係員は『獣医の話によるとメインクーンの血が入っているのかもしれない、』とのことで『大きいのはその為かもしれない』とのことだった。
だが基本はミックスで仔猫の癖にどこか不敵な面魂の仔猫は、ビリーに威嚇もしないが甘えるような仕草もしない、無垢な瞳でオドオド、あるいはきょとんと円らな瞳で見上げるというのでもなく、
ただじっとそこに存在しているだけのように見えた。
『静かで穏やかな子です。
男の子で身体は大きいけれど、
どっしり構えたような性格の子ですので、小さなお子さんともきっと仲良くなれると思いますよ、

ちょっと何を考えているのか、
つかみどころの無いところはありますが、大変、悧口だと思います。
基本、優しい子で弱いもの苛めとかする性格の子ではありません、
それに』
と職員は言った。
『この子、ハンサムでしょう?
先輩の男性職員がこう言ったんですよ、フランスの俳優のシャルル・ボワイエに似てるって、』
女性職員は笑いながら
『残念ながら私はその人を見たことがまだ無いので、どんな人かは解りませんけど、私なら…そうねえ堂々としてるからイーストウッドに似てるような気がしますけど』
『クリント・イーストウッド?
あのマカロニウェスタンの若い俳優?』
『ええ、彼、素敵じゃないですか?私、正直白人の俳優を素敵だなあと思うことってそんなに無いんですけどあの人は特別かも、』
『……』
ビリーは女性職員のいかにも人の善い笑顔を見て、乙女の夢を潰したくないと何も言わずにただお茶を濁すように笑って済ませた。
ビリーは自分も動物は好きなほうだがそこまで動物を擬人化して思ったりは出来なかったからだ。
『でもこの子は猫なんだよ?』
と内心言いたかったが、犬にせよ猫にせよ動物が好きでたまらない人達というものは、多分そういうものなのだろうと彼は思った。
動物に対する夢や熱狂がちょっとばかり並みより強いのだ。
黒人のすらりと背の高い妙齢のその女性は、化粧っけの無い艶のある美しい褐色の肌と動物への配慮なのだろう、爪も短くマニキュアの類いはアクセサリーと共に一切していなかった。
その代わり色とりどりのビーズを編み込んだ小さな三つ編みをたくさん肩の上に揺らしながら何度も愛おしげに仔猫の首筋や胸元を、丁寧にさすりつつ、その額や濡れた鼻や瞼にキスの雨を降らせた。
それを見て、ビリーは内心
『美女と野獣ならぬ美女と仔猫か…。
お似合いのふたり過ぎて、離れるのがもったいないくらいだな』
と思った。

『この子は本当は私が貰いたいくらいなんですけど…。
もう今以上に猫や犬が増えてしまうと私も責任を持った動物達との暮らしが出来なくなってしまうので…』
その長く濃い睫毛に縁取られた、濡れた黒曜石のような大きな瞳は一体何頭の遺棄された動物達の悲しみや傷ついた姿や心や叫びを見て聴いてきたのだろう。
目の前の仔猫の幸せで安泰な行く末を願い、案じていることは明白で、
ふてぶてしいような態度の大きな仔猫を見て最初はゴージャスな子だね、と寄ってくる人々もその誰にも心を開かない頑(かたく)な態度に
『もう少し懐っこいほうがいいかな』『仔猫らしさが無いね』
『やっぱり犬のほうがいいかな?陽気で』
などと言って立ち去ってゆくのを見てきた彼女は胸を傷めているのはそのすがるような哀切をこめた瞳と仔猫の美点を頻(しき)りに伝えようとする懸命さにも見てとれた。
ビリーが大きな暖かい手のひらでその無愛想な仔猫を耳の辺りから肩、首筋と撫でさすり、顔の輪郭と顎の横ラインを掻くようにしてやると大きな仔猫はそれが気持ちいいのか、ビリーの手のひらに片耳をくっつけ、そのまま体重をかけるような仕草をとり、
急にゴロゴロと低く喉を鳴らした。
『まぁ!
こんなことは珍しいんですよ、
なかなかこの子はこんな風にしないので、だから誤解されてしまうんです。
でも本当は凄くいい子なんですよ皆さんよく知りもしないで勝手に決めつけてしまわれて…
私、悲しいんです、
よくお前も少しは仔猫らしく愛想よく振る舞ったら?って云うんですけどどうも今一つお上手が苦手みたいで』
『でも…こんなに僕には優しくしてくれているね』
『ええ、貴方は猫の扱いがお上手ですね、それと…
この子は特別賢くて多分この人なら僕を幸せに出来る人だって解ったのかもしれません、
猫はsix senseがあるってよく言いますから、私達には解らない何かを感じたのかも』

『……』ビリーは黙って笑ったが、そう言われて見た猫の瞳は確かに鏡の中に映る鏡のようにその奥深くどこまでも回廊が続いているかのように見えた。
確かに猫は、とビリーは思った。
よく魔女の使いだとか、神の化身だとか単に謎めいて美しいなどとも云われるが、犬のどこか茶目っ気のある呑気な明るさとは違って、確かにその透明度の高い瞳や流線型のフォルムは妖しい美しさがあり、ゆえに人々は猫に対して勝手な想像を掻き立てられ易いのかもしれない。

でもそれは猫にとっては案外迷惑な話であるかもしれないのに、
と 彼は思って微笑むと、大きな仔猫の頭にその温かい手をさながらねぎらうように乗せた。
職員の猫好き女性は更にこう言いつのった。
『貴方は興味がありそうに感じるのでお教えしますけど、この子の足の指は5本もあるんですよ』
『5本?それは…猫としては珍しいことなのかね?』
『う~ん…
この子がメインクーンの血が入っていることは確かだってことかもしれません、
メインクーンには5本指の子が時々居るらしくてそれは他の猫種ではあまりよくあることではないんです』
『そう』ビリーは微笑んではいたがなんとなく興味を削がれた。
それを敏感に察したのか女性はなんとか自分が贔負な猫の魅力を伝えようと必死になるのがビリーには微笑ましかった。
『パパズ・キャットと同じです』
『パパズ・キャット?』
『アーネスト・ヘミングウェイをご存知ですか?
『作家の?』
『ええ、私、本は読んだことはないんですけど』
『僕もあまり無いな、
誰がために鐘は鳴るとか戦争と平和くらいしか…
ああ、あと老人と海はよかったな、うん、あれはよかった』
『それだけ読んでたら充分です』と彼女はちょっぴりムッとしたような顔を見せたもののすぐに零(こぼ)れるような微笑(びしょう)に変わり、
その黒い大きな瞳は悪戯っぽく優しい女豹のように綺羅めいた。
『でもそのヘミングウェイが猫好きで有名だったのはご存知ですか?』彼女はそれを言うだけでももう嬉しそうだった。
『いや、それは初耳だな』
『私はヘミングウェイの本は知りませんけどヘミングウェイが猫好きだったってことだけはよく知っているんです。』
と女性は真っ白い歯を見せて笑うとまるで平和の象徴である猫はすべてを魅了してしまうのだ、
エジプトの神様ですらね、とでも言いたげな微笑みに、愛する猫の未来を願ってどんなに猫という小さな美しい獣が偉大な芸術家を魅了したかを熱っぽく語った。
『ヘミングウェイは自分の愛猫の血を絶やさないようにする為に、愛猫が性成熟すると雌猫をもらってきて、そして仔猫が生まれて、その仔猫が雄だとまたよそから、お嫁さんをもらってきて…。
雌だと雄を貰ってきて掛け合わせるというふうに自分が一番最初に愛した猫の血を決して絶やさないよう、上手に他の猫と掛け合わせながら、増やすというか…
途切れることなくその血の維持をしていったんです』

『ほうそれが五つ指の猫と何か関係が?』
『そうなんです、
一番最初に彼が愛した猫が五つ指のメインクーンだったんですが、のちに掛け合わせて増えていったその猫の子孫達も皆、ミックスなのに五つ指の仔猫達だったんです、
厳密にはそうではない普通の4本指の子もいたことはあったそうなんですが、そういう子も含めてファンからはアメリカのパパの愛称で呼ばれていたヘミングウェイは、どの子も皆、可愛がったらしいんですが…見て下さい、ほら、
ミックスなのにこの子も立派な五つ指、
見てこの大きなお手々、
まるで大きなマフィンみたいにキュートでしょう?
立派な肉球と素晴らしい五つの指を持つ精悍で美しい男の子!』
と彼女は仏頂面極まる仔猫にそこがたまらないのだというように抱きしめてキスをした。
『パパズ・キャットと全く同じです!だってヘミングウェイの猫の子孫は今でもその血が絶えないようにと掛け合わせられ続けていて五つ指の猫がアメリカの各地に…
いえ、世界中に貰われて現存するんですよ、そしてそのパパの猫の血はこれからもパパと猫を愛する人々によって大切に受け継がれてゆくんです。

だから、もしかしたらこの子はパパズキャットの流れを組む子なのかもしれませんよ?
ねっ?ミステリアスなこの子にはそういった想像が決してただの想像とは思えないくらいぴったりだと思いませんか?
きっときっと…この子はパパズ・キャットの末裔なんです。
今尚、人々から愛されるあの伝説的な猫の貴族です。』
猫を貰い受け、キャリーバッグを下げて、車の中へ入るとビリーはアニマルシェルターのガレージまで名残り惜しげに見送ってくれた女性職員の泣きべそをかいた顔を見て、今度は隣のシート上のキャリーの覗き窓から見える仏頂面の猫の横顔とを見合わせた。
そしてふとその時、仔猫の名前を思いついた。
全くコインの表と裏ほど違うその顔もその様子もどちらも違うのに不思議ならくらいその両方が魅力的だった。
‘’命は面白い‘’とビリーは思った。
それは何も人間だけに言えることではない、
手をふりながら仔猫の幸せをひたすらに請い願い、そして神に祈り、だんだんリアウィンドーごしに小さく遠ざかってゆく女性の熱い涙のその温度がビリーにまで伝わってくるような思いに彼はなった。
『おい、プレイボーイ、
あんなに心優しくて可愛い女性にそんな冷たい態度でお別れも惜しまないなんて、
お前さんけっこう冷たいんだな?』
『ギャ…』と返事をするように低い仔猫じゃないような声で返事をした猫の横顔は、しかし一瞬泣いているように見え、ビリーははっとした。
無論、次の瞬間そんなことはなくあれは目の錯覚だったのか?と思いはしたものの、ビリーは仔猫が仔猫なりに彼女と別れなければならない運命であることを本能的に知っていたのかもしれない、
そのために本当は好ましい彼女と親しくなり過ぎないように努めていたのかもしれないと感じ、猫の想いに胸を突かれた。
そして彼は一際、優しい声で仔猫にこう言った。

『決めたよ、カーボーイ、
お前の名前、
お前はロイだ、どうだい?
いい名前だろう?』
女性職員が泣きながらいつまでもシェルターの前で、その姿が遠く小さく見えなくなるまで立ち尽くし、手を振り続けていたその姿は高速道路を走りながらもビリーの脳裡に何度も蘇った。
そして彼は女性のユニフォームの胸についていたネームプレートを思い出してこう言った。
『なぁロイ、彼女にそう言ってあげたらよかったかもしれないな、
きっと喜んでくれただろうに…』
女性職員の名前はロイスだった。

そして同時にふとヘミングウェイは自殺したのではなかったか?
と思い出したが、彼はそんなことはどうでもよいことのように感じられた。
ヘミングウェイをそれだけ彼女は知らなかったのだろう、
ロイスが愛した伝説はアメリカのパパと呼ばれた作家ヘミングウェイ自身やその作品よりもその愛猫達の連綿と雑種化しながら受け継がれる人々の想いがこめられた愛という血脈と絆のほうだったのだ。それでよい、そのほうがよいと彼は思った。
そして彼は思った。
『素晴らしい猫を手に入れたぞ!今日のエミリーの誕生日祝いにぴったりだ。』

エミリーは猫が欲しいと言い出したのは野良猫を見てそのしなやかさと高い塀の上へもひらりと飛び乗る敏捷さがまるで小さな豹のようでとてもクールで神秘的で、
たちまち魅了されてしまったからだった。
しかし野良猫はなかなか捕まえることが出来ず、触ろうとしたエミリーはしたたか猫パンチを受けた上に小さな指に穴が空くほど噛みつかれ、麻酔をすると余計痛いからと彼女はその穴へ消毒薬を染み込ませた棒を医師から差し込まれ大泣きした癖にその怪我が癒えぬうちからもう野良猫を追いかけ回しなんとか仲良くなろうと苦闘するのを見かねたエイプリルが
『ちょっとでも目を離すともう猫を追いかけていて…
いっそのことおうちに猫が居たら良いのではないでしょうか?
きっとよほど好きなんですよ、
本人も私、猫に夢中なの、猫に恋に落ちたの、なんてどこで聴いて覚えたんだかそんなこと言っていますし、』
と提言したほどだった。
普通は猫に痛い目に遭わされたらトラウマになって猫を怖がるようなになるだろうに、とエイプリルは思った。
エミリーはトラウマどころか、
ホテルの美しい庭園に居る白鳥が岸に上がって休んでいるところをそっと後ろから近づいてそのたっぷりと肉厚な羽根を畳んだ固く締まった軆を撫でさすり、野太い悲鳴を上げた白鳥に執拗につつき回され、茫然自失となり彫像のように固まっているところを父親に横からまるで人さらいのように救出されたこともあった。
が、彼女は動物に関する限りそういった経験がトラウマ化することは全く無いようで、『猫も白鳥も悪くないわ、私がびっくりさせてしまったの』
と庇うほどだった。

エイプリルはそんなエミリーが可愛かったが奇妙なところのある不思議な子供だとも感じていた。
まずどうも人との距離感が解らないのか誰にでも馴れ馴れし過ぎた。見知らぬ人にねえねえと話しかけてはなんの脈絡もなく自分の興味のある話を一方的に話し出したりする。まだ幼いからなのかもしれないと思ったが場の空気を察することは苦手らしく同い年の子供同士や子供の親や自分の母親からさえもよく烈火の如く怒られてばかりいた。
人がなんとなく不快に感じるようなことを思いついたらそのまま口に気がつくと出してしまっているらしくそのことに悪気は全く無いのだが、まるで人を怒らせる天才のようだとエイプリルは思った。
『あなたの歯は汚いわ、
ちゃんと磨いているの?
もっと取り出した入れ歯みたいに丁寧に磨かないとダメよ』
などと言えば嫌われてしまうのは当然だろう。
一体全体どこで覚えるのかやたらと小難しい言葉や比喩を使って話したがるのも可愛げがないと思われる原因となっていたが本人は、その事にあまり気づいてはいないようだった。
小難しい言葉や比喩で子供らしい話の内容が語られるのでちぐはぐな感じがしてエミリーは賢いふりをしているだけの小生意気な少女のようによく思われた。
‘’子供だから仕方無いのだろう、
そのうちコミュニケーションを重ねてゆくうち、いろいろなことを経験して覚えてゆき言葉のリスクを回避する知恵もついてゆくに違いない‘’とエイプリルは思ったが、どうもそれだけではないような気がした。
エミリーは独り遊びが好きで、友達から一緒に遊ぼうと誘われると時々癇癪を起こしては問題児扱いをされた。
エミリーに叩かれた、突き飛ばされたという子供達の親からクレームを入れられ大切な孫息子をひっぱたかれた孫息子の祖母から『リメンバー・パールハーバー』などと嫌がらせの電話を受けたエミリーの母ミヨコは憤慨し、そのストレスの発散の場はどうしても問題の種子であるエミリー自身に向かった。
『どうしてナイジェルをひっぱたいたりしたの?相手は男の子よ、貴女は女の子なのに男の子をひっぱたくなんて』
『ひっぱたいてなんかいない、
殴ったのよ、ボクサーみたいに』『じゃ、もっと悪いじゃないの!どうしてそんなことをしたの?』『あのね、私、空気中にあるお城に迎えられてたくさんの虫と人々と、たくさんの虫と人々の血を引く何かと一緒に凄くうっとりしながら熱心に遊んでいたの、
とても楽しく語らっていたのにナイジェルがみんなでボールで遊ぼうって私の腕を掴んで無理矢理、連れてゆこうとしたのよ、
私はそんなことして遊びたくないからほっといて頂戴って言ったのに、‘’子供はみんなで仲良く遊ぶものだってママが言っていた、
エミリーみたいにいつも独りで、ぼーっとしているのは良くないって言っていた‘’って私に言ったのよ、私はぼーっとなんかしてないわ、それに嫌がっているのに無理矢理私を立たせて連れてゆこうとしたから』
『だからパンチしたっていうの?まぁなんて野蛮な子なんでしょう、暴力で解決しようとなんかしては駄目よ』
『暴力?』
『叩いたり殴ったり、蹴ったりすることよ?
貴女は猫や動物には優しいのに、子供達の間ではいつも問題を起こすわね』
『私、暴力ふるってなんかいないわ』『ふるってるじゃないの、
ボクサーみたいに殴っていいのはボクサーだけなの、
それ以外は殴ったりしちゃ駄目!』
『でもママもすぐに私を殴るよね?ママは殴ったり蹴ったりしてもいいの?ボクサーじゃないのに?私、ママがよく殴るからついそうなっちゃうんだもの』
『……』
『それに嫌がってるのに無理矢理自分達の世界に押し込めようとするのはある意味暴力じゃないの?』
『…え?なんですって?ある意味?』
『私は他の子供達とは持ってる文化が違うのよ、』

『…文化…』
『だから一緒に遊んでも楽しくないの、
分かち合えないもの、お互いに』『……』ミヨコは驚いて無言となってしまった。
『あの子は賢いんだかそれとも、ちょっとオツムのヒューズが飛んでいて、そのせいで少しばっかり狂人の素質があるんだか、
本当に理解に苦しむわ、』
ミヨコはアデルの靴下を編みながら良人(おっと)にそう言った。
この頃、妻がビリーに隠れて時々煙草を吸ったり寝る前に独りでウィスキーを飲んだりしていることも彼は知っていた。
それだけミヨコのストレスは大変なものなのだろうと彼は敢えて何も言わなかった。

『アデルがエミリーから将来ヘンな影響を受けなきゃいいんだけど』『大丈夫だろう、確かにエミリーは、少し変わった子供ではあるが…成長の過程で徐々に落ち着いてくるかもしれないよ?』
『そうかしら?
私、あの子は普通ではないと感じてしまうの、一度ニューヨークの児童向けのクリニックで脳の検査とか受けさせたほうがいいんじゃないかしら?』
『う~ん…その必要はまだ無いだろう、問題児というほどでもないよ、時々男の子並みの喧嘩をするくらい、まぁ些かお転婆さんといった程度なんじゃないかな』
『男の子を打ち負かしたりするのよ、あの子ってば、
唯一仲良しのシェリーを苛めたかなんかした男の子をボコボコにしてしまったんだから、シェリーを泣かしたら承知しないから、って言って仇打ちをしたらしいわ、
シェリーは飛び上がって大喜びしてくれたってエミリーは得意になっていたけれど…。
後からイーサンのお祖母様やご両親にこってり絞られたのは…
ああもう去年のことなのね』
『勇敢なんだよ、
弱いもの虐めを許せないんだろう、だってエミリーは弱い年下の子供や女の子や動物は決して虐めたりはしないだろう?
彼女が歯向かうのはいつも…
自分より遥かに強くて力もある乱暴な男の子や高圧的な大人だったりする、
つまり誤解されがちだけど…
本当は優しい…キングコングみたいな女の子なんだよ?
ほら、キングコングは文化が違うから周りから攻撃を受けるが、本当は純粋なところもあって根は優しい…』
『何がキングコングよ!?
冗談も休み休みにして、ビリー、酷いわ!
エミリーは女の子なのよ?
勇敢だなんて…普通でいいのよ、
普通で!
もっと、優しいだけの…可愛げのある女の子らしい…
キングコングだなんて…
小公女ならまだしも…キングコングだなんて…!』
と言ってミヨコは泣きながら編みかけの靴下で思わず鼻をかんだ。
『ごめんよ、無神経なことを言って…でもそんな積もりじゃなかったんだ、キングコングはピュアで僕は素敵だと思ったから…
仲良しの大好きなシェリーを庇って喧嘩になったのもキングコングが政府のアタックから愛する人を守ろうとした心意気にどこか似てる気がしてね、

でも確かに娘に使う喩(たと)えではないな、
今のエミリーはまるで女の子の格好をした男の子みたいにガサガサしてはいるが、そのうち落ち着いてくるさ、まだエミリーは幼い、
児童向けクリニックだなんて時期尚早だよ、彼女の自然な成長を、もっと長い目で見てあげようよ』
『私はアデルが心配なのよ、
去年なんかアデルがやっとよちよち歩きを始めて…もし妹が危ないところへ近づきそうになったらママに教えてねっていう意味で妹を見ててとエミリーに頼んだのに、
本当にただじっと見てるだけだったのよ?
妹がよちよち歩きをしたまま廊下へ出てゆこうとしているのにエミリーったら私に何も言わなかったの、
ママ、危ないから早く来て、とか教えてくれそうなものなのに、
なんにも言わない、ただ見てただけなのよ??
廊下の外は踊り場だけど、その先は階段でしょう?
偶々(たまたま)私がすぐに見つけたから無事だったけど…
どうして何も言わないのっ!?
って怒ってもママは見てろとしか言わなかっただなんて云うのよ?
信じられないわ、
どこかおかしいのよ、
何がどうおかしいのか私にも難しくてはっきりとは言えないんだけど…でもなんと言ったらいいのかしら、とにかくエミリーは普通じゃないわ、上手く云えないけど他の子供達には絶対、機能している何かがあの子には生まれつき機能していないか、もともと欠落してしまっているのか…
あるいは生まれつき異常なのよ』

『そんな…そこまで…いくらなんでも考え過ぎだよ、ミヨコ、
そこまで云ってはエミリーが可愛そうだ…』
『いいえ、私、時々こう思ってしまうの、
エミリーさえ居なかったら私と貴方とアデルと三人、完璧なファミリーなのにって、あの子はその完璧で平和なハーモニーを乱す不協和音で、キーティング家の汚点でしかないって』
『……』ビリーはただミヨコを黙って固く抱き寄せた。
そうすると愛しい妻は苦悩の涙を流しながらも彼の腕の中でたとえ一過性であったとしても安堵の様子を深々と羽根を揃えて休む蝶のように見せた。

‘’彼女は今、難しい子供を育てるのに疲れていて少々ノイローゼ気味なのだ、だからこんな言葉を思わず発してしまうのだ、それは今彼女に余裕がそれだけ無くてとても辛いからであって、決して本心からではないのだ…‘’
とビリーは思った。
増してやエミリーとビリーとは血の繋がりが無い、
その事へのビリーに対するミヨコの負い目や背徳感じみた気持ちに苦しんでいることは確かだと彼は思った。
いくらそれはビリー自身も選んだことなのだから、これからも安心して共に担う大切な人生だからと言い聴かせてもミヨコはまだ不安げだった。
ビリーは、妻の不安を払拭してやりたいあまり、娘のエミリーの不安や寂しい思いにまで思いを馳せる余裕が彼もまた無かった。
たくましいエミリーはこれからいくらでも成長してゆくしそれと共に変化もしてゆく。
だが大人のミヨコは自分が慰めてやらなくては母親としての不安は消えることがない、
そう思った彼はつい妻ばかりを構い、エミリーを無視しがちとなっていった。
ある時、ビリーは兄のアンブローズの友達の小児科医を兄の新しいチェーン店のオープン記念パーティーの席上で紹介され、思いきってエミリーの話をしてみた。
『高機能性自閉症という可能性はあると思いますが、エミリーの絵を見てふと…これは私の印象でしかないのですが』
とその医師はそう云いながらも、どこか躊躇しつつ、しかしそれをどうしても言いたげな様子が見てとれた。
『はい?』
とビリーは薄い微笑みを無理に浮かべると動揺を隠した。
『サヴァン症候群って聴いたことありますか?』
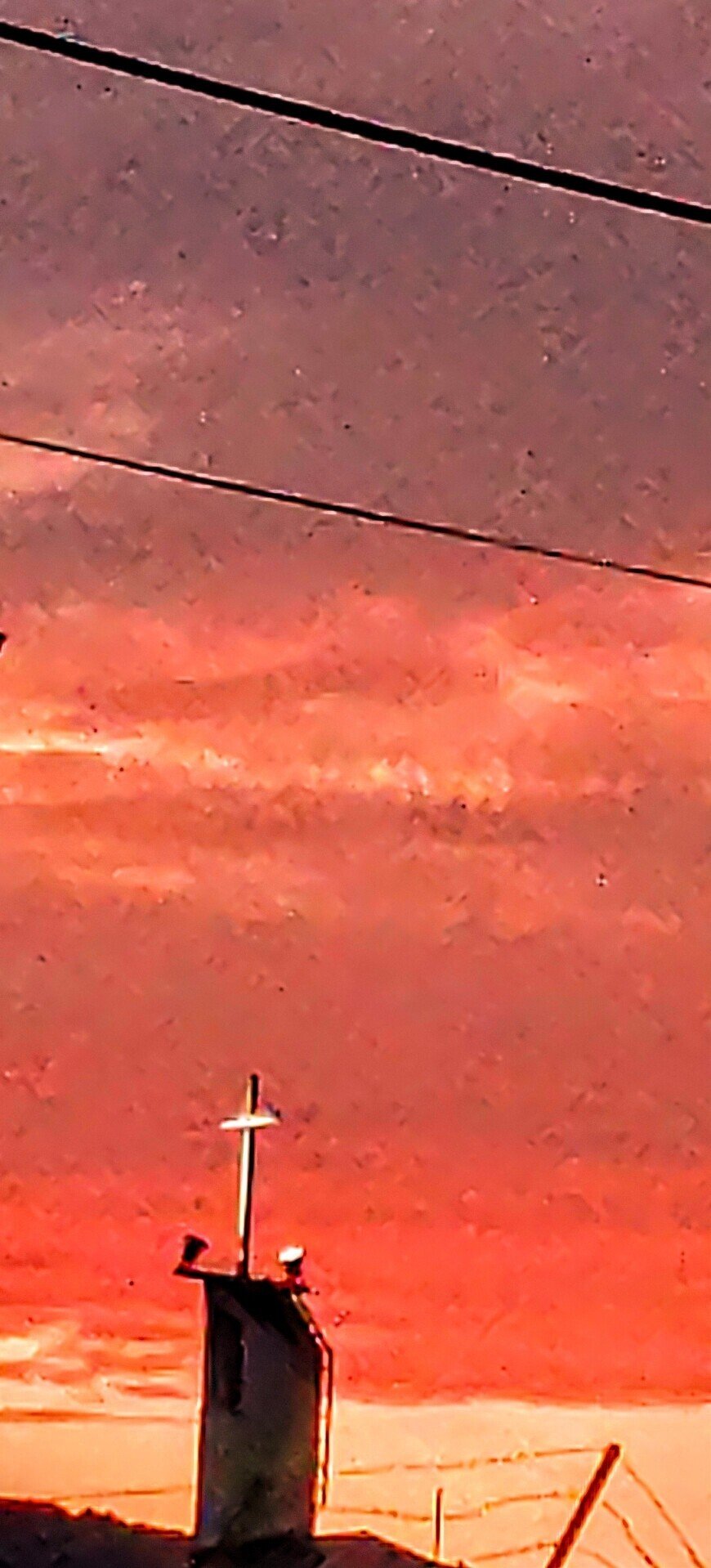
『サヴァン…』
『六歳であの絵は…いかになんでもと思いましてね、最初見た時、
一瞬白黒の写真かと思いました。
あれは鉛筆画だと貴方のお兄さんから聴きましたが…』
『アンブローズが…いつそんな、
絵を…』
『彼のうちへ娘さんが来た時に描いてお兄さんへ渡したんだそうです。お兄さんはショックに近いほどその絵を見て戦慄したと言っていました。私も見たんですがね、本当にあれを六歳の女の子が独りで描いたとはとても思えません、でもだとしたら…』
『その…サヴァンとかいう』
『かもしれませんし、そうではないかもしれません、
まだサヴァンについてのちゃんとしたテストやそれに付随した定義が曖昧なので検査で判然とするような段階にはまだなっていないのです、ですが過去の芸術家にはサヴァンだったのではないかとされる、あくまでもこれは推測ですが…
画家や作家はたくさん居ます。
お嬢さんは全く楽譜は読めないのに一度聴いただけであらゆる難しい楽曲を全て完璧に弾くことが出来るとか…』
『でも…エミリーはまだ…
六歳なんですよ?
それに確かに変わったとこはありますが、あとはごく普通の小さな女の子です』
と言ったビリーはふと思いついたようにこう言い直した。
『まあ、そんなに小さくはありませんが、でも少女です』
『サヴァンだと断言しているわけではないのですよ、ただ可能性はゼロではありません、
むしろ普通の児童よりは可能性は高いと私は感じています。
あの絵を見れば、誰しもそう感じるでしょう、小さな天才だと』『小さな…天才…』

『もしそうだとしたら貴方は画家でいらっしゃることですし、その貴方の血を濃く受け継いだということでしょう、貴方の親族にたとえば学者がいたとか著名な作家がいたとか…ありますか?』
『いえ、うちはそんなことは』
とビリーは狼狽を隠せなかった。アンブローズはエミリーと弟は血が繋がっていないことはどうやら伏せてドクターに話したらしい。ビリーにもミヨコにも配慮をしてくれたのだろうと彼は思った。『隔世遺伝なども考えられますよ、まあサヴァンにせよ高機能性自閉症にせよ、遺伝と決まったわけではありませんが…これは障害ではありますが、悪いことばかりではありません、つまり光の照射の仕方によってはある意味、天からの贈り物なのです。
…大切に育てて上げて下さい、
丁寧に指南しながら彼女の良いところを伸ばしてあげれば将来が見ものとなる可能性は無限にあります。』
『……』

『どうしても単なる問題児としか思えない時は是非私のところへ連れてきて下さい、サヴァンの検査結果を出すことはできませんが、
いろんな検査をしてエミリーの得意な分野や不得手なもの、
何が出来て何が理解しづらいのか、こだわりの異常なまでの強さや反復的な行動やパターン化された暮らしや遊びかたなどに安心感を覚えたり、予測不可能なことが急に起きるとパニックに陥ったり極端な不安感にさらされて心理面でももちろんですが肉体的にも失神するなど特別な反応が生まれたりはあるのか…
またコミュニケーションに問題があるのか、
社会的コミュニケーションの質的な問題、
人との会話のやりとりによる質的な問題、他者との距離のとりかたが苦手かどうか?
大人でもあるんですよ、
様々な人の言葉の裏や意図、
社交辞令の意味への察知が出来ずに何気なく言った言葉や行動が問題視され、怒られたり、場合によっては訴えられたり会社をクビになったりとかね…。
またエミリーのような幼い子供の場合だと学校に上がったりするとどうしてもイジメに遇ったりしやすくなります。
変わっていると村八分にされたりなどの暮らしの中での困難や苦痛が増えてくる可能性は多いにあります。人は人種や宗教といった多様性を認めようと口では言いながらも実は異質なものを気味悪く感じたり、疎んじたり、自分の世界から切り捨ててしまいたい、排除したいと感じてしまうものです。
しかし排除される側の人達に悪意や害意があるわけではないところが悲劇となることがあります。
それは決してわざとやっているわけではなくても他者の地雷を踏んでしまうリスクが生まれつきあるからです。
だとしたら具体的にはどういう場面や場合が多いのか?どうすればそれを回避出来るのか?
親御さんには知る必要があります。
つまり、コミュニケーションによる困難さが彼女を苦しめて不自由な生きづらさを与えてはいないか、様々なことを今は調べることは出来るんですよ、
幼い頃から訓練してしまえば先天的なことなので完治はしなくともだいぶそういった困難を和らげ、回避に近い方法やその為のスキルを身につけることが出来ます。
ですが大人になるまで放置しておいてはそれらはもうとても本人の努力だけでは難しいものとなってしまいます

ですがどんな部分がどれだけ苦手でどんなことでどれだけの力を発揮する能力が隠されているのか?それらはすべて科学的な数値として顕著に現れて、立証されるんです。そうして上げたいとは思いませんか?人生という道に極端な迷いかたをしてしまいかねない障害を持つ子供をいかにして導いてあげるかがこれからのアメリカの課題です。
まだこの研究分野は始まったところですからね、
外国によってはまだそういった概念すら無いでしょう。』

『異質…コミュニケーションによる困難…他者の地雷を踏んでしまう生まれつきのリスク?
エミリーはまだ六歳なんですよ?社会的コミュニケーション性の質的な問題だなんて…そんなこと』
『質的な問題というのはつまり、質的な障害という意味です。
エミリーは恐らくなんらかの脳の障害があります。
アンブローズから聴いた様々な話からして間違いは無いでしょう。
サヴァンでないとしても脳の生まれつきの器質の違いによる障害は恐らくあるはずです。』

『……』
『しかしそれに勝るとも劣らない、それを上回るような素晴らしい才能の芽も同時に豊かにあります。
失礼かもしれませんが奥様のことをお兄さんから聴いたのですが…
その芽を奥様が摘むようなことにならなければよいがと私は危惧しているんです』
『…妻がですか?
そんな馬鹿な…妻は娘を心配してはいますが愛していますよ、
そりゃあそうでしょう?娘なんですから、』
『でもエミリーはアザだらけだとアンブローズは言っていました。これはなんだ?とアンブローズが聴くとママは私がきっと嫌いだからこんなことをするの、とエミリーが言っていたと…』
『それは…しかし少々体罰をしてしまうくらいはどんな親にでもあることですよ』
『少々で指の骨を折るほどのことがあるでしょうか?背中も紫いろに腫れ上がっていたとお兄さんから聴きました。』
『……』
『よくあることなんです。
そういった非凡なお子さんを育てるのはストレスの多いことです。私は何も奥様独りを責めているわけではありません、
奥様もまた悩み、苦しんでおられるはずです。
ですがそういった環境は無論、
奥様にも、そして何よりお子さんの今後の成長にとって決っして、よいものとはいえません』

『兎に角、一度クリニックへお嬢さんを連れてきて下さい、
待っていますよ、アンブローズも心配しているんですよ、エミリーは彼に懐いていますからね、
私も一度逢ってみたいんです。
あの素晴らしい鉛筆画の作者にね』
と、そのニューヨークの児童ブレインクリニックの院長であるというカーキがかった浅黒い肌が印象的なドクター・イカヴァニの名刺をビリーは手渡されたものの、
そのまま何となく三年が過ぎ、
やがて一家は日本へ行くこととなった。
しかしビリーの頭の中にサヴァンという言葉は、まるで偏頭痛のようにしがみついてその先、十年以上も離れることは決してなかった。



…to be continued…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
