
小説『エミリーキャット』第39章・タンブル・ウィードを追いかけて
『父はニューヨークのことを本当は好きだったんだと思うわ、
きっと愛憎の両方に、振り子のように揺れ動いていたんだと思う…。』
と、エミリーは言うとそっとベッドの上に起き直り、顔に乱れ落ちた長い髪を中指で掬(すく)い上げ、片耳に掛けると気がつかないほど微かなため息をついた。
エミリーに倣うように身を起こした彩の視線からまるで逃げるように、エミリーは急に立ち上がると、
濃い飴色のアップライトへと歩み寄った。
黙ってピアノの蓋を開けると、彼女は椅子に座ってしばらくは何も言わなかった。
その沈黙は酷く長く彩には感じられ、耐えきれずに彩が立ち上がろうとすると同時にエミリーがピアノをいきなり奏で始めた。
彩は心の中で呟いた。
''この曲…仕事であの不思議な街に迷い込んだ時聴いた曲と同じだわ…"

『私、嬰(エイ)ハ短調の楽曲ばかり弾くと言われたことがあるわ、
でもそんなこと無いんだけどな…
多分それらの曲のほうがきっと印象に残りやすいのね』
『エミリー、その曲、
ベートーベンじゃないでしょう?
じゃ…モーツァルト?違う?
じゃショパン?…違うの?
バッハって感じじゃないし…
ラフマニノフ?…
そうかあ…じゃあねえ…』
とエミリーが答えないので彩はもともとクラシックにそう強いわけではなかったが、知っている限りの音楽家の名前を挙げた。
しかしエミリーは黙ってどれも頭を左右に振るだけだった。
彩は立ち上がるとそっとピアノを弾くエミリーの後ろへ回り込み、その水鳥のように長い首筋にキスをした。
エミリーは彩の不馴れなキスに、
くすぐったそうに小さく笑い声をあげ、ピアノを中断した。
エミリーは彩のほうへと座ったまま向き直った。彩は黙ってエミリーの肩へと両腕を回し、彼女の膝の上へ横座りするとエミリーを抱き締めた。
エミリーはピアノの前の長椅子のシートを姿勢をずらせて彩を隣へと招き入れた。
彩は隣に座ったまま暫くエミリーの演奏を眺めた。
さっきとはまた曲が違う…。
と彩は思った。
『私が隣に居て、弾きにくいんじゃないの?』
『いいえ全然』
また途中でふいに曲が変わり、エミリーの節が目立つわけではないが、どこか青年じみた指が細波(さざなみ)のようにクリーム色に黄ばんだ古い象牙の鍵盤の上で小刻みにスウィングする。
彩はそれを見て木の葉(このは)が小止み無く軽快な風に舞うようにキラキラと光りながら、揺れ動く様を思い出した。

そんな時の木の葉の揺れる先端は、まるでピアノを早弾きする人の指先を想わせる…彩はよくそう思って風に旋回する木の葉を見ていたが、今、目の前で見るエミリーの指の動きはあの風をはらみ、更にその風に波打たれて微細なダンスを見せる、あの木の葉の先端そのものだった。
初夏の緑雨(りょくう)に打たれ、
その虹を映した雨粒を雨後も尚、
上の枝葉から下の枝葉へと光を弾(はじ)きながら、たわみながら、
リズミカルに光の粒を滴らせる森の麗姿を、彩はこんな真夜中の室内で、しかも間近に見る思いがした。
小止み無く吹く涼風(すずかぜ)に揺られるように小さな舞踏を繰り広げる美しい森の手が、彩の目の前にある。それは森でありながら同時に、エミリーで、それらがなんの相反も矛盾も無く自然と融合して今彩の目の前にあるのだ。
エミリーの指先は、そして腕は、
風を味方につけた小さな彩の腕の中に独り占め出来るほどのささやかな森であり、その森は風も吹かない空間でさえ旋回するかのような小刻みな、ダイヤモンドの駒となって綺羅めくトリルを奏で続ける。
ひとつの曲が終るまでに彩は森に抱かれ導かれ、
その半貴石よりも透明な風と空気に満たされた森の中で光の欄干に寄って、そっと息づき、ゆったりと砂金を含んだ狭霧が左側に向かって旋回する小宇宙を見下ろした。
と同時に見上げてもいた。
それらは矛盾ではなく鏡像の如く彩の眼前に顕現した。


『…だった?』
エミリーが唐突に問うてきたのを彩ははっと目覚めるように訊いて驚いたようにエミリーの顔を見た。
『えっ…ごめんなさい、何?
何か言った?』
『聴いてなかったの、』
エミリーは笑って『お母さんのこと、彩は覚えてる?』
『…ああ…』
と彩は言葉を失い『母は私を産む時に亡くなったから…全く記憶はないの、残念ながら写真の一枚すら持ってないから…。
侠骨盤による難産による死亡って私が持っている母子手帳には書いてあるけど…
本当のところはよく解らないのよ、その難産で開腹オペになったんだけどそのオペの執刀医のミスで出血が止まらなくなって意識不明となって亡くなったという話もあるから…。
でも私は赤ん坊だったから…
もう真実は解らないわ、

本当のこと言うと母の執刀医の病院まで調べて問い合わせてみたんだけど…本当のことを知りたかったから…
何も責めるとかではなくて、兎に角母に関することならなんでもいいから真実を知りたかったの、
でも…既にその医師は他界していたの、
母を執刀した時、既にかなりご高齢であったらしくてオペをしたおよそ二年後にお亡くなりになっていたわ…』
『お父さんは…?』
『父はね…もうまるで解らないの、どこの誰なのかも…母は結婚していたんだけど…放浪癖があった人みたいで…
日本中あちこちほっつき歩いて旅していたみたい、厳密には旅じゃなくてただ彷徨っていただけみたいな…
家庭で何故か落ち着けなかったようでご主人を置いて放浪してしまってなかなか家にじっとしていることが出来なかったようね…
…でもきっと何かあったのよ、
母が家柄が違うとか言われてご主人やご主人の家族から苛められていたって説もあるのよ、
母はもしかしたら居づらかったのかもしれないわ、
家庭に安らぎを見いだせなかったのかも…だから…だからあんなことを…』

『彩…』
エミリーは彩を抱き寄せた。
『彩、私達は残念だけどあまり暖かい家庭や安心出来る環境や両親には恵まれなかったけど…
これから私達がその家庭を作りましょう、家庭っていうとみんなはご主人がいて奥様がいて、子供達が…って決めつけてしまうけれど…
いいじゃない?別に、
そんな枠にとらわれていなくても…
私達はもう家族よ、

彩はここを自分の家庭、家だと思ってくれていいし、故郷(ふるさと)だと思ってもらえたら私はとても嬉しいわ、私と彩は家族、姉妹であり、同時にソウルメイトでもある、
猫達はひとり残らず私と彩の愛する子供達よ』
彩はエミリーの肩に頭をもたせ掛けて言った。
『嬉しい…私、もうずっとエミリーの傍で暮らしたい、みんなと一緒にここでこうして棲みたいわ…』
『私もそうして欲しいと思ってるわ、』
『今の会社を辞めて…
いろいろなことを精算して…
そしてここへ来たい…
森でエミリーと猫達と暮らしたい』そう言い終わったあとに彩は目を閉じて言った。
『…もう疲れたの…何もかも…』
エミリーは彩をいつの間にか自分のショールの中にすっぽりと抱き寄せていた。
『…それといつの日か…
エミリーと一緒にニューヨークへ行ってみたいな…』
エミリーはそれには答えず苦笑した。
『彩にはカリフォルニアの光も似合いそうだわ、
もちろんニューヨークも素敵なところだったけど…』
『サンディエゴって私、聴いたことあるわ、ヨットハーバーが沢山あるところでしょう?』

『そうよ、だから時々ヨットレースも行われるみたいなんだけど…
それは私は見たことが無いわ、
正直言ってカリフォルニアは私の体質にはあまり合わなかったから…』

『そうなの?どうして?』
『光が強過ぎたの、
あまりにも強烈よ、目も肌もまるで射抜かれるみたい、
ただだいたいの人達にとっては環境としてはよいとこだと思うわ、
湿度が低いというよりはもう本当にカラッとしてて…
ともすれば乾燥しがちだから、
それには気をつけたほうがよかったけど…でもだからこそなんでしょうね、
どんな真夏日でも木陰へ入るともうクーラーに当たるよりもずっと心地好くて涼しいの、

だからサンディエゴでは真夏の外出先で思わずカフェなんかに避暑の為に逃げ込む必要が無かったわ、
だって暑けりゃ木陰や建物の陰に滑り込めばいいんだもの、地べたに座るのなんてやだって、潔癖な日本人なら思うでしょうね、
でも向こうでは誰もが平気でどこにでも座っていたわ、
バス・ストップのベンチがご老人でいっぱいな時は道路にさえ座るくらいだもの、
日本人はティーン以外はそんなことしないでしょう?椅子のあるとこしか座らないわよね、
喫茶店とか待ち合い室とか駅の座席とか…。』

『エミリーはサンディエゴで生まれたの?』
『いいえ、父と母が結婚したのはニューヨークへふたりで戻ってからだったわ、でも暫くニューヨークに住んでいたものの、やっぱりサンディエゴへまた戻ったの、サンディエゴへ戻る前に中西部のシカゴやボストンへ寄って一年、半年と居たこともあるけれど…
サンディエゴは私の体質に合わないところではあったけどニューヨークの次にやっぱり印象に残る街だわ』『お父様の作品はサンディエゴでは認められたの?』
『…いいえ残念だけど…
認められるまではゆかなかったの、
でも…サンディエゴでの個展はまあまあ好評ではあったのよ、その時の新聞の論評も概ね好意的で…
父は物凄く慕っていた兄のアンブローズのことを同時にいつも気にしていて…"兄がもしかしたら好意的に書かせたのかもしれない‘’って…』『新聞記者に?』
『ええ、でも多分そんなことアンブローズ叔父さんはしないわ、
力があったとしてもそれはしないと思うわ、叔父さんは歳の離れた弟ではあったけど父のことを本当に気にかけていたし、本当に愛していたと思うから…
父も叔父さんのことを兄というよりはまるで父親のように感じていたのかもしれないわね、
父は本当はニューヨークへ帰りたかったんでしょうけど…
サンディエゴで自分が少しは受け入れられたように感じたからなんでしょうね、暫く棲むことにしたの、
でも理由はそれだけじゃないわ、
思わぬ出逢いがあったから…』
『お母様ね?』
『そう…』
エミリーの話すふたりの出逢いは彼女が語るとまるで自分とは縁の無い遠い国での誰かにまつわる話のようだった。
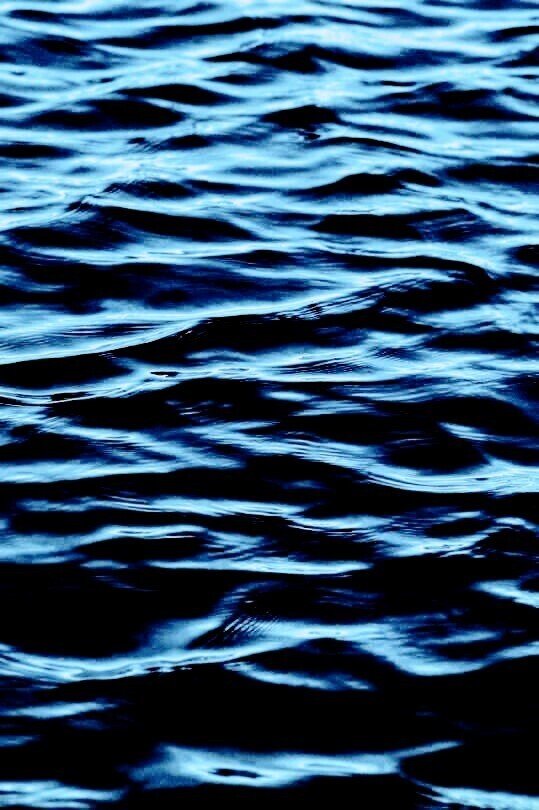
それは遠い遠い昔、
まだ日本人の留学生が珍しい時代でもあったという。
エミリーの父はニューヨークから、サンフランシスコ経由でLA、
そしてサンディエゴへと向かった。
当時のロサンジェルス空港の外国人搭乗口にはalien''エイリアン"という文字がくっきりと緑色のネオンで記されており、まだそのようなSF映画が公開などされるより遥か昔のことなので誰もがそんなことなど気にもかけない時代だった。
青年はありとあらゆる国を渡り歩いた旅人だったというのに飛行機が大嫌いだった。
気圧で耳は痛くなるし機内食も不味い、ファーストクラスの席を兄がとってやろうとしても青年は頑なに断った。ファーストクラスが墜落した時、一番死亡率が高いんだと彼は言った。
死亡率の高さだけじゃない、
遺体の損傷の度合いも高いと聴く、ウェルダンのステーキのように黒焦げになって発見などされたくないというのが彼の詭弁だった。
LAからサンディエゴまで飛ぶという小さなミニジェットのような可愛らしい飛行機を目の当たりにした時、青年は呆気にとられたと同時に不安にもなった。
『まるで自家用ジェット機だね、』するとプロペラの傍にいてテイクオフ前の総点検をしていたエンジニアの男達の中のひとりが、油まみれの手袋に握った工具で小型飛行機を指し示すとこう言った。
『サンディエゴ行きのこの小さな飛行機を見てみんな笑うんだ、
笑うしかないんだろうな、
おいおいなんでこんなにちっさいんだ?て聴いてくる奴も居るけれど、そんなこと俺に聴かれても知ったことか』彼はイギリス青年の肩を叩いてこう言った。
『自家用ジェットだなんて言ってくれたやつぁあんたが初めてだよ、
嬉しいね』
『あんまりキュートで乗るのが不安になるがね、こんな飛行機に乗るのは僕は印度以来だよ、まあ、あれはセスナだったが…。
やぁ綺麗なスパナを持ってるな、
それって』と青年は言ったがその先の『僕は工具をモデルに絵を描いたことがあるんだ』
と言う言葉は敢えて飲み込んだ。
その絵は様々な工具がクローバーやタンポポやルピナスの咲く野原に何故か散乱している絵だった。
メガネレンチの円の間から野生のムスカリが咲き、傍らには聖書が半分に途切れて描かれてあった。
『スパナ?…
ってことはあんたはイギリス人か、アメリカじゃスパナなんてなかなか呼ばないよ、アメリカじゃスパナはレンチだ
だけどこれはレンチじゃない、
これはプライヤーだ、
これをレンチと思うだなんてあんた相当機械や工具には疎いんだな、
男ならレンチとプライヤーの区別くらい一目瞭然だろう?あんたもしかして、車の修理も自分でやったことないんじゃないか?』
青年が眉根を寄せていやな顔をしても、初老を既に過ぎた感じのする小肥りの修理工は人懐っこくて尚且つ馴れ馴れしい。
『そうだな…確かに私にはそのようなことは出来ない』
よく日に焼けた赤ら顔の老人は
『そりゃあ勿体無い、誰かに習うといい、善良なアメリカ人にね、
そんなやつぁサンディエゴ中どこにでも居るよ』
と言って彼は腰に下げた汚れ切った革の工具入れから大きな銀色の工具を取り出すと自慢気に語った。
『これがレンチだよ、
正真正銘のレンチだ、
コンビネーションタイプって言ってね、オープン・エンド・レンチ16ぶんの9インチ、
片方でボルトを絞めてもう片方はこの鋭い嘴のような部分でボルトの摘まみの部分を動かしたりするのに使うんだ。あんたの言う通りこういった工具類は確かに綺麗だ、
クロムバナジウム銅製だよ、
しかし、工具に興味を示すくらいならもう少し勉強してからにしたほうがいいな坊や、お前さん自分の車のタイヤ交換も恐らくは独りで出来まいて、
アメリカの男は18にもなりゃみんな父親に教えてもらって独りで交換出来るようになっているのが当たり前だがね、
イギリス人はそんな綺麗なカフス・ボタンの選び方や、靴の磨きかたをタイヤの交換の代わりに教わるのかね?

しかしあんたの発音はやっぱり俺から聴けば同じ英語でも全然違うな、アメリカの英語はもっと…』
と男は何か言いたそうに毛むくじゃらの大きな腕をプロペラのように旋回させていたが『リズミカルだし、柔らかいよ、聴いてて耳に心地好いんだ、中にはブロークンだなんて呼ぶ連中も居るそうだがな』
『そうか、それは失敬したな、
ずいぶん訛りがこちらに感化されて少しはなめらかになってきたかと思っていたんだが』
『いや、少し固いよ、あんた達はcan(キャン)でなくcan(カン)って発音するだろう?
しかし道理でお上品だと思った、
あんたはじゃあ、あれかね?
アパートメントをフラット、
サブウェイをアンダーグラウンドだなんて国じゃ呼ぶのかね?』
それに対して青年はまるで答えなかった。
レンチもろくに見抜けないまま、
知ったかぶりで専門家に問うたのがそもそもの間違いだったし、だいたいこのオヤジは些か喋り過ぎる。
『サンディエゴへは観光かい?』
懲りないカリフォルニア焼けのオヤジは質問をやめない。
悪気は無いし青年にただ興味があるだけなのだが、彼にしてみればそんな興味本位の目を張り巡らして質問責めにされるのは些か苦痛だった。
『サンディエゴへは兄の紹介で仕事で行くところなんだ』
『いいところさ、
イースト・コーストが好きな人にはウェスト・コーストはのどかではあっても垢抜けない街と映るかもしれないがね、一年中温暖だし雨がほとんど降らないから乾燥はするが、
ニューヨークに比べたら治安もいいほうだ、フルーツも海の幸も旨い、
サンディエゴのアボカドを食えば、よそじゃもうアボカドは食えなくなるに決まってる、何しろニューヨークなんかとは鮮度が違うよ』
『そうなの?』
と生意気なイギリス青年はたいして興味を示さずに、ハットをかぶり直すとカリフォルニアでは嫌味にしか見えないラベンダーグレーのスーツでステッキを握ったまま、中は8人も乗れないのではないかというほど狭くて小さなどこか埃っぽい飛行機へと乗り込んだ。
乗り込む時、彼は言った。
『空気が悪いな』
彼はいきなりカリフォルニアに着いた途端、ヤング・アメリカンならぬオールド・アメリカンの先制パンチを浴びたような思いになって早くも不愉快になっていた。
せっかくはるばる来たというのに、サンディエゴもあまり期待するようなところじゃないのかもしれないなと彼は思った。
サンディエゴに到着後、彼の荷物が空港に何故か届いておらずあと2、3日お待ちくださいとの空港からの説明で彼は仕方無く迎えに来ていた兄の友人でDJをやっているというブライアンの車に乗り込んだ。
『こんなことはよくあることなんだ、アメリカ人はだらしがないから』と言った英語がイギリスの発音であることに青年ははっとした。
『カリフォルニアにアメリカの友人がいるとアンブローズが言っていたのでつい貴方はアメリカ人かと』『確かにこちらに棲んでもう長いんでね、まぁ言ってみれば半ばもうアメリカ人のようなものだ、
今日は君の兄さんに頼まれて車で来たんだが、カリフォルニアといっても広い、
僕はロサンジェルスのサンタモニカに住んでいるんだ。
そこから君のお迎えを頼まれて来たんだ、アンブローズは元気かい?相変わらず独身なの?
彼はモテると思うのに』
『相変わらずモテてはいるようだけど女性がもしかしたら嫌いなのかもしれないな、男が好きというわけでも無いんだが…
ああそれから兄はとても元気だよ、
僕のことで頭を痛めてる以外はね』

個展を開くホルトンプラザへと真っ先に寄りたかったが、当面2ヶ月近く住むアパートメントを彼は紹介された。アルカホン・ブルバードというお世辞にもあまり治安の良さそうとはいえない場所にあるアパートメントではあったものの、ドアも窓もオートロックの三階で、ガレージもアパートメントの厳重な警備の敷地内にあるというので、慎重な兄のアンブローズから許可がおりた場所だった。
備え付けの家具があるのだからあまり綺麗とはいえなくとも文句は言えないなと青年は思った。
自分だって働いて貯めた金は持っていたが、兄がそれは出来るだけ使わずに貯めておけ、これくらいは私が面倒は見れる、兄が何故自分をここまできめ細かく親のように良くしてくれるのかを彼は頭では理解しているつもりでもそれについて深く考えたくはなかった。
アパートメントを出て近所の観察を兼ねてふたりは街をそぞろ歩いた。
ニューヨークほどではないが、ストリート・ガールがたまに声を掛けてくる。
『ここはダウンタウンの一部と似たとこがあって、つまり割りと性犯罪が多いんだ、君も美しいから気を付けたほうがいいかもしれないぜ』
『僕は女性じゃない』
と青年は笑いながらふと、"ガーネット・ストリート''という標識のあるファーマシーの前で、雨も降っていないのに何故だかその軒下に立ち、雨宿りでもしているような様子の異国の少女に視線が止まった。
というより釘付けになった。
少女は中国人か日本人か、
長い真っ直ぐの豊かな黒髪は腰にまで届きそうだ。

柘榴(ざくろ)のような深い赤茶のミニ丈のワンピースを着て足首で折り返す白いソックスの上から足の甲にストラップが一本通る黒の革靴を履き、サンディエゴには似つかわしくない服装がかえって新鮮に青年の目には映った。
大きな黒い瞳は心許無げに夕暮れに差し掛かろうとしているオレンジと淡い薄桃いろに染まった空を眺めている。
少女の瞳から次の瞬間、夕陽に染まったピンクゴールドの涙が零れ落ちその頬を伝うのを彼は呆然と立ちすくんで眺めた。
『おい、どうした?
中国娘にやられたのか?連中見た目は幼げだが意外とフォクシーだっていうぜ』
『フォクシー?』
『ズル賢いとこはあってもホットだってことさ、
でも気を付けろよ、ファーマシーの前で泣いてるような女は絶対、
お手合わせ願ったりなんかしたら、ろくなもんじゃないに決まってるんだ、』
『なんで?』
『どうせ病気持ちさ、一見スイートだがフッカーかもしれん気を付けろ』
後ろ髪引かれながらも彼はその場を後にした。
ディナーを食べたあと彼らはブライアンの車で砂漠を貫くハイウェイをひたすらにドライブしてみた。
4月といえどももう少しすればサンディエゴは時計の針を調節しなくてはならない時季サマータイムとなる、
夕陽が傾くのも遅く7時過ぎてもまだ充分に明るい、サマータイムともなれば夜の8時でもまだまだ明るいのだ。
ブライアンが車を走らせている間、ずっと黙っていた青年は急に瞳を輝かせてこう言った。
『見つけた!止まって!
カリフォルニアに来て一番見たかったものを見つけたんだ!』
停車するなり彼は無人の広い道路へと全速力で駆けていった。
『おーいなんだ?どうしたっていうんだ?』とブライアンが言うと青年は生き生きと頬を紅潮させて振り返ると言った。
『見つけた!こいつだよ、
タンブル・ウィード!回転草さ、』そう言った彼の足元には、小さな渇いた枯れ枝や枯れ草のようなものが固くごわごわと密に絡まって、球状となったものがあった。
『昔、テレビの西部劇でよくこいつがコロコロ砂漠の中を走り回ってるのを見て、僕はずっとこれに憧れていたんだ、ガンマンの後ろに風に吹かれて幾つも転がっているのを見て
一体あれはなんなんだろう?って、
ガンマンなんかには目もくれずに、ひたすらこのタンブル・ウィードばかり目で追っていた、
やったぞ!
初めて本物に逢えた!』

『弟は変わっているとアンブローズは言っていたが本当だな』
ブライアンは車から出て煙草に火を点けながら言った。
しかしその言葉にはただ笑顔を見せただけで、青年は嬉しそうにしゃがみ込むと路面の回転草を仔犬か何かに対するように嬉しげに愉しげに、しきりに撫でさすった。
すると渇いた砂漠の風が熱く吹いてきてタンブル・ウィードはコロコロとハイウェイの端の砂漠の奥に向かって転がっていった。
見ると砂漠の向こうには大小取り混ぜて沢山のタンブル・ウィードがまるで青年が追ってくるのから逃げるかのように散り散りになって転がっていった。
青年は砂漠の奥へ奥へとタンブル・ウィードを追って、驚くほど遠くまで駆けていった。
その為、俊足な青年の姿は見る見る
小さな点のようになっていった。
驚いたブライアンの叫ぶ声が、遠く青年の耳にまで風に乗って聴こえてきた。
『おーい!馬鹿な真似はよせ、
子供じゃないんだから帰ってくるんだ!そんなもの、こっちにあと二ヶ月も棲んでいたら、いやでもまたお目にかかれるさ、
そいつら季節風で街中にまで到来してくるんだから、別にそう珍しいものじゃないんだよ!』

タンブル・ウィードを追いかけながら彼は何故だかときめいていた。
何故だろう?と彼は思った。
目の前が薔薇いろに見える、
ああなんて陳腐なんだ、
この陳腐さはもしかしたら…
と彼は走りながら独りで笑った。
希望が見えてきたような不思議な気持ちに今にも彼の肩甲骨から翼が生えそうな気分になった。
テイク・オフって気分だと彼は思った。
そして走りながら彼は空を見上げた。その空にあのピンクゴールドの夕陽を映した、涙にくれる東洋の少女の面影が浮かんだ。
彼は思った。
『彼女にまた逢えるだろうか?』

ガーネット・ストリートという治安の悪い小汚い街角で見たガーネット・ブラウンの服を着た長い黒髪の少女、また逢えたらいいのに、
いや、なんだかきっとまた逢えるような気がするんだ』
彼はまるで気がふれたように笑いながら、ブライアンが必死になって止めるのも聴かず、どこまでも果てしない砂漠を走っていった。



To be continued…
