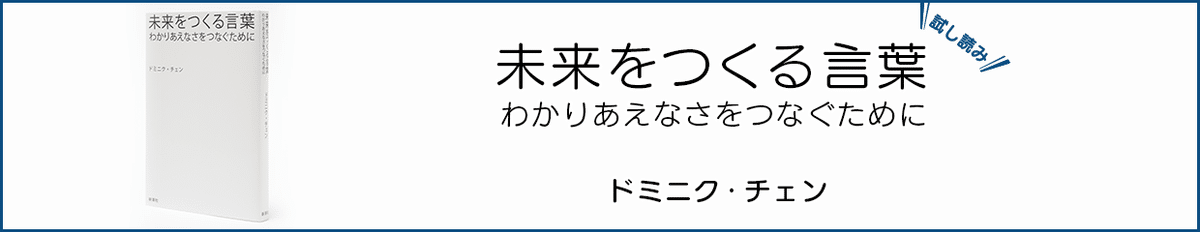2010年代とはどんな時代だったのか?(No. 850)
考える人 メールマガジン
2020年1月30日号(No. 850)
入江敦彦さん「御つくりおき」が『京都でお買いもん 御つくりおきの楽しみ』として発売!
入江敦彦さんのセンスが光るオーダーメイドのお買い物と楽しい交友録が綴られた人気連載「御つくりおき」が、『京都でお買いもん 御つくりおきの楽しみ』として発売されました!
〈京都では、老舗や職人さんと仲良うしましょ。〉
こういうのほしいな。愛用の品が壊れた。そんなとき京都人は専門店に“オーダー”する。ポットの割れた蓋。ひと振りで京が香り立つ魔法の粉。極上のごはんのためのおひつと茶碗。百年使えるトートバッグ。特別なシャツ、鞄、帽子、靴――日常を輝かせるささやかな贅沢。京都エッセイの名手による、暮らしの楽しみの極意。
ぜひお読みください!
2010年代とはどういう時代だったのか――ポップ・カルチャーから探る『2010s』試し読み!
レディー・ガガ、ラップミュージック、Spotify、Netflix、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)、『ゲーム・オブ・スローンズ』など、2010年代のポップ・カルチャーを、宇野維正氏と田中宗一郎氏が総括する新刊『2010s』(2020年1月30日発売)。音楽から映像作品、メディアに至るまで、〝社会の映し鏡〟としてのポップ・カルチャー、その進化と変容、時代精神に迫ります。
同書の制作意図や動機、内容についてまとめた、宇野氏による「はじめに」を掲載しました。
来週には「第1章 レディー・ガガとピッチフォークの時代」も公開します。お楽しみに!
いまもっとも注目すべき情報学者、ドミニク・チェンの『未来をつくる言葉』試し読み&サイン本プレゼント!
「考える人」で連載していたドミニク・チェンさん「未来を思い出すために」が、『未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために』と改題して刊行されました!
〈この人が関わると物事が輝く! 気鋭の情報学者がデジタル表現の未来を語る。〉
ぬか床をロボットにしたらどうなる? 人気作家の執筆をライブで共に味わう方法は? 遺言を書くこの切なさは画面に現れるのか? 湧き上がる気持ちやほとばしる感情をデジタルで表現する達人――その思考と実践は、分断を「翻訳」してつなぎ、多様な人が共に在る場をつくっていく。ふくよかな未来への手引となる一冊。
「考える人」では、本の冒頭を一部試し読みできます。
また、刊行を記念して、ドミニク・チェンさんのサイン入り『未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために』を抽選で3名様にプレゼント。締め切りは2/11(火・祝)23:59!
ご応募はこちらから↓
アクセスランキング
■第1位 吉川トリコ「おんなのじかん」
9.「この人の子どもを産みたいと思った」
なぜ人は子どもを欲しい/欲しくないと思うのか。「欲しい」と思う人でもその理由はさまざま。気になるけど、話しづらいテーマに率直に向き合う吉川さんの連載が、今回も初登場1位!
■第2位 東浩紀「アクションとポイエーシス」
「新潮」先月号に掲載された東さんの論考「アクションとポイエーシス」がネットでも大きな反響を呼び、引き続きランクイン。「あいちトリエンナーレ・その後」特集を掲載した今月号の「新潮」も好評発売中です!
■第3位 ドミニク・チェン『未来をつくる言葉』試し読み
はじまりとおわりの時
〈この人が関わると物事が輝く! 気鋭の情報学者がデジタル表現の未来を語る。〉いま注目の情報学者ドミニク・チェンさんの新刊試し読みがランクイン。連載時にはなかった、書き下ろしですので、連載当時からの愛読者の方もぜひお読みください。
最新記事一覧
■津村記久子 さん「やりなおし世界文学」(1/24)
(14)普通の女と普通の男――ロレンス 『チャタレイ夫人の恋人』
今回は取り上げたのは、あの『チャタレイ夫人の恋人』! 津村さんの感想は「読んでよかった。なんか元気出たわ」。〈最後の一文は感動的で笑える。(略)親身になってくれる気のいい人みたいな小説だった〉。
■飯間浩明「分け入っても分け入っても日本語」(1/27)
「ブドウ」
辞書編纂者としてあちこちに引っ張りだこの飯間さんによる、身近な言葉の語源を探る連載、約1年ぶりの更新です!!
飯間さんが「意外で面白い語源のチャンピオン」だと思う日本語は、なんと「ブドウ」! そこには確かに浪漫がありました。
■岡ノ谷一夫「おかぽん先生青春記」(1/28)
ガラ子との遠距離交際
生物心理学者・岡ノ谷一夫さんの青春記。ひとりでガラパゴス諸島に行くほど行動力と好奇心旺盛な「ガラ子」との距離を縮めたおかぽん青年。ついに遠距離恋愛を始めますが、ガラ子が行くのはなんとバヌアツ!
■猪木武徳「デモクラシーと芸術」(1/29)
芸術に付きものの真贋論争。では、音楽のオリジナルとは何か。モーツァルトの曲のオリジナルは、作曲家本人がピアノ・パートを弾きながら指揮した「弾き振り」演奏だけなのか?
■村井理子「村井さんちの生活」(1/29)
答えが出ないことなんて当たり前だと思っていた
悩みに答えが出ないなんて当たり前。アタマではわかっていても、いざ直面してみると……子供の成績も琵琶湖の水位も悩ましい! そして、いつのまにか子どもは自分の足で先を歩いていくものですね。
編集長のお気に入り◎坪内祐三『昼夜日記』
坪内祐三さんが1月13日に亡くなってから、自宅にある坪内さんの本『古くさいぞ私は』や『昭和の子供だ君たちも』などをぱらぱらと読み返しているのですが、ああ、この本の中に坪内さんがいるな、と思わず再読したのが『昼夜日記』でした。
この本については1年半前のメールマガジン790号にこんな風に書いてます。
10月23日(火)
坪内祐三さんの『昼夜日記』を読む。
「本の雑誌」で連載中の「読書日記」と、「小説現代」で2016年9月号まで連載していた「酒中日記」を合体させたもの。2014年6月からの日記は、二段組みの上段は昼の「読書日記」、下段は夜の「酒中日記」と別々のテクストが並んでいて、坪内さんの人生の二つの側面が分裂して描かれているような不思議な印象がある。
もともと私は、人の日記を読むのが大好きなのだが(書くのはそれほど好きではない)、特に坪内さんの日記本は楽しみにしている。興味があることが変わったり、行く店が変わったり。古い日記をたまに読み返すと、前に読んだときには気づかなかった細部に気づく。新宿や神保町の街が頻繁に描かれる。時代の定点観測だ。
再読して、つくづく、今後、こういう日記をかける人はもう出てこないだろうな、と思いました。
坪内さんという人は一つのジャンルのようなもので、これだけ広範囲の関心で古い雑誌を読んだり、ナイト・クルージングして飲み明かしたりする人は、ほかにいません。マニアックな知識がありながら、反射神経がよくて、顔が広い。マニアックなのに、狭いところにいかず、どこかメジャー性がある。22日のお通夜に参列してきましたが、ものすごい人で、あれだけ焼香に行列ができているのを初めて見ました。
そして、個人的には、本当に文芸雑誌を細かく読んで、よくお電話くださり、企画を褒めてくださったり、注意してくださったり、間違えを指摘してくださる親切な人でもありました。
今はとにかく悲しいだけですが、きっとこの先、数年の時間をかけて私たちは、坪内さんという大きな書き手、そして何より大きな読み手の不在を何度も実感することになるでしょう。
突然の悲報だったので、「小説新潮」の最新2月号には、いつもと同じように連載「玉電松原物語」が載っています。週刊文春の長期連載「文庫本を狙え!」をはじめとして、かなりの数の連載がいきなり急にストップしてしまいました。残酷なことです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■note
https://note.com/kangaerus
■Twitter
https://twitter.com/KangaeruS
■Facebook
https://www.facebook.com/Kangaeruhito/
Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.
発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71
新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/
メールマガジンの登録・退会
https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いいなと思ったら応援しよう!