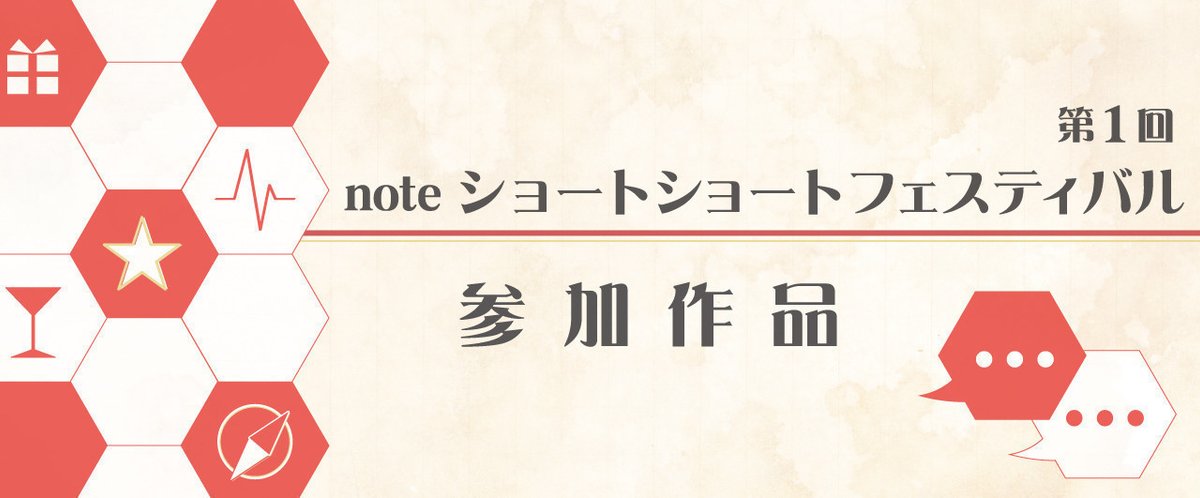
ファインダー越しの恋
満員電車は嫌い。
いつもなるべく早めの電車に乗って、混んだ車両は避けてきた。理由は単純だ。痴漢に遭いたくないからだ。
高校生になって毎日電車を利用するようになってからはほぼ毎日、時間や乗る場所を変えても被害に遭った。声は出せなかった。大学生になり、制服から解放されると何の色気もないパーカーやTシャツとジーンズといった組み合わせばかりを着るようになった。髪も常に短くし、女の子らしく見えないよう振る舞った。
それでも――。
痴漢には遭うし、交際した男の子達は皆大抵キス以上のことを求めてきた。
だから私の恋愛はいつも長続きしなかった。周りの女の子達には、「美希って男をとっかえひっかえして、いいご身分よね。」などと陰口をたたかれた。ほざいてろ!――そう思った。
私は加倉井美希。25歳。都内のデザイン事務所の一般事務として勤めるようになって3年。最近やっと仕事にも慣れてきて、浅い人付き合いにも慎重になりつつも少し余裕が出てきた。
休日には読書をしたり、溜まったビデオを観たりすることが多かったのだが、その日はあまりにも気持ちの良い天気だったので、昔買って押し入れに仕舞ったままだった真っ赤なコンデジを引っ張り出し、近くの公園に散歩がてら行ってみた。
ツンと冷えた澄んだ空気にくっきりとした青空。葉の落ちた広葉樹林。足元の落ち葉をサクサク言わせながらカメラを手に冬の日曜の遅い朝の公園を歩く。
犬の散歩をする人。ジョギングをする人。子どもとキャッチボールやシャボン玉で遊ぶ親子連れ。公園の景色をスケッチブックに描く人――ファインダー越しにそれらを眺める。
趣味……と呼べるほどのことではなかったが、こうしてカメラのファインダーを覗いていると、日々すり減らした神経が、ささくれだった心の傷が、静かに修復されていくのが分かった。
その公園に写真を撮りに行くのが週末のルーティンとなってしばらくたったある日の事。
今日は夕日を撮ろうと思って昼下がりからの外出だった。陽が傾いてくると一気に冷えてくる。
「ふぅ~。寒くなってきた。」
ひとしきりシャッターを押して気が済んだ私は、荷物をベンチに下ろして鞄から温かいコーヒーの入った水筒を取り出した、その時だった。
突然、後ろから何者かに抱きつかれて手で口を塞がれ、ベンチの後ろの繁みの方へと引きずられた。
薄暗くなりかけていた公園には、ほとんど人影はなかった。ベンチに当たって下に落ちた水筒のフタがカラカラと音を立てた。
(ヤバイ……)
声は出せなかったが、必死に抵抗していると
「コラ!!何をしているんだ!!」
怒気を含んだ低い男性の声が辺りに鋭く響く。
私を押さえつけていた男の手が一瞬弱まった隙に、私は男を突き飛ばし、間一髪で離れることができた。
声は私達から少し離れた所からだった。その声に驚いたのか、男は一目散に逃げて行ってしまった。捕まえることはできなかったが、おかげで私は助かった。
「お嬢さん、大丈夫ですか?ケガはありませんか?」
「……はい。ありがとうございます。大丈夫です。」
やや放心気味に私が答えると、その男性はとてもホッとした様子でふわっと顔を柔らかくほころばせて、
「それは良かった……。」
と言った。
瞬間、――どうやら私は恋に落ちたらしい。
よく見ると、私の父ほどの年齢のその男性(後で知ったが、前島紘三さん。61歳)は、しかし体つきは逞しく、いつも穏やかにその公園の片隅で絵を描いていたのが、私の撮った何枚もの写真から分かった。
それからというもの、名も知らぬその男性を、気づくと私はいつもファインダー越しに見つめていた。絵を描く彼。落ちているゴミをさり気なく拾い、自分で持ってきたスーパーの袋にそっとしまう彼。ケガして衰弱した子猫を抱えてどこかへと(おそらく動物病院に?)連れて行った彼……。
彼がとても優しい顔で微笑むのを私は知っている。
それは――私に対してではないけれど。
(了)
いいなと思ったら応援しよう!

