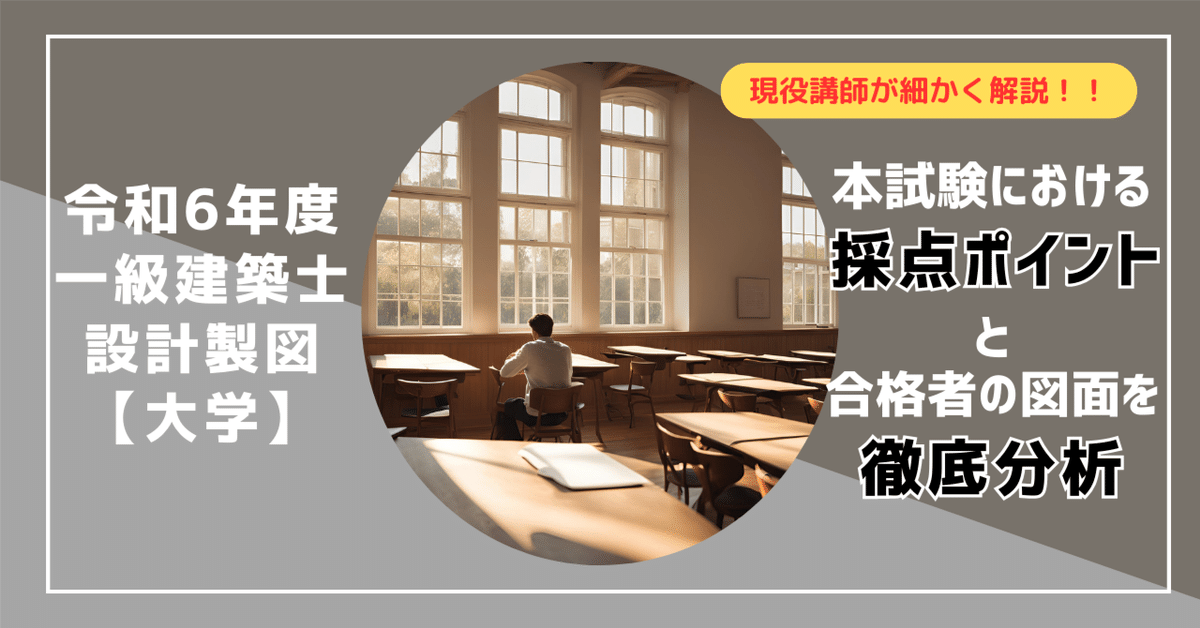
【一級建築士】令和6年度 設計製図本試験における採点ポイントと合格者図面の徹底分析【大学】
こんにちは、かねっつです。
12月25日に令和6年度設計製図試験の合格発表が発表され、新たな一級建築士が誕生しました。まずは受験生として挑戦した方々、本当にお疲れ様でした。
今回は建築士法改正以降、史上最悪の全体合格率8.8%を叩き出した令和6年度の設計製図試験について分析していきます。
※この無料記事を読み終えるのに、約20分かかり、有料記事を読み終えるのに、約55分かかります。
ココナラでは、一級建築士設計製図の添削を始めました!
この時期限定で定期購入をしていただくと、2回目以降から10%OFFになります。
詳しくはコチラをチェック!↓
■ランクⅠになるヒントは採点のポイントにある
国土交通省から発表された合格基準等については、コチラからダウンロードできます。
採点のポイントを細かく分析してみます。
(2)建築計画の②では設計趣旨にもあった『ユニバーサルデザイン』が採点のポイントとして挙げられています。ユニバーサルデザインとは、障がいの有無に限らず可能な限り誰もが利用できるデザインを指しますが、設計製図試験において1番メジャーなのは、車椅子駐車場からの移動円滑経路を明確に計画することでしょう。他にバリアフリートイレは介護者も介護しやすいように、出入口の扉を自動扉とし、使う人に寄り添った計画としたり、JIS規格のピクトサインを用いて障がいの有無に限らず視認性のよい計画としたなど、学生や職員のみならず、多様化した建築計画となっているかが重要です。
(3)構造計画では、①基礎免震構造と②講堂の構造計画が採点ポイントでした。基礎免震構造は課題文冒頭でも述べられており、必要なクリアランスが確保されているか、免震構造に誤りがないかがポイントとなっています。断面図に免震基礎が表現されていても、計画の要点(2)で正しい断面詳細が表現できていな(或いは、断面図と整合性がとれていな)ければ減点対象であることは明白です。
次に講堂の構造計画ですが、多くの人は無柱空間で計画したかと思います。無柱空間を構築するためにPC梁で計画できているか、断面図においては適切な梁せいで計画されているかが採点のポイントとなります。また天井仕上げについては、面積が200㎡を超え利用者が日常利用する室となるため、特定天井を採用することが適切と言えます。適切なので必須ではありませんが、計画の要点(3)では講堂の天井等落下防止対策について問われているため、積極的に採用することが好ましいです。冒頭の設計条件(3)で『大地震等の自然災害が発生した際に〜(省略)〜帰宅困難者の一時滞在に配慮した計画』が条件としても求められていることから、講堂の構造計画がどれほど採点に影響されたかが分かります。
(4)設備計画でも、前述した帰宅困難者が安全に一時滞在できるよう配慮した計画がポイントとなっており、大地震が起きても設備が継続的に機能できることが重要です。同じく(4)設備計画の②では、屋上に設置する設備機器等の計画が採点のポイントとなっています。空調システムに必要な熱源機が計画されているか、BCP対策として太陽光パネル等を積極的に採用しているかがポイントとなります。
これらの採点ポイントは、計画の要点等ともリンクしています。つまりこの採点ポイントは如何に建築士として提案力があり、ランクⅠに上がれるかが求められいます。惜しくもランクⅡやⅢになった方で、プランニングや重大な不適合のミス等をしていない方は、計画の要点等の知識不足や提案力不足が要因で惜しい結果となったと思います。
■ランクⅢとⅣを合わせて約72%
受験生だった方は既にご存じだと思いますので、合格率について深掘りしませんが、建築士法改正から過去最低の合格率を叩き出しました。これは一次試験の学科合格率が高かった(23.3%で昨年から+7.1%)ことや『大学』という用途が初出題であるため、模範回答に前例がなく、採点にも大きく影響したのだと思います。
ただ、過去問から対策が可能なものもあり、例えば令和6年度の課題発表時で『大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。』と追加されましたが、これは平成27年の本試験で計画の要点等でも同じ文言がありました。そしてこの年は、基礎免震構造だったこともあり十分な試験対策は可能でした。
この合格率の結果で注目すべきところは、ランクⅢとⅣの割合です。ランクⅢが23.9%、ランクⅣが48.0%、合わせて約72%と非常に多い結果です。建築士法が改正され、実務経験を有していない大学生等も受験できるようになったことから、採点がより厳格化されたと言わざるを得ません。ここでよりランクⅠに上がるためには、プランニングと建築基準法の遵守に加え、知識と提案力をどれほど詰め切れるかが勝負だと思います。まさにこの試験の肝です。
■階段は合否を左右する
採点結果区分の設計条件に関する基礎的な不適合に『階段の不成立』が追加されました。この不適合は、令和4年度にも挙げられています。設計製図の試験ではバリアフリーを考慮して計画することは当然ですが、設計趣旨でユニバーサルデザインに触れていることもあり、例年よりも重点的に採点したのでしょう。
また段床型の講堂とするため、最上段と最下段で天井高が異なります。講堂を1層のみで計画した場合、階高を基本の4mより高くしないといけないため、階段の蹴上と段数にも影響してきます。採点項目として挙げられているということは、採点官が段数を数えて適法な階段計画となっているかを確認しているということが考えられます。もしくは、階高4.5mを超えているのに1.5回転と平面図に図示していなければ、蹴上寸法が不適合となるため失格と判断しているのだとも考えられます。
いずれにしても、階段の作図を明瞭に表現する必要があり蔑ろにすることはできないということです。エスキスで躓く前に、早い段階で階段のパーツ練習をすることが大事です。
■正直言います。合格者は少なかったです
ハッキリここで言います。合格者4人の25%でした。自分の中では現実的に考えたら30〜35%かなってぐ思ってたから、正直ここ最近の講師人生で1番悔しいです。年末年始で復元の分析してnoteにまとめます。ほんとに悔しいの一言。そもそも全員合格目指してるのに半分にも満たないのは情けない。戒める。
— かねっつ。 (@kkiknd928) December 25, 2024
少し自分自身の話をさせてください。
悔しい思いをどこかに吐き出したくて、X(旧Twitter)でもポストしました。今年は昨年の反省を活かし、担当受講生とのコミュニケーションを密に取るよう心がけ、どんな試験問題が出ても対応できるように事細かく指導していました。もちろん作図用紙の赤チェックも怠りませんでした。採点会を終えて「今年は7人ぐらいかな…」と感じていましたが、結果はそれを下回り言葉にならないくらい悔しい思いをしました。
担当校舎の教務課長は「校舎としてはいい出来だし、短期生でこの結果は悪くない」と言われたものの、私の目標は担当受講生全員合格(敵わないとしても8割合格)ですから、全く満足していません。どれだけ策を練って指導したとしても、この結果は力不足の指導力そのものの結果だと思っています。
いくら指導を改善したとはいえ、結果として反映されないのであれば指導力はそれまでです。私が講師をやっている理由が【建築士を目指す受講生の全員合格】である以上、まだまだ改善しなければなりません。今回の記事は、そういった想いも込めて例年よりも、より細かく分析した記事にしています。
■合格者の共通点は、すなわち提案力
合格した受講生さんの4人中3人は初受験者、1人は2回目の受験でした。
最低限守るべき条件(要求室が欠落していない、免震計画に誤りがない、アプローチ計画に問題がない等)以外で、合格した受講生さんの特徴と、惜しくも不合格だった受講生さんと比較して、気づいた部分と特別違った作図表現(太字で表記しています)をしている部分を挙げてみました。
講堂を1階にし、長辺を長手側に計画している。
ホワイエを計画したり、広いホールを形成している。
5階建てで計画している。
EVホールを、広く計画している。
入り組んだ廊下形状としていない。
教室と研究室を、東西の道路面に向けて計画している。
惜しくも不合格だった受講生さんとで、大きく違っていた計画を挙げてみました。しかし私自身、この6項目が合格に直接結びついた大きな要因とは思っていません。この6項目は、最低限建築士として備えるべき知識及び技能の提案力(以下、建築士としての提案力)をしなければならない項目だと思います。
具体的に説明します。
例えば階数の計画ですが、例年階数の指定がなく要求室の面積から推測して自分で階数を指定しなければなりません。設計製図試験では作図上高層階にすると、断面図が収まらなくなる(平面図と被る)ことや道路(隣地、北川)斜線に抵触する恐れがあるため、4階か5階が最も多く出る標準回答の階数です。
ただこの理由とは別に、建築士としての提案力として高層階にしない理由はもうひとつあります。それは、経済性への配慮や工期の短縮、使用する材料を少なくしCO2排出の削減に貢献するなど、中低層建築物にした方が施工性や構造部材のメリットが多いからです。つまり高層階で計画するということは、ワンフロアの計画に余裕が出来て、要求室の計画も容易になるが、主要構造部の断面積が大きくなったり、基礎が深くなるデメリットもあるということです。こういったことを鑑みると、例え課題条件を満たしていたとしても、建築士としての提案力には欠けてしまうと判断されるのではないかと考えます。
先ほど挙げた6項目は、課題文の中にヒントはあるものの、明確に課題条件として求められてはいません。だからこそ必要最低限の条件を満たした上で、建築士としての提案力が試されているのです。
この建築士としての提案力は、どれだけ建築計画において知識をもっているかが重要です。実務経験のない大学生等の受験者数が増えたことで、より厳格な採点が行われていることは明白です。プランニングと法令遵守は、出来て当然であり、これからの試験対策は提案力で差がつきます。
無料記事ではここまでですが、有料記事ではこの6項目をベースに、実際の担当した受講生さんの復元図を用いて、今年度の採点ポイントと交えながら深掘りをしていきます。惜しくも不合格だった受講生さんにも触れながら、何が原因でダメだったのかも分析しています。
今年度試験の振り返りをしたい方や来年度に受験を控えている受験生の方は、是非読んでほしい記事です。
※お試しとして、途中まで無料で読めます。
noteでは一級建築士の設計製図試験について綴っております。
X(旧Twitter)では建築関係を中心にツイートする他、日常のことも呟いています。ぜひフォローをよろしくお願いします!
フォローはnoteのプロフィール、または下記からもチェックできます!
■採点ポイントを徹底分析
先ほどの合格者にあった6項目と、惜しくも不合格だった受講生さんで何が原因なのかを分析していきます。それと同時に、今回の採点ポイントはどのようなところに隠されていたのかを紐解いていきたいと思います。
・講堂の計画
設置階について、設計条件(3)で『大地震等の自然災害が発生した際に〜(省略)〜帰宅困難者の一時滞在に配慮した計画』とするため、合格者の殆どが1階に計画しています。私が担当した受講生さんの中で1・2層の2層とした方はいませんでした。この図面の受講生さんは、1・2層の2層分とせず1層の階高を5mにしています。そのため階段も基本のカタチ7m×4mの階段としたことで1回転では昇降できなくなる(蹴上寸法が高くなる)ため、階段には1.5回転と表記しています[図解1]。

試験元の標準回答例は、1階のみと1・2層の2層の両パターンで出しています。講堂の使い方が学内のイベント等にも利用され、一時滞在の避難場所として足腰に不自由な高齢な帰宅困難者が、容易に利用できるよう配慮することから、設置階は1階が望ましいと考えられます。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
