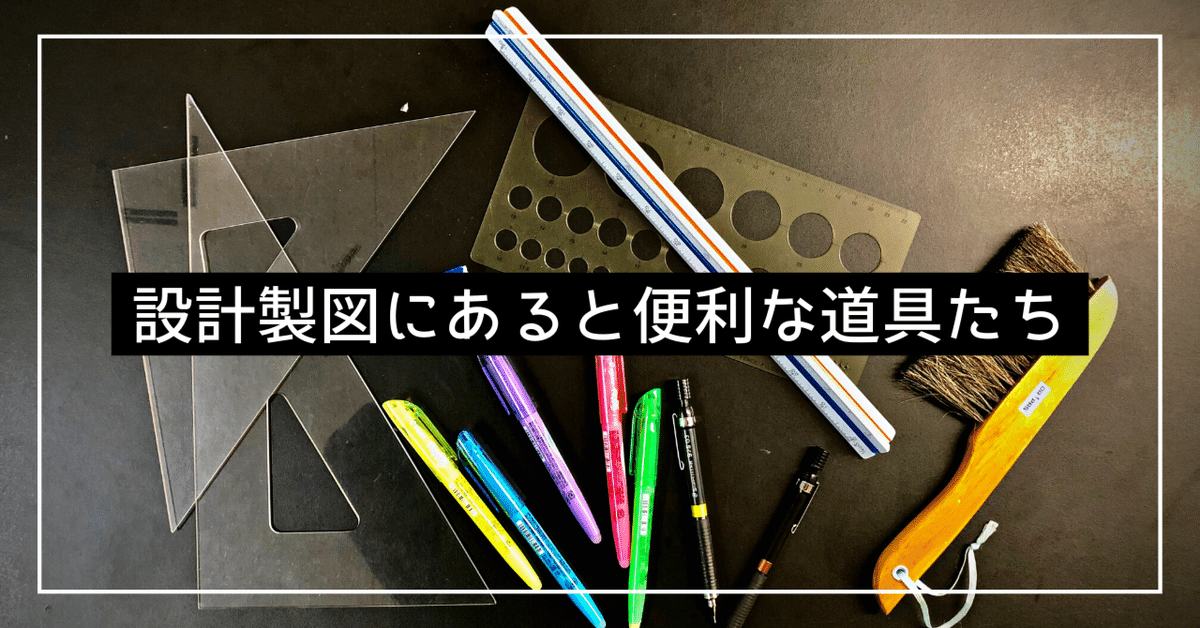
【保存版】一級建築士 設計製図にあると便利な道具たち
こんにちは、かねっつです。
本日もnoteをご覧いただきありがとうございます!
今回は、一級建築士試験の設計製図において揃えておきたい役立つ道具を紹介したいと思います。これを揃えておけば、試験時間内に漏れのない作図ができる道具をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を読み終えるのに、約23分かかります。
設計製図は、車の運転と一緒で・・・
学生時代に授業で設計製図をしたきりというもの、社会人になってからは平行定規すら触っていない人も多いはず。また現役大学生でさえ、CADが主流になっている世の中なので、なかなか手書きの図面を描いていない学生さんもいるはずです。
手書き図面経験者でも、そうでない人も実は一緒で練習していくうちに図面の綺麗さや速さは上達していきます。
では、いち早く上達するにはどうしたらよいか?
その答えは、使い慣れた道具を使用することです。
車の免許を持っている方は、教習所でこんなことを言われたことありませんか?「運転するときは、履き慣れた靴で運転してください」と。(僕だけでしょうか…)
製図も同じで普段から使っている(もしくは学生時代で使っていた道具)を使うことが大事です。道具の持ち具合や筆圧は、自然と身体が覚えています。設計製図では、普段から使い慣れている道具で挑んでください。もちろん新しく揃えるものもあると思います。身体が慣れるまで日々の練習で身体に染み込ませてください。
設計製図で合格に導く道具たちの紹介
ここからは私が実際に使用していた道具を紹介していきます。
製図試験をストレート合格に導いてくれた道具たちです!
1.平行定規

平行定規と言っても大きく分けて3種類あり「マルスライナー」「ドラパスボード」「ライナーボード」に分けられます。機能性に大きな差はありませんが、平行定規の重さが若干異なっていたり、ケースが防水ケースなものがあったりします。それぞれの特徴をご紹介します。
マルスライナー
平行定規の安定性に優れているため、無難な平行定規です。他の2種に比べて重い(本体重量3.2kg程度な)のがデメリットです。ドラパスボード
多くの建築学校が採用しているほど、スタンダードな平行定規です。迷ったらドラパスボードで良いです。ライナーボード
本体重量が約2.5kgという超軽量なのがウリの平行定規です。角度が最大10度までいけるので、座高の低い方にオススメです。ただし、金額が他メーカーに比べて5,000円ほど高いのがデメリットです。
オススメなのは、男性ならマルスライナー、女性ならドラパスボードです。中古品を購入する際に注意してほしいのは、【角度調整に不備がないか】【平行定規の調節ネジがしっかり動くか】この2点は必ず確認してください。
2.シャープペンシル

オススメは、ペンテルのグラフギア500というシャープペンシルです。特徴はペン先が細いため、平行定規に当てやすくブレない線を描くことができます。持ち手の部分が六角形なので持ちやすく、長時間の利用でも手が疲れないのが利点です。私は3種類のシャープペンシルを持ってますが、0.4は使いませんでした。筆圧が強い方は、0.7を2本と0.5を1本で十分です。それぞれの使い分けについては、別のnoteでお話ししたいと思います。
3.シャープペンシルの芯

シャープペンシル同様、ペンテルのアイン替え芯です。基本、替え芯はシャープペンシルと同じメーカーのものを選んでください。他メーカーだと、うまく芯が出てこなかったり、ノックしているときにペンの中で折れることがあります。また、アイン替え芯の良いところは筆圧の強い人でも折れにくいことです。芯の内部は『シュタイン構造』という蜂の巣のような構造になっており、芯全体を支える役割になっています。設計製図試験で大事なのは印象度です。印象度は、躯体線を濃く仕上げることや細線をハッキリ描くことが重要で、それに適しています。オススメの芯の濃さは、【2B】か【B】です。HBはオススメしません。
4.消しゴム

一般的な消しゴムで十分です。ただ、試験会場には最低でも5個持っていくことをオススメします。私の知人が、試験当日消しゴムを10個持っていき、試験終了時には5個になっていたぐらい慌てていたらしいです。モノを探す、拾う動作だけでも大きなタイムロスになりますので、多めに準備しておきましょう。
写真の中でオススメなのは、1番右に写っているノック式消しゴムです。作図中の細かい部分や、大きな消しゴムで消すと余計なところまで消えてしまうのを防ぐのに効果的です。道具の中に、字消し版というのがありますが、ノック式の消しゴムさえあれば字消し版は不要です。むしろ試験で使っている人をあまり見かけないです。
5.ノック式蛍光マーカー

課題分の読み取りや1/400のエスキスで使います。大事なのは、ノック式ということです。蓋付きとの違いは、課題文の読み取りの時にチェックのタイミングによって色分けをするのですが、その際にいちいち蓋を取ったり嵌め直したりする手間が省けるということです。課題文の読み取りについては、別のnoteでもお話ししたいと思いますので、そちらを参考にしてみてください。5色は必ず用意してください。(資格学校で色を指定することもあります)課題条件が多いと1/400の中で色が足りなくなり、私のように色が増えます。作図の際にエスキスが見やすい色を選んでください。
6.テンプレート

円、楕円、三角形、四角形のみが描ける型板でなければなりません。NGなテンプレート例を下記に記載しておきます。
家具、衛生器具、建築部位、建築設備の描けるもの
円、楕円、三角形、四角形の組み合わせによって家具や衛生器具等が容易に描けてしまうもの
数字やアルファベットが描けるもの
点線、破線、一点鎖線等が容易に引けるもの
また、目印としてマークやシールを貼っているのもNGになります。マークについては見つかるか微妙なとこですが、万が一チェックされても没収されないようにしておきましょう。私は総合資格に通っていたので、写真の水色にテンプレートを使っていました。結構いい金額するのですが、3年近く使っていても現役です。意外と物持ちがいい…。
7.ドラフティングテープ

オススメは、スコッチのドラフティングテープです。私が使っていたのは厚さ12mmのもので嵩張らないのでちょうどいいサイズです。本体にカッターが付いているので便利なのも特徴です。人によっては、若干粘着力が足りないと感じる人もいるようですが、私はそこまで気にならないです。製図用紙に合わせて爪で擦るように貼るとしっかり仮止めされます。剥がす時も製図用紙が破れずに剥がれます。さすが、3Mさんですね。
8.電卓

使っていたのは、シャープのEL-N431-Xという商品です。シンプルで数字キーが大きいので打ちやすさがあります。これも、日頃から使い慣れているものであれば何でもOKです…と言いたいところですが、試験会場に持ち込み不可の電卓もあります。令和4年度に試験元から出ている資料を掲載します。
簡潔に言うと関数電卓がNGということです。複雑な計算ができる電卓は避けるようにしましょう。
9.勾配定規

一級建築士で勾配定規?と思われる方もいると思いますが、理由は2つあります。1つは、昨今の設計製図試験ではRC造であっても勾配屋根の課題が出てもおかしくないことから、資格学校のほうでも勾配屋根の対策をしています。もう1つが大きな理由ですが、縦線を引く時に簡単に引けるからです。
勾配定規には、角度を調整する締め付けネジがあります。その部分を持ち手にすると、縦線を簡単に引けたり平行移動が簡単にでき時間短縮に繋がりますので、1本持っていることをオススメします。
10.その他に持っていると便利な道具
赤ボールペン(ゼブラのサラサ0.5)
フリクション4色ボールペン
三角スケール ←紹介していませんが必需品!30cmがオススメです。
道具は余計に持っておくこと
消しゴム編でも書きましたが、特に小さい文具は予備は持っておくことです。
ちなみに私は、二級建築士の試験日の試験前に勾配定規が折れました。予備を持っていなかったのでドラフティングテープで補修して挑みましたが、その時は、かなり冷や汗をかきました。そういった事態があってもすぐ対応できるようにしておきましょう。メンタル面でも救われます。
何事も事前準備が大切です。道具を上手く使いこなせば、作図のスピードも格段に上がります。年々課題が難しくなっているということは、作図漏れが増えるということです。早い段階で準備をしておきましょう。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました!
noteでは一級建築士の設計製図試験について綴っております。
Twitterでは建築関係を中心にツイートする他、日常のことも呟いています。
ぜひお気軽にフォローを、よろしくお願いします!
フォローはnoteのプロフィール、または下記からもチェックできます!
