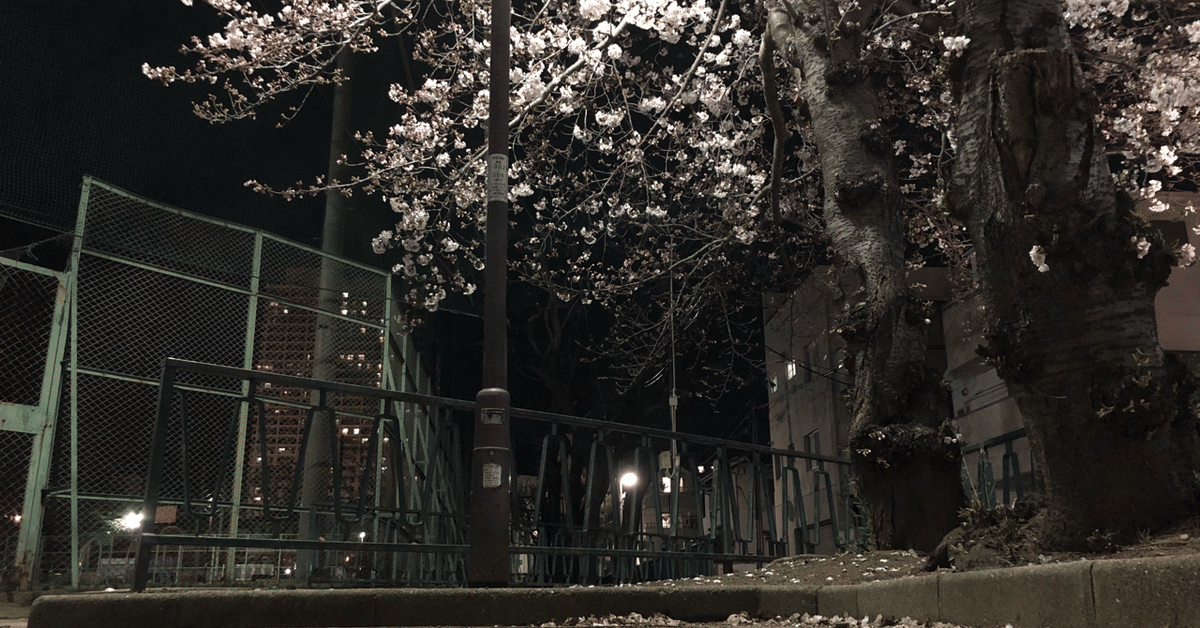
「現実」ってなんだ!→「現にあるもの」はただ「現にあるもの」として見る、しかし頼むべきは「現在を超えたもの」ってことは言えないだろうか?
~「現実」ってなんだ!→「現にあるもの」はただ「現にあるもの」として見る、しかし頼むべきは「現在を超えたもの」ってことは言えないだろうか?~
(28,044字)
□手洗いの意義を発見し消毒によって産婦の死亡率を下げたセンメルヴェイス・イグナーツ・フュレプ医師は、精神科病棟で受けた暴行による傷がもとで敗血症により1865年に死去したといわれる。享年47歳。彼の理論が広く認められたのは死後数年を経過した後であった。
□■□■
1、今月の文章について
今月の田中美知太郎先生の文章は、論文集『ロゴスとイデア』の中の「現実」です。
今回も長いので、facebookのカレンダーのコメント欄よりもnoteの方が良いだろうと思いました。
『ロゴスとイデア』(1947(昭和22)年. 岩波書店)は、《哲学上の問題をそれ自体として追求して世に問われた最初の著書》です。
(《》:藤澤令夫「あとがき」田中美知太郎『哲学からの考察−自然と人間−』(1986(昭和61)年. 岩波書店…著者の御逝去は1985年)
つまり、思考の努力をさほど必要としないエッセイと違って、進むのにずいぶんと時間がかかる文章ということです。
もっとも、時間がかかるのは私だけかもしれません。
「私は、何ら独特の論理を用いたりすることもないから、読者には普通の判断力と良識とを期待するだけである」と田中先生は「あとがき」で書かれています。
普通の人ならさくさく進むのでしょう、きっと。
けれども私は行ったり来たり、時には図を書いたりして、なんとかしてだいぶ進んできて、やっと『ロゴスとイデア』の次の論文集である『善と必然との間に−人間的自由の前提となるもの−』(1952年. 岩波書店)の中盤まできていたのですが、しかし、ちょっと思うところがあり、また最初に戻って「現実」をはじめから読んでみることにしました。
この状態を「現実」の文章の中からちょっと拝借して説明しますと、
----
「このような可能性に対してはAはBであるとか、Bでないとかいう、一定の有が考えられる。例えば私は眼を開けていることも出来るし、閉じていることも出来るが、いまは開けているとか、閉じているとかいう場合がそれである。」(二節より)
----
↑
というように、私は気にせずどんどん進むことも、そして戻ることもどちらも可能なのですが、いまは戻ることを選んでいるわけです。
まぁ要するにまた遠回りをしているということです。
田中先生は、知識も思考力も想像力も不足している私のような者でも途中でくじけることのないように、なるべく平明な言葉で書いてくださっておりますので、私はたいへん助かっています。
□■□■
2、新型コロナと原発の話
とはいうものの、私は1月からずっと情報の渦の中に巻き込まれています。
世界的に流行しているCOVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2(サーズ・コブ・ツー)は、私の住んでいる兵庫県でも猛威をふるっております。
3月は気をつけるべきことが一気に増え、ただ情報を受け取るだけではとても対応が出来ない状態です。
また、3月といえば3.11です。
私は原発のことについてよく知らなかったので、3月は少し集中して勉強し、ようやく何が問題なのかを把握する糸口をつかむことができました。
↓
・原発そのものの仕組み。
・「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」のメリット(無過失責任)とデメリット(責任集中…原子力損害の賠償責任は電力会社のみが負い、メーカーや個人は責任を負わない)。
・民事事件として→
・運転差止め訴訟(運転差止め仮処分申請も含む)
・株主代表訴訟
・損害賠償請求
・国家賠償請求
・原発メーカー訴訟(「責任集中」制度は違憲であり無効であることを確認するための裁判)
→プラス、刑事事件としての立件を目指す刑事告訴や刑事告発を組み合わせる。
(参考:河合弘之『原発訴訟が社会を変える』2015. 集英社新書)
・爆発事故で影響を受けた方々(帰還困難区域内外問わず)への支援の不足。
・作業員さんの労働環境の問題…被ばくによる健康問題、重層下請け構造、労災申請、損害賠償等。1970年代~・2011年~・除染作業、それぞれに共通している問題もあるし、改善されてきている部分もある。
・作業員さんの作業は原発の稼働中より定期検査(定検)がメイン。そもそも、原発がこんなに人出を要する職場だとは!!まさか雇用を生みだすためにわざとそうしている??
・福島第一原発の廃炉の問題。
→最低でも40年以上は続くが、その間の人員確保、労働条件、福利厚生、作業環境等。地域住民への賠償等。
(参考:西澤 丞『福島第一 廃炉の記録』2018. みすず書房、池田 実『福島原発作業員の記』2016. 八月書館、ハッピー『福島第一原発収束作業日記』2015. 河出文庫)
(伝える。遺す。廃炉の記録。 - 廃炉プロジェクト|ビジュアルコンテンツ|東京電力ホールディングス株式会社
https://www.tepco.co.jp/decommission/visual/ )
↑
糸口をつかんだだけで、自分なりの判断はこれからです。
そして、放射性物質とそこから出る放射線については、何がどうどれだけ危険なのか、私は未だによくわかっていません。
ところで、情報を「摂取する」という言い方は、いかにも気取った感じだというご指摘をいただきました。
しかし私にとって情報は、食物や栄養と同じなので、やっぱり「摂取」じゃないかなぁと今のところ思っています。
おなかがすいたら食べるし、めんどくさい時は食べないし。
収集、と書き換えたこともありますが、何か良い言い方はないものだろうか…。
あ、「せっしゅ」の方です、「しょうしゅ」の方ではなくて。
□■□■
3、メロス島人にとって「現実」とは
それはともかくとして、多量の情報の処理に追われる毎日が続くと、どうしても考える時間や心の余裕が不足してきます。
そんなある日のこと。
「トゥキュディデスの罠」という言葉を教えてもらいました。
この動画がきっかけです。
↓
トゥキュディデスに学ぶ習近平政権の行方(前編) - YouTube
もぎせかチャンネル 2018/08/11
https://www.youtube.com/watch?v=asxTKSkP_FY
→何それ?でもメロス島のお話なら知ってるよ!
→「現実」の論文の中にあったはず!読み返してみよう!
→あれ、私、ぜんぜん理解できてなかったのかも…
→というより自分に都合のいいフィルターかかりすぎ…
→私の解釈、だいぶ間違ってるんでは?これはやばい!!
→いったん戻って、少し時間をかけて進んでみよう…
→いや、案外間違ってないかも、でも人に説明できない…
→ということはやっぱり理解できてないってこと…
→けど、そうだったのか!ってことを発見できた!
→かといって理解できてるとは言えないか…
→基礎的なものがだいぶ不足してるから…(−_−;)
(↑イマココ)
* *
メロス島の人々、つまり敗者は、「現実を見ないことに、かえって救いを見出そうとしてい」たから、酷い目にあったと言えます。
スパルタ側連合軍は助けに来ないとわかっていれば良かったのに。
ではメロス島人だけが「当にならないものを当にした」のでしょうか。
否、勝者であるアテナイ人も、「阿諛の言葉を信じて、現実を見のがして」いるのです。
「アテナイ人が頼みにした現有の海軍勢力は、その後間もなくシケリア遠征によって失われてしまったのである」
* *
・気になるけど時間がないよ!って方は、最後の六節から読んでみてください。
・少しなら時間あるよ!って方は、四節からがおすすめです。
・メロス島のお話は、二節です。
・でも本当は「現実」の超越性を考えられる、三節も結構おもしろいのですが。
(理論と実践の統一?とか、社会>個人の違和感とか…)
・しかしどこかを少しでも読んだらきっと、一節の内容が気になってくると思いますw
↑
おせっかいをやく理由は、途中で読むのをやめてしまっては誤解の多い読み方になるのでは…それではあまりにもったいない!と私が余計な心配をしているからです。
なにしろこの論文で多用されている接続詞は、「しかしながら」なのです(^^)
ところで、「トゥキュディデスの罠」の名付け親は、米国の政治学者グレアム・アリソンのようです。
古代ギリシアのペロポネソス戦争のお話がもとになっています。
新興国のアテナイが、旧覇権国家であるスパルタの地位を脅かしました。
挑戦したんですね。
2400年前くらい前にトゥキュディデスは、『戦史』(または『歴史』)に、そのことを詳しく書いたようです。
私は読んでいませんが、前述した「もぎせかチャンネル」で詳しい説明をしてくださっています。
なお念のため、「トゥキュディデスの罠」自体のお話とは少し離れますが、私は以下のことにも気を配っておこうと思います。
----------------
ツキュディデスの歴史において、アテナイ帝国の没落といふやうなものが、ひとつの運命的必然として見られてゐたといふやうな解釈は、どうも成立たないやうである。
〔中略〕
目的論は必然論を逆にしたものなのである。しかし問題は、偶然が目的のためと解釈され得るといふ可能性は、それだけでは事実がさうであつたといふことの保証にはならないといふことにある。無論また可能性がそれ自体で、その必然性をつくり出すわけではない。そのためには運命とか神の摂理とか、あるひは歴史の理性とかいふ別の原理が必要なのである。しかしわれわれがツキュディデスにおいて見るのは、あくまでも人間的な過誤であつて、運命の必然ではないのである。
----
(田中美知太郎「二 われわれが求めようとする全体的・統一的視点」『ツキュディデスの場合』昭和45年. 筑摩書房. pp. 54-55)
----------------
* *
現在への執着は、「現にあるものだけを頼みにするということ」から起こるようです。
しかしそれは現実的でないとも言えます。
私は、過去・現在・未来、という時間軸とか、「希望」というようなものではなくて、「現在を超えたもの」というようなものを考えてみたいと思いました。
自分の行動は何によって規定されているのか。
もっとも、「永遠なるもの」は、連続してつながっているものの延長なのか、そうじゃないのか、それともそのどちらとも言えるのか、今の私にはまだわかりません。
プラトンの前半生は「苛酷な現実経験」にみちていました。
プラトンの「理想主義」は、現実との闘争から生まれてきました。
プラトンは、どんなものを「頼むべきもの」としていたのでしょうか。
以上、いつものように前置きが長くなりましたが今月も、田中美知太郎先生の著作権継承者である田中氏に感謝しながら、ここに書き写しをさせていただく次第です。
□■□■
4、前置き不要の方はすぐにこちらから↓
【田中美知太郎「現実 −主として παρόν πάθος の意味における−」】
発表:1942(昭和17)年11月『思想』
所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店
今回の引用:1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房
1941 日ソ中立条約締結。南部仏印進駐。ハワイ真珠湾攻撃:太平洋戦争(~1945)。国民学校令公布。大西洋憲章。独ソ戦争。
1942 翼賛選挙。ミッドウェー海戦。関門海底トンネル開通。
1943 ガダルカナル撤退。学徒出陣。イタリア降伏。カイロ会談。
(年表:山川出版社『詳説日本史B』p. 424より)
------------------
一
現にあるものだけを頼みにするということが、もしも現実的だとするならば、それはアリスティッポスの次のような主張のうちに、最も明らかに認められはしないであろうか。アエリアヌス(*)の伝えるところによれば、アリスティッポスは将来を憂えたり、既往を嘆いたりすることの愚を戒めて、ひとが心を用いなければならないのは、ただ一日一日だけのことであり、しかもその一日のうちでも、ひとが現に何かを為したり、考えたりしている、その時その時のことしかないということを教えて、「自分たちのものとしては、現にあるものしかないのだ」(μόνον γαρ ημέτερον είναι το παρόν)という主張をのべたということである。けだし既往は失われてもはやなく、将来への期待は、それが実現されるか否か明らかではないからである。いわゆるアリスティッポスの快楽主義というものは一方において、このような現実主義の考え方を基礎にするものであった。この一派に属するアンニケリスの学派は、人生の目的というようなものを否定して、ただ個々の行為に個々別々の目的を認め、これをそれぞれの行為から得られる快楽であると主張した(**)のであるが、人生全体の幸福というようなものと、刹那刹那の快楽とを厳に区別して、むしろ後者に第一義的の意味を認めようとするのが、アリスティッポス以来のいわゆるキュレネ学派に見られる根本思想のひとつなのである(***)。人生の幸福というような考えは、快苦の個々の場合を超えて、人生を全体として観察しなければならないから、それは必然にアリスティッポスの現実主義的な立場を否定することになるのである。
(*) Aelianus, Varia historia XIV. 6.
(**) Clemens Alex., Stromateis II. 417B.
(***)Diogenes Laertius II. 87-88 ; ibid. 93.
しかしながら、現実という ものをアリスティッポスの、このようないわゆる刹那主義の立場だけで見るということには、無論いろいろな異論が考えられるであろう。現実というものは、快苦というような個人のパトスのうちに見出されるものではない。それはむしろそのような個人的感情を超えたところに発見されるものでなければならないとも言われる。プラトンの第六書簡と称せられるものの中には、エラストス、コリスコスという二人のアカデメイア学徒が、プラトンによって、同学派の先輩たる実際政治家ヘルメイアスに紹介されているが、これら両人は多年学内にあって温良健全な人々と生活を共にし、イデア研究に専念して来たのであって、邪悪な者どもとの交渉には全く無経験であるから、今度はそういう者どもから身を守り世渡りの智慧が真の学問の妨げとなることのないように、世間的な修行が必要になったのだと語られている(*)。現実というものは、何かそのような場合に、世間へ出て始めて発見されるものなのかも知れない。これとは反対に、学問や理論は何かそのような現実から遊離した存在のようにも考えられるであろう。Hic Rhodus, hic salta!は、アイソポスに物語られているままでは、ひとが何も知らないと思って勝手な法螺を吹いている男への一大痛棒となるのであるが、時にはまた理論家や理想家に対するいわゆる現実の挑戦的な呼び声としても聞かれるであろう。プラトンはこのような挑戦に応じて、齢六十を過ぎてから、あらゆる困難を知りながらも、二度まで海を渡って、ロドスならぬ、シケリアに赴いたのである。それは二十年来の知己ディオンのために、出来るだけのことをして、その政治改革の志を遂げさせようとする、師友としての情から出たものであると共に、また哲学への誠実によるものでもあった。有名な第七書簡のうちには、「自分が全くただ言葉だけの人間であって、実際の仕事には、あえて少しも手を触れようとしない者なのだというようなことを認めるのは、何よりもまず自分自身に対して恥ずかしいことであって、到底これを自分に許すことは出来なかった」(三二八C)と述べられている。それは哲学への裏切り(三二八E、三三九E )であり、わが身の哲学者としての一分を汚すこと(三二九B)なのであった。しかしながら事件は、プラトンがひそかに恐れていたような不幸に終り、ディオンも暗殺されてしまった。しかしそれは決してプラトンを顚倒させるようなものではなかった。ディオンを失うことはたしかに悲しむべきことに相違ないが、しかしディオンを死なせた事情には、今さらプラトンを驚かすようなものは何もなかった(θαυμαστόν ονδεν)のである(**)。
(*) Epistula VI. 322DE. cf. Plato, Respublica VII. 539E.
(**)Epistula VII. 351D.
ところが人々は、プラトン晩年のシケリア行について、理想家が始めて(原文ママ)現実の困難に当面したひとつの場合を見ようとする。好んで説をなす者は、プラトンがこの現実からの教訓によって、イデア論を放棄したとか、これに重大な修正を加えるに至ったとか、いろいろ面白い説を発明する。いわゆるプラトンの後期思想そのものについては、また別に取扱わなければならない問題があると思われるけれども、しかしプラトン晩年のシケリア行をもってアカデメイアを巣立つ青年学徒の場合と同じ、始めての現実発見を考えようとすることは、明らかに謬見である。プラトンはペロポネソス戦争の始めに生れ、その青年時代を通じて戦時生活のあらゆる困難を経験し、しかも年少にして政治に志した彼は、その家柄からよく政界の表裏に通ずることが出来たのである。四〇四年の敗戦につぐ革命期には、感激や希望や恐怖や失望や嫌悪のあらゆるものを経験し、三九九年のソクラテス訴訟事件をめぐっては、いっそう深刻な教訓を社会の現実から学ぶことが出来たのである。プラトンの前半生は苛酷な現実経験にみちていて、ソクラテスの前半生と著しい対照をなすとも言われる。プラトンの理想主義は、このような現実との闘争から生れて来たのであって、晩年のシケリア行の発端をなすものは、祖国の政治に絶望したプラトンが、齢およそ四十にしてシケリアに遊び、ディオニュシオス独裁下の腐敗した生活環境のうちにあって、なおよくプラトンの政治理想に耳を傾け、生活のうちに哲学を生かす情熱と実践力をもった一青年ディオンと相識るに至ったという一事にあると言わなければならない。それから二十年後、当時のギリシア世界にあって最大の国家と目されたシュラクサイ帝国に、正しい政治を実現しようとするディオンの運動が始められた時に、プラトンはこれを助けて、労の身を二度までも海を渡り、その後も四〇四年の革命当時と同じ熱心をもって、事件の推移を見守り、その成行にあらゆる希望をつないだのであるが(*)、十五年の紆余曲折の後、ディオンの暗殺をもってすべては水泡に帰したのである。それは老年のプラトンにとって、たしかに手ひどい精神的打撃であったには相違ない。プラトンの生涯は最後まで失望であった。しかしながら、その故にプラトンの哲学的信念が動揺したように思う者があるならば、それはプラトンを知らない者である。プラトンの哲学はそんな甘い空想ではない。空中楼閣ではない。彼の哲学を生んだ前半生の現実経験から見て、ディオンの事件もまた今さら彼を驚かすようなものではなかったと言わなければならない。およそ一々の事件によって動揺するようなものは、哲学の名に値しないであろう。
(*) プラトンの第四書簡と称せらるものには、事件の詳報を知ろうとするプラトンのなみなみならぬ関心と、ディオン周囲の不安な形勢を察知して、ディオンのために心配しながら、それとなくディオンに忠告する、プラトンのあたたかい心づかいが示されている。この書簡の真作偽作の論はしばらくおき、そこに語られているようなことをほぼ事実に近いものと想像するのに、ひとは特別の困難を感じないであろう。
しかしながら、プラトンのシケリア行をいかに見るかということは、いま当面の問題ではない。われわれは現実というものを、アリスティッポスの刹那主義の意味において、現にあるもの、確実にわれわれの所有となっているものと解したのであるが、他面それはむしろ、そのようなわれわれ個人の所有の外にあるものとも見えたのである。それは何かわれわれが世間に出てそこで発見しなければならないもののようにも思われたのである。人々はそれを何か世間知らずの理想家や理論家を嘲笑するための存在であるかのようにも想像したのである。プラトン晩年の事件に関して、上述の伝説を作り上げたのも、この種の現実論であったと言うことが出来る。しかしながら、理想と現実、理論と実際というような対立は、われわれには未だ早すぎる問題なのである。われわれはしばらく理想を忘れ、理論をすてるとしよう。そしてただ現実を個人的所有から離れて、社会的所有の立場において見ることにしよう。
二
それにはトゥキュディデスの読者によく知られている、かのメロス島の事件を例にとって見るのがいいかも知れない。それはペロポネソス戦争が、アルキビアデスの登場によって第二の段階に入ってからのことで、紀元前四一六年春、アテナイ側同盟軍の一部兵力が、当時中立国であったメロス島に上陸し、メロス島政府が中立政策をとって、アテナイ側につくことを拒否したために、これを攻囲して、ついに成年男子を皆殺しにし、婦女子を奴隷に取ったという事件である。メロス島側の兵力も、経済力も言うに足りないものであったから、これはペロポネソス戦争の全局から見て、全くの地方的小事件と目すべきものであった。しかしトゥキュディデスは、アテナイ没落の主要原因たるシケリア遠征のことを記すに先立って、この一小事件と見えるもののために、第五巻の第八四節から第一一六節までの、比較的長い記述を捧げているのである。われわれはそこにギリシア文学作品の手法を見ることが出来るかもしれない。ヒュブリスは罰せられなければならなかったのである。しかしながら、われわれ当面の問題はその点にはない。われわれの仕事は、メロス島上陸後のアテナイ軍によって派遣された代表者が、メロス島政府の要人に向って発する、極めて露骨な言葉のうちに、メロス島国家の現実を見ることである。
まずアテナイ代表は、メロス島の要人たちに向って、「もし諸君が現にあるところのもの、現に諸君が見ているものをもととして、そこから国家の安全を計ろうとするのではなく、いまに起るかもしれないことの見込みから、それを論じたり何かするために、ここに出て来られたのなら、われわれはもう何も話すことはないのである」(八七)という言葉をもって、会談の内容が現実的なことに限られなければならないことを明らかにする。従って彼等は、かつてペルシアの来寇を撃攘して、全ギリシアを救ったものはアテナイであるから、当然ギリシア諸国はアテナイの指導に服すべきであるとか、あるいはメロス島民に不正不義の行いがあったから、膺懲の軍を起したのであるというような、納得のいかない美名を用いようともしない代りに、またメロス島側からも、自分たちはもとスパルタ側の移民であるけれども、この度の戦争には参加せず、アテナイに対して別に敵性行為はとっていないというような、無用の弁解を聞こうともしない。アテナイの要求するところは、余計な犠牲を出さずにメロス島を支配することであって、メロス島側もそれによって安全が保証されるわけであるから、これは双方にとっていいことなのだというのである。しかしメロス島の人々にとっては、アテナイに支配されることがいいことだとは無論認められなかった。彼等は中立国として友好関係をつづけることを提議するが、弱国との友好関係のごときものは、強国にとって何らの意味もないことは、その敵対関係が何らの脅威ともならないのと同じことで、むしろ強国が弱国と友好関係を結ぶことは、強国に何か弱みがあるように解される危険を伴うとて、アテナイ側はこれを一蹴してしまう。しかしこのような中立国侵略は、他の中立国を敵に廻す危険がありはしないかと注意されるのであるが、アテナイは未だ防備に手間どっている大陸の中立国などを恐れはしない、むしろ海上帝国の護りを固める上において、メロス島のごときものが、自国の勢力外に放置されてあることの危険の方をはるかに恐れるものであると答える。しかしメロス島側としては、アテナイがその帝国を維持するためにかかる暴挙をも辞さぬ一方、征服された国家も自由独立を回復するためにあらゆる危険を冒している時、なお自由と独立を保持している国が、これを守る努力もせずに、たやすく他国の奴隷となるのは、あまりに意気地がなく、恥ずかしいことであると考える。無論、意地や名誉は対等の力があってからの話で、弱小国にはただ保全の問題があるばかりだとも言われるが、しかし勝敗は時の運、戦争には偶然がはたらくから、いま直ぐ降参してしまったのでは、何の望みもないことになるが、何とかやって行けば、未だ何か望みがあるかも知れないと見られる。「望みとな!」とアテナイ代表は叫ぶ。「なるほどそれは危険にのぞんで元気をつけてくれるものだが、余力があって望みをもつのなら、万一害を受けても、身を亡ぼすことにはならないけれど、ありったけのものをすっかりこれに賭けたのでは~~といっても、希望というものは気前よく何でものみこむのが本来なのだから、それが当り前かも知れないが~~それがふいになってから、それの正体を確かめたところで、もはやそれに対して身を守る手段は残されていないことになる。諸君は弱国の人であって、危機一髪のところにいるのだから、みずから求めてそんな目に遭うようなことはしないがいい。また諸君は、未だ人力によって助かる道があるのに、窮地に陥って、目に見えていた望みが失われると、卜占託宣などの目に見えない望みにすがる、世の馬鹿者どもの真似をしてはいけない。あんなものははかない望みによって、破滅をもたらすだけのものなのだ。」(一〇三)
こう言われても、メロス島の人々は、なるほど万一の偶然を頼んで強国アテナイと争うことは、もし偶然のめぐみが公正なものでなかったとしたら、難しいことに相違ないが、正しい立場で不義と戦う自分たちには神明の加護があり、同族の誼みにはスパルタ軍の救援があるであろうと考える。しかしアテナイ人に言わせれば、強者が支配するのは天地自然の理法であって、わが方に特別の不正ありとは思われない。スパルタ人の救援に至っては、メロス島人のお目出たさにあきれ、その愚を憐むのみ。そもそもスパルタ人なる者は、功利打算の権化であって、大して役にも立たない味方を助けるために、単なる好意や義理だけで、海上の危険を冒してメロス島救援に来るようなことは、到底あり得ないのである。無論、スパルタ側連合軍のうちには、アテナイ海上警戒線を突破して、メロス島救援に来着する者も絶無とは言えないであろうし、報復的にアテナイの領土を攻撃する者もあるであろう。しかしそのようなことは既に経験ずみである。アテナイ軍は、隣国を攻めるにも連合軍を語らわねばならぬスパルタ軍とは異り、未だ敵を恐れて攻略を中止したことは一度もないのである。
「しかし考えて見ると、諸君は自国の安全を議すると称しながら、これだけ言葉を費して、未だ人がそれなら国家は救われるであろうと認めるようなものを、何ひとつ言っていないのである。諸君の頼みとする最強の拠点は未来にかけられた希望であって、諸君の現有するところのものは、既に諸君に対して戦備を完了している勢力に比べて、まことに微弱、到底勝味はないのである。僕たちは一旦退場するから、その間に諸君がこれよりもっと正気にかえらなければ、とんだ違算をやることになるぞ」(一一一)とアテナイ人は、なおもメロス島要人に警告するけれども、メロス島政府の回答は「否」であった。ここにおいて、アテナイ人代表は最後の言葉を語ることになる。「とにかく、このような決定をするところから見ると、ひとり諸君だけが、眼前の事実よりもいまに起りそうなことの方を確実だと判断し、われわれの前に現われていないものを、そうあれかしとねがうが故に、既に起りつつあるかのように観察しているらしく思われる。諸君はスパルタ軍や偶然や希望をこの上なく信用して、これに大部分のものを賭けているが、それは諸君の破滅となるであろう。」(一一三)
われわれがアテナイ人のこれらの言葉において見るものは何であるか。それはアリスティッポスの刹那主義においても見られたと同じ、ただ現にあるもの(τα παροντα)を信ぜよ、希望(ελπισ)によって欺かれるなという思想である。思うに、あらゆる希望的観測をすてて、眼前にあるものをそのまま見るところに、現実というものがあるのではないか。ちょうどこれは spes に対する res の関係であって、 realitas という言葉もそのひとつの意味においてこのようなものを指しているのではないかと思われる。無論、 realitas という言葉には意味のいろいろな面があるし、現実という言葉も、哲学の術後としてほかになお ενεργεια,actus-actuali:as,Wirklichkeit などの訳語にも用いられている。これらはいずれも哲学語として、ヨーロッパでは、それぞれ永い歴史と伝統とをもっているから、われわれはこれの学術語としての使用には慎重を期さなければならない。アリストテレス以来これらの言葉は主として可能性との対立に用いられているが、その可能性にもいろいろなものが考えられる。AがBであることも出来るし、Bでないことも出来るという可能性もそのひとつであろう。このような可能性に対してはAはBであるとか、Bでないとかいう、一定の有が考えられる。例えば私は眼を開けていることも出来るし、閉じていることも出来るが、いまは開けているとか、閉じているとかいう場合がそれである。これに対して他の可能性と考えられるのは、能力としての技術や知識である。ひとが仕事を休んでいる時や夜眠っている時には、これらは可能性に止まる。しかし仕事をしている時には、それは現にはたらいているのである。第三の可能性としては、素材のもっている受容性が挙げられるであろう。素材というものは、加工において見られるように、量や質や場所などのいろいろな変化を受け容れることが出来るからである。その無限定性は限定の可能性なのである。第四には、いわゆる可能的存在というものが考えられる。近代ではこれは概念上の可能性、観念的可能性として考えられ、形式的真理に関係して取扱われるが、古代においてはむしろ素材が主に考えられている。種子は樹木の可能態であり、木材は家の可能的存在なのである。「子供は未だ一人前ではなく、ただその望みがあるだけなのだ」(Puer non est res, sed spes)という言葉に見られる、かの spes と res の対立も、むしろこの意味に考えなければならないであろう。ものは可能の実現と解されている。
かくてわれわれは、現実という言葉が、これらのいろいろな意味を伝える上において、必ずしも充分なものではないことを知らなければならない。しかもこの哲学語は、他の流行的な哲学語と同じように、一般の言葉のうちに濫用されて、もとの意味限定を失うとともに、たびたびの使用によって、いつの間にか別の意味を中心に不透明な結晶をなしつつあるのを見るのである。このような場合にわれわれは、いわゆる現実と、ドイツ哲学が Wirklichkeit について与えている概念規定とを直接、何の考えもなしに結びつけて、事物の哲学的基礎づけをしているかのような錯覚を抱いたりしてはならないのである。” Unzeitgemäße Betrachtungen " の筆者は、今日特に興味をもって読まるべき「ダヴィット・シュトラウス」のうちで、カントやショーペンハウエルの文章がラテン語に翻訳出来るのに、シュトラウスの文章が出来ないのは、それがよりドイツ的だからではなく、その思考が混乱していて、論理を欠いているからだと語って、ラテン語に翻訳出来るかどうかを思想家吟味の一手段に用いているが、われわれもまた自己自身の思考を明確にするために、このような手段を利用することが出来るであろう。われわれはヨーロッパの哲学語に、ただ訳もなく出来あいの訳語を機械的に当てて行く代りに、われわれの用いるそれらの哲学俗語が、他の言語では何と言われるであろうかを考えてみる必要がある。無論、それらの困難な場合が少なくないであろう。その困難な試みが、われわれに思想の明確ということを教えてくれるのである。ソクラテスの教えに従えば、何かを語りながら、それが何を意味するのか、他人に少しも分らせることの出来ない人は、実際には何も考えていないのであって、その思考はにせ智慧に過ぎないのである。そして他国の言語に当てはめて考えることこそまさにかかる他の人との対話なのである。われわれがアリスティッポスやトゥキュディデスを用いて、現実を παρόν πάθος として規定したのも、実はかかる試みだったのである。無論、ここでも哲学言語との意味関連が全く失われてしまっているのではない。しかしながら、単なる言葉だけについて、そのいろいろな意味に渡りをつけることは、いまのわれわれの仕事ではないであろう。
三
かくて、現実というものは、それが「現にあるもの」を意味する限り、社会的見地に立っても、個人的な立場から見ても、その間に区別はないと考えられる。しかしながら、人々は社会的現実の方を優位に考えようとするかもしれない。既に見られたように、現実というものは何か個人的所有を超えたもののようにも考えられるからである。現実は世間に出て学ぶものなのであった。しかしながら、このような現実観には何が前提されているであろうか。そこには一方、現実を可能の実現として見る本来の哲学的な考え方が認められるかも知れない。その場合の可能性とは、いうまでもなく観念的可能性である。そしてこの観念的可能性が人々のいわゆる理想なのである。それは更に個人的な希望もしくは感傷と見なされる。かかる希望(spes)に対して、現実(res)は超個人的なものと考えられ、この超個人的性は手取り早く世間とおきかえられるのである。そして現実はいわゆる理想家を嘲笑する存在になる。この考え方の特色は、既に見られた現実と希望との区別を、そのまま社会と個人の区別に配当するところに認められる。理想家の登場は余興の一役を演ずるためである。しかしながら、世間に現実を求めるこの考え方は、社会的見地に立っているようで、実は個人の立場から考えているのである。現実は絶えず個人の外に考えられるが、その超越性は常に個人にとっての超越性として見られている。個人はその希望や夢想を抱きながら、あるいは勇敢に、あるいはおずおずと世間に出て行くと、そこで痛い目にあわされ、現実を見させられて、すごすごと自分自身へ引き下って来る。それが現実経験であって、これが度かさなれば、痛い目にも慣れ、いちいち自分自身に立ちかえるほどの感傷もなくなり、やがて現実経験の初心者たちを嗤う立場になる。そうなれば、現実はもはや自分の問題ではなく、他人の滑稽な問題となる。ちょうど恋愛経験のようなものかもしれない。心に余裕のある人は、好意的に微笑し、若さを失わない心は、自分自身の青春を回想するかも知れないが、それはもはや他人の問題であり、昔のわが夢なのである。いずれにしても現実は、世間知らずの問題なのである。さきの区別で言えば、社会から区別され、希望や夢想だけを割当てられた個人なしには考えられない問題なのである。ここに永遠の青年である理想家の登場するきっかけが見られる。
しかしながら、理想家の登場は、いわゆる現実に観念性を与えることになるのではないかと思われる。理想家の立場からは、現実は可能の実現として考えられる。その場合の可能は、近代哲学の考えでは、観念的可能性であり、概念上の可能性なのである。そしてかかる可能の実現が事実上ほとんど不可能であることは、これの現実的存在を可能的存在の彼方に望み見られる目的とか、限界とか、理念とか呼ばせる結果となる。観念的可能性は部分的に、ただ不完全にしか実現されないで、なお可能性のままに止まっているが、現実存在はかかる可能性の全き実現、あるいは実現の極(εντελέχεια)と解される。理想家は観念の夢想に耽れば耽るほど、その現実は絶望的な遠さから、あらゆる魅力をもって呼びかけて来る。しかしその現実は夢想の極にあるのである。ちょうどそれは病者の夢みる健康が病的に明るく輝いているようなものである。そして病者が普通の健康者に理想の実現を見るように、実現の困難のみを経験した理想家は、既に現実として与えられているものに驚異しなければならなかった。それはいずれも理想の実現、可能的存在の現実化、ひとつの εντελέχεια と解される。それは理論と実践の統一、内なるものと外なるものとの一致などと呼ばれる。そしてこのような美しい哲学的理解が、世間にのみ現実を見ようとする俗見と、そのまま無造作に結びつく時、社会が絶対的存在となる。個人の希望や夢想を無視する社会の存在は、個人にとって超越的なものとなったが、その恐しさがかつては自然を神としたように、いまは社会を神としている。観念論哲学はその神学なのである。しかしながら、世間は理想家を嘲笑する俗人の集りであって、彼等にとっては、そのような夢想的現実はどこにも存在しないのである。個人的な希望に対するその冷酷の故に、われわれは世間を強力な存在であると考える。しかしながら、美辞麗句をきらうアテナイ人が、メロス島国家について暴露したように、それもまた個々の人間と同じような弱点をもつ存在なのである。だからわれわれは簡単に社会的現実を個人的現実よりも優位に考えてしまうことは出来ないのである。われわれはもう一度アリスティッポスの刹那主義について考えてみなければならぬ。
アリスティッポスの立場からすれば社会的現実というようなものも、ただ個人のパトスにおいてのみ存在するものなのである。厳密な意味において「現にあるもの」とは、各人のかかるパトスよりほかにはないと考えられる。ここにパトスと言われるのは、ひとが外から受け取るすべてを指しているのである。世間に出ていろいろな目にあうのも、自然のうちにいろいろなことを感ずるのも、みなひとしくパトスなのである。古人の伝えるところによれば、アリスティッポス一派の人々は、われわれが確実に把握することが出来るのはパトスだけであって、これらがそこから出て来るもとのものは把握されないと教えたと言われている(*)。セクストス・エンペイリコスの説明によると、それは例えば音声というようなものについて、聞かれたままのパトスとしての音声のほかに、かかるパトスを生ぜしめたものとしての音声は存在しないという主張になる(**)。われわれがものを白いと見、甘いと感ずる時、そのパトスに虚偽はないのであるが、しかしかかるパトスを生ぜしめたものを白いとか、甘いとか主張することには誤謬がある。なぜなら、白くないものを白く見、甘くないものを甘いと感じているのかも知れないからである。つまり確実に、誤謬なく把握されるのはパトスだけなのである。しかもそのパトスは個人的なものと考えらている。白いとか甘いとかいうのも、名前だけが共通なのであって、実際のパトスは各人別々なのである。「われわれは自分のパトス以外に何も捉えることは出来ない」と言われている(***)。
(*) Diog. L. II. 92.
(**) Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VI. 53.
(***)ibid. VII. 191-196.
無論、このような主張は、今日のわれわれにとって、別に珍しいものではない。またセクストスの説明が、どこまでアリスティッポスの思想に帰せられていいかも疑問である。しかしながら、それはいまわれわれが問題にしようとしていることではない。われわれがアリスティッポスにおいて見るのは、一種の現実観の徹底である。現にあるもの(παρόν )というのは、時間の上のいわゆる現在だけではない。それは何か身近かにあるもの、手近かにあるものを指している。παράの意味はむしろそれである。眼前にあるものと言われるのもそのためである。足下を見よと言うのもその故である。時間的に見れば、スパルタの連合軍は海を越えた大陸にいま存在しているのである。しかしそれがメロス島に現れるのは何時のことか分らないのである。われわれは距離を無視して、これを同時存在者と見なしても、一方が他方に駆けつけて来るには時間がかかるから、アテナイ人はそれを現在あるものとは認めなかったのである。現実には時間上の現在だけでなく、あらゆる意味の現在が要求されるのである。近さが要求されるのである。そのような場合、個人のパトスは、最も身近かな存在として、まず何よりも現実であると言わなければならなくなる。これに反して、いわゆる社会的現実というようなものは、この立場からすれば、かかる個人的パトスのうちに見出されるか、あるいはかかるパトスを生ぜしめるものとして、パトスの外にあるが故に、直接に把握されぬ非現実とならなければならぬ。われわれが頼らねばならぬのは、われわれによって確実に把握されるものでなければならぬ。それは現にあるがままのわが身わが心のほかにはない。アリスティッポスの哲学は、このような認識を基礎にするものだと言うことが出来るかも知れない。
しかしながら、アリスティッポスの現実主義はパトスを究極とすることから更に一歩を進めて、そのパトスの中でも、快苦のパトスをもって最究極のものであるとすることにおいて、恐らく最後の徹底に至るのではないかと思われる。アリスティッポスの現実主義といわゆる快楽主義との関係については、刹那の快楽のみを認めて、人生の幸福というようなものを否定するところに、その相関性を見たのであるが、しかしそこでは既に快楽主義が前提されていて、現実主義はそれに附随する他の問題、すなわち「個々の快楽が主であるか、それともそれらの快楽を集めた人生全体の幸福が主であるか(*)」というような問題の解決に用いられているのである。しかしながら、現実主義は快楽主義の生成そのものにも何らかの関連をもっているのではないかと思われる。もとより快楽主義なるものは、いわゆる「善」の問題について、万人の求める最後のもの、ただそれだけの値打で求められ、それを得れば何人も満足するようなものとして、快楽を挙げる立場なのであるから、頼むに何が最も確実であるかというような問題とは、直接関係はしないように思われる。しかしながら、プラトンの『ピレポス』(三六C以下)において、快楽主義批判のために、「いつわりの快」(ψευδεις ηδοναι)の存在が苦心して論証されているのを知っている者は、真偽論が快楽主義の成立に重大な意味をもっていることを見のがしはしないであろう。無論、快苦に真偽の別があるというような主張は、快楽主義の立場からでなくとも、既にわれわれにとって意外である。しかしその意外な感じのうちに、快楽主義を保証するひとつの前提がかくされているのである。それは何であるか。われわれはパトスがそれ自体としては無偽であるのを見た。しかしながら、白さや甘さの場合においては、白くないものを白と見、甘くないものを甘いと感じているのかも知れないという不安があった。感覚されたものをそのまま“あり”と認める極端な感覚主義の立場に立つのでない限り、この不安は無根ではないように思われる。しかしながら、ありもしないことを真実と信じて喜ぶ、そのよろこびにいつわりはないのである。すなわち知覚に錯誤があっても、それに伴う快苦にはうそがないのである。ただ快苦の比較対照において、その大小強弱の感覚に誤差があって、極端の場合には、苦痛のないことが一種の快と感じられたりするような事実が指摘されるけれども、これもパトスとしては無偽なのである。従ってわれわれは、アリスティッポスがパトス一般について語った、確実無偽ということは、特に快苦のパトスに当るものであることを認めなければならない。また従って、現在の快楽のみを認めるということは、最も確実なものを善として生きることにもなるわけである。そしてアリスティッポスの現実主義は、この快楽主義において、最も現実的な拠りどころを得たと言うことができるであろう。
(*)Diog. L. II. 87
四
しかしながら、このような現実主義は、それがパトス(受け取られたもの)の現実主義である点において、ひとつの限界を示していると言うことが出来る。これは最も確実なものとして自己のパトスを拠りどころとするのであるが、しかしそのパトスに対して、ひとはただこれを受取るだけであって、その去来をいかんともなすことが出来ない。パトスの現実主義は純然たる受動の立場にある。従って、快楽主義といっても、積極的に快楽を追求する立場にはない。なぜなら、その場合には、未だ眼前にない快楽を求めて、現在の苦痛を忍ぶということが起って来るけれども、それは明らかにアリスティッポスの刹那主義に矛盾し、今にわが所有となるかも知れないものを、単なる希望によって、現にあるものよりも確実であると信ずることに外ならないからである。ひとは現にあるものだけを信じなければならない。しかし現にあるものは外から与えられたものであって、そこに受け取られたものにはただ快だけが含まれていて、苦は少しも混入していないことを希望したところで、現実はこれを許さないであろう。快苦は他のもろもろのパトスと共に既に与えられているのである。ひとはそこで一方を選び、他方を捨てることの自由を想像するかも知れない。しかしながら、パトスの去来はわが力の及ばぬところで、現にあるものを否定することは、まさに現実主義の否定となるであろう。現実主義の立場に立つ限り、この種の快楽主義は、与えられたものを甘受し、苦はこれを忍び、快はこれを楽しむという行き方をするより外はないであろう。アリスティッポスはいかなる場所、いかなる時、いかなる人にも調子を合わせることを知っていて、どんな場合にも自分の役割を演じ損うことはなく、どんなことにぶつかっても、上手にこれに対処したと言われている(*)。また彼は快楽を味わうのに、ただ現にあるものからこれを取り、現在ないものを追求して苦労するようなことはなかったとも言われている(**)。恐らくこの現在を楽しむというところに、彼の哲学は存したのであろう。しかしながら、既往を追わず、明日を頼まず、ただ今日この時を楽しむというようなことも、それは必ずしも容易とは言われないであろう。希望に欺かれず、後悔に悩まされず、ただあるがままの現在を受け取って、くさぐさの憂き思いを抑えながら、楽しみを楽しむというようなことには、ひとつの断乎たる精神を必要とするのである。その忍苦の一面には、いわゆるストア主義と共通するものを認めることが出来るであろう。快楽主義は、このようなパトスの現実主義を基礎にもつ時、一種悲壮な哲学的精神となり、他面また昔の悟道にも似たところのものを示すことになるのである。
(*)Diog. L. II. 66.
(**)ibid.
しかしながら、パトスの現実主義は受難者(παθητος)の哲学であり、敗者の哲学であるとも言われるであろう。無抵抗に現在を受け容れて、忍苦のうちに辛うじて心の平和を楽しむというようなことは、子供の泣き寝入りと異らず、その悟りといっても、薄日の当っている煤け障子に蠅が一匹とまっているのを眺めているような、一種寒々とした風景を思い出させるに過ぎない。勝ちほこった顔と声とが、「汝の現実を見よ」と指さしながら、敗者の悲壮な哲学を嘲笑するであろう。パトスの現実主義は、視野をパトスだけに限り、これだけに頼ろうとする時、強いて何かを見落としているのではないだろうか。われわれはこの点を現実主義と快楽主義のひとつの矛盾に認めることが出来るように思う。アリスティッポスの現実主義がその快楽主義において、ひとつの究極に達するのをわれわれは見た。快苦のパトスこそ現実中の現実、ひとが頼みとする最後のものなのである。ところが、この快苦のパトスにおいてわれわれは、それが必ずしも現にあるものを必要とはしないことを見るのである。われわれは眼前の悲惨を忘れるために、しばらくこれには眼を閉じて、過去の楽しい思い出や、未来のすばらしい希望のうちに我を没入させることがある。それはひとつの現実逃避である。しかし快苦のパトスはどこまでも現在であり、過去の思い出や未来の希望もやはり現在なのである。しかしこれを唯一つの現在とするためには、われわれは他の現在を忘れなければならなかった。それには一種の精神的努力が必要なのである。現在を楽しむためには、現在する苦悩を抑える忍苦が必要であった。快楽主義の生活は、哲人にして始めて可能なのであった。しかし現在を楽しむということだけについて言えば、われわれは必ずしも現在だけを相手にして、忍苦のために不必要な苦労をするには及ばないのである。われわれは現にあるものから逃避して、夢幻の世界に遊びながら、現在の快楽だけをわがものとすることも出来るのである。アリスティッポスの快楽主義は、現にあるものだけを頼みとする厳格な現実主義の上に立っていたのであるが、しかしその究極において、かえって現実逃避を許すものとなった。この矛盾はどこから生じたのであろうか。
それは現在の快苦だけを他のパトスから区別した為であろうか。特にこれを現実中の現実と見て、これだけに生きようとするところに、その原因があるのであろうか。しかしながら、快苦のパトスは、確実無偽の点で特に他のパトスから区別されるものであった。しかもこの確実無偽という点が、またパトス一般を特に現実たらしめたのである。そしてわれわれは、ひとが最も確実なものに頼って生きようとするのを、非難すべきいかなる理由も発見し得ないのである。いまパトスの現実主義が、快楽主義として徹底された時に、かえって現実逃避のごとき矛盾を示したとすれば、それはパトスの現実主義そのもののうちに、何かそのような矛盾が含まれていたからであろうと考えられる。われわれは現にあるものだけを頼みにしようとした時、これを現にないものから厳しく区別しなければならなかった。そしてこの現にあるものを各人のパトスとして規定した時には、パトスを生ぜしめる外物からパトスそのものを区別して、前者については断定をさし控え、ただ後者のみをわがものとして頼るように心掛けたのである。すなわちパトスの現実主義は現在のパトスを他のあらゆるものから引き離す努力によって成立しているのである。それはちょうどその快楽主義としての徹底が、他のパトスは現在のものでも一切これを無視して、ただ現在の快楽だけに生きようとしているのと同じである。そして現在の他のパトスを無視するところに、その現実逃避が見られたのである。また従って、われわれがパトスだけに生きようとした時にも、既に現実が見落されていたのではないかと疑われる。パトスとパトスを生ぜしめるものとが区別され、現実はパトスのみに限られたけれども、そこに既に現実逃避の原因があったのではないかと疑われる。現実は個人が受け取るパトスだけに尽きるのではなく、かえってかかるパトスを与えるものこそ、すぐれた意味において現実なのではないかと考えられるからである。無論、かかるものは個人のパトスを離れて、直接には把握されないと言われるであろう。これをパトスから切り離して、それだけを現実とすることは、パトスだけに現実を見る場合よりも、もっと疑わしく思われるであろう。現実は両者の切断のうちにはなく、両者の相関のうちにある。パトスはパトス以外のものを指しているところに現実性をもっている。現実は、個人と世間の場合に見られたように、一種の超越性を含んでいる。パトスがそれ自体に止まらずに、何か自体を超えるものをもっているところに、かえって現実性がある。受け取られたものとしてのパトスは、受けることにおいて、既にかかる関係を含んでいる。受けるものは与えるものと共に見られなければならない。現実はそこにおいて始めて完きものとして、見落しなく把握されたことになるのかもしれない。
われわれはパトスの現実主義を純受動の立場と考えた。しかしながら、現在を楽しむということは、努力なしには出来ないことであった。日日是好日というためには、大へんな苦労が必要なのである。眼前の事柄を無視して、白昼夢を描くことには、一種の精神集中がなければならない。同じようにして、白を見、甘さを感じながら、かかるパトスを生ぜしめたものについて、白いとも甘いとも言うまい、思うまいとすることは、大へんな努力なのである。純受動の立場というものは、このような精神の能動(ポイエーシス)の上に築かれているのである。パトス(受動)としての現実は、外からのポイエーシスのほかに、それ自体の根底にもポイエーシスをもっているのである。そしてその能動は、パトスを外物から区別する時に、既にパトスの外に及んでいたのである。われわれはこのようなポイエーシスからも現実を考えることが出来るのではないか。敗者の現実主義と見えたものも、実際は頑強な抵抗線をもっていたのである。恐らく現実は、このような勝敗の境にあるのかも知れない。われわれは別に勝者の現実というようなものを考えて見なければならない。
五
われわれはもう一度メロス島事件にかえって見ることにしよう。そして今度はわれわれをアテナイ人の立場においてみることにしよう。われわれはそこにおいて何を見るであろうか。アテナイ人が現に所有しているところのものは、メロス島の人々のそれに比して、明らかに圧倒的優勢である。それはメロス島人の現実と同じように、間違いなく現在している。ただ注意して見ると、メロス島人の現実は未来の希望から厳しく区別され、これとの対照によって、かえってその現在のパトスがますます切実に感じられるようなものであったが、アテナイ人の現実にはかかる区別や対立が感じられない。アテナイ人はスパルタ人がメロス島人を助けに来るようなことはないと考え、もしメロス島の人人(原文ママ)がアテナイの要求を容れないなら、彼等の救われる他のいかなる機会もなく、彼等にはただ破滅あるのみだということを、まるで現在のことであるかのように語っている。未来は現在とひとつなのである。そして過去はただこの現在のために存在したと考えられるであろう。あるいは過去は思い出すまでもなく、現在とひとつになっているのであろう。アテナイ人にとって、この世はいつまでもわが世なのである。そこにはパトスとこれを生ぜしめるものとの区別はない。すべては見られた通りに存在し、すべては現れてしまっている。強いて眼を閉じ、見ない工夫をしなければならないようなものは何もない。視界はどこまでも延び、それの及ぶところ、すべては平伏し、どこにも抵抗は感じられない。他のものは、人も国も物もすべてがわが支配に服し、既にわがものとなり、われの一部をなしているから、われわれは一歩退いて守らなければならないような自己をも感じないのである。勝者の現実は敗者の現実と正反対なのである。勝者の現実は全世界であるが、敗者の現実はわが身わが心の外にない。敗者は他のすべてを失った故に、せめてこれだけはと言えるものを自分のために見出そうとする。しかし勝者は既にすべてをわがものとしているから、特にわがものと呼ばるべきものを確保する必要を感じないのである。無論、勝者にも我はある。否、彼等は通俗の意味における利己主義の権化である。すべては彼のためにあり、彼のものなのであって、それ以外のものは認められない。アテナイ人の露骨な言葉はこれを明示した。しかしながら、勝者の自我は多数の人々に取囲まれて、社会的栄誉に身を飾りながら、儀礼の中心に立っているような存在で、その声を録音し、その姿を写真に撮れば、それで全部となるようなものなのである。勝者の現実においては、すべてが外に現われて、世界全体にひろがっている。これに対して敗者の自我は外に現われずに、内部に閉じ籠る。一方は浅薄で、他方は深刻である。一方は明るく、他方は暗い。パトスの現実主義については、既にその限界をわれわれは見た。彼等はパトスの外をことさら見ないようにしている。内心の工夫によって、外界を無視しようとしている。そこに彼等の現実逃避が見られたのである。これに対して、この世の勝者たちはすべてを見る。何ものをも避けない。そして見られたものが全部であると信じている。彼等にとっては内面は存在しない。およそ存在するものは外に現われてしまっているのである。外面化が存在の原理である。しかしながら、見られざるもの、未だ現われざるものが驕慢の勝者を奈落の底に没落させるのである。
ペネロペの求婚者たちにとって、現在オデュッセウスがどこにも見られないということは、オデュッセウスが存在しないということであった。予言者は彼等に警告して、オデュッセウスはやがて帰って来るであろうと言うけれども、彼等はこれを信じない。彼等の眼は何らそのような兆候を見ないからである。「もうオデュッセウスは遠いところで亡くなってしまったのだ」というのが彼等の判断であった(*)。実際、眼前の事実だけで判断すれば、オデュッセウスはなきものであった。だから、その希望から言えば、オデュッセウスの帰宅を信じたい人たちさえも、もはやそのことは断念していたのである。忠僕エウマイオスは、オデュッセウスその人の口から、オデュッセウスが帰って来ると告げられても、旅の乞食が饗応の御礼に気やすめを言ってくれたのだとしか受け取らない。求婚者たちは、オデュッセウスのいないのをよいことにして、その館に入り浸り、ほしいままに飲食して、ペネロペに言い寄ったりしていたのである。彼等は無論そこに現われた乞食姿のオデュッセウスをそれと認めることは出来なかった。それは見られた通りの存在なのである。内心に彼等の破滅を計画しつつあるオデュッセウスのごときものはどこにも見られなかった。だから彼等はその乞食がオデュッセウスの強弓を引いてみごと的を射当てた時にも、未だ覚らなかったのである。また既に彼等の首領株であったアンティノオスが殪された時でも、未だ分らなかったのである。オデュッセウスが彼等を罵って犬と呼び、「貴様たちはおれがもうトロイアからは帰って来ない者だと思いこんで、わが家を荒し、女どもは手ごめにし、ひそかにわが妻にまで言い寄っていたのだ。まことに神々を畏れず、人の世の正義の怒のやがて来るのを思わぬ所業、いまこそ汝等には何人にも破滅の運命はのがれられぬところだぞ(**)」と叫んだので、始めてそれと知り、蒼ざめた恐怖が彼等を捉えたのである。彼等は見ていて、見なかったのである。そこに世の勝者たちの見る現実の限界がある。ソロンは同胞をいましめて、「諸君は人の侫弁諛辞(ねいべんゆじ)に注意を奪われて、その現になしつつあることを見ようとしない」(Fr. 11, Bergk)と述べているが、世の勝者たちは阿諛の言を愛して、自分の都合のいいようにしか世界を見ず、他のすべてが自分の思う通りに動き、自分のためにあるのを当然のことのように考えている。そこに彼等の重大な見落しがある。彼等は甘言に注意を奪われて、現実(ἔργον γιγνομενον)を見落しているのである。しかもこの見落しは、敗者のそれのように意識的ではないから、かえって救い難いのである。それはいつまでも気づかれない無智のようなものである。彼等はただ破滅と失敗によって、彼等の見ていた現象が現実ではなくて、仮象に過ぎなかったことを知るのである。
(*) Homerus, Odyssea II. 157-184.
(**)ibid. XXII. 35-41.
六
かくて現実は、内面のパトスだけに限られるものではなかったように、また外面の現象だけに尽きるものでもなかったのである。無論、ひとはすぐに両者の統一とか、綜合とかいうものを考えるであろう。しかしそれはいかにして可能なのであろうか。いかなる見地において可能なのであろうか。外から内面を見ることは出来ないが、しかし内部から外を見ることは出来るかも知れない。ひとが内面のパトスのみに頼った時、その外はあえて見ることを欲しなかっただけで、見ることが不可能なのではなかったとも考えられるからである。しかしながら、われわれは外を見ることによって何を得ることが出来るであろうか。そこではすべてがこの世の勝者の所有なのである。われわれはわが身ひとつの自由さえもないのである。われわれは彼等の利己主義に奉仕し、彼等のための存在を保持するために、あらゆる犠牲を強いられ、容赦のない取扱いを受けているのである。われわれのものとしてもつことが出来るのは、われわれが彼等から受けた被害(パトス)だけなのである。われわれは無力な敗者であって、ほかに何をすることも出来ない。あるいはメロス島人のごとく、スパルタ人の来援を頼み、あるいはオデュッセウスの忠実な家人たちのように、主人の帰るのを待つとしても、それは何れもはかない望みであって、現在の苦痛は加わるばかりである。だから哲学は、そういう事実には眼を閉じ、自分だけで自分を慰めることを教えたのである。余計な考えごとをせず、何のためを問うことなしに、ただ仕事のうちに楽しみを見つけよとも教えるであろう。自分よりもっと不幸な人がいると考えて、その比較のうちに幸福の錯覚を楽しめとも語るであろう。パトスの現実主義はこのような智慧なのであった。見ぬこと、考えぬことのうちに救いがあると考えられている。行動とか実践とかいうような合言葉も、ただ考えぬことに救いをもとめているのなら、一種の現実逃避に過ぎないであろう。このような行動は決して真のポイエーシスではない。われわれはパトスだけに生きる人々のうちに、かえってポイエーシスの存在を認めたのであるが、そういう仕方で自己を守ることの努力に堪えなくなると、人々は外からの流れに無抵抗に身を委せて、手取り早くこれに溺れようとする。それは純受動なのである。人々のいう実践は多くの場合、仕込まれた犬の行動を思い出させる。われわれはそれを彼自身の行動と解して、あらゆる道徳的解釈をほどこすのであるが、しかし実際は教え込まれたことを反復しているに過ぎないのである。それは受動の反射に過ぎない。およそ自己の内部から出た行為でなければ、それは彼自身の行為とは言われないであろう。彼は他から行動を受け取って、これを他に取次いでいるに過ぎない。彼は媒体であって、主体ではない。この世の勝者の支配するところ、自己のパトスに一線を画して、そこに守るべき内面の世界を見出した者を除いては、すべてが媒体であり、受動的運動者なのである。かくてわれわれは、内面の世界を出て外を見たところで、やはり見なかったことの賢さをもう一度発見するだけのことである。われわれは再び眼を閉じ、内面の世界に引き籠るより外はないであろう。それとも自己の守りをすてて、外面の世界に投降し、勝者の皮相なものの見方に同化し、彼等とその愚を共にし(συνασοφειν )(*)ながら、その受動的行動によって、彼等とその没落をも共にすべきであろうか。アリスティッポスの刹那主義は、その極において、かかる自己否定を含むものであった、そこにわれわれの内面の世界に引き籠りながら、なお恐れなければならないパトス現実主義の弱点があるのではないか。
(*)Euripides, Phoenissae 394.
われわれはどこに現実を求むべきであろうか。勝者は阿諛の言葉を信じて、現実を見のがしているし、敗者は現実を見ないことに、かえって救いを見出そうとしている。われわれはそこに見落されたものが互いに補い得るかも知れないと信じたのであるが、しかし両者を合せても、別に新しい全体は得られなかったのである。われわれの不足はどこから補われなければならないのであろうか。否、われわれの不足は何なのであろうか。われわれは「現にあるもの」から出発して来た。アリスティッポスもアテナイ人も、われわれの頼むべきはそれだけであると教えた。いまにスパルタ人が助けに来るかも知れないという、メロス島人の見込みはたしかに当にならない希望であった。しかしながら、彼等だけが当にならないものを当にしたのであろうか。決してそうではない。アテナイ人が頼みにした現有の海軍勢力は、その後間もなくシケリア遠征によって失われてしまったのである。現にあるものを頼む方が、今にあるかも知れないものを頼むより確実であるとは、必ずしも言えないように思われる。無論、現にあるものとしては、パトスの所有の方がわれわれにとってもっと確実だと言われるであろう。しかしながら、来る者は拒まず、去る者は追わず、その時その時のパトスを受け取って、それ以上のものを求めないという生活は、たしかに後悔もなければ、欺かれることもない確実無比の生き方であるが、しかしそれは又どのパトスにも執着せず、何ものをも当にしないということなのである。現にあるものだけを頼るということは、これをいつまでも当にはしないということである。勝者の不幸はどこにあるかと言えば、その現在をいつまでも当にしなければならないところにある。しかし現在は現在においてしか当にならないのである。それをいつまでも当にしようとすれば、われわれは忽ち自分の当にしていたものによって欺かれなければならない。現象は仮象となってしまう。それはちょうど一二年の形勢によってものを見る、いわゆる sub specie bienni の世界史的考察が、世界史そのものによって反芻されてしまうのと同じことである。現実とは何かこのようなものなのであろう。われわれは現にあるものだけを見て来たが、現実はまたその否定でもあったのである。われわれがいろいろな場合に認めなければならなかった現実の超越性とは、何かこのようなところにあったのかも知れない。われわれがパトスを超えたところに考えなければならなかった現実も、外界や世間だけではなく、かえってこのようなパトスの去来そのものにあったのかも知れない。しかしその否定とは何であろうか。いまやわれわれは、現にあるものだけの考察を離れて、もっと別なところから現実を見なければならなくなったのである。それは同時にまた、ただ現在に堪えることを目的としたパトス現実主義の倫理からわれわれを解放することにもなるであろう。果してわれわれの頼むべきは現在だけであろうか?ひとは現にあるものだけを頼む時、窮地にあっては死を決するより外はないであろう。しかしながら、現にあるものをただ現にあるものとして見る余裕があれば、現にあるものを一擲して、また新しく出直すことも出来れば、昨日までの蝸角の争いを心しずかに眺めることも出来るであろう。われわれは現にあるものだけを頼みにするのが現実的だと考えて来たのであるが、しかし現在への執着はもはや現実的ではないであろう。現実はそのような執着を超えて行くものである。従ってまたわれわれが頼むべきものも何か現在を超えたものでなければならない。それは実は永遠なるものなのである。
----
【田中美知太郎「現実 −主として παρόν πάθος の意味における−」】
発表:1942(昭和17)年11月『思想』
所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店
今回の引用:1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 5-31.
----------------
