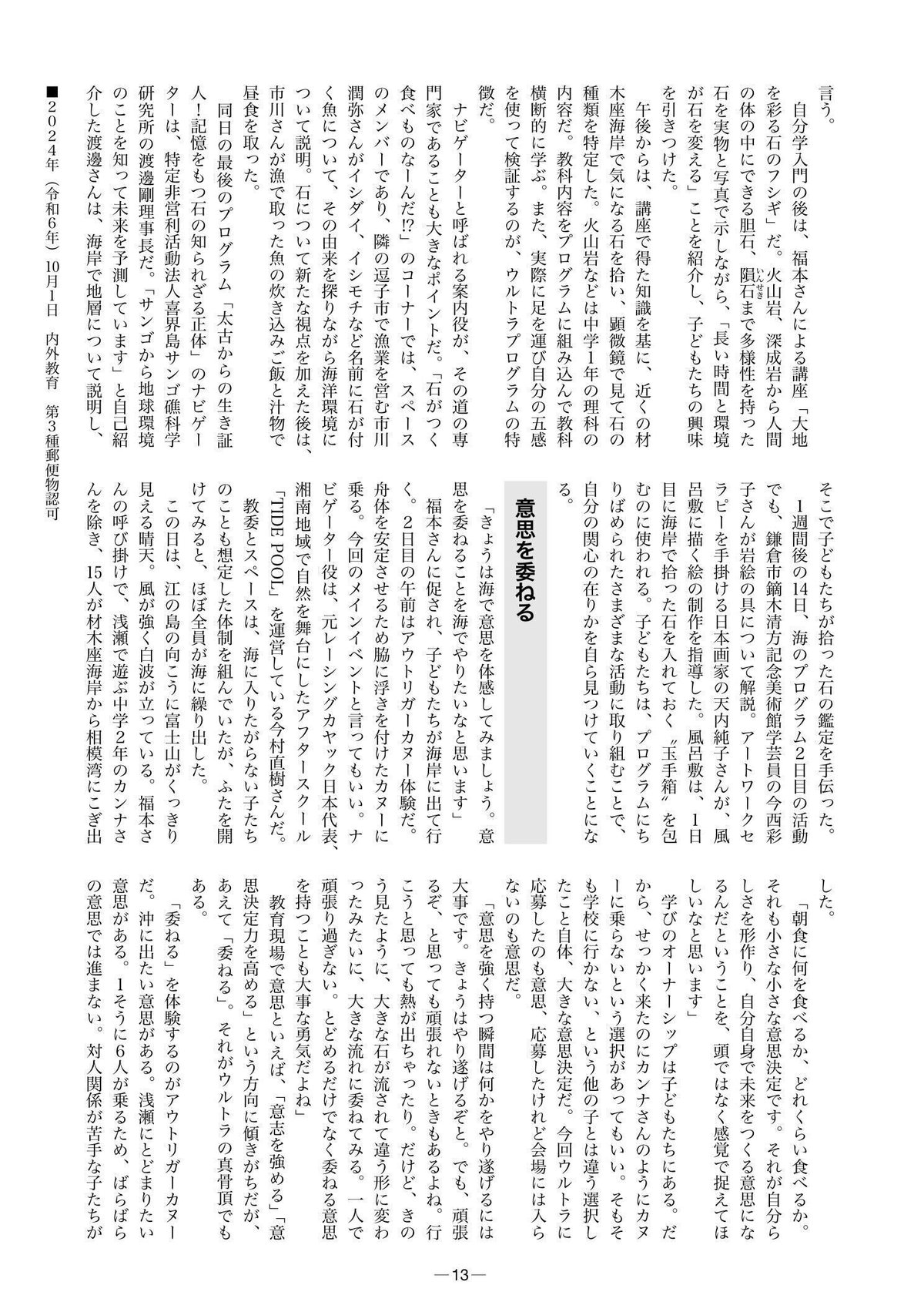【学びの多様化学校を創る④後編】「自分らしさ」見つける3日間 -新教科ウルトラとは
教育長の高橋洋平です。
『内外教育』の田幡記者が、鎌倉市の「学びの多様化学校」開校に向けた取組について取材し、紙面に取り上げてくださっています。
第4回分について、掲載許可をいただきましたのでnoteでは、<前編><後編>として掲載させていただきます。
https://note.com/kamakuracity_edu/n/n1b2ddc27c331
連続性
ウルトラは、この後10月に浄智寺などで行われる「森のプログラム─いしのキセキ─」の後、来年度以降も単発のプログラムとして実施される予定であるとともに、前述の通り、由比ガ浜中の総合的な学習の時間に教科として引き継がれる。通常、中学校の総合学習は1年生が年間50時間、2・3年生が70時間となっている。これに対して、由比ガ浜中では140時間。週換算で4時間が充てられ、まさに中心的なカリキュラムとなる。引き継ぐに当たり、高橋教育長はこう考えている。
「単発のウルトラでは、時間が限られます。が、 新教科は1年間を通した帯の学びになるので自由度が高まり、よりいろんなことができると思っています。例えば、今回の風呂敷のようなアート作品にしても、自分で材料を集め、自分なりの作り方で取り組めます。最終的にはそれぞれが自分自身の興味関心に応じた目標やワークを設定し、テーマを選び鎌倉のリソースを使って探究する〝マイプロジェクト〟にしたい。それを地域の人とつくる。その発想は新教科に色濃く出て多様性を増していくと思います」
ウルトラは教委からスペースへの委託事業でありながら、毎回、教育長をはじめ、指導主事ら教委関係者が、子どもたち一人一人に対応するコミュニケーターなどとして参加し、深く関わる官民の協働事業と言っていい。コミュニケーターとして参加した教委の荒川瑞恵指導主事は「子どもたちが安心できる温かい雰囲気だったり、子どもが納得するまで待ったり、ウルトラの環境は学びの多様化学校でもつくれると思います」と話す。
ただ、ウルトラは、ロケットで400近いプログラムを企画・運営してきたスペースの福本さんの発想やアイデアに負う部分が大きいのも事実だ。福本さんの世界観を具現化してきた。関連する活動内容を考え、人脈を駆使して講師を依頼。スペースがスケジュール管理から備品の調達まで担ってきた。福本さん自身、「職人的に作り込み過ぎました」と自嘲する。由比ガ浜中では、教員がこの役割を担うが、職人技を一般化するのは難しい。
このため、市教委とスペースは、地域で教育支援に関わるNPO関係者や教員らを対象にウルトラのエッセンスを学ぶ研修会「かまくらULTLAリサーチラボ」(本誌24年1月 19日付参照)を23年末から始め、今回のプログラムも地域のフリースクールなどと協力してつくってきた。前述のアウトリガーカヌーの今村さんはそのメンバーの一人だ。高橋教育長が続ける。
「学習者中心と考えた時、今回は特に、ウルトラの積み上げがあるから、学びの多様化学校に走っていけるという連続性を感じました。半数が多様化学校の説明会に来てくれた子たちです。多様化学校にどんな子たちが来て、どんな雰囲気になるのかイメージできました。どんな学び方なら学びに向かえるか、トライ・アンド・エラーができた。子どもたちのどんなところを伸ばしていけばいいかイメージを持つことができました。スペースさんとは、今後も一緒に走り続けたいと思って います」
「普通になりたい」
海のプログラム3日目。最終日は、前日にカヌーに乗って一度「委ね」た意思を、今度は「とどめる」体験だ。
「とどめて委ねる。委ねたらとどめる。くるくるとサイクルするものだと思うんです。自然の中には常に不自然さ、不安定さがあり、変化する多様性がある。自然から学ぶことで、人間もありのままの姿を取り戻していくことができると思っています」と福本さんは言う。
会場は江ノ島電鉄長谷駅から徒歩5分の所に在る合掌造りの古民家を改築した施設だ。近くの水難よけの石上神社について、鎌倉国宝館学芸員の有山佳孝さんの説明を受けてから、実際に参拝。その後は、初日に拾った石に未来への意思を託すワークだ。意思を託した石は、意思をつづった短冊と共に玉手箱に入れ、2日目に作成した風呂敷に包んで持ち帰った。
「多様化学校に受かりますように」。玉手箱に入れる前、子どもたち同士、保護者らにも共有されたそれぞれの意思の中には、小学6年生、幸太さんのこんな願いもあった。幸太さんは多様化学校転入学には必須となる、8月の学校説明会に参加している。ウルトラには今回初参加で、3日間を通して入学への意思を強めたようだ。
「みんなと同じ普通になりたい」。2日目、カヌーには乗らなかったカンナさんの願いだ。カンナさんはNPO法人「かまくら冒険遊び場やまもり」の活動に参加しており、リサーチラボから関わっている冒険遊び場の坪井玲子理事長に誘われて今回、ウルトラに参加した。
初日は室内のにおいや人の多さが気になって部屋に入れなかった。厳しい残暑の中、長袖のパーカーを羽織ったまま、ずっと会場のテラスでコミュニケーターたちと時間を過ごした。2日目は海で遊んだ。3日目、自分の思いを言葉にして表現 し、皆に伝えた。帰り際には笑顔が見られるようになった。今回3日間で最も大きな変化を見せた一人だ。
カンナさんは多様化学校の説明会にも参加している。多様化学校はウルトラの精神を引き継ぎ、「自分らしさ」を見つけ、「自分のなりたい姿へ成長していくことを支援」する場だ。「普通にな りたい」と言うカンナさんの思いとは正反対だ。「普通になりたい」と願う不登校の子たちは少なくない。カンナさんを含めそうした思いの子たちに多様化学校は何ができるのか。カンナさんの願いを、高橋教育長は「われわれへの問い掛けと受け止めました」と言い、こう続けた。
「自分らしさを突き付けることはしないけれど、自分はこれでいいんだと思えるようにするには、どんなアプローチの仕方があるか。正解はありませんが、考え続け、試し続けるということだと思います。われわれの仕事は今まで以上に大きいも のになりました」(田幡秀之=内外教育編集部)
(2024年10月1日『内外教育』掲載文)