
中学生フラクタル川柳
人生は、何本かの道。
その道を選ぶ、それが道。
それが、人生。
この妙にうっとうしい川柳は、中学2年の頃、私のクラスメイトが詠んだ句である。
彼は、学年の流行語大賞を総なめしていた男だった。発言が多い方ではなかったが、ごく稀にとんでもなくインパクトのある発言を残す。それを見逃さない私の学年のユーキャンは、優秀だった。
なぜ今になってこの句を思い出したのか。それは最近私が興味を持っている"L-system"(Lindenmayer system)との関連性を感じたからだ。彼の句は、その再帰的な構造がL-systemと非常に似通っている。
L-systemとは何か
L-systemは、1968年に植物の成長過程をモデル化するためにアリステッド・リンデンマイヤーによって提唱された形式文法だ。落胆しないで頂きたいのだが、この"L"は、みなさんが愛してやまないあのリンド・L・テイラーのことではない。
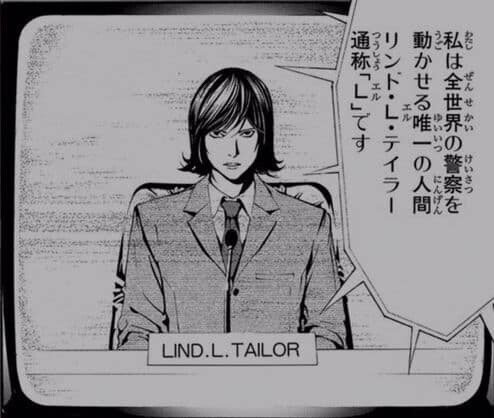
基本的には次の3つの要素で構成される。
Axiom(公理): 初期状態を表す文字列。
置換ルール(Production Rules): 特定の文字や記号を、別の文字列に置き換える規則。
反復適用: 置換ルールを繰り返し適用することで、文字列が成長していく。
L-systemは植物の葉や枝の形状、さらにはフラクタル図形を生成するために使われるが、彼の川柳も同様のルールで解釈できるのではないかと思った。
川柳をL-system化する試み
まずは、彼の句をL-systemの置換ルールに定式化してみよう。
「人生」は何本かの道であるので、置換規則として:
「人生」 → 「道道道道」
「道」を選ぶので、
「道道道道」 → 「道道道道」
選ばれた「道」が再び「人生」を構成するので、
「道」 → 「人生」
彼の句をL-systemの置換ルールとして定式化するなら、例えばこうだ。
「人生」 → 「道道道道」
「道道道道」 → 「道道道道」
「道」 → 「人生」
このように設定して、生成を進めていく。
Axiom(初期文)
「人生とは道である。」
1回目の生成
「道道道道とは人生である。」
2回目の生成
「道道道道とは道道道道である。」
3回目の生成
「道道人生道とは道道道道である。」
4回目の生成
「道道道道道道道とは道道人生道である。」
5回目の生成
「道道道道道道道とは道道道道道道道道道。」
読むほどに、うっとうしさが際立つ結果になった。しかし、その再帰性と無限に続く可能性にはどこか惹かれるものがある。
図示する試み
次に、この句を視覚化するために、L-systemの生成規則を以下のように設定して図示してみた。
A = FB
B = [FC][FC][FFA][FC]
C = FD
D = [FC][FC][FC][FC]
以下の図は、その生成過程を表したものである。



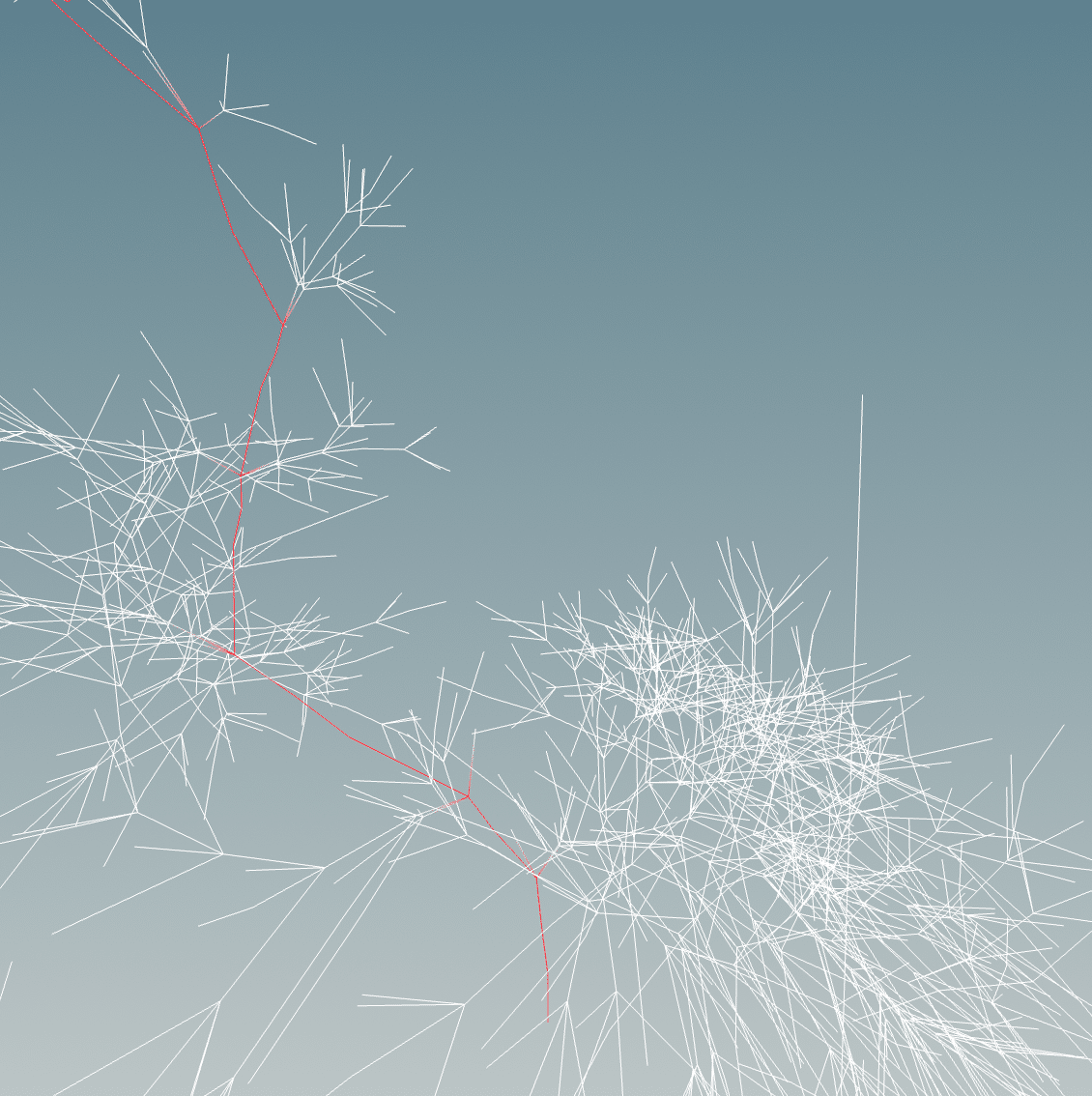
結論
川柳をL-systemとして捉えることで、彼の句に潜む構造の奥深さを再発見できた。ただし、これが彼の真意に近づけたかどうかは分からない。
もっとも、彼が意図していたかどうかなど関係なく、この試み自体が"道を歩む"行為にほかならない。
私たちはこのような再帰的な道の中で、自ら選択し、進み続ける。
その繰り返し、それが道。
それが、人生、なのだろう。
