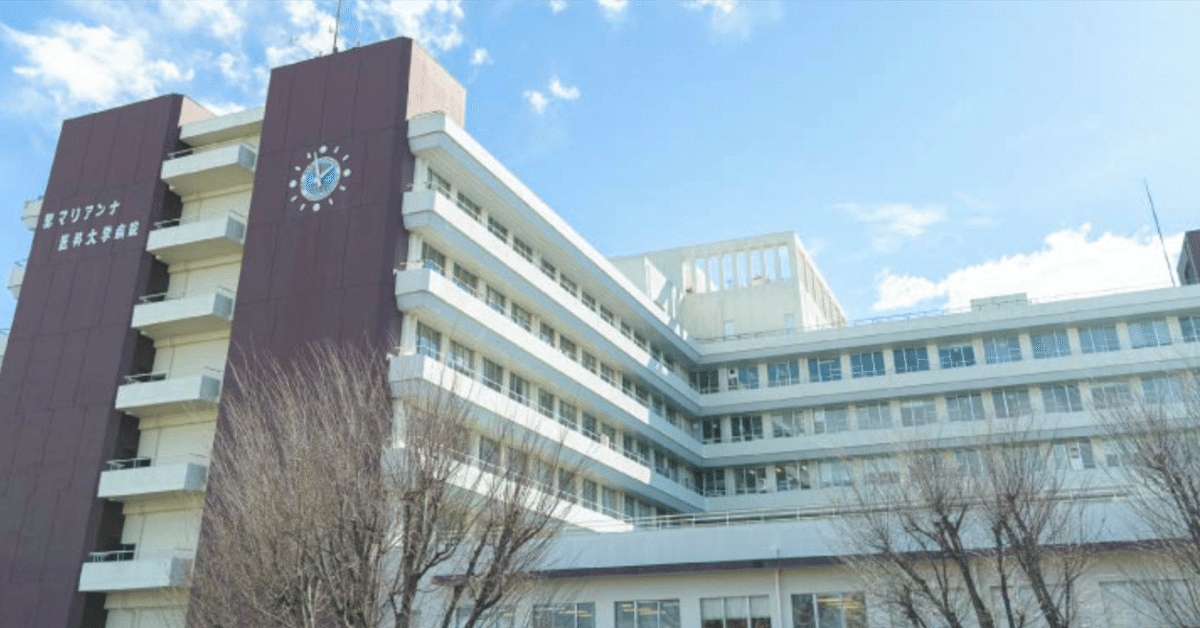
聖マリアンナ医科大学医学部 後期試験(2022~2025年度)
試験日程
2022年度: 出願は例年2月中旬~下旬に実施。一次試験は3月上旬、一次合格発表は試験約1週間後、二次試験(小論文・面接等)は3月中旬、最終合格発表は3月下旬に行われました。
2023年度: 出願期間は2023年2月6日~2月20日。一次試験日は3月2日(木)、一次合格発表は3月8日(水)。二次試験日は3月10日(金)、最終合格発表は3月17日(金)でした。一次試験会場は東京(五反田)、二次試験は大学本校舎(神奈川)で実施。
2024年度: 出願期間は2024年2月17日~2月27日。一次試験日は3月5日(火)、一次合格発表は3月11日(月)。二次試験日は3月15日(金)、最終合格発表は3月21日(木)に行われました。一次試験会場はパシフィコ横浜、二次試験は本校舎で実施。
2025年度(最新: 令和7年度): 出願期間は2025年2月17日(月)~2月27日(木)〔郵送書類締切: 2月28日〕です。一次試験日は2025年3月6日(木)に予定されており、試験会場はパシフィコ横浜ノースで実施されます。一次試験合格発表日は3月11日(火)、二次試験日は3月14日(金)(本校舎にて実施)、最終合格発表日は**3月21日(金)**となっています(入学手続締切日は3月26日)。
※いずれの年度も、一般選抜(後期)は募集人員約10名程度と少人数の募集です。試験日程は年度によって若干異なりますが、概ね出願2月下旬まで→一次試験3月上旬→二次試験3月中旬→合格発表3月下旬というスケジュールで推移しています。
試験科目・形式
一次試験(学科試験):
英語(100点) – コミュニケーション英語Ⅰ~Ⅲおよび論理・表現Ⅰ~Ⅲ相当の範囲。試験時間90分。
数学(100点) – 数学ⅠA・ⅡB・Ⅲ・Cから出題(数学Bは数列、数学Cはベクトル・平面曲線と複素数平面が範囲)。試験時間90分。
理科(200点) – 物理、化学、生物から2科目選択(各100点×2科目)。それぞれ高校範囲の基礎および発展が出題範囲。理科2科目合わせて試験時間150分(各科目75分程度の配分)。
※一次試験の合計配点は400点です。
二次試験(面接・小論文等):
小論文(50点) – 医学や社会問題に関するテーマなどで短めの論述試験が課されます。
面接(50点) – 複数教員による個人面接。人柄・適性や出願書類(調査書や志望理由書等)の内容も含めて評価されます。面接前に適性検査(約30分)も実施されます。
※二次試験まで含めた総合計点は500点満点です。
科目の基準点: 英語・数学の筆記試験には足切りとなる基準点(最低得点ライン)が設けられており、1科目でも基準点に満たない場合は他の成績が良くても不合格となります。また、小論文や面接で著しく適性を欠くと判断された場合も不合格となることがあります。したがって全科目バランスよく得点することが重要です。
出題傾向(2022~2024年度)
総合傾向: 2021年度に一時的な試験時間配分の変更がありましたが、2022年度以降は例年ほぼ安定した出題形式が続いています。問題量は多めですが試験時間も十分に確保されており、基礎~標準レベルの問題を着実に得点できる実力が求められます。各科目で記述式の設問が含まれ、思考力や表現力を問う問題も多い傾向です。
英語: 大問は例年3題構成で、長文読解2題+会話文1題という形式です。長文のテーマは医学・科学に関する内容が中心ですが、語彙レベル自体は標準的で、基本的な読解力がストレートに反映される問題が多くなっています。設問では内容説明を日本語で記述させる問題が多く、近年は「100~150字以内」と指定された要約問題も出題されています。文中の下線部和訳といったピンポイントの設問よりも、段落全体の論旨把握や文脈理解を問う傾向が強く、文章全体の論理展開を追う読解力が重要です。会話文問題は選択肢形式ですが、実質は文法・語法の正誤や適切な応答を問う内容で、過去に出題されていた英語の誤り指摘問題が形を変えて復活したような設問となっています。難易度は長文読解・会話ともに標準的で、基本を押さえていれば対応可能ですが、記述量が多いため時間配分に注意が必要です。
数学: 大問は例年4題出題され、うち第1~3問は答えのみ記入、第4問は証明を含む記述式というパターンです(2021年度のみ英語と合算150分の特殊形式でしたが、2022年度以降は90分で数学単独に戻りました)。頻出分野としてデータの分析(統計的な資料の読み取り・分析問題)が挙げられます。これは医学部入試では珍しい出題ですが、聖マリアンナでは継続的に出題されているため、疎かにせず対策が必要です。また**整数問題(数論)**も度々出題されており、幅広い分野から満遍なく問題が出る傾向です。近年は全体的な難易度はやや抑えられ解きやすくなっていますが、基礎的な問題と発想に時間を要する問題が混在し、メリハリのある出題になりがちです。特に大問4では数学A・B分野(場合の数・確率や数列など)を題材に証明させる問題が定番となっています。対策: 標準的な問題集で入試基礎レベルを網羅するとともに、証明問題にも積極的に取り組み、解答を論理的に書く練習が必要です。計算量の多い問題もあるため、ケアレスミスを防ぎ正確に解く訓練も重要になります。
理科: 理科は受験選択科目により傾向が異なりますが、いずれも記述式や論述式の設問を含むのが特徴です。試験時間150分を2科目で使えるため比較的余裕はありますが、その分記述量が多く採点も厳格な傾向です。各科目の概要は以下のとおりです:
物理: 大問4~5題程度。小問集合の計算穴埋め問題(易しめ~標準)が第1問にあり、第2問以降は典型的な力学・電磁気などの問題が記述式で出題されます。公式の導出過程や単位の記入を要求する設問、実験結果のグラフ選択問題などが頻出です。分野の偏りは少なく、原子物理分野からも毎年のように出題されています。問題数が多く計算もそれなりにありますが、時間自体は十分与えられているため、重い計算は後回しにするなどの時間配分で対応可能です。教科書の細部(欄外やコラム的な内容)から知識を問われることもあるため、教科書を隅々まで通読しておくと安心です。難易度は標準レベルが中心で、「日頃の学習成果がそのまま反映されやすい」良問揃いと言えます。
化学: ここ数年は大問2題構成で、試験時間も2科目で150分となったため、従来(2020年頃まで)の大問3~4題構成から簡素化されています。有機化学の比重が減少しており、特に高分子化合物の出題は2021~2022年度は見られませんでしたが、2023年度に久々に高分子分野からの出題がありました。ただし内容は教科書範囲の基本的なもので、難解な設問ではありません。典型的な計算問題や論述問題に加え、実験操作や構造式を書く描図問題など多彩な形式で出題されます。論述は「○行以内で説明しなさい」という形で解答行数が指定されることが多く、要点を簡潔にまとめる力が求められます。全体として教科書レベルの標準的な問題が中心で、基本原理の正確な理解と応用力を測る内容です。
生物:全問が記述式で、用語記入や考察の論述が中心です。大問は3題出題され、分野は生命現象の各領域(例: 生殖と発生、生体の環境応答、生態と環境など)から幅広く出題されます。設問形式は計算問題、論述問題、グラフや模式図の作図問題など多岐にわたります。かつては論述に字数指定(○字以内)がある問題が多かったですが、近年は「○行以内」と行数指定の形式が主流です。2022~2024年度も行数指定の記述が含まれました。試験時間は理科2科目合計で150分と長めなので問題量は多いものの時間切れにはなりにくいですが、実験考察や論述に慣れていないと時間を要するでしょう。難易度自体は教科書の基本事項から標準レベルの問題が多く、一部にオリジナルな切り口の問題が混じる程度です。対策: 生物現象について自分の言葉で説明する練習を日頃から積み、記述答案を論理的に構成する力を養うことが不可欠です。
合格ライン・合格状況
合格最低点: 一般選抜(後期)の具体的な合格最低点(合格ライン)は公表されていません。公式発表では点数に関する情報は非公開となっており、正確なボーダーは不明です。しかし募集人員が10名程度と非常に狭き門であることから、合格者の学科試験得点率は極めて高いと推測されます。一次試験400点中で見れば、概ね8~9割程度の得点が合格に必要と考えられます。また前述のとおり数学・英語に科目別基準点があるため、どれか一科目でも極端に失点するとその時点で不合格となります。すなわち全科目でバランスよく高得点を取ることが求められ、特に英語・数学で大きく崩れることのないよう注意が必要です。
合格者数と倍率: 一般後期入試では例年受験者数は約1,000名超、最終合格者数は10名前後という構図で推移しています。年度別の志願状況は以下の通りです:
2022年度(令和4年度入試)志願者数:約1,200名、実受験者数:約1,036名、最終合格者数11名。倍率は約94倍に達しました(実受験者ベースで算出)。
2023年度(令和5年度入試)志願者数:1,184名、実受験者数:1,030名、最終合格者数12名。倍率は約86倍と依然非常に高い水準でした。
2024年度(令和6年度入試)志願者数:1,517名、実受験者数:1,307名、最終合格者数10名。倍率は約130倍に跳ね上がりました。志願者増加の要因として、この年は他大学の後期日程との試験日重複が無かったことが挙げられます(前年は藤田医科大学後期などと日程が重なり、一部志願者が分散しました)。2024年度は募集10名に対し1,500名超が出願する異例の倍率となり、狭き門がさらに厳しくなりました。
※参考: 一次試験の段階での選抜も厳しく、例えば2024年度は1,307名中99名のみが一次試験合格(約7.5%通過)となり、そこから最終的に10名前後に絞られるという高い淘汰率でした。
合格者の傾向: 合格者数自体がごくわずかなため、毎年の合格者の内訳(現役・浪人別や男女比など)は大きく変動することがあります。ただし一般的に見ると、聖マリアンナ医科大学の後期試験は他大学の医学部に最後まで合格できなかった受験生の**「ラストチャンス」**的な位置づけになることも多く、高偏差値層の浪人生なども多数受験します。そのため合格者の学力層はかなり高く、正規合格者はほぼ全員が他大学医学部にも合格できるレベルとも言われます。繰上合格(補欠合格繰上げ)の状況は公表されていませんが、後期入試は辞退も少ない傾向のため、追加合格はごく僅かと推測されます。
2025年度試験日に向けた受験対策
2025年度の聖マリアンナ医科大学医学部後期入試まで残り時間わずかですが、最後までできる対策・準備を以下にまとめます。
過去問研究: 聖マリアンナ医科大学の過去の入試問題(特に後期日程のもの)に必ず目を通し、出題形式や難易度になれておきましょう。過去問演習を通じて時間配分や記述解答の書き方もシミュレーションしておきます。大学公式サイトで過去問題が公開されていますので活用してください。
数学対策:証明問題への対応が合否を分けることが多いため、誘導なしで証明を書ける練習をしておきましょう。特に頻出の整数問題や場合の数・確率、数列などは典型的な証明パターンを押さえておくことが大切です。またデータの分析に関する問題が出る可能性が高いので、統計的な資料読み取りや標準偏差・分散の計算などにも慣れておくと安心です。時間は90分と長めですが、計算ミスひとつで大きく減点されるため、計算過程を丁寧に確認する癖をつけましょう。
英語対策: 医学・科学分野の英文長文が出題される傾向があるため、科学記事など少し専門的な英文を読んで内容要約を日本語で書く練習をしてください。ただ単に和訳するのではなく、筆者の主張や論理の流れを捉え、自分の言葉で簡潔にまとめる訓練が有効です。また英文法や会話表現の問題も出題されるので、文法事項の総復習も行いましょう。特に会話文中の適切な応答や語句整序など、過去問で問われた形式の問題を演習し、ケアレスミスを減らすようにします。英単語や熟語は基礎~標準レベルで十分対応できますが、医学用語が出ても文脈で推測できるよう普段から科学記事等で語彙に触れておくと良いでしょう。
理科対策:選択2科目それぞれの教科書範囲を漏れなく復習しましょう。聖マリアンナでは各科目とも出題分野に偏りがなく、典型問題から教科書の細部まで幅広く問われる可能性があります。例えば化学では高分子や有機の細かい知識、物理では原子分野の基本事項、生物では実験手法やデータ解析など、他大学では頻出でないテーマもカバーされています。教科書や資料集を通読し、苦手分野を無くすようにしてください。また記述答案の練習も重要です。生物や化学では「〜について説明せよ」「理由を述べよ」といった記述設問が必ず出ます。模範解答例を参考に、簡潔で要点を押さえた記述が書けるよう繰り返し練習しましょう。物理でも計算過程の記述や図示を要求されるので、途中式や考え方を他人に伝えるつもりで書く練習をしておくと、本番で落ち着いて対応できます。
時間配分の訓練:本番同様の時間割で演習を行い、長時間の試験に慣れておきます。英語90分→数学90分→理科150分(計330分)の連続した試験時間を想定し、過去問や模擬問題で通し演習をするのがおすすめです。途中で集中力が切れないよう、日頃から長時間勉強する際に休憩の取り方や栄養補給(試験当日の昼食等)にも気を配りましょう。また各科目ごとの時間配分計画を決めておき、英語では記述に時間をかけすぎない、理科では難問に固執しすぎない等、自分なりの戦略を練っておくことも大切です。
小論文対策: 小論文は50点配点と比重は高くありませんが、医学部としての適性を見る重要な機会です。医療倫理、医療と社会の問題、医師としての志望動機に絡めたテーマなどが想定されるため、医療ニュースや倫理的トピックに目を通し、自分の意見を400~600字程度でまとめる練習をしておきましょう。構成としては序論・本論・結論を意識し、結論部分で簡潔に自分の立場を示す書き方が望ましいです。過去に出題された小論文テーマがあれば、それに沿って書いてみて、塾の先生や学校の先生に添削をお願いすると良い対策になります。
面接対策: 面接では志望理由や医師になりたい動機、大学で学びたいこと、さらには高校時代の活動や長所短所などオーソドックスな質問が中心ですが、答えに詰まらないようあらかじめ回答を準備して練習しておきましょう。特に聖マリアンナ医科大学を志望する理由(建学の精神や地域医療への貢献などに共感している点)を自分の言葉で説明できるようにしておくと好印象です。医療者としての倫理観や適性も見られますので、「将来どんな医師になりたいか」「医師に必要な資質とは何か」といった問いにも自分なりの考えを整理しておくと安心です。面接練習ではハキハキとした口調や礼儀も確認し、どんな質問にも落ち着いて答えられる態度を心がけましょう。
科目間のバランス調整: 最後に、聖マリアンナ後期では一つでも苦手科目があると致命的です。基準点未達で不合格にならないよう、直前期でも弱点補強に努めてください。例えば英単語や化学の無機分野など暗記系は直前まで点数を伸ばせます。数学の典型問題や物理・生物の重要実験は何度も解き直して確実に得点できるようにしておきましょう。本番では得意科目で稼ぎつつ苦手科目で大崩れしないことが合格への鍵です。
以上を念頭に、限られた時間を有効に使って対策を進めてください。聖マリアンナ医科大学後期試験は超難関ですが、出題傾向は掴みやすく努力が結果に結びつきやすい試験とも言えます。最後まで諦めず、万全の準備で試験日に臨んでください。健闘を祈ります。
