
APOフェス全20回まとめレポート【濃すぎる8月でした】
こんにちは。かぐやです。
教育実習をもっと実りのあるものにするためにクラウドファンディングを実施した“もあふるオンライン教育実習”の共同代表を務めたり、学童・テニスコーチ・体育教室で子どもたちと関わる仕事をしたりしています。
秋からは大学院を休学して、ゆとりをつくります。ワクワクしておりますが、もあふるのプロジェクトを中心に、自分のやりたいことを前に進めるために、活動していきます。
先日、クラウドファンディングが終了しました。
たくさんの応援メッセージ、そしてご支援本当にありがとうございました。第1期のプログラムも開始して、バタバタではありますが、着実に進んでおります。
「これでいいのか?」という疑念を持ち続けて、このプロジェクトをみんなでベターにしていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。
さて!
今年の8月は20名の登壇者をお呼びして、いろんな分野で活動されている方から「知る」「学ぶ」、そして分野を超えた「理解」へということを目的としてAPOフェスを開催しました。

「誰もが、誰かの理解者・支援者になれる社会」を目指すAPO connectsの企画です。
僕は運営メンバーの1人。ということで、リアルタイムで参加できなかったものはアーカイブで視聴しました。
全20回分をここでレポートいたします。
ちなみにイベントのアーカイブはすでにご購入いただけないのですが、もしご希望があれば何かしらの対応を考えたいと思います。

No1 さきさん&みのりさん『幸せは選べる〜女同士の結婚式を挙げるまで〜』
さきさん、みのりさんのお話を聞いて、「当たり前」の選択肢がもっと増えたらいいなと思いました。
幸せの選択肢を選ぶのは自分たちで、どんな選択肢を選んでも周囲の反応は選べない。
だからこそ自分の意思を大切にして生きることが豊かさにつながるのではないかと考えました。
何よりお二人が幸せそうで素敵な時間でした。
ありがとうございました。
【結婚しました💍】
— さき🏳️🌈同性パートナーとの日常 (@karafuru_sm) December 16, 2020
今日大切な方からの承認の拍手を
いただけました😭😭
いろいろなことがあったけれど、
自分が選んだ愛のカタチを大切にしていきます。
3月の披露宴がたのしみー!#みんなきてね pic.twitter.com/IVmnUapF5k
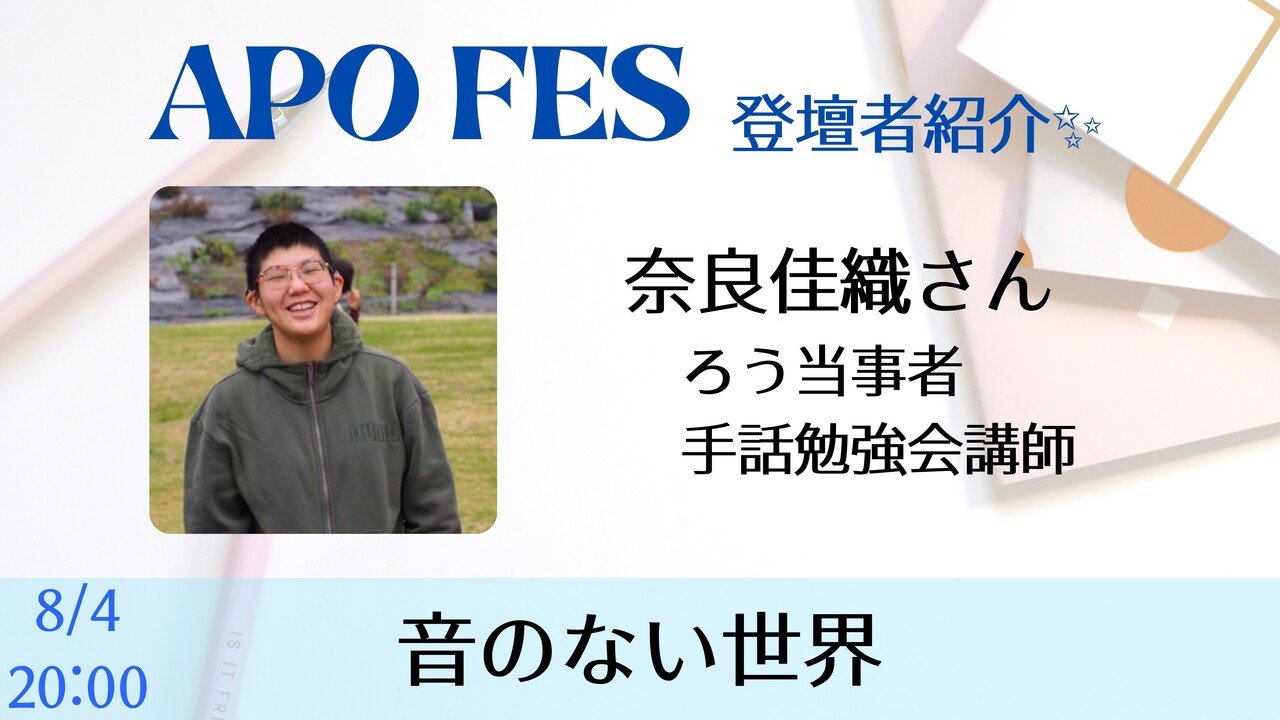
No2 奈良佳織さん『音のない世界』
火曜日夜22時より手話勉強会の講師をしてくださっている奈良さんの会でした。
「音のない世界」について、聴覚障害の種類や特別支援学校の現場などを中心に学び、「へぇ、知らなかった!」がたくさんありました。
運営一同「視野が広がった」と実感している様子でした。
ありがとうございました。
第8回 #手話勉強会
— かぐや☂️もあふる~性教育の教育実習~クラファン中🔥 (@kaguya_daiki) July 20, 2021
今日は40個くらい覚えた!!!
ときどき会話の中で手話を出すように
なってきました。
もっと会話できるように
練習していきたいですね。
毎週火曜日の夜やってますので
参加したい方はいつでもご連絡を😆
今日もありがとうございました! pic.twitter.com/rYpFKSFwcH
もしよかったら一緒に手話を学びませんか?
興味のある方はご連絡お待ちしています!

No3 安部顕(へいなか)さん『塀の中の事例集〜まだどこにも書いていない個人的な実践の話〜』
去年の10月頃に直接お会いしてから何度かお会いして大変お世話になっている、へいなかさん。
今回もキレキレのスライドと引き込まれる話し方・内容で余韻がすごかったです。
少年院で実際にどんな生徒と関わってどうなっていったのかという事例をお話しいただきました。
「社会で生きていく」ということを前提に「あなたが本当になりたい姿はどこ?」という部分を見通しさせて指導をしているということが改めてへいなかさんらしいなと感じました。
教育や育児、保育などいろんな場面で参考になるお話が聞けるので、ぜひ皆さんも聞いてみてほしいです。
ありがとうございました。
【超略歴】
— 安部顕|問題児対応のプロ (@Heino_naka) July 12, 2021
・私大文系卒
・内装資材のルート営業3年
・少年院の教官9年
・カウンセラー(今ここ)
【資格】
・公認心理師
・教員免許(中高社会系)
・矯正護身術上級
【特技】
・ダンスとバスケ
・人前で話すこと
【趣味】
・漫画と映画と小説
【著書】
・ 塀の中の教室https://t.co/X5DzQyUI2L
少年院について書かれた入門書が大人気です。口語調で読みやすいので初めて少年院について学びます、という方にはおすすめです!

No4 あやねさん『わたしの生き方と子どもたちの生き方〜学級経営の視点から考える〜』
あやねさんは去年から存じていましたが、プレゼンをお聞きするのは初めてでした。
上越教育大学教職員大学院の西川先生がつくった『学び合い』の考え方についてのお話でした。
誰1人取り残さない教育ということが「無理でしょ」「難しい」で済まされるものではなく、子どもたち同士の関わり合いを引き出し、学びあう空間がつくられるイメージで語られました。
ありがとうございました。

No5 原田瑞穂さん『西成出身の女子大生が語る!〜私が社会問題に向き合う理由〜』
誰もが気軽に行動を起こせるように、「SDGsダイアリー」を立ち上げたり、学校などで講演活動を行なったり、イベントをたくさん開催したりしている瑞穂さん。
画面上でもひしひしと瑞穂さんのエネルギーが伝わってくるので、お話を聞くだけで元気になりました。
「楽しい」からとどんどん新しいことにチャレンジするその行動力は本当に尊敬します。
僕もアイデアは口に出して直感を大事に行動していこうと思います。
ありがとうございました。
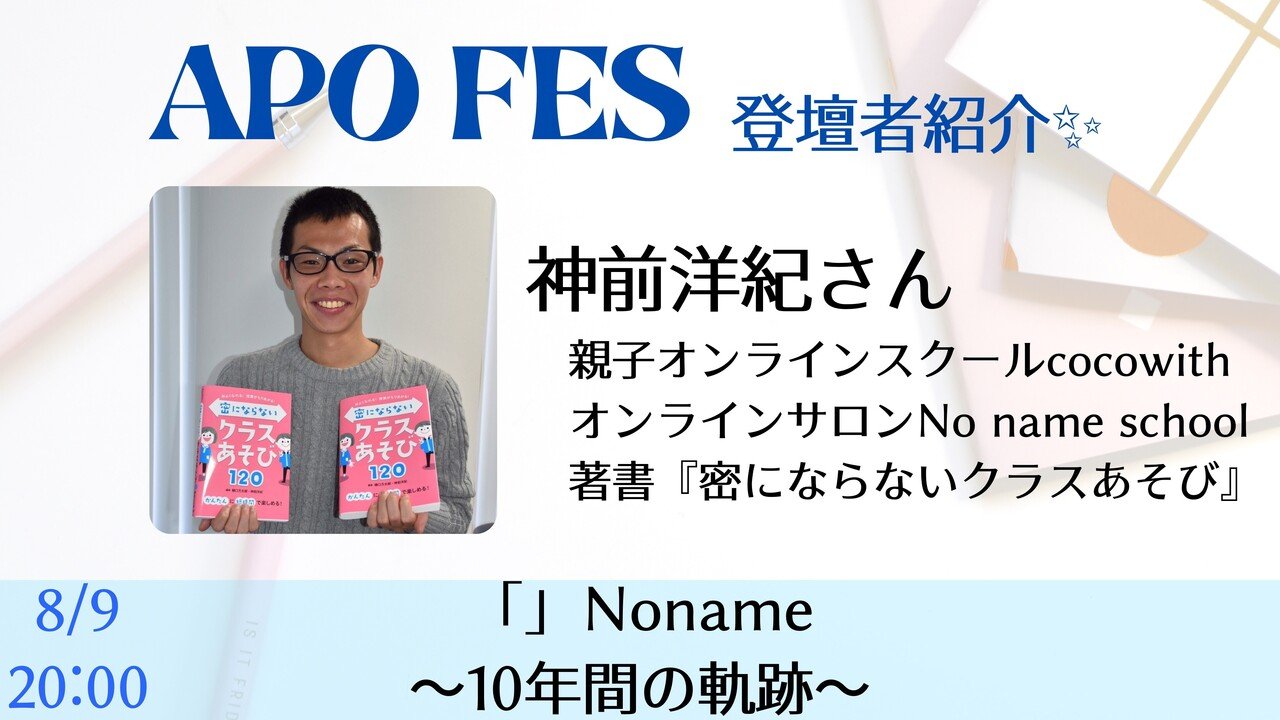
No6 神前洋紀さん『「」Noname〜10年間の軌跡〜』
お世話をしあっている、ざるさん。(見守りあっているの方が正しいですね笑)
オンラインサロンNo name familyに出会ったのが去年の7月ごろ。そこからの出会いの豊かさやメンバーの家族のような居心地の良さは、本当に楽しいです。
いつもありがとうございます。
彼の大学時代からの10年間を振り返る会でした。
彼の行動力も巻き込み力もすごいなぁと思っていますが、
・年齢は関係ない
・行動はノリと勢い
ここは本当に分かるなぁと思いました。
彼も僕も「なんでもいいんです」とちょいちょいつぶやくのですが、実は構ってちゃんのざるさんとこれからも仲良くしたいです(どんな文脈)。
ありがとうございました。
経験の差は読書で埋めることができます。夏休みはそのチャンス。
— No name school🌈神前洋紀「密にならないクラスあそび120」 (@rungorungo_) August 6, 2021
5年間で1000冊以上読んできた僕が、厳選した本の紹介です。https://t.co/epbmfRHde0
彼のTwitterはぜひフォローしてみてください。時々辛口なのが好きです。
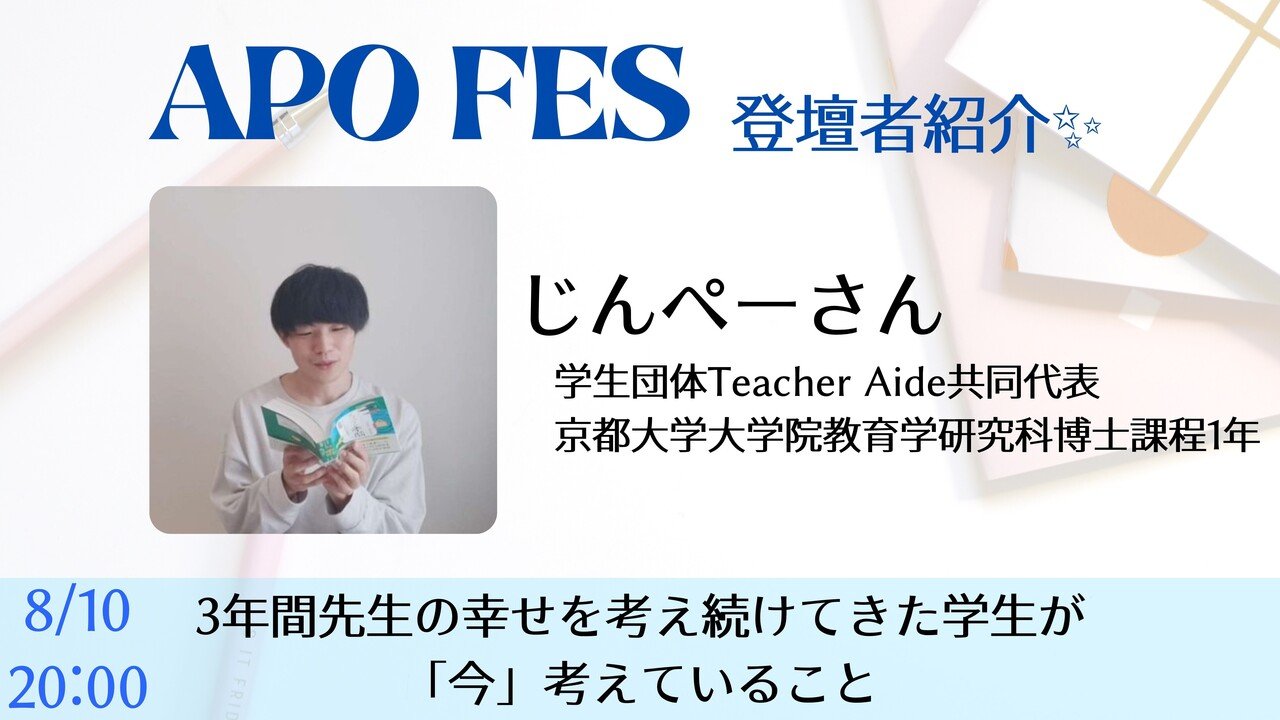
No7 じんぺーさん『3年間先生の幸せを考え続けてきた学生が「今」考えていること』
昨年の7月ごろにNo name schoolで出会った、教育系学生団体といえばこれ!のトップに君臨する、じんぺーさん(この紹介の仕方はよくない)。
「教員一人ひとりを幸せに」するために活動している学生団体Teacher Aideの共同代表を務めています。今回は、その始まりや初期の挑戦などからお話を聞くことができて新鮮でした。
“理念”を軸にゆるりとかつ全国の学生を巻き込んでいるこのTeacher Aideでの活動は今後もゆるりとかつできることから少しずつやっていきたいですね。
僕は茨城支部としてもう少し茨城県の学生に存在をまずは知ってもらえる機会を設けたいな。
また考えましょう。
ありがとうございました。
【ぼくが教員を目指さない理由とそれでも教育に一石を投じたい理由】
— じんぺー☂️Jimpei Hitsuwari (@hitsuwari5th) November 5, 2018
ついに書いてしまった、、
前の記事、「これまでで1番読んで欲しいかも」って書いたけど、早速更新。
教員の方、辞めた方、目指されている方、それ以外のみなさんに読んで頂きたいです。https://t.co/0XdCKb35m7
この記事は多くの人に読まれているのでぜひ。
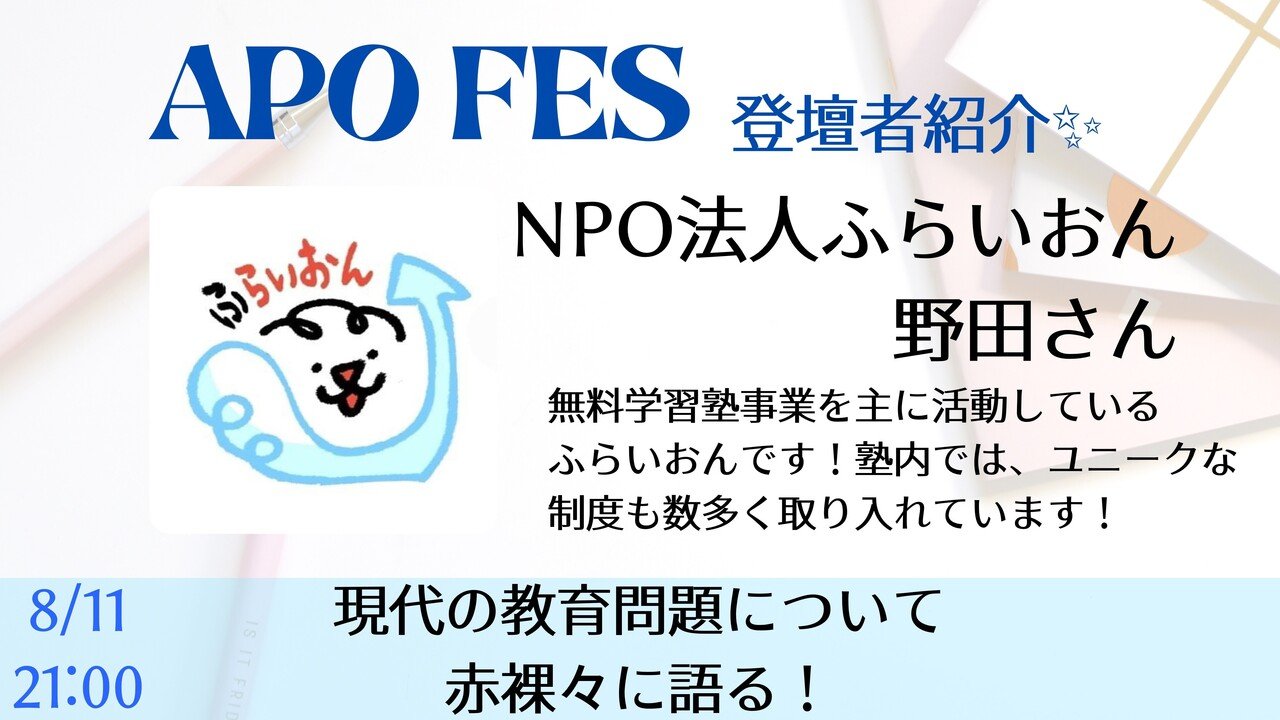
No8 NPO法人ふらいおん野田さん『現代の教育問題について赤裸々に語る!』
学生でNPO法人を立てるだけでもすごいのに、今ではさらに無料学習塾に加えて、プログラミング教室、英語アプリ、教室を3校舎まで拡大、などその活動のキャパシティが本当にありえないです。
【超特大発表最終日!!!】
— NPO法人 ふらいおん✈ 🔥クラファン挑戦中!!!🔥 (@flyonproject20) August 13, 2021
最後の発表は…
ふらいおんは明日、
8/14㈯8:00〜から・・・
クラウドファンディングを開始いたします‼️‼️‼️
「無料学習塾」というものを、もっと多くの人に知ってもらいたい。
そして、その活動を継続し続けるために。
改めて、明日の8:00スタートです…! pic.twitter.com/N9z3VcTm7W
僕がこれまで出会ってきた中でトップクラスに入るくらい「空いた口が塞がらない」すごさを感じました(学生がやってるんですよ!?)。
その中で活動している野田さんの教育に関するプレゼンはデータ付きでわかりやすくていろんな疑問が生まれて、考えされられました。
今、ふらいおんさんはクラファンを実施中です。
ぜひご関心のある方はこちらからページをご覧になってください。
ありがとうございました。
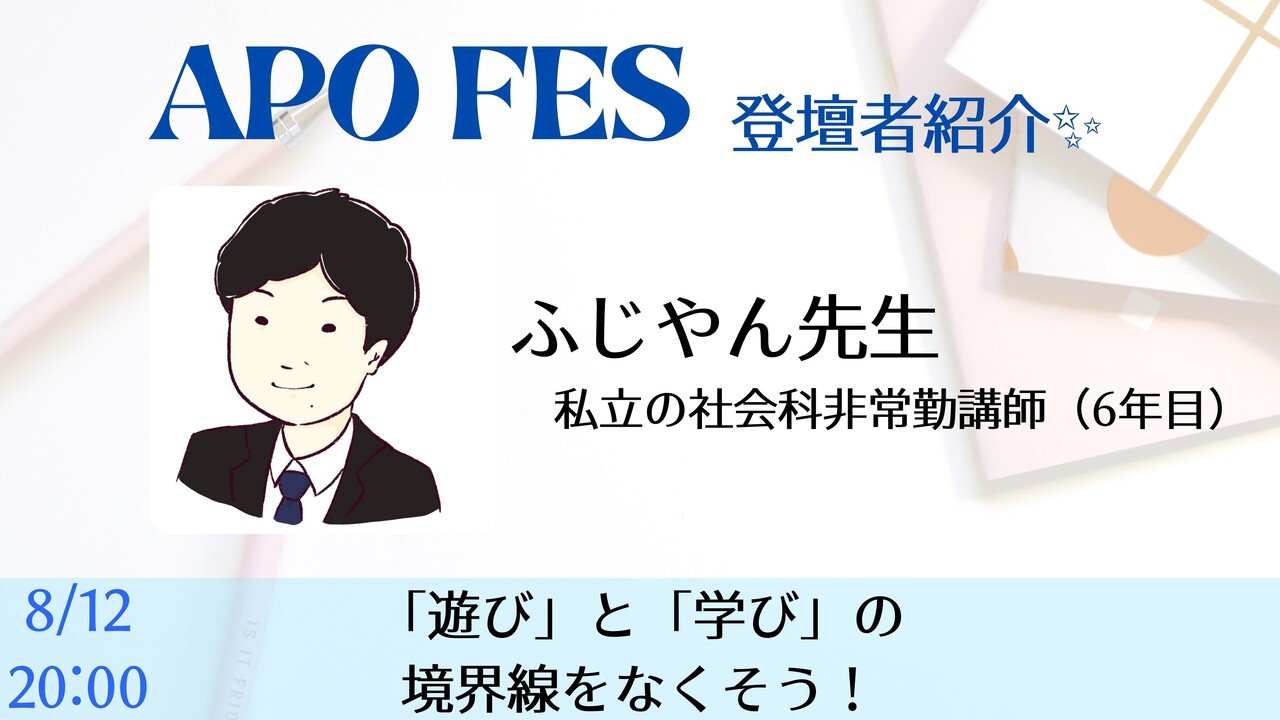
No9 ふじやん先生『「遊び」と「学び」の境界線をなくそう!』
いやぁ。感無量でした。
普段はひたすら喋るふじやん先生を見ることがないので、どんなお話が聞けるのか楽しみだったのですが、「喋り続けるけど参加者も楽しい」をモットーにしている彼のお話は、さすがでした。
「学び」の意味を教えるよりも、「遊び」のような「学び」を通してあとから「学び」の意味を感じたり考えたりすることにつながるといいというのがすごく共感しました。
興味を持てば勝手に学ぶ。だから興味を持つまでが大切だなぁと。
嵐と岩倉使節団のくだりからの理論がめちゃめちゃ面白くて本当に面白かったです。(語彙力を失った)
ふじやん先生から社会科の授業を受けたらどうなったんだろうなぁとも思いました。
ありがとうございました。
【メディア出演(初)】
— ふじやん先生/PLAYFUL Teacher (@fujiyan_ws) November 22, 2020
Re・riseNews様にインタビューしていただきました。
私のビジョンなんかを素敵な記事にしていただいてます。
初めてのインタビューで下の原稿見てたり時折目が寝てるみたいになったり慣れてない感がバレバレですが、よろしければご覧ください。https://t.co/jNpoHKsfYx
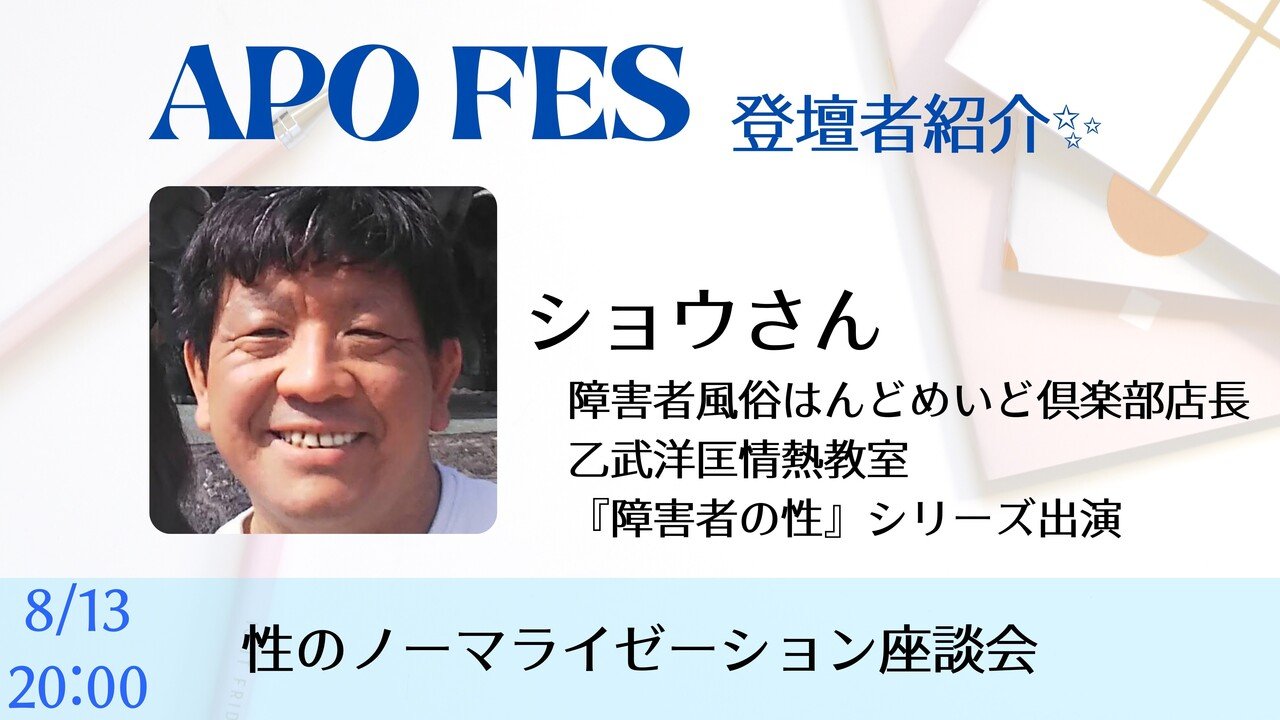
No10 ショウさん『性のノーマライゼーション座談会』
障害者の風俗。と聞いて皆さんはどんなイメージを持つでしょうか?
ショウさんはこのサービスを福祉として提供するよりは、健常者(区別のために使います)が楽しんでいるような文化を心のバリアフリーを得て楽しめるようにしているとのことでした。
ハンディキャップの有無に関わらずその人の力を見定めることなく、その人が持てる可能性を精一杯引き出すことが重要かもしれないと改めて感じました。
「社会の平等」の捉え方はそれぞれですが、僕は最近「支え合う」ことに視点がいきすぎて、“自律”という言葉すら使っていないなぁということに気づきました。
そして自分の立場を言い訳にしないことが押し付けられる社会はあまり好きじゃないなぁと思いました。
バランスが難しいですね…。また考えたいテーマです。
乙武洋匡さんのチャンネルでも登場されていたので、ぜひご覧ください。
ありがとうございました。
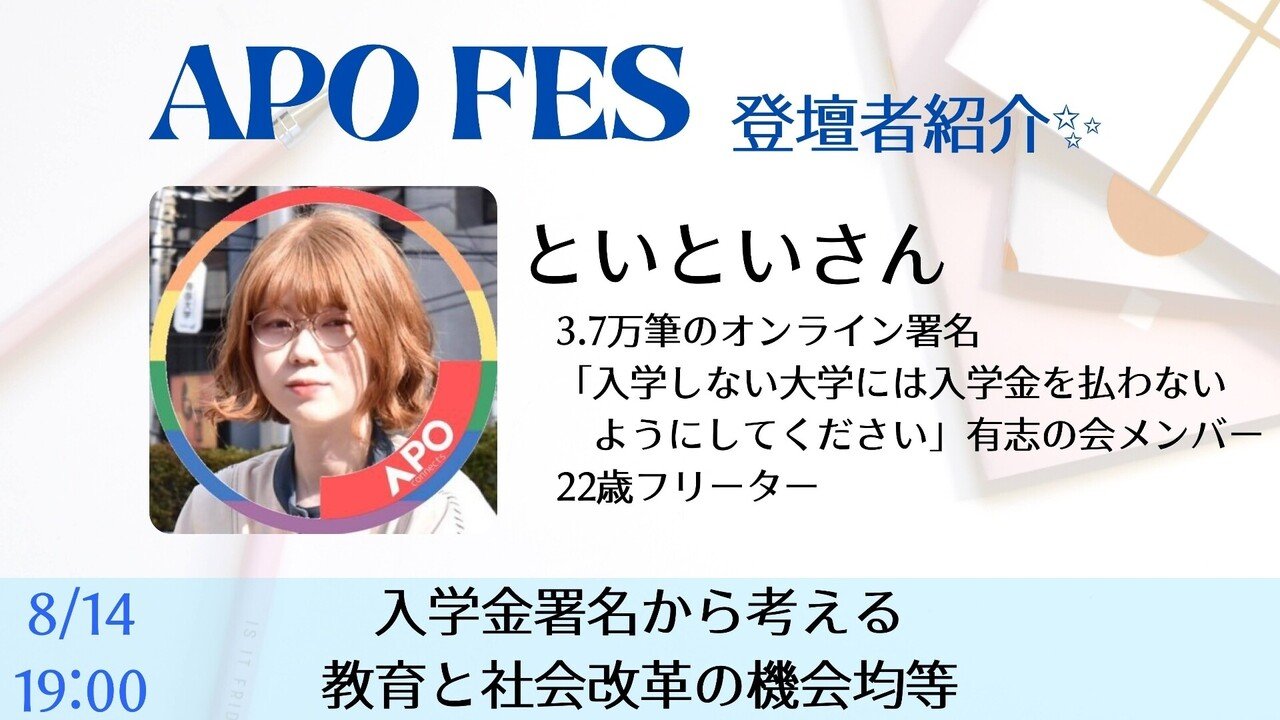
No11 といといさん『入学金署名から考える教育と社会改革の機会均等』
改めて、入学金署名について、詳しくお話を聞くことができました。
といといの考えている部分は僕もすごく共感するものがあって、この署名活動は意義あるものだと思いました。
「選択肢が狭められる」要因が仕組みで解決できるのであれば僕は改善すべきだと思います。
「本当に困っている人は声を挙げることができない」
ことの問題の重要性はいろんな分野でいえるなと。すごく、どうしたらいいのだろうという気持ちになりました。
そもそも声を挙げることが特権的だという話をしていましたが、特権的であることを生かさない理由はないと思いますし、でもその声を挙げることができない人が挙げられるようにするためには何ができるかなぁということも考えていきたいです。
【受験における「入学金」の納入時期延長を求める署名】を始めました。
— 入学しない大学には入学金を払わなくていいようにしてください! (@dvg7h0aybolhe1v) March 19, 2021
入学しない大学にも数十万円「入学金」を払う必要がある今の仕組みが、多くの受験生の選択肢を狭めています。
全ての受験生が平等に受験をできるよう、ご協力お願いします!#拡散希望 #学費 https://t.co/gqdaMgmRH1
ぜひ内容をみて共感したら署名をお願いいたします。
ありがとうございました。

No12 おいだきさん『Brio〜多様な性について考え、誰もが「イキイキと」生きる姿を描く手帳を作成した理由〜』
おいだきさんのお話を直接お聞きすることができてよかったです。
Brioは僕も実は購入させていただきました。
時間が空いた時にパラパラと全部読んでみたのですが、知らなかった「知識」がたくさん詰まっていて、そして多様な性のあり方が可視化されることで、ますます一人ひとりの違いが「あたりまえだ」という感覚が芽生えました。
多くの人にこの手帳が届いてそのことやもっといろんなことに気づくきっかけをもたらすことができたらいいなと思いました。
ありがとうございました。

No13 あゆみさん『持続可能な教育現場の在り方とは』
あゆみんはすごいのよ。
まず授業中に・・・(割愛)。そこに視点を持っていたということがすごいですし、大学選びで教授の存在を軸に決めるというもの、僕にとってはレベルが違うなと思うことです。笑
あゆみんのこれまでの活動について、じっくりと聞くことができました。
TEST「学校インターン」は必ずこれからの時代で広がっていく概念です。それ以外にもたくさんのプロジェクトを起こしています。(そんなにやっとったんかいというツッコミを入れとこう)
身近にこんなにもパワフルに活動をしている人がいるというのは心強く感じます。
また共にあゆみましょう、あゆみん(ニヤついた方にはチキン南蛮をご馳走しましょう)。
ありがとうございました。
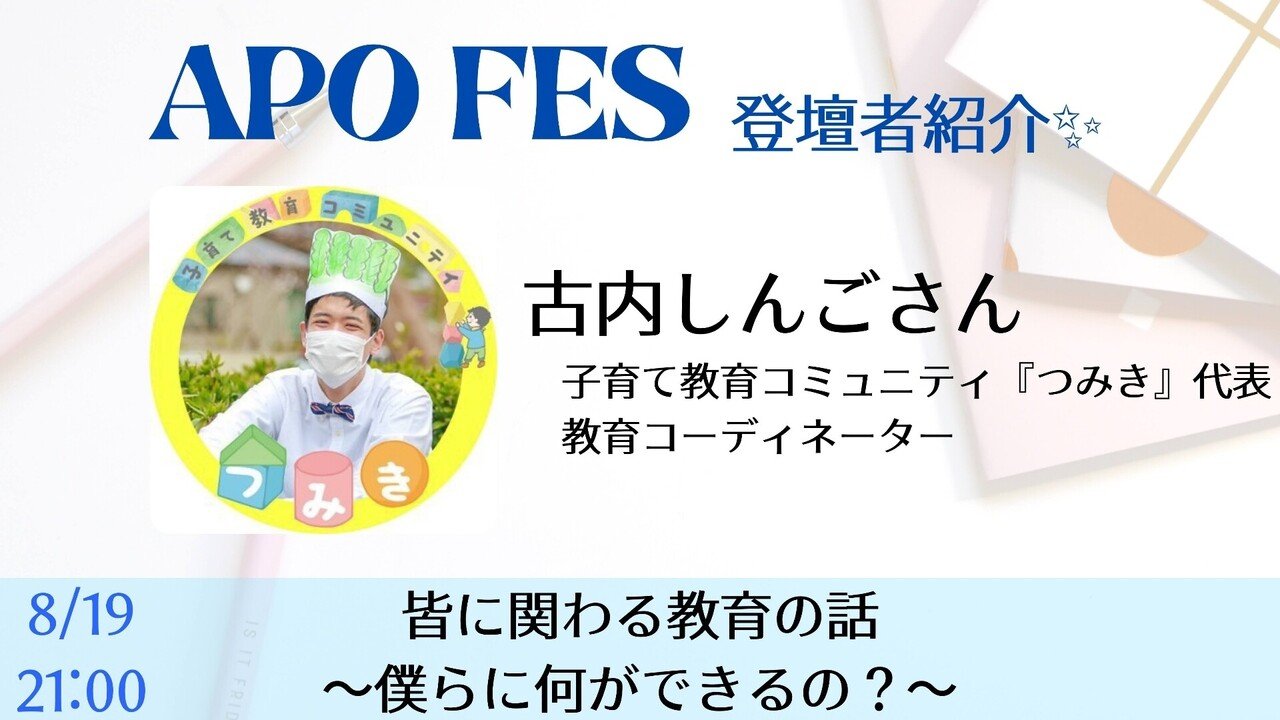
No14 古内しんごさん『皆に関わる教育の話〜僕らに何ができるの?〜』
久しぶりに。
しんごさんのお話を聞いて、改めて彼の教育に対する思いのアツさに感銘を受けましたし、一緒にこの場で教育について正解のない問いを考える哲学対話の時間が貴重で。
大好きでした。
教育を自分ごとにできるかどうかは本当にタイミングやきっかけが何かあるのだと思います。
それは押し付けられるものではないけど、少しでも多くの人がそのきっかけをもてるように、僕は僕にできることをやっていきたいなと思いました。
◆本格始動◆
— 子育て教育コミュニティ『つみき』 (@tsumiki_edu) August 9, 2021
子育て教育コミュニティ『つみき』
【つ】… 繋ぐ
【み】… 皆を
【き】… 教育で
~ 学びあい 育ちあい ~
始動して約2ヶ月。
HP・LP等も全て整いました✏️
『つみき』に至る背景・理念。
読むだけでもいいので、読んでくださったら嬉しいです🍀
⬇️ pic.twitter.com/NyxvOimebU
しんごさんの立ち上げたコミュニティは僕はまだ参加していませんが、きっとすてきな学びがたくさんあると思います。
必要な方に届きますように。
ありがとうございました。
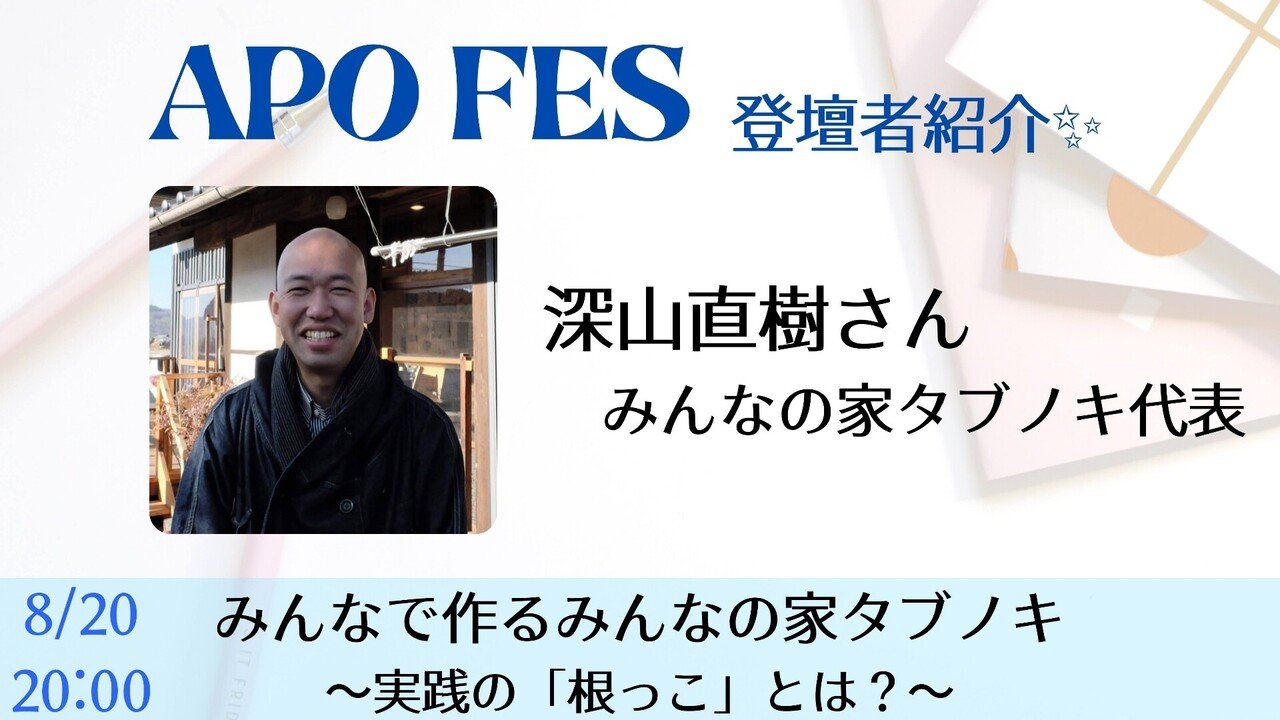
No15 深山直樹さん『みんなで作るみんなの家タブノキ〜実践の「根っこ」とは?〜』
僕がつくりたい「居場所」は、地域の子どもたちから高齢者の方まで、すべての世代の方が気軽に立ち寄って遊んだり、生活の一部を共有したり、畑を耕したりすることができる場所です。
みんなの家タブノキはそんな僕がやりたいものに限りなく近いものだと思いました。
昨年度、福祉系の学生から学んだ、「富山型デイサービス」というワードも出てきて、興味が湧きました。簡単にいうと、障害者福祉と高齢者福祉を合体させた施設のことです。(*正確ではないかもしれません)
これからの時代ではそういった地域の人が誰でも繋がれる場所というのが、すてきな学びの場になると思います。(これまでの時代でもか…!)
「時間割を決めない」
これはとても共感しました。時間割ができた時点で楽しさが半減しますし、偶然的な出会いや学びが減ってしまいます。
今度タブノキにお伺いできることになったので、自分のやりたい居場所づくりをさらにイメージを深めたいと思います。
楽しみです!
タブノキでは今のところBGMを流していない。生活音がとても心地よいから。暮らしの音のバリエーションとハーモニーはそこにある関係性を表しているように思う。 pic.twitter.com/xydbKGTy11
— みんなの家タブノキ (@tabunoki36) December 1, 2020
あぁ、この動画本当にすてきだ。。。
ありがとうございました。
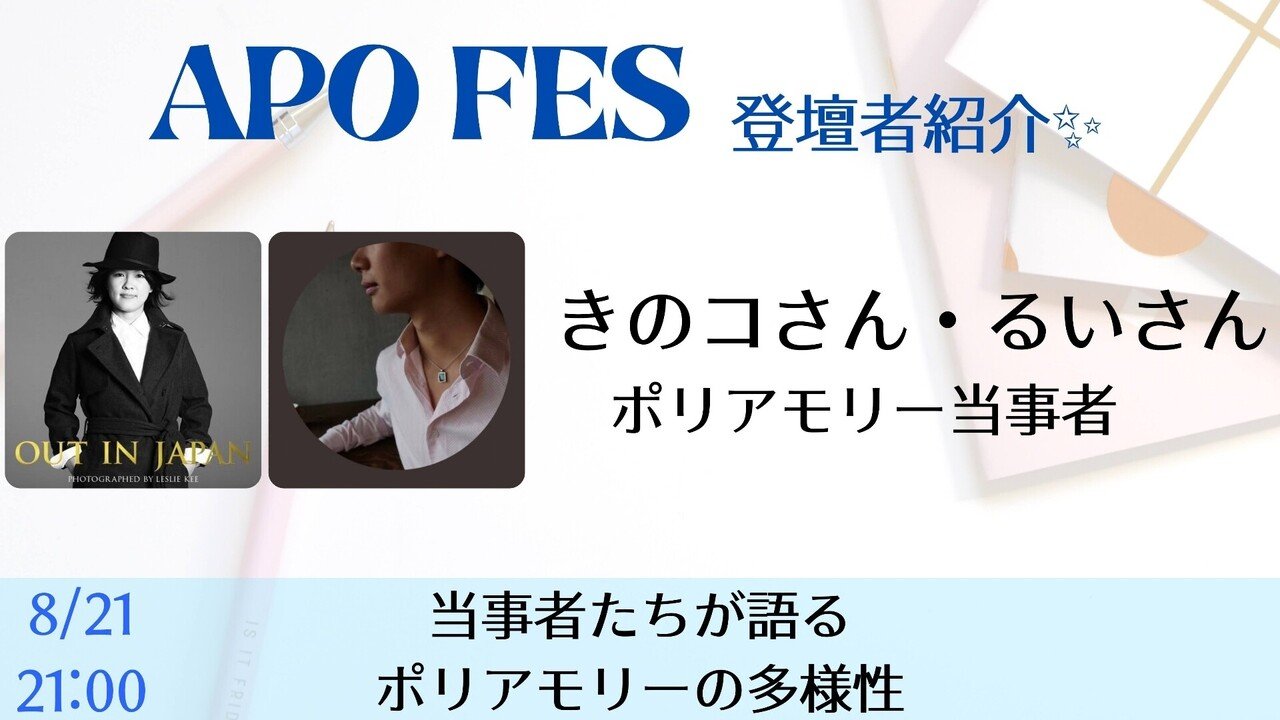
No16 きのコさん・るいさん『当事者たちが語る ポリアモリーの多様性』
とても、衝撃的でした。
ポリアモリーという概念は昨年度くらいに知りましたが、当事者の声を聞くのは初めてで、ポリアモリーにもいろんな形があるということを学びました。
ポリアモリーというのは次のような恋愛のあり方です。
関係者全員の合意を得て、
複数のパートナーとの間で
親密な恋愛・性愛関係をもつこと
まだまだ認知も低く、受け入れられる人は多くはないかもしれません。
でも、お話を聞く中で、それは一つの恋愛のあり方であって、豊かな人生のための一つと選択肢としてあるんだなぁということを学びました。
お互いがコミュニケーションをとって理想の形を模索するというのは、モノアモリーでも一緒ですよね。
とても学びの多い時間でした。
ありがとうございました。
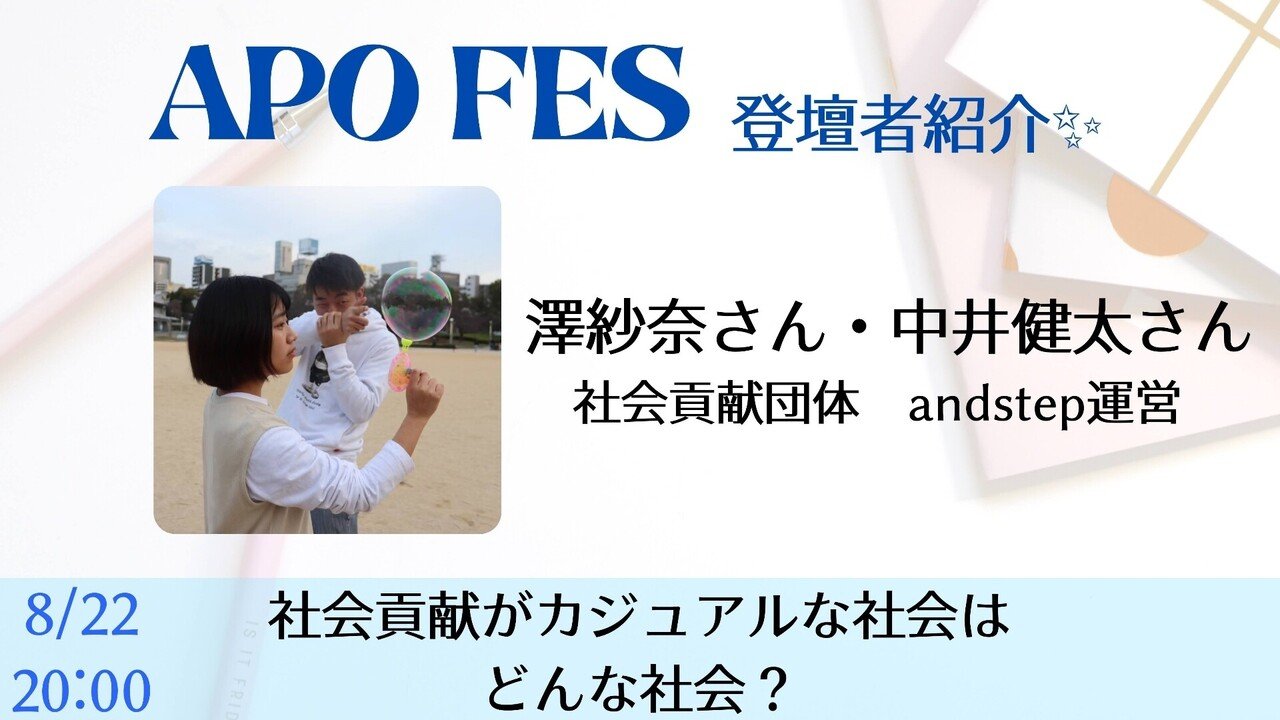
No17 澤紗奈さん・中井健太さん『社会貢献がカジュアルな社会はどんな社会?』
さなとちゃん。二人のパワーもすごくて何度かお会いしてますが、お別れのときのほうが元気になって帰ることができます。笑
社会貢献って何?
カジュアルって何?
僕が思うのは、このandstepの運営の二人ほど「楽しそうに」プレゼンをする人ってなかなかいないなぁということです。
この活動の理念のように、お二人のお話がすごく親しみやすく、身近に感じられるので、「一緒に活動したい!」と思えるのだと思います。
これからもandstepの活動は見守りつつ一緒にできることはやっていきたいですね!
身近なもので遊べるようなテーマでYouTubeも発信中なのでぜひ見てみてください!
ありがとうございました。
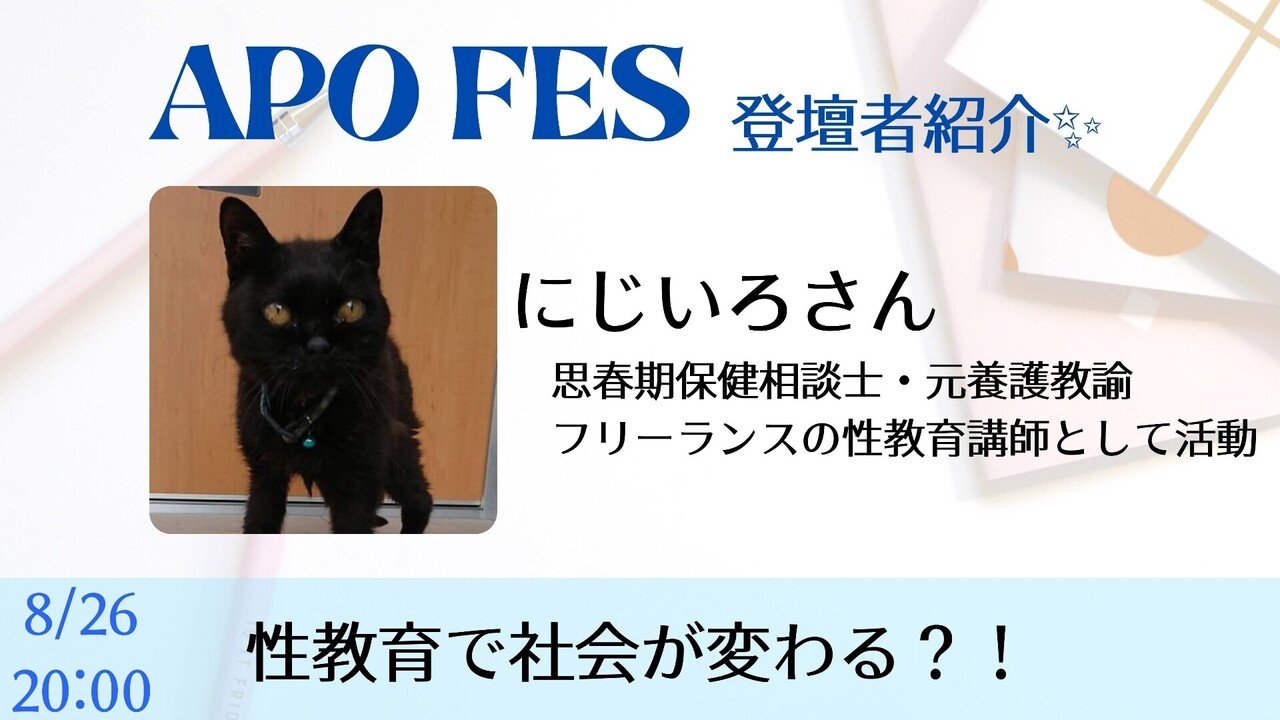
No18 にじいろさん『性教育で社会が変わる?!』
にじいろさんはもあふる第1期の講師としてもお世話になります。
過去には性教育に関する記事を何度も書かれており、日本における性教育の普及に大きなエネルギーを注がれています。
「幸せに生きるため」の性教育で、
だれもが生きやすい社会をつくりたい。
にじいろさんが紹介した村瀬先生のこの言葉が響きました。
善いか悪いかは人によって異なるものだと思います。
それを選び取るために必要な知識を得て、自分なりの幸せのための選択ができるように性教育が広がっていくといいなと思いました。
僕自身の活動もそうやって見直してみたいです。
ありがとうございました。
にじいろさんの記事は多くの人に読まれています。ぜひ一度ご覧になってください。
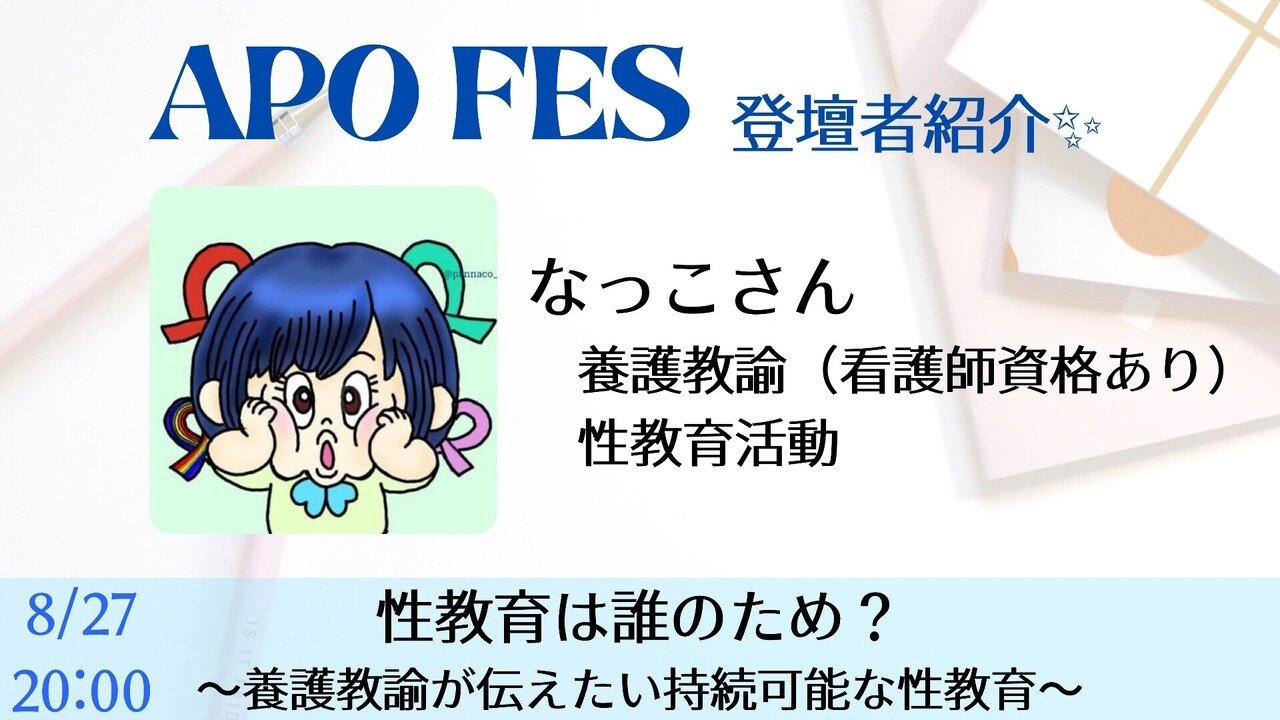
No19 なっこさん『性教育は誰のため?〜養護教諭が伝えたい持続可能な性教育〜』
なっこさんは、養護教諭としてSDGsを軸に学校に働きかけて性教育の内容を伝える取り組みをしているお話をされていました。
月経指導、生理用品配布、研修への参加などの実際の現場のお話を聞いて、学校の中でこうして活動を進められている事例をもっと多くの学校の先生が認知して、取り組みの連鎖が起こるといいなぁと思いました。
持続可能な性教育のために、
・目的意識が明確で共有されている
・リスクだけを取り上げて「やらない」ことを選ばない
・取り組みや情報のシェアだけで◎
といった点をおっしゃっていましたが、これはどの現場においても言えることだなと。
変えていくとなったときにできることからやっていくというのはよく言われますが、「得た情報を回覧で回す」など具体的なエピソードを聞くだけでハードルが一気に下がる気がします。
僕も子どもたちと関わる場面で他の職員さんと情報共有してできることをやっていきたいです。
ありがとうございました。
#APOフェス
— なっこ🌈 (@pannaco_roll) August 27, 2021
ありがとうございました!
みなさんのコメントや反応に助けられました🙏現状を知っていただけただけでも感謝です。
持続可能な性教育の要素は私自身の課題でもあります😌できることから少しずつ。そして、性教育のハードルを下げ、一歩踏み出してみるきっかけを考え続け作っていきます
質問がある方などは、ぜひなっこさんに直接メッセージを送っていただけたらと思います。
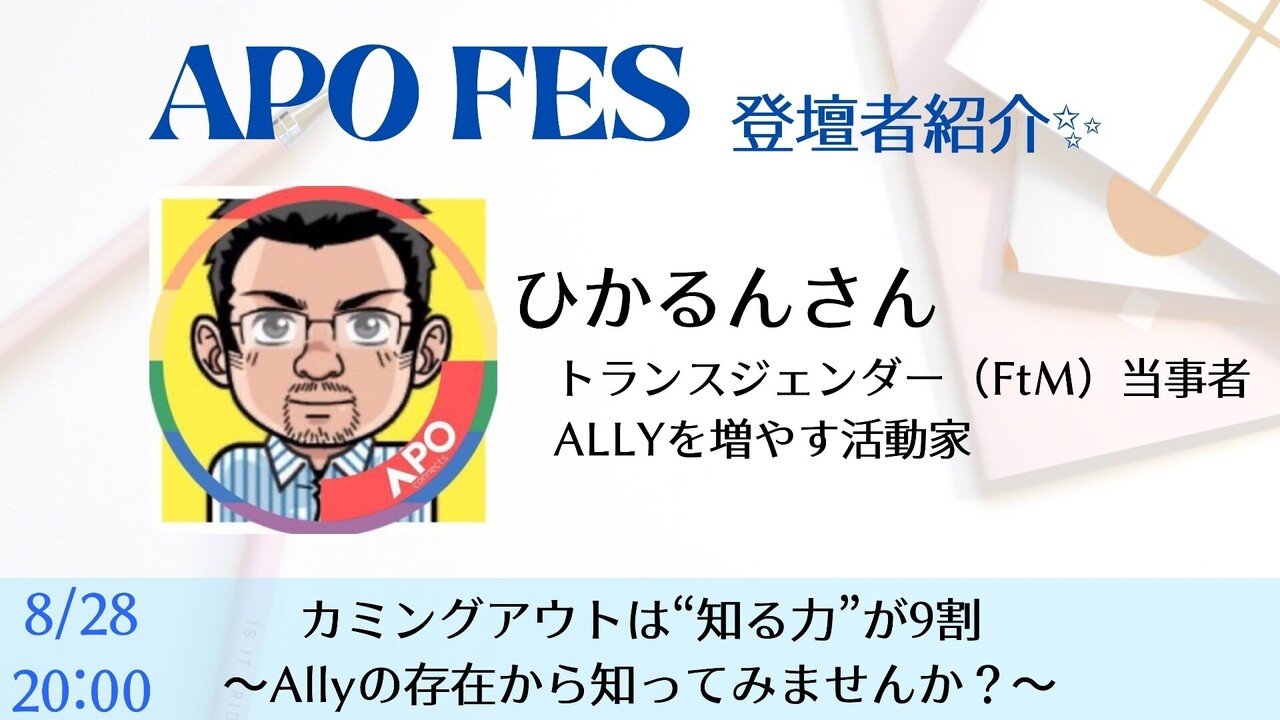
No20 ひかるんさん『カミングアウトは“知る力”が9割〜Allyの存在から知ってみませんか?〜』
僕はAllyです。この言葉を知ってから僕はAllyになろうと思いました。
ただ声を大きくして表明することはしていないのですが、それは、誰もが違うということを当たり前のように受け入れられる社会であってほしいからです。
今回のお話で、ひかるんさんが「Allyを広める」活動を始めるきっかけが考えものでした。色んな過去があって、今の活動に至っている。それはとても素敵なことだと思いました。
まず「知る」ことがやさしさにつながる。逆に言うと、知らないが偏見を生み出し、不幸を生み出します。このAPOフェスでお伝えしたいことがまさにひかるんさんのお話ででてきました。
ありがとうございました。
クラウドファウンディングの支援募集を開始しました!
— ひかるん@9/1~クラファン挑戦中🌈ALLY(アライ)を広める人 (@ftm_hikaru) August 31, 2021
目標300万円を
10/20までに達成します!
ご支援・応援・拡散、
よろしくお願いします🌈
🔽クラファンページhttps://t.co/FYR7HIeVV9
🔽公式Twitterにて
最新情報配信@translife_movie https://t.co/HPphcaSwWk
ひかるんさんは、現在クラウドファンディングに挑戦中です!応援しています。
ありがとうございました。
以上でレポートを締めようと思います。
僕自身の視野が広がる良い8月となりました。ご登壇くださった皆さん、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。
そして、この記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2021/09/03 かぐや


